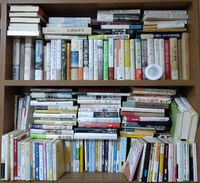2025年02月01日
2025年1月の記録
今年もしっちゃかめっちゃかな選本で行こう。
読む必要のない本は、慎重に見定めて。
<今月のデータ>
購入10冊、購入費用7,169円。
読了12冊。
積読本334冊(うちKindle本157冊)。

 いとも優雅な意地悪の教本 (集英社新書)の感想
いとも優雅な意地悪の教本 (集英社新書)の感想
2016年「すばる」連載。「意地悪」が主題のよもやま話。バカ、デブに代表される二文字の罵倒言葉は、気分に直結して脊髄反射的に発せられる簡潔な性質ゆえに連打してしまうが、知性を駆使した意地悪な言葉は一発で効くとか、質問に答えず四の五のと冗長に続く答弁は、知性が低いのではなく、知性とモラルが分離しているがゆえにその下品さを自覚せずにいられるからとか、すごいことをやってもすごいということを理解する才能がある人にしか理解されないとか、まあ意地悪な文章のオンパレードで爆笑してしまった。樋口一葉を読みたくなった。
読了日:01月30日 著者:橋本 治
 ちゃぶ台13 特集:三十年後
ちゃぶ台13 特集:三十年後
読了日:01月26日 著者:ミシマ社
 ドイツ人のすごい働き方 日本の3倍休んで成果は1.5倍の秘密の感想
ドイツ人のすごい働き方 日本の3倍休んで成果は1.5倍の秘密の感想
社会に浸透した労働観をはじめ、教育制度、商習慣、法整備まで素地がかなり異なる点は踏まえておくべきだろう。長期休暇取得や急な欠員を受容する"バックアップシステム"とは、タスク整理や情報共有のシステム化と同時に、余裕を持ったリソース管理が要となる。それはつまり人件費の増加を意味し、かつ生産性を高く保つには、経営効率が確保されていなければならない。ドイツの中小企業割合が日本同様99%を超えている点を考え併せれば、全経営者が教育を受けた経営のプロとは考え難く、経営者および社会の認識に日本との差がありそうだ。
読了日:01月25日 著者:西村 栄基
 老警 (角川文庫)の感想
老警 (角川文庫)の感想
老警とはだれか。練られたミステリ。多すぎる情報を疎んでいるとしてやられる。男は女を、親は我が子と組織を、組織は組織と組織内の権力闘争を想って意を決し、それぞれ隠密に行動する。徹底的に被害者やその家族に焦点を当てない、描こうとすらしない、非情がとかく心地悪い。しかし事件が結末を見、終章で作者が書きたかったものが露わになったとき、彼らと彼らの家族に対する私たちの態度は、見ようとしない、無いものであるかのように扱う、同様の非情であると糾弾されたように感じた。閉じてしまったものを開くにはどうすればよいのだろう。
読了日:01月19日 著者:古野 まほろ
 ぼくは古典を読み続ける 珠玉の5冊を堪能するの感想
ぼくは古典を読み続ける 珠玉の5冊を堪能するの感想
連続講義の新書化。古典のススメ。今は古典新訳文庫や池澤夏樹編集があるので、古典もとっつきやすくなったものだと思う。だからといって、関心を持てるまでにはそれなりに本を読む時間と、人生の経験値を積み上げることが必要なのではないかな。特に私のように読書は娯楽であると認識して育った人間には。そのうち、より深いものへの渇望が生まれる、そんな印象を覚えた。若いうちにわからないなりに読んでおくにこしたことはないのだけど。気候が安定して政治も安定する豊かな時代には文化や学術が世界同時多発かつ爆発的に発達するのが興味深い。
読了日:01月17日 著者:出口 治明
 マハーバーラタ: インド千夜一夜物語 (光文社新書 47)の感想
マハーバーラタ: インド千夜一夜物語 (光文社新書 47)の感想
正月に観るインド映画の基礎知識として。しかし「マハーバーラタ」は長すぎて、しかもパンダヴァvs.カウラヴァの物語以外にも、今昔物語や禅問答めいた小話が多々収められているようだ。本書はそれをピックアップしたもの。登場人物は神、聖仙、王、賢者と堂々たる面子だが、性欲をつい我慢でけんかった話が多くて笑った。生命力旺盛である。デヴァとアスラの戦いも面白い。バラモンが編纂したものなので多分にヒンズー寄りと思いきや、アスラがドラヴィダ、デヴァがアーリアなのにデヴァが侵略したことを認めていて、これもまた大らかである。
読了日:01月13日 著者:山際 素男
 現代家庭療法百科の感想
現代家庭療法百科の感想
亡き祖父母の本棚を整理して出てきた本を貰い受けた。主婦の友社、昭和58年の刊。家族の体調が悪くなったとき、昔はネット検索なんてないから、このぶ厚い本を祖母も熱心にめくったのだろう。症状と治療法に始まり、漢方療法、ツボの図解から民間療法まで、痛苦を和らげるためのさまざまの方法を、各分野の専門家監修のもとまとめている。病気の説明は現代に劣るかもしれないが、東洋医学や生活の知恵はむしろ現代より充実していると思われるので手元に置く。本書は医師による適正な治療と争うためではなく、むしろ補う目的とする編集後記が熱い。
風邪・インフルエンザの民間療法を抜き書きしてみる。焼いた梅干し。ショウガ湯。ネギとみそ。するめとネギ。ゴボウとみそ。シイタケとはちみつ。レンコンとキンカン。干し柿。卵酒。黒豆。コマツナ。シソ。ニラ。ニンニク。ヤマイモ。酢。キンカン。ショウガ酒。みそ酒。ネギ。玄米とミカン。黒豆とクルミ。キク。ヨモギ。ニワトコの花。ドクダミ。ゆず湯。梅酢。and so on。エンドレス。これがよかろうあれがよかろうと、それぞれに試して得た生活の知恵は、健康になりたい、家族を楽にしたいと願う人々の思いの集合体である。胸アツ。
読了日:01月13日 著者:
 転がる珠玉のように (単行本)の感想
転がる珠玉のように (単行本)の感想
「婦人公論」連載。若干短めのエッセイ。新型コロナの流行期に被っているので、医療関係者や家族の病、死の話題が多め。つられて始終涙ぐんだ。コロナ禍が明けたとて、物価高と生活苦、人不足の話題には事欠かない。でも地べた目線の話は温かみがある。そこにこそ希望を感じる。ならば「クリスマス・キャロル」の精神はなくとも、地べた目線は常に忘れずにありたい。あと、エッセイに起承転結が無いといけないわけではないと思った。起承だけでも、著者のエッセンスはじゅうぶんに発揮されている。Never too late.って素敵な言葉。
著者が保育士になったとき、1年目は子供に病気をもらいまくったが、2年目には鋼鉄の体になったという。人間の体は免疫がつくようにできている。しかし、私たちは今こんなに感染症に振り回されている。これはなぜなのだろう。コロナ禍期の強い行動規制が解除されてもう数年が経つ。隔離やマスクを外した反動だけではないのではないか。過消毒やマイクロバイオームの損失によって、人間という生物自体が弱くなっているんじゃないかとまで思う。あと記憶のスパンも短くなってるが、これはきっとスマホにより依存するようになった、情報過多のせいだ。
読了日:01月12日 著者:ブレイディ みかこ
 インド夜想曲 (白水Uブックス 99 海外小説の誘惑)の感想
インド夜想曲 (白水Uブックス 99 海外小説の誘惑)の感想
友人の消息を追って始まるインドの旅。インドの実在の場所を、主人公は初めてではなさそうにするする進んでいく。しかし、主人公の思考がインドらしくない。外国人だから当たり前だけど。行く先々で出会う相手との対話に戸惑い、苛立ち、でも着地点は最初から決まっていたような。持て余す夜の時間の無聊を慰めるためのような。その感じが西洋的で、物語としては私は好きではなかった。一個人の中で完結する、排他的なよそよそしさ、と名づけてみる。私のほうの気持ちがインドに寄りすぎているのかも。夜の駅や、高級ホテルの場面の雰囲気が好い。
読了日:01月11日 著者:アントニオ タブッキ
 “手”をめぐる四百字: 文字は人なり、手は人生なりの感想
“手”をめぐる四百字: 文字は人なり、手は人生なりの感想
季刊「銀花」連載。原稿用紙1枚の文章はエッセイとしては短い。しかし百様ならぬ五十様の手跡に目が釘付けになった。写真で挟まれたさまざまの手仕事はもちろん、紙一枚の上に表れる文章のなんと自由なこと。達筆どころか、字面が揃わなかったり、マスからはみ出たり、そもそもマス目を手書きしたり。ああ、これでいいんだ、と、近頃自分の手書き文字の汚さに辟易していた私は胸が軽くなったのだ。出版社からいただいた原稿用紙を持ち出し、写経用の筆ペンで、文字を書く遊びを始めた。マスからついはみ出るような、大らかな字を書く人になりたい。
読了日:01月09日 著者:白洲 正子
 東の海神(わだつみ) 西の滄海 十二国記 3 (新潮文庫)の感想
東の海神(わだつみ) 西の滄海 十二国記 3 (新潮文庫)の感想
この正月に引いたおみくじは最高の内容だった。占いというより激励だった。その流れで再読。私にとってこの本は"初心"みたいなもの、かもしれない。小松尚隆は私のメンターなのだ。『なんだ。そう悲壮な顔をしてどうする。どうせなるようにしかならん。軽く構えろ』。国の存亡の危機にあって発した台詞。上に立つ者の心構え、というか。国を守るため自身は必死に考え、体を張って動くのだけれども、どれだけ苦しくてもそれは自分が引き受けるのだと腹を決め、人々には堂々と接し、鷹揚に笑ってみせる。そうあるべしと心得て、今年に挑みたい。
『民は王などいなくても立ち行く。民がいなければ立ち行かないのは王のほうだ。民が額に汗して収穫したものを掠め取って、王はそれで食っている。その代わりに民が一人一人ではできぬことをやってやる』。
読了日:01月07日 著者:小野 不由美
 ガラム・マサラ!の感想
ガラム・マサラ!の感想
のっけからフルスピードでまくしたてるから、無分別な青春ギャングものに手を出したかと後悔しかけたが、どうして、これはこれでリアルな現代インド社会を俯瞰した物語の運びが興味深い。チャイ売りの屋台稼業は、インドの社会階層としては中の下の下だそうだ。テレビ番組の人気者になるという上っ面な狂騒と、金持ちになりたいというインド人のいつの時代も変わらぬ夢(?)を土台に、ドタバタが繰り広げられる。"インド人なのに"電子煙草を吸う、また伝統的でない薬物を摂取する、欧米文化にかぶれたインテリ階級への嫌みがスパイス。
『アビはバターチキンが売り切れた結婚式ビュッフェ会場のおじさんのような眼で僕たちを見ていた。それくらい怒っていた』。『食べ放題のビュッフェにいるパンジャブ人のように、僕の心臓は爆発しそうだった』。こういう比喩が秀逸でゲラゲラ笑ってしまう。そしてSRKとアーリア・バットはもはや鉄板ネタね。
読了日:01月01日 著者:ラーフル・ライナ
注: は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。
読む必要のない本は、慎重に見定めて。
<今月のデータ>
購入10冊、購入費用7,169円。
読了12冊。
積読本334冊(うちKindle本157冊)。

 いとも優雅な意地悪の教本 (集英社新書)の感想
いとも優雅な意地悪の教本 (集英社新書)の感想2016年「すばる」連載。「意地悪」が主題のよもやま話。バカ、デブに代表される二文字の罵倒言葉は、気分に直結して脊髄反射的に発せられる簡潔な性質ゆえに連打してしまうが、知性を駆使した意地悪な言葉は一発で効くとか、質問に答えず四の五のと冗長に続く答弁は、知性が低いのではなく、知性とモラルが分離しているがゆえにその下品さを自覚せずにいられるからとか、すごいことをやってもすごいということを理解する才能がある人にしか理解されないとか、まあ意地悪な文章のオンパレードで爆笑してしまった。樋口一葉を読みたくなった。
読了日:01月30日 著者:橋本 治

 ちゃぶ台13 特集:三十年後
ちゃぶ台13 特集:三十年後読了日:01月26日 著者:ミシマ社
 ドイツ人のすごい働き方 日本の3倍休んで成果は1.5倍の秘密の感想
ドイツ人のすごい働き方 日本の3倍休んで成果は1.5倍の秘密の感想社会に浸透した労働観をはじめ、教育制度、商習慣、法整備まで素地がかなり異なる点は踏まえておくべきだろう。長期休暇取得や急な欠員を受容する"バックアップシステム"とは、タスク整理や情報共有のシステム化と同時に、余裕を持ったリソース管理が要となる。それはつまり人件費の増加を意味し、かつ生産性を高く保つには、経営効率が確保されていなければならない。ドイツの中小企業割合が日本同様99%を超えている点を考え併せれば、全経営者が教育を受けた経営のプロとは考え難く、経営者および社会の認識に日本との差がありそうだ。
読了日:01月25日 著者:西村 栄基

 老警 (角川文庫)の感想
老警 (角川文庫)の感想老警とはだれか。練られたミステリ。多すぎる情報を疎んでいるとしてやられる。男は女を、親は我が子と組織を、組織は組織と組織内の権力闘争を想って意を決し、それぞれ隠密に行動する。徹底的に被害者やその家族に焦点を当てない、描こうとすらしない、非情がとかく心地悪い。しかし事件が結末を見、終章で作者が書きたかったものが露わになったとき、彼らと彼らの家族に対する私たちの態度は、見ようとしない、無いものであるかのように扱う、同様の非情であると糾弾されたように感じた。閉じてしまったものを開くにはどうすればよいのだろう。
読了日:01月19日 著者:古野 まほろ

 ぼくは古典を読み続ける 珠玉の5冊を堪能するの感想
ぼくは古典を読み続ける 珠玉の5冊を堪能するの感想連続講義の新書化。古典のススメ。今は古典新訳文庫や池澤夏樹編集があるので、古典もとっつきやすくなったものだと思う。だからといって、関心を持てるまでにはそれなりに本を読む時間と、人生の経験値を積み上げることが必要なのではないかな。特に私のように読書は娯楽であると認識して育った人間には。そのうち、より深いものへの渇望が生まれる、そんな印象を覚えた。若いうちにわからないなりに読んでおくにこしたことはないのだけど。気候が安定して政治も安定する豊かな時代には文化や学術が世界同時多発かつ爆発的に発達するのが興味深い。
読了日:01月17日 著者:出口 治明

 マハーバーラタ: インド千夜一夜物語 (光文社新書 47)の感想
マハーバーラタ: インド千夜一夜物語 (光文社新書 47)の感想正月に観るインド映画の基礎知識として。しかし「マハーバーラタ」は長すぎて、しかもパンダヴァvs.カウラヴァの物語以外にも、今昔物語や禅問答めいた小話が多々収められているようだ。本書はそれをピックアップしたもの。登場人物は神、聖仙、王、賢者と堂々たる面子だが、性欲をつい我慢でけんかった話が多くて笑った。生命力旺盛である。デヴァとアスラの戦いも面白い。バラモンが編纂したものなので多分にヒンズー寄りと思いきや、アスラがドラヴィダ、デヴァがアーリアなのにデヴァが侵略したことを認めていて、これもまた大らかである。
読了日:01月13日 著者:山際 素男

 現代家庭療法百科の感想
現代家庭療法百科の感想亡き祖父母の本棚を整理して出てきた本を貰い受けた。主婦の友社、昭和58年の刊。家族の体調が悪くなったとき、昔はネット検索なんてないから、このぶ厚い本を祖母も熱心にめくったのだろう。症状と治療法に始まり、漢方療法、ツボの図解から民間療法まで、痛苦を和らげるためのさまざまの方法を、各分野の専門家監修のもとまとめている。病気の説明は現代に劣るかもしれないが、東洋医学や生活の知恵はむしろ現代より充実していると思われるので手元に置く。本書は医師による適正な治療と争うためではなく、むしろ補う目的とする編集後記が熱い。
風邪・インフルエンザの民間療法を抜き書きしてみる。焼いた梅干し。ショウガ湯。ネギとみそ。するめとネギ。ゴボウとみそ。シイタケとはちみつ。レンコンとキンカン。干し柿。卵酒。黒豆。コマツナ。シソ。ニラ。ニンニク。ヤマイモ。酢。キンカン。ショウガ酒。みそ酒。ネギ。玄米とミカン。黒豆とクルミ。キク。ヨモギ。ニワトコの花。ドクダミ。ゆず湯。梅酢。and so on。エンドレス。これがよかろうあれがよかろうと、それぞれに試して得た生活の知恵は、健康になりたい、家族を楽にしたいと願う人々の思いの集合体である。胸アツ。
読了日:01月13日 著者:
 転がる珠玉のように (単行本)の感想
転がる珠玉のように (単行本)の感想「婦人公論」連載。若干短めのエッセイ。新型コロナの流行期に被っているので、医療関係者や家族の病、死の話題が多め。つられて始終涙ぐんだ。コロナ禍が明けたとて、物価高と生活苦、人不足の話題には事欠かない。でも地べた目線の話は温かみがある。そこにこそ希望を感じる。ならば「クリスマス・キャロル」の精神はなくとも、地べた目線は常に忘れずにありたい。あと、エッセイに起承転結が無いといけないわけではないと思った。起承だけでも、著者のエッセンスはじゅうぶんに発揮されている。Never too late.って素敵な言葉。
著者が保育士になったとき、1年目は子供に病気をもらいまくったが、2年目には鋼鉄の体になったという。人間の体は免疫がつくようにできている。しかし、私たちは今こんなに感染症に振り回されている。これはなぜなのだろう。コロナ禍期の強い行動規制が解除されてもう数年が経つ。隔離やマスクを外した反動だけではないのではないか。過消毒やマイクロバイオームの損失によって、人間という生物自体が弱くなっているんじゃないかとまで思う。あと記憶のスパンも短くなってるが、これはきっとスマホにより依存するようになった、情報過多のせいだ。
読了日:01月12日 著者:ブレイディ みかこ

 インド夜想曲 (白水Uブックス 99 海外小説の誘惑)の感想
インド夜想曲 (白水Uブックス 99 海外小説の誘惑)の感想友人の消息を追って始まるインドの旅。インドの実在の場所を、主人公は初めてではなさそうにするする進んでいく。しかし、主人公の思考がインドらしくない。外国人だから当たり前だけど。行く先々で出会う相手との対話に戸惑い、苛立ち、でも着地点は最初から決まっていたような。持て余す夜の時間の無聊を慰めるためのような。その感じが西洋的で、物語としては私は好きではなかった。一個人の中で完結する、排他的なよそよそしさ、と名づけてみる。私のほうの気持ちがインドに寄りすぎているのかも。夜の駅や、高級ホテルの場面の雰囲気が好い。
読了日:01月11日 著者:アントニオ タブッキ
 “手”をめぐる四百字: 文字は人なり、手は人生なりの感想
“手”をめぐる四百字: 文字は人なり、手は人生なりの感想季刊「銀花」連載。原稿用紙1枚の文章はエッセイとしては短い。しかし百様ならぬ五十様の手跡に目が釘付けになった。写真で挟まれたさまざまの手仕事はもちろん、紙一枚の上に表れる文章のなんと自由なこと。達筆どころか、字面が揃わなかったり、マスからはみ出たり、そもそもマス目を手書きしたり。ああ、これでいいんだ、と、近頃自分の手書き文字の汚さに辟易していた私は胸が軽くなったのだ。出版社からいただいた原稿用紙を持ち出し、写経用の筆ペンで、文字を書く遊びを始めた。マスからついはみ出るような、大らかな字を書く人になりたい。
読了日:01月09日 著者:白洲 正子
 東の海神(わだつみ) 西の滄海 十二国記 3 (新潮文庫)の感想
東の海神(わだつみ) 西の滄海 十二国記 3 (新潮文庫)の感想この正月に引いたおみくじは最高の内容だった。占いというより激励だった。その流れで再読。私にとってこの本は"初心"みたいなもの、かもしれない。小松尚隆は私のメンターなのだ。『なんだ。そう悲壮な顔をしてどうする。どうせなるようにしかならん。軽く構えろ』。国の存亡の危機にあって発した台詞。上に立つ者の心構え、というか。国を守るため自身は必死に考え、体を張って動くのだけれども、どれだけ苦しくてもそれは自分が引き受けるのだと腹を決め、人々には堂々と接し、鷹揚に笑ってみせる。そうあるべしと心得て、今年に挑みたい。
『民は王などいなくても立ち行く。民がいなければ立ち行かないのは王のほうだ。民が額に汗して収穫したものを掠め取って、王はそれで食っている。その代わりに民が一人一人ではできぬことをやってやる』。
読了日:01月07日 著者:小野 不由美
 ガラム・マサラ!の感想
ガラム・マサラ!の感想のっけからフルスピードでまくしたてるから、無分別な青春ギャングものに手を出したかと後悔しかけたが、どうして、これはこれでリアルな現代インド社会を俯瞰した物語の運びが興味深い。チャイ売りの屋台稼業は、インドの社会階層としては中の下の下だそうだ。テレビ番組の人気者になるという上っ面な狂騒と、金持ちになりたいというインド人のいつの時代も変わらぬ夢(?)を土台に、ドタバタが繰り広げられる。"インド人なのに"電子煙草を吸う、また伝統的でない薬物を摂取する、欧米文化にかぶれたインテリ階級への嫌みがスパイス。
『アビはバターチキンが売り切れた結婚式ビュッフェ会場のおじさんのような眼で僕たちを見ていた。それくらい怒っていた』。『食べ放題のビュッフェにいるパンジャブ人のように、僕の心臓は爆発しそうだった』。こういう比喩が秀逸でゲラゲラ笑ってしまう。そしてSRKとアーリア・バットはもはや鉄板ネタね。
読了日:01月01日 著者:ラーフル・ライナ

注:
 は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。 Posted by nekoneko at 17:00│Comments(0)
│読書