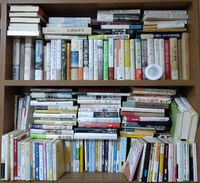2024年02月01日
2024年1月の記録
年末年始はニュースフィードに書評が溢れた。
あれもこれも面白そうだとは思ったものの、
人は皆嗜好/指向が違うものだという事実は忘れずに読む本を選びたい。
あと、深さもある程度見当をつけられるはずなので、
話題の本でも底の見当がつくものには手を出さないようにしたい。
と言った端から買ってしまった。
<今月のデータ>
購入14冊、購入費用13,636円。
読了13冊。
積読本321冊(うちKindle本159冊)。

 武漢コンフィデンシャルの感想
武漢コンフィデンシャルの感想
フィクションである。不謹慎か。でも面白かった。武漢という土地は中国の要衝として歴史が深く、病毒研究所も擁するとあっては、そちら系の人々が水面下で血眼になった様が改めて想像される。新型コロナの蔓延さなか、手嶋さんの血も騒いだのだろう。2019年の武漢をプロローグに、列強に蝕まれた時代の武漢、ワシントンDCの炭疽菌テロ、日本陸軍の七三一部隊、雨傘運動下の香港と、各国を股にかけて物語は進む。たくましく、また美しいひとの物語。しかしいつもの幅広い知識・教養が騒々しい。大国の遣りくちに甲斐なくもため息が出た。
読了日:01月31日 著者:手嶋 龍一
 首都消失 (徳間文庫)の感想
首都消失 (徳間文庫)の感想
1983-84年の新聞連載小説。東京、ブラックアウト。通信も交通も遮断される。日本ごと沈めなくとも、首都を機能不全にしただけで国の存在すら危うくなる。その設定の下に描かれるのは、打ちひしがれる国民ではなく、日本の未来のために闘う男たちだ。戦後の混乱を見た壮年と、知らず現状に憤る若者の反発も絡めつつ、日本国家が民主主義と独立を維持するために何をやらなければならないかの模擬が続く。なかでも防衛(外交)は熾烈な捻じ込みが続き、日本の平和というやつの脆さが強調される。やりすぎに感じるが、当時の共通認識だったのか。
読了日:01月24日 著者:小松左京
 帰れない村 福島県浪江町「DASH村」の10年 (集英社文庫)の感想
帰れない村 福島県浪江町「DASH村」の10年 (集英社文庫)の感想
福島県浪江町、旧津島村。2011年の原発事故による放射能汚染がひどく、住民の帰還の見通しが立たないまま10年が経過した。朝日の連載。600年の歴史がある旧家も、旧満州から引き揚げた人々が命がけで開拓した田畑も、住民が戻ることなく朽ち、草木に覆われていった。故郷を『予期せぬ理由で一方的にはく奪される』痛みが全編に滲む。詮無い仮定だが、もし、戻れる目処が示されていたら、痛みは和らいだか。人々はもっと帰還できたか。今の能登に既視感を覚える。必ず故郷に戻れると、国が被災者に明言しなきゃ、離れられないだろうに。
読了日:01月22日 著者:三浦 英之
 自閉症の僕が跳びはねる理由 (角川文庫)の感想
自閉症の僕が跳びはねる理由 (角川文庫)の感想
自閉症の人と私はどこが違うのだろう。そのヒントがあれば、接するとっかかりも得られるかもと思った。しかし、五感の知覚、言語や記憶処理、感情制御などどれも私とは違う形で発達しているらしい。知性が劣るとか鈍いとか、そういうことではない。人の目を見て発話できないのは私と同じ。わかっていても「できない」。この本は文章による表現という手段を手に入れた著者が13歳の時に書いた。この本の出版を、自閉症の子供を持った世界中の親たちは歓迎したという。子供の心の内面や行動の理由を理解したい。その手掛かりを得たい切実さを想った。
読了日:01月21日 著者:東田 直樹
 シャンタラム(中) (新潮文庫)の感想
シャンタラム(中) (新潮文庫)の感想
なんということ。辛すぎる。失われた笑顔、失われた友情。ムンバイは違いすぎる人間がごった混ぜかつ過密だけど、自分以外の人間がいるから生きていけることを強烈に思わせる。裏切りも投獄も、苦境から舞い戻るリンの姿はかっこよすぎるくらいだ。しかし愛する人を失ったリンの、なんと弱っちいことか。『インド人みたいな心はどこにもない』。歌い、踊り、楽しむことを彼らは独りでやらない。いつも誰かと、誰かのためにやっている。自分で選んだことも、誰かが選んだことによって自分が変わることも、全て編み上げるように人生は進んでいくのだ。
読了日:01月21日 著者:グレゴリー・デイヴィッド ロバーツ
 動画でわかる ヒモトレ入門の感想
動画でわかる ヒモトレ入門の感想
母が脚に違和感を覚えているので対処を教えようと思い、前に読んだ「ヒモトレ革命」を探したが誰に貸したままなのか見当たらない。もはや本屋にも置かれていないので、別のを取り寄せた。ごく薄いが、ひもを使ったトレーニング方法とひも巻きのエッセンスはこれで十分。思いもかけない異分野の専門家たちが、実際にひもを使った効果を言語化しているのは非常に興味深い。身体にまつわる職業がら、素人のぼんやりした感覚とは精度が違う、"変化"が瞬時に知覚されるようなのだ。なんと不思議な人体。ともあれ、まずは巻いてみて、実感してもらおう。
読了日:01月19日 著者:小関 勲
 アナキズム入門 (ちくま新書1245)の感想
アナキズム入門 (ちくま新書1245)の感想
アナキズムって何。という疑問から。国家や権力というものがいつの時代も公平でない以上、それらへの反発や怒り、闘争を元とするアナキズムは、国家と同じだけ歴史を持つ概念ということになる。言葉で抽象的に突き詰めるのは好きじゃないし、その歴史にもあまり興味はなかったのだが、面白かった。狭義では政府や権力集中の否定、ただ広義にはコモンなど馴染みのある意味合いになる。そして人生を労働、生活、地域、自然環境に密接なものと前提して考えることは、私が普段感じていることごとと親和性が高い。クロポトキン。ルクリュ。気になる。
読了日:01月18日 著者:森 元斎
 ほんとうの定年後 「小さな仕事」が日本社会を救う (講談社現代新書)の感想
ほんとうの定年後 「小さな仕事」が日本社会を救う (講談社現代新書)の感想
平均余命までの長い"定年後"を日本人はどう暮らそうとするか。企業の定年規定も年金受給も続々後ろ倒しになり、現役時代と変わらずフルタイムで束縛されて働くなんて人生は気が滅入る。老年期に入っても社会からは労働の担い手、個人としては老後資金の補填のためと語られることが多いが、その働き方は企業の対応如何ではなく、現役時代とは違うスタイルに変わるのだそうだ。短時間勤務や自営などに転じ、意識が学びや社会活動、家庭、趣味に振り向けられると知って安堵した。それにより人生の充足感も得ている、皆がそうなることを願う。
読了日:01月17日 著者:坂本 貴志
 ムスコ物語の感想
ムスコ物語の感想
母に続き息子デルス君にまつわるエッセイ、こちらも興味深かった。マリさんと伴侶の決断に伴って世界を転々とする生活を強制されたことは、日本では奇特な性質を息子に備えた。マリさんはボヘミアンという捉えかたで書いたが、あとがきにデルス君は無謀な親たちに翻弄される成り行きを我慢していたと書き、母の思い及ばないくらい、母親の影響力というものは絶大なのだと知れる。ともあれ今後が楽しみな青年だ。NHKの番組に出演しては各国の著名人と語り合うマリさんが、差別や理不尽な出来事に遭うたび悪態をつきまくるのが意外かつ好ましい。
読了日:01月14日 著者:ヤマザキ マリ
 ダンス・イン・ザ・ファーム 周防大島で坊主と農家と他いろいろの感想
ダンス・イン・ザ・ファーム 周防大島で坊主と農家と他いろいろの感想
地方移住の、ひとつのケース。ミュージシャン稼業が行き詰ってからの転身である。周防大島への移住も農業も、著者より奥さんに先見の明があったと言うべきか。移住し、比較的若手として地域の担い手となり、人の役に立つ。だけなら、こういう人生でなければ私も選んだかもしれないと思う。しかし、それだけでなく人を集めるイベントを企画して、地域や個人の営みを活性化し、またタルマーリーや森田真生氏ら、志向の合った人々が繋がっていくダイナミズムが、私には縁遠いものと感じる。ともあれ、やれそうなことをなんでもやってみる心意気は大事。
読了日:01月13日 著者:中村明珍
 集まる場所が必要だ――孤立を防ぎ、暮らしを守る「開かれた場」の社会学の感想
集まる場所が必要だ――孤立を防ぎ、暮らしを守る「開かれた場」の社会学の感想
頼れるのは遠くの親戚より近くの他人。生活や街の設計は気になっている。著者は社会的インフラの持つ機能と重要性を説く。人々の対面での交流を促進するインフラは、住民の交流や互助行動を増やし、結果として人々のQOLを向上させる。そのための施設を新規に建てるのではなく、既にあるインフラに交流機能を持たせる、また違う機能を持つ施設を掛け合わせるなどの取組が目覚ましい。営利目的ではなく、遠慮や警戒をせずにいることができる、異質な人々がなにかを共有できる場所って大事。市民農園や緑地でもよいのだ。大事なのは排除しないこと。
読了日:01月06日 著者:エリック・クリネンバーグ
 おやじはニーチェ: 認知症の父と過ごした436日の感想
おやじはニーチェ: 認知症の父と過ごした436日の感想
去年ショーペンハウアーで締めたので、明けはニーチェで。周りがこれは認知症だと思ったら認知症なのだそうだ。著者は体は元気な認知症の父と同居することになる。目を離せないから、理不尽さに怒りながらも対話を繰り返す。その反応を理解したいと認知症関連をはじめ言語学、古典文学、哲学まで書籍を読み漁る。父をハムレットに重ね見るあたりなど、つい「まさに!」と納得しかけたが、やっぱりその人の元々の性格じゃないですか。幸か不幸かすぐ忘れるから、試行錯誤しながらやっていける。『忘れるということは、なんとよいことだろう』、か。
読了日:01月03日 著者:髙橋 秀実
 巡礼の感想
巡礼の感想
物語はゴミ屋敷から始まる。臭いや不衛生も当然ながら、主の理解不能な行動に近隣の人々は苛立っている。拾い集めてまでゴミを溜め込む行為は確かに理解不能なのだが、顔の見える距離に暮らしていても、だらしないの悪いのと表層的に切り捨てて、元より知ろうともしない関係性が、皆を追い込んでいく。そして主に視点が移る。昭和らしい一家の年月。誰が悪いわけでもなく、人と人がただやっていくことが難しい。人の業や掛け違い、こじれた記憶が具現化したのだ。守る義務を課せられた者が家に絡めとられるやるせなさ。最後には手放せて良かった。
読了日:01月01日 著者:橋本 治
注: は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。
あれもこれも面白そうだとは思ったものの、
人は皆嗜好/指向が違うものだという事実は忘れずに読む本を選びたい。
あと、深さもある程度見当をつけられるはずなので、
話題の本でも底の見当がつくものには手を出さないようにしたい。
と言った端から買ってしまった。
<今月のデータ>
購入14冊、購入費用13,636円。
読了13冊。
積読本321冊(うちKindle本159冊)。

 武漢コンフィデンシャルの感想
武漢コンフィデンシャルの感想フィクションである。不謹慎か。でも面白かった。武漢という土地は中国の要衝として歴史が深く、病毒研究所も擁するとあっては、そちら系の人々が水面下で血眼になった様が改めて想像される。新型コロナの蔓延さなか、手嶋さんの血も騒いだのだろう。2019年の武漢をプロローグに、列強に蝕まれた時代の武漢、ワシントンDCの炭疽菌テロ、日本陸軍の七三一部隊、雨傘運動下の香港と、各国を股にかけて物語は進む。たくましく、また美しいひとの物語。しかしいつもの幅広い知識・教養が騒々しい。大国の遣りくちに甲斐なくもため息が出た。
読了日:01月31日 著者:手嶋 龍一

 首都消失 (徳間文庫)の感想
首都消失 (徳間文庫)の感想1983-84年の新聞連載小説。東京、ブラックアウト。通信も交通も遮断される。日本ごと沈めなくとも、首都を機能不全にしただけで国の存在すら危うくなる。その設定の下に描かれるのは、打ちひしがれる国民ではなく、日本の未来のために闘う男たちだ。戦後の混乱を見た壮年と、知らず現状に憤る若者の反発も絡めつつ、日本国家が民主主義と独立を維持するために何をやらなければならないかの模擬が続く。なかでも防衛(外交)は熾烈な捻じ込みが続き、日本の平和というやつの脆さが強調される。やりすぎに感じるが、当時の共通認識だったのか。
読了日:01月24日 著者:小松左京

 帰れない村 福島県浪江町「DASH村」の10年 (集英社文庫)の感想
帰れない村 福島県浪江町「DASH村」の10年 (集英社文庫)の感想福島県浪江町、旧津島村。2011年の原発事故による放射能汚染がひどく、住民の帰還の見通しが立たないまま10年が経過した。朝日の連載。600年の歴史がある旧家も、旧満州から引き揚げた人々が命がけで開拓した田畑も、住民が戻ることなく朽ち、草木に覆われていった。故郷を『予期せぬ理由で一方的にはく奪される』痛みが全編に滲む。詮無い仮定だが、もし、戻れる目処が示されていたら、痛みは和らいだか。人々はもっと帰還できたか。今の能登に既視感を覚える。必ず故郷に戻れると、国が被災者に明言しなきゃ、離れられないだろうに。
読了日:01月22日 著者:三浦 英之

 自閉症の僕が跳びはねる理由 (角川文庫)の感想
自閉症の僕が跳びはねる理由 (角川文庫)の感想自閉症の人と私はどこが違うのだろう。そのヒントがあれば、接するとっかかりも得られるかもと思った。しかし、五感の知覚、言語や記憶処理、感情制御などどれも私とは違う形で発達しているらしい。知性が劣るとか鈍いとか、そういうことではない。人の目を見て発話できないのは私と同じ。わかっていても「できない」。この本は文章による表現という手段を手に入れた著者が13歳の時に書いた。この本の出版を、自閉症の子供を持った世界中の親たちは歓迎したという。子供の心の内面や行動の理由を理解したい。その手掛かりを得たい切実さを想った。
読了日:01月21日 著者:東田 直樹

 シャンタラム(中) (新潮文庫)の感想
シャンタラム(中) (新潮文庫)の感想なんということ。辛すぎる。失われた笑顔、失われた友情。ムンバイは違いすぎる人間がごった混ぜかつ過密だけど、自分以外の人間がいるから生きていけることを強烈に思わせる。裏切りも投獄も、苦境から舞い戻るリンの姿はかっこよすぎるくらいだ。しかし愛する人を失ったリンの、なんと弱っちいことか。『インド人みたいな心はどこにもない』。歌い、踊り、楽しむことを彼らは独りでやらない。いつも誰かと、誰かのためにやっている。自分で選んだことも、誰かが選んだことによって自分が変わることも、全て編み上げるように人生は進んでいくのだ。
読了日:01月21日 著者:グレゴリー・デイヴィッド ロバーツ
 動画でわかる ヒモトレ入門の感想
動画でわかる ヒモトレ入門の感想母が脚に違和感を覚えているので対処を教えようと思い、前に読んだ「ヒモトレ革命」を探したが誰に貸したままなのか見当たらない。もはや本屋にも置かれていないので、別のを取り寄せた。ごく薄いが、ひもを使ったトレーニング方法とひも巻きのエッセンスはこれで十分。思いもかけない異分野の専門家たちが、実際にひもを使った効果を言語化しているのは非常に興味深い。身体にまつわる職業がら、素人のぼんやりした感覚とは精度が違う、"変化"が瞬時に知覚されるようなのだ。なんと不思議な人体。ともあれ、まずは巻いてみて、実感してもらおう。
読了日:01月19日 著者:小関 勲
 アナキズム入門 (ちくま新書1245)の感想
アナキズム入門 (ちくま新書1245)の感想アナキズムって何。という疑問から。国家や権力というものがいつの時代も公平でない以上、それらへの反発や怒り、闘争を元とするアナキズムは、国家と同じだけ歴史を持つ概念ということになる。言葉で抽象的に突き詰めるのは好きじゃないし、その歴史にもあまり興味はなかったのだが、面白かった。狭義では政府や権力集中の否定、ただ広義にはコモンなど馴染みのある意味合いになる。そして人生を労働、生活、地域、自然環境に密接なものと前提して考えることは、私が普段感じていることごとと親和性が高い。クロポトキン。ルクリュ。気になる。
読了日:01月18日 著者:森 元斎

 ほんとうの定年後 「小さな仕事」が日本社会を救う (講談社現代新書)の感想
ほんとうの定年後 「小さな仕事」が日本社会を救う (講談社現代新書)の感想平均余命までの長い"定年後"を日本人はどう暮らそうとするか。企業の定年規定も年金受給も続々後ろ倒しになり、現役時代と変わらずフルタイムで束縛されて働くなんて人生は気が滅入る。老年期に入っても社会からは労働の担い手、個人としては老後資金の補填のためと語られることが多いが、その働き方は企業の対応如何ではなく、現役時代とは違うスタイルに変わるのだそうだ。短時間勤務や自営などに転じ、意識が学びや社会活動、家庭、趣味に振り向けられると知って安堵した。それにより人生の充足感も得ている、皆がそうなることを願う。
読了日:01月17日 著者:坂本 貴志

 ムスコ物語の感想
ムスコ物語の感想母に続き息子デルス君にまつわるエッセイ、こちらも興味深かった。マリさんと伴侶の決断に伴って世界を転々とする生活を強制されたことは、日本では奇特な性質を息子に備えた。マリさんはボヘミアンという捉えかたで書いたが、あとがきにデルス君は無謀な親たちに翻弄される成り行きを我慢していたと書き、母の思い及ばないくらい、母親の影響力というものは絶大なのだと知れる。ともあれ今後が楽しみな青年だ。NHKの番組に出演しては各国の著名人と語り合うマリさんが、差別や理不尽な出来事に遭うたび悪態をつきまくるのが意外かつ好ましい。
読了日:01月14日 著者:ヤマザキ マリ

 ダンス・イン・ザ・ファーム 周防大島で坊主と農家と他いろいろの感想
ダンス・イン・ザ・ファーム 周防大島で坊主と農家と他いろいろの感想地方移住の、ひとつのケース。ミュージシャン稼業が行き詰ってからの転身である。周防大島への移住も農業も、著者より奥さんに先見の明があったと言うべきか。移住し、比較的若手として地域の担い手となり、人の役に立つ。だけなら、こういう人生でなければ私も選んだかもしれないと思う。しかし、それだけでなく人を集めるイベントを企画して、地域や個人の営みを活性化し、またタルマーリーや森田真生氏ら、志向の合った人々が繋がっていくダイナミズムが、私には縁遠いものと感じる。ともあれ、やれそうなことをなんでもやってみる心意気は大事。
読了日:01月13日 著者:中村明珍
 集まる場所が必要だ――孤立を防ぎ、暮らしを守る「開かれた場」の社会学の感想
集まる場所が必要だ――孤立を防ぎ、暮らしを守る「開かれた場」の社会学の感想頼れるのは遠くの親戚より近くの他人。生活や街の設計は気になっている。著者は社会的インフラの持つ機能と重要性を説く。人々の対面での交流を促進するインフラは、住民の交流や互助行動を増やし、結果として人々のQOLを向上させる。そのための施設を新規に建てるのではなく、既にあるインフラに交流機能を持たせる、また違う機能を持つ施設を掛け合わせるなどの取組が目覚ましい。営利目的ではなく、遠慮や警戒をせずにいることができる、異質な人々がなにかを共有できる場所って大事。市民農園や緑地でもよいのだ。大事なのは排除しないこと。
読了日:01月06日 著者:エリック・クリネンバーグ

 おやじはニーチェ: 認知症の父と過ごした436日の感想
おやじはニーチェ: 認知症の父と過ごした436日の感想去年ショーペンハウアーで締めたので、明けはニーチェで。周りがこれは認知症だと思ったら認知症なのだそうだ。著者は体は元気な認知症の父と同居することになる。目を離せないから、理不尽さに怒りながらも対話を繰り返す。その反応を理解したいと認知症関連をはじめ言語学、古典文学、哲学まで書籍を読み漁る。父をハムレットに重ね見るあたりなど、つい「まさに!」と納得しかけたが、やっぱりその人の元々の性格じゃないですか。幸か不幸かすぐ忘れるから、試行錯誤しながらやっていける。『忘れるということは、なんとよいことだろう』、か。
読了日:01月03日 著者:髙橋 秀実

 巡礼の感想
巡礼の感想物語はゴミ屋敷から始まる。臭いや不衛生も当然ながら、主の理解不能な行動に近隣の人々は苛立っている。拾い集めてまでゴミを溜め込む行為は確かに理解不能なのだが、顔の見える距離に暮らしていても、だらしないの悪いのと表層的に切り捨てて、元より知ろうともしない関係性が、皆を追い込んでいく。そして主に視点が移る。昭和らしい一家の年月。誰が悪いわけでもなく、人と人がただやっていくことが難しい。人の業や掛け違い、こじれた記憶が具現化したのだ。守る義務を課せられた者が家に絡めとられるやるせなさ。最後には手放せて良かった。
読了日:01月01日 著者:橋本 治

注:
 は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。 Posted by nekoneko at 13:09│Comments(0)
│読書