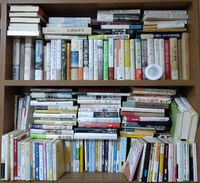2018年04月02日
2018年3月の記録
Kindle本で読みたいものをチェックするのに、ほしい物リストに入れておく。
読みたい本が増えすぎて、たぶん300冊くらいになっている。
たぶん、というのは、システム変更で冊数がわからなくなったから。
リストに入れた本の検索もできなくなって、そのまま放置。
日替わりセールのメールも来なくなって、Kindle本を買うことが減った。
不便さには不満だが、衝動買いが減るのはいいことだ。
<今月のデータ>
購入14冊、購入費用13,646円。
読了14冊。
積読本108冊(うちKindle本21冊)。

3月の読書メーター
読んだ本の数:14
 ほんとうの環境問題の感想
ほんとうの環境問題の感想
池田氏の散文の後に、養老先生との対談がある形式。氏の持論はトンデモに聞こえるが、いわゆる温暖化や廃棄物問題にしても、再考の価値が多々ある。つまり、省エネや新しい消費材の普及を国連及び政府が号令することにより、世界各国営利企業が開発を競い、無駄な購買を煽るなど確かにあるからだ。しかし、読み手に対する敬意が決定的に足りない。例えば殺処分される犬を廃犬と呼び、殺処分するくらいなら食料自給率を上げるために食べたらどうだなど、表現が乱暴で到底受け入れられない。知性の下品な発露と呼びたい。真剣に読む気が削がれて残念。
読了日:03月30日 著者:池田 清彦,養老 孟司
 雪男は向こうからやって来た (集英社文庫)の感想
雪男は向こうからやって来た (集英社文庫)の感想
「雪男はいない」は証明できない。そして著名な登山家を含め幾人もが同じダウラギリ山系近くで目撃したとあっては只事でない。日本での調査と現地での探索との構成が綿密で、飽きさせない。そこは物理的にも精神的にも、人間には尋常ならぬ場所だ。様々な条件が重なったとき、人は雪原に「目撃する」。エピローグで著者は、現地での自身の体験と心象の変化、目撃者の証言や客観的データを冷静に分析する。この真面目さ、私は好きだ。タイトルも、その意味がわかった瞬間、人生の運命の不思議さに震えた。良いノンフィクション。続編ぜひ期待します。
読了日:03月28日 著者:角幡 唯介
 日本人は何を食べてきたか―食の民俗学の感想
日本人は何を食べてきたか―食の民俗学の感想
マクドゥーガルによれば、クレタ人たちは低糖質の質素な食事によって身体のパフォーマンスを最大限まで発揮したという。では、高糖質の米を主食とする日本人はどうだったか。日本人もかつては、現代人が信じられない程高い身体能力を発揮していた。実は米が半分も入らない糅飯(かてめし)を主食に、地で採れる菜と共に、一汁一菜で少しずつ食べていたようだ。「白い米をいっぱい食う」は貧しさ故の幻想でしかなく、現代日本人は明らかに食べ過ぎである。ちなみに冠婚葬祭等で供される会席が食べきれない量なのは、家内に持ち帰る宗教的慣わしの為。
読了日:03月25日 著者:神崎 宣武
 辺境中毒! (集英社文庫)の感想
辺境中毒! (集英社文庫)の感想
息抜きに。2011年までに各紙に掲載されたもので、主にアジアでの単行本からはみ出たエピソードと、対談。対談相手には内澤さんや角幡氏もおり、話の盛り上がりようを見ると、系統は近いのだろう。「未知の本当」は私の大好物だ。話の内容から、対談と各氏の著作との時系列がわかる。ブックガイドも面白そうで、漏らさずメモを取った。なぜなら、他方面からこれらの本を紹介される機会はないと予想されるから。底抜けに面白い高野本の、骨となる考え方をうかがい知れる。他の長編を読んでからがおすすめ。『旅に持って行くには燃費のよい本』。
読了日:03月22日 著者:高野 秀行
 老いる家 崩れる街 住宅過剰社会の末路 (講談社現代新書)の感想
老いる家 崩れる街 住宅過剰社会の末路 (講談社現代新書)の感想
「焼畑的」とは言い得て妙で、将来の資産である農地をどんどん潰して、20年程しか持たない一軒家や賃貸住宅を建てる風景はもう珍しくない。中高層マンションも増える一方で、個人・企業とも余りに近視眼的だ。原因は1968年に制定された都市計画法の緩和改正、地方分権としての市町村への権限移譲に主にあると見た。超高齢化と人口減少が確実な日本で、もはや建物や土地は資産にならない。行政の再規制・誘導が急がれるだろう。放棄された空き家を管理し、有益な運用を担う非営利組織「ランドバンク」が興味深い。日本でも検討されたようだ。
読了日:03月19日 著者:野澤 千絵
 石牟礼道子歳時記 (1978年)の感想
石牟礼道子歳時記 (1978年)の感想
1978年刊。ご本人が「歳時記」と銘打って選んだのではないだろう。装丁は素敵だが、ただ12編のエッセイ集だ。著者の文章は多数あるだろうに、なぜこれらが選ばれたかは不明。日々の描写の、身に沁み込んだ暮らしの様子や、おそらく意識せずに使うような土地の言葉が滋味深く、面白い。まだ見ぬ子孫のためにと年寄りが果樹を庭に植える習わし「手型の樹」、不知火湾へ牡蠣など海のものを採りに行く高揚感など、生き生きとして胸が切なくなる。ただ、石牟礼文学の魅力は人々の発声する「言葉」にあると私は思っているから、もの足りなく思った。
読了日:03月18日 著者:石牟礼 道子
 LEAN IN(リーン・イン) 女性、仕事、リーダーへの意欲の感想
LEAN IN(リーン・イン) 女性、仕事、リーダーへの意欲の感想
社会で女性が働くことにまつわる問題と、解決の糸口を提起する。COOの地位は、強固な野心ではなく、やりたいと思った仕事を選んだ結果だ。しかし女性故に、交渉や提案には男性の何倍もの注意と先回りが必要だった。自分を殺さず、より良く生きるための考え方を書き留める。男女問わず、キャリアパスは今や梯子でなくジャングルジム。道は一つではないと考える柔軟さと、長期の計画を立てない勇気。率直に個人的な事情を明かし相談する勇気。感情は仕事と切り離せないものと認める勇気。自分にも他人にも厳しいことを良しとしてきた私への提言だ。
読了日:03月18日 著者:シェリル・サンドバーグ
 ゆるめる力 骨ストレッチの感想
ゆるめる力 骨ストレッチの感想
骨が豊かと書いて體。筋肉ではなく骨を意識し、身体の連携を保ったままで身体をゆるめることに主眼を置く。身体のストレッチ本は多々あるけれど、このメソッドは流行りものと流すのはもったいないと思う。まあ、私は自分の身体感覚を信じることができない性質なので、甲野先生の思想を受け継ぐ方の着眼したメソッドなら間違いないという論理だ。自分に必要なメソッドを備忘の為に書き出す。手首肩甲骨ストレッチ、鎖骨ひねり、手首腰伸ばし、烏口突起ほぐし、腸ほぐし、マグロの中落ち、手ほどき・足ほどき、手のひら返し、中指ウォーキング。
読了日:03月18日 著者:松村 卓
 限りなく完璧に近い人々 なぜ北欧の暮らしは世界一幸せなのか?の感想
限りなく完璧に近い人々 なぜ北欧の暮らしは世界一幸せなのか?の感想
遠く離れた北欧の社会システムを日本人は賛美する。世界的にその傾向は強く、著者は集団妄想を粉砕すべく貪欲に調査した。5か国各々を訪れ、扱き下ろし、持ち上げ、歴史や政治、生活、国民性、その差異を上手く描写している。互いに近隣国に思うところがあっても、総じてうまくいっているようで、やはり麗しく、魅力的だ。「人生を主体的に生きる」社会を希求し、なお変わることができる柔軟性がある。北欧ミステリは総じて陰惨だが、社会の暗部を憂慮する面が強く出るのだろう。時間をかけて読んだのに、やはり国がごっちゃになった。
読了日:03月16日 著者:マイケル・ブース
 北海に消えた少女(ハヤカワ・ミステリ文庫)の感想
北海に消えた少女(ハヤカワ・ミステリ文庫)の感想
口も腕も立つ女性ジャーナリスト。全力で仕事をこなし、恋を選ぶこともできる。しかし社会が男女平等を標榜しようとも、心身を脅かされる危険性は男性より女性が断然高いと著者は明に暗に示す。残虐な犯罪を追う中で、主人公は身の丈を超えた危険の予感に震える。助けを求めたときに、警察も家族も当てにならないと知った絶望感が、独力で事件を解決する方向へと彼女を動かす。翻訳も含め、小説として洗練されていないことにより、心許なさが増幅される。服の管理ができないなど細かいキャラ立てが上手い。恋の行方にはこちらが焦がれ死にしそうだ。
読了日:03月10日 著者:ローネ タイルス,Lone Theils
 方丈記の感想
方丈記の感想
鎌倉時代のエッセイ。老境に至り過去を思い起こして書き残したもの。案外短い。古文の素養が程々でも、素読で大意は掴める。学生の頃は、なるほど昔の日本人は粗野で卑しかったんやなぁと感慨していたが、こちらも大人になると現代の日本人もなんら変わらんなぁという感想に変わる。方丈とはいえ立派な構築物だし、隠棲とは羨ましくもあるけれど、鴨長明も覚ったようでいて、なにがあったんか知らんがひねこびた性格が捨てきれない業がにじむ。静かで憂いない、自分の為だけの暮らし。飢饉のとき、山へ移り住んだ人々がいたという。困ったら山だ。
読了日:03月08日 著者:鴨 長明
 遺言。 (新潮新書)の感想
遺言。 (新潮新書)の感想
丁寧に書かれたエッセイ。行儀よく論理が並び、得意技の縦横無尽飛びも無し。ただし必要と考える以上の説明は突っ撥ねられるから、襟を正して読む気にさせられる。さて、ヒトの社会は「意識」ありき。論理的なはずの説明に、養老節が可笑しすぎる。しかしそれはヒトの存在を自ら限った場所に置く行為のおかしさでもある。情報や科学をヒトが世界を理解するための手段とする一方、それが意識の仕業だと常に前提する必要があるだろうと。意識と感覚の乖離及び対立への警鐘。養老先生自身の人生を通じた探求との密接を感じ取れる論理が深い。脚下照顧。
読了日:03月06日 著者:養老 孟司
 小暮写眞館(下) (講談社文庫)の感想
小暮写眞館(下) (講談社文庫)の感想
当然ながら、花菱家にも闇はあるのである。上巻で丁寧に張られた伏線は、下巻で丁寧に回収される。わずか、ついに小暮さんには会えなかったことが、心残りのような余韻として漂う。宮部さんは「模倣犯」のような辛い物語を書くのが嫌になったと言う。読み手だってそうだ。人生の機微を知るほど、登場人物の痛みを無意識に汲んで、実生活に響く位の衝撃を受けることだってある。だから、痛ましい事件の起きない物語を求めるのだ。ただ、刑事事件が起きないからといって、痛みがないわけではない。ピカちゃんの涙は、大人の悲しみを超えて余りあった。
読了日:03月02日 著者:宮部 みゆき
 あなたに褒められたくて (集英社文庫)の感想
あなたに褒められたくて (集英社文庫)の感想
父が自身の母を亡くした春に。タイトルの「あなた」はお母様のことと予感して手に取ったエッセイ。あの口調で思い出を語り、読み手の情を喚起する、成熟した男の象徴、高倉健。だけではなかった。好んで重ねた外国への旅や、故郷の北九州の海のエピソード。でも、格好良いだけの本にはしたくなかったのだろう。欲しくなった物は後先考えず買っちゃう困ったさんだったり、映画撮影現場のスタッフにしかける嘘やいたずらが小学生みたいな発想で、かつ犯罪すれすれだったり、ついには「もてる」って自分で言っちゃった。偶像視、してたみたい…。
読了日:03月01日 著者:高倉 健
注: はKindleで読んだ本。
はKindleで読んだ本。
読みたい本が増えすぎて、たぶん300冊くらいになっている。
たぶん、というのは、システム変更で冊数がわからなくなったから。
リストに入れた本の検索もできなくなって、そのまま放置。
日替わりセールのメールも来なくなって、Kindle本を買うことが減った。
不便さには不満だが、衝動買いが減るのはいいことだ。
<今月のデータ>
購入14冊、購入費用13,646円。
読了14冊。
積読本108冊(うちKindle本21冊)。

3月の読書メーター
読んだ本の数:14
 ほんとうの環境問題の感想
ほんとうの環境問題の感想池田氏の散文の後に、養老先生との対談がある形式。氏の持論はトンデモに聞こえるが、いわゆる温暖化や廃棄物問題にしても、再考の価値が多々ある。つまり、省エネや新しい消費材の普及を国連及び政府が号令することにより、世界各国営利企業が開発を競い、無駄な購買を煽るなど確かにあるからだ。しかし、読み手に対する敬意が決定的に足りない。例えば殺処分される犬を廃犬と呼び、殺処分するくらいなら食料自給率を上げるために食べたらどうだなど、表現が乱暴で到底受け入れられない。知性の下品な発露と呼びたい。真剣に読む気が削がれて残念。
読了日:03月30日 著者:池田 清彦,養老 孟司
 雪男は向こうからやって来た (集英社文庫)の感想
雪男は向こうからやって来た (集英社文庫)の感想「雪男はいない」は証明できない。そして著名な登山家を含め幾人もが同じダウラギリ山系近くで目撃したとあっては只事でない。日本での調査と現地での探索との構成が綿密で、飽きさせない。そこは物理的にも精神的にも、人間には尋常ならぬ場所だ。様々な条件が重なったとき、人は雪原に「目撃する」。エピローグで著者は、現地での自身の体験と心象の変化、目撃者の証言や客観的データを冷静に分析する。この真面目さ、私は好きだ。タイトルも、その意味がわかった瞬間、人生の運命の不思議さに震えた。良いノンフィクション。続編ぜひ期待します。
読了日:03月28日 著者:角幡 唯介

 日本人は何を食べてきたか―食の民俗学の感想
日本人は何を食べてきたか―食の民俗学の感想マクドゥーガルによれば、クレタ人たちは低糖質の質素な食事によって身体のパフォーマンスを最大限まで発揮したという。では、高糖質の米を主食とする日本人はどうだったか。日本人もかつては、現代人が信じられない程高い身体能力を発揮していた。実は米が半分も入らない糅飯(かてめし)を主食に、地で採れる菜と共に、一汁一菜で少しずつ食べていたようだ。「白い米をいっぱい食う」は貧しさ故の幻想でしかなく、現代日本人は明らかに食べ過ぎである。ちなみに冠婚葬祭等で供される会席が食べきれない量なのは、家内に持ち帰る宗教的慣わしの為。
読了日:03月25日 著者:神崎 宣武
 辺境中毒! (集英社文庫)の感想
辺境中毒! (集英社文庫)の感想息抜きに。2011年までに各紙に掲載されたもので、主にアジアでの単行本からはみ出たエピソードと、対談。対談相手には内澤さんや角幡氏もおり、話の盛り上がりようを見ると、系統は近いのだろう。「未知の本当」は私の大好物だ。話の内容から、対談と各氏の著作との時系列がわかる。ブックガイドも面白そうで、漏らさずメモを取った。なぜなら、他方面からこれらの本を紹介される機会はないと予想されるから。底抜けに面白い高野本の、骨となる考え方をうかがい知れる。他の長編を読んでからがおすすめ。『旅に持って行くには燃費のよい本』。
読了日:03月22日 著者:高野 秀行

 老いる家 崩れる街 住宅過剰社会の末路 (講談社現代新書)の感想
老いる家 崩れる街 住宅過剰社会の末路 (講談社現代新書)の感想「焼畑的」とは言い得て妙で、将来の資産である農地をどんどん潰して、20年程しか持たない一軒家や賃貸住宅を建てる風景はもう珍しくない。中高層マンションも増える一方で、個人・企業とも余りに近視眼的だ。原因は1968年に制定された都市計画法の緩和改正、地方分権としての市町村への権限移譲に主にあると見た。超高齢化と人口減少が確実な日本で、もはや建物や土地は資産にならない。行政の再規制・誘導が急がれるだろう。放棄された空き家を管理し、有益な運用を担う非営利組織「ランドバンク」が興味深い。日本でも検討されたようだ。
読了日:03月19日 著者:野澤 千絵

 石牟礼道子歳時記 (1978年)の感想
石牟礼道子歳時記 (1978年)の感想1978年刊。ご本人が「歳時記」と銘打って選んだのではないだろう。装丁は素敵だが、ただ12編のエッセイ集だ。著者の文章は多数あるだろうに、なぜこれらが選ばれたかは不明。日々の描写の、身に沁み込んだ暮らしの様子や、おそらく意識せずに使うような土地の言葉が滋味深く、面白い。まだ見ぬ子孫のためにと年寄りが果樹を庭に植える習わし「手型の樹」、不知火湾へ牡蠣など海のものを採りに行く高揚感など、生き生きとして胸が切なくなる。ただ、石牟礼文学の魅力は人々の発声する「言葉」にあると私は思っているから、もの足りなく思った。
読了日:03月18日 著者:石牟礼 道子
 LEAN IN(リーン・イン) 女性、仕事、リーダーへの意欲の感想
LEAN IN(リーン・イン) 女性、仕事、リーダーへの意欲の感想社会で女性が働くことにまつわる問題と、解決の糸口を提起する。COOの地位は、強固な野心ではなく、やりたいと思った仕事を選んだ結果だ。しかし女性故に、交渉や提案には男性の何倍もの注意と先回りが必要だった。自分を殺さず、より良く生きるための考え方を書き留める。男女問わず、キャリアパスは今や梯子でなくジャングルジム。道は一つではないと考える柔軟さと、長期の計画を立てない勇気。率直に個人的な事情を明かし相談する勇気。感情は仕事と切り離せないものと認める勇気。自分にも他人にも厳しいことを良しとしてきた私への提言だ。
読了日:03月18日 著者:シェリル・サンドバーグ
 ゆるめる力 骨ストレッチの感想
ゆるめる力 骨ストレッチの感想骨が豊かと書いて體。筋肉ではなく骨を意識し、身体の連携を保ったままで身体をゆるめることに主眼を置く。身体のストレッチ本は多々あるけれど、このメソッドは流行りものと流すのはもったいないと思う。まあ、私は自分の身体感覚を信じることができない性質なので、甲野先生の思想を受け継ぐ方の着眼したメソッドなら間違いないという論理だ。自分に必要なメソッドを備忘の為に書き出す。手首肩甲骨ストレッチ、鎖骨ひねり、手首腰伸ばし、烏口突起ほぐし、腸ほぐし、マグロの中落ち、手ほどき・足ほどき、手のひら返し、中指ウォーキング。
読了日:03月18日 著者:松村 卓
 限りなく完璧に近い人々 なぜ北欧の暮らしは世界一幸せなのか?の感想
限りなく完璧に近い人々 なぜ北欧の暮らしは世界一幸せなのか?の感想遠く離れた北欧の社会システムを日本人は賛美する。世界的にその傾向は強く、著者は集団妄想を粉砕すべく貪欲に調査した。5か国各々を訪れ、扱き下ろし、持ち上げ、歴史や政治、生活、国民性、その差異を上手く描写している。互いに近隣国に思うところがあっても、総じてうまくいっているようで、やはり麗しく、魅力的だ。「人生を主体的に生きる」社会を希求し、なお変わることができる柔軟性がある。北欧ミステリは総じて陰惨だが、社会の暗部を憂慮する面が強く出るのだろう。時間をかけて読んだのに、やはり国がごっちゃになった。
読了日:03月16日 著者:マイケル・ブース

 北海に消えた少女(ハヤカワ・ミステリ文庫)の感想
北海に消えた少女(ハヤカワ・ミステリ文庫)の感想口も腕も立つ女性ジャーナリスト。全力で仕事をこなし、恋を選ぶこともできる。しかし社会が男女平等を標榜しようとも、心身を脅かされる危険性は男性より女性が断然高いと著者は明に暗に示す。残虐な犯罪を追う中で、主人公は身の丈を超えた危険の予感に震える。助けを求めたときに、警察も家族も当てにならないと知った絶望感が、独力で事件を解決する方向へと彼女を動かす。翻訳も含め、小説として洗練されていないことにより、心許なさが増幅される。服の管理ができないなど細かいキャラ立てが上手い。恋の行方にはこちらが焦がれ死にしそうだ。
読了日:03月10日 著者:ローネ タイルス,Lone Theils
 方丈記の感想
方丈記の感想鎌倉時代のエッセイ。老境に至り過去を思い起こして書き残したもの。案外短い。古文の素養が程々でも、素読で大意は掴める。学生の頃は、なるほど昔の日本人は粗野で卑しかったんやなぁと感慨していたが、こちらも大人になると現代の日本人もなんら変わらんなぁという感想に変わる。方丈とはいえ立派な構築物だし、隠棲とは羨ましくもあるけれど、鴨長明も覚ったようでいて、なにがあったんか知らんがひねこびた性格が捨てきれない業がにじむ。静かで憂いない、自分の為だけの暮らし。飢饉のとき、山へ移り住んだ人々がいたという。困ったら山だ。
読了日:03月08日 著者:鴨 長明

 遺言。 (新潮新書)の感想
遺言。 (新潮新書)の感想丁寧に書かれたエッセイ。行儀よく論理が並び、得意技の縦横無尽飛びも無し。ただし必要と考える以上の説明は突っ撥ねられるから、襟を正して読む気にさせられる。さて、ヒトの社会は「意識」ありき。論理的なはずの説明に、養老節が可笑しすぎる。しかしそれはヒトの存在を自ら限った場所に置く行為のおかしさでもある。情報や科学をヒトが世界を理解するための手段とする一方、それが意識の仕業だと常に前提する必要があるだろうと。意識と感覚の乖離及び対立への警鐘。養老先生自身の人生を通じた探求との密接を感じ取れる論理が深い。脚下照顧。
読了日:03月06日 著者:養老 孟司

 小暮写眞館(下) (講談社文庫)の感想
小暮写眞館(下) (講談社文庫)の感想当然ながら、花菱家にも闇はあるのである。上巻で丁寧に張られた伏線は、下巻で丁寧に回収される。わずか、ついに小暮さんには会えなかったことが、心残りのような余韻として漂う。宮部さんは「模倣犯」のような辛い物語を書くのが嫌になったと言う。読み手だってそうだ。人生の機微を知るほど、登場人物の痛みを無意識に汲んで、実生活に響く位の衝撃を受けることだってある。だから、痛ましい事件の起きない物語を求めるのだ。ただ、刑事事件が起きないからといって、痛みがないわけではない。ピカちゃんの涙は、大人の悲しみを超えて余りあった。
読了日:03月02日 著者:宮部 みゆき
 あなたに褒められたくて (集英社文庫)の感想
あなたに褒められたくて (集英社文庫)の感想父が自身の母を亡くした春に。タイトルの「あなた」はお母様のことと予感して手に取ったエッセイ。あの口調で思い出を語り、読み手の情を喚起する、成熟した男の象徴、高倉健。だけではなかった。好んで重ねた外国への旅や、故郷の北九州の海のエピソード。でも、格好良いだけの本にはしたくなかったのだろう。欲しくなった物は後先考えず買っちゃう困ったさんだったり、映画撮影現場のスタッフにしかける嘘やいたずらが小学生みたいな発想で、かつ犯罪すれすれだったり、ついには「もてる」って自分で言っちゃった。偶像視、してたみたい…。
読了日:03月01日 著者:高倉 健

注:
 はKindleで読んだ本。
はKindleで読んだ本。 Posted by nekoneko at 08:43│Comments(0)
│読書