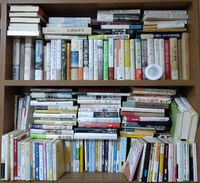2022年01月05日
2021年12月の記録
積読は一気に加速して300冊の大台を突破した。
半分は電子書籍になった。
電子書籍の市場が熟成しつつあるということなのか、明らかにセールが増えた。
年末などモグラたたきのようで大変だった。財布が。
新刊では考えられないような値段で"本"が手元に転がり込んでくるので、情報の獲得に怠りないよう毎日PC画面を眺め渡している。
装丁が素敵な本や、電子で読んで手元に置きたいものは本で買い直すが、電子市場が活性化すればするほど本の印刷や装丁にかかるコストは逆に増し、贅沢品になってゆくのだろう。
<今月のデータ>
購入32冊、購入費用36,849円。
読了12冊。
積読本301冊(うちKindle本136冊、Honto本14冊)。

12月の読書メーター
読んだ本の数:12
 エレファントム 象はなぜ遠い記憶を語るのかの感想
エレファントム 象はなぜ遠い記憶を語るのかの感想
海に臨む象の姿が心に残る。地位ある者も貧しき者も欧米人も現地人も、皆して象を狩った長い時代の果てに南アフリカの今がある。著者はローレンツに教えを乞う機会を得ながら拒み、デズモンド・モリスに師事して動物行動学を学んだ。象を"自然の生んだ大天使"と呼ぶ。その歴史や生態を追ったのは、著者が幼い頃出会った白い象と!カンマの記憶があったからだ。象は遊び、おどけ、怒り、超低周波音や足音を使ってはるか遠くの象と意思疎通する。象のことを理解したいならこちらをお勧めしたい。人間の知らないことはまだまだあるに違いないから。
当然、ワトソン氏も動物園という施設には懐疑的だったが、動物行動学者としてヨハネスブルグ動物園の勤務を引き受けた。そこにいたデライラは、初対面のワトソン氏に食べ物より友情を求め、檻の中で先に逝った同族を悼む儀式を行ない、ライオンとワトソン氏の間に立ちはだかって全身で威嚇する姿を見せる。象の世界の深さを、おおかたの人間は理解どころか、未だ知ってすらいないのだ。現代の動物園は、当時より進化しているだろうか。それとも、現代の動物園の象は、象から象へ伝わる智を受け継ぐ術もなく孤立し、鬱々と過ごしているのだろうか。
読了日:12月28日 著者:ライアル・ワトソン
 歌おう、感電するほどの喜びを!〔新版〕 (ハヤカワ文庫 SF フ 16-8)の感想
歌おう、感電するほどの喜びを!〔新版〕 (ハヤカワ文庫 SF フ 16-8)の感想
ブラッドベリのことは、これからは「SF作家」じゃなくて「稀代のストーリーテラー」と呼ぼう。これらの短編小説は全てがSFではない。しかしどれも冒頭でぐっと掴まれ、どこへ連れていかれるのかとわくわくするものばかりだ。『その穴から、機械油がゆっくりとしたたり落ちる』。たった1文で見える世界が転換する鮮やかさといったらたまらない。短編集にありがちなこととして、私はいつかこの本を読んだことを失念して再度手に取るかもしれない。そうしたらもう一度最初から楽しむことができる。それはもはや祝福されるべき事態だと思うのだ。
読了日:12月27日 著者:レイ・ブラッドベリ
 逃北 つかれたときは北へ逃げます (文春文庫 の 16-6)の感想
逃北 つかれたときは北へ逃げます (文春文庫 の 16-6)の感想
どこかさびれた場所、観光客の行かない地元民だけの場所、両親や祖母のゆかりの場所。能町さんの逃げる先はいつも北という。私も、北は好きだ。というより、皮膚のすぐ外側を冷えた空気が吹き去っていくその身一つ感、孤独感が落ち着く。南のように、身の内にこもったものが外へ溶け出ていくことなく、自分の中で処理することを強いる、ストイックさを気に入っている。地球の北端に人が暮らす景色を、私も見てみたい。北海道の人が北海道を愛するように、グリーンランドの人はなぜグリーンランドを愛して暮らせないのだろう。あんなに美しいのに…。
読了日:12月25日 著者:能町 みね子
](https://m.media-amazon.com/images/I/51IK6P-CdqL._SL120_.jpg) 週刊東洋経済 2021年9/4特大号[雑誌](すごいベンチャー100 2021年最新版)の感想
週刊東洋経済 2021年9/4特大号[雑誌](すごいベンチャー100 2021年最新版)の感想
「すごいベンチャー100」特集。いつの間にやら日本のスタートアップ企業の資金調達も、ベンチャーキャピタルや事業会社による投資が大部分を占めるようになり、何億もの資本金を集める企業も散見される。日本にもスタートアップの波が来ていると言えるのだろうか? 海外との比較記事を探してみたい。分野も多岐にわたるが、紹介されているのはデジタルや先端技術を使った技術革新が経済成長や社会貢献につながるというものが多い。経済誌なのでそこが強調されている可能性も想定しておく。トレンドは以前ソーシャルゲーム、今SaaSとのこと。
ある人のある着想が企業の形になり、耳目を集め、資金を集め、人を雇い、動き始める。会社が生まれ、育ち、変異し、あるいは別の流れに合流し、あるいは消えていく、有機的なうねり。それがここに取材されただけでもこんなにあるなんて、眩暈がしそうになった。日本のどこかで起きた動きが、現代ではインターネットを通じて素早く詳しく、私みたいな一般人でも知ることができる、そんな時代なのだなあ。
読了日:12月24日 著者:

季刊環境ビジネス2022年冬号の感想
至上命題は「環境・社会問題に対応しつつ、事業を成長させる」である。SDG'sを謳った新しい産業=飯のタネ探しに総がかりで血眼だ。WWFのCOP26についての寄稿も弱い。ほんとうに社会のためになる選択の手掛かりを探して、上滑りしがちな目をなだめながら読んだ。電気の自家消費はいずれ必須になるだろう。洋上風力発電が注目を集めているが、国がぶち上げたとおりに成功するとは思えない。発電場所と使用場所の距離がどんどん遠くなる。特集では東京水産振興会長谷理事の寄稿が現状と展望に堂々と釘を刺していて少しだけすっきりした。
読了日:12月21日 著者:
 国家を考えてみよう (ちくまプリマー新書)の感想
国家を考えてみよう (ちくまプリマー新書)の感想
『民主主義国家で、「政治って、どこかで関係ない誰かがやってるんでしょ?」というような声が平気で出て来たら、それはもう衆愚政治です』。国民の国家とは何か。国家主義は何が違うか。若者を念頭において、部活などわかりやすい例えで説く。この国をなんとかしなければならない焦燥感。批判するために論じるのではない。おおもとを理解して、自ずと非に気づき、曲げさせないためだ。末尾に自民党の憲法改正草案に触れる。憲法は権力者を縛って国民を守るものであって、権力者を守って国民を縛るのは憲法ではない。『国家は我々国民のものである』
初めには言葉遊びのように古今東西の「国」を表わす言葉を挙げていく。国の土台が領土か人間かが如実に現れているとは、面白いなあ。国とか藩とか、身分によって見えているものが違うのは外国も似た部分があるようには思うけど。政と暮らしの乖離が日本人のメンタリティに深く影響しているという指摘が興味深い。国の頂点に天皇を頂いたときから綿々と、土地所有や支配の構図にはズレがあり、日本人の「国」に対する感覚は「国家」と結びついていない。自分たちが主体となって国家を動かすということがピンとこない理由、そういうことなのかなと。
読了日:12月21日 著者:橋本 治
 クレイジーで行こう! グーグルとスタンフォードが認めた男、「水道管」に挑むの感想
クレイジーで行こう! グーグルとスタンフォードが認めた男、「水道管」に挑むの感想
米国でスタートアップ(=ベンチャー企業)を立ち上げた日本人の奮闘記。同じ"ビジネス"でも受け継いだものと新しく立ち上げるものでは全然違う。なにしろ軍資金が元手にある訳ではなく、顧客との契約を成立させるまでは収入ゼロ、製品づくりも営業活動も、給与も家賃も、投資家から集めた借金からのスタートなのだ。考えただけでひりひりする。氏は事業を磨く作業をルービックキューブに例える。ビジネスの方向性が社会の需要に沿っていて、「光るものがあれば使ってみよう」と考える顧客がいて、企業が伸びていける、そんな社会であってほしい。
読了日:12月08日 著者:加藤 崇
 同志少女よ、敵を撃ての感想
同志少女よ、敵を撃ての感想
評判に違わぬ読みごたえ。第二次世界大戦、ソ連の対ドイツ戦線という、日本人には取っつきにくい設定にもかかわらず、現代にも続く普遍的な視点も織り込まれ、読ませる。近しい者も故郷も失ったら、私は死にたいと思う。しかしその瞬間の衝動を逃したら、惰性で生きてしまうのかもしれない。そのうちに後ろ向きなそれを前向きに反転させる怒りや恨み、復讐心を抱いたら、誰かを"守りたい"と思い始めたら、私でも武器を取るのかもしれない。人を敵と呼び、殺すことをも正当化するのかもしれない。非常時、そこには、想像するほど段差は無いのかも。
ジェンダーや慰安婦の問題、民族問題、ソ連から東欧・中央アジアにかけての地政学も、まったく現代に繋がった深いテーマだ。折しも、ロシアがウクライナに侵攻するのではなど報道されている。この文献の多さ、読み捨てのエンタメにはもったいない骨太感だった。いや、すごいもの読みました。今ならアレクシエーヴィッチ「戦争は女の顔をしていない」読めるかもしれん。
読了日:12月06日 著者:逢坂 冬馬
 猫の學校: 猫と人の快適生活レッスン (ポプラ新書)の感想
猫の學校: 猫と人の快適生活レッスン (ポプラ新書)の感想
猫がふたりして旅立ってのち、残されたひとりの戸惑いと寂しさは生半可でなく、人間へのもっと一緒にいて!もっと撫でて!の要求が叫びのようになってきた。これはお互い良くないと、腹を括り、新たに猫を迎えることにした。とはいえ、仔猫を迎えるのは13年ぶり。復習のために再読。家の中に猫が1匹か複数かでの違いについての章が、実感として迫る。複数頭いるとくっついて寝たり遊んだりできる以外に、健康面、精神面でも利点が多い。単独だと人間との間に共依存めいた関係が生じるので、やはり複数の関係をつくったほうが良いのだと納得した。
読了日:12月04日 著者:南里 秀子
 渦巻ける烏の群の感想
渦巻ける烏の群の感想
シベリアに駐留する日本軍の話。軍隊の論理、男の論理で動く兵営から少しでも逃れようと、男たちはささやかな食べ物を手土産に携えて、それぞれにロシア人の家に上がり込む。欲しかったのは刺激や性欲が満たされる情事ではなくて家庭の温かさだった、とは、冷えきった地に出征した経験者ならではの実感だろう。中隊は約200人と聞く。表題の意味が察せられた時、白と黒の強烈なコントラストが脳内に想像せられて慄然とする。小豆島に生まれ、また生を終えた作家とは恥ずかしながら知らなかった。青空文庫ではなくまとまった文庫で読んでみたい。
読了日:12月03日 著者:黒島 伝治
 小豆島
小豆島
読了日:12月02日 著者:黒島 伝治
 ねこのふしぎ話の感想
ねこのふしぎ話の感想
描かれたのは昭和。人と猫の距離感って、いつの時代もこんな感じなんやろなあ。いるのが当たり前の日々。ちょっとうっとうしい日もある。でも笑えるわけでもない、泣けるわけでもない、ほんの小さなエピソードがとても大事で。でも言葉にしたらやっぱりあまりに些細で、他人には届かなくて。『こんなに 問いかけてくる瞳の奥が 空っぽなわけがないよね』。逝った猫への消えることのない追慕の気持ちも、その気配が家の中に現れるのを心待ちにする気持ちも、この著者なら当たり前のことのように「わかるわ」と言ってくれそうな気がした。
読了日:12月02日 著者:やまだ 紫
注: は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。
半分は電子書籍になった。
電子書籍の市場が熟成しつつあるということなのか、明らかにセールが増えた。
年末などモグラたたきのようで大変だった。財布が。
新刊では考えられないような値段で"本"が手元に転がり込んでくるので、情報の獲得に怠りないよう毎日PC画面を眺め渡している。
装丁が素敵な本や、電子で読んで手元に置きたいものは本で買い直すが、電子市場が活性化すればするほど本の印刷や装丁にかかるコストは逆に増し、贅沢品になってゆくのだろう。
<今月のデータ>
購入32冊、購入費用36,849円。
読了12冊。
積読本301冊(うちKindle本136冊、Honto本14冊)。

12月の読書メーター
読んだ本の数:12
 エレファントム 象はなぜ遠い記憶を語るのかの感想
エレファントム 象はなぜ遠い記憶を語るのかの感想海に臨む象の姿が心に残る。地位ある者も貧しき者も欧米人も現地人も、皆して象を狩った長い時代の果てに南アフリカの今がある。著者はローレンツに教えを乞う機会を得ながら拒み、デズモンド・モリスに師事して動物行動学を学んだ。象を"自然の生んだ大天使"と呼ぶ。その歴史や生態を追ったのは、著者が幼い頃出会った白い象と!カンマの記憶があったからだ。象は遊び、おどけ、怒り、超低周波音や足音を使ってはるか遠くの象と意思疎通する。象のことを理解したいならこちらをお勧めしたい。人間の知らないことはまだまだあるに違いないから。
当然、ワトソン氏も動物園という施設には懐疑的だったが、動物行動学者としてヨハネスブルグ動物園の勤務を引き受けた。そこにいたデライラは、初対面のワトソン氏に食べ物より友情を求め、檻の中で先に逝った同族を悼む儀式を行ない、ライオンとワトソン氏の間に立ちはだかって全身で威嚇する姿を見せる。象の世界の深さを、おおかたの人間は理解どころか、未だ知ってすらいないのだ。現代の動物園は、当時より進化しているだろうか。それとも、現代の動物園の象は、象から象へ伝わる智を受け継ぐ術もなく孤立し、鬱々と過ごしているのだろうか。
読了日:12月28日 著者:ライアル・ワトソン
 歌おう、感電するほどの喜びを!〔新版〕 (ハヤカワ文庫 SF フ 16-8)の感想
歌おう、感電するほどの喜びを!〔新版〕 (ハヤカワ文庫 SF フ 16-8)の感想ブラッドベリのことは、これからは「SF作家」じゃなくて「稀代のストーリーテラー」と呼ぼう。これらの短編小説は全てがSFではない。しかしどれも冒頭でぐっと掴まれ、どこへ連れていかれるのかとわくわくするものばかりだ。『その穴から、機械油がゆっくりとしたたり落ちる』。たった1文で見える世界が転換する鮮やかさといったらたまらない。短編集にありがちなこととして、私はいつかこの本を読んだことを失念して再度手に取るかもしれない。そうしたらもう一度最初から楽しむことができる。それはもはや祝福されるべき事態だと思うのだ。
読了日:12月27日 著者:レイ・ブラッドベリ

 逃北 つかれたときは北へ逃げます (文春文庫 の 16-6)の感想
逃北 つかれたときは北へ逃げます (文春文庫 の 16-6)の感想どこかさびれた場所、観光客の行かない地元民だけの場所、両親や祖母のゆかりの場所。能町さんの逃げる先はいつも北という。私も、北は好きだ。というより、皮膚のすぐ外側を冷えた空気が吹き去っていくその身一つ感、孤独感が落ち着く。南のように、身の内にこもったものが外へ溶け出ていくことなく、自分の中で処理することを強いる、ストイックさを気に入っている。地球の北端に人が暮らす景色を、私も見てみたい。北海道の人が北海道を愛するように、グリーンランドの人はなぜグリーンランドを愛して暮らせないのだろう。あんなに美しいのに…。
読了日:12月25日 著者:能町 みね子

](https://m.media-amazon.com/images/I/51IK6P-CdqL._SL120_.jpg) 週刊東洋経済 2021年9/4特大号[雑誌](すごいベンチャー100 2021年最新版)の感想
週刊東洋経済 2021年9/4特大号[雑誌](すごいベンチャー100 2021年最新版)の感想「すごいベンチャー100」特集。いつの間にやら日本のスタートアップ企業の資金調達も、ベンチャーキャピタルや事業会社による投資が大部分を占めるようになり、何億もの資本金を集める企業も散見される。日本にもスタートアップの波が来ていると言えるのだろうか? 海外との比較記事を探してみたい。分野も多岐にわたるが、紹介されているのはデジタルや先端技術を使った技術革新が経済成長や社会貢献につながるというものが多い。経済誌なのでそこが強調されている可能性も想定しておく。トレンドは以前ソーシャルゲーム、今SaaSとのこと。
ある人のある着想が企業の形になり、耳目を集め、資金を集め、人を雇い、動き始める。会社が生まれ、育ち、変異し、あるいは別の流れに合流し、あるいは消えていく、有機的なうねり。それがここに取材されただけでもこんなにあるなんて、眩暈がしそうになった。日本のどこかで起きた動きが、現代ではインターネットを通じて素早く詳しく、私みたいな一般人でも知ることができる、そんな時代なのだなあ。
読了日:12月24日 著者:

季刊環境ビジネス2022年冬号の感想
至上命題は「環境・社会問題に対応しつつ、事業を成長させる」である。SDG'sを謳った新しい産業=飯のタネ探しに総がかりで血眼だ。WWFのCOP26についての寄稿も弱い。ほんとうに社会のためになる選択の手掛かりを探して、上滑りしがちな目をなだめながら読んだ。電気の自家消費はいずれ必須になるだろう。洋上風力発電が注目を集めているが、国がぶち上げたとおりに成功するとは思えない。発電場所と使用場所の距離がどんどん遠くなる。特集では東京水産振興会長谷理事の寄稿が現状と展望に堂々と釘を刺していて少しだけすっきりした。
読了日:12月21日 著者:
 国家を考えてみよう (ちくまプリマー新書)の感想
国家を考えてみよう (ちくまプリマー新書)の感想『民主主義国家で、「政治って、どこかで関係ない誰かがやってるんでしょ?」というような声が平気で出て来たら、それはもう衆愚政治です』。国民の国家とは何か。国家主義は何が違うか。若者を念頭において、部活などわかりやすい例えで説く。この国をなんとかしなければならない焦燥感。批判するために論じるのではない。おおもとを理解して、自ずと非に気づき、曲げさせないためだ。末尾に自民党の憲法改正草案に触れる。憲法は権力者を縛って国民を守るものであって、権力者を守って国民を縛るのは憲法ではない。『国家は我々国民のものである』
初めには言葉遊びのように古今東西の「国」を表わす言葉を挙げていく。国の土台が領土か人間かが如実に現れているとは、面白いなあ。国とか藩とか、身分によって見えているものが違うのは外国も似た部分があるようには思うけど。政と暮らしの乖離が日本人のメンタリティに深く影響しているという指摘が興味深い。国の頂点に天皇を頂いたときから綿々と、土地所有や支配の構図にはズレがあり、日本人の「国」に対する感覚は「国家」と結びついていない。自分たちが主体となって国家を動かすということがピンとこない理由、そういうことなのかなと。
読了日:12月21日 著者:橋本 治

 クレイジーで行こう! グーグルとスタンフォードが認めた男、「水道管」に挑むの感想
クレイジーで行こう! グーグルとスタンフォードが認めた男、「水道管」に挑むの感想米国でスタートアップ(=ベンチャー企業)を立ち上げた日本人の奮闘記。同じ"ビジネス"でも受け継いだものと新しく立ち上げるものでは全然違う。なにしろ軍資金が元手にある訳ではなく、顧客との契約を成立させるまでは収入ゼロ、製品づくりも営業活動も、給与も家賃も、投資家から集めた借金からのスタートなのだ。考えただけでひりひりする。氏は事業を磨く作業をルービックキューブに例える。ビジネスの方向性が社会の需要に沿っていて、「光るものがあれば使ってみよう」と考える顧客がいて、企業が伸びていける、そんな社会であってほしい。
読了日:12月08日 著者:加藤 崇

 同志少女よ、敵を撃ての感想
同志少女よ、敵を撃ての感想評判に違わぬ読みごたえ。第二次世界大戦、ソ連の対ドイツ戦線という、日本人には取っつきにくい設定にもかかわらず、現代にも続く普遍的な視点も織り込まれ、読ませる。近しい者も故郷も失ったら、私は死にたいと思う。しかしその瞬間の衝動を逃したら、惰性で生きてしまうのかもしれない。そのうちに後ろ向きなそれを前向きに反転させる怒りや恨み、復讐心を抱いたら、誰かを"守りたい"と思い始めたら、私でも武器を取るのかもしれない。人を敵と呼び、殺すことをも正当化するのかもしれない。非常時、そこには、想像するほど段差は無いのかも。
ジェンダーや慰安婦の問題、民族問題、ソ連から東欧・中央アジアにかけての地政学も、まったく現代に繋がった深いテーマだ。折しも、ロシアがウクライナに侵攻するのではなど報道されている。この文献の多さ、読み捨てのエンタメにはもったいない骨太感だった。いや、すごいもの読みました。今ならアレクシエーヴィッチ「戦争は女の顔をしていない」読めるかもしれん。
読了日:12月06日 著者:逢坂 冬馬

 猫の學校: 猫と人の快適生活レッスン (ポプラ新書)の感想
猫の學校: 猫と人の快適生活レッスン (ポプラ新書)の感想猫がふたりして旅立ってのち、残されたひとりの戸惑いと寂しさは生半可でなく、人間へのもっと一緒にいて!もっと撫でて!の要求が叫びのようになってきた。これはお互い良くないと、腹を括り、新たに猫を迎えることにした。とはいえ、仔猫を迎えるのは13年ぶり。復習のために再読。家の中に猫が1匹か複数かでの違いについての章が、実感として迫る。複数頭いるとくっついて寝たり遊んだりできる以外に、健康面、精神面でも利点が多い。単独だと人間との間に共依存めいた関係が生じるので、やはり複数の関係をつくったほうが良いのだと納得した。
読了日:12月04日 著者:南里 秀子
 渦巻ける烏の群の感想
渦巻ける烏の群の感想シベリアに駐留する日本軍の話。軍隊の論理、男の論理で動く兵営から少しでも逃れようと、男たちはささやかな食べ物を手土産に携えて、それぞれにロシア人の家に上がり込む。欲しかったのは刺激や性欲が満たされる情事ではなくて家庭の温かさだった、とは、冷えきった地に出征した経験者ならではの実感だろう。中隊は約200人と聞く。表題の意味が察せられた時、白と黒の強烈なコントラストが脳内に想像せられて慄然とする。小豆島に生まれ、また生を終えた作家とは恥ずかしながら知らなかった。青空文庫ではなくまとまった文庫で読んでみたい。
読了日:12月03日 著者:黒島 伝治

 小豆島
小豆島読了日:12月02日 著者:黒島 伝治

 ねこのふしぎ話の感想
ねこのふしぎ話の感想描かれたのは昭和。人と猫の距離感って、いつの時代もこんな感じなんやろなあ。いるのが当たり前の日々。ちょっとうっとうしい日もある。でも笑えるわけでもない、泣けるわけでもない、ほんの小さなエピソードがとても大事で。でも言葉にしたらやっぱりあまりに些細で、他人には届かなくて。『こんなに 問いかけてくる瞳の奥が 空っぽなわけがないよね』。逝った猫への消えることのない追慕の気持ちも、その気配が家の中に現れるのを心待ちにする気持ちも、この著者なら当たり前のことのように「わかるわ」と言ってくれそうな気がした。
読了日:12月02日 著者:やまだ 紫
注:
 は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。 Posted by nekoneko at 11:40│Comments(0)
│読書