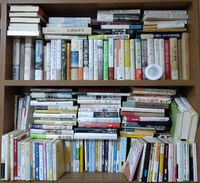2023年12月05日
2023年11月の記録
この季節。
エアコンをつけ始めると、部屋の開口部は閉めなければならない。
猫たちは主張する。
廊下へ出たい! 部屋へ入りたい! 廊下へ出たい! 部屋へ入りたい!
開けてくれなきゃドアに爪を立てて自分で開けてみせる!
都度、私は立ちあがってドアを開けることを繰り返す。
座ってもすぐに呼ばれるので集中できず、苛々と本を撫でまわしている。
<今月のデータ>
購入14冊、購入費用11,269円。
読了10冊。
積読本330冊(うちKindle本159冊、Honto本3冊)。
Honto本、ちびちびと消化していたけれど、Booxも捨て、スマホで読む気も起きず、
諦めて放棄することにした。
「月は無慈悲な夜の女王」、「死の鳥」、「シベリア追跡」。
Kindleでいずれ買い直すことになりそう。

 日本のコメ問題-5つの転換点と迫りくる最大の危機 (中公新書 2701)の感想
日本のコメ問題-5つの転換点と迫りくる最大の危機 (中公新書 2701)の感想
素人へのわかりやすさを心がけて書かれてはいるが、需給や政局により度重ねた政策変更には、素人の頭は追いつかない。つまり、技術の進歩に伴い、少ない労働力で多くの収穫が可能になった。需給から言えば米の収穫量はもう少し減ったほうが、米農家や米産業のためには良い、らしい。しかし余った田んぼをどうするか。小麦や大豆他への転作畑地化、また加工用米、飼料用米に切り替えてでも、いざというとき再び米をつくれる道が残された土地であってほしい。とは感傷か。そして飼料用米は経済的に成り立たない。補助金じゃぶじゃぶを是とするべきか。
田んぼとしての認定ルール。5年以内に、一度は水を張ること。それをしないと田んぼ認定が受けられず、補助金がもらえない。補助金は大きなインセンティヴとして機能してきた。だけど、余った田んぼの活用方法として植えた果樹や設置したビニールハウス、放牧した牛を除去するのは現実的でない。では何が田んぼで何が畑なのか?? もうわからん。補助金の問題が根深すぎて、にっちもさっちもいかない感じがする。とりあえず米も農作物も値上げしよう。スイーツに2,000円出せて、野菜の300円を高く感じるのは間違ってる。
読了日:11月29日 著者:小川 真如
 ゾンビ化するアメリカ 時代に逆行する最高裁、州法、そして大統領選の感想
ゾンビ化するアメリカ 時代に逆行する最高裁、州法、そして大統領選の感想
相変わらず日本人から見ると桁の外れた国だなあ。器がでかいようで、なんか生きにくそう。フロリダ州の「ザ・ヴィレッジズ」に度肝を抜かれる。高齢者限定の住宅を建ててつくった、裕福な高齢者限定のコミュニティ、住人は13万人。高齢者が余生を平穏に楽しく暮らすための街。そこまでやるのか。それって、欲求を純粋に求めた形とはいえ、人間社会としてすごく歪だと思う。幸せかな。政治ネタには溜息しか出ないけど、音楽や映画はそのさほど長くない歴史も多様性も映して、だから魅力的で、だから町山さんはアメリカが好きなんだろうと想像する。
「ガラスの天井」ならぬ「ガラスの崖(Glass Cliff)」が現れた。その企業が崖っぷちに追い詰められた時、女性や少数民族が経営陣に抜擢される現象とのこと。曰く、"独自の感性で画期的なアイデアが出ることを期待して"。それって、日本にも既にあるよな。今まで散々、男ばっかりで社会や会社を仕切ってきて、雲行きが怪しくなったら「女性の力」だの「女性らしい感性で」だの、調子の良い事この上ない。ましてや失敗したときには「ほらね」と言わんばかりに責任をなすりつけようとするとはどこまで女々しいのか。その手には乗らんぞ。
読了日:11月24日 著者:町山 智浩
 老後を動物と生きるの感想
老後を動物と生きるの感想
他者との交流や心身の自由が限られてくる老年期こそ、伴侶動物と暮らすべきだとずっと思ってきた。しかし日本では、安全面、衛生面、管理面などの障壁が先に立って、飼い犬/猫と一緒に入れる老人ホームなどは今も香川県内にはほぼ無い。この本は、老人福祉施設での動物飼育において、規定しておくべき要件のチェックリストや問題点についての論考集である。スイス、ドイツ、オーストリアにおいては、この本が出た2004年の時点で施設への動物受入れが格段に増えているとある。日本は訪問動物が限界だろうか。意地でも猫と離れず自宅で死にたい。
老年期に動物と暮らそうと思うと、人間が先に死んだ場合の備えがどうしたって必要になる。余生の飼養を引き受ける契約も民間団体レベルではあるが、システムとして不安定には違いなく、社会の仕組みとして確立できないものかと思う。外国ではティアハイムの延長として考える精神的素地があるが、日本ではブリーディングのように金儲け目的の悪徳業者がはびこりそうな気がして安心できない。うーん。
読了日:11月23日 著者:マリアンヌ ゲング,デニス・C. ターナー
 あなたが私を竹槍で突き殺す前にの感想
あなたが私を竹槍で突き殺す前にの感想
タイトルに負けず内容も衝撃的なディストピア小説。より右傾化した日本で総理大臣は小池百合子(推定)、日韓関係は断絶、ヘイトクライムは激増、悪質化の一途にある。在日韓国人の生きる場所を奪う政策が支持され、新大久保にもコリアンの居場所はほとんどない。怖いのは、これが少々過激すぎる設定ではあっても、現実と地続きに見えることだ。著者の来歴を検索したい気持ちを抑えて読み終えた。奥付、同い年の在日韓国人三世だった。同じ日本を生きてきて、私と彼に見える世界がどれだけ隔たっているか。片や強い怒り、片や深い諦めに息が止まる。
『日本国家に刃向かう不逞鮮人』って福田村事件からそのままスライドしてきたみたいな言葉だ。外国にルーツのある人々と共生するための社会制度がことごとく廃止される日本。マイナンバーカード提示義務化に伴う本名開示強制、通名禁止、ヘイトスピーチ解消法廃止、外国人への生活保護給付禁止、特別永住者制度廃止、外国人を対象外とするベーシックインカムの検討。そこまで積極的ではなくとも、そういう排他的な動きにひょっと繋がるのでは、と思ってしまう気配とか、実際に人権を侵害している法制とか、あるからフィクションだと割り切れない。
読了日:11月23日 著者:李龍徳
 海をあげる (単行本)の感想
海をあげる (単行本)の感想
海をもらう。絶望の海。海のような絶望。上間さんは穏やかな、柔らかい声で、相手に伝わるようゆっくり話す人だ。でも心の中にはこんなに憤りと悲しみを抱えていたのだと知る。米軍基地の爆音、水道水汚染や環境破壊、暴力。『いま、まっただなかで暮らしているひとは、どこに逃げたらいいのかわからない』。その深さを想い、言葉にならない。自身も普天間に暮らしながら、困難を抱える若者の、女性たちの言葉を聞く。受け止め、生きることを助ける。当事者でない私たちができることも、たぶん似ている。耳を澄まし、受け止めること。傍に立つこと。
沖縄県に顕著な、貧困状態にある人の多さを社会問題と大局的に捉え、解決方法を模索することも大事だ。しかしそのデータからは思い及ぶことの難しい、たくさんの若者、女性たちそれぞれの痛み、苦しみ、絶望と諦めがあることは見えづらい。ほんとうに酷い。実の親ですら、そして行政にも頼れない若者たちに差し伸べる手は必ず必要だ。その行為すら阻害されて、諦めて流される背中を見送るのはどんな思いだったろう。そこから、若い母親と乳児を保護し、節目を寿いで送り出すシェルター「おにわ」の立ち上げに繋がっていく。なんと尊い営みか。
沖縄に生まれてもいない、育ってもいない、暮らしてもいない私は徹底的に外野だ。むしろ加害者の側ですらある。その私が、沖縄に、沖縄の人々に対してどうあればよいのかは、ずっと考えていることだ。この本を読んで、書き上げた感想、自分で読んで「きれいごとだ」と感じる。とりあえず、読んで終わりにしないと決める。
読了日:11月13日 著者:上間 陽子
 おらおらでひとりいぐも (河出文庫)の感想
おらおらでひとりいぐも (河出文庫)の感想
脳内ひとりごとだだ洩れ系、大好き。止めどのない思考は、濁流となりせせらぎとなり奔流となり、そのときどきの思いに駆られてあっちこっち迷走しながら、人は生きている。辻褄?そんなもん合う訳ないやん。『おらの生ぎるはおらの裁量に任せられているのだな。おらはおらの人生を引き受げる』。女の業もちゃんと書いていて、傷つけた人のこと、離れてしまったきりの人のこと、悔やむけれど、しかたないやん、生きるしかないやん、という苦みも含め、東北弁で書ききったことに喝采をおくる。解説は町田康、これはもうね、当然すぎるね。
読了日:11月12日 著者:若竹千佐子
 福田村事件 -関東大震災・知られざる悲劇の感想
福田村事件 -関東大震災・知られざる悲劇の感想
関東大震災直後、デマに煽られて「朝鮮人」9人を虐殺したが、実は香川県からの行商人家族の集団だった。妊婦や幼児まで手にかけ、利根川に遺体を突き流した実在の事件だ。朝鮮人であるか否かの事実に関わらず数百人で少数を暴行のうえ虐殺したこと。国のためだったと言い張って悔いず、有罪判決は不服と上告までしたこと。村人から被告に見舞金を出したこと。歴史に残らないよう揃って口を閉ざしたこと。人間の、不変の愚かさがくっきり出ている。怖いのは事件そのものだけでなく、事件を無かったことのように忘れること。そこにぐらいは抗いたい。
被告のひとりの証言。『日本刀を持って出掛けると群衆のなかから、貴様は見物にきたのかと怒鳴りましたので、ついやったような訳です。私は実際相手を斬ったにもかかわらず、予審で三回も否認したのは、摂政宮殿下には玄米を召し上がられている際、不逞鮮人のために国家はどうなることかと憂れへの余りやったような次第ですが、監獄に入れられたので癪にさわったから、事実を否認したのです』。
被害者の地元の女性の証言。『日本人と朝鮮人とまちがえたということは、香川県の言葉と朝鮮の言葉はそんなに似とるんやろかなあ、なんでかしらんと思っておりました。こちらでは朝鮮の人はよくアメ売りに来ました。その人の言葉はなまりとかでわかりました。あの言葉と讃岐の言葉がなんでわからないのかなあ、関東の人ってひどい人やなあと私は思いました。罪のない人をまちがったか何か知らんけど殺すとはひどいとおもいましたよ。それが頭に残っています』。
香川県内には1990年代で46カ所同和地区があったと聞き、その多さに驚いた。瀬戸内海地方は温暖な気候や、人や物の往来の多さのわりに耕せる土地が少ないため、貧しかったと宮本常一も言っていた。面積が小さい香川県は特に、1軒当たりの農地が狭く、小作率も全国一高かった。そのことが、香川の売薬行商人が全国で2番目に多いなど、行商人が多かった理由だろう。「四国辺土」の遍路のことといい、香川県は災害が少なくて良いなど、わりとのほほんとした風土のように自称するが、なかなか深い闇を抱えているのだと最近になって戦慄している。
読了日:11月08日 著者:辻野弥生
 生命海流 GALAPAGOSの感想
生命海流 GALAPAGOSの感想
福岡センセイ、念願叶う。ダーウィンのマーベル号と同じ航路を取ってガラパゴスの島々を旅した記念の誌。装丁も豪華だ。船やコック、ガイドを雇った贅沢な旅とはいえ、自称ニセモノ・ナチュラリストの福岡先生には(きっと私にも)ガラパゴスの自然は厳しいのだろう。それこそ体験しなければわからない。釣竿を持って行ったくらいだから、獲ったり釣ったり生物を子細に観察する機会が全く禁じられたのは誤算だったのではないかしら。ダーウィンの頃は何でもやり放題、捕り放題で大量の標本や剥製を持ち帰ったのにとひき比べてみせるのが微笑ましい。
植物や微生物は『自分たちに必要な分だけ栄養分を作ったり、作ったアンモニアを独占するのではなく、いつも少しだけ多めに活動して、それを他の生命に分け与えてくれた。利己的にならず他を利することもつまり利他性があった。余裕があるところに利他性が生まれ、利他性が生まれると初めて共生が生まれる。利他性はめぐりめぐってまた自分のところに戻ってくる』。そうして何もなかった島に生命は満ちた。生命レベルの利他が無ければ、そもそも生命の繁栄は無かったとの指摘は、壮大で、考えてもみなかったことだった。
読了日:11月05日 著者:福岡 伸一
 オリガ・モリソヴナの反語法 (集英社文庫)の感想
オリガ・モリソヴナの反語法 (集英社文庫)の感想
初めての小説とは信じられない。実在するのは教師の存在と電信記録、自身の体験だけ。あとは時代の動乱に絡めた人々の受難の歴史、全て日露の膨大な文献にあたって創りあげた架空とは。ソ連という大きな枠組みの中での、女性たちの受難。子供も無縁でいられない。外国籍の人とのつき合いは用心しなさいと教えられ、キューバ危機の報に初恋の人への告白を決心する。人は時代とも世界とも無縁ではいられない。それがむき出しになるソ連と、何も知らないまま守られる日本のいずれが特別なのか、いずれにせよその落差が人の成熟を決するように感じた。
物語として、凄く面白かった。でもそれは米原さん自身がプラハで過ごした幼少期、そこで得た体験や学び方、知識無しにはあり得なくて、かの地の子どもたちがどのような常識と教養を身につけさせられるか、一方で日本の教育がどのような性質のものであるかを痛感せずにいられない。登場人物の痛みを想像する一方で、我が身のほうも苦いものが残る。よい読書体験でした。
読了日:11月03日 著者:米原 万里
 オーガニック植木屋の庭づくり: 暮らしが広がるガーデンデザインの感想
オーガニック植木屋の庭づくり: 暮らしが広がるガーデンデザインの感想
ひきちさんの本は4冊目。内容が劇的に違う訳ではないのだけれど、眺めてはイメージをつくり直す過程を繰り返すのが楽しい。今回は「オーガニックとはなにか」「自分の暮らしに合う庭とは」など大きな、かつ現実的な問い立てから、各アイテムの設置方法、望ましい仕様などを細かく書いている。低いレイズドベッド、バイオネスト、野外炉、インセクトホテル、排水用浸透層、睡蓮鉢、雨庭など、やってみたいけれど自分でやれるのかこれは。なものばかり挙げているな私。ま、実際にやってみるこったな。売っている堆肥の性質、注意点は憶えておきたい。
読了日:11月02日 著者:ひきちガーデンサービス 曳地トシ+曳地義治
注: は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。
エアコンをつけ始めると、部屋の開口部は閉めなければならない。
猫たちは主張する。
廊下へ出たい! 部屋へ入りたい! 廊下へ出たい! 部屋へ入りたい!
開けてくれなきゃドアに爪を立てて自分で開けてみせる!
都度、私は立ちあがってドアを開けることを繰り返す。
座ってもすぐに呼ばれるので集中できず、苛々と本を撫でまわしている。
<今月のデータ>
購入14冊、購入費用11,269円。
読了10冊。
積読本330冊(うちKindle本159冊、
Honto本、ちびちびと消化していたけれど、Booxも捨て、スマホで読む気も起きず、
諦めて放棄することにした。
「月は無慈悲な夜の女王」、「死の鳥」、「シベリア追跡」。
Kindleでいずれ買い直すことになりそう。

 日本のコメ問題-5つの転換点と迫りくる最大の危機 (中公新書 2701)の感想
日本のコメ問題-5つの転換点と迫りくる最大の危機 (中公新書 2701)の感想素人へのわかりやすさを心がけて書かれてはいるが、需給や政局により度重ねた政策変更には、素人の頭は追いつかない。つまり、技術の進歩に伴い、少ない労働力で多くの収穫が可能になった。需給から言えば米の収穫量はもう少し減ったほうが、米農家や米産業のためには良い、らしい。しかし余った田んぼをどうするか。小麦や大豆他への転作畑地化、また加工用米、飼料用米に切り替えてでも、いざというとき再び米をつくれる道が残された土地であってほしい。とは感傷か。そして飼料用米は経済的に成り立たない。補助金じゃぶじゃぶを是とするべきか。
田んぼとしての認定ルール。5年以内に、一度は水を張ること。それをしないと田んぼ認定が受けられず、補助金がもらえない。補助金は大きなインセンティヴとして機能してきた。だけど、余った田んぼの活用方法として植えた果樹や設置したビニールハウス、放牧した牛を除去するのは現実的でない。では何が田んぼで何が畑なのか?? もうわからん。補助金の問題が根深すぎて、にっちもさっちもいかない感じがする。とりあえず米も農作物も値上げしよう。スイーツに2,000円出せて、野菜の300円を高く感じるのは間違ってる。
読了日:11月29日 著者:小川 真如

 ゾンビ化するアメリカ 時代に逆行する最高裁、州法、そして大統領選の感想
ゾンビ化するアメリカ 時代に逆行する最高裁、州法、そして大統領選の感想相変わらず日本人から見ると桁の外れた国だなあ。器がでかいようで、なんか生きにくそう。フロリダ州の「ザ・ヴィレッジズ」に度肝を抜かれる。高齢者限定の住宅を建ててつくった、裕福な高齢者限定のコミュニティ、住人は13万人。高齢者が余生を平穏に楽しく暮らすための街。そこまでやるのか。それって、欲求を純粋に求めた形とはいえ、人間社会としてすごく歪だと思う。幸せかな。政治ネタには溜息しか出ないけど、音楽や映画はそのさほど長くない歴史も多様性も映して、だから魅力的で、だから町山さんはアメリカが好きなんだろうと想像する。
「ガラスの天井」ならぬ「ガラスの崖(Glass Cliff)」が現れた。その企業が崖っぷちに追い詰められた時、女性や少数民族が経営陣に抜擢される現象とのこと。曰く、"独自の感性で画期的なアイデアが出ることを期待して"。それって、日本にも既にあるよな。今まで散々、男ばっかりで社会や会社を仕切ってきて、雲行きが怪しくなったら「女性の力」だの「女性らしい感性で」だの、調子の良い事この上ない。ましてや失敗したときには「ほらね」と言わんばかりに責任をなすりつけようとするとはどこまで女々しいのか。その手には乗らんぞ。
読了日:11月24日 著者:町山 智浩

 老後を動物と生きるの感想
老後を動物と生きるの感想他者との交流や心身の自由が限られてくる老年期こそ、伴侶動物と暮らすべきだとずっと思ってきた。しかし日本では、安全面、衛生面、管理面などの障壁が先に立って、飼い犬/猫と一緒に入れる老人ホームなどは今も香川県内にはほぼ無い。この本は、老人福祉施設での動物飼育において、規定しておくべき要件のチェックリストや問題点についての論考集である。スイス、ドイツ、オーストリアにおいては、この本が出た2004年の時点で施設への動物受入れが格段に増えているとある。日本は訪問動物が限界だろうか。意地でも猫と離れず自宅で死にたい。
老年期に動物と暮らそうと思うと、人間が先に死んだ場合の備えがどうしたって必要になる。余生の飼養を引き受ける契約も民間団体レベルではあるが、システムとして不安定には違いなく、社会の仕組みとして確立できないものかと思う。外国ではティアハイムの延長として考える精神的素地があるが、日本ではブリーディングのように金儲け目的の悪徳業者がはびこりそうな気がして安心できない。うーん。
読了日:11月23日 著者:マリアンヌ ゲング,デニス・C. ターナー
 あなたが私を竹槍で突き殺す前にの感想
あなたが私を竹槍で突き殺す前にの感想タイトルに負けず内容も衝撃的なディストピア小説。より右傾化した日本で総理大臣は小池百合子(推定)、日韓関係は断絶、ヘイトクライムは激増、悪質化の一途にある。在日韓国人の生きる場所を奪う政策が支持され、新大久保にもコリアンの居場所はほとんどない。怖いのは、これが少々過激すぎる設定ではあっても、現実と地続きに見えることだ。著者の来歴を検索したい気持ちを抑えて読み終えた。奥付、同い年の在日韓国人三世だった。同じ日本を生きてきて、私と彼に見える世界がどれだけ隔たっているか。片や強い怒り、片や深い諦めに息が止まる。
『日本国家に刃向かう不逞鮮人』って福田村事件からそのままスライドしてきたみたいな言葉だ。外国にルーツのある人々と共生するための社会制度がことごとく廃止される日本。マイナンバーカード提示義務化に伴う本名開示強制、通名禁止、ヘイトスピーチ解消法廃止、外国人への生活保護給付禁止、特別永住者制度廃止、外国人を対象外とするベーシックインカムの検討。そこまで積極的ではなくとも、そういう排他的な動きにひょっと繋がるのでは、と思ってしまう気配とか、実際に人権を侵害している法制とか、あるからフィクションだと割り切れない。
読了日:11月23日 著者:李龍徳
 海をあげる (単行本)の感想
海をあげる (単行本)の感想海をもらう。絶望の海。海のような絶望。上間さんは穏やかな、柔らかい声で、相手に伝わるようゆっくり話す人だ。でも心の中にはこんなに憤りと悲しみを抱えていたのだと知る。米軍基地の爆音、水道水汚染や環境破壊、暴力。『いま、まっただなかで暮らしているひとは、どこに逃げたらいいのかわからない』。その深さを想い、言葉にならない。自身も普天間に暮らしながら、困難を抱える若者の、女性たちの言葉を聞く。受け止め、生きることを助ける。当事者でない私たちができることも、たぶん似ている。耳を澄まし、受け止めること。傍に立つこと。
沖縄県に顕著な、貧困状態にある人の多さを社会問題と大局的に捉え、解決方法を模索することも大事だ。しかしそのデータからは思い及ぶことの難しい、たくさんの若者、女性たちそれぞれの痛み、苦しみ、絶望と諦めがあることは見えづらい。ほんとうに酷い。実の親ですら、そして行政にも頼れない若者たちに差し伸べる手は必ず必要だ。その行為すら阻害されて、諦めて流される背中を見送るのはどんな思いだったろう。そこから、若い母親と乳児を保護し、節目を寿いで送り出すシェルター「おにわ」の立ち上げに繋がっていく。なんと尊い営みか。
沖縄に生まれてもいない、育ってもいない、暮らしてもいない私は徹底的に外野だ。むしろ加害者の側ですらある。その私が、沖縄に、沖縄の人々に対してどうあればよいのかは、ずっと考えていることだ。この本を読んで、書き上げた感想、自分で読んで「きれいごとだ」と感じる。とりあえず、読んで終わりにしないと決める。
読了日:11月13日 著者:上間 陽子

 おらおらでひとりいぐも (河出文庫)の感想
おらおらでひとりいぐも (河出文庫)の感想脳内ひとりごとだだ洩れ系、大好き。止めどのない思考は、濁流となりせせらぎとなり奔流となり、そのときどきの思いに駆られてあっちこっち迷走しながら、人は生きている。辻褄?そんなもん合う訳ないやん。『おらの生ぎるはおらの裁量に任せられているのだな。おらはおらの人生を引き受げる』。女の業もちゃんと書いていて、傷つけた人のこと、離れてしまったきりの人のこと、悔やむけれど、しかたないやん、生きるしかないやん、という苦みも含め、東北弁で書ききったことに喝采をおくる。解説は町田康、これはもうね、当然すぎるね。
読了日:11月12日 著者:若竹千佐子

 福田村事件 -関東大震災・知られざる悲劇の感想
福田村事件 -関東大震災・知られざる悲劇の感想関東大震災直後、デマに煽られて「朝鮮人」9人を虐殺したが、実は香川県からの行商人家族の集団だった。妊婦や幼児まで手にかけ、利根川に遺体を突き流した実在の事件だ。朝鮮人であるか否かの事実に関わらず数百人で少数を暴行のうえ虐殺したこと。国のためだったと言い張って悔いず、有罪判決は不服と上告までしたこと。村人から被告に見舞金を出したこと。歴史に残らないよう揃って口を閉ざしたこと。人間の、不変の愚かさがくっきり出ている。怖いのは事件そのものだけでなく、事件を無かったことのように忘れること。そこにぐらいは抗いたい。
被告のひとりの証言。『日本刀を持って出掛けると群衆のなかから、貴様は見物にきたのかと怒鳴りましたので、ついやったような訳です。私は実際相手を斬ったにもかかわらず、予審で三回も否認したのは、摂政宮殿下には玄米を召し上がられている際、不逞鮮人のために国家はどうなることかと憂れへの余りやったような次第ですが、監獄に入れられたので癪にさわったから、事実を否認したのです』。
被害者の地元の女性の証言。『日本人と朝鮮人とまちがえたということは、香川県の言葉と朝鮮の言葉はそんなに似とるんやろかなあ、なんでかしらんと思っておりました。こちらでは朝鮮の人はよくアメ売りに来ました。その人の言葉はなまりとかでわかりました。あの言葉と讃岐の言葉がなんでわからないのかなあ、関東の人ってひどい人やなあと私は思いました。罪のない人をまちがったか何か知らんけど殺すとはひどいとおもいましたよ。それが頭に残っています』。
香川県内には1990年代で46カ所同和地区があったと聞き、その多さに驚いた。瀬戸内海地方は温暖な気候や、人や物の往来の多さのわりに耕せる土地が少ないため、貧しかったと宮本常一も言っていた。面積が小さい香川県は特に、1軒当たりの農地が狭く、小作率も全国一高かった。そのことが、香川の売薬行商人が全国で2番目に多いなど、行商人が多かった理由だろう。「四国辺土」の遍路のことといい、香川県は災害が少なくて良いなど、わりとのほほんとした風土のように自称するが、なかなか深い闇を抱えているのだと最近になって戦慄している。
読了日:11月08日 著者:辻野弥生

 生命海流 GALAPAGOSの感想
生命海流 GALAPAGOSの感想福岡センセイ、念願叶う。ダーウィンのマーベル号と同じ航路を取ってガラパゴスの島々を旅した記念の誌。装丁も豪華だ。船やコック、ガイドを雇った贅沢な旅とはいえ、自称ニセモノ・ナチュラリストの福岡先生には(きっと私にも)ガラパゴスの自然は厳しいのだろう。それこそ体験しなければわからない。釣竿を持って行ったくらいだから、獲ったり釣ったり生物を子細に観察する機会が全く禁じられたのは誤算だったのではないかしら。ダーウィンの頃は何でもやり放題、捕り放題で大量の標本や剥製を持ち帰ったのにとひき比べてみせるのが微笑ましい。
植物や微生物は『自分たちに必要な分だけ栄養分を作ったり、作ったアンモニアを独占するのではなく、いつも少しだけ多めに活動して、それを他の生命に分け与えてくれた。利己的にならず他を利することもつまり利他性があった。余裕があるところに利他性が生まれ、利他性が生まれると初めて共生が生まれる。利他性はめぐりめぐってまた自分のところに戻ってくる』。そうして何もなかった島に生命は満ちた。生命レベルの利他が無ければ、そもそも生命の繁栄は無かったとの指摘は、壮大で、考えてもみなかったことだった。
読了日:11月05日 著者:福岡 伸一
 オリガ・モリソヴナの反語法 (集英社文庫)の感想
オリガ・モリソヴナの反語法 (集英社文庫)の感想初めての小説とは信じられない。実在するのは教師の存在と電信記録、自身の体験だけ。あとは時代の動乱に絡めた人々の受難の歴史、全て日露の膨大な文献にあたって創りあげた架空とは。ソ連という大きな枠組みの中での、女性たちの受難。子供も無縁でいられない。外国籍の人とのつき合いは用心しなさいと教えられ、キューバ危機の報に初恋の人への告白を決心する。人は時代とも世界とも無縁ではいられない。それがむき出しになるソ連と、何も知らないまま守られる日本のいずれが特別なのか、いずれにせよその落差が人の成熟を決するように感じた。
物語として、凄く面白かった。でもそれは米原さん自身がプラハで過ごした幼少期、そこで得た体験や学び方、知識無しにはあり得なくて、かの地の子どもたちがどのような常識と教養を身につけさせられるか、一方で日本の教育がどのような性質のものであるかを痛感せずにいられない。登場人物の痛みを想像する一方で、我が身のほうも苦いものが残る。よい読書体験でした。
読了日:11月03日 著者:米原 万里

 オーガニック植木屋の庭づくり: 暮らしが広がるガーデンデザインの感想
オーガニック植木屋の庭づくり: 暮らしが広がるガーデンデザインの感想ひきちさんの本は4冊目。内容が劇的に違う訳ではないのだけれど、眺めてはイメージをつくり直す過程を繰り返すのが楽しい。今回は「オーガニックとはなにか」「自分の暮らしに合う庭とは」など大きな、かつ現実的な問い立てから、各アイテムの設置方法、望ましい仕様などを細かく書いている。低いレイズドベッド、バイオネスト、野外炉、インセクトホテル、排水用浸透層、睡蓮鉢、雨庭など、やってみたいけれど自分でやれるのかこれは。なものばかり挙げているな私。ま、実際にやってみるこったな。売っている堆肥の性質、注意点は憶えておきたい。
読了日:11月02日 著者:ひきちガーデンサービス 曳地トシ+曳地義治
注:
 は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。 Posted by nekoneko at 10:35│Comments(0)
│読書