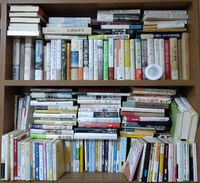2023年11月01日
2023年10月の記録
ひと月にこれだけ読めているのに「読めてない!」と感じるのは、
積読の山に追い立てられているからだろう。
客観的には冊数は読めているし、読むべき本も数冊は読んでいる。
晩酌の量を減らせばもっと読めるかもよ、と自分を唆しておく。
一石二鳥。
<今月のデータ>
購入17冊、購入費用20,501円。
読了16冊。
積読本324冊(うちKindle本152冊、Honto本3冊)。

 太陽の黄金(きん)の林檎〔新装版〕 (ハヤカワ文庫SF)の感想
太陽の黄金(きん)の林檎〔新装版〕 (ハヤカワ文庫SF)の感想
皇帝の不興を買う「空飛ぶ機械」や、音を垂れ流す機械をアイスの海に沈める「殺人」など、それぞれテイストが違って凄い。なかでも断然「ぬいとり」が好き。女の手は家の内外に絶え間なく働き、心地よさを、生活を、自他の人生をつくりあげる。まるで意思を持っているかのように動き続ける。もし、明日世界が終わると知ったら、その手は働くことをやめるだろうか? 男の手がとっとと仕事を諦め、動きを止めたとしても、女の手は世界が燃え尽きるその瞬間まで働き続ける、その幻想的な様が素敵。こういうのに出会えるから、短編集は面白い。
読了日:10月29日 著者:レイ ブラッドベリ
 家は生態系―あなたは20万種の生き物と暮らしているの感想
家は生態系―あなたは20万種の生き物と暮らしているの感想
いやぁ面白かった。人間の住む環境は微生物だらけだと私は知っている。見えない微生物が世界に大きな役割を担っているとも知っている。しかし家の中に少なくとも8000種近くの生物がいると聞くとさすがにたじろいだ。布団やソファは無論、冷蔵庫にも給湯器にも水道水にも…? 読者の引きつった顔を想像して楽しむかのように、ロブ・ダンは研究の成果から話を展開していく。現代人はついそれらを殲滅できないかと考えるが、その大半は無害または有益で、殺菌は悪手。家の中も外と同様、多様性があってこそ人間の身体は健全に保たれると指摘する。
トキソプラズマの章が興味深い。人間を含む多くの哺乳類が感染するトキソプラズマ原虫の最終目的地は、ネコ科動物の腸管上皮の内層である。トキソプラズマ原虫は宿主にリスクテイキングな行動を促し、おそらくはネコ科動物に遭遇しやすく(捕食されやすく)していると考えられる。人間は操縦されているのだ。フランスでは全国民の50%以上に不顕性感染の証拠が見られた。アメリカで20%以上。感染率が生活や行動の様式によるなら日本はもっと低いか。自由や冒険への指向性、民族性と絡めると、人類の歴史をも左右し得る壮大なテーマではないか。
読了日:10月28日 著者:ロブ・ダン
 沖縄から貧困がなくならない本当の理由 (光文社新書)の感想
沖縄から貧困がなくならない本当の理由 (光文社新書)の感想
私が知らない沖縄が書かれている。米軍基地問題において、不満を抑え込むためのじゃぶじゃぶの補助金は、確かに自治体を自律失調に陥れているだろう。同調圧力という日本人特性を更に煮詰めたようなシマ社会も、沖縄県民を総じて幸せにはしていないように見える。「真面目(マーメー)」が最大級の侮辱言葉だと沖縄大学の学生は調査に回答したという。出る杭を折れるまでとことんブチのめすとあれば、どういうメンタリティだろう。全国に突出した貧困の原因を、著者は自尊心の低さに見出している。こういう見方があるととりあえず記憶しておく。
読了日:10月25日 著者:樋口 耕太郎
 薬膳ナムル手帖: 野菜のおいしい作りおきの感想
薬膳ナムル手帖: 野菜のおいしい作りおきの感想
ナムル好き。なぜなら手順が簡単。調味料の種類が少ない。野菜が摂れる。味つけに困らない。日持ちがする。そして野菜は1種類でいい。夫も喜んで食べる。それで薬膳?ええやん! というので飛びついた。通年ある野菜でもよし、旬の野菜はもっとよし。にんにくはたくさん刻んでオリーブオイル/ごま油に漬けておくと日持ちするしすぐに使える。オプションもナッツやきくらげなど常備しているようなものでよい。あとは、油を入れすぎてギトギトにして気持ち悪くならないようにつくるだけ。
読了日:10月23日 著者:植木もも子
 保育士よちよち日記――お散歩、お昼寝、おむつ替え…ぜんぜん人手が足りませんの感想
保育士よちよち日記――お散歩、お昼寝、おむつ替え…ぜんぜん人手が足りませんの感想
子どもって驚異だよなあ。毎日預かる大変さは想像を絶する。『保育士の仕事は感情労働だ』と著者は言う。予測不能の事態や理不尽な要求、業務過多といった要素は他の職業と変わらない。しかし危険回避と、子どもは大人の張りぼてを見抜くから、常に感情で向き合うのはしんどいという意味か。一方、園児の好意もストレートに得られて幸せホルモンどばどばなら、自尊心とか叱って思いどおりの行動をさせようとか、くだらなく思えないものだろうか。他職種からの転職組、数々の保育園を経験した派遣保育士だからこその構造的発見もあるとよかった。
園長をトップとした厳格なヒエラルキー組織。組織としては変革しにくいだろう。そうでなくても親や役所や世間に対して「なにかあったら大変」意識が強く、厳格化された統一ルールに従うことを求められる。強烈な閉鎖性と同調圧力を感じる。同僚にも干渉しない。有期契約の著者は「園によって違うよね」と肩をすくめて済ませるが、それではますます保育士のなり手も減り、しんどくなっていくだけなんじゃないか。と、親や祖父母の就労証明書を毎年手書きさせられる労務担当者は思う。
読了日:10月22日 著者:大原 綾希子
 新たなるインド映画の世界の感想
新たなるインド映画の世界の感想
再読。前回より観た本数も回数も増えて、ラーマ王子とシータ姫そうだったのか!などと瞠目すること多し。言語や宗教の多様ぶりもさながら、映画製作自体が各文化圏で独立していること、音楽も分業制になっていて、古典音楽の習得が必須なことなど、奥深くて面白過ぎる。ただし俳優の多くは映画カーストの出身とか、サルマーン・カーンはひき逃げ事件の悪印象を払拭するために「バジュランギおじさん~」で善い人を演じたとか、知りたくないこともままあるものだ。また知りすぎると感性で観られなくなってしまう部分もあるので、程々で。
読了日:10月19日 著者:夏目 深雪,松岡 環,高倉 嘉男,安宅 直子,岡本 敦史,浦川 留
 東京プリズン (河出文庫)の感想
東京プリズン (河出文庫)の感想
過去と現在、現実と幻想が入り交じって読みづらいが、ヘラジカもベトナムの双子も、最後の公開ディベートに向けて主人公を導く存在である。『日本の天皇ヒロヒトには、第二次世界大戦の戦争責任がある』。アメリカ人にこれを言われると、腹にずんと重い衝撃を感じ、反動でぐっとせり上がるものがある。じゃあ日本人は、いくつもの都市を絨毯爆撃し原発を落とし一方的に裁いたアメリカの所業を、どのように考え、何を求めるのか。あの戦争は加害と被害が両輪だ。今は"同盟国"だろうと、お互い何も思わないほど過去ではない。おそらくこれからも。
マッカーサーは昭和天皇に11回も直接会い、話し、天皇という人と在りかたに理解を深めたのだろう。しかし一般に、アメリカ人は大日本帝国憲法や訳語の定義に沿って昭和天皇こそ第一戦犯と捉え、断罪を求める。日本人にとっての天皇を、歴史の浅いアメリカ、さらに一神教を信仰する国民が大多数のアメリカで、理解することはかなり難しいだろう。そして日本人が自分たちにとっての天皇の存在を論理的に説明することもまた難しいことを自覚し、その双方を理解しておく必要がある。ということをこの小説は独特な形で描いている。
願わくば、日本の子供たちに戦争を起こした日本のことをちゃんと教えてください。拠って立つ自国の歴史の真実を知らないまま、心の備えを持たないまま諸外国の人と向き合うなんて、残酷で恥ずかしい事をさせるな。憲法をヘンな文章だねとか主語が無いのなんでとか言いながらでも、知って、考える素地を養うことは義務教育の義務だ。
読了日:10月14日 著者:赤坂 真理
 ひとはなぜ戦争をするのか (講談社学術文庫)の感想
ひとはなぜ戦争をするのか (講談社学術文庫)の感想
アインシュタインとフロイトの往復書簡。1932年、アインシュタインはフロイトなら戦争の問題解決を阻む障害を取り除く方法を示唆できるのではと問うた。手紙は1通ずつで長くはなく、後半は養老先生と斎藤環氏による解説である。アインシュタイン53歳、フロイト76歳、両者ともユダヤ人でナチスの興隆に伴い西側へ亡命した。フロイトは『文化の発展を促せば、戦争の終焉へ向けて歩み出すことができる』と手紙を締めたが、未だそうはならない。パレスチナ/イスラエル紛争の報道を見るにつけ、ユダヤ人すらそうなら、何が希望かと空を仰ぐ。
読了日:10月13日 著者:アルバート アインシュタイン,ジグムント フロイト
 給料の上げ方: 日本人みんなで豊かになるの感想
給料の上げ方: 日本人みんなで豊かになるの感想
「日本人の勝算」を読んだのが2019年。政府に直接働きかけ、大企業中小企業を叱咤し、しかし遅々として変わらない日本。ならばとアトキンソン氏は被雇用者に語りかけることにした。立ち上がれ、自己防衛せよと。経営者側の視点でも有用である。近く負担が重くなる日本で、氏の算出した給与上昇率はベア1.4%、定期昇給2.8%で年4.2%。提供するものに価値があるか。値上げにつながる付加価値を提供できるか、また目指しているか。そのうえで給料を上げ続けることができるか。氏が読者に問いかける要点は、即ち企業の課題である。
GDPや物価の上昇を是とする現状への懐疑心は暫時保留として。労働生産性について少しは理解が及んだように思う。「労働生産性が低い」とは個々人の働きの効率が悪いことではない。人の生みだしたものの価値は、不断の努力によってより高いものになるはずで、さすれば価格は上がるはずで、労働者への分配も上がるべきと考える。違っているかもしれないが、とりあえずそのように納得した。
氏は大企業寄りの論調だったように記憶していたが、今回「従業員100~300人の中堅企業がバランスが良い」としていて、目が留まった。労働分配率も、大企業や零細企業より程良いようだ。『厳しさが増すこれからの時代は、環境の変化を先取りし、その都度対応策を打ちながら規模を拡大させていくのが、もっとも現実的かつ有効な企業の成長の道筋のように感じます。つまり、重要なのは単純な規模の大小ではなく、適切なタイミングで適切な規模へ成長することなのです』。
読了日:10月11日 著者:デービッド・アトキンソン
 辺境の怪書、歴史の驚書、ハードボイルド読書合戦の感想
辺境の怪書、歴史の驚書、ハードボイルド読書合戦の感想
このお二人のセンスで選んだ課題図書を巡っての対談は面白い。辺境に住む民族は未開なのではなく、あえて稲作や道具を放棄した、とか、国境線近くは辺境だが交易の舞台でもある、とか、朝鮮出兵は文化を均質化する効果をもたらした、とか、数多の研究結果、見聞録から、自身の体験も含めて考え併せ、「世界の見方」をつくっていくのだ。点と点が繋がって"知の網"になる。高野さんはそれを「教養」の形成過程と感じたという。文明や豊かさについて考え直すことの知的興奮はこちらにも伝染して、自分がどんどん「常識」から外れていくのが楽しい。
読了日:10月10日 著者:高野 秀行,清水 克行
 ガルヴェイアスの犬 (新潮クレスト・ブックス)の感想
ガルヴェイアスの犬 (新潮クレスト・ブックス)の感想
小さな村、ガルヴェイアス。ある日宇宙から落ちてきた巨大な物の正体が何なのかは最後までわからない。ただ空気中に硫黄の臭いが満ち、パンは不味くなった。想像しただけでもしんどい。それでも人は弱くも、愚かにも、悲しくも、だましだまし生きていく。小さな村の人間関係は絡まり合っている。あるエピソードに登場する脇役が次のエピソードの主役になり、関係が輪郭を取りながら物語は進む。郵便配達人のジャネイロは、1年に1度訪れるギニアの地で人が変わったように生き生きとする。それでもガルヴェイアスに戻るのは、自分の場所だからか。
『誰にだって、運命の場所ってもんがあるのさ。誰の世界にも中心がある。あたしの場所はあんたのよりましだとか、そんなことは関係ないの。自分の場所ってのは他人のそれと比べるようなものじゃない。自分だけの大事なもんだからね。どこにあるかなんて、自分にしかわからないの。みんなの目に見える物にはその形の上に見えない層がいくつも重なっているんだ。自分の場所をだれかに説明しようったって無理だよ、わかっちゃもらえないからね』
読み終えたら、また最初から読みたくなる。ひとつには、人柄や人間関係がひととおりわかったから、改めてその人たちの行ないを違った目で見られること。ひとつには、一度気づいたからといって、小さな村の人々は暮らしかたを変えてしまえたりはしなくて、また同じループを数年ごと、数十年ごとに繰り返すだろうから。エンドレスなのだ。
読了日:10月09日 著者:ジョゼ・ルイス ペイショット
 「昭和天皇実録」の謎を解く (文春新書)の感想
「昭和天皇実録」の謎を解く (文春新書)の感想
宮内庁が編纂した昭和天皇の実録は61冊に及ぶという。生涯通じた記録の中でも、対談の焦点は戦前から戦後に集中する。最初から軍人として育てられた唯一の天皇。立憲君主として、神の子孫として、また軍の総統としてのお立場がある故の相克の深さを読み解く。止めることができない懊悩でやせ細る陛下の様子、実母である皇太后に疎開を拒否された日の苦しみなど、私には厳しそうで怖いおじいさんでしかなかった昭和天皇が一人の若い人間として像を結んだ。いたわしい、と思った。他方で、実録編纂の目的に天皇像の形成がある点も留めておきたい。
『我が国は軍事国家だったんだなあと、しみじみわかりました。もう、軍事のことばかりですよ』(半藤)。戦況が悪くなる前から、軍部は本当の戦況を陛下に報告しない。陛下にもそれがわかっていたから、アメリカの短波放送を頼りにご自身で情報を得、あるべき方向を模索していたという。担ぎ上げながら、天皇の意志を平然と無視する陸軍。『軍部にとって天皇とは、最高指揮官などではなく、神殿の壁のようなもの』だったとする半藤さんの評が印象深い。
読了日:10月07日 著者:半藤 一利,御厨 貴,磯田 道史,保阪 正康
 (074)船 (百年文庫)の感想
(074)船 (百年文庫)の感想
海。日本のまわりを囲む海。ある日は荒れ、ある日は凪ぐ水面の上で、隔絶された船の上では大漁に高揚したり漂流に絶望したりと、ぎゅっと濃縮された人間模様が展開される。なににしてもダイナミックな様相を見せる海の上だからだろうか、あるいは狭い船の上で強調して見えるからだろうか、人々の心の動きもダイナミックに描かれる3篇。なかでも「海神丸」は約2カ月もの太平洋漂流である。陸を離れて何千年も経ったようなと思われるほど、簡単には訪れない死、また一方で簡単に訪れる死。その非業の様相にもまた、海は何を思うことなく在るのみだ。
読了日:10月07日 著者:近藤 啓太郎,野上 弥生子,徳田 秋声
 新編 日本の面影 (2) (角川ソフィア文庫)の感想
新編 日本の面影 (2) (角川ソフィア文庫)の感想
『私この小泉八雲、日本人よりも本当の日本を愛するです』。引き続き日本愛に満ちた文章。雑誌に掲載する体裁ではなく、本当に愛していたのだとしみじみ読む。「伯耆から隠岐へ」は逸品だ。蒸気船に乗るくだりなどは、乗り心地の悪さに閉口したことを軽妙に書くのも楽しそうだ。一方、帰りの便では穏やかな憂鬱を描き切る、こちらも印象が深い。物質社会から離れた自然への敬慕。晩年に東京の西大久保に屋敷を買って住むのに、静かな環境と和の設えを喜んだという。『余り喜ぶの余りまた心配です。この家に住む事永いを喜びます』。2年余で死去。
読了日:10月03日 著者:ラフカディオ・ハーン
 サピエンス日本上陸 3万年前の大航海の感想
サピエンス日本上陸 3万年前の大航海の感想
人類は3万5000年前に琉球列島に到達し、5000年の間に日本列島全体に拡がったとされる。その過程を検証するプロジェクト。今の日本人の祖となるだけの人々が、広大な大陸から、島影の見えない海へ、漕ぎ出そうと考えたのはなぜか。海面下がどうなっているか、目指す地がどの方向にあるかわからない。失敗は死に直結した。著者は『海に立ち向かった挑戦者』と結論する。人類は直ちに必要のない事に挑む。命がけの遊びを面白がるのは現代も同じだ。拡大解釈すれば、人類が瞬く間に地球全体に拡がって支配者となった理由も。悪い気はしない。
狩猟採集民であった先祖は現代人よりも身体能力に優れ、生きるための必要以上のことに好奇心を持って挑み、技術は無くとも物を創る能力に長けていた。彼らを、現代の自分たちより劣ったものとして考える癖が染みついているのを自覚する。これを鮮やかに取り払いたいと考えている。その流れとしてグレーバーの新刊を読みたい。しかし5,500円か…。
読了日:10月01日 著者:海部 陽介
注: は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。
積読の山に追い立てられているからだろう。
客観的には冊数は読めているし、読むべき本も数冊は読んでいる。
晩酌の量を減らせばもっと読めるかもよ、と自分を唆しておく。
一石二鳥。
<今月のデータ>
購入17冊、購入費用20,501円。
読了16冊。
積読本324冊(うちKindle本152冊、Honto本3冊)。

 太陽の黄金(きん)の林檎〔新装版〕 (ハヤカワ文庫SF)の感想
太陽の黄金(きん)の林檎〔新装版〕 (ハヤカワ文庫SF)の感想皇帝の不興を買う「空飛ぶ機械」や、音を垂れ流す機械をアイスの海に沈める「殺人」など、それぞれテイストが違って凄い。なかでも断然「ぬいとり」が好き。女の手は家の内外に絶え間なく働き、心地よさを、生活を、自他の人生をつくりあげる。まるで意思を持っているかのように動き続ける。もし、明日世界が終わると知ったら、その手は働くことをやめるだろうか? 男の手がとっとと仕事を諦め、動きを止めたとしても、女の手は世界が燃え尽きるその瞬間まで働き続ける、その幻想的な様が素敵。こういうのに出会えるから、短編集は面白い。
読了日:10月29日 著者:レイ ブラッドベリ

 家は生態系―あなたは20万種の生き物と暮らしているの感想
家は生態系―あなたは20万種の生き物と暮らしているの感想いやぁ面白かった。人間の住む環境は微生物だらけだと私は知っている。見えない微生物が世界に大きな役割を担っているとも知っている。しかし家の中に少なくとも8000種近くの生物がいると聞くとさすがにたじろいだ。布団やソファは無論、冷蔵庫にも給湯器にも水道水にも…? 読者の引きつった顔を想像して楽しむかのように、ロブ・ダンは研究の成果から話を展開していく。現代人はついそれらを殲滅できないかと考えるが、その大半は無害または有益で、殺菌は悪手。家の中も外と同様、多様性があってこそ人間の身体は健全に保たれると指摘する。
トキソプラズマの章が興味深い。人間を含む多くの哺乳類が感染するトキソプラズマ原虫の最終目的地は、ネコ科動物の腸管上皮の内層である。トキソプラズマ原虫は宿主にリスクテイキングな行動を促し、おそらくはネコ科動物に遭遇しやすく(捕食されやすく)していると考えられる。人間は操縦されているのだ。フランスでは全国民の50%以上に不顕性感染の証拠が見られた。アメリカで20%以上。感染率が生活や行動の様式によるなら日本はもっと低いか。自由や冒険への指向性、民族性と絡めると、人類の歴史をも左右し得る壮大なテーマではないか。
読了日:10月28日 著者:ロブ・ダン
 沖縄から貧困がなくならない本当の理由 (光文社新書)の感想
沖縄から貧困がなくならない本当の理由 (光文社新書)の感想私が知らない沖縄が書かれている。米軍基地問題において、不満を抑え込むためのじゃぶじゃぶの補助金は、確かに自治体を自律失調に陥れているだろう。同調圧力という日本人特性を更に煮詰めたようなシマ社会も、沖縄県民を総じて幸せにはしていないように見える。「真面目(マーメー)」が最大級の侮辱言葉だと沖縄大学の学生は調査に回答したという。出る杭を折れるまでとことんブチのめすとあれば、どういうメンタリティだろう。全国に突出した貧困の原因を、著者は自尊心の低さに見出している。こういう見方があるととりあえず記憶しておく。
読了日:10月25日 著者:樋口 耕太郎

 薬膳ナムル手帖: 野菜のおいしい作りおきの感想
薬膳ナムル手帖: 野菜のおいしい作りおきの感想ナムル好き。なぜなら手順が簡単。調味料の種類が少ない。野菜が摂れる。味つけに困らない。日持ちがする。そして野菜は1種類でいい。夫も喜んで食べる。それで薬膳?ええやん! というので飛びついた。通年ある野菜でもよし、旬の野菜はもっとよし。にんにくはたくさん刻んでオリーブオイル/ごま油に漬けておくと日持ちするしすぐに使える。オプションもナッツやきくらげなど常備しているようなものでよい。あとは、油を入れすぎてギトギトにして気持ち悪くならないようにつくるだけ。
読了日:10月23日 著者:植木もも子
 保育士よちよち日記――お散歩、お昼寝、おむつ替え…ぜんぜん人手が足りませんの感想
保育士よちよち日記――お散歩、お昼寝、おむつ替え…ぜんぜん人手が足りませんの感想子どもって驚異だよなあ。毎日預かる大変さは想像を絶する。『保育士の仕事は感情労働だ』と著者は言う。予測不能の事態や理不尽な要求、業務過多といった要素は他の職業と変わらない。しかし危険回避と、子どもは大人の張りぼてを見抜くから、常に感情で向き合うのはしんどいという意味か。一方、園児の好意もストレートに得られて幸せホルモンどばどばなら、自尊心とか叱って思いどおりの行動をさせようとか、くだらなく思えないものだろうか。他職種からの転職組、数々の保育園を経験した派遣保育士だからこその構造的発見もあるとよかった。
園長をトップとした厳格なヒエラルキー組織。組織としては変革しにくいだろう。そうでなくても親や役所や世間に対して「なにかあったら大変」意識が強く、厳格化された統一ルールに従うことを求められる。強烈な閉鎖性と同調圧力を感じる。同僚にも干渉しない。有期契約の著者は「園によって違うよね」と肩をすくめて済ませるが、それではますます保育士のなり手も減り、しんどくなっていくだけなんじゃないか。と、親や祖父母の就労証明書を毎年手書きさせられる労務担当者は思う。
読了日:10月22日 著者:大原 綾希子

 新たなるインド映画の世界の感想
新たなるインド映画の世界の感想再読。前回より観た本数も回数も増えて、ラーマ王子とシータ姫そうだったのか!などと瞠目すること多し。言語や宗教の多様ぶりもさながら、映画製作自体が各文化圏で独立していること、音楽も分業制になっていて、古典音楽の習得が必須なことなど、奥深くて面白過ぎる。ただし俳優の多くは映画カーストの出身とか、サルマーン・カーンはひき逃げ事件の悪印象を払拭するために「バジュランギおじさん~」で善い人を演じたとか、知りたくないこともままあるものだ。また知りすぎると感性で観られなくなってしまう部分もあるので、程々で。
読了日:10月19日 著者:夏目 深雪,松岡 環,高倉 嘉男,安宅 直子,岡本 敦史,浦川 留
 東京プリズン (河出文庫)の感想
東京プリズン (河出文庫)の感想過去と現在、現実と幻想が入り交じって読みづらいが、ヘラジカもベトナムの双子も、最後の公開ディベートに向けて主人公を導く存在である。『日本の天皇ヒロヒトには、第二次世界大戦の戦争責任がある』。アメリカ人にこれを言われると、腹にずんと重い衝撃を感じ、反動でぐっとせり上がるものがある。じゃあ日本人は、いくつもの都市を絨毯爆撃し原発を落とし一方的に裁いたアメリカの所業を、どのように考え、何を求めるのか。あの戦争は加害と被害が両輪だ。今は"同盟国"だろうと、お互い何も思わないほど過去ではない。おそらくこれからも。
マッカーサーは昭和天皇に11回も直接会い、話し、天皇という人と在りかたに理解を深めたのだろう。しかし一般に、アメリカ人は大日本帝国憲法や訳語の定義に沿って昭和天皇こそ第一戦犯と捉え、断罪を求める。日本人にとっての天皇を、歴史の浅いアメリカ、さらに一神教を信仰する国民が大多数のアメリカで、理解することはかなり難しいだろう。そして日本人が自分たちにとっての天皇の存在を論理的に説明することもまた難しいことを自覚し、その双方を理解しておく必要がある。ということをこの小説は独特な形で描いている。
願わくば、日本の子供たちに戦争を起こした日本のことをちゃんと教えてください。拠って立つ自国の歴史の真実を知らないまま、心の備えを持たないまま諸外国の人と向き合うなんて、残酷で恥ずかしい事をさせるな。憲法をヘンな文章だねとか主語が無いのなんでとか言いながらでも、知って、考える素地を養うことは義務教育の義務だ。
読了日:10月14日 著者:赤坂 真理

 ひとはなぜ戦争をするのか (講談社学術文庫)の感想
ひとはなぜ戦争をするのか (講談社学術文庫)の感想アインシュタインとフロイトの往復書簡。1932年、アインシュタインはフロイトなら戦争の問題解決を阻む障害を取り除く方法を示唆できるのではと問うた。手紙は1通ずつで長くはなく、後半は養老先生と斎藤環氏による解説である。アインシュタイン53歳、フロイト76歳、両者ともユダヤ人でナチスの興隆に伴い西側へ亡命した。フロイトは『文化の発展を促せば、戦争の終焉へ向けて歩み出すことができる』と手紙を締めたが、未だそうはならない。パレスチナ/イスラエル紛争の報道を見るにつけ、ユダヤ人すらそうなら、何が希望かと空を仰ぐ。
読了日:10月13日 著者:アルバート アインシュタイン,ジグムント フロイト

 給料の上げ方: 日本人みんなで豊かになるの感想
給料の上げ方: 日本人みんなで豊かになるの感想「日本人の勝算」を読んだのが2019年。政府に直接働きかけ、大企業中小企業を叱咤し、しかし遅々として変わらない日本。ならばとアトキンソン氏は被雇用者に語りかけることにした。立ち上がれ、自己防衛せよと。経営者側の視点でも有用である。近く負担が重くなる日本で、氏の算出した給与上昇率はベア1.4%、定期昇給2.8%で年4.2%。提供するものに価値があるか。値上げにつながる付加価値を提供できるか、また目指しているか。そのうえで給料を上げ続けることができるか。氏が読者に問いかける要点は、即ち企業の課題である。
GDPや物価の上昇を是とする現状への懐疑心は暫時保留として。労働生産性について少しは理解が及んだように思う。「労働生産性が低い」とは個々人の働きの効率が悪いことではない。人の生みだしたものの価値は、不断の努力によってより高いものになるはずで、さすれば価格は上がるはずで、労働者への分配も上がるべきと考える。違っているかもしれないが、とりあえずそのように納得した。
氏は大企業寄りの論調だったように記憶していたが、今回「従業員100~300人の中堅企業がバランスが良い」としていて、目が留まった。労働分配率も、大企業や零細企業より程良いようだ。『厳しさが増すこれからの時代は、環境の変化を先取りし、その都度対応策を打ちながら規模を拡大させていくのが、もっとも現実的かつ有効な企業の成長の道筋のように感じます。つまり、重要なのは単純な規模の大小ではなく、適切なタイミングで適切な規模へ成長することなのです』。
読了日:10月11日 著者:デービッド・アトキンソン

 辺境の怪書、歴史の驚書、ハードボイルド読書合戦の感想
辺境の怪書、歴史の驚書、ハードボイルド読書合戦の感想このお二人のセンスで選んだ課題図書を巡っての対談は面白い。辺境に住む民族は未開なのではなく、あえて稲作や道具を放棄した、とか、国境線近くは辺境だが交易の舞台でもある、とか、朝鮮出兵は文化を均質化する効果をもたらした、とか、数多の研究結果、見聞録から、自身の体験も含めて考え併せ、「世界の見方」をつくっていくのだ。点と点が繋がって"知の網"になる。高野さんはそれを「教養」の形成過程と感じたという。文明や豊かさについて考え直すことの知的興奮はこちらにも伝染して、自分がどんどん「常識」から外れていくのが楽しい。
読了日:10月10日 著者:高野 秀行,清水 克行

 ガルヴェイアスの犬 (新潮クレスト・ブックス)の感想
ガルヴェイアスの犬 (新潮クレスト・ブックス)の感想小さな村、ガルヴェイアス。ある日宇宙から落ちてきた巨大な物の正体が何なのかは最後までわからない。ただ空気中に硫黄の臭いが満ち、パンは不味くなった。想像しただけでもしんどい。それでも人は弱くも、愚かにも、悲しくも、だましだまし生きていく。小さな村の人間関係は絡まり合っている。あるエピソードに登場する脇役が次のエピソードの主役になり、関係が輪郭を取りながら物語は進む。郵便配達人のジャネイロは、1年に1度訪れるギニアの地で人が変わったように生き生きとする。それでもガルヴェイアスに戻るのは、自分の場所だからか。
『誰にだって、運命の場所ってもんがあるのさ。誰の世界にも中心がある。あたしの場所はあんたのよりましだとか、そんなことは関係ないの。自分の場所ってのは他人のそれと比べるようなものじゃない。自分だけの大事なもんだからね。どこにあるかなんて、自分にしかわからないの。みんなの目に見える物にはその形の上に見えない層がいくつも重なっているんだ。自分の場所をだれかに説明しようったって無理だよ、わかっちゃもらえないからね』
読み終えたら、また最初から読みたくなる。ひとつには、人柄や人間関係がひととおりわかったから、改めてその人たちの行ないを違った目で見られること。ひとつには、一度気づいたからといって、小さな村の人々は暮らしかたを変えてしまえたりはしなくて、また同じループを数年ごと、数十年ごとに繰り返すだろうから。エンドレスなのだ。
読了日:10月09日 著者:ジョゼ・ルイス ペイショット
 「昭和天皇実録」の謎を解く (文春新書)の感想
「昭和天皇実録」の謎を解く (文春新書)の感想宮内庁が編纂した昭和天皇の実録は61冊に及ぶという。生涯通じた記録の中でも、対談の焦点は戦前から戦後に集中する。最初から軍人として育てられた唯一の天皇。立憲君主として、神の子孫として、また軍の総統としてのお立場がある故の相克の深さを読み解く。止めることができない懊悩でやせ細る陛下の様子、実母である皇太后に疎開を拒否された日の苦しみなど、私には厳しそうで怖いおじいさんでしかなかった昭和天皇が一人の若い人間として像を結んだ。いたわしい、と思った。他方で、実録編纂の目的に天皇像の形成がある点も留めておきたい。
『我が国は軍事国家だったんだなあと、しみじみわかりました。もう、軍事のことばかりですよ』(半藤)。戦況が悪くなる前から、軍部は本当の戦況を陛下に報告しない。陛下にもそれがわかっていたから、アメリカの短波放送を頼りにご自身で情報を得、あるべき方向を模索していたという。担ぎ上げながら、天皇の意志を平然と無視する陸軍。『軍部にとって天皇とは、最高指揮官などではなく、神殿の壁のようなもの』だったとする半藤さんの評が印象深い。
読了日:10月07日 著者:半藤 一利,御厨 貴,磯田 道史,保阪 正康

 (074)船 (百年文庫)の感想
(074)船 (百年文庫)の感想海。日本のまわりを囲む海。ある日は荒れ、ある日は凪ぐ水面の上で、隔絶された船の上では大漁に高揚したり漂流に絶望したりと、ぎゅっと濃縮された人間模様が展開される。なににしてもダイナミックな様相を見せる海の上だからだろうか、あるいは狭い船の上で強調して見えるからだろうか、人々の心の動きもダイナミックに描かれる3篇。なかでも「海神丸」は約2カ月もの太平洋漂流である。陸を離れて何千年も経ったようなと思われるほど、簡単には訪れない死、また一方で簡単に訪れる死。その非業の様相にもまた、海は何を思うことなく在るのみだ。
読了日:10月07日 著者:近藤 啓太郎,野上 弥生子,徳田 秋声
 新編 日本の面影 (2) (角川ソフィア文庫)の感想
新編 日本の面影 (2) (角川ソフィア文庫)の感想『私この小泉八雲、日本人よりも本当の日本を愛するです』。引き続き日本愛に満ちた文章。雑誌に掲載する体裁ではなく、本当に愛していたのだとしみじみ読む。「伯耆から隠岐へ」は逸品だ。蒸気船に乗るくだりなどは、乗り心地の悪さに閉口したことを軽妙に書くのも楽しそうだ。一方、帰りの便では穏やかな憂鬱を描き切る、こちらも印象が深い。物質社会から離れた自然への敬慕。晩年に東京の西大久保に屋敷を買って住むのに、静かな環境と和の設えを喜んだという。『余り喜ぶの余りまた心配です。この家に住む事永いを喜びます』。2年余で死去。
読了日:10月03日 著者:ラフカディオ・ハーン

 サピエンス日本上陸 3万年前の大航海の感想
サピエンス日本上陸 3万年前の大航海の感想人類は3万5000年前に琉球列島に到達し、5000年の間に日本列島全体に拡がったとされる。その過程を検証するプロジェクト。今の日本人の祖となるだけの人々が、広大な大陸から、島影の見えない海へ、漕ぎ出そうと考えたのはなぜか。海面下がどうなっているか、目指す地がどの方向にあるかわからない。失敗は死に直結した。著者は『海に立ち向かった挑戦者』と結論する。人類は直ちに必要のない事に挑む。命がけの遊びを面白がるのは現代も同じだ。拡大解釈すれば、人類が瞬く間に地球全体に拡がって支配者となった理由も。悪い気はしない。
狩猟採集民であった先祖は現代人よりも身体能力に優れ、生きるための必要以上のことに好奇心を持って挑み、技術は無くとも物を創る能力に長けていた。彼らを、現代の自分たちより劣ったものとして考える癖が染みついているのを自覚する。これを鮮やかに取り払いたいと考えている。その流れとしてグレーバーの新刊を読みたい。しかし5,500円か…。
読了日:10月01日 著者:海部 陽介

注:
 は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。 Posted by nekoneko at 15:31│Comments(0)
│読書