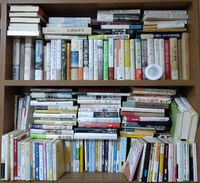2024年04月01日
2024年3月の記録
読み過ぎである。
引越作業の多忙で読めなかった反動、と言えばそうだが、
逆に引越が落ち着いて手持ち無沙汰になったということだろう。
運動不足だし、情報過多。
腰を据えて読まなければ理解できないノンフィクションや、登場人物が多すぎる小説でなければ、読むことで自分にたいした負荷はかからないと思っていたけれど、実はかなり疲弊しているようだ。
<今月のデータ>
購入13冊、購入費用12,678円。
読了20冊。
積読本325冊(うちKindle本155冊)。

 愚か者、中国をゆく (光文社新書 350)の感想
愚か者、中国をゆく (光文社新書 350)の感想
香港に住む10年前、星野さんは香港中文大学に留学し、社会主義色強い中国を旅した。その20年後に訪れた中国は、資本主義色を濃くしていた。公共交通システムから何から、スケールが違う。広大な国土、桁違いの人口、国家の成り立ちに由来する非合理的で超平等な社会の在りかた。わが手に得られるものに対する熱量が尋常でない。星野さんはそれらに納得したうえで、資本主義を取り込んだ中国の行く先を危惧した。『中国では何かが起きる時、徹底的に、破壊的に起きるからである』。人々の長く培った飢餓感は今も暴走している気がする。"激烈"。
「国」がでかすぎて、中国は…と話していても、全体の話はできていない前提が常に頭の隅にある。多様な民族を内包しながら、よくもあの広さの「国」を保てていると改めて驚嘆する。
読了日:03月27日 著者:星野博美
 自閉症は津軽弁を話さない 自閉スペクトラム症のことばの謎を読み解く (角川ソフィア文庫)の感想
自閉症は津軽弁を話さない 自閉スペクトラム症のことばの謎を読み解く (角川ソフィア文庫)の感想
「自閉症の子供は方言を話さない」という世間の認識を、専門家が調査する。そんなわかりやすそうなことがそれまで検証されていなかったのかと驚くが、学術的理論と現場の段差、それが最も大きそうだ。さて、自閉スペクトラム症は社会性の障害と言われる。子供が母語を習得する過程で必要な、家族など周囲の模倣や意図の読み取りに難があること、他方で繰り返し見られる映画やアニメからは言語を学びやすいことにこの現象が繋がってくると知った。社会的意味や心理的距離は理解が難しくても、ひとつ用法を覚えれば方言を使うことはできるのでは。
読了日:03月23日 著者:松本 敏治
 ブラフマンの埋葬 (講談社文庫)の感想
ブラフマンの埋葬 (講談社文庫)の感想
なぜこの小説を読もうと思ったのだったか。猫でも犬でもなくても、毛が生えて温かくてまっすぐ見つめてくる生き物、それだけで人は愛着を持ってしまう。タイトルに埋葬とあれば、身構えつつ読まざるを得ないではないか。主人公は独りだ。やって来る人々も独りだ。主人公は見知らぬ五人家族の写真を買って飾る。家族を想像する。独りでなくなりたかったのだろうか。娘を伴侶にして二人になりたかったのだろうか。身勝手でブラフマンに冷淡な娘を、ほんとうに?
読了日:03月20日 著者:小川 洋子
 読書アンケート2023――識者が選んだ、この一年の本の感想
読書アンケート2023――識者が選んだ、この一年の本の感想
月刊誌「みすず」で読んでみたいと思っていた読者アンケートは、月刊誌「みすず」が休刊になり、単独で冊子として発刊された。内容は、各界知識人139名が、2023年に読んだ本で印象深かった本を数冊挙げ、所感を添えるもの。寄稿した知識人のうち私が知っているのは数名で、挙げられた本に至っては700冊近いなかで数冊という、自らの教養と関心のへっぽこぶりを思い知らされた。絶版で読みそびれているイスラエル人作家アモス・オズは、取り寄せて読む。何人もが挙げたデイヴィッド・グレーバー「万物の黎明」は、ひきつづき頑張る。
「万物の黎明」について。『(偶像を)破壊するだけの天才はけっこういると思うんですけど、グレーバーの場合、なぜ破壊しなければならないのか、破壊した後に何が立ち上がるのか、という本人のヴィジョンが明確なところが一線を画しているんだと思います』。ブレイディみかこ
読了日:03月19日 著者:
 園芸家の一年 (平凡社ライブラリー)の感想
園芸家の一年 (平凡社ライブラリー)の感想
再読。自由にできる地面を手に入れた途端、私は飽かず眺めては、ああするのはどうだろう、ここはどうしたらいいだろう、あの木は植えたい、これも植えたい、植える場所がまだ決まってないのに球根が届いてしまった、枯れ木のような枝をいつまでもにやにや眺めている、他所様の田畑の草花が羨ましい、など、それはもうチャペックの描くアマチュア園芸家そのものに他ならないのに気づいて、微笑ましく思うのだ。しかしそこには自然に通じるなにか深遠なものがあると、これもこの歳になって気づいたことだ。『一年じゅう春であり、一生、青春時代だ』。
『未来は、わたしたちの先にあるのではない。もうここに、芽の形で存在しているのだから。未来は、もうわたしたちといっしょになっている。今わたしたちといっしょにいないものは、未来になっても存在しないだろう。わたしたちには芽が見えないが、それは芽が地面の下にあるからだ。わたしたちに未来が見えないのは、未来がわたしたちの中にあるからだ。』
読了日:03月19日 著者:カレル チャペック
 なんでもないもの 白洲正子エッセイ集<骨董> (角川ソフィア文庫)の感想
なんでもないもの 白洲正子エッセイ集<骨董> (角川ソフィア文庫)の感想
先日、実用にしなそうな漆芸の箱に惚れ、迷いに迷って購入を申し出た。結局は抽選に外れて手に入らなかったのだが、待っている間に白洲正子の「買ってみなきゃわからないのよ」を思い出した。各媒体に書かれたエッセイ。このざっくばらんな、真実を言い刺すような物言いが好きで、憧れる。先の名言は、続けて日常に使うことをも勧める。使ってこそ眼は養われ、日々の愉しみは増し、ものに味がつくのだと。陶磁器や工芸品、古道具は年々好きになっていて、安いものから気張ったものも、遅まきながら好事家になってみようと、こっそり企んでいる。
『私はあえて「発見」という言葉を用いたが、古いものの中から生活に合ったものを見出すのは、利休以来の日本人の伝統である。現代は独創ばやりの世の中だが、現在を支えているのが過去ならば、先ず古く美しい形をつかまねば、新しいものが見える道理はない。こんな自明のことを皆忘れている。忘れているのではなく、ふり返るのが恐ろしいらしい。が、伝統をしょって生きて行く勇気のないものに、何で新しいものを生み出す力が与えられよう』。
読了日:03月18日 著者:白洲 正子
 シャンタラム(下) (新潮文庫)の感想
シャンタラム(下) (新潮文庫)の感想
インドから広大で殺伐とした戦地アフガニスタンへ。日々に溢れていた音楽がぱったり止む。リンはここでも徹頭徹尾当事者ではない。ただカーデルバイと友のために決断した成り行きから、そこにいる。ムジャヒディンたちの傍に居、ムンバイに戻ればまたマフィアの傍に居て、知己を弔う。嘯いてはみるが、自身に大義は無い。祖国を失った者たちはムンバイに吹きだまり、また戻ってくる。逝ったはずの者たちも戻ってきて涙を誘う。ああ、読み終わってしまった…。ムンバイに帰りたい。もう一度初めから、リンが愛した皆に出会いたい。カノをハグしたい。
『ときには正しい理由から、まちがったことをしなければならないこともある。大事なのは、その理由が正しいものであると確信し、自分はまちがったことをしていると認めることだ』とカーデルバイは教えた。マフィア稼業であり、戦争のことだ。カーデルは考え抜いた末にそう信じることで、マフィアの王であり続けた。しかしジョーパダパッティなら、貧しくとも、正しい理由から正しいことをするのが自然でいられるんじゃないのか、リン。仲間を喪って、死者を赦すことを覚えて、そのたび自由になって、リンはようやく帰る場所を見つけることができた。
人は結局は土地と女のために戦っているのだとリンは言う。自ら戦地に赴くムジャヒディンのような戦士のことだ。死への崖っぷちぎりぎりの血みどろの日々が続けば、ごたいそうな大義や理由など吹っ飛んでしまう。ふと現実に戻って、戦争行為をしている地のことを想像するとき、平和な地から戦争行為をつべこべ言うことの空々しさを思った。インドとパキスタンの戦争を題材にした「Raazi」を英語字幕で観ていたら、"nature of war"という言葉が目に焼き付いた。戦争の本質。戦争は守りたいものを守ろうとする人間の本質なのか。
読了日:03月15日 著者:グレゴリー・デイヴィッド ロバーツ
 1㎡からはじめる自然菜園の感想
1㎡からはじめる自然菜園の感想
好きにしていい地面を手に入れたので、2平方メートルを自家菜園にすべく掘り返し始めた。ど素人としては、理想めいた方向で指南に沿ってとりあえずやってみるしかない。最初にだけ堆肥を入れて野菜が育つ土をつくったら、あとは草マルチと野菜自身の力で肥料の要を無くす。言うは易し。自分に自然農法ができるのか。それから母がよく言う連作障害、これを避けるための組み合わせプランがいろいろ紹介されている。イラストがまたかわいいのね。落花生から始めたいので、2区画、5月までに土づくり、そのあとに草の種を植えて育てます。
読了日:03月14日 著者:竹内孝功
 人類の終着点 戦争、AI、ヒューマニティの未来 (朝日新書)の感想
人類の終着点 戦争、AI、ヒューマニティの未来 (朝日新書)の感想
民主主義後退の点で知の巨人たちの見解は一致する。私は民主主義の終わりを目の当たりにしているのかもしれず、トッド氏の示唆する、民主主義の次に来る何かを心待ちにしたい気もする。いずれ、人口減少と外国への物的人的依存の克服には痛みを伴うのだろう。西欧vs.世界の様相も興味深い。欧米は直接的な植民地支配は止めても、経済的搾取やイデオロギーの押し付けを止めていない。一方、世界の諸国が持つそれぞれの論理は経済発展とともに明瞭になり、新しくて複雑な国家バランスが現れつつある。意思決定集団を細かく分割するのがよさそう。
安宅氏のAI談義を聞いていると、人間劣化促進機かブルシット・ジョブ判定機としか思えない。AI研究者であるウィテカー氏の指摘は正鵠を射ている。AIと名づけてしまっているそれは知能ではなく、感覚も持っていない、大規模な統計システムでしかない。それは政府や企業など権力者が、権力を簡単に行使できるようにするツールで、一般人を監視し、評価し、管理するためにある。懸念すべきはAIそのものの暴走ではなく権力の暴走。かつ、AIの喧伝によって誰が利益を得ているのかは常に考えておきたい。『現実から目を背けないでください』。
読了日:03月14日 著者:エマニュエル・トッド,マルクス・ガブリエル,フランシス・フクヤマ,メレディス・ウィテカー,スティーブ・ロー,安宅 和人,岩間 陽子,手塚 眞,中島 隆博
 海からの贈りものの感想
海からの贈りものの感想
落合恵子訳版も読んでみた。格調の高さで有名な吉田健一訳よりもやわらかく、より自然なエッセイとして読め、むしろ物足りなく感じたくらいだ。リンドバーグ49歳の著作。以前読んだ時より私の年齢が近づいているので、当然に受け取れたのかもしれない。ひとりの時間について。やらなければならない事や気にかける事が多すぎて、家でひとりになっても自らを顧みる機会をつい後回しにして、ごぞごぞしてしまう。自らを"満たす"ためには、内なる静寂を感じ取るためのひとりの時間を自ら「切実に欲する」よう心がけたほうが良いとするのには同感だ。
読了日:03月10日 著者:アン・モロウ リンドバーグ
 世界の終わりを先延ばしするためのアイディア 人新世という大惨事の中で (単行本)の感想
世界の終わりを先延ばしするためのアイディア 人新世という大惨事の中で (単行本)の感想
物語は人を動かす。その文脈で言えば、『私たちはひとつの人類である』という物語に私たちは縛られているのではないか。アメリカや西欧諸国に過剰に迎合し、同じ規範によって行動しなければならないとばかりイデオロギーを取り込んできた。だから、著者の"ひとつの人類"でいることをやめようという提言には不意を突かれた。多様性を叫びながら、自分たちの意に沿わない少数民族の多様性を踏み潰し、収奪するやりかたには否を。まだ残っている自民族の智を、人類の均質化から注意深く拾い守る意志が、いつか世界の終わりを先延ばしする力となる。
著者はブラジルの先住民族、クレナッキ族である。ブラジルには2010年の時点で305の民族と274の言語が確認されている。しかし著者の生まれた1950年代以降、「白人の開発行為」によって先住民族は森と川を奪われ、著者も流浪を余儀なくされた一人である。民族と文化は凄まじい勢いで減っているはずだ。人食い人種などの俗説も白人が意図的に流布した嘘である。ほんとうは多様な英知を持った民であるにもかかわらず、自分たちに抵抗するから迫害した。知れば知るほど反吐の出る所業だ。「万物の黎明」とつながっている。
西洋における概念と土着の叡智が一人の中に結実する様に感嘆したが、それだってどこか上から見ているような言い分であって、お前は何様だ。自ら恥ずかしく思うとともに撤回する。
読了日:03月08日 著者:アイウトン・クレナッキ
 冬物語 (文春文庫 な 26-6)の感想
冬物語 (文春文庫 な 26-6)の感想
この冬を多忙に送ったせいか、それとも更年期症状か、急に不安になって心臓が大きく打つようなことが増えている。南木さんの文章には薬効がある。南木さんがエッセイに書いた幼少期や闘病期の景色に途切れなく繋がるような、静かな短編集。南木さんが診た人、見送った人や、過去の自らを想いながら描いている。受け入れるほかない運命を、なんとか受け入れられるような心持ちになれそうな、静かな諦観が優しくて、身体の力が抜ける。焦りや不安が解けていく。『末期の目に映る空は見慣れたものより青いのだろうか』。この空は、あの人も見た空。
読了日:03月07日 著者:南木 佳士
 デジタル生存競争の感想
デジタル生存競争の感想
どうしてこの人はこんなことを言うのか。どう考えたら目の前の困っている人を無視して宇宙や火星に莫大な私財をつぎ込めるのか。世界的IT長者に感じていることへの答えに近い。ITにせよ科学技術にせよ、一事に秀でている人は視野が狭いというか、その一事を至上として物事を考えるのだろう。利益が出るか否かが評価基準になり、資本主義が寄ってたかって誉めそやした結果、見たいものしか見ない。そしてありもしない終末に脅えて、一人の人間としては、毛布に頭を突っ込んで震えているのと変わらない。それが排他的になれる理由なんだろう。
読了日:03月07日 著者:ダグラス・ラシュコフ
 図解でわかる 14歳からの水と環境問題の感想
図解でわかる 14歳からの水と環境問題の感想
①図解と易しい表現でわかりやすく、問題の根深さを理解させてくれる。水資源に極端な偏りがある中国とインド。干ばつに苦しむサハラ以南アフリカ。産業利用で地下水を枯渇させるアメリカ。さらに国にまたがる「国際河川」は関係諸国にはシビアな問題だ。ということはそこに資本主義企業が目をつけないはずがない。日本人としては水の問題というと自然災害がいちばんに挙がるが、上下水道の民間委託も国内に聞く話で、他人事ではない。そして『食糧の輸入は他国の水を奪うこと』は日本人には見えにくい、鈍感になりがちな大問題。
②当たり前のことながら、水は歴史上に帝国や都市を築いた基盤である。水は必ずしも人間の都合に合わせていつでも使える状況にはない。多くある場所(大河)では暴れるし、少ない場所(地下水脈)では探り当て、それを皆が使えるように技術を工夫することが豊かさだったのだ。世界各地で生み出された優れたシステムにはどれも感嘆するばかりだが、利用する人口の増加と、気候変動による環境変化で、持続可能性が脅かされている。
③気候変動により、自然環境は変化する。その変化によって影響を受けない地域はほとんど無いのだろう。自然災害によって、または水不足により生活が成り立たなくなって、人々は生きるためにと農村を捨てて都市へ集中する。産業と生活によって水は汚染される。これらの解決策が無いようにしか思えず、次巻を待つ。巨大ダム否定の流れ。国境を跨いで紛争の種になるだけでなく、日本でも山から海への循環が絶たれる弊害は前から言われ続けている。つくったダムを無くす…ことは現実としてあり得るのだろうか。
④人間が変えることができるのは、人為的システムの部分だけ。堤防や地下調整池は対処である。水を飲用水に変える技術はともかく、新しい技術と施設で何とかしようとする取組み、特にCO2削減を掲げた水素エネルギーという、環境負荷を結果的に増やすやつを紹介してどうする。節水という微々たる「解決のために」も、14歳には身近に感じてもらうために必要かもしれないが、まったく解決策ではない。むしろどこから目標はCO2削減にすり替わったのか。この締めくくりが非常識になる未来を願う。
読了日:03月05日 著者:インフォビジュアル研究所
 ラーマーヤナ―インド古典物語 (下) (レグルス文庫 (2))の感想
ラーマーヤナ―インド古典物語 (下) (レグルス文庫 (2))の感想
あっという間に読み終えてしまった。ラーマ王子は無事シータ姫と相まみえ、国へ戻り、正しく治めました。おしまい。バールミキがその顛末をラーマの息子たちに伝え、語り継いだ。という形になっている。ラーマの治世は千年続いた。ラーマはヴィシュヌ神の生まれ変わりだからね。でもヒンドゥー教の神話じゃなくて"叙事詩"で、お話だけど、ラーマが大縦断したアヨージャからセイロン島まで、実在の地名がわかっていて、史跡があったりする。ラーマの名を取った地名や廟がある。少なくとも紀元前2世紀から語り継がれる物語。スケールがでかすぎる。
カイケイー妃とマンタラーのくだりは絶妙だ。人が悪い気を起こすのに悪魔は必要ない。すぐ後悔してももう元には戻せない苦み加減が好き。インドラジッドの葬列はきっとヒンドゥーの様式そのままなのだろう。火は浄化を意味するのか、象徴的に使われる。物語の中で、悪魔にさらわれたシータは火の中をくぐって純潔を証明しなければならない。シータは悪いことしてないのに。ジャーハルを連想し、また女を火に入れるのかともやもやした。インドとセイロン島の間はGoogleで見ると大きなエンジェルロードみたい。橋のエピソードはいかにもだなあ。
読了日:03月04日 著者:河田 清史
 病気にならない食う寝る養生: 予約の取れない漢方家が教えるの感想
病気にならない食う寝る養生: 予約の取れない漢方家が教えるの感想
著者のツイッターが好きで、日々読んでいるおかげで、中医学の考えかたが自分に根づいてきたと感じる。春だから、新月だから、からだの調子がこうなのだとわかっていると、楽である。この冬はわかっていながら無理をしたので、昨日は部屋に転がって日向でこれを読んでいた。今作は食べることと寝ることに特化している。むしろそこを改善するだけでたいていの不調は解消する。対処薬の要らない身体でありたい。食べものの性質を覚えるのは苦手。つまり、旬のものを、温かくして、よく噛んで、いろいろ食べる。睡眠は問題なし。身土不二、心がける。
読了日:03月03日 著者:櫻井 大典
 ラーマーヤナ―インド古典物語 (上) (レグルス文庫 (1))の感想
ラーマーヤナ―インド古典物語 (上) (レグルス文庫 (1))の感想
ラージャマウリの流れからつい買ってしまった。難解かと思いきや子供にも読める訳文で、インドを舞台にした長い昔ばなしみたいだ。序の解説には、これは吟誦詩人たちが口伝で各地に拡め、それはインドのみならず東南アジアまで広大に伝わる、誰でも知っているお話だという。勇者ラーマが艱難を乗り越え、聖者の力を貰いながら悪魔と戦う物語を、みな固唾をのんで聴き入ったことだろう。その構図は、形式も中身の構成も現代の映画と同じだ。楽しみの中に核と力がある。そしてシータ、いったいなぜなんだー!
読了日:03月02日 著者:河田 清史
注: は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。
引越作業の多忙で読めなかった反動、と言えばそうだが、
逆に引越が落ち着いて手持ち無沙汰になったということだろう。
運動不足だし、情報過多。
腰を据えて読まなければ理解できないノンフィクションや、登場人物が多すぎる小説でなければ、読むことで自分にたいした負荷はかからないと思っていたけれど、実はかなり疲弊しているようだ。
<今月のデータ>
購入13冊、購入費用12,678円。
読了20冊。
積読本325冊(うちKindle本155冊)。

 愚か者、中国をゆく (光文社新書 350)の感想
愚か者、中国をゆく (光文社新書 350)の感想香港に住む10年前、星野さんは香港中文大学に留学し、社会主義色強い中国を旅した。その20年後に訪れた中国は、資本主義色を濃くしていた。公共交通システムから何から、スケールが違う。広大な国土、桁違いの人口、国家の成り立ちに由来する非合理的で超平等な社会の在りかた。わが手に得られるものに対する熱量が尋常でない。星野さんはそれらに納得したうえで、資本主義を取り込んだ中国の行く先を危惧した。『中国では何かが起きる時、徹底的に、破壊的に起きるからである』。人々の長く培った飢餓感は今も暴走している気がする。"激烈"。
「国」がでかすぎて、中国は…と話していても、全体の話はできていない前提が常に頭の隅にある。多様な民族を内包しながら、よくもあの広さの「国」を保てていると改めて驚嘆する。
読了日:03月27日 著者:星野博美

 自閉症は津軽弁を話さない 自閉スペクトラム症のことばの謎を読み解く (角川ソフィア文庫)の感想
自閉症は津軽弁を話さない 自閉スペクトラム症のことばの謎を読み解く (角川ソフィア文庫)の感想「自閉症の子供は方言を話さない」という世間の認識を、専門家が調査する。そんなわかりやすそうなことがそれまで検証されていなかったのかと驚くが、学術的理論と現場の段差、それが最も大きそうだ。さて、自閉スペクトラム症は社会性の障害と言われる。子供が母語を習得する過程で必要な、家族など周囲の模倣や意図の読み取りに難があること、他方で繰り返し見られる映画やアニメからは言語を学びやすいことにこの現象が繋がってくると知った。社会的意味や心理的距離は理解が難しくても、ひとつ用法を覚えれば方言を使うことはできるのでは。
読了日:03月23日 著者:松本 敏治

 ブラフマンの埋葬 (講談社文庫)の感想
ブラフマンの埋葬 (講談社文庫)の感想なぜこの小説を読もうと思ったのだったか。猫でも犬でもなくても、毛が生えて温かくてまっすぐ見つめてくる生き物、それだけで人は愛着を持ってしまう。タイトルに埋葬とあれば、身構えつつ読まざるを得ないではないか。主人公は独りだ。やって来る人々も独りだ。主人公は見知らぬ五人家族の写真を買って飾る。家族を想像する。独りでなくなりたかったのだろうか。娘を伴侶にして二人になりたかったのだろうか。身勝手でブラフマンに冷淡な娘を、ほんとうに?
読了日:03月20日 著者:小川 洋子

 読書アンケート2023――識者が選んだ、この一年の本の感想
読書アンケート2023――識者が選んだ、この一年の本の感想月刊誌「みすず」で読んでみたいと思っていた読者アンケートは、月刊誌「みすず」が休刊になり、単独で冊子として発刊された。内容は、各界知識人139名が、2023年に読んだ本で印象深かった本を数冊挙げ、所感を添えるもの。寄稿した知識人のうち私が知っているのは数名で、挙げられた本に至っては700冊近いなかで数冊という、自らの教養と関心のへっぽこぶりを思い知らされた。絶版で読みそびれているイスラエル人作家アモス・オズは、取り寄せて読む。何人もが挙げたデイヴィッド・グレーバー「万物の黎明」は、ひきつづき頑張る。
「万物の黎明」について。『(偶像を)破壊するだけの天才はけっこういると思うんですけど、グレーバーの場合、なぜ破壊しなければならないのか、破壊した後に何が立ち上がるのか、という本人のヴィジョンが明確なところが一線を画しているんだと思います』。ブレイディみかこ
読了日:03月19日 著者:
 園芸家の一年 (平凡社ライブラリー)の感想
園芸家の一年 (平凡社ライブラリー)の感想再読。自由にできる地面を手に入れた途端、私は飽かず眺めては、ああするのはどうだろう、ここはどうしたらいいだろう、あの木は植えたい、これも植えたい、植える場所がまだ決まってないのに球根が届いてしまった、枯れ木のような枝をいつまでもにやにや眺めている、他所様の田畑の草花が羨ましい、など、それはもうチャペックの描くアマチュア園芸家そのものに他ならないのに気づいて、微笑ましく思うのだ。しかしそこには自然に通じるなにか深遠なものがあると、これもこの歳になって気づいたことだ。『一年じゅう春であり、一生、青春時代だ』。
『未来は、わたしたちの先にあるのではない。もうここに、芽の形で存在しているのだから。未来は、もうわたしたちといっしょになっている。今わたしたちといっしょにいないものは、未来になっても存在しないだろう。わたしたちには芽が見えないが、それは芽が地面の下にあるからだ。わたしたちに未来が見えないのは、未来がわたしたちの中にあるからだ。』
読了日:03月19日 著者:カレル チャペック
 なんでもないもの 白洲正子エッセイ集<骨董> (角川ソフィア文庫)の感想
なんでもないもの 白洲正子エッセイ集<骨董> (角川ソフィア文庫)の感想先日、実用にしなそうな漆芸の箱に惚れ、迷いに迷って購入を申し出た。結局は抽選に外れて手に入らなかったのだが、待っている間に白洲正子の「買ってみなきゃわからないのよ」を思い出した。各媒体に書かれたエッセイ。このざっくばらんな、真実を言い刺すような物言いが好きで、憧れる。先の名言は、続けて日常に使うことをも勧める。使ってこそ眼は養われ、日々の愉しみは増し、ものに味がつくのだと。陶磁器や工芸品、古道具は年々好きになっていて、安いものから気張ったものも、遅まきながら好事家になってみようと、こっそり企んでいる。
『私はあえて「発見」という言葉を用いたが、古いものの中から生活に合ったものを見出すのは、利休以来の日本人の伝統である。現代は独創ばやりの世の中だが、現在を支えているのが過去ならば、先ず古く美しい形をつかまねば、新しいものが見える道理はない。こんな自明のことを皆忘れている。忘れているのではなく、ふり返るのが恐ろしいらしい。が、伝統をしょって生きて行く勇気のないものに、何で新しいものを生み出す力が与えられよう』。
読了日:03月18日 著者:白洲 正子

 シャンタラム(下) (新潮文庫)の感想
シャンタラム(下) (新潮文庫)の感想インドから広大で殺伐とした戦地アフガニスタンへ。日々に溢れていた音楽がぱったり止む。リンはここでも徹頭徹尾当事者ではない。ただカーデルバイと友のために決断した成り行きから、そこにいる。ムジャヒディンたちの傍に居、ムンバイに戻ればまたマフィアの傍に居て、知己を弔う。嘯いてはみるが、自身に大義は無い。祖国を失った者たちはムンバイに吹きだまり、また戻ってくる。逝ったはずの者たちも戻ってきて涙を誘う。ああ、読み終わってしまった…。ムンバイに帰りたい。もう一度初めから、リンが愛した皆に出会いたい。カノをハグしたい。
『ときには正しい理由から、まちがったことをしなければならないこともある。大事なのは、その理由が正しいものであると確信し、自分はまちがったことをしていると認めることだ』とカーデルバイは教えた。マフィア稼業であり、戦争のことだ。カーデルは考え抜いた末にそう信じることで、マフィアの王であり続けた。しかしジョーパダパッティなら、貧しくとも、正しい理由から正しいことをするのが自然でいられるんじゃないのか、リン。仲間を喪って、死者を赦すことを覚えて、そのたび自由になって、リンはようやく帰る場所を見つけることができた。
人は結局は土地と女のために戦っているのだとリンは言う。自ら戦地に赴くムジャヒディンのような戦士のことだ。死への崖っぷちぎりぎりの血みどろの日々が続けば、ごたいそうな大義や理由など吹っ飛んでしまう。ふと現実に戻って、戦争行為をしている地のことを想像するとき、平和な地から戦争行為をつべこべ言うことの空々しさを思った。インドとパキスタンの戦争を題材にした「Raazi」を英語字幕で観ていたら、"nature of war"という言葉が目に焼き付いた。戦争の本質。戦争は守りたいものを守ろうとする人間の本質なのか。
読了日:03月15日 著者:グレゴリー・デイヴィッド ロバーツ
 1㎡からはじめる自然菜園の感想
1㎡からはじめる自然菜園の感想好きにしていい地面を手に入れたので、2平方メートルを自家菜園にすべく掘り返し始めた。ど素人としては、理想めいた方向で指南に沿ってとりあえずやってみるしかない。最初にだけ堆肥を入れて野菜が育つ土をつくったら、あとは草マルチと野菜自身の力で肥料の要を無くす。言うは易し。自分に自然農法ができるのか。それから母がよく言う連作障害、これを避けるための組み合わせプランがいろいろ紹介されている。イラストがまたかわいいのね。落花生から始めたいので、2区画、5月までに土づくり、そのあとに草の種を植えて育てます。
読了日:03月14日 著者:竹内孝功
 人類の終着点 戦争、AI、ヒューマニティの未来 (朝日新書)の感想
人類の終着点 戦争、AI、ヒューマニティの未来 (朝日新書)の感想民主主義後退の点で知の巨人たちの見解は一致する。私は民主主義の終わりを目の当たりにしているのかもしれず、トッド氏の示唆する、民主主義の次に来る何かを心待ちにしたい気もする。いずれ、人口減少と外国への物的人的依存の克服には痛みを伴うのだろう。西欧vs.世界の様相も興味深い。欧米は直接的な植民地支配は止めても、経済的搾取やイデオロギーの押し付けを止めていない。一方、世界の諸国が持つそれぞれの論理は経済発展とともに明瞭になり、新しくて複雑な国家バランスが現れつつある。意思決定集団を細かく分割するのがよさそう。
安宅氏のAI談義を聞いていると、人間劣化促進機かブルシット・ジョブ判定機としか思えない。AI研究者であるウィテカー氏の指摘は正鵠を射ている。AIと名づけてしまっているそれは知能ではなく、感覚も持っていない、大規模な統計システムでしかない。それは政府や企業など権力者が、権力を簡単に行使できるようにするツールで、一般人を監視し、評価し、管理するためにある。懸念すべきはAIそのものの暴走ではなく権力の暴走。かつ、AIの喧伝によって誰が利益を得ているのかは常に考えておきたい。『現実から目を背けないでください』。
読了日:03月14日 著者:エマニュエル・トッド,マルクス・ガブリエル,フランシス・フクヤマ,メレディス・ウィテカー,スティーブ・ロー,安宅 和人,岩間 陽子,手塚 眞,中島 隆博

 海からの贈りものの感想
海からの贈りものの感想落合恵子訳版も読んでみた。格調の高さで有名な吉田健一訳よりもやわらかく、より自然なエッセイとして読め、むしろ物足りなく感じたくらいだ。リンドバーグ49歳の著作。以前読んだ時より私の年齢が近づいているので、当然に受け取れたのかもしれない。ひとりの時間について。やらなければならない事や気にかける事が多すぎて、家でひとりになっても自らを顧みる機会をつい後回しにして、ごぞごぞしてしまう。自らを"満たす"ためには、内なる静寂を感じ取るためのひとりの時間を自ら「切実に欲する」よう心がけたほうが良いとするのには同感だ。
読了日:03月10日 著者:アン・モロウ リンドバーグ
 世界の終わりを先延ばしするためのアイディア 人新世という大惨事の中で (単行本)の感想
世界の終わりを先延ばしするためのアイディア 人新世という大惨事の中で (単行本)の感想物語は人を動かす。その文脈で言えば、『私たちはひとつの人類である』という物語に私たちは縛られているのではないか。アメリカや西欧諸国に過剰に迎合し、同じ規範によって行動しなければならないとばかりイデオロギーを取り込んできた。だから、著者の"ひとつの人類"でいることをやめようという提言には不意を突かれた。多様性を叫びながら、自分たちの意に沿わない少数民族の多様性を踏み潰し、収奪するやりかたには否を。まだ残っている自民族の智を、人類の均質化から注意深く拾い守る意志が、いつか世界の終わりを先延ばしする力となる。
著者はブラジルの先住民族、クレナッキ族である。ブラジルには2010年の時点で305の民族と274の言語が確認されている。しかし著者の生まれた1950年代以降、「白人の開発行為」によって先住民族は森と川を奪われ、著者も流浪を余儀なくされた一人である。民族と文化は凄まじい勢いで減っているはずだ。人食い人種などの俗説も白人が意図的に流布した嘘である。ほんとうは多様な英知を持った民であるにもかかわらず、自分たちに抵抗するから迫害した。知れば知るほど反吐の出る所業だ。「万物の黎明」とつながっている。
西洋における概念と土着の叡智が一人の中に結実する様に感嘆したが、それだってどこか上から見ているような言い分であって、お前は何様だ。自ら恥ずかしく思うとともに撤回する。
読了日:03月08日 著者:アイウトン・クレナッキ

 冬物語 (文春文庫 な 26-6)の感想
冬物語 (文春文庫 な 26-6)の感想この冬を多忙に送ったせいか、それとも更年期症状か、急に不安になって心臓が大きく打つようなことが増えている。南木さんの文章には薬効がある。南木さんがエッセイに書いた幼少期や闘病期の景色に途切れなく繋がるような、静かな短編集。南木さんが診た人、見送った人や、過去の自らを想いながら描いている。受け入れるほかない運命を、なんとか受け入れられるような心持ちになれそうな、静かな諦観が優しくて、身体の力が抜ける。焦りや不安が解けていく。『末期の目に映る空は見慣れたものより青いのだろうか』。この空は、あの人も見た空。
読了日:03月07日 著者:南木 佳士
 デジタル生存競争の感想
デジタル生存競争の感想どうしてこの人はこんなことを言うのか。どう考えたら目の前の困っている人を無視して宇宙や火星に莫大な私財をつぎ込めるのか。世界的IT長者に感じていることへの答えに近い。ITにせよ科学技術にせよ、一事に秀でている人は視野が狭いというか、その一事を至上として物事を考えるのだろう。利益が出るか否かが評価基準になり、資本主義が寄ってたかって誉めそやした結果、見たいものしか見ない。そしてありもしない終末に脅えて、一人の人間としては、毛布に頭を突っ込んで震えているのと変わらない。それが排他的になれる理由なんだろう。
読了日:03月07日 著者:ダグラス・ラシュコフ

 図解でわかる 14歳からの水と環境問題の感想
図解でわかる 14歳からの水と環境問題の感想①図解と易しい表現でわかりやすく、問題の根深さを理解させてくれる。水資源に極端な偏りがある中国とインド。干ばつに苦しむサハラ以南アフリカ。産業利用で地下水を枯渇させるアメリカ。さらに国にまたがる「国際河川」は関係諸国にはシビアな問題だ。ということはそこに資本主義企業が目をつけないはずがない。日本人としては水の問題というと自然災害がいちばんに挙がるが、上下水道の民間委託も国内に聞く話で、他人事ではない。そして『食糧の輸入は他国の水を奪うこと』は日本人には見えにくい、鈍感になりがちな大問題。
②当たり前のことながら、水は歴史上に帝国や都市を築いた基盤である。水は必ずしも人間の都合に合わせていつでも使える状況にはない。多くある場所(大河)では暴れるし、少ない場所(地下水脈)では探り当て、それを皆が使えるように技術を工夫することが豊かさだったのだ。世界各地で生み出された優れたシステムにはどれも感嘆するばかりだが、利用する人口の増加と、気候変動による環境変化で、持続可能性が脅かされている。
③気候変動により、自然環境は変化する。その変化によって影響を受けない地域はほとんど無いのだろう。自然災害によって、または水不足により生活が成り立たなくなって、人々は生きるためにと農村を捨てて都市へ集中する。産業と生活によって水は汚染される。これらの解決策が無いようにしか思えず、次巻を待つ。巨大ダム否定の流れ。国境を跨いで紛争の種になるだけでなく、日本でも山から海への循環が絶たれる弊害は前から言われ続けている。つくったダムを無くす…ことは現実としてあり得るのだろうか。
④人間が変えることができるのは、人為的システムの部分だけ。堤防や地下調整池は対処である。水を飲用水に変える技術はともかく、新しい技術と施設で何とかしようとする取組み、特にCO2削減を掲げた水素エネルギーという、環境負荷を結果的に増やすやつを紹介してどうする。節水という微々たる「解決のために」も、14歳には身近に感じてもらうために必要かもしれないが、まったく解決策ではない。むしろどこから目標はCO2削減にすり替わったのか。この締めくくりが非常識になる未来を願う。
読了日:03月05日 著者:インフォビジュアル研究所

 ラーマーヤナ―インド古典物語 (下) (レグルス文庫 (2))の感想
ラーマーヤナ―インド古典物語 (下) (レグルス文庫 (2))の感想あっという間に読み終えてしまった。ラーマ王子は無事シータ姫と相まみえ、国へ戻り、正しく治めました。おしまい。バールミキがその顛末をラーマの息子たちに伝え、語り継いだ。という形になっている。ラーマの治世は千年続いた。ラーマはヴィシュヌ神の生まれ変わりだからね。でもヒンドゥー教の神話じゃなくて"叙事詩"で、お話だけど、ラーマが大縦断したアヨージャからセイロン島まで、実在の地名がわかっていて、史跡があったりする。ラーマの名を取った地名や廟がある。少なくとも紀元前2世紀から語り継がれる物語。スケールがでかすぎる。
カイケイー妃とマンタラーのくだりは絶妙だ。人が悪い気を起こすのに悪魔は必要ない。すぐ後悔してももう元には戻せない苦み加減が好き。インドラジッドの葬列はきっとヒンドゥーの様式そのままなのだろう。火は浄化を意味するのか、象徴的に使われる。物語の中で、悪魔にさらわれたシータは火の中をくぐって純潔を証明しなければならない。シータは悪いことしてないのに。ジャーハルを連想し、また女を火に入れるのかともやもやした。インドとセイロン島の間はGoogleで見ると大きなエンジェルロードみたい。橋のエピソードはいかにもだなあ。
読了日:03月04日 著者:河田 清史

 病気にならない食う寝る養生: 予約の取れない漢方家が教えるの感想
病気にならない食う寝る養生: 予約の取れない漢方家が教えるの感想著者のツイッターが好きで、日々読んでいるおかげで、中医学の考えかたが自分に根づいてきたと感じる。春だから、新月だから、からだの調子がこうなのだとわかっていると、楽である。この冬はわかっていながら無理をしたので、昨日は部屋に転がって日向でこれを読んでいた。今作は食べることと寝ることに特化している。むしろそこを改善するだけでたいていの不調は解消する。対処薬の要らない身体でありたい。食べものの性質を覚えるのは苦手。つまり、旬のものを、温かくして、よく噛んで、いろいろ食べる。睡眠は問題なし。身土不二、心がける。
読了日:03月03日 著者:櫻井 大典

 ラーマーヤナ―インド古典物語 (上) (レグルス文庫 (1))の感想
ラーマーヤナ―インド古典物語 (上) (レグルス文庫 (1))の感想ラージャマウリの流れからつい買ってしまった。難解かと思いきや子供にも読める訳文で、インドを舞台にした長い昔ばなしみたいだ。序の解説には、これは吟誦詩人たちが口伝で各地に拡め、それはインドのみならず東南アジアまで広大に伝わる、誰でも知っているお話だという。勇者ラーマが艱難を乗り越え、聖者の力を貰いながら悪魔と戦う物語を、みな固唾をのんで聴き入ったことだろう。その構図は、形式も中身の構成も現代の映画と同じだ。楽しみの中に核と力がある。そしてシータ、いったいなぜなんだー!
読了日:03月02日 著者:河田 清史

注:
 は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。 Posted by nekoneko at 15:28│Comments(0)
│読書