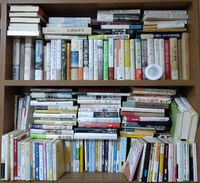2014年04月01日
2014年3月の読書
余暇があったらあっただけ本につぎ込みたい気分が続く。
とはいえ、年度末やらなんやらでどうにも忙しいので、
これで心身のバランスを取ろうとしているのだろうと思います。
積読本129冊。気になっている本405冊。
消費税増税駆け込みでハードカバーの本を購入。
久しぶりに図書館へ行ってみた。
読みたい本がずらり並ぶ光景に目が回りそうになった。
距離が近くなったし、自転車も買ったから、本を借りる生活もいいな。

2014年3月の読書メーター
読んだ本の数:11冊
 RDG レッドデータガール はじめてのお使い (カドカワ銀のさじシリーズ)の感想
RDG レッドデータガール はじめてのお使い (カドカワ銀のさじシリーズ)の感想
物語が始まり、世界観がぼんやりとかたちを取りだした。世間一般に言ってあまりにどんくさい女の子は、特化した能力に長けている模様だが、今のところは潜在的なもので成長の余地がもの凄くありそう。「おつかい」とは読み終わってみれば意味深な副題でした。雷のくだりはホラーかと思ったよ。
読了日:3月29日 著者:荻原規子
 取り返しのつかないものを、取り返すために――大震災と井上ひさし (岩波ブックレット)の感想
取り返しのつかないものを、取り返すために――大震災と井上ひさし (岩波ブックレット)の感想
原発と憲法改正については、現首相の言うこと、メディアの喧伝すること、根本がおかしいと感じている。その、おかしいと感じている引っかかりは、決して流して忘れてしまわないことだ。なんとなくと感じるものが、どうやら生物としての危険信号である可能性は小さくない。今の時勢下で育つ子供は、原発は是、憲法改正は必須と教えられて育つ。その子達が長じてそれらを否と言えるか。私は恐ろしい。私も希求する。そして正しくないことが成されてしまわないよう願う。
読了日:3月26日 著者:大江健三郎,内橋克人,なだいなだ,小森陽一
 李陵 (青空文庫POD(ポケット版))の感想
李陵 (青空文庫POD(ポケット版))の感想
李陵と司馬遷。タイトルは李陵だけど、主人公はこの二人としておかしくない。国主によって辛い境遇に落とされたのち、それぞれなにを選びどう生きたか。忸怩として一生を終えた李陵と、ひたすら史記を完成させるために生きながらえた司馬遷。李陵は人生の肝心を思い切ることができなかったのだな。
読了日:3月25日 著者:中島敦
 さよならドビュッシー (宝島社文庫)の感想
さよならドビュッシー (宝島社文庫)の感想
クラシック音楽絡みのミステリといえば、物静かな中に不穏さの響く展開を予想していたけれど、これは終始戦い続ける主人公の闘争記のような、派手さが印象強い。薀蓄が厚く、音楽に素養のない私は持て余し気味だった。ミステリとしての帰結には納得。謎の鍵は、感情、だったかな。
読了日:3月25日 著者:中山七里
 イスラム飲酒紀行の感想
イスラム飲酒紀行の感想
私も酒飲みであるが、休肝日はそれとなくある。酒飲みあるあるが満載で楽しい。でも読みどころはそこだけじゃない。なんたって、酒を飲んではいけない戒律を持つイスラム教徒が主権を握る国なのだ。本来飲めないはずなのに探したら必ずあって、地元の人たちとわいわい飲める。そのことを真面目に考察すると深い、よい旅行記。楽しんで読むのが正解。
読了日:3月22日 著者:高野秀行
 動物が幸せを感じるとき―新しい動物行動学でわかるアニマル・マインドの感想
動物が幸せを感じるとき―新しい動物行動学でわかるアニマル・マインドの感想
「動物の幸せ」を題に置かれたために、訝しみながら読む羽目に。豚の章でやっと本の主題を捉え、読み直した。翻訳の際、ミスリードな邦題をつけた上に章立てを入れ替えたそうで、大きなお世話だった。著者は牛、豚等産業動物の施設監査の専門家であり、これはアニマル・ウェルフェアへの導入書である。著者は食用動物と人間の関係は共生と結論した。時代が経済を優先する程、動物福祉は減退しがちだ。人間が肉を食べる以上、動物に不要な苦痛を与えないことは必須で、人間も含めた動物の扱いは改善され続けるべきだ。携わる姿勢に敬服。お勧めです。
読了日:3月21日 著者:テンプル・グランディン,キャサリン・ジョンソン
 暗い森 (ハヤカワ・ミステリ文庫)の感想
暗い森 (ハヤカワ・ミステリ文庫)の感想
快作。「呪い!」で投げ出さなくてよかった。海外小説には本国での発表順と日本での出版順が違うことがままあるそうで、この本も「古い骨」より前に発表された作品。ギデオンがジュリーと出会った事件で、きゅんきゅんできます。ジュリーの本領も発揮されます。謎に奥行きがあって、はらはらさせてくれて、人物立ても抜群で言うことなし。謎解きの会話につい気を取られていると、背景で変なことをやってる人を見逃しそうになりますよ。「暗い森=The Dark Place」の意味するところを考えると、読後感しんみりも。
読了日:3月16日 著者:アーロンエルキンズ
 穴 HOLES (ユースセレクション)の感想
穴 HOLES (ユースセレクション)の感想
不条理劇的な設定かな、と思いながら読み進めると、並行した別時系列の挿話で謎が明かされ、なぜそのようなことになったかが読み手にもわかる。その頃には冒険譚に突入していて、ノンストップで読める物語だった。ゼロはいい子だな。その良さがわかって、信じたように行動できるスタンリーもいい子だ。中学生くらいで読ませたい。
読了日:3月13日 著者:ルイス・サッカー
 犬部!の感想
犬部!の感想
人間に放棄された、又は迷子の動物を保護し、心身をケアし、新しい飼い主へ橋渡しするシビアな活動だ。動物を捨てない。飼ったら生涯世話をする。全ての人がこれを守れば犬部はいらない。それができない大人がどれだけ多いことか。どころか飼えなくなった動物は犬部が引取るべきと考える大人すらいる。一般の保護活動と同じことをしながら、それでも「犬部は社会から甘やかされている」と思う部員がいるという。まだ20歳そこらだぞ。大人たち恥を知れ。動物を可能な限り助けたい。その思いは着実に続いている。彼らに果てない倖があるよう、願う。
読了日:3月10日 著者:片野ゆか
 山の人生 (角川ソフィア文庫)の感想
山の人生 (角川ソフィア文庫)の感想
山人(やまひと)は、いたのだ。曰く山女、山姥、山男等々。生身で二本足で、意思疎通も不可能ではないのに、同胞と呼ぶには異様の、山で生きることを選んだ漂泊者は確かにいた。数多の目撃談や伝説として存在が口伝されるうちに巨人になったり獣じみた外見になったりするのは、目撃し伝える側の人間の心がその存在を畏れ、隔たりを求めたからなのだろう。一方、身内の失踪など説明のつけられない事象への理由づけとして現れる「山の民」は妖怪、天狗、鬼、また土俗の神として伝わり、今薄れつつある。奥深いし、失くすのはもったいないわ。
読了日:3月2日 著者:柳田国男,山折哲雄
 チェルノブイリ・ダークツーリズム・ガイド 思想地図β vol.4-1の感想
チェルノブイリ・ダークツーリズム・ガイド 思想地図β vol.4-1の感想
チェルノブイリでは原発事故から四半世紀を経て、観光ツアーが行われている。風化させないよう、歴史を可視化しておくこと。原発と空っぽの街。文字の記録でなく、現地で体感することに意義があるという。正しく考えるために、知る場を維持するのだ。福島はどうか。今はまだ傷が癒えていない。しかし25年後、福島第一原発近隣地を「観光地化」するためには必要なものを残しておかなくてはならない。著者たちが模索の一環として訪問し、関係者にインタビューした記録。人間は忘れやすい生き物。六本木の冬の電飾を思い出し、激しく同意する。
読了日:3月1日 著者:東浩紀,津田大介,開沼博,速水健朗,井出明,新津保建秀,上田洋子,越野剛,服部倫卓,小嶋裕一,徳岡正肇,河尾基
注: はKindleで読んだ本。
はKindleで読んだ本。
とはいえ、年度末やらなんやらでどうにも忙しいので、
これで心身のバランスを取ろうとしているのだろうと思います。
積読本129冊。気になっている本405冊。
消費税増税駆け込みでハードカバーの本を購入。
久しぶりに図書館へ行ってみた。
読みたい本がずらり並ぶ光景に目が回りそうになった。
距離が近くなったし、自転車も買ったから、本を借りる生活もいいな。

2014年3月の読書メーター
読んだ本の数:11冊
 RDG レッドデータガール はじめてのお使い (カドカワ銀のさじシリーズ)の感想
RDG レッドデータガール はじめてのお使い (カドカワ銀のさじシリーズ)の感想物語が始まり、世界観がぼんやりとかたちを取りだした。世間一般に言ってあまりにどんくさい女の子は、特化した能力に長けている模様だが、今のところは潜在的なもので成長の余地がもの凄くありそう。「おつかい」とは読み終わってみれば意味深な副題でした。雷のくだりはホラーかと思ったよ。
読了日:3月29日 著者:荻原規子

 取り返しのつかないものを、取り返すために――大震災と井上ひさし (岩波ブックレット)の感想
取り返しのつかないものを、取り返すために――大震災と井上ひさし (岩波ブックレット)の感想原発と憲法改正については、現首相の言うこと、メディアの喧伝すること、根本がおかしいと感じている。その、おかしいと感じている引っかかりは、決して流して忘れてしまわないことだ。なんとなくと感じるものが、どうやら生物としての危険信号である可能性は小さくない。今の時勢下で育つ子供は、原発は是、憲法改正は必須と教えられて育つ。その子達が長じてそれらを否と言えるか。私は恐ろしい。私も希求する。そして正しくないことが成されてしまわないよう願う。
読了日:3月26日 著者:大江健三郎,内橋克人,なだいなだ,小森陽一
 李陵 (青空文庫POD(ポケット版))の感想
李陵 (青空文庫POD(ポケット版))の感想李陵と司馬遷。タイトルは李陵だけど、主人公はこの二人としておかしくない。国主によって辛い境遇に落とされたのち、それぞれなにを選びどう生きたか。忸怩として一生を終えた李陵と、ひたすら史記を完成させるために生きながらえた司馬遷。李陵は人生の肝心を思い切ることができなかったのだな。
読了日:3月25日 著者:中島敦

 さよならドビュッシー (宝島社文庫)の感想
さよならドビュッシー (宝島社文庫)の感想クラシック音楽絡みのミステリといえば、物静かな中に不穏さの響く展開を予想していたけれど、これは終始戦い続ける主人公の闘争記のような、派手さが印象強い。薀蓄が厚く、音楽に素養のない私は持て余し気味だった。ミステリとしての帰結には納得。謎の鍵は、感情、だったかな。
読了日:3月25日 著者:中山七里
 イスラム飲酒紀行の感想
イスラム飲酒紀行の感想私も酒飲みであるが、休肝日はそれとなくある。酒飲みあるあるが満載で楽しい。でも読みどころはそこだけじゃない。なんたって、酒を飲んではいけない戒律を持つイスラム教徒が主権を握る国なのだ。本来飲めないはずなのに探したら必ずあって、地元の人たちとわいわい飲める。そのことを真面目に考察すると深い、よい旅行記。楽しんで読むのが正解。
読了日:3月22日 著者:高野秀行

 動物が幸せを感じるとき―新しい動物行動学でわかるアニマル・マインドの感想
動物が幸せを感じるとき―新しい動物行動学でわかるアニマル・マインドの感想「動物の幸せ」を題に置かれたために、訝しみながら読む羽目に。豚の章でやっと本の主題を捉え、読み直した。翻訳の際、ミスリードな邦題をつけた上に章立てを入れ替えたそうで、大きなお世話だった。著者は牛、豚等産業動物の施設監査の専門家であり、これはアニマル・ウェルフェアへの導入書である。著者は食用動物と人間の関係は共生と結論した。時代が経済を優先する程、動物福祉は減退しがちだ。人間が肉を食べる以上、動物に不要な苦痛を与えないことは必須で、人間も含めた動物の扱いは改善され続けるべきだ。携わる姿勢に敬服。お勧めです。
読了日:3月21日 著者:テンプル・グランディン,キャサリン・ジョンソン
 暗い森 (ハヤカワ・ミステリ文庫)の感想
暗い森 (ハヤカワ・ミステリ文庫)の感想快作。「呪い!」で投げ出さなくてよかった。海外小説には本国での発表順と日本での出版順が違うことがままあるそうで、この本も「古い骨」より前に発表された作品。ギデオンがジュリーと出会った事件で、きゅんきゅんできます。ジュリーの本領も発揮されます。謎に奥行きがあって、はらはらさせてくれて、人物立ても抜群で言うことなし。謎解きの会話につい気を取られていると、背景で変なことをやってる人を見逃しそうになりますよ。「暗い森=The Dark Place」の意味するところを考えると、読後感しんみりも。
読了日:3月16日 著者:アーロンエルキンズ
 穴 HOLES (ユースセレクション)の感想
穴 HOLES (ユースセレクション)の感想不条理劇的な設定かな、と思いながら読み進めると、並行した別時系列の挿話で謎が明かされ、なぜそのようなことになったかが読み手にもわかる。その頃には冒険譚に突入していて、ノンストップで読める物語だった。ゼロはいい子だな。その良さがわかって、信じたように行動できるスタンリーもいい子だ。中学生くらいで読ませたい。
読了日:3月13日 著者:ルイス・サッカー
 犬部!の感想
犬部!の感想人間に放棄された、又は迷子の動物を保護し、心身をケアし、新しい飼い主へ橋渡しするシビアな活動だ。動物を捨てない。飼ったら生涯世話をする。全ての人がこれを守れば犬部はいらない。それができない大人がどれだけ多いことか。どころか飼えなくなった動物は犬部が引取るべきと考える大人すらいる。一般の保護活動と同じことをしながら、それでも「犬部は社会から甘やかされている」と思う部員がいるという。まだ20歳そこらだぞ。大人たち恥を知れ。動物を可能な限り助けたい。その思いは着実に続いている。彼らに果てない倖があるよう、願う。
読了日:3月10日 著者:片野ゆか
 山の人生 (角川ソフィア文庫)の感想
山の人生 (角川ソフィア文庫)の感想山人(やまひと)は、いたのだ。曰く山女、山姥、山男等々。生身で二本足で、意思疎通も不可能ではないのに、同胞と呼ぶには異様の、山で生きることを選んだ漂泊者は確かにいた。数多の目撃談や伝説として存在が口伝されるうちに巨人になったり獣じみた外見になったりするのは、目撃し伝える側の人間の心がその存在を畏れ、隔たりを求めたからなのだろう。一方、身内の失踪など説明のつけられない事象への理由づけとして現れる「山の民」は妖怪、天狗、鬼、また土俗の神として伝わり、今薄れつつある。奥深いし、失くすのはもったいないわ。
読了日:3月2日 著者:柳田国男,山折哲雄

 チェルノブイリ・ダークツーリズム・ガイド 思想地図β vol.4-1の感想
チェルノブイリ・ダークツーリズム・ガイド 思想地図β vol.4-1の感想チェルノブイリでは原発事故から四半世紀を経て、観光ツアーが行われている。風化させないよう、歴史を可視化しておくこと。原発と空っぽの街。文字の記録でなく、現地で体感することに意義があるという。正しく考えるために、知る場を維持するのだ。福島はどうか。今はまだ傷が癒えていない。しかし25年後、福島第一原発近隣地を「観光地化」するためには必要なものを残しておかなくてはならない。著者たちが模索の一環として訪問し、関係者にインタビューした記録。人間は忘れやすい生き物。六本木の冬の電飾を思い出し、激しく同意する。
読了日:3月1日 著者:東浩紀,津田大介,開沼博,速水健朗,井出明,新津保建秀,上田洋子,越野剛,服部倫卓,小嶋裕一,徳岡正肇,河尾基
注:
 はKindleで読んだ本。
はKindleで読んだ本。 Posted by nekoneko at 23:04│Comments(0)
│読書