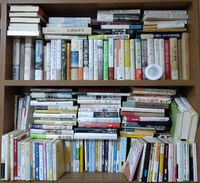2017年04月01日
2017年3月の記録
ソーシャルライブラリーに一時的にログインできなくなって心底焦った。
ソーシャルライブラリーがないと、積読本の全体を把握できない。
ソーシャルライブラリーがないと、読んだ本のジャンルバランスがわからない。
ソーシャルライブラリーがないと、自分がどれだけ本に投資しているかがわからない。
つまり、本買いたい欲求が暴走する。
いつ終了するかわからない無料のアプリに依存しているのは、まずい。
かといって、エクセルで上記要望を満たせるようなものを組めるか。
家計簿アプリを本専用で使うのはどうだろう。
手段を模索せねばならぬ。
ただいま積読本87冊(うちKindle本19冊)。

3月の読書メーター読んだ本の数:11
 まんが よくわかる 工事現場の安全の感想
まんが よくわかる 工事現場の安全の感想
あまり本を読まない現場員のために、これなら目を通してもらえるのではと期待して備えつけた。とはいえ、現場に出ない私にも、それぞれの安全対策が必要である理由の部分に知らないことがままあり、為になった。統括の現場監督だけではなく全作業員に知らしめたい内容で、良い。読了日:03月31日 著者:一般財団法人 建設物価調査会
 へらへらぼっちゃん (講談社文庫)の感想
へらへらぼっちゃん (講談社文庫)の感想
町田さんのエッセイは、日々のくだらないようでどうでもいいようなことを連ねているために、人間性まで如何かと危ぶむのだけれど、それとは全く別の次元で、文体が強力に感染する性質を持っている。危険至極。本や音楽に関する部分も頭に入って来ない。なぜかと考えるに、『人生も物語もありゃしねぇ、無目的に瞬間だけが輝いてスパークしている』パンクの感覚に主軸があるからではないだろうか。私はつい、本に人生や物語を求める癖がついている。だから、読んで空回りして疲れるのだろう。読了日:03月28日 著者:町田 康
 脊梁山脈の感想
脊梁山脈の感想
乙川氏の親の世代だろうか。大戦後外地から復員した青年が命と金を手に入れ、縁から近江木地師の系譜足跡を辿る。それは日本人の祖に遡る壮大な歴史観につながり、また『戦争の残り香』に左右される女たち其々の生きかたも絡んで、大河のように大きく静かな物語である。しかし『性根を据えて人生を楽し』んでいない主人公が無為の傍観者のようで、かといって描く要素は多く、乙川氏自らの籠めたかった想いを散漫にしてしまった印象だ。苛烈な女たちも薄い壁を隔てたように遠い。残念。私はもっと入り込んで、墓標と山なみをありありと眺めたかった。読了日:03月24日 著者:乙川 優三郎
 NYの人気セラピストが教える 自分で心を手当てする方法の感想
NYの人気セラピストが教える 自分で心を手当てする方法の感想
『心の痛みにシンプルな救急箱を』。心の不調を身体の怪我や病気に例えていてわかりやすい。真っ当に大人になり、人並みに気持ちの整理をつけることができるつもりの私でも、読んでいるうちに思い出す痛みがある。孤独に強硬に対処した記憶や裏切りの罪悪感を、今でも心の底に抱えていることに気づくのだ。日常でついやってしまう思考のループは一利なし。他者視点で観ることで解釈し直し、気持ちの整理をつけることができる。他人に意見をもらうのも有効か。実際に心の傷を抱えている人はもちろん、健常と思っている人にも、有効な作用のある本。読了日:03月23日 著者:ガイ・ウィンチ
 ダーク・タワー〈5〉カーラの狼〈上〉 (新潮文庫)の感想
ダーク・タワー〈5〉カーラの狼〈上〉 (新潮文庫)の感想
前巻から6年の間をおき、ダークタワーシリーズは再開した。暗黒の塔に呼ばれたらしい。文章が、年月を経てよりキングに深化している。泥沼の夜の場面など、余りに異様で怖気をふるう。このような場面を軽く混ぜ込んでくるあたりがキングならではなのだ。さて、calla。callahan。セイラムズ・ロットから幾つかの町を経て来たと思しきキャラハン神父。黒で締めた姿が渋い。が、またえらいものを背負いこまされたようだ。また、ドナルド・トランプも登場する。キング、トランプが大統領選挙で勝ったときやさぐれとったもんね(笑)。読了日:03月16日 著者:スティーヴン キング
 ぼくらの民主主義なんだぜ (朝日新書)の感想
ぼくらの民主主義なんだぜ (朝日新書)の感想
『もしかしたら、わたしたちは、「正しい」民主主義を一度も持ったことなどないのかもしれない』。民主主義。不可解な言葉だ。著者のアンテナは、情報溢れる日本で情報を得る箇所を示唆する。基本は、地に足つけて暮らす中で問題にぶち当たっている人の言葉なのだ。それを誠実に伝えようとする人の言葉なのだ。メディアの、国会の、言葉で議論することしか知らない人々の言葉ではないのだ。欠陥に満ちた社会で、『それを「見よう」という強い意志を持つ、僕たちのような素人』。視、聴き、口をへの字に結んで黙々考える。世界に謙虚に向かうために。読了日:03月13日 著者:高橋源一郎
 最後の秘境 東京藝大:天才たちのカオスな日常の感想
最後の秘境 東京藝大:天才たちのカオスな日常の感想
瀬戸内芸術祭の作品には、よくわからんものが沢山ある。山なみ芸術祭は、もっとわからんかった。きれいとか、悲しいとか、ことばにならないとか、心動かせず困惑する作品のほうが私には多い。なんでこれを創ったんかと首を傾げつつ居心地悪く鑑賞していたあれらは、ひょっとすると創った本人にも創る主眼などなく、「おもしろいかも」の結果だったのかもしれない。そう思えば創作者との、私の勝手な断絶感も、若干やわらぐ気がする。技術の部分と、欲求の部分とが、最大限に育まれ触発される場所、それが藝大なんだと大いに納得した。まさに異界。読了日:03月11日 著者:二宮 敦人
 ねこ検定 公式ガイドBOOK (廣済堂ベストムック 346号)の感想
ねこ検定 公式ガイドBOOK (廣済堂ベストムック 346号)の感想
愛玩動物飼養管理士が監修と聞いて読んでみる。今流行りの検定の形を取っているが、猫と暮らす人向けの実用書として良書。情報量が多く、健康管理、手入れなど基本項目はもちろん、保護猫や老猫ケアなどのシリアスな面から、猫カフェの紹介や猫漫画で猫好きのフェティッシュをくすぐるところまで、実に行き届いている。管理士として監修した清水氏も、プロデュースした神保町にゃんこ堂も、猫愛の方向性が素晴らしい。猫好き管理士の端くれとして自分を不甲斐なく思う。読了日:03月11日 著者:神保町にゃんこ堂
 どんなに体がかたい人でもベターッと開脚できるようになるすごい方法の感想
どんなに体がかたい人でもベターッと開脚できるようになるすごい方法の感想
読むための本として見ると、苦笑せざるを得ない。冗長な小説部分が本全体の大方を占めており、それを除けば本の体裁を成さないからだ。つまりメソッド自体はほんの数ページのもの。開脚ができるようになるとは、すなわち脚の裏側の筋を伸ばし、柔らかくすることである。メソッドはよく練られており、良いものだと思う。私も開脚する自分を夢にまで見たくちだが、足りないのは毎日続ける根性だと知っている。そんな自分を誘導して、なんとか開脚できる自分になりたい。そう思っている人に「ベターッ」で上手く訴求した点がヒットの要因といえる。読了日:03月09日 著者:Eiko
 七回死んだ男 (講談社文庫)の感想
七回死んだ男 (講談社文庫)の感想
特異設定ミステリ。なるほど。通常でない状況を自ら設定し、その縛りの中で「フェア」なミステリを展開する手法は、ミステリ作家にとって魅惑なのだろう。いわゆる孤島や密室も縛りであり、その縛りの中でどんな手が使えるか考えるのはミステリの醍醐味だけれど、こういった特異な設定はまた違った、世界観の設定と言ったらよいだろうか、新しく開放しながら縛る、これまた発想が試される。その作家のわくわく感が垣間見えて面白い。読了日:03月08日 著者:西澤 保彦
 (115)猫の學校: 猫と人の快適生活レッスン (ポプラ新書)の感想
(115)猫の學校: 猫と人の快適生活レッスン (ポプラ新書)の感想
キャットシッターとしてたくさんの飼い猫を世話してきた南里さんの経験値は非常に高い。猫のプロである。若干スピリチュアルに感じる面も、猫の静かで雄弁な眼差しと長くつきあってきた結論と思えば納得できる。活性炭サプリや人用爪切りなど、ノウハウはさっそく導入したい。南里さんが「お手当て」と呼んでいるボディタッチは、近年の学術研究結果に照らしても有効。浸透してほしい。『殺処分ゼロの前に取り組むべきは、子どもたちに命の教育をすることと、犬や猫の不妊手術を普及させること、子犬や子猫を繁殖させて販売することを止めること』。読了日:03月05日 著者:南里 秀子
注: はKindleで読んだ本。
はKindleで読んだ本。
ソーシャルライブラリーがないと、積読本の全体を把握できない。
ソーシャルライブラリーがないと、読んだ本のジャンルバランスがわからない。
ソーシャルライブラリーがないと、自分がどれだけ本に投資しているかがわからない。
つまり、本買いたい欲求が暴走する。
いつ終了するかわからない無料のアプリに依存しているのは、まずい。
かといって、エクセルで上記要望を満たせるようなものを組めるか。
家計簿アプリを本専用で使うのはどうだろう。
手段を模索せねばならぬ。
ただいま積読本87冊(うちKindle本19冊)。

3月の読書メーター読んだ本の数:11
 まんが よくわかる 工事現場の安全の感想
まんが よくわかる 工事現場の安全の感想あまり本を読まない現場員のために、これなら目を通してもらえるのではと期待して備えつけた。とはいえ、現場に出ない私にも、それぞれの安全対策が必要である理由の部分に知らないことがままあり、為になった。統括の現場監督だけではなく全作業員に知らしめたい内容で、良い。読了日:03月31日 著者:一般財団法人 建設物価調査会
 へらへらぼっちゃん (講談社文庫)の感想
へらへらぼっちゃん (講談社文庫)の感想町田さんのエッセイは、日々のくだらないようでどうでもいいようなことを連ねているために、人間性まで如何かと危ぶむのだけれど、それとは全く別の次元で、文体が強力に感染する性質を持っている。危険至極。本や音楽に関する部分も頭に入って来ない。なぜかと考えるに、『人生も物語もありゃしねぇ、無目的に瞬間だけが輝いてスパークしている』パンクの感覚に主軸があるからではないだろうか。私はつい、本に人生や物語を求める癖がついている。だから、読んで空回りして疲れるのだろう。読了日:03月28日 著者:町田 康

 脊梁山脈の感想
脊梁山脈の感想乙川氏の親の世代だろうか。大戦後外地から復員した青年が命と金を手に入れ、縁から近江木地師の系譜足跡を辿る。それは日本人の祖に遡る壮大な歴史観につながり、また『戦争の残り香』に左右される女たち其々の生きかたも絡んで、大河のように大きく静かな物語である。しかし『性根を据えて人生を楽し』んでいない主人公が無為の傍観者のようで、かといって描く要素は多く、乙川氏自らの籠めたかった想いを散漫にしてしまった印象だ。苛烈な女たちも薄い壁を隔てたように遠い。残念。私はもっと入り込んで、墓標と山なみをありありと眺めたかった。読了日:03月24日 著者:乙川 優三郎
 NYの人気セラピストが教える 自分で心を手当てする方法の感想
NYの人気セラピストが教える 自分で心を手当てする方法の感想『心の痛みにシンプルな救急箱を』。心の不調を身体の怪我や病気に例えていてわかりやすい。真っ当に大人になり、人並みに気持ちの整理をつけることができるつもりの私でも、読んでいるうちに思い出す痛みがある。孤独に強硬に対処した記憶や裏切りの罪悪感を、今でも心の底に抱えていることに気づくのだ。日常でついやってしまう思考のループは一利なし。他者視点で観ることで解釈し直し、気持ちの整理をつけることができる。他人に意見をもらうのも有効か。実際に心の傷を抱えている人はもちろん、健常と思っている人にも、有効な作用のある本。読了日:03月23日 著者:ガイ・ウィンチ

 ダーク・タワー〈5〉カーラの狼〈上〉 (新潮文庫)の感想
ダーク・タワー〈5〉カーラの狼〈上〉 (新潮文庫)の感想前巻から6年の間をおき、ダークタワーシリーズは再開した。暗黒の塔に呼ばれたらしい。文章が、年月を経てよりキングに深化している。泥沼の夜の場面など、余りに異様で怖気をふるう。このような場面を軽く混ぜ込んでくるあたりがキングならではなのだ。さて、calla。callahan。セイラムズ・ロットから幾つかの町を経て来たと思しきキャラハン神父。黒で締めた姿が渋い。が、またえらいものを背負いこまされたようだ。また、ドナルド・トランプも登場する。キング、トランプが大統領選挙で勝ったときやさぐれとったもんね(笑)。読了日:03月16日 著者:スティーヴン キング
 ぼくらの民主主義なんだぜ (朝日新書)の感想
ぼくらの民主主義なんだぜ (朝日新書)の感想『もしかしたら、わたしたちは、「正しい」民主主義を一度も持ったことなどないのかもしれない』。民主主義。不可解な言葉だ。著者のアンテナは、情報溢れる日本で情報を得る箇所を示唆する。基本は、地に足つけて暮らす中で問題にぶち当たっている人の言葉なのだ。それを誠実に伝えようとする人の言葉なのだ。メディアの、国会の、言葉で議論することしか知らない人々の言葉ではないのだ。欠陥に満ちた社会で、『それを「見よう」という強い意志を持つ、僕たちのような素人』。視、聴き、口をへの字に結んで黙々考える。世界に謙虚に向かうために。読了日:03月13日 著者:高橋源一郎

 最後の秘境 東京藝大:天才たちのカオスな日常の感想
最後の秘境 東京藝大:天才たちのカオスな日常の感想瀬戸内芸術祭の作品には、よくわからんものが沢山ある。山なみ芸術祭は、もっとわからんかった。きれいとか、悲しいとか、ことばにならないとか、心動かせず困惑する作品のほうが私には多い。なんでこれを創ったんかと首を傾げつつ居心地悪く鑑賞していたあれらは、ひょっとすると創った本人にも創る主眼などなく、「おもしろいかも」の結果だったのかもしれない。そう思えば創作者との、私の勝手な断絶感も、若干やわらぐ気がする。技術の部分と、欲求の部分とが、最大限に育まれ触発される場所、それが藝大なんだと大いに納得した。まさに異界。読了日:03月11日 著者:二宮 敦人
 ねこ検定 公式ガイドBOOK (廣済堂ベストムック 346号)の感想
ねこ検定 公式ガイドBOOK (廣済堂ベストムック 346号)の感想愛玩動物飼養管理士が監修と聞いて読んでみる。今流行りの検定の形を取っているが、猫と暮らす人向けの実用書として良書。情報量が多く、健康管理、手入れなど基本項目はもちろん、保護猫や老猫ケアなどのシリアスな面から、猫カフェの紹介や猫漫画で猫好きのフェティッシュをくすぐるところまで、実に行き届いている。管理士として監修した清水氏も、プロデュースした神保町にゃんこ堂も、猫愛の方向性が素晴らしい。猫好き管理士の端くれとして自分を不甲斐なく思う。読了日:03月11日 著者:神保町にゃんこ堂
 どんなに体がかたい人でもベターッと開脚できるようになるすごい方法の感想
どんなに体がかたい人でもベターッと開脚できるようになるすごい方法の感想読むための本として見ると、苦笑せざるを得ない。冗長な小説部分が本全体の大方を占めており、それを除けば本の体裁を成さないからだ。つまりメソッド自体はほんの数ページのもの。開脚ができるようになるとは、すなわち脚の裏側の筋を伸ばし、柔らかくすることである。メソッドはよく練られており、良いものだと思う。私も開脚する自分を夢にまで見たくちだが、足りないのは毎日続ける根性だと知っている。そんな自分を誘導して、なんとか開脚できる自分になりたい。そう思っている人に「ベターッ」で上手く訴求した点がヒットの要因といえる。読了日:03月09日 著者:Eiko
 七回死んだ男 (講談社文庫)の感想
七回死んだ男 (講談社文庫)の感想特異設定ミステリ。なるほど。通常でない状況を自ら設定し、その縛りの中で「フェア」なミステリを展開する手法は、ミステリ作家にとって魅惑なのだろう。いわゆる孤島や密室も縛りであり、その縛りの中でどんな手が使えるか考えるのはミステリの醍醐味だけれど、こういった特異な設定はまた違った、世界観の設定と言ったらよいだろうか、新しく開放しながら縛る、これまた発想が試される。その作家のわくわく感が垣間見えて面白い。読了日:03月08日 著者:西澤 保彦

 (115)猫の學校: 猫と人の快適生活レッスン (ポプラ新書)の感想
(115)猫の學校: 猫と人の快適生活レッスン (ポプラ新書)の感想キャットシッターとしてたくさんの飼い猫を世話してきた南里さんの経験値は非常に高い。猫のプロである。若干スピリチュアルに感じる面も、猫の静かで雄弁な眼差しと長くつきあってきた結論と思えば納得できる。活性炭サプリや人用爪切りなど、ノウハウはさっそく導入したい。南里さんが「お手当て」と呼んでいるボディタッチは、近年の学術研究結果に照らしても有効。浸透してほしい。『殺処分ゼロの前に取り組むべきは、子どもたちに命の教育をすることと、犬や猫の不妊手術を普及させること、子犬や子猫を繁殖させて販売することを止めること』。読了日:03月05日 著者:南里 秀子
注:
 はKindleで読んだ本。
はKindleで読んだ本。 Posted by nekoneko at 12:00│Comments(0)
│読書