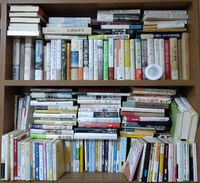2018年10月01日
2018年9月の記録
『海の見える一箱古本市&せとうちのみの市』に参加することになりました。
もちろん、自分の読み終わった本からセレクトするのです。
そのため、今月いっぱいはリアル本を優先して、積読の消化にかかっています。
基本的には、もう読み返すことはないだろうと思っている本なのですが、
下心で、キャッチーなタイトルの本を選んでみたりしています。
幼児期、「本屋さんになりたい」と言っていたこともありましたし、
本好きが集まるイベントで、私の並べた本に興味を持ってくれた人と会話する。
なんて、想像しただけで楽しすぎて興奮してしまいます(笑)。
11月3日(土) 10:00〜15:00、北浜alleyにお越しくださいませ。

<今月のデータ>
購入29冊、購入費用21,980円。
読了16冊。
積読本122冊(うちKindle本39冊)。

9月の読書メーター
読んだ本の数:16
 (002)絆 (百年文庫)の感想
(002)絆 (百年文庫)の感想
海音寺潮五郎、ドイル、山周。意図して散らした選択と、贅沢に配置されたフォントがこの文庫集の魅力で、読む側はゆったり味わい、つい比べてみる。さて山周の「山椿」は鮮やかな短編だ。修羅場の後、はたと主馬の内心が描かれなくなる。あれこれ展開を測ってみるが、主人公の心情という鍵がなければ先を見通せない読み手を弄するように、思う方向へゆかず焦れったい。この頁数で大転換からの大団円は、いや見事。魂の存在を信じる人々の物語だった。結びの愛嬌がまた、梶井家の先の明るさを思わせて好い。こういう出会いがあると全巻集めたくなる。
読了日:09月30日 著者:海音寺潮五郎,コナン・ドイル,山本周五郎
 秘密の花園 (光文社古典新訳文庫)の感想
秘密の花園 (光文社古典新訳文庫)の感想
子供の頃、この物語が好きだった。今でもほとんど覚えているのだから、繰り返し読んだのだろう。今読んでも素敵な物語。どこが好きだったか子供だった自分に訊いてみたい。母を持たず、外界を知らない二人の子供が、徐々にイギリスの春の美しさを知り、何物にも代えがたい日々を送り、伸びやかになっていく様子は読んでいて気持ちが好い。子供心に憧憬した記憶はないけれど、ここにはやはり魔法がある。バーネットは61歳でこの物語を書き始めたという。アメリカの華やかな社交界も経験したバーネットも、自然と庭を愛したのだろうと想像した。
読了日:09月26日 著者:バーネット
 日本の気配の感想
日本の気配の感想
現政権やその周辺の人々のやることなすこと言うこと、舌鋒鋭く指摘していてすかっとする。もはや「曲芸」なんて表現が痛快で笑い転げた。こういう事を書き続けてくれる人がここにもいた。今の政治やメディアの様子が、異様だと感じながらも、毎日苛立ち、怒ることは疲れるし孤独だ。見ないふりをして忘れるほうが楽だ。だが著者はそれを怒り、繰り返し指摘し続ける事が重要なのだと何度も言う。『憤怒がないからこそ、この日本は空気や気配などという主体なきものにハンドルを握られてしまうのだ』。身近な話題になると、だいぶ面倒臭い人の感あり。
読了日:09月26日 著者:武田砂鉄
 猫にGPSをつけてみた 夜の森 半径二キロの大冒険の感想
猫にGPSをつけてみた 夜の森 半径二キロの大冒険の感想
市の中心まで車で10分なのに隣家は300m離れている。そんな夢のような立地が存在するのか。家の外を自由に遊び回る飼い猫の姿は今や幻。近所への迷惑や車の事故、心無い人の虐待など、現代の日本では夢だと思っていた。さて、GPS装着のくだりはほんの一部だ。一般に、市街地での猫の行動範囲はせいぜい半径数百mと言われるが、民家が疎らな土地では半径1kmを超えるようだ。猫も生態系の一部。環境に合わせるのだな。『我が家は猫を飼っているんじゃなく、人間と猫との生活圏が、一部分重なっているだけなのかもしれない』が素敵すぎ。
読了日:09月24日 著者:高橋のら
 パパは脳研究者 子どもを育てる脳科学の感想
パパは脳研究者 子どもを育てる脳科学の感想
著者待望の子供は興味津々の研究対象でもある。4歳になるまでの毎月、娘の様子を題材に書かれた連載だ。脳の神経細胞の数は、産まれてから3歳になるまでに約7割が排除されるという。「三つ子の魂百まで」は本当だ。だからやれ早期教育に邁進すべきかというと全くそうでない。子供にどのように何を教えるべきか、自らの方針を元に著者は娘に接する。最後に娘で実験(!)するのだが、その結果に感動してしまった。こういうことが理解できたら子育てがもっと面白いだろうと思う。折よく姪っ子が生後2か月なので、この本は妹夫婦に遣ることにする。
『一般に、記憶力のいい人ほど、想像力がない傾向があります』。記憶力が優れた人は、隅々までをよく思い出せるから、覚えていない部分を想像力で埋める必要がないからという論理だ。なんだか、自分の記憶力の悪さに感謝したくなった。常に想像力が鍛えられているってことだものね! 記憶力が破格に良い友人のことも思い出し、納得、さらに同情までしてしまったのはかなり不遜(笑)。ただし、記憶を定着させるにはいわゆるアウトプットが大事な点は変わりない。他人に自分の体験や知識を説明しようとすると、いつもしどろもどろなんだよね…。
読了日:09月23日 著者:池谷 裕二
 猫のための家庭の医学 一家に一冊ネコの健康本 愛猫の健康寿命が延びるの感想
猫のための家庭の医学 一家に一冊ネコの健康本 愛猫の健康寿命が延びるの感想
『猫に不愉快な思いをさせてはいけません』。著者は東京下町の獣医師で、情報は信頼できる。家庭の医学と表題されているものの、猫の性質、生活、成長、病気まで、暮らしに必要なことは網羅されている。概して飼い主に手厳しい。猫への振る舞いが人間都合でないか、配慮が足りているか、はたまた手を抜かなかったかと、反省しきりだ。異状が発生したときに読むより、普段から時折読み返したい本。「ねこ先生のお悩み相談室」などユーモアが秀逸な点も良く、猫飼いさんには全力でお勧めしたい。『人間側からの決めつけはだいたいムダに終わります』。
読了日:09月20日 著者:野澤 延行
 空白の五マイル チベット、世界最大のツアンポー峡谷に挑む (集英社文庫)の感想
空白の五マイル チベット、世界最大のツアンポー峡谷に挑む (集英社文庫)の感想
辺境ノンフィクションといえば高野秀行だが、角幡氏も冒険遺伝子を持つ探検家の一人だ。中国、チベットの奥地にある峡谷ツアンポーの完全踏破を目指す旅。過去の探検家たちの足跡を知的にまとめる一方、斜面を転げ落ちたり、食物が底を突いて飢えたり、帰還してこれを書いているのだから死んでないのだろう、と信じながら読んだ。私自身、先日の山登りで、一歩違えば死ぬような岩場を経て頂に辿り着けてしまった。あれが行けたのだから、とさらに危なっかしい岩場に挑もうとするのが、冒険ということなんだろうか。人間の冒険心って凄まじい。
読了日:09月19日 著者:角幡 唯介
 この残酷な世界でどう生きようか (幻冬舎plus+)の感想
この残酷な世界でどう生きようか (幻冬舎plus+)の感想
2017年1月の新春対談。世界の動きとメディアの役割、ジャーナリズムについて。日曜朝のテレビ番組の、力強い目つきと語り口が印象深い安田氏が、津田氏とのこの対話の中では迷い、憤り、笑う様子が新鮮だ。二人とも様々な話題の現地を訪れており、それぞれ披露する体感としての情報には驚くものが多い。それにしても日本国内も世界も、どんどん情報は多く深くなっていて、全ての案件を正しく把握し追うことはもはや難しい。どうアンテナを張っていいか、最近は悩んでいる。津田氏『「この世界はクソだ」と認識することからスタートしないと』。
読了日:09月19日 著者:津田大介,安田菜津紀
 神への長い道 (角川文庫)の感想
神への長い道 (角川文庫)の感想
同じ時代のせいか、短くなるほど星新一と区別がつかなくなる。さて表題作、主人公は退屈している。人間の脳が"肉体の分際にすぎた”と感じ、一人の人間が体験できることはみな体験し、生きる意欲を起こさせる対象が何もないと思って絶望している。それに対し終盤、宇宙の成長に人類の子孫の脳みそが寄与するという確証を得て、生きる意欲を俄然取り戻した主人公の様子は対照的だ。精神の力はまだまだ限界ではない。それは人類の精神、脳への期待の裏返しと言える。最近特に、精神の力こそ限界だと感じているので、この物語に昭和を感じるのだろう。
読了日:09月19日 著者:小松 左京
 山小屋で、会いましょう! 楽しみ広がる「お泊まり登山」の感想
山小屋で、会いましょう! 楽しみ広がる「お泊まり登山」の感想
石鎚山頂上山荘にて、消灯前に布団の中で。日帰り登山客の下りて行った後の、静かな時間。美しい時間。山登りで疲れていても、目一杯楽しみたいから眠くない。天気が良かったとか悪かったとか、カメラを抱えて一喜一憂したり、知らない人と話に花を咲かせたりは本当に貴重だ。そういう楽しさをもっと知っている人のエッセイは面白かった。私は石鎚しか泊まったことがないが、もっと他の、特に人がごった返していそうで敬遠している日本アルプス系の小屋(と縦走)も楽しそうで泊まってみたくなった。目標80歳まで、細く長くつきあっていきたいな。
風が強く、9月でも寒い夜だったので、夕飯をいただいてから消灯までの時間を仕方なく屋内で過ごす。廊下の本棚には山関連の月刊誌数種からエッセイ、漫画までよくもこれだけという冊数が並べられている。こんな日には重宝するなぁ。
読了日:09月16日 著者:鈴木 みき
 我々はなぜ我々だけなのか アジアから消えた多様な「人類」たち (ブルーバックス)の感想
我々はなぜ我々だけなのか アジアから消えた多様な「人類」たち (ブルーバックス)の感想
アフリカに起源した人類がアジアへ到達する中には、ホモ・サピエンスの祖先とは違う進化をした者がいたという。この本は彼らに関する化石発掘と検証、仮説を追う内容だ。私が興味を持ったのは、ホモ・サピエンスが彼らに比べて短期間に世界分布した件だ。道具の創出で気候に対応し、海を渡ることができた。でもそれは世界のホモ・サピエンスが種として均質になる要因となり、今も続いている。海部陽介氏の「移動と交流と共有と均質化という大きな歴史の流れは、もう止められない」という言葉が印象に残る。人類も動植物も。均質化って嫌な響きだ。
読了日:09月12日 著者:川端 裕人
 アフガニスタンの仏像は破壊されたのではない恥辱のあまり崩れ落ちたのだの感想
アフガニスタンの仏像は破壊されたのではない恥辱のあまり崩れ落ちたのだの感想
詩的な表題。イランの映画監督が東隣の国アフガニスタンの悲惨を慨嘆したレポートの言葉だ。『仏像は、恥辱のために崩れ落ちたのだ。アフガニスタンの虐げられた人びとに対し世界がここまで無関心であることを恥じ、自らの偉大さなど何の足しにもならないと知って砕けたのだ』。ソ連の侵攻、内戦により荒れた国土に、隣国パキスタンで教育されたタリバンが台頭した。部族意識の高い遊牧民の国には国家の認識がないと著者は言う。戦争と武器売買、麻薬精製以外の産業がない国。レポートが書かれたのは9.11前夜だった。今はどうなっているだろう。
今も何も、正直に言って、イメージもなければ知識もない遠いアフガニスタンを想像することは終始できなかったのだ。餓死した人々の遺体で埋め尽くされた道など、現実とかけ離れすぎて、真実だということすら、私は本当には信じることができていないのではないだろうか。このレポートに書かれた風習や歴史をぼんやり頭に留めることしか、結局はできないのだろうと、読み終えたばかりの今の時点で既に思う。
読了日:09月11日 著者:モフセン マフマルバフ
 なぜ僕はドキュメンタリーを撮るのか (講談社現代新書)の感想
なぜ僕はドキュメンタリーを撮るのか (講談社現代新書)の感想
ドキュメンタリー番組は、私が出会っていない世界を見られるから、視野が広がった気になる。義憤や公憤を覚える。しかしそれが新書書籍化されると、文章を読み慣れた身には違和感が生じる。その原因が今回解った。映像は様々なテクニックを使って作り手の意図を潜ませる。客観的事実を読んでいるはずなのに、例えば感情を喚起する表現が文章に顕在化すると、つまらないどころか不快なのだ。番組もまた客観的真実ではない。それに相反する形態で撮られる著者の「観察映画」はどのような感覚がするか、見てみたい。『「観察」の対義語は「無関心」』
読了日:09月09日 著者:想田 和弘
![[図解]トヨタの片づけ](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/5154DgQbjTL._SL120_.jpg) [図解]トヨタの片づけの感想
[図解]トヨタの片づけの感想
「トヨタの片づけ」の図解版。章立てもそのままで、多色刷りの図を多用することによって視覚で内容を捉えられるようになっている。補足の文章にもフォントの大きさと色を効果的に使用しており、見やすい。見開きB4の大きめサイズなので、Kindle自炊の要領で背を切り落し、社内掲示に使うつもりだ。とにかく文章を読むのが苦痛な、かつ片づけの出来ない社員のアイキャッチとなることを期待する。もっと詳しく知りたいと申し出る社員…はいないとは思うが、彼には本のほうを貸し出せるよう、会社の本棚に備えつけた。
読了日:09月07日 著者:OJTソリューションズ
 外来種は本当に悪者か?: 新しい野生 THE NEW WILDの感想
外来種は本当に悪者か?: 新しい野生 THE NEW WILDの感想
この論旨は間違っている。外来種侵入の是非を語る際に貢献の度合いや経済効果、結果の可否で測るべきではないし、生物多様性の足し算引き算など認識錯誤にも程がある。自然に変化はつきもの。自然はその時々の動的平衡点を見つける。だからと言って人間が故意に、水質浄化や緑化などの「目的」のために自然を操作しようと持ち込む行為は容認できない。なぜなら人間都合ばかりで、自然への敬意を欠くからだ。外来種を駆除殲滅する行為と大差ない。人間は大昔から自然に手を加えたが自然は復元したと言うが、だとしても、今は人間の活動規模が違う。
確かに在来種保護の動きは動物愛護に似て過激になりがちで、それはどちらも動植物の生命がかかっているからだ。タイムリミットがあるからだ。結果をもってすれば外来種排斥運動が労力や資金を空費することもあるだろう。でもそれは地球温暖化対策と同じではないか。人間は自然を理解しきれていないのだから。極端な外来種排斥はもはや意味がない。だとしても、在来種の保護がまるきり必要ないとは、私は思わない。例えばレッドリストにある膨大な在来哺乳動物に匹敵するだけの新哺乳動物が、今地球上に生まれているだろうか? 人間に責任は、ある。
手こずった。これまでの自然保護、特に外来種排斥の歴史を概観し、近年の変化しつつある自然への認識を問題提起することに意義はある。しかし問題なのは、データの利用がでたらめだと、環境保護主義者を丸ごとひっくるめて揶揄かつ非難していることだ。では、著者が引用している膨大な研究および調査結果のどこまでが信頼性に足るデータか、著者自身精査しただろうか? 自分の主張をもっともらしく見せるために論旨をすり替え捻じ曲げ、またデータを捏造する人間がいるのは、どの立場でも同じだ。参考にはするが、私は鵜呑みにはしないことにする。
読了日:09月06日 著者:フレッド・ピアス
 反省させると犯罪者になります (新潮新書)の感想
反省させると犯罪者になります (新潮新書)の感想
タイトルは過激だが、拙速に反省させようとするとかえってその人の態度のみならず人生を悪くするという真面目な主旨だ。ミスを重ねる社員に反省文を書かせる対応に疑問を感じて手に取った。悪いことをしてバレたときの人間の心理は反省でなく後悔、これは納得だ。『悪いことをしたら謝ればいい』『ただまじめに過ごせばいい』と思っているうちは事態は良くならない。話題が感情の抑圧へ向いたあたりから他人より我が身のことを考え始めた。反省は抑圧を生む。抑圧と怒り、寂しさと怒りは、実は近い。今更だが、自分の性質を知っておいていいと思う。
読了日:09月04日 著者:岡本 茂樹
注: はKindleで読んだ本。
はKindleで読んだ本。
もちろん、自分の読み終わった本からセレクトするのです。
そのため、今月いっぱいはリアル本を優先して、積読の消化にかかっています。
基本的には、もう読み返すことはないだろうと思っている本なのですが、
下心で、キャッチーなタイトルの本を選んでみたりしています。
幼児期、「本屋さんになりたい」と言っていたこともありましたし、
本好きが集まるイベントで、私の並べた本に興味を持ってくれた人と会話する。
なんて、想像しただけで楽しすぎて興奮してしまいます(笑)。
11月3日(土) 10:00〜15:00、北浜alleyにお越しくださいませ。

<今月のデータ>
購入29冊、購入費用21,980円。
読了16冊。
積読本122冊(うちKindle本39冊)。

9月の読書メーター
読んだ本の数:16
 (002)絆 (百年文庫)の感想
(002)絆 (百年文庫)の感想海音寺潮五郎、ドイル、山周。意図して散らした選択と、贅沢に配置されたフォントがこの文庫集の魅力で、読む側はゆったり味わい、つい比べてみる。さて山周の「山椿」は鮮やかな短編だ。修羅場の後、はたと主馬の内心が描かれなくなる。あれこれ展開を測ってみるが、主人公の心情という鍵がなければ先を見通せない読み手を弄するように、思う方向へゆかず焦れったい。この頁数で大転換からの大団円は、いや見事。魂の存在を信じる人々の物語だった。結びの愛嬌がまた、梶井家の先の明るさを思わせて好い。こういう出会いがあると全巻集めたくなる。
読了日:09月30日 著者:海音寺潮五郎,コナン・ドイル,山本周五郎
 秘密の花園 (光文社古典新訳文庫)の感想
秘密の花園 (光文社古典新訳文庫)の感想子供の頃、この物語が好きだった。今でもほとんど覚えているのだから、繰り返し読んだのだろう。今読んでも素敵な物語。どこが好きだったか子供だった自分に訊いてみたい。母を持たず、外界を知らない二人の子供が、徐々にイギリスの春の美しさを知り、何物にも代えがたい日々を送り、伸びやかになっていく様子は読んでいて気持ちが好い。子供心に憧憬した記憶はないけれど、ここにはやはり魔法がある。バーネットは61歳でこの物語を書き始めたという。アメリカの華やかな社交界も経験したバーネットも、自然と庭を愛したのだろうと想像した。
読了日:09月26日 著者:バーネット

 日本の気配の感想
日本の気配の感想現政権やその周辺の人々のやることなすこと言うこと、舌鋒鋭く指摘していてすかっとする。もはや「曲芸」なんて表現が痛快で笑い転げた。こういう事を書き続けてくれる人がここにもいた。今の政治やメディアの様子が、異様だと感じながらも、毎日苛立ち、怒ることは疲れるし孤独だ。見ないふりをして忘れるほうが楽だ。だが著者はそれを怒り、繰り返し指摘し続ける事が重要なのだと何度も言う。『憤怒がないからこそ、この日本は空気や気配などという主体なきものにハンドルを握られてしまうのだ』。身近な話題になると、だいぶ面倒臭い人の感あり。
読了日:09月26日 著者:武田砂鉄
 猫にGPSをつけてみた 夜の森 半径二キロの大冒険の感想
猫にGPSをつけてみた 夜の森 半径二キロの大冒険の感想市の中心まで車で10分なのに隣家は300m離れている。そんな夢のような立地が存在するのか。家の外を自由に遊び回る飼い猫の姿は今や幻。近所への迷惑や車の事故、心無い人の虐待など、現代の日本では夢だと思っていた。さて、GPS装着のくだりはほんの一部だ。一般に、市街地での猫の行動範囲はせいぜい半径数百mと言われるが、民家が疎らな土地では半径1kmを超えるようだ。猫も生態系の一部。環境に合わせるのだな。『我が家は猫を飼っているんじゃなく、人間と猫との生活圏が、一部分重なっているだけなのかもしれない』が素敵すぎ。
読了日:09月24日 著者:高橋のら
 パパは脳研究者 子どもを育てる脳科学の感想
パパは脳研究者 子どもを育てる脳科学の感想著者待望の子供は興味津々の研究対象でもある。4歳になるまでの毎月、娘の様子を題材に書かれた連載だ。脳の神経細胞の数は、産まれてから3歳になるまでに約7割が排除されるという。「三つ子の魂百まで」は本当だ。だからやれ早期教育に邁進すべきかというと全くそうでない。子供にどのように何を教えるべきか、自らの方針を元に著者は娘に接する。最後に娘で実験(!)するのだが、その結果に感動してしまった。こういうことが理解できたら子育てがもっと面白いだろうと思う。折よく姪っ子が生後2か月なので、この本は妹夫婦に遣ることにする。
『一般に、記憶力のいい人ほど、想像力がない傾向があります』。記憶力が優れた人は、隅々までをよく思い出せるから、覚えていない部分を想像力で埋める必要がないからという論理だ。なんだか、自分の記憶力の悪さに感謝したくなった。常に想像力が鍛えられているってことだものね! 記憶力が破格に良い友人のことも思い出し、納得、さらに同情までしてしまったのはかなり不遜(笑)。ただし、記憶を定着させるにはいわゆるアウトプットが大事な点は変わりない。他人に自分の体験や知識を説明しようとすると、いつもしどろもどろなんだよね…。
読了日:09月23日 著者:池谷 裕二
 猫のための家庭の医学 一家に一冊ネコの健康本 愛猫の健康寿命が延びるの感想
猫のための家庭の医学 一家に一冊ネコの健康本 愛猫の健康寿命が延びるの感想『猫に不愉快な思いをさせてはいけません』。著者は東京下町の獣医師で、情報は信頼できる。家庭の医学と表題されているものの、猫の性質、生活、成長、病気まで、暮らしに必要なことは網羅されている。概して飼い主に手厳しい。猫への振る舞いが人間都合でないか、配慮が足りているか、はたまた手を抜かなかったかと、反省しきりだ。異状が発生したときに読むより、普段から時折読み返したい本。「ねこ先生のお悩み相談室」などユーモアが秀逸な点も良く、猫飼いさんには全力でお勧めしたい。『人間側からの決めつけはだいたいムダに終わります』。
読了日:09月20日 著者:野澤 延行
 空白の五マイル チベット、世界最大のツアンポー峡谷に挑む (集英社文庫)の感想
空白の五マイル チベット、世界最大のツアンポー峡谷に挑む (集英社文庫)の感想辺境ノンフィクションといえば高野秀行だが、角幡氏も冒険遺伝子を持つ探検家の一人だ。中国、チベットの奥地にある峡谷ツアンポーの完全踏破を目指す旅。過去の探検家たちの足跡を知的にまとめる一方、斜面を転げ落ちたり、食物が底を突いて飢えたり、帰還してこれを書いているのだから死んでないのだろう、と信じながら読んだ。私自身、先日の山登りで、一歩違えば死ぬような岩場を経て頂に辿り着けてしまった。あれが行けたのだから、とさらに危なっかしい岩場に挑もうとするのが、冒険ということなんだろうか。人間の冒険心って凄まじい。
読了日:09月19日 著者:角幡 唯介
 この残酷な世界でどう生きようか (幻冬舎plus+)の感想
この残酷な世界でどう生きようか (幻冬舎plus+)の感想2017年1月の新春対談。世界の動きとメディアの役割、ジャーナリズムについて。日曜朝のテレビ番組の、力強い目つきと語り口が印象深い安田氏が、津田氏とのこの対話の中では迷い、憤り、笑う様子が新鮮だ。二人とも様々な話題の現地を訪れており、それぞれ披露する体感としての情報には驚くものが多い。それにしても日本国内も世界も、どんどん情報は多く深くなっていて、全ての案件を正しく把握し追うことはもはや難しい。どうアンテナを張っていいか、最近は悩んでいる。津田氏『「この世界はクソだ」と認識することからスタートしないと』。
読了日:09月19日 著者:津田大介,安田菜津紀

 神への長い道 (角川文庫)の感想
神への長い道 (角川文庫)の感想同じ時代のせいか、短くなるほど星新一と区別がつかなくなる。さて表題作、主人公は退屈している。人間の脳が"肉体の分際にすぎた”と感じ、一人の人間が体験できることはみな体験し、生きる意欲を起こさせる対象が何もないと思って絶望している。それに対し終盤、宇宙の成長に人類の子孫の脳みそが寄与するという確証を得て、生きる意欲を俄然取り戻した主人公の様子は対照的だ。精神の力はまだまだ限界ではない。それは人類の精神、脳への期待の裏返しと言える。最近特に、精神の力こそ限界だと感じているので、この物語に昭和を感じるのだろう。
読了日:09月19日 著者:小松 左京

 山小屋で、会いましょう! 楽しみ広がる「お泊まり登山」の感想
山小屋で、会いましょう! 楽しみ広がる「お泊まり登山」の感想石鎚山頂上山荘にて、消灯前に布団の中で。日帰り登山客の下りて行った後の、静かな時間。美しい時間。山登りで疲れていても、目一杯楽しみたいから眠くない。天気が良かったとか悪かったとか、カメラを抱えて一喜一憂したり、知らない人と話に花を咲かせたりは本当に貴重だ。そういう楽しさをもっと知っている人のエッセイは面白かった。私は石鎚しか泊まったことがないが、もっと他の、特に人がごった返していそうで敬遠している日本アルプス系の小屋(と縦走)も楽しそうで泊まってみたくなった。目標80歳まで、細く長くつきあっていきたいな。
風が強く、9月でも寒い夜だったので、夕飯をいただいてから消灯までの時間を仕方なく屋内で過ごす。廊下の本棚には山関連の月刊誌数種からエッセイ、漫画までよくもこれだけという冊数が並べられている。こんな日には重宝するなぁ。
読了日:09月16日 著者:鈴木 みき
 我々はなぜ我々だけなのか アジアから消えた多様な「人類」たち (ブルーバックス)の感想
我々はなぜ我々だけなのか アジアから消えた多様な「人類」たち (ブルーバックス)の感想アフリカに起源した人類がアジアへ到達する中には、ホモ・サピエンスの祖先とは違う進化をした者がいたという。この本は彼らに関する化石発掘と検証、仮説を追う内容だ。私が興味を持ったのは、ホモ・サピエンスが彼らに比べて短期間に世界分布した件だ。道具の創出で気候に対応し、海を渡ることができた。でもそれは世界のホモ・サピエンスが種として均質になる要因となり、今も続いている。海部陽介氏の「移動と交流と共有と均質化という大きな歴史の流れは、もう止められない」という言葉が印象に残る。人類も動植物も。均質化って嫌な響きだ。
読了日:09月12日 著者:川端 裕人

 アフガニスタンの仏像は破壊されたのではない恥辱のあまり崩れ落ちたのだの感想
アフガニスタンの仏像は破壊されたのではない恥辱のあまり崩れ落ちたのだの感想詩的な表題。イランの映画監督が東隣の国アフガニスタンの悲惨を慨嘆したレポートの言葉だ。『仏像は、恥辱のために崩れ落ちたのだ。アフガニスタンの虐げられた人びとに対し世界がここまで無関心であることを恥じ、自らの偉大さなど何の足しにもならないと知って砕けたのだ』。ソ連の侵攻、内戦により荒れた国土に、隣国パキスタンで教育されたタリバンが台頭した。部族意識の高い遊牧民の国には国家の認識がないと著者は言う。戦争と武器売買、麻薬精製以外の産業がない国。レポートが書かれたのは9.11前夜だった。今はどうなっているだろう。
今も何も、正直に言って、イメージもなければ知識もない遠いアフガニスタンを想像することは終始できなかったのだ。餓死した人々の遺体で埋め尽くされた道など、現実とかけ離れすぎて、真実だということすら、私は本当には信じることができていないのではないだろうか。このレポートに書かれた風習や歴史をぼんやり頭に留めることしか、結局はできないのだろうと、読み終えたばかりの今の時点で既に思う。
読了日:09月11日 著者:モフセン マフマルバフ
 なぜ僕はドキュメンタリーを撮るのか (講談社現代新書)の感想
なぜ僕はドキュメンタリーを撮るのか (講談社現代新書)の感想ドキュメンタリー番組は、私が出会っていない世界を見られるから、視野が広がった気になる。義憤や公憤を覚える。しかしそれが新書書籍化されると、文章を読み慣れた身には違和感が生じる。その原因が今回解った。映像は様々なテクニックを使って作り手の意図を潜ませる。客観的事実を読んでいるはずなのに、例えば感情を喚起する表現が文章に顕在化すると、つまらないどころか不快なのだ。番組もまた客観的真実ではない。それに相反する形態で撮られる著者の「観察映画」はどのような感覚がするか、見てみたい。『「観察」の対義語は「無関心」』
読了日:09月09日 著者:想田 和弘
![[図解]トヨタの片づけ](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/5154DgQbjTL._SL120_.jpg) [図解]トヨタの片づけの感想
[図解]トヨタの片づけの感想「トヨタの片づけ」の図解版。章立てもそのままで、多色刷りの図を多用することによって視覚で内容を捉えられるようになっている。補足の文章にもフォントの大きさと色を効果的に使用しており、見やすい。見開きB4の大きめサイズなので、Kindle自炊の要領で背を切り落し、社内掲示に使うつもりだ。とにかく文章を読むのが苦痛な、かつ片づけの出来ない社員のアイキャッチとなることを期待する。もっと詳しく知りたいと申し出る社員…はいないとは思うが、彼には本のほうを貸し出せるよう、会社の本棚に備えつけた。
読了日:09月07日 著者:OJTソリューションズ
 外来種は本当に悪者か?: 新しい野生 THE NEW WILDの感想
外来種は本当に悪者か?: 新しい野生 THE NEW WILDの感想この論旨は間違っている。外来種侵入の是非を語る際に貢献の度合いや経済効果、結果の可否で測るべきではないし、生物多様性の足し算引き算など認識錯誤にも程がある。自然に変化はつきもの。自然はその時々の動的平衡点を見つける。だからと言って人間が故意に、水質浄化や緑化などの「目的」のために自然を操作しようと持ち込む行為は容認できない。なぜなら人間都合ばかりで、自然への敬意を欠くからだ。外来種を駆除殲滅する行為と大差ない。人間は大昔から自然に手を加えたが自然は復元したと言うが、だとしても、今は人間の活動規模が違う。
確かに在来種保護の動きは動物愛護に似て過激になりがちで、それはどちらも動植物の生命がかかっているからだ。タイムリミットがあるからだ。結果をもってすれば外来種排斥運動が労力や資金を空費することもあるだろう。でもそれは地球温暖化対策と同じではないか。人間は自然を理解しきれていないのだから。極端な外来種排斥はもはや意味がない。だとしても、在来種の保護がまるきり必要ないとは、私は思わない。例えばレッドリストにある膨大な在来哺乳動物に匹敵するだけの新哺乳動物が、今地球上に生まれているだろうか? 人間に責任は、ある。
手こずった。これまでの自然保護、特に外来種排斥の歴史を概観し、近年の変化しつつある自然への認識を問題提起することに意義はある。しかし問題なのは、データの利用がでたらめだと、環境保護主義者を丸ごとひっくるめて揶揄かつ非難していることだ。では、著者が引用している膨大な研究および調査結果のどこまでが信頼性に足るデータか、著者自身精査しただろうか? 自分の主張をもっともらしく見せるために論旨をすり替え捻じ曲げ、またデータを捏造する人間がいるのは、どの立場でも同じだ。参考にはするが、私は鵜呑みにはしないことにする。
読了日:09月06日 著者:フレッド・ピアス
 反省させると犯罪者になります (新潮新書)の感想
反省させると犯罪者になります (新潮新書)の感想タイトルは過激だが、拙速に反省させようとするとかえってその人の態度のみならず人生を悪くするという真面目な主旨だ。ミスを重ねる社員に反省文を書かせる対応に疑問を感じて手に取った。悪いことをしてバレたときの人間の心理は反省でなく後悔、これは納得だ。『悪いことをしたら謝ればいい』『ただまじめに過ごせばいい』と思っているうちは事態は良くならない。話題が感情の抑圧へ向いたあたりから他人より我が身のことを考え始めた。反省は抑圧を生む。抑圧と怒り、寂しさと怒りは、実は近い。今更だが、自分の性質を知っておいていいと思う。
読了日:09月04日 著者:岡本 茂樹

注:
 はKindleで読んだ本。
はKindleで読んだ本。 Posted by nekoneko at 10:43│Comments(0)
│読書