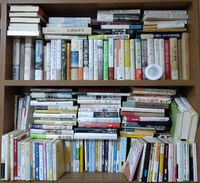2021年11月01日
2021年10月の記録
衆院選の投票を終えて一夜明け、惨憺たる結果を目の当たりにする。
日本はますます生きづらい国になるだろう。
そこに、私が得てきた知識も倫理も、絶望感を助長するばかりだ。
私は何のために本を読んでいるのだろうか。
<今月のデータ>
購入22冊、購入費用23,830円。
読了18冊。
積読本272冊(うちKindle本114冊、Honto本13冊)。

10月の読書メーター
読んだ本の数:18
 崩れ (講談社文庫)の感想
崩れ (講談社文庫)の感想
文さん72歳、52kg。執着したのは「崩れ」、なんと山崩れと暴れ川である。窮屈なズボンをはき、人に負ぶってもらってでも登り我が目で確かめるのだ。無意識のうちに心に貯めた『ものの種が芽に置きあがる時の力は、土を押し破るほど強い』。文さんの、炎が噴き出るような気性が発揮される。「木」が生命力の象徴であるのに対比し、山崩れは荒涼や麓の命を脅かす存在だ。恐怖に圧倒されながら、崩落の打当たって割れる落石の真新しい断面の美をも瞬間に捉える。文さんの文章は、自身の感性を逃さず、豊かだ。大山の崩れを思い浮かべつつ読んだ。
読了日:10月28日 著者:幸田 文
 動物園は進化する (ちくまプリマー新書)の感想
動物園は進化する (ちくまプリマー新書)の感想
動物園でゾウを飼育展示するようになった当初は見世物だったのが、時代と共に動物を通じて自然のしくみを教える、種を保存するなど機能を変えてきた。体が大きいゆえに飼育係の安全問題は喫緊であり、動物福祉も言われる今、変わりつつあるという。しかし繁殖は上手くいっていない。繁殖するためにはゾウが自然体で生きられる環境が必要だ。なのに群れの構造が複雑なゾウの少数飼育やコンクリートと鉄の檻、夜に自由に歩いたり食べたりできないスケジュール、なにより他者の視線など、人間に置き換えれば当たり前のことが動物のことになると難しい。
『ゾウの自然な生活を参考にして、家族群をつくり繁殖させる。そのためには、日々進歩する科学に基づいた飼育方針のもと、古い飼育方法ではなく、ゾウに適した高度な生息環境を整え、これまで無視してきた動物の福祉に配慮する』。その志は尊い。だけれども。
私は動物園の動物を憐憫する子供だったので、そもそも動物園にゾウは必要かとの疑念が消せない。私たちも、飼育に関わる人たちも、ゾウやライオンやが動物園にいる前提で話をする。だけどリアルな映像や情報の溢れる現代に、日本全国に何百もの動物園と100頭余ものゾウをはじめとする大型動物は必要だろうか。環境破壊や密猟がなくならないから動物園で種の保存をという考え方に、私はぞっとする。動物の餌代など"維持コスト"を議論するくらいなら、どのみち"触れあい"とは無縁な動物たちの飼育は諦めようという方向にはならないのだろうか。
読了日:10月25日 著者:川口 幸男,アラン ルークロフト
 彼岸花が咲く島の感想
彼岸花が咲く島の感想
話し言葉だけではなく、地の文の言葉にも違和感が激しく、なかなか読み進まない。普段使っている母語の機微を、ごく無意識に使い分けていることに改めて気づかされる。芥川賞だから、日本語を"正しく"使っていないといけないという規則はないはずなのに、ならばなぜこの作品が選ばれたのかと神経を鋭くして読んでしまう自分は、嫌な奴だ。さて、拓慈。最も身近な、異なる存在。彼を怖いと感じるのはなぜなのだろう。男だから。無知ゆえの無邪気さをぶつけてくるから。決定的に共有できないものが立ちはだかるから。それは理不尽なことだろうか?
読了日:10月22日 著者:李 琴峰
![農家が教える 竹やぶ減らし 2021年 10 月号 [雑誌]: 現代農業 増刊](https://m.media-amazon.com/images/I/51pUqClFyEL._SL120_.jpg) 農家が教える 竹やぶ減らし 2021年 10 月号 [雑誌]: 現代農業 増刊の感想
農家が教える 竹やぶ減らし 2021年 10 月号 [雑誌]: 現代農業 増刊の感想
際限なく増殖する竹林と人の闘い。苦労されている人には申し訳ないけれど、自然との知恵比べみたいで面白かった。タケノコやメンマで食べて美味しいのも良し、竹チップに粉砕して発酵させ、堆肥化するのも良し。いや好い。専門誌で繰り返し特集されるほど繁殖力の強い竹に困らされても、私たちはまだまだ自分たちの生活に役立てることができるのだ。なかでも、高さ1mで切るだけという、竹の生態を逆手にとった根絶やし方法は、よくぞ見出したと感嘆する。竹やぶはたいてい里との境目でもあるので、イノシシ対策も兼ねた自然との格闘技みたいだな。
読了日:10月21日 著者:
 ヤマケイ新書 山を買うの感想
ヤマケイ新書 山を買うの感想
自分の山が欲しいと思っていた頃があって、それは新型コロナやソロキャンの流行より前からなのだけど、それは安易な衝動であろう、と戒めのために読んでみた。さすがヤマケイ。甘くない。ゆるくない。しかしやっぱり欲しくなってしまった。ここに出てくる人々が山を買い求めた目的は様々で、なかでも山を守ることに使命感を見出した人たちへの共感と共振は、固定資産税ぐらい何年でも払ったるわ!という気分にさせる。『荒れた山を美しい里山に戻しながら、楽しむ』。そうだそうだと乗り気になりかける私に、立ちはだかる数多の障害の解説が詳しい。
読了日:10月19日 著者:福崎 剛
 マイル81 わるい夢たちのバザールI (文春文庫 キ 2-61 わるい夢たちのバザール 1)の感想
マイル81 わるい夢たちのバザールI (文春文庫 キ 2-61 わるい夢たちのバザール 1)の感想
"カップ"と"取っ手"の湧いて出る泉が健在であることに感謝する。「UR」は以前、原語で読もうとしたことがある。キングの文体を非ネイティヴが読むなど無謀だったと改めて思った。キーボード付Kindleは懐かしく、キングが『ちび助マシン』にわくわくする気配が好ましい。パラドックス警察より怖いのは、文学の研究者にとっては専門の作家の知らない作品が続々出現する事態であり、私にとっては買えども未読の本が並んでいる現実ではないかな。『わしの名前ではない』。「砂丘」の結末は私も大好きだ。しゃれこうべのニヤニヤ笑い最高。
読了日:10月17日 著者:スティーヴン・キング
 西日本大震災に備えよ 日本列島大変動の時代 (PHP新書)の感想
西日本大震災に備えよ 日本列島大変動の時代 (PHP新書)の感想
3.11以降、日本列島は『「大地変動の時代」が始まってしまった』。2030年代に発生が予測されるM9級の南海トラフ巨大地震をはじめ、東日本に再度の大地震、それに誘発される直下型地震。これらの発生は地球科学の分野では既定路線だという。活動周期や地盤の沈下/隆起現象の解析などの具体的な根拠を読み、自分が生きているうちに必ず来ると知り、備えなければならないと思いつつも、正常性バイアスとは厄介なもので、困ったなあ、とただぼやいている。日本人古来のメンタリティなどに思いをはせている場合ではない。備えんか自分。
今の日本列島が置かれた状況は、9世紀の日本に似ているのだという。9世紀は一般人には遠すぎるが、地球科学者には直近。驚嘆。
読了日:10月16日 著者:鎌田 浩毅
 アメリカ人の4人に1人はトランプが大統領だと信じているの感想
アメリカ人の4人に1人はトランプが大統領だと信じているの感想
我が家は"あめしる"も欠かさず見る町山ファンなので、たいていの話題は町山さんから既に聞いたものだ。それにしても議事堂占拠は有り得ない事態だった。だからこそバイデン大統領の就任式が、オバマのとは違う意味で胸にずしりときたことを思い出した。さて、富豪たちの宇宙旅行合戦。ウィリアム王子の言うように、今やらないかんことはそれや無いやろ、である。全ての富豪に社会貢献の義務があるわけではない。だったら不労所得には重税をかけて社会に強制還元してもらわねば。Kindleを生んだ功績は多大なれど、ベゾスにはがっかりだ。
読了日:10月16日 著者:町山 智浩
 武漢日記:封鎖下60日の魂の記録の感想
武漢日記:封鎖下60日の魂の記録の感想
湖北省武漢市が突如封鎖された、新型コロナ発生ごく初期の60日間の記録。新型コロナの本質的な事象は既にここにある。あと1週間の我慢だ。ワクチンができるまでの我慢だ。初期のそんな心持が今となっては新鮮なほど、あれはほんの始まりでしかなかったと知れる。発生場所が中国であるという一点で、私たちの頭の中にはフィルターがかかった。特殊な国家だからと。この本を読んで感じたのは、著者も著者のまわりの人々も、信じているということ。民主主義ではなくとも、在る秩序。人々との紐帯。善なるものへの信頼。『法治社会』としての中国を。
『政治的公正』の名分のもとに、ネット検閲官によってWeb上の投稿が通告なく削除されるのはよくあることのようだ。それでも諦めず思うことを投稿し、削除を免れたものによって意思を表明し、人々と意思疎通する。削除されることがわかっていても、怒りを表明する。そういう形で、社会は正しくあることができると、信じているようだ。それでも、バルガス=リョサの著作が本屋の棚から消えたことを知り、彼がなにか発言をしたからではないかと推測し、気落ちしている。その先には何が残るのだろう。先日読んだSF、馬伯庸の「沈黙都市」を想う。
読了日:10月15日 著者:方方
 出版翻訳家なんてなるんじゃなかった日記の感想
出版翻訳家なんてなるんじゃなかった日記の感想
なぜこの時代に、出版社と翻訳家の契約が書面でなく口頭なのか。そもそもそこに問題があると思うが、それにしても印税カットも出版中止も、出版社の翻しようが酷いのなんの。著者のプライドゆえの災厄とは言いきれず、出版社の大小の問題とも判じきれず、こちらまで出版業界不信になりそう。私の支払った代金は正当に翻訳者に届いているのか。商業主義的と出版社を非難するのは簡単だが、出版不況と言われると、あのしっかりしたつくりの美しいものに正当な対価を払わない読者側の問題も絡む。これからは本を買うのに出版社も選ぶ時代かもしれない。
今年のノーベル文学賞を受賞したグルナ氏の著作は和訳されるのかどうか、翻訳本をつくるには時間がかかる。まず翻訳しなければどのような感触の作品か出版社にもわからないのが、翻訳本の事情のややこしいところだ。今頃、出版社が翻訳家に最短期間で訳せるかせっついているところかもしれない。売れるチャンスなのだから。だけど翻訳本は以前に比べますます売れないのだろう、有名作家の新刊小説でも、地方の書店は置いていないことが多いものなあ。出版物数がやたら多いのも問題だろうし。つい安い本の方を選んじゃうのも問題だろうし。難しい。
読了日:10月10日 著者:宮崎 伸治
 ゴッホのあしあと (幻冬舎文庫)の感想
ゴッホのあしあと (幻冬舎文庫)の感想
「たゆたえども沈まず」の副読本と謳ったエッセイ。「たゆたえども~」のどの部分が創作だったか明らかにされていて興味深い。中野京子さんが“爆発し続けた”と表現したゴッホの晩年5年間。その起爆剤はパリと浮世絵だった。ゴッホの絵の奥底にある彼の孤独を探り当て、対象として眺めるんじゃなくて手繰り寄せるような、そんな感受性があるから、原田マハは小説を書けるのだと思った。一方、林忠正が同胞のはずの日本人から国賊呼ばわりされた当人であると知る。私はこちらを手繰ってみたい。
読了日:10月09日 著者:原田マハ
 たゆたえども沈まず (幻冬舎文庫)の感想
たゆたえども沈まず (幻冬舎文庫)の感想
重吉、忠正、テオと登場し、フィンセントが現れて、役者は揃う。フィクションである日本人の、重吉にはテオの心情描写、忠正にはフィンセントの運命示唆が役割として割り振られ、それがしかも対比構造になっている。私は彼らの本当のところを知らないながら、上手いな、面白いなぁ、と思った。中野京子さんの本の続きで言うと、印象派の画家たちは、被写体の心情や立場に関心をもたなかったかもしれないけれど、自身の絵を描きたい情熱には真摯だった。日々食べるものにも事欠きながらも描くことをやめない、やめられない情熱なんて想像もつかない。
読了日:10月09日 著者:原田マハ
 聊斎志異の怪 (角川ソフィア文庫)の感想
聊斎志異の怪 (角川ソフィア文庫)の感想
17世紀中国のあやかし説話集。幽霊が賄賂を贈ったり嫉妬したり、取っ組み合いの喧嘩を始めたりと騒々しく人間臭い。性愛絡みの物語も多く、幽玄という美的感覚が中国にはないのかとぼやいてみるが、思い返せば日本の説話だって似たようなもの。説話は骨組であって、要は想像力の膨らませようか。現に巻末の芥川と太宰が翻案した作品から、原案に肉をつけると物語として違和感がないとわかる。これは彼らの膨らませ方が上手いこともあろうけれども、中国と日本の物語の構造もきっと似ているのだろう。「狐の嫁女」は映像にしたらさぞ美しかろうな。
『これはきみの心だ。きみの作文が下手なのは、きみの心の毛穴がふさがっていたためだから、いま、冥途にある千万の心の中からよいものを一つ選び出して、きみの心と取り替えたのだ。きみの心は取っておいて、不足した冥途の分を補充するのだ』。と閻魔王のとこの判官が主人公のイマイチな文才の改善に便宜を図ってくれる。なんとも人間の願望の透けて見えることよ。さらに奥さんの顔と性根も美しい人のそれと取り替えてくれるという「首のすげかえ」は至れり尽くせり。閻魔王のとこの判官さんは、そんなに退屈しとったのだろうか。
読了日:10月08日 著者:蒲 松齢
 印象派で「近代」を読む 光のモネから、ゴッホの闇へ (NHK出版新書)の感想
印象派で「近代」を読む 光のモネから、ゴッホの闇へ (NHK出版新書)の感想
印象派は『何が描かれているかより、どんなふうに描かれているか』を重視する代わり、悲惨も鬱屈も顧みることない、人の心の深みとは切り離された絵画だった。当時の庶民同様、西洋史の教養も無しに眺めていた私に、絵は背景を知って観るのが面白いと中野さんは教えてくれる。ただ楽しむための絵画にも時代背景はある。屋外で描くという行為自体がたいへんな変革だったとか、エッフェル塔は醜いと嫌われたとか、中でも踊り子や上流階級の妻やお針子や、その時代の人々、同時に画家自身の生き方が絵の中に現れていると新たに知って俄然楽しくなる。
読了日:10月07日 著者:中野 京子
 老いた家 衰えぬ街 住まいを終活する (講談社現代新書)の感想
老いた家 衰えぬ街 住まいを終活する (講談社現代新書)の感想
全国民を挙げての大ババ抜き大会である。人口が急減を始めるなか、それはもう既に始まっていて、たとえば20年後に処分できそうにない不動産を今買うなどもってのほかで、親や親族の不動産が転がり込んでくる可能性や、近隣が放棄物件で荒廃する可能性を考えれば、無縁でいられない人の方が多そうだ。個人ではどうしようもないケースも考えると、個人を厳罰化しても根本的な解決にはならず、マッチングにせよ近隣需要への橋渡しにせよ、譲渡推進にも早晩限界が出るのではないのかしら。法制面をはじめ、ババをババでなくする仕組みづくりが急務。
町を歩いていて明らかに空き家とわかる物件でも、様々な事情で放置/留置されている事情がある。所有者が施設に入ったなどはこの本にも書かれているが、不動産屋さんと話していると、親族や近隣住民との関係の都合で、堂々と売りに出すことができない様々の問題があるのだそうだ。かといって売れない実家、山林や原野="負動産"にかかる税金などの経費は年々かかり続け、ボディブローのように効いてくるのだから、持ち続けることにも無理がある。いやー、どうすんだこれ。
読了日:10月05日 著者:野澤 千絵
 猫と住まいの解剖図鑑の感想
猫と住まいの解剖図鑑の感想
我が家の猫は1匹になってしまったけれど、縁があるなら、また猫を迎えたい。で、猫ズに優しい家を妄想する。猫を優先にして家をつくるのは本末転倒で、人間のための家を設計する中で、猫にも優しい工夫をするべきという前提には同意する。脱走防止に引き戸をつけるなどもよいけれど、今はいろいろな商材が出ていて、爪とぎやキャットウォークはもちろん、壁の漆喰塗りや、窓を開けておくための格子もDIYできるという情報がためになった。和のしつらえも案外大丈夫と知る。障子や襖は貼り直せばよく、畳も爪とぎされそうで実は大丈夫らしい。
読了日:10月03日 著者:いしまるあきこ
 「男女格差後進国」の衝撃: 無意識のジェンダー・バイアスを克服する (小学館新書)の感想
「男女格差後進国」の衝撃: 無意識のジェンダー・バイアスを克服する (小学館新書)の感想
セミナーで紹介された本。以前「女性活躍」と言われると、もやっとした違和感が拭えなかった。余計な意味合いが含蓄されて感じた。ではなく「ジェンダー・ギャップの解消」なら、目的は明瞭で社会の目標として掲げてよいと思う。さて、性別に基づく無意識の決めつけは男性だけでなく女性にもあり、地域差や世代差もある。組織において"女性ならではの"視点をという言い方もそれ自体が決めつけ的なものだが、できることがあるとすれば、「少数派としての体験」を生かして、マイノリティ属性の人の困りそうな状況を察知し、解消を発想することかも。
グローバル・ジェンダー・ギャップ指数(経済分野)の算出根拠は ①女性の労働参加率 ②類似職業の男女賃金格差 ③全体の男女賃金格差 ④管理職に占める女性比率 ⑤総合職・専門職に占める女性比率。家事育児介護の負担をアウトソーシングできる国柄の国の方が指数が高くなる傾向にある。公共サービスとしてアウトソーシングできる北欧の国と同様、新興国・途上国であるアジアやアフリカにも指数が高い国がある。それは、所得の多い家は低所得の女性を雇って家事育児介護をさせることができるので、自分も働きに出られるからであるとのことだ。
読了日:10月02日 著者:治部 れんげ
 これってホントにエコなの?の感想
これってホントにエコなの?の感想
人間はものを造る。運ぶ。使う。捨てる。それらは地球環境には全て負荷になる。衣食住、毎日毎日の膨大な選択で、負荷を減らせる選択について書いている。関心があっても眩暈がしてくる分量だが、それによって環境負荷を減らすための原則が解ると同時に、より複合的な問題、一律に答えを出せない問いが多い事実も、浮き彫りになっている。つまり選択は程度の問題で、次善の策を取るしかないことも解って、選んでいくしかないのだ。カーボンオフセットは、自力で解決できないから金銭で協力しようという行為。必要だけど、取組として本質的ではない。
自然の中で分解されない化学物質を使った洗剤より、水を余分に使ってでも自然に還る原料を使った洗剤で食器を洗うほうがグリーン。キッチンペーパーを使い捨てするより、水や洗剤を使ってでもふきんを洗濯して繰り返し使う方がグリーン。FSC認証のバージンパルプでつくったトイレットペーパーよりも、再生紙でつくったトイレットペーパーを選ぶほうがグリーン。
読了日:10月01日 著者:ジョージーナ・ウィルソン=パウエル
注: は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。
日本はますます生きづらい国になるだろう。
そこに、私が得てきた知識も倫理も、絶望感を助長するばかりだ。
私は何のために本を読んでいるのだろうか。
<今月のデータ>
購入22冊、購入費用23,830円。
読了18冊。
積読本272冊(うちKindle本114冊、Honto本13冊)。

10月の読書メーター
読んだ本の数:18
 崩れ (講談社文庫)の感想
崩れ (講談社文庫)の感想文さん72歳、52kg。執着したのは「崩れ」、なんと山崩れと暴れ川である。窮屈なズボンをはき、人に負ぶってもらってでも登り我が目で確かめるのだ。無意識のうちに心に貯めた『ものの種が芽に置きあがる時の力は、土を押し破るほど強い』。文さんの、炎が噴き出るような気性が発揮される。「木」が生命力の象徴であるのに対比し、山崩れは荒涼や麓の命を脅かす存在だ。恐怖に圧倒されながら、崩落の打当たって割れる落石の真新しい断面の美をも瞬間に捉える。文さんの文章は、自身の感性を逃さず、豊かだ。大山の崩れを思い浮かべつつ読んだ。
読了日:10月28日 著者:幸田 文

 動物園は進化する (ちくまプリマー新書)の感想
動物園は進化する (ちくまプリマー新書)の感想動物園でゾウを飼育展示するようになった当初は見世物だったのが、時代と共に動物を通じて自然のしくみを教える、種を保存するなど機能を変えてきた。体が大きいゆえに飼育係の安全問題は喫緊であり、動物福祉も言われる今、変わりつつあるという。しかし繁殖は上手くいっていない。繁殖するためにはゾウが自然体で生きられる環境が必要だ。なのに群れの構造が複雑なゾウの少数飼育やコンクリートと鉄の檻、夜に自由に歩いたり食べたりできないスケジュール、なにより他者の視線など、人間に置き換えれば当たり前のことが動物のことになると難しい。
『ゾウの自然な生活を参考にして、家族群をつくり繁殖させる。そのためには、日々進歩する科学に基づいた飼育方針のもと、古い飼育方法ではなく、ゾウに適した高度な生息環境を整え、これまで無視してきた動物の福祉に配慮する』。その志は尊い。だけれども。
私は動物園の動物を憐憫する子供だったので、そもそも動物園にゾウは必要かとの疑念が消せない。私たちも、飼育に関わる人たちも、ゾウやライオンやが動物園にいる前提で話をする。だけどリアルな映像や情報の溢れる現代に、日本全国に何百もの動物園と100頭余ものゾウをはじめとする大型動物は必要だろうか。環境破壊や密猟がなくならないから動物園で種の保存をという考え方に、私はぞっとする。動物の餌代など"維持コスト"を議論するくらいなら、どのみち"触れあい"とは無縁な動物たちの飼育は諦めようという方向にはならないのだろうか。
読了日:10月25日 著者:川口 幸男,アラン ルークロフト

 彼岸花が咲く島の感想
彼岸花が咲く島の感想話し言葉だけではなく、地の文の言葉にも違和感が激しく、なかなか読み進まない。普段使っている母語の機微を、ごく無意識に使い分けていることに改めて気づかされる。芥川賞だから、日本語を"正しく"使っていないといけないという規則はないはずなのに、ならばなぜこの作品が選ばれたのかと神経を鋭くして読んでしまう自分は、嫌な奴だ。さて、拓慈。最も身近な、異なる存在。彼を怖いと感じるのはなぜなのだろう。男だから。無知ゆえの無邪気さをぶつけてくるから。決定的に共有できないものが立ちはだかるから。それは理不尽なことだろうか?
読了日:10月22日 著者:李 琴峰
![農家が教える 竹やぶ減らし 2021年 10 月号 [雑誌]: 現代農業 増刊](https://m.media-amazon.com/images/I/51pUqClFyEL._SL120_.jpg) 農家が教える 竹やぶ減らし 2021年 10 月号 [雑誌]: 現代農業 増刊の感想
農家が教える 竹やぶ減らし 2021年 10 月号 [雑誌]: 現代農業 増刊の感想際限なく増殖する竹林と人の闘い。苦労されている人には申し訳ないけれど、自然との知恵比べみたいで面白かった。タケノコやメンマで食べて美味しいのも良し、竹チップに粉砕して発酵させ、堆肥化するのも良し。いや好い。専門誌で繰り返し特集されるほど繁殖力の強い竹に困らされても、私たちはまだまだ自分たちの生活に役立てることができるのだ。なかでも、高さ1mで切るだけという、竹の生態を逆手にとった根絶やし方法は、よくぞ見出したと感嘆する。竹やぶはたいてい里との境目でもあるので、イノシシ対策も兼ねた自然との格闘技みたいだな。
読了日:10月21日 著者:
 ヤマケイ新書 山を買うの感想
ヤマケイ新書 山を買うの感想自分の山が欲しいと思っていた頃があって、それは新型コロナやソロキャンの流行より前からなのだけど、それは安易な衝動であろう、と戒めのために読んでみた。さすがヤマケイ。甘くない。ゆるくない。しかしやっぱり欲しくなってしまった。ここに出てくる人々が山を買い求めた目的は様々で、なかでも山を守ることに使命感を見出した人たちへの共感と共振は、固定資産税ぐらい何年でも払ったるわ!という気分にさせる。『荒れた山を美しい里山に戻しながら、楽しむ』。そうだそうだと乗り気になりかける私に、立ちはだかる数多の障害の解説が詳しい。
読了日:10月19日 著者:福崎 剛

 マイル81 わるい夢たちのバザールI (文春文庫 キ 2-61 わるい夢たちのバザール 1)の感想
マイル81 わるい夢たちのバザールI (文春文庫 キ 2-61 わるい夢たちのバザール 1)の感想"カップ"と"取っ手"の湧いて出る泉が健在であることに感謝する。「UR」は以前、原語で読もうとしたことがある。キングの文体を非ネイティヴが読むなど無謀だったと改めて思った。キーボード付Kindleは懐かしく、キングが『ちび助マシン』にわくわくする気配が好ましい。パラドックス警察より怖いのは、文学の研究者にとっては専門の作家の知らない作品が続々出現する事態であり、私にとっては買えども未読の本が並んでいる現実ではないかな。『わしの名前ではない』。「砂丘」の結末は私も大好きだ。しゃれこうべのニヤニヤ笑い最高。
読了日:10月17日 著者:スティーヴン・キング
 西日本大震災に備えよ 日本列島大変動の時代 (PHP新書)の感想
西日本大震災に備えよ 日本列島大変動の時代 (PHP新書)の感想3.11以降、日本列島は『「大地変動の時代」が始まってしまった』。2030年代に発生が予測されるM9級の南海トラフ巨大地震をはじめ、東日本に再度の大地震、それに誘発される直下型地震。これらの発生は地球科学の分野では既定路線だという。活動周期や地盤の沈下/隆起現象の解析などの具体的な根拠を読み、自分が生きているうちに必ず来ると知り、備えなければならないと思いつつも、正常性バイアスとは厄介なもので、困ったなあ、とただぼやいている。日本人古来のメンタリティなどに思いをはせている場合ではない。備えんか自分。
今の日本列島が置かれた状況は、9世紀の日本に似ているのだという。9世紀は一般人には遠すぎるが、地球科学者には直近。驚嘆。
読了日:10月16日 著者:鎌田 浩毅

 アメリカ人の4人に1人はトランプが大統領だと信じているの感想
アメリカ人の4人に1人はトランプが大統領だと信じているの感想我が家は"あめしる"も欠かさず見る町山ファンなので、たいていの話題は町山さんから既に聞いたものだ。それにしても議事堂占拠は有り得ない事態だった。だからこそバイデン大統領の就任式が、オバマのとは違う意味で胸にずしりときたことを思い出した。さて、富豪たちの宇宙旅行合戦。ウィリアム王子の言うように、今やらないかんことはそれや無いやろ、である。全ての富豪に社会貢献の義務があるわけではない。だったら不労所得には重税をかけて社会に強制還元してもらわねば。Kindleを生んだ功績は多大なれど、ベゾスにはがっかりだ。
読了日:10月16日 著者:町山 智浩

 武漢日記:封鎖下60日の魂の記録の感想
武漢日記:封鎖下60日の魂の記録の感想湖北省武漢市が突如封鎖された、新型コロナ発生ごく初期の60日間の記録。新型コロナの本質的な事象は既にここにある。あと1週間の我慢だ。ワクチンができるまでの我慢だ。初期のそんな心持が今となっては新鮮なほど、あれはほんの始まりでしかなかったと知れる。発生場所が中国であるという一点で、私たちの頭の中にはフィルターがかかった。特殊な国家だからと。この本を読んで感じたのは、著者も著者のまわりの人々も、信じているということ。民主主義ではなくとも、在る秩序。人々との紐帯。善なるものへの信頼。『法治社会』としての中国を。
『政治的公正』の名分のもとに、ネット検閲官によってWeb上の投稿が通告なく削除されるのはよくあることのようだ。それでも諦めず思うことを投稿し、削除を免れたものによって意思を表明し、人々と意思疎通する。削除されることがわかっていても、怒りを表明する。そういう形で、社会は正しくあることができると、信じているようだ。それでも、バルガス=リョサの著作が本屋の棚から消えたことを知り、彼がなにか発言をしたからではないかと推測し、気落ちしている。その先には何が残るのだろう。先日読んだSF、馬伯庸の「沈黙都市」を想う。
読了日:10月15日 著者:方方

 出版翻訳家なんてなるんじゃなかった日記の感想
出版翻訳家なんてなるんじゃなかった日記の感想なぜこの時代に、出版社と翻訳家の契約が書面でなく口頭なのか。そもそもそこに問題があると思うが、それにしても印税カットも出版中止も、出版社の翻しようが酷いのなんの。著者のプライドゆえの災厄とは言いきれず、出版社の大小の問題とも判じきれず、こちらまで出版業界不信になりそう。私の支払った代金は正当に翻訳者に届いているのか。商業主義的と出版社を非難するのは簡単だが、出版不況と言われると、あのしっかりしたつくりの美しいものに正当な対価を払わない読者側の問題も絡む。これからは本を買うのに出版社も選ぶ時代かもしれない。
今年のノーベル文学賞を受賞したグルナ氏の著作は和訳されるのかどうか、翻訳本をつくるには時間がかかる。まず翻訳しなければどのような感触の作品か出版社にもわからないのが、翻訳本の事情のややこしいところだ。今頃、出版社が翻訳家に最短期間で訳せるかせっついているところかもしれない。売れるチャンスなのだから。だけど翻訳本は以前に比べますます売れないのだろう、有名作家の新刊小説でも、地方の書店は置いていないことが多いものなあ。出版物数がやたら多いのも問題だろうし。つい安い本の方を選んじゃうのも問題だろうし。難しい。
読了日:10月10日 著者:宮崎 伸治

 ゴッホのあしあと (幻冬舎文庫)の感想
ゴッホのあしあと (幻冬舎文庫)の感想「たゆたえども沈まず」の副読本と謳ったエッセイ。「たゆたえども~」のどの部分が創作だったか明らかにされていて興味深い。中野京子さんが“爆発し続けた”と表現したゴッホの晩年5年間。その起爆剤はパリと浮世絵だった。ゴッホの絵の奥底にある彼の孤独を探り当て、対象として眺めるんじゃなくて手繰り寄せるような、そんな感受性があるから、原田マハは小説を書けるのだと思った。一方、林忠正が同胞のはずの日本人から国賊呼ばわりされた当人であると知る。私はこちらを手繰ってみたい。
読了日:10月09日 著者:原田マハ
 たゆたえども沈まず (幻冬舎文庫)の感想
たゆたえども沈まず (幻冬舎文庫)の感想重吉、忠正、テオと登場し、フィンセントが現れて、役者は揃う。フィクションである日本人の、重吉にはテオの心情描写、忠正にはフィンセントの運命示唆が役割として割り振られ、それがしかも対比構造になっている。私は彼らの本当のところを知らないながら、上手いな、面白いなぁ、と思った。中野京子さんの本の続きで言うと、印象派の画家たちは、被写体の心情や立場に関心をもたなかったかもしれないけれど、自身の絵を描きたい情熱には真摯だった。日々食べるものにも事欠きながらも描くことをやめない、やめられない情熱なんて想像もつかない。
読了日:10月09日 著者:原田マハ
 聊斎志異の怪 (角川ソフィア文庫)の感想
聊斎志異の怪 (角川ソフィア文庫)の感想17世紀中国のあやかし説話集。幽霊が賄賂を贈ったり嫉妬したり、取っ組み合いの喧嘩を始めたりと騒々しく人間臭い。性愛絡みの物語も多く、幽玄という美的感覚が中国にはないのかとぼやいてみるが、思い返せば日本の説話だって似たようなもの。説話は骨組であって、要は想像力の膨らませようか。現に巻末の芥川と太宰が翻案した作品から、原案に肉をつけると物語として違和感がないとわかる。これは彼らの膨らませ方が上手いこともあろうけれども、中国と日本の物語の構造もきっと似ているのだろう。「狐の嫁女」は映像にしたらさぞ美しかろうな。
『これはきみの心だ。きみの作文が下手なのは、きみの心の毛穴がふさがっていたためだから、いま、冥途にある千万の心の中からよいものを一つ選び出して、きみの心と取り替えたのだ。きみの心は取っておいて、不足した冥途の分を補充するのだ』。と閻魔王のとこの判官が主人公のイマイチな文才の改善に便宜を図ってくれる。なんとも人間の願望の透けて見えることよ。さらに奥さんの顔と性根も美しい人のそれと取り替えてくれるという「首のすげかえ」は至れり尽くせり。閻魔王のとこの判官さんは、そんなに退屈しとったのだろうか。
読了日:10月08日 著者:蒲 松齢

 印象派で「近代」を読む 光のモネから、ゴッホの闇へ (NHK出版新書)の感想
印象派で「近代」を読む 光のモネから、ゴッホの闇へ (NHK出版新書)の感想印象派は『何が描かれているかより、どんなふうに描かれているか』を重視する代わり、悲惨も鬱屈も顧みることない、人の心の深みとは切り離された絵画だった。当時の庶民同様、西洋史の教養も無しに眺めていた私に、絵は背景を知って観るのが面白いと中野さんは教えてくれる。ただ楽しむための絵画にも時代背景はある。屋外で描くという行為自体がたいへんな変革だったとか、エッフェル塔は醜いと嫌われたとか、中でも踊り子や上流階級の妻やお針子や、その時代の人々、同時に画家自身の生き方が絵の中に現れていると新たに知って俄然楽しくなる。
読了日:10月07日 著者:中野 京子

 老いた家 衰えぬ街 住まいを終活する (講談社現代新書)の感想
老いた家 衰えぬ街 住まいを終活する (講談社現代新書)の感想全国民を挙げての大ババ抜き大会である。人口が急減を始めるなか、それはもう既に始まっていて、たとえば20年後に処分できそうにない不動産を今買うなどもってのほかで、親や親族の不動産が転がり込んでくる可能性や、近隣が放棄物件で荒廃する可能性を考えれば、無縁でいられない人の方が多そうだ。個人ではどうしようもないケースも考えると、個人を厳罰化しても根本的な解決にはならず、マッチングにせよ近隣需要への橋渡しにせよ、譲渡推進にも早晩限界が出るのではないのかしら。法制面をはじめ、ババをババでなくする仕組みづくりが急務。
町を歩いていて明らかに空き家とわかる物件でも、様々な事情で放置/留置されている事情がある。所有者が施設に入ったなどはこの本にも書かれているが、不動産屋さんと話していると、親族や近隣住民との関係の都合で、堂々と売りに出すことができない様々の問題があるのだそうだ。かといって売れない実家、山林や原野="負動産"にかかる税金などの経費は年々かかり続け、ボディブローのように効いてくるのだから、持ち続けることにも無理がある。いやー、どうすんだこれ。
読了日:10月05日 著者:野澤 千絵

 猫と住まいの解剖図鑑の感想
猫と住まいの解剖図鑑の感想我が家の猫は1匹になってしまったけれど、縁があるなら、また猫を迎えたい。で、猫ズに優しい家を妄想する。猫を優先にして家をつくるのは本末転倒で、人間のための家を設計する中で、猫にも優しい工夫をするべきという前提には同意する。脱走防止に引き戸をつけるなどもよいけれど、今はいろいろな商材が出ていて、爪とぎやキャットウォークはもちろん、壁の漆喰塗りや、窓を開けておくための格子もDIYできるという情報がためになった。和のしつらえも案外大丈夫と知る。障子や襖は貼り直せばよく、畳も爪とぎされそうで実は大丈夫らしい。
読了日:10月03日 著者:いしまるあきこ
 「男女格差後進国」の衝撃: 無意識のジェンダー・バイアスを克服する (小学館新書)の感想
「男女格差後進国」の衝撃: 無意識のジェンダー・バイアスを克服する (小学館新書)の感想セミナーで紹介された本。以前「女性活躍」と言われると、もやっとした違和感が拭えなかった。余計な意味合いが含蓄されて感じた。ではなく「ジェンダー・ギャップの解消」なら、目的は明瞭で社会の目標として掲げてよいと思う。さて、性別に基づく無意識の決めつけは男性だけでなく女性にもあり、地域差や世代差もある。組織において"女性ならではの"視点をという言い方もそれ自体が決めつけ的なものだが、できることがあるとすれば、「少数派としての体験」を生かして、マイノリティ属性の人の困りそうな状況を察知し、解消を発想することかも。
グローバル・ジェンダー・ギャップ指数(経済分野)の算出根拠は ①女性の労働参加率 ②類似職業の男女賃金格差 ③全体の男女賃金格差 ④管理職に占める女性比率 ⑤総合職・専門職に占める女性比率。家事育児介護の負担をアウトソーシングできる国柄の国の方が指数が高くなる傾向にある。公共サービスとしてアウトソーシングできる北欧の国と同様、新興国・途上国であるアジアやアフリカにも指数が高い国がある。それは、所得の多い家は低所得の女性を雇って家事育児介護をさせることができるので、自分も働きに出られるからであるとのことだ。
読了日:10月02日 著者:治部 れんげ

 これってホントにエコなの?の感想
これってホントにエコなの?の感想人間はものを造る。運ぶ。使う。捨てる。それらは地球環境には全て負荷になる。衣食住、毎日毎日の膨大な選択で、負荷を減らせる選択について書いている。関心があっても眩暈がしてくる分量だが、それによって環境負荷を減らすための原則が解ると同時に、より複合的な問題、一律に答えを出せない問いが多い事実も、浮き彫りになっている。つまり選択は程度の問題で、次善の策を取るしかないことも解って、選んでいくしかないのだ。カーボンオフセットは、自力で解決できないから金銭で協力しようという行為。必要だけど、取組として本質的ではない。
自然の中で分解されない化学物質を使った洗剤より、水を余分に使ってでも自然に還る原料を使った洗剤で食器を洗うほうがグリーン。キッチンペーパーを使い捨てするより、水や洗剤を使ってでもふきんを洗濯して繰り返し使う方がグリーン。FSC認証のバージンパルプでつくったトイレットペーパーよりも、再生紙でつくったトイレットペーパーを選ぶほうがグリーン。
読了日:10月01日 著者:ジョージーナ・ウィルソン=パウエル
注:
 は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。 Posted by nekoneko at 13:04│Comments(0)
│読書