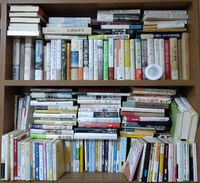2022年10月01日
2022年9月の記録
内田樹先生の講演を聴きに行った。
初めて聞く先生の声は柔らかかった。意外に感じた。
ルヌガンガさんが内田先生の本を持って来ていて、サインが頂けるということで1冊を急いで選んだ。
ちらと危惧したとおり、1年前に既に読んでおり、しかも比較的気に入らなかったものだった。
安田先生との対談本にすればよかった。
しかし内田先生に私の言葉を伝えて、にっこり笑っていただいたことは忘れない。
<今月のデータ>
購入19冊、購入費用21,977円。
読了15冊。
積読本328冊(うちKindle本161冊、Honto本6冊)。

9月の読書メーター
 女には向かない職業 (ハヤカワ・ミステリ文庫)の感想
女には向かない職業 (ハヤカワ・ミステリ文庫)の感想
修道院で暮らした過去や、他人を安易に容れない性格による、ドライな世界観を持った若い探偵という設定。若干こなれない、上滑りな印象を受けるのは、シリーズ初作だからか。依頼を受け、予想外に淡々と乗り込んだカテージは、真実が明るみに出るにつれて穏やかな明るい隠れ家からおぞましい悪意に浸食された空き家へ変貌する。その過程もどこかしっくりこない感触だが、この物語の読みどころは事件解決後、ダルグリッシュ警視との攻防戦なのだ。このダルグリッシュ警視がシリーズ本流らしく、引力のある登場人物。買っちゃってるので続編を読む。
読了日:09月25日 著者:P.D.ジェイムズ
 営繕かるかや怪異譚 その弐 (角川文庫)の感想
営繕かるかや怪異譚 その弐 (角川文庫)の感想
違和感、気配と経て、怪異は凝って視覚化する。その経緯を書くのが小野さんは上手いのである。ていうか、今回は具現化しすぎて、これはこれで怖い。紐とか鎌とか、悪霊シリーズの再現である。中では、物と、人の思いが絡んだ怪異が印象に残った。物に残る魂。リサイクルや古物を取り入れた暮らしは流行りとて、物を大切に使う暮らしとは同義でない。逆に粗末にすることもある例である。工夫と横着は違う。『ものを作るのは手間暇かかるものよ。手間暇を惜しむから、あなたはすぐ奇抜なことに走るの』。隅田さんが素敵なキャラになってきた。
読了日:09月22日 著者:小野 不由美
 ビーグル号世界周航記 ダーウィンは何をみたか (講談社学術文庫)の感想
ビーグル号世界周航記 ダーウィンは何をみたか (講談社学術文庫)の感想
航海記そのものではなく、著書からの抜粋を子供向けに編集した本「ビーグル号で世界を巡る旅の中でダーウィン氏が見たもの」の翻訳である。19世紀、ダーウィンが体験した事物が事細かに記録されている。各地の民族や土地の描写を読むのは楽しい。なぜなら、乗馬でボラスの扱いを失敗して南米ガウーチョ人に笑われた逸話や、タヒチ人への開けっぴろげな賛美など、西洋人らしからぬ偏りのない観察眼、旺盛な好奇心と道義心は、正直で愛すべき人物と認定するにじゅうぶんだからだ。原始林を「"自然という神"が生み出した殿堂」と呼ぶのも好ましい。
1835年2月20日11時半、ダーウィンはチリで地震に遭遇する。『ひどい地震はたちまちわれわれの古い連想を破ってしまう。堅固そのものを象徴するような大地が、流体の上のうすい皮のようにわれわれの足元で動いた。地震は一秒で、何時間の反省によっても産みだせないような奇妙な不安な心持を、心の中につくりあげてしまった』。そしてもしイギリスが地震の暴威にさらされたらどのような事態になるかと震撼している。地震に遭ったことがなかったと見える。地震は、地震が頻発する地に生きる民族の精神性に大きな影響を与えているのだろうな。
読了日:09月21日 著者:チャールズ・ロバート・ダーウィン
 おくのほそ道(全) ビギナーズ・クラシックス 日本の古典 (角川ソフィア文庫―ビギナーズ・クラシックス)の感想
おくのほそ道(全) ビギナーズ・クラシックス 日本の古典 (角川ソフィア文庫―ビギナーズ・クラシックス)の感想
ある本を読もうと思って、そういえば原本を読んでいないことに思い至り、さらりと読んでみる。深川の草庵から、芭蕉は自ら荷物を担いで旅に出る。笠敷いたり賽銭踏んだりしては、泣く。感動の誇張表現なのか、あるいは歩いて旅をするという行為が当たり前でも安全でもないゆえに、感情が増幅されるのだろうか。実際に歩いてみたらわかるのだろうか。先達の詠んだ和歌や俳句への知識が深い。当然、記憶している。この旅は、知己を訪ねる旅でもなく、名所巡りでもなく、先達の足跡を辿る旅だったのだろう。安田先生の芭蕉を歩く旅の、あれも読もう。
読了日:09月19日 著者:松尾芭蕉
 「十二国記」30周年記念ガイドブックの感想
「十二国記」30周年記念ガイドブックの感想
もうガイドブックなんて読んでも目新しい発見は無いくらい繰り返し読んできたと自信はありつつ、小野主上のインタビューと短編はやはり逃がせないと購入。辻村深月のエッセイが上手くて、同じ時間を共有した者としてじんと震える。そしてなんといっても小野さんの肉声である。悪霊シリーズ以来、自らの言葉で語られる場がほとんどなくなって、綾辻さんから漏れ聞くだけだったから、、、あれ、そういえば何年か前のインタビュー誌はどこへいったっけ? ともかくお身体を大事にしていただきたい。あと、A0サイズの十二国記の地図見てみたいです。
読了日:09月18日 著者:
 これは、アレだなの感想
これは、アレだなの感想
テレビの普及期からよほどメディア漬けでこられたんじゃないかと想像するほど、テレビ、漫画、本、音楽、映画、今はネトフリ他ストリーミング配信まで、あらゆる媒体で発表される作品を渉猟されてきたようだ。そのデータベースを 「これ」から「アレ」へと、古今東西思いのままに発想を飛ばされるのを、こちらは口をぽかんと開けて拝聴していればよいだけだが、ご本人にはかなり大変な作業になったらしい。たくさんの作品の「これ」と「アレ」を見定めてゆけば、生まれる感動が薄れるかと思えばそうではないらしく、「鬼滅の刃」は泣くらしい。
読了日:09月17日 著者:高橋 源一郎
 破船 (新潮文庫)の感想
破船 (新潮文庫)の感想
極貧の漁村。タコ、イワシ、サンマ、塩と、自然の恵みに依存した営みは季節に沿い正しく繰り返される。漁獲は村人の糧の多寡に直結し、頻繁に身売りが行われる。物語の中で季節は執拗に繰り返され、お船様が現れた頃には読み手も生き延びるためのムラの論理をやむなく思い始める。しかしそれは、村外の人間の死と表裏だ。著者が描きたかったのは、その貧しき人の心のさもしさと生々しい生への執着の捻じれなのだろう。幼い伊作は父親に代わり、漁に出る。年ごとに上手くなり、家の母や弟妹を想う。そんな日々の積み重ねも疫病によって無に帰すのだ。
この村は、穀物の栽培もおぼつかず、漁獲が少なければ即、飢えてしまう。数年に一度の破船から奪ったもので数年を食いつなぐ、つまり破船が無ければ生きていけないから、破船をお船様と呼んで乞い願うようになる。この村には、未来があってはならないのだ。病んだ者ではなく、病まなかった者が出て行けばよかったのに。
読了日:09月15日 著者:吉村 昭
 エネルギーをめぐる旅――文明の歴史と私たちの未来の感想
エネルギーをめぐる旅――文明の歴史と私たちの未来の感想
ブラボー! 感動未だ冷めやらず。石油会社の一社員の立ち位置にありながら、偏らない姿勢でエネルギーという巨大テーマに深い関心を持ち続ける意志がすごい。そして人がライフワークを抱いていると、様々な方面から知は集まってくる。すなわち、専攻の化学分野に留まらず、科学、哲学、歴史、地学と多角的に情報を整理し、エネルギーという抽象的な存在の本質に迫ることで人類の未来に希望を見出そうとする著者の誠実な試みは、人間の英知そのものと呼びたい。さらにそれを他者に分け与えんと執筆の労を担ってくださった著者に心から敬意を表する。
『エネルギー問題とは、単に技術革新に期待するだけでは解決できない複雑な問題』『安易な技術革新信仰を捨て、より深いところでエネルギー問題に正対すること』『環境負荷を全く気にすることなく人類が好き勝手に使ってよいような完璧なエネルギー源など、そもそもこの世には存在しない』『個々の省エネ技術はむしろ社会全体のエネルギー消費量を増やす傾向があるとなると、知識の蓄積で成り立っている現代文明を維持・発展させていくためには、エネルギー消費量を引き続き増やし続けていくほか手立てがなくなってしまいます。』
著者は核融合反応による原子力発電を希望の発電システムと見定めている。しかしその実現には世界中の英知と資本を結集した開発によって、今の人類の技術からはずっと先の技術革新を成さなければならない。目下としては、ヒトの脳が持つ際限のないエネルギー獲得への欲求を自覚し、太陽光エネルギー、水素、省エネ、地産地消を前提とした分散型システムなど、できること全てをやらなければならないとしている。『何もないところからエネルギーを作り出す技術、ないしはエネルギーの質の劣化を逆転させる技術、そのいずれもが実現不可能なのです』。
「旅のおわりに」と「謝辞」の真摯さ率直さは好ましく、「謝辞」の締めくくりにはほろりとしてしまった。英治出版の社長の心意気にも感謝したい。おかげで著者の英知を私が受け取ることができたのだから。電子書籍の末尾も末尾、いつもなら本を閉じてしまうところに文字を発見。"TO MAKE THE WORLD A BETTER PLACE - Eiji Press, Inc." かっこいい!
読了日:09月15日 著者:古舘 恒介
 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー (新潮文庫)の感想
ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー (新潮文庫)の感想
カトリック系の私立小学校から、公立の"元底辺中学校"へ進学。息子君と家族の日々遭遇する事件は、持っている歴史や文化の相違上、日本ではありえず、同時にイギリスの内側でずっと同じ階級にいては当たり前すぎて気づけない種類の問題を可視化する。著者持ち前の元気でパンクな語り口と、社会制度への知識が読み応えに繋がっている。ボランティアの感覚が日本と絶対的に違う。相互扶助の精神が遍在する社会の姿や、多様な人々が共生するにあたって避けられない摩擦の例、それをより良い方向へ変えていこうと組まれる教育の在りかたが興味深い。
読了日:09月12日 著者:ブレイディみかこ
 独りでいるより優しくての感想
独りでいるより優しくての感想
ミステリのようで、つまるところ、黙然の物語であると私は思う。素直でよく笑う少女。泊陽の薄情や、如玉の拒絶に戸惑い、結果として犯罪に加担した苦しさはいかばかりか。それから渡米までの数年間については結局触れられていないが、その後の挙動には影が残る。相手は訳わからんだろう。だから、ジョセフとの関係を取り戻せたことはすごく良かったと感じるのだ。『先へ進む? それはアメリカのもので、私はそれをいいこととは思ってないよ』。芯からアメリカナイズされるのではなく、黙然が黙然であるところの女性で在れる結末を好ましく思った。
読了日:09月10日 著者:イーユン リー
 にごりえの感想
にごりえの感想
文体が好きで、何度か読んでいたはずなのに、「文人悪妻」にちらりと出た結末に覚えがなかった自分に驚く。いやー、お力が健気で、かわいらしいやらいたわしいやらで、そちらが印象に強くて、最終章のがらりと展開してチョンと終わる、テンポの加減のせいかしら。「曽根崎心中」とやや混同している向きもあり。刀傷の描写をじっくりと読むと、お力の振舞いがまざまざと見えるようであり、やっぱりなんとも痛ましい物語である。
読了日:09月06日 著者:樋口 一葉
 文人悪妻 (新潮文庫)の感想
文人悪妻 (新潮文庫)の感想
男性向け週刊誌の連載かと勘繰るノリと、女性たちの精気と色気に中てられてクラクラしてくる。流れでたまたま「文人」と題しただけで、さして「悪」妻でもない。森しげでもさほど悪く書かれていない。むしろ、妻の役目を務め上げた、あるいは強かに生き抜いた明治~昭和時代の著名な男性の伴侶、または自身が著名な女性への賛歌である。男性にしろ女性にしろ、文人という人種の伴侶は難しい。しかし、その人生経験を見事に文学作品に昇華する姿には、「まじか…」しか出ない。著者の文学への造詣ゆえ、混ぜ込まれる作品を片っ端から漁りたくなる。
読了日:09月06日 著者:嵐山 光三郎
 ウルフ・ウォーズ オオカミはこうしてイエローストーンに復活したの感想
ウルフ・ウォーズ オオカミはこうしてイエローストーンに復活したの感想
オオカミ再導入をいかに成し得たかの記録。野性大型動物の乱獲による急減と、人間と家畜動物の急増が、オオカミによる"被害"を増やした点は同じである。しかし"絶滅"させた日本と違い、アメリカでは国境の向こう側や隣州に同種がいるので、民間人による殺戮と家畜被害の補償の法制化が主である。先にニホンオオカミの本を読んだせいで熱が入らない頭で考える。ある種が100年を生き繋ぐのに、そもそも何頭残っていれば可能だろうか。その頭数のオオカミが、いくら人間の脚が山中で不自由といえ、発見されず生き延びられるか疑問に思えてきた。
先日、鴻池朋子の「みる誕生」を観に行った。知らなかったのだが、鴻池さんはオオカミやキツネの毛皮をいくつも吊るす展示をする。顔も足指もある毛皮に私が動揺していると、学芸員さんが近づいて、「オオカミの毛皮です。日本はいませんが、外国では害獣なので。インターネットで販売されていて、買えるそうです。」と説明した。冬毛だろうか、毒殺だろうか、手の甲で触れたハイイロオオカミの深い毛並みは、名状し難い激情を生んだ。泣きたかった。
読了日:09月04日 著者:ハンク・フィッシャー
 貧困パンデミック――寝ている『公助』を叩き起こすの感想
貧困パンデミック――寝ている『公助』を叩き起こすの感想
2020~2021年の、各支援団体の状況がわかる。新型コロナでもともと不安定だった雇用が奪われ、困窮の末住まいも失った人が急増した。そして福祉崩壊、相談崩壊。支援団体の人々は支援をしながら行政に申入れし、抗議し、地道に変えていく。一方で政治家によるネガキャンは大々的に報道され、確実に人々の心を侵食していく。国の組織としてのしなやかさの欠如が、日本をますます生きづらい場所にする。行政の支援を受けるのに、やりとりを録音しておくべきだなんて常態は酷すぎる。「自助も共助も限界に来ている。今こそ、公助の出番だ」。
読了日:09月03日 著者:稲葉 剛
 「身体」を忘れた日本人 JAPANESE, AND THE LOSS OF PHYSICAL SENSESの感想
「身体」を忘れた日本人 JAPANESE, AND THE LOSS OF PHYSICAL SENSESの感想
2020年に亡くなったC.W.ニコル氏と養老先生の対談、2014年。ニコル氏はアファンの森をつくったり馬を使役したり学校創設に関わったりと活動の幅広く、養老先生も保育園の理事長を引き受けたりされているので、日本の未来を想って、日本の自然や子供のために尽力している共通点がある。"We have to be gardeners"。感覚は違いを発見するもの。意識は同じを見つけるもの。どちらに傾きすぎても生きづらいけれど、感覚の世界の奥深さを忘れては人は生きられないのだよという大切なメッセージ。広い土地欲しい。
読了日:09月03日 著者:養老孟司,C.W.ニコル
注: は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。
初めて聞く先生の声は柔らかかった。意外に感じた。
ルヌガンガさんが内田先生の本を持って来ていて、サインが頂けるということで1冊を急いで選んだ。
ちらと危惧したとおり、1年前に既に読んでおり、しかも比較的気に入らなかったものだった。
安田先生との対談本にすればよかった。
しかし内田先生に私の言葉を伝えて、にっこり笑っていただいたことは忘れない。
<今月のデータ>
購入19冊、購入費用21,977円。
読了15冊。
積読本328冊(うちKindle本161冊、Honto本6冊)。

9月の読書メーター
 女には向かない職業 (ハヤカワ・ミステリ文庫)の感想
女には向かない職業 (ハヤカワ・ミステリ文庫)の感想修道院で暮らした過去や、他人を安易に容れない性格による、ドライな世界観を持った若い探偵という設定。若干こなれない、上滑りな印象を受けるのは、シリーズ初作だからか。依頼を受け、予想外に淡々と乗り込んだカテージは、真実が明るみに出るにつれて穏やかな明るい隠れ家からおぞましい悪意に浸食された空き家へ変貌する。その過程もどこかしっくりこない感触だが、この物語の読みどころは事件解決後、ダルグリッシュ警視との攻防戦なのだ。このダルグリッシュ警視がシリーズ本流らしく、引力のある登場人物。買っちゃってるので続編を読む。
読了日:09月25日 著者:P.D.ジェイムズ

 営繕かるかや怪異譚 その弐 (角川文庫)の感想
営繕かるかや怪異譚 その弐 (角川文庫)の感想違和感、気配と経て、怪異は凝って視覚化する。その経緯を書くのが小野さんは上手いのである。ていうか、今回は具現化しすぎて、これはこれで怖い。紐とか鎌とか、悪霊シリーズの再現である。中では、物と、人の思いが絡んだ怪異が印象に残った。物に残る魂。リサイクルや古物を取り入れた暮らしは流行りとて、物を大切に使う暮らしとは同義でない。逆に粗末にすることもある例である。工夫と横着は違う。『ものを作るのは手間暇かかるものよ。手間暇を惜しむから、あなたはすぐ奇抜なことに走るの』。隅田さんが素敵なキャラになってきた。
読了日:09月22日 著者:小野 不由美
 ビーグル号世界周航記 ダーウィンは何をみたか (講談社学術文庫)の感想
ビーグル号世界周航記 ダーウィンは何をみたか (講談社学術文庫)の感想航海記そのものではなく、著書からの抜粋を子供向けに編集した本「ビーグル号で世界を巡る旅の中でダーウィン氏が見たもの」の翻訳である。19世紀、ダーウィンが体験した事物が事細かに記録されている。各地の民族や土地の描写を読むのは楽しい。なぜなら、乗馬でボラスの扱いを失敗して南米ガウーチョ人に笑われた逸話や、タヒチ人への開けっぴろげな賛美など、西洋人らしからぬ偏りのない観察眼、旺盛な好奇心と道義心は、正直で愛すべき人物と認定するにじゅうぶんだからだ。原始林を「"自然という神"が生み出した殿堂」と呼ぶのも好ましい。
1835年2月20日11時半、ダーウィンはチリで地震に遭遇する。『ひどい地震はたちまちわれわれの古い連想を破ってしまう。堅固そのものを象徴するような大地が、流体の上のうすい皮のようにわれわれの足元で動いた。地震は一秒で、何時間の反省によっても産みだせないような奇妙な不安な心持を、心の中につくりあげてしまった』。そしてもしイギリスが地震の暴威にさらされたらどのような事態になるかと震撼している。地震に遭ったことがなかったと見える。地震は、地震が頻発する地に生きる民族の精神性に大きな影響を与えているのだろうな。
読了日:09月21日 著者:チャールズ・ロバート・ダーウィン

 おくのほそ道(全) ビギナーズ・クラシックス 日本の古典 (角川ソフィア文庫―ビギナーズ・クラシックス)の感想
おくのほそ道(全) ビギナーズ・クラシックス 日本の古典 (角川ソフィア文庫―ビギナーズ・クラシックス)の感想ある本を読もうと思って、そういえば原本を読んでいないことに思い至り、さらりと読んでみる。深川の草庵から、芭蕉は自ら荷物を担いで旅に出る。笠敷いたり賽銭踏んだりしては、泣く。感動の誇張表現なのか、あるいは歩いて旅をするという行為が当たり前でも安全でもないゆえに、感情が増幅されるのだろうか。実際に歩いてみたらわかるのだろうか。先達の詠んだ和歌や俳句への知識が深い。当然、記憶している。この旅は、知己を訪ねる旅でもなく、名所巡りでもなく、先達の足跡を辿る旅だったのだろう。安田先生の芭蕉を歩く旅の、あれも読もう。
読了日:09月19日 著者:松尾芭蕉

 「十二国記」30周年記念ガイドブックの感想
「十二国記」30周年記念ガイドブックの感想もうガイドブックなんて読んでも目新しい発見は無いくらい繰り返し読んできたと自信はありつつ、小野主上のインタビューと短編はやはり逃がせないと購入。辻村深月のエッセイが上手くて、同じ時間を共有した者としてじんと震える。そしてなんといっても小野さんの肉声である。悪霊シリーズ以来、自らの言葉で語られる場がほとんどなくなって、綾辻さんから漏れ聞くだけだったから、、、あれ、そういえば何年か前のインタビュー誌はどこへいったっけ? ともかくお身体を大事にしていただきたい。あと、A0サイズの十二国記の地図見てみたいです。
読了日:09月18日 著者:
 これは、アレだなの感想
これは、アレだなの感想テレビの普及期からよほどメディア漬けでこられたんじゃないかと想像するほど、テレビ、漫画、本、音楽、映画、今はネトフリ他ストリーミング配信まで、あらゆる媒体で発表される作品を渉猟されてきたようだ。そのデータベースを 「これ」から「アレ」へと、古今東西思いのままに発想を飛ばされるのを、こちらは口をぽかんと開けて拝聴していればよいだけだが、ご本人にはかなり大変な作業になったらしい。たくさんの作品の「これ」と「アレ」を見定めてゆけば、生まれる感動が薄れるかと思えばそうではないらしく、「鬼滅の刃」は泣くらしい。
読了日:09月17日 著者:高橋 源一郎

 破船 (新潮文庫)の感想
破船 (新潮文庫)の感想極貧の漁村。タコ、イワシ、サンマ、塩と、自然の恵みに依存した営みは季節に沿い正しく繰り返される。漁獲は村人の糧の多寡に直結し、頻繁に身売りが行われる。物語の中で季節は執拗に繰り返され、お船様が現れた頃には読み手も生き延びるためのムラの論理をやむなく思い始める。しかしそれは、村外の人間の死と表裏だ。著者が描きたかったのは、その貧しき人の心のさもしさと生々しい生への執着の捻じれなのだろう。幼い伊作は父親に代わり、漁に出る。年ごとに上手くなり、家の母や弟妹を想う。そんな日々の積み重ねも疫病によって無に帰すのだ。
この村は、穀物の栽培もおぼつかず、漁獲が少なければ即、飢えてしまう。数年に一度の破船から奪ったもので数年を食いつなぐ、つまり破船が無ければ生きていけないから、破船をお船様と呼んで乞い願うようになる。この村には、未来があってはならないのだ。病んだ者ではなく、病まなかった者が出て行けばよかったのに。
読了日:09月15日 著者:吉村 昭
 エネルギーをめぐる旅――文明の歴史と私たちの未来の感想
エネルギーをめぐる旅――文明の歴史と私たちの未来の感想ブラボー! 感動未だ冷めやらず。石油会社の一社員の立ち位置にありながら、偏らない姿勢でエネルギーという巨大テーマに深い関心を持ち続ける意志がすごい。そして人がライフワークを抱いていると、様々な方面から知は集まってくる。すなわち、専攻の化学分野に留まらず、科学、哲学、歴史、地学と多角的に情報を整理し、エネルギーという抽象的な存在の本質に迫ることで人類の未来に希望を見出そうとする著者の誠実な試みは、人間の英知そのものと呼びたい。さらにそれを他者に分け与えんと執筆の労を担ってくださった著者に心から敬意を表する。
『エネルギー問題とは、単に技術革新に期待するだけでは解決できない複雑な問題』『安易な技術革新信仰を捨て、より深いところでエネルギー問題に正対すること』『環境負荷を全く気にすることなく人類が好き勝手に使ってよいような完璧なエネルギー源など、そもそもこの世には存在しない』『個々の省エネ技術はむしろ社会全体のエネルギー消費量を増やす傾向があるとなると、知識の蓄積で成り立っている現代文明を維持・発展させていくためには、エネルギー消費量を引き続き増やし続けていくほか手立てがなくなってしまいます。』
著者は核融合反応による原子力発電を希望の発電システムと見定めている。しかしその実現には世界中の英知と資本を結集した開発によって、今の人類の技術からはずっと先の技術革新を成さなければならない。目下としては、ヒトの脳が持つ際限のないエネルギー獲得への欲求を自覚し、太陽光エネルギー、水素、省エネ、地産地消を前提とした分散型システムなど、できること全てをやらなければならないとしている。『何もないところからエネルギーを作り出す技術、ないしはエネルギーの質の劣化を逆転させる技術、そのいずれもが実現不可能なのです』。
「旅のおわりに」と「謝辞」の真摯さ率直さは好ましく、「謝辞」の締めくくりにはほろりとしてしまった。英治出版の社長の心意気にも感謝したい。おかげで著者の英知を私が受け取ることができたのだから。電子書籍の末尾も末尾、いつもなら本を閉じてしまうところに文字を発見。"TO MAKE THE WORLD A BETTER PLACE - Eiji Press, Inc." かっこいい!
読了日:09月15日 著者:古舘 恒介

 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー (新潮文庫)の感想
ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー (新潮文庫)の感想カトリック系の私立小学校から、公立の"元底辺中学校"へ進学。息子君と家族の日々遭遇する事件は、持っている歴史や文化の相違上、日本ではありえず、同時にイギリスの内側でずっと同じ階級にいては当たり前すぎて気づけない種類の問題を可視化する。著者持ち前の元気でパンクな語り口と、社会制度への知識が読み応えに繋がっている。ボランティアの感覚が日本と絶対的に違う。相互扶助の精神が遍在する社会の姿や、多様な人々が共生するにあたって避けられない摩擦の例、それをより良い方向へ変えていこうと組まれる教育の在りかたが興味深い。
読了日:09月12日 著者:ブレイディみかこ
 独りでいるより優しくての感想
独りでいるより優しくての感想ミステリのようで、つまるところ、黙然の物語であると私は思う。素直でよく笑う少女。泊陽の薄情や、如玉の拒絶に戸惑い、結果として犯罪に加担した苦しさはいかばかりか。それから渡米までの数年間については結局触れられていないが、その後の挙動には影が残る。相手は訳わからんだろう。だから、ジョセフとの関係を取り戻せたことはすごく良かったと感じるのだ。『先へ進む? それはアメリカのもので、私はそれをいいこととは思ってないよ』。芯からアメリカナイズされるのではなく、黙然が黙然であるところの女性で在れる結末を好ましく思った。
読了日:09月10日 著者:イーユン リー
 にごりえの感想
にごりえの感想文体が好きで、何度か読んでいたはずなのに、「文人悪妻」にちらりと出た結末に覚えがなかった自分に驚く。いやー、お力が健気で、かわいらしいやらいたわしいやらで、そちらが印象に強くて、最終章のがらりと展開してチョンと終わる、テンポの加減のせいかしら。「曽根崎心中」とやや混同している向きもあり。刀傷の描写をじっくりと読むと、お力の振舞いがまざまざと見えるようであり、やっぱりなんとも痛ましい物語である。
読了日:09月06日 著者:樋口 一葉

 文人悪妻 (新潮文庫)の感想
文人悪妻 (新潮文庫)の感想男性向け週刊誌の連載かと勘繰るノリと、女性たちの精気と色気に中てられてクラクラしてくる。流れでたまたま「文人」と題しただけで、さして「悪」妻でもない。森しげでもさほど悪く書かれていない。むしろ、妻の役目を務め上げた、あるいは強かに生き抜いた明治~昭和時代の著名な男性の伴侶、または自身が著名な女性への賛歌である。男性にしろ女性にしろ、文人という人種の伴侶は難しい。しかし、その人生経験を見事に文学作品に昇華する姿には、「まじか…」しか出ない。著者の文学への造詣ゆえ、混ぜ込まれる作品を片っ端から漁りたくなる。
読了日:09月06日 著者:嵐山 光三郎

 ウルフ・ウォーズ オオカミはこうしてイエローストーンに復活したの感想
ウルフ・ウォーズ オオカミはこうしてイエローストーンに復活したの感想オオカミ再導入をいかに成し得たかの記録。野性大型動物の乱獲による急減と、人間と家畜動物の急増が、オオカミによる"被害"を増やした点は同じである。しかし"絶滅"させた日本と違い、アメリカでは国境の向こう側や隣州に同種がいるので、民間人による殺戮と家畜被害の補償の法制化が主である。先にニホンオオカミの本を読んだせいで熱が入らない頭で考える。ある種が100年を生き繋ぐのに、そもそも何頭残っていれば可能だろうか。その頭数のオオカミが、いくら人間の脚が山中で不自由といえ、発見されず生き延びられるか疑問に思えてきた。
先日、鴻池朋子の「みる誕生」を観に行った。知らなかったのだが、鴻池さんはオオカミやキツネの毛皮をいくつも吊るす展示をする。顔も足指もある毛皮に私が動揺していると、学芸員さんが近づいて、「オオカミの毛皮です。日本はいませんが、外国では害獣なので。インターネットで販売されていて、買えるそうです。」と説明した。冬毛だろうか、毒殺だろうか、手の甲で触れたハイイロオオカミの深い毛並みは、名状し難い激情を生んだ。泣きたかった。
読了日:09月04日 著者:ハンク・フィッシャー
 貧困パンデミック――寝ている『公助』を叩き起こすの感想
貧困パンデミック――寝ている『公助』を叩き起こすの感想2020~2021年の、各支援団体の状況がわかる。新型コロナでもともと不安定だった雇用が奪われ、困窮の末住まいも失った人が急増した。そして福祉崩壊、相談崩壊。支援団体の人々は支援をしながら行政に申入れし、抗議し、地道に変えていく。一方で政治家によるネガキャンは大々的に報道され、確実に人々の心を侵食していく。国の組織としてのしなやかさの欠如が、日本をますます生きづらい場所にする。行政の支援を受けるのに、やりとりを録音しておくべきだなんて常態は酷すぎる。「自助も共助も限界に来ている。今こそ、公助の出番だ」。
読了日:09月03日 著者:稲葉 剛

 「身体」を忘れた日本人 JAPANESE, AND THE LOSS OF PHYSICAL SENSESの感想
「身体」を忘れた日本人 JAPANESE, AND THE LOSS OF PHYSICAL SENSESの感想2020年に亡くなったC.W.ニコル氏と養老先生の対談、2014年。ニコル氏はアファンの森をつくったり馬を使役したり学校創設に関わったりと活動の幅広く、養老先生も保育園の理事長を引き受けたりされているので、日本の未来を想って、日本の自然や子供のために尽力している共通点がある。"We have to be gardeners"。感覚は違いを発見するもの。意識は同じを見つけるもの。どちらに傾きすぎても生きづらいけれど、感覚の世界の奥深さを忘れては人は生きられないのだよという大切なメッセージ。広い土地欲しい。
読了日:09月03日 著者:養老孟司,C.W.ニコル

注:
 は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。 Posted by nekoneko at 10:52│Comments(0)
│読書