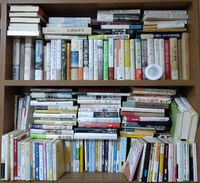2023年05月02日
2023年4月の記録
10年来積読だったソローの「森の生活」読破を諦めた。
岩波文庫で字が小さいから…と電子書籍で買い直しもしたが、だめ。
有名な本は偉いと無条件に信じていた頃に勢いで読むのが正解だったか。
<今月のデータ>
購入11冊、購入費用13,832円。
読了12冊。
積読本330冊(うちKindle本158冊、Honto本3冊)。

 暗がり礼賛 明かりと電気の歴史と地球温暖化の感想
暗がり礼賛 明かりと電気の歴史と地球温暖化の感想
読む途中で「木綿リサイクル」の著者と気づいた。道理で、集めた情報の切り貼りである。著者ご本人は何の専門家でもない。ただ、火の発見から始まるエネルギーのエントロピー増大を現代の電力過剰消費につなげるところは上手い。この流れのいったいどこに人類が踏み止まれるポイントがあっただろうか。昔から学びつつ新しい暮らし方を生み出すことは、理性で考えれば可能だし、個人レベルではあり得る。しかし経済産業省も電力会社も、電力消費量を減らす方向性には全力で抵抗するだろう。今までもこれからも。私たちは、もう止まれない。
読了日:04月29日 著者:前田啓一
 雑草のくらし (福音館の科学シリーズ)の感想
雑草のくらし (福音館の科学シリーズ)の感想
今、ちょうど道端のスイバが色づいている。空き地に茂る草。まったく珍しくもない。なのに、なんて未知の世界なんだろう。それぞれが持てる武器を使って、しばしの栄華を極める。でもそれは毎年は続かなくって、次々と入れ替わっていくものだなんて、気づきもしなかった。ただし、人間が刈ったり抜いたり手を加えれば話は別で、たいてい毎年同じようなものが生えているように記憶している。何もしなければ、空き地は草むらから草藪へと変貌していく。地下の根っこの力は恐ろしいほどだ。地面は、人間がちょっとこま間借りしているようなものだなあ。
読了日:04月29日 著者:甲斐 信枝
 土を喰う日々: わが精進十二ヵ月 (新潮文庫)の感想
土を喰う日々: わが精進十二ヵ月 (新潮文庫)の感想
時短やタイパがもてはやされる時代ゆえに、氏のエッセイはより沁みる。丁寧な料理を、すなわち手間がかかることと認識するべきではない。その食材と正面から向き合うことで旬を捉え、滋味を味わい、味覚と記憶の繋がりに気づくことができる。『旬を喰うこととはつまり土を喰うこと』。その豊かさを我がものにしたいと願う。老人は季節の煮物を尊ぶとある。自分にあと何度季節が巡ってくるかに思いが至るとき、ようやくその時にしかできない作業や食事を愛おしく思えるのだろう。毎年読んでみたいような、そしたら少しはこの境地に近づけるだろうか。
こんにゃくは指でちぎる。豆腐はにぎりつぶす。味がしみやすいと同時に、その感触もまた食事の一部なんだなあと思う。そして自然と食事もつながっていて、山椒、 地梨子にスグリと、身近にないことが悔しく、きっと庭に植えようなど決め込んでみる。持てる時間が限られるなかで、他になにができるだろう。
読了日:04月27日 著者:水上 勉
 小説 不如帰 の感想
小説 不如帰 の感想
明治31年より「国民新聞」で連載の、文語体で書かれた小説。連続ドラマを観ているように面白かった。文語体ゆえに文を咀嚼しないと読めないのだが、慣れると美しい抑揚や流れに身を委ねるのが心地よい。かといって情景や心の機微を丁寧に味わっていると、これまた流れるように挟まれる皮肉や揶揄に吹き出してしまう。著者も楽しんで書いたと想像される。『この愛をば何人もつんざくあたわじ』。知人から耳にした実話を基にしたため、結末は最初から決まっていたようだ。当時の女性が置かれた立場もさることながら、浪子の悲運に涙が止まらない。
時は明治末期、日清戦争の前後。華族は資産や身分を保証された一方、士官として従軍もした。戦闘を野球のプレーに比べたり、戦艦の寄港地付で手紙や荷物を送るなど、先の戦争とは違った意味で日本人に戦争が身近だった時代である。徴兵ではない、職業軍人が戦地へ赴くことは任務であり責務であり、愛が危機に瀕しているからといって、征くのをやめて妻の元に戻るなどという感覚は皆無だよなあ。そして怪我が治りきらずともまた乗艦するのである。国民新聞が官僚や軍人寄りの立ち位置だった建前かとも考えたが、これは私のほうが平和ボケなのだろう。
読了日:04月26日 著者:徳冨 蘆花
 自然農・栽培の手引きの感想
自然農・栽培の手引きの感想
福岡正信翁の「何もしない農法」は必要十分以外を何もしないの意である。この本はその流れを汲む考え方と作業の実際を、優しい挿画も用いて細かく説明している。耕さない。できる限り土を動かさない。収穫後の作物の葉や茎も草も根から抜かない。刈り取り、土の上へ敷く。土に戻す。つまり土を裸にしないことで施肥や灌水の必要がなくなり、しかし土はどんどん豊かになっていくという。自然農を学び、実践する著者が、土や作物が変わっていった実感と感動を率直に綴っている。その体感が確信となって自然農への信頼が溢れている。まず大豆と落花生。
読了日:04月20日 著者:鏡山悦子
 台湾海峡一九四九の感想
台湾海峡一九四九の感想
満州事変勃発が1931年。侵略国日本が敗戦と共に退き、その後中国国内では国共内戦が起きた。隣人同士で殺し合いを続け、最終的に追い詰められた国民党が台湾へ渡ったのが1949年だった。膨大な資料や証言によって、著者は一人ひとりにとっての戦争を記録する。『人の頭蓋骨がどんな脆いか、どれくらいの大きさか、あなたは知らない』。それはアレクシェーヴィチの著作を読む感触に似ていた。しかしこちらの事実は、少なくとも半分がたは日本人の我が事のはずだ。彼らが何十年も身の内に留めて耐えた言葉を、受け取る義務があると私は思う。
ロシアの戦場で五百万人のドイツ兵が死に、捕虜収容所で百万人のドイツ兵が虐待を受けて死んだ。『ドイツ人が全世界に大きな災難をもたらしたことを知っていて、なお虐待を受けた百万人のドイツ人のために不平を訴える権利がある?』とドイツ人の若者が言う。この構図は日本にも当てはまる。日本人はアジア諸国や連合国軍の人々にどれほどの非道をしでかしたか知っているだろうか? 今の日本に生きていて、耳に入るのは原爆の悲劇であり、せいぜい大陸や南方で被った困苦である。被害のみを声高に語るのは片手落ちだと終戦の季節の来るたび思う。
日本陸軍は占領支配した朝鮮、中国、台湾の若者を募り、日本兵として南方へ送った。しかし日本出身の兵士と同等には扱わず、虐待し、現地民や連合国軍兵士の虐殺を強いた。敗戦後、上長である日本兵たちは生きろと彼らに言い置いて自決し、また処刑された。同じく日本軍の一兵卒であった私たちの祖父らは帰還し、戦地でどのような行為をしたかを妻子に語らなかった。今は日本を好意的に見てくれる人も多い。だからといって、祖父らの大陸での所業を無かったことにはしてはならない。その折り合いは私の中でつかない。つけずに、いつまでも抱く。
読了日:04月18日 著者:龍 應台
 その可能性はすでに考えた (講談社文庫)の感想
その可能性はすでに考えた (講談社文庫)の感想
『その可能性はすでに考えた。』は探偵の決め台詞である。全ての可能性を潰せばそれは「不可能」と呼べるのか。可能性が無限大であれば証明そのものが不可能だ。さらにひとつの可能性/不可能性が他の可能性を潰す自家撞着に陥る場合は深掘りするほど増える。底なしの論理遊び。しっかしまあ、ひとつの不可能事件の真相を究明するのに、ぎゅうぎゅうに要素を詰め込んだものだ。中国の四字熟語、言い廻し、拷問や宗教の蘊蓄。即アニメ化できそうなキャラ造形。国際色豊かなのも、百合も、きっと後々に勃発する何かの伏線なのだろう。気にはなる。
読了日:04月16日 著者:井上 真偽
 白昼夢の森の少女 (角川ホラー文庫)の感想
白昼夢の森の少女 (角川ホラー文庫)の感想
どれも面白い。するりと入り込む異界。『路地裏に人形を抱いた女がいた。』なんて書き出されるともうぞくぞくする。ホラーとは違う、ファンタジーでもない、恒川ワールドは年を経て様々な要素を加えてもぶれていない。こう言っては申し訳ないけれど、テーマに沿って編んだ短編集よりも、先入観なしに読めるばらばらなもののほうが、長さも趣向も展開も結末も見当がつかなくて、つまりまとまりなど考えすぎずに身を委ねられるので楽しい。「タイプライターズ」でテレビに初出演された恒川さんはとてもキュートでした。全部読み返したくなった。
読了日:04月15日 著者:恒川 光太郎
 わたしは英国王に給仕した (河出文庫)の感想
わたしは英国王に給仕した (河出文庫)の感想
あるチェコ人給仕の一生。彼の人生では次々と『信じられないことが現実にな』った。このしっちゃかめっちゃかがチェコの常識に照らしてどうかが私には判断がつかないことと、第二次世界大戦下で母国を占領したドイツ人を、抵抗せず受け入れる者の視点で描写していることを面白く感じた。そしてこれらが次元の異なる理不尽である点も。稼いだ紙幣を部屋中に敷き詰めて愛でる青年期から、巨万の富を得、失い、人里離れた荒野の肉体労働と孤独に身を埋める晩年へ。ドタバタから静寂へ。ズデニェクの存在によって対照的に浮かび上がる生き方もまた深い。
読了日:04月10日 著者:ボフミル フラバル
 山崎実業アイデアBOOKの感想
山崎実業アイデアBOOKの感想
好き。しゅっとしているところと、プラスチックでないところ、仕組みがシンプルであるところ、マグネット式やフック式で相手側に加工を要しないところ。今やアイテム数が増えすぎて、ネット上でラインナップが把握できないまでになっているので本刊行は嬉しい。以前から不便に思っていたあたりの解決法に留まらず、次々と繰り出されるアイデアに、ついそのアイテムを使うために自宅を改造したくなってくるという逆転現象が起きるのは、山崎実業ファンのあるある。待て!落ち着け! ここはという箇所から、ひとつずつ取り入れていこうではないか。
読了日:04月09日 著者:
 自然農法 わら一本の革命の感想
自然農法 わら一本の革命の感想
自然農法の祖、バイブルと目される本である。著者が編み出した肥料も農薬も耕うん機も使わない「何もしない農法」は人間の究極の知恵、ではなく、人間は絶対に自然には勝てないことの証と言いきる。それはもはや宗教じみて、だからこそ強い。著者の農法は欧米の有機農業にも影響を与えたと言われるが、それが単に方法論で留まるなら、自分の自然農法とは非なるものと切り捨てる。『仏教でいう大乗的な自然農法と、便宜的な小乗的な自然農法』との比喩は言い得て妙だ。わかりやすい。『人間は自然を壊せても、自然をつくることはできない』。
消費者の『少しでも外観のいいもの、きれいなもの、大きなものを買おうという、ほんのわずかの気持ちが、百姓をここまで追いこみ、苦しめている』。スーパーの売り場で、私だって選ぶ。同じ価格でも形のより良い玉ねぎを消費者が選べば、スーパーは形の悪い玉ねぎを事前に弾くだろう。しなびた小松菜を敬遠すれば、"長持ちさせることができる"パッケージを開発し、それはコスト増となる。過度な選別や無駄な品種改良、ひいては自然なものや適正な価格を外れていってしまう現象は私たちが招き、結果的に農家を苦しめていると鮮やかに糾弾する。
読了日:04月08日 著者:福岡 正信
 安曇野の白い庭 (新潮文庫)の感想
安曇野の白い庭 (新潮文庫)の感想
若い頃に読んだ氏の「白い庭」の経緯を確かめたかった。しかしやはり氏の傲慢さと他者蔑視に、嫌悪感を持て余す。350坪の土地に、俺は女や女みたいに軟弱な男にはできない仕事をやり上げたのだと自画自賛して憚らない。庭とは思いつきを手あたり次第に植えては挽き倒し植え直しを繰り返す自己満足である。自慢げに花の咲き誇る庭を眺めやるカラー写真。力と意志で現実を捻じ曲げられると信じている庭師の人間性がどうであれ、木は枝を高く伸ばし花は咲き誇る。それは逆に自然の持つ健やかさを、そして人間の小ささを証明しているように見えた。
読了日:04月01日 著者:丸山 健二
注: は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。
岩波文庫で字が小さいから…と電子書籍で買い直しもしたが、だめ。
有名な本は偉いと無条件に信じていた頃に勢いで読むのが正解だったか。
<今月のデータ>
購入11冊、購入費用13,832円。
読了12冊。
積読本330冊(うちKindle本158冊、Honto本3冊)。

 暗がり礼賛 明かりと電気の歴史と地球温暖化の感想
暗がり礼賛 明かりと電気の歴史と地球温暖化の感想読む途中で「木綿リサイクル」の著者と気づいた。道理で、集めた情報の切り貼りである。著者ご本人は何の専門家でもない。ただ、火の発見から始まるエネルギーのエントロピー増大を現代の電力過剰消費につなげるところは上手い。この流れのいったいどこに人類が踏み止まれるポイントがあっただろうか。昔から学びつつ新しい暮らし方を生み出すことは、理性で考えれば可能だし、個人レベルではあり得る。しかし経済産業省も電力会社も、電力消費量を減らす方向性には全力で抵抗するだろう。今までもこれからも。私たちは、もう止まれない。
読了日:04月29日 著者:前田啓一
 雑草のくらし (福音館の科学シリーズ)の感想
雑草のくらし (福音館の科学シリーズ)の感想今、ちょうど道端のスイバが色づいている。空き地に茂る草。まったく珍しくもない。なのに、なんて未知の世界なんだろう。それぞれが持てる武器を使って、しばしの栄華を極める。でもそれは毎年は続かなくって、次々と入れ替わっていくものだなんて、気づきもしなかった。ただし、人間が刈ったり抜いたり手を加えれば話は別で、たいてい毎年同じようなものが生えているように記憶している。何もしなければ、空き地は草むらから草藪へと変貌していく。地下の根っこの力は恐ろしいほどだ。地面は、人間がちょっとこま間借りしているようなものだなあ。
読了日:04月29日 著者:甲斐 信枝
 土を喰う日々: わが精進十二ヵ月 (新潮文庫)の感想
土を喰う日々: わが精進十二ヵ月 (新潮文庫)の感想時短やタイパがもてはやされる時代ゆえに、氏のエッセイはより沁みる。丁寧な料理を、すなわち手間がかかることと認識するべきではない。その食材と正面から向き合うことで旬を捉え、滋味を味わい、味覚と記憶の繋がりに気づくことができる。『旬を喰うこととはつまり土を喰うこと』。その豊かさを我がものにしたいと願う。老人は季節の煮物を尊ぶとある。自分にあと何度季節が巡ってくるかに思いが至るとき、ようやくその時にしかできない作業や食事を愛おしく思えるのだろう。毎年読んでみたいような、そしたら少しはこの境地に近づけるだろうか。
こんにゃくは指でちぎる。豆腐はにぎりつぶす。味がしみやすいと同時に、その感触もまた食事の一部なんだなあと思う。そして自然と食事もつながっていて、山椒、 地梨子にスグリと、身近にないことが悔しく、きっと庭に植えようなど決め込んでみる。持てる時間が限られるなかで、他になにができるだろう。
読了日:04月27日 著者:水上 勉

 小説 不如帰 の感想
小説 不如帰 の感想明治31年より「国民新聞」で連載の、文語体で書かれた小説。連続ドラマを観ているように面白かった。文語体ゆえに文を咀嚼しないと読めないのだが、慣れると美しい抑揚や流れに身を委ねるのが心地よい。かといって情景や心の機微を丁寧に味わっていると、これまた流れるように挟まれる皮肉や揶揄に吹き出してしまう。著者も楽しんで書いたと想像される。『この愛をば何人もつんざくあたわじ』。知人から耳にした実話を基にしたため、結末は最初から決まっていたようだ。当時の女性が置かれた立場もさることながら、浪子の悲運に涙が止まらない。
時は明治末期、日清戦争の前後。華族は資産や身分を保証された一方、士官として従軍もした。戦闘を野球のプレーに比べたり、戦艦の寄港地付で手紙や荷物を送るなど、先の戦争とは違った意味で日本人に戦争が身近だった時代である。徴兵ではない、職業軍人が戦地へ赴くことは任務であり責務であり、愛が危機に瀕しているからといって、征くのをやめて妻の元に戻るなどという感覚は皆無だよなあ。そして怪我が治りきらずともまた乗艦するのである。国民新聞が官僚や軍人寄りの立ち位置だった建前かとも考えたが、これは私のほうが平和ボケなのだろう。
読了日:04月26日 著者:徳冨 蘆花

 自然農・栽培の手引きの感想
自然農・栽培の手引きの感想福岡正信翁の「何もしない農法」は必要十分以外を何もしないの意である。この本はその流れを汲む考え方と作業の実際を、優しい挿画も用いて細かく説明している。耕さない。できる限り土を動かさない。収穫後の作物の葉や茎も草も根から抜かない。刈り取り、土の上へ敷く。土に戻す。つまり土を裸にしないことで施肥や灌水の必要がなくなり、しかし土はどんどん豊かになっていくという。自然農を学び、実践する著者が、土や作物が変わっていった実感と感動を率直に綴っている。その体感が確信となって自然農への信頼が溢れている。まず大豆と落花生。
読了日:04月20日 著者:鏡山悦子
 台湾海峡一九四九の感想
台湾海峡一九四九の感想満州事変勃発が1931年。侵略国日本が敗戦と共に退き、その後中国国内では国共内戦が起きた。隣人同士で殺し合いを続け、最終的に追い詰められた国民党が台湾へ渡ったのが1949年だった。膨大な資料や証言によって、著者は一人ひとりにとっての戦争を記録する。『人の頭蓋骨がどんな脆いか、どれくらいの大きさか、あなたは知らない』。それはアレクシェーヴィチの著作を読む感触に似ていた。しかしこちらの事実は、少なくとも半分がたは日本人の我が事のはずだ。彼らが何十年も身の内に留めて耐えた言葉を、受け取る義務があると私は思う。
ロシアの戦場で五百万人のドイツ兵が死に、捕虜収容所で百万人のドイツ兵が虐待を受けて死んだ。『ドイツ人が全世界に大きな災難をもたらしたことを知っていて、なお虐待を受けた百万人のドイツ人のために不平を訴える権利がある?』とドイツ人の若者が言う。この構図は日本にも当てはまる。日本人はアジア諸国や連合国軍の人々にどれほどの非道をしでかしたか知っているだろうか? 今の日本に生きていて、耳に入るのは原爆の悲劇であり、せいぜい大陸や南方で被った困苦である。被害のみを声高に語るのは片手落ちだと終戦の季節の来るたび思う。
日本陸軍は占領支配した朝鮮、中国、台湾の若者を募り、日本兵として南方へ送った。しかし日本出身の兵士と同等には扱わず、虐待し、現地民や連合国軍兵士の虐殺を強いた。敗戦後、上長である日本兵たちは生きろと彼らに言い置いて自決し、また処刑された。同じく日本軍の一兵卒であった私たちの祖父らは帰還し、戦地でどのような行為をしたかを妻子に語らなかった。今は日本を好意的に見てくれる人も多い。だからといって、祖父らの大陸での所業を無かったことにはしてはならない。その折り合いは私の中でつかない。つけずに、いつまでも抱く。
読了日:04月18日 著者:龍 應台
 その可能性はすでに考えた (講談社文庫)の感想
その可能性はすでに考えた (講談社文庫)の感想『その可能性はすでに考えた。』は探偵の決め台詞である。全ての可能性を潰せばそれは「不可能」と呼べるのか。可能性が無限大であれば証明そのものが不可能だ。さらにひとつの可能性/不可能性が他の可能性を潰す自家撞着に陥る場合は深掘りするほど増える。底なしの論理遊び。しっかしまあ、ひとつの不可能事件の真相を究明するのに、ぎゅうぎゅうに要素を詰め込んだものだ。中国の四字熟語、言い廻し、拷問や宗教の蘊蓄。即アニメ化できそうなキャラ造形。国際色豊かなのも、百合も、きっと後々に勃発する何かの伏線なのだろう。気にはなる。
読了日:04月16日 著者:井上 真偽

 白昼夢の森の少女 (角川ホラー文庫)の感想
白昼夢の森の少女 (角川ホラー文庫)の感想どれも面白い。するりと入り込む異界。『路地裏に人形を抱いた女がいた。』なんて書き出されるともうぞくぞくする。ホラーとは違う、ファンタジーでもない、恒川ワールドは年を経て様々な要素を加えてもぶれていない。こう言っては申し訳ないけれど、テーマに沿って編んだ短編集よりも、先入観なしに読めるばらばらなもののほうが、長さも趣向も展開も結末も見当がつかなくて、つまりまとまりなど考えすぎずに身を委ねられるので楽しい。「タイプライターズ」でテレビに初出演された恒川さんはとてもキュートでした。全部読み返したくなった。
読了日:04月15日 著者:恒川 光太郎

 わたしは英国王に給仕した (河出文庫)の感想
わたしは英国王に給仕した (河出文庫)の感想あるチェコ人給仕の一生。彼の人生では次々と『信じられないことが現実にな』った。このしっちゃかめっちゃかがチェコの常識に照らしてどうかが私には判断がつかないことと、第二次世界大戦下で母国を占領したドイツ人を、抵抗せず受け入れる者の視点で描写していることを面白く感じた。そしてこれらが次元の異なる理不尽である点も。稼いだ紙幣を部屋中に敷き詰めて愛でる青年期から、巨万の富を得、失い、人里離れた荒野の肉体労働と孤独に身を埋める晩年へ。ドタバタから静寂へ。ズデニェクの存在によって対照的に浮かび上がる生き方もまた深い。
読了日:04月10日 著者:ボフミル フラバル

 山崎実業アイデアBOOKの感想
山崎実業アイデアBOOKの感想好き。しゅっとしているところと、プラスチックでないところ、仕組みがシンプルであるところ、マグネット式やフック式で相手側に加工を要しないところ。今やアイテム数が増えすぎて、ネット上でラインナップが把握できないまでになっているので本刊行は嬉しい。以前から不便に思っていたあたりの解決法に留まらず、次々と繰り出されるアイデアに、ついそのアイテムを使うために自宅を改造したくなってくるという逆転現象が起きるのは、山崎実業ファンのあるある。待て!落ち着け! ここはという箇所から、ひとつずつ取り入れていこうではないか。
読了日:04月09日 著者:
 自然農法 わら一本の革命の感想
自然農法 わら一本の革命の感想自然農法の祖、バイブルと目される本である。著者が編み出した肥料も農薬も耕うん機も使わない「何もしない農法」は人間の究極の知恵、ではなく、人間は絶対に自然には勝てないことの証と言いきる。それはもはや宗教じみて、だからこそ強い。著者の農法は欧米の有機農業にも影響を与えたと言われるが、それが単に方法論で留まるなら、自分の自然農法とは非なるものと切り捨てる。『仏教でいう大乗的な自然農法と、便宜的な小乗的な自然農法』との比喩は言い得て妙だ。わかりやすい。『人間は自然を壊せても、自然をつくることはできない』。
消費者の『少しでも外観のいいもの、きれいなもの、大きなものを買おうという、ほんのわずかの気持ちが、百姓をここまで追いこみ、苦しめている』。スーパーの売り場で、私だって選ぶ。同じ価格でも形のより良い玉ねぎを消費者が選べば、スーパーは形の悪い玉ねぎを事前に弾くだろう。しなびた小松菜を敬遠すれば、"長持ちさせることができる"パッケージを開発し、それはコスト増となる。過度な選別や無駄な品種改良、ひいては自然なものや適正な価格を外れていってしまう現象は私たちが招き、結果的に農家を苦しめていると鮮やかに糾弾する。
読了日:04月08日 著者:福岡 正信
 安曇野の白い庭 (新潮文庫)の感想
安曇野の白い庭 (新潮文庫)の感想若い頃に読んだ氏の「白い庭」の経緯を確かめたかった。しかしやはり氏の傲慢さと他者蔑視に、嫌悪感を持て余す。350坪の土地に、俺は女や女みたいに軟弱な男にはできない仕事をやり上げたのだと自画自賛して憚らない。庭とは思いつきを手あたり次第に植えては挽き倒し植え直しを繰り返す自己満足である。自慢げに花の咲き誇る庭を眺めやるカラー写真。力と意志で現実を捻じ曲げられると信じている庭師の人間性がどうであれ、木は枝を高く伸ばし花は咲き誇る。それは逆に自然の持つ健やかさを、そして人間の小ささを証明しているように見えた。
読了日:04月01日 著者:丸山 健二
注:
 は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。 Posted by nekoneko at 13:20│Comments(0)
│読書