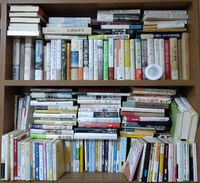2024年06月01日
2024年5月の記録
自分はなにか大いなる存在によって生かされた。
より正確に表現しようとするなら生き延びさせられた、
と感じる出来事があった。
激しい自己嫌悪と、非現実感と、感謝と。
ようやく前向きになってきたのは、忘却のおかげもあるだろうけれど。
生きているうちに何事か成す。
生き延びたのはこのためだったと思えるように、夢見つつ深く植える。
<今月のデータ>
購入20冊、購入費用17,515円。
読了12冊。
積読本329冊(うちKindle本162冊)。

 デオナール アジア最大最古のごみ山――くず拾いたちの愛と哀しみの物語の感想
デオナール アジア最大最古のごみ山――くず拾いたちの愛と哀しみの物語の感想
東京23区と同じ面積に2000万人がひしめく"夢の街"ムンバイ、その裏側。ムンバイの住民が出すごみはその南東、デオナールの集積場に運ばれる。際限なく増え続けるごみの巨大な山の、麓に住む貧しい人々は有価物を拾って現金収入を得る。定職が無く教育は受けられず貧困から逃れられず、危険物や有毒ガスで身体を損ない、心の健康も損なうかと思いきや、家族への愛も恋心もお洒落心も溢れていて、胸を衝かれる。気の毒に思う。これで人生の収支は釣り合っているというのか。産まれた子に「あなたのものはなにも無いのよ」と告げる胸中ぞ。
ちなみに東京23区の住民は980万人。ムンバイは過密だ。なのに裕福な家庭でもごみ箱すらなく、分別率は10%以下。分別し、有価物を再生に回す役割を担っているのはデオナールの民だった。Deonar Dumping Ground。ごみの山、コンクリートの壁、路地に積まれた拾い集めたと思しき物、それらから生きる糧を得ている人々の住まいは、ストリートビューで見ることができる。汚職、詐欺、手抜き、行き違いなどによって、行政の施策が進まない。ごみ搬入禁止令も、巨大な廃棄物発電所をつくる計画も混沌のうちに頓挫している。
読了日:05月30日 著者:ソーミャ ロイ
 海底大陸の感想
海底大陸の感想
レトロ図書館と銘打った装丁に惹かれて。少年向けSF、連載されたのは昭和14年と太平洋戦争直前だ。ニューヨークからフランスへ向かうイギリスの豪華客船に、日本人の少年がボーイとして勤務している至って平和なシーンから始まる。そこに『水母に目玉をつけたような』海底人との接触が起きるのだが、生き延びるためとはいえ、目玉の出たクラゲには噛みつきたくない! 『やはり貴下は日本人ですなあ、感心いたしました』というくすぐりとか、日本人が東洋王道主義や正義を主張して正しい側で在ろうとする辺り、時代の空気ではあっただろう。
読了日:05月21日 著者:海野 十三
![季刊地域57号(2024春) [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51KoPQakULL._SL120_.jpg) 季刊地域57号(2024春) [雑誌]の感想
季刊地域57号(2024春) [雑誌]の感想
日本農業新聞を止め、こちらを定期購読することにした。特集は「農地を守る」。注目記事は農地取得の話。農地を取得する必要条件の一つ、経営しなければならない面積の下限が去年廃止された。他の条件はあるものの、大きな変化ではある。あと、放棄農地の活用例。少ない労力で現代ならではの需要に応えるアイデアが興味深い。つまり、農業をちょっとだけ始めてみたい人がやりやすくなったのだ。農地を守るのは行政ではなく民の力。『年をとっても、規模が小さくても、誰もが農業を続けられるようにすること。農家を増やし農地を分かち合うこと』。
経済界が旗を振る法人化、集約化は地域の力を弱めるとも指摘されている。
読了日:05月19日 著者:
 豊饒の海 第一巻 春の雪 (新潮文庫)の感想
豊饒の海 第一巻 春の雪 (新潮文庫)の感想
三島は、と大上段から評せるほど読んでいる訳ではないのだけれど、彼の美へのこだわりを思い返すに、清顕という人格を愛してはいないだろう。どちらかと言えば飯沼や本多の側に自分を映しているように感じる。飯沼や本多に清顕を糾弾させながら、執拗に清顕の内在論理を解き、色気を描写して、それをまた飯沼や本田に目を奪わさせる、その捻じれ具合がなんとも湿っぽい。ゆえに末期は呆気なかった。対極は聡子。貴族階級の生温い決まり事に沿って優雅に生きているとみせて、究極の気儘と決断を一気に貫く潔さ。最初から破滅を肯じて、見事だった。
読了日:05月17日 著者:三島 由紀夫
 不合理だからうまくいく: 行動経済学で「人を動かす」 (ハヤカワ文庫 NF 405)の感想
不合理だからうまくいく: 行動経済学で「人を動かす」 (ハヤカワ文庫 NF 405)の感想
人間の知性は進化すると私は盲信してしまうが、理性は進化しないと知っている。今回も人生を左右する原理に迫る研究結果が楽しすぎる。人生は選択の連続だ。ある選択の一刹那、相手に苛立っていると、その人にもやりとりの背景となる企業にも公正な行動を取らない傾向が強くなる。一時的な感情が、感情と関係ないはずの決定をも左右する。そしてその決定は、その後似た案件でも似た決定をする基軸となる可能性が高いのだ。つまりパターン化する。となると、ひとつの選択はその人の未来をいかようにも変える起点になる。一瞬の選択で、終生ですよ。
親子喧嘩や夫婦喧嘩のような、同じ相手とのやり取りはパターンが固着しやすい。余計な感情が混じっていないか一瞬内観すること、自分が感情的だと自覚したら決定を先送りすることは、いわゆる「機嫌よく生きたほうがうまくいく」を証明していることになる。相手に報復する行動は、喜びと同じ脳部位、線条体を活性化することがわかっている。それは生物として、元始的なアクションということになる。社会的生物である人間にとって、お互いに信頼することは基本的要素である。そうなると謝罪、共感を表す、他者をなだめる行為の重要性にも理解が及ぶ。
読了日:05月16日 著者:ダン・アリエリー
 国民の違和感は9割正しい (PHP新書)の感想
国民の違和感は9割正しい (PHP新書)の感想
違った角度から物事を見る目は大事だ。堤さんの場合、国際NGOや米国野村證券勤務で培ったアンテナによる国際情勢や政府動向の情報、解釈に三度唸らされる。ガザ沖の天然ガス田、新NISA推進に食い込むパソナ、農業事業支援もパソナ、SNS検閲。日本だけでなく他の民主主義国の政府も、国民の目に触れないよう推し進めたい思惑や皮算用で国民を誤誘導しようとするものなのだ。監視しよう。抵抗しよう。『〈民は愚かで弱い〉というのは、私たちがそれを受け入れ、自信を失い、無力になることで得をする誰かからの、刷り込みにすぎません』。
『〈政府は決して、リターンのない投資はしない。メディアが創る物語が、外からどう見えようと、金は嘘をつかないからだ〉』。『「なぜ戦争が無くならないか? 学者や新聞記者はあれこれ分析したがるが、目を皿のようにして入り口ばかり見ていても、戦争の裏側などわからないだろう。金の流れと出口を見るんだ、一目瞭然だよ」』。国民の信仰心や道義心すら、真の目的のカモフラージュとして、殴り合いを続けるための燃料として利用される。科学技術は進歩しても、人間自体は古来なんにも変わっていないのだと、いつになれば私は理解するのか。
読了日:05月15日 著者:堤 未果
 犯罪小説集 (角川文庫)の感想
犯罪小説集 (角川文庫)の感想
長編小説のピースになりそうな短編集。作者の長編が概ねそうであるように、心底性根が捻じ曲がった悪人は登場しない。なのにどの短編も明るくは終われず、読み終えて、何が犯罪だったのか、誰が犯罪を犯したのかすら思案してしまうものもある。人の心のちょっとした隙間。何かが欠落した穴。それらを持たない大人などこの世にいない。そこから道を踏み外すのは数十年生きた人生のほんの一瞬だ。例えば善次郎の真面目な人生の、豪士の気弱な優しさの、どこを「だからはお前は」と責められるだろう。作者の思惑どおりはまってしまった。巧い。
読了日:05月12日 著者:吉田 修一
 八ヶ岳南麓からの感想
八ヶ岳南麓からの感想
上野さんが50代で建てた山の家「鹿野苑」。上野さんの著書では最も軽いエッセイだ。生活者の気づきに、社会学者のシビアな観察がときどき混じる。マンション暮らしから一軒家への移行にまつわる事々には親近感もあれど、こちらは避暑地、それゆえの興味深い話題も多かった。地域コミュニティのつきあいは「必要ない」の意味。家と家の距離が密でなく、引退した夫婦者ばかりだから、近所のインフラ維持管理は行政だけに任せるということか。田んぼがなければ井手浚いも必要なく、上水は井戸から、下水は浸透桝から地中へ。協同の必要がないのか。
読了日:05月07日 著者:上野 千鶴子
 カレー移民の謎 日本を制覇する「インネパ」 (集英社新書)の感想
カレー移民の謎 日本を制覇する「インネパ」 (集英社新書)の感想
そうか、ネパールだったのか。日本産のチェーン店ではない、外国人の経営する"インドカレー"の店は地方にも増えた。40年余前、インド人に連れられてきたネパール人のコックたちは独立し、それがコックの技能資格を利用した出稼ぎビジネスモデルとして地方にも広がった。その経緯を知ると、インド宮廷料理(ムグライ)の本質からは離れたかもしれないが、むしろ日本式に適応して今の形があると言っていい。生きるため稼ぐために遠い日本を目指したすべての人に敬意を表して、私は「インネパ」とは呼ばずに、楽しんでいただくことにする。
読了日:05月05日 著者:室橋 裕和
 百姓たちの江戸時代 (ちくまプリマー新書 110)の感想
百姓たちの江戸時代 (ちくまプリマー新書 110)の感想
江戸末期の百姓の例を挙げている。長野の坂本家は百姓でありながら地主、よろず屋、宿屋、金貸しも営む。金銭の出入りは多く、道具から装飾品、嗜好品まで購入する生活様式は現代に近く感じる。千葉の前嶋家は稲作、多種の畑作、山仕事と地主。家族全員が手に職を持って自給と販売に携わるのが基本形で、労働だけを売るのは避けたとのこと。坂本家でも同じだっただろうか。村の管理下にある共有インフラの整備は村人で協力するものだったが、入会地は徐々に分割、私有化されていたようだ。所有の概念が今と違って興味深い。そこをもう少し知りたい。
読了日:05月02日 著者:渡辺 尚志
 虫といっしょに庭づくり―オーガニック・ガーデン・ハンドブックの感想
虫といっしょに庭づくり―オーガニック・ガーデン・ハンドブックの感想
新しい庭に虫たちがやってきた。ひたすら観察しているが、それらをどう遇してよいのか皆目わからないので助けを求める。特にイモムシ、ケムシ。そうですか、テデトールですか…。食害が嫌なら必ず自らとどめを刺せと曳地さんは言う。それは責任だと。オーガニックとは農薬・化学肥料を使わないこと。努めて木を健やかに保ち、多種多様な生きものと共存すること。蟻、蜘蛛にはいてもらう。さらにテントウムシ、鳥に来てもらう。この方針で行けるところまで行こう。冬にはバードフィーダーを置きたい。
読了日:05月02日 著者:ひきちガーデンサービス
注: は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。
より正確に表現しようとするなら生き延びさせられた、
と感じる出来事があった。
激しい自己嫌悪と、非現実感と、感謝と。
ようやく前向きになってきたのは、忘却のおかげもあるだろうけれど。
生きているうちに何事か成す。
生き延びたのはこのためだったと思えるように、夢見つつ深く植える。
<今月のデータ>
購入20冊、購入費用17,515円。
読了12冊。
積読本329冊(うちKindle本162冊)。

 デオナール アジア最大最古のごみ山――くず拾いたちの愛と哀しみの物語の感想
デオナール アジア最大最古のごみ山――くず拾いたちの愛と哀しみの物語の感想東京23区と同じ面積に2000万人がひしめく"夢の街"ムンバイ、その裏側。ムンバイの住民が出すごみはその南東、デオナールの集積場に運ばれる。際限なく増え続けるごみの巨大な山の、麓に住む貧しい人々は有価物を拾って現金収入を得る。定職が無く教育は受けられず貧困から逃れられず、危険物や有毒ガスで身体を損ない、心の健康も損なうかと思いきや、家族への愛も恋心もお洒落心も溢れていて、胸を衝かれる。気の毒に思う。これで人生の収支は釣り合っているというのか。産まれた子に「あなたのものはなにも無いのよ」と告げる胸中ぞ。
ちなみに東京23区の住民は980万人。ムンバイは過密だ。なのに裕福な家庭でもごみ箱すらなく、分別率は10%以下。分別し、有価物を再生に回す役割を担っているのはデオナールの民だった。Deonar Dumping Ground。ごみの山、コンクリートの壁、路地に積まれた拾い集めたと思しき物、それらから生きる糧を得ている人々の住まいは、ストリートビューで見ることができる。汚職、詐欺、手抜き、行き違いなどによって、行政の施策が進まない。ごみ搬入禁止令も、巨大な廃棄物発電所をつくる計画も混沌のうちに頓挫している。
読了日:05月30日 著者:ソーミャ ロイ

 海底大陸の感想
海底大陸の感想レトロ図書館と銘打った装丁に惹かれて。少年向けSF、連載されたのは昭和14年と太平洋戦争直前だ。ニューヨークからフランスへ向かうイギリスの豪華客船に、日本人の少年がボーイとして勤務している至って平和なシーンから始まる。そこに『水母に目玉をつけたような』海底人との接触が起きるのだが、生き延びるためとはいえ、目玉の出たクラゲには噛みつきたくない! 『やはり貴下は日本人ですなあ、感心いたしました』というくすぐりとか、日本人が東洋王道主義や正義を主張して正しい側で在ろうとする辺り、時代の空気ではあっただろう。
読了日:05月21日 著者:海野 十三
![季刊地域57号(2024春) [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51KoPQakULL._SL120_.jpg) 季刊地域57号(2024春) [雑誌]の感想
季刊地域57号(2024春) [雑誌]の感想日本農業新聞を止め、こちらを定期購読することにした。特集は「農地を守る」。注目記事は農地取得の話。農地を取得する必要条件の一つ、経営しなければならない面積の下限が去年廃止された。他の条件はあるものの、大きな変化ではある。あと、放棄農地の活用例。少ない労力で現代ならではの需要に応えるアイデアが興味深い。つまり、農業をちょっとだけ始めてみたい人がやりやすくなったのだ。農地を守るのは行政ではなく民の力。『年をとっても、規模が小さくても、誰もが農業を続けられるようにすること。農家を増やし農地を分かち合うこと』。
経済界が旗を振る法人化、集約化は地域の力を弱めるとも指摘されている。
読了日:05月19日 著者:
 豊饒の海 第一巻 春の雪 (新潮文庫)の感想
豊饒の海 第一巻 春の雪 (新潮文庫)の感想三島は、と大上段から評せるほど読んでいる訳ではないのだけれど、彼の美へのこだわりを思い返すに、清顕という人格を愛してはいないだろう。どちらかと言えば飯沼や本多の側に自分を映しているように感じる。飯沼や本多に清顕を糾弾させながら、執拗に清顕の内在論理を解き、色気を描写して、それをまた飯沼や本田に目を奪わさせる、その捻じれ具合がなんとも湿っぽい。ゆえに末期は呆気なかった。対極は聡子。貴族階級の生温い決まり事に沿って優雅に生きているとみせて、究極の気儘と決断を一気に貫く潔さ。最初から破滅を肯じて、見事だった。
読了日:05月17日 著者:三島 由紀夫
 不合理だからうまくいく: 行動経済学で「人を動かす」 (ハヤカワ文庫 NF 405)の感想
不合理だからうまくいく: 行動経済学で「人を動かす」 (ハヤカワ文庫 NF 405)の感想人間の知性は進化すると私は盲信してしまうが、理性は進化しないと知っている。今回も人生を左右する原理に迫る研究結果が楽しすぎる。人生は選択の連続だ。ある選択の一刹那、相手に苛立っていると、その人にもやりとりの背景となる企業にも公正な行動を取らない傾向が強くなる。一時的な感情が、感情と関係ないはずの決定をも左右する。そしてその決定は、その後似た案件でも似た決定をする基軸となる可能性が高いのだ。つまりパターン化する。となると、ひとつの選択はその人の未来をいかようにも変える起点になる。一瞬の選択で、終生ですよ。
親子喧嘩や夫婦喧嘩のような、同じ相手とのやり取りはパターンが固着しやすい。余計な感情が混じっていないか一瞬内観すること、自分が感情的だと自覚したら決定を先送りすることは、いわゆる「機嫌よく生きたほうがうまくいく」を証明していることになる。相手に報復する行動は、喜びと同じ脳部位、線条体を活性化することがわかっている。それは生物として、元始的なアクションということになる。社会的生物である人間にとって、お互いに信頼することは基本的要素である。そうなると謝罪、共感を表す、他者をなだめる行為の重要性にも理解が及ぶ。
読了日:05月16日 著者:ダン・アリエリー
 国民の違和感は9割正しい (PHP新書)の感想
国民の違和感は9割正しい (PHP新書)の感想違った角度から物事を見る目は大事だ。堤さんの場合、国際NGOや米国野村證券勤務で培ったアンテナによる国際情勢や政府動向の情報、解釈に三度唸らされる。ガザ沖の天然ガス田、新NISA推進に食い込むパソナ、農業事業支援もパソナ、SNS検閲。日本だけでなく他の民主主義国の政府も、国民の目に触れないよう推し進めたい思惑や皮算用で国民を誤誘導しようとするものなのだ。監視しよう。抵抗しよう。『〈民は愚かで弱い〉というのは、私たちがそれを受け入れ、自信を失い、無力になることで得をする誰かからの、刷り込みにすぎません』。
『〈政府は決して、リターンのない投資はしない。メディアが創る物語が、外からどう見えようと、金は嘘をつかないからだ〉』。『「なぜ戦争が無くならないか? 学者や新聞記者はあれこれ分析したがるが、目を皿のようにして入り口ばかり見ていても、戦争の裏側などわからないだろう。金の流れと出口を見るんだ、一目瞭然だよ」』。国民の信仰心や道義心すら、真の目的のカモフラージュとして、殴り合いを続けるための燃料として利用される。科学技術は進歩しても、人間自体は古来なんにも変わっていないのだと、いつになれば私は理解するのか。
読了日:05月15日 著者:堤 未果

 犯罪小説集 (角川文庫)の感想
犯罪小説集 (角川文庫)の感想長編小説のピースになりそうな短編集。作者の長編が概ねそうであるように、心底性根が捻じ曲がった悪人は登場しない。なのにどの短編も明るくは終われず、読み終えて、何が犯罪だったのか、誰が犯罪を犯したのかすら思案してしまうものもある。人の心のちょっとした隙間。何かが欠落した穴。それらを持たない大人などこの世にいない。そこから道を踏み外すのは数十年生きた人生のほんの一瞬だ。例えば善次郎の真面目な人生の、豪士の気弱な優しさの、どこを「だからはお前は」と責められるだろう。作者の思惑どおりはまってしまった。巧い。
読了日:05月12日 著者:吉田 修一

 八ヶ岳南麓からの感想
八ヶ岳南麓からの感想上野さんが50代で建てた山の家「鹿野苑」。上野さんの著書では最も軽いエッセイだ。生活者の気づきに、社会学者のシビアな観察がときどき混じる。マンション暮らしから一軒家への移行にまつわる事々には親近感もあれど、こちらは避暑地、それゆえの興味深い話題も多かった。地域コミュニティのつきあいは「必要ない」の意味。家と家の距離が密でなく、引退した夫婦者ばかりだから、近所のインフラ維持管理は行政だけに任せるということか。田んぼがなければ井手浚いも必要なく、上水は井戸から、下水は浸透桝から地中へ。協同の必要がないのか。
読了日:05月07日 著者:上野 千鶴子

 カレー移民の謎 日本を制覇する「インネパ」 (集英社新書)の感想
カレー移民の謎 日本を制覇する「インネパ」 (集英社新書)の感想そうか、ネパールだったのか。日本産のチェーン店ではない、外国人の経営する"インドカレー"の店は地方にも増えた。40年余前、インド人に連れられてきたネパール人のコックたちは独立し、それがコックの技能資格を利用した出稼ぎビジネスモデルとして地方にも広がった。その経緯を知ると、インド宮廷料理(ムグライ)の本質からは離れたかもしれないが、むしろ日本式に適応して今の形があると言っていい。生きるため稼ぐために遠い日本を目指したすべての人に敬意を表して、私は「インネパ」とは呼ばずに、楽しんでいただくことにする。
読了日:05月05日 著者:室橋 裕和

 百姓たちの江戸時代 (ちくまプリマー新書 110)の感想
百姓たちの江戸時代 (ちくまプリマー新書 110)の感想江戸末期の百姓の例を挙げている。長野の坂本家は百姓でありながら地主、よろず屋、宿屋、金貸しも営む。金銭の出入りは多く、道具から装飾品、嗜好品まで購入する生活様式は現代に近く感じる。千葉の前嶋家は稲作、多種の畑作、山仕事と地主。家族全員が手に職を持って自給と販売に携わるのが基本形で、労働だけを売るのは避けたとのこと。坂本家でも同じだっただろうか。村の管理下にある共有インフラの整備は村人で協力するものだったが、入会地は徐々に分割、私有化されていたようだ。所有の概念が今と違って興味深い。そこをもう少し知りたい。
読了日:05月02日 著者:渡辺 尚志

 虫といっしょに庭づくり―オーガニック・ガーデン・ハンドブックの感想
虫といっしょに庭づくり―オーガニック・ガーデン・ハンドブックの感想新しい庭に虫たちがやってきた。ひたすら観察しているが、それらをどう遇してよいのか皆目わからないので助けを求める。特にイモムシ、ケムシ。そうですか、テデトールですか…。食害が嫌なら必ず自らとどめを刺せと曳地さんは言う。それは責任だと。オーガニックとは農薬・化学肥料を使わないこと。努めて木を健やかに保ち、多種多様な生きものと共存すること。蟻、蜘蛛にはいてもらう。さらにテントウムシ、鳥に来てもらう。この方針で行けるところまで行こう。冬にはバードフィーダーを置きたい。
読了日:05月02日 著者:ひきちガーデンサービス
注:
 は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。 Posted by nekoneko at 12:01│Comments(0)
│読書