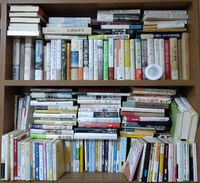2016年02月01日
2015年1月の記録
うむ。読んでいるわりに積読が減らぬ。
つい、細切れの時間で読める、軽い感触のもので日々回転させてしまい、
ずっしりした本がいつまでも残ってしまうのです。
積読本91冊。

2016年1月の読書メーター
読んだ本の数:12冊
 先生、巨大コウモリが廊下を飛んでいます!―鳥取環境大学の森の人間動物行動学の感想
先生、巨大コウモリが廊下を飛んでいます!―鳥取環境大学の森の人間動物行動学の感想
野生生物とのエピソードは文句なしに面白い。観察が深いのだ。しかし、読者への配慮が全く足りない。中途半端な落ちなどいらないから、太字にする文を厳選して、エピソードを最後まで書けと出版社の誰も言わなかったのか。擬人化も、的外れに思えて…。こういう研究者、いるよね。悪い人じゃないんだけど、だいぶ野生生物寄りな。
読了日:1月25日 著者:小林朋道
 お金をちゃんと考えることから逃げまわっていたぼくらへ (PHP文庫)の感想
お金をちゃんと考えることから逃げまわっていたぼくらへ (PHP文庫)の感想
西暦2000年の対談。違和感があるのはほぼ日の規模程度で、お二人は普遍的な人生論を語り合っている。邱氏の逸話はとかく規格外だが、人生にこうあるべき型などない。なのに時代の醸す雰囲気から外れることを恐れ不安がるのは、お金のことに限らず無意味なのだ。私たちは各々のものさしで量る。『林深則鳥棲 水廣則魚游』とは、人にもお金にも言える。人を容れる度量を持てば、人は寄る。金持ちになりたかったら、お金を儲けるより、お金を入れる器を大きくする努力をしたほうがいいのだ。未来を見通すには、過去に固執しすぎないこと。
読了日:1月23日 著者:糸井重里,邱永漢
 山に生きる人びと (河出文庫)の感想
山に生きる人びと (河出文庫)の感想
鳥獣の狩猟、木や植物の採取細工、鉱物の採掘など、訳あってわざわざ人里離れた山の中で暮らしをつないだ人々がいる。著者は訪ね歩き、対話や少ない資料の端々から山に住む人々の生き方を丹念に拾い考察している。同じ日本に生きても、生活の立て方が平地に住む者と違う。定住する暮らしも平地とは違った様子だが、生業に応じて移り歩く暮らしは、日本に欠かせないものながら異質だ。現代もまたそこからの変化の途中であると気づいて震える。文明の発達により山に住む者と平地に住む者の差は狭まり、狭まりきらないまま過疎化し失われかけている。
読了日:1月22日 著者:宮本常一
 リカーシブル (新潮文庫)の感想
リカーシブル (新潮文庫)の感想
自分の子供でもおかしくない年齢の子が主人公の学園ミステリなんて、読むのはもうきついわ。と思っていたが、今ずしりと重い読後感をもて余している。なぜなら、彼女が受ける理不尽は大人が受ける類のものだし、それを彼女は打たれ強く耐えてみせる。この歪みを彼女らにひっ被せたくはなかった。ビターなミステリ。
読了日:1月21日 著者:米澤穂信
 オオカミの護符の感想
オオカミの護符の感想
実家の土蔵に貼られた「オイヌさま」の護符を発端とし、その由来や風習を辿り広げてゆく、パーソナルなルポである。オイヌさまは即ちニホンオオカミであり、護符として配られる土地は関東近辺に限られるようだが、オオカミ信仰自体は日本各地に存在する。ということはオオカミは人を襲うこともあった一方、イノシシやシカから農作物を守ってくれる、日本人にとって畏敬すべき存在だったと考えていい。自然や天候の象徴である「お山」と、山から来る「オイヌさま」を謙虚な気持ちで信仰する暮らしは、厳しいながら、日本人の心を安らかにしただろう。
読了日:1月17日 著者:小倉美惠子
 ネコの看取りガイドの感想
ネコの看取りガイドの感想
愛猫との別れなど想像もしたくないのが心情だが、そういう訳にもいかない。ならば年老いた猫になにをしてやればよいか、どう配慮すれば心安らかに旅立たせることができるか、想像し、備えることは大切だ。老猫がかかりやすい病気や終末期のケアの視点から、今気をつけておくべき体調管理のポイントが書かれている。それなりの年齢に差し掛かった猫がいるなら、定期的に読み返したい良書。知識を得て、猫にとって最良の対処をしてきたと思えるなら、旅立たせた後の後悔も少なくて済むはずだ。猫のクオリティオブライフ。最上のものにしてやりたい。
読了日:1月15日 著者:服部幸
 ダーク・タワー〈2〉運命の三人〈下〉 (新潮文庫)の感想
ダーク・タワー〈2〉運命の三人〈下〉 (新潮文庫)の感想
塔が呼んでいる。この物語がキングを呼び続けたように。彼と行動を共にする者にはいずれ死が訪れるだろう。ローランドのために。そのことを知ってなお、人に愛着し、非道を自責し、恐怖する程度に、ローランドは優しい。人の心を持たないことを恐れ、獣に堕ちた者の払う地獄の対価を恐れることは、概念化された宗教心とは違う、人の心に原始的に湧き起こる衝動なのかもしれない。その証拠に奴らは仲間を悼んだりしない。ディド・ア・チック? ダム・ア・チャム? 奴らはなにを問いかけているのか。その問いに私たちはなにを投影するのか。
読了日:1月14日 著者:スティーヴンキング
 人が育つ仕組みをつくれ!: リーダとして一番に心得ることの感想
人が育つ仕組みをつくれ!: リーダとして一番に心得ることの感想
個人主義では、一人ひとりが自分のことで手いっぱいになれば集団の力は発揮できない。米国方式一辺倒でなく東洋思想も取り混ぜて、日常的、継続的に人が育つような職場環境を意識的につくる大切さを説いている。「明の知」「暗の知」「黙の知」、なかでも「黙の知」の考え方に感銘を受けた。つまり、OJTや講習を通して知識やノウハウを伝えることだけが、知を育む活動ではない。それだけでは人はこちらが思うようには育たない。人を育てようという考え方はいっそ捨てる。社内の空気で人を育てる。うちのような小型企業にはそれが大切のようだ。
読了日:1月14日 著者:常盤文克
 鴻池剛と猫のぽんた ニャアアアン!の感想
鴻池剛と猫のぽんた ニャアアアン!の感想
猫飼いの日常の、どちらかといえば癒しではなく飼い主への試練が描かれていて、素手で受け止める件など、共感で笑いが止まらなくなる。飼い主の性格がずぼらであるほど、アクシデントが頻発することを発見。それを猫は楽しむし、飼い主は弱り切るようだ。なるほどー。
読了日:1月12日 著者:鴻池剛
 しんがり 山一證券最後の12人 (講談社+α文庫)の感想
しんがり 山一證券最後の12人 (講談社+α文庫)の感想
「しんがり」のメンバーは仕組まれ、立場上そうせざるを得なかった者のいる一方、やるかたない思いを果たすために自ら参じた者もいた。彼らの成した調査は賞賛されるべきもので、そこにスポットを当てた試みが良い。大蔵省の思惑はともかく、山一證券の幹部はなにを見ていたのか。「しんがり」たちの腹を据えた姿勢に相対し、取締役たちのなんと暗愚なこと。個人ではなく企業を軸に考える人材のはずなのに、社内の力関係や個人の利害に囚われ、大局を見ず、逃げた。菊野のスタンスが素敵。「わしに言え。なんでも聞いてやるぞ。菊野じゃからな」!
読了日:1月8日 著者:清武英利
 山賊ダイアリー(1) (イブニングKC)の感想
山賊ダイアリー(1) (イブニングKC)の感想
狩猟やその考え方への許容は、当時より増しているのではないか。この漫画が巻を重ねていることがその証拠だ。もう猟師になりたい願望も失せたが、動植物の小ネタが楽しい。1巻は半額セールで手に入れた。続きは迷うな…。独白調なのに丁寧語なのがヘンで微笑ましい。
読了日:1月3日 著者:岡本健太郎
 南総里見八犬伝 (角川ソフィア文庫―ビギナーズ・クラシックス (SP90))の感想
南総里見八犬伝 (角川ソフィア文庫―ビギナーズ・クラシックス (SP90))の感想
南総里見八犬伝はとてつもなく長いのだそうだ。1冊の価値は数十万円相当、一般的な読者は貸本屋から借りて読んだ。アクション、ドラマ、ミステリ、ファンタジー、なんでもありだ。んなアホな、と思いつつ痛快で、当時このような娯楽があったとは、読者はさぞ続きが楽しみだっただろう。当世のベストセラー作家は20年以上かけて物語を完成させた。時代が近いせいか、原文もよみやすい。私も信乃や荘介、毛野に萌えながら、このような物語だったのかと満足した。全編制覇は、遠慮します。
読了日:1月2日 著者:曲亭馬琴,石川博
注: はKindleで読んだ本。
はKindleで読んだ本。
つい、細切れの時間で読める、軽い感触のもので日々回転させてしまい、
ずっしりした本がいつまでも残ってしまうのです。
積読本91冊。

2016年1月の読書メーター
読んだ本の数:12冊
 先生、巨大コウモリが廊下を飛んでいます!―鳥取環境大学の森の人間動物行動学の感想
先生、巨大コウモリが廊下を飛んでいます!―鳥取環境大学の森の人間動物行動学の感想野生生物とのエピソードは文句なしに面白い。観察が深いのだ。しかし、読者への配慮が全く足りない。中途半端な落ちなどいらないから、太字にする文を厳選して、エピソードを最後まで書けと出版社の誰も言わなかったのか。擬人化も、的外れに思えて…。こういう研究者、いるよね。悪い人じゃないんだけど、だいぶ野生生物寄りな。
読了日:1月25日 著者:小林朋道
 お金をちゃんと考えることから逃げまわっていたぼくらへ (PHP文庫)の感想
お金をちゃんと考えることから逃げまわっていたぼくらへ (PHP文庫)の感想西暦2000年の対談。違和感があるのはほぼ日の規模程度で、お二人は普遍的な人生論を語り合っている。邱氏の逸話はとかく規格外だが、人生にこうあるべき型などない。なのに時代の醸す雰囲気から外れることを恐れ不安がるのは、お金のことに限らず無意味なのだ。私たちは各々のものさしで量る。『林深則鳥棲 水廣則魚游』とは、人にもお金にも言える。人を容れる度量を持てば、人は寄る。金持ちになりたかったら、お金を儲けるより、お金を入れる器を大きくする努力をしたほうがいいのだ。未来を見通すには、過去に固執しすぎないこと。
読了日:1月23日 著者:糸井重里,邱永漢

 山に生きる人びと (河出文庫)の感想
山に生きる人びと (河出文庫)の感想鳥獣の狩猟、木や植物の採取細工、鉱物の採掘など、訳あってわざわざ人里離れた山の中で暮らしをつないだ人々がいる。著者は訪ね歩き、対話や少ない資料の端々から山に住む人々の生き方を丹念に拾い考察している。同じ日本に生きても、生活の立て方が平地に住む者と違う。定住する暮らしも平地とは違った様子だが、生業に応じて移り歩く暮らしは、日本に欠かせないものながら異質だ。現代もまたそこからの変化の途中であると気づいて震える。文明の発達により山に住む者と平地に住む者の差は狭まり、狭まりきらないまま過疎化し失われかけている。
読了日:1月22日 著者:宮本常一

 リカーシブル (新潮文庫)の感想
リカーシブル (新潮文庫)の感想自分の子供でもおかしくない年齢の子が主人公の学園ミステリなんて、読むのはもうきついわ。と思っていたが、今ずしりと重い読後感をもて余している。なぜなら、彼女が受ける理不尽は大人が受ける類のものだし、それを彼女は打たれ強く耐えてみせる。この歪みを彼女らにひっ被せたくはなかった。ビターなミステリ。
読了日:1月21日 著者:米澤穂信
 オオカミの護符の感想
オオカミの護符の感想実家の土蔵に貼られた「オイヌさま」の護符を発端とし、その由来や風習を辿り広げてゆく、パーソナルなルポである。オイヌさまは即ちニホンオオカミであり、護符として配られる土地は関東近辺に限られるようだが、オオカミ信仰自体は日本各地に存在する。ということはオオカミは人を襲うこともあった一方、イノシシやシカから農作物を守ってくれる、日本人にとって畏敬すべき存在だったと考えていい。自然や天候の象徴である「お山」と、山から来る「オイヌさま」を謙虚な気持ちで信仰する暮らしは、厳しいながら、日本人の心を安らかにしただろう。
読了日:1月17日 著者:小倉美惠子
 ネコの看取りガイドの感想
ネコの看取りガイドの感想愛猫との別れなど想像もしたくないのが心情だが、そういう訳にもいかない。ならば年老いた猫になにをしてやればよいか、どう配慮すれば心安らかに旅立たせることができるか、想像し、備えることは大切だ。老猫がかかりやすい病気や終末期のケアの視点から、今気をつけておくべき体調管理のポイントが書かれている。それなりの年齢に差し掛かった猫がいるなら、定期的に読み返したい良書。知識を得て、猫にとって最良の対処をしてきたと思えるなら、旅立たせた後の後悔も少なくて済むはずだ。猫のクオリティオブライフ。最上のものにしてやりたい。
読了日:1月15日 著者:服部幸
 ダーク・タワー〈2〉運命の三人〈下〉 (新潮文庫)の感想
ダーク・タワー〈2〉運命の三人〈下〉 (新潮文庫)の感想塔が呼んでいる。この物語がキングを呼び続けたように。彼と行動を共にする者にはいずれ死が訪れるだろう。ローランドのために。そのことを知ってなお、人に愛着し、非道を自責し、恐怖する程度に、ローランドは優しい。人の心を持たないことを恐れ、獣に堕ちた者の払う地獄の対価を恐れることは、概念化された宗教心とは違う、人の心に原始的に湧き起こる衝動なのかもしれない。その証拠に奴らは仲間を悼んだりしない。ディド・ア・チック? ダム・ア・チャム? 奴らはなにを問いかけているのか。その問いに私たちはなにを投影するのか。
読了日:1月14日 著者:スティーヴンキング
 人が育つ仕組みをつくれ!: リーダとして一番に心得ることの感想
人が育つ仕組みをつくれ!: リーダとして一番に心得ることの感想個人主義では、一人ひとりが自分のことで手いっぱいになれば集団の力は発揮できない。米国方式一辺倒でなく東洋思想も取り混ぜて、日常的、継続的に人が育つような職場環境を意識的につくる大切さを説いている。「明の知」「暗の知」「黙の知」、なかでも「黙の知」の考え方に感銘を受けた。つまり、OJTや講習を通して知識やノウハウを伝えることだけが、知を育む活動ではない。それだけでは人はこちらが思うようには育たない。人を育てようという考え方はいっそ捨てる。社内の空気で人を育てる。うちのような小型企業にはそれが大切のようだ。
読了日:1月14日 著者:常盤文克
 鴻池剛と猫のぽんた ニャアアアン!の感想
鴻池剛と猫のぽんた ニャアアアン!の感想猫飼いの日常の、どちらかといえば癒しではなく飼い主への試練が描かれていて、素手で受け止める件など、共感で笑いが止まらなくなる。飼い主の性格がずぼらであるほど、アクシデントが頻発することを発見。それを猫は楽しむし、飼い主は弱り切るようだ。なるほどー。
読了日:1月12日 著者:鴻池剛
 しんがり 山一證券最後の12人 (講談社+α文庫)の感想
しんがり 山一證券最後の12人 (講談社+α文庫)の感想「しんがり」のメンバーは仕組まれ、立場上そうせざるを得なかった者のいる一方、やるかたない思いを果たすために自ら参じた者もいた。彼らの成した調査は賞賛されるべきもので、そこにスポットを当てた試みが良い。大蔵省の思惑はともかく、山一證券の幹部はなにを見ていたのか。「しんがり」たちの腹を据えた姿勢に相対し、取締役たちのなんと暗愚なこと。個人ではなく企業を軸に考える人材のはずなのに、社内の力関係や個人の利害に囚われ、大局を見ず、逃げた。菊野のスタンスが素敵。「わしに言え。なんでも聞いてやるぞ。菊野じゃからな」!
読了日:1月8日 著者:清武英利
 山賊ダイアリー(1) (イブニングKC)の感想
山賊ダイアリー(1) (イブニングKC)の感想狩猟やその考え方への許容は、当時より増しているのではないか。この漫画が巻を重ねていることがその証拠だ。もう猟師になりたい願望も失せたが、動植物の小ネタが楽しい。1巻は半額セールで手に入れた。続きは迷うな…。独白調なのに丁寧語なのがヘンで微笑ましい。
読了日:1月3日 著者:岡本健太郎

 南総里見八犬伝 (角川ソフィア文庫―ビギナーズ・クラシックス (SP90))の感想
南総里見八犬伝 (角川ソフィア文庫―ビギナーズ・クラシックス (SP90))の感想南総里見八犬伝はとてつもなく長いのだそうだ。1冊の価値は数十万円相当、一般的な読者は貸本屋から借りて読んだ。アクション、ドラマ、ミステリ、ファンタジー、なんでもありだ。んなアホな、と思いつつ痛快で、当時このような娯楽があったとは、読者はさぞ続きが楽しみだっただろう。当世のベストセラー作家は20年以上かけて物語を完成させた。時代が近いせいか、原文もよみやすい。私も信乃や荘介、毛野に萌えながら、このような物語だったのかと満足した。全編制覇は、遠慮します。
読了日:1月2日 著者:曲亭馬琴,石川博

注:
 はKindleで読んだ本。
はKindleで読んだ本。 Posted by nekoneko at 17:19│Comments(0)
│読書