2024年01月05日
2023年の総括

2023年、読んだ本の冊数は170冊。
購入費用156,650円。
積読本320冊(うちKindle本157冊)。
ゴリラにせよインドにせよ、自分が世界を捉える視野の枠組ごと変えてみることは、相手の立場になって考えるとか、異なる切り口を探るなどの方法よりも、劇的にものの見えかたを変えると知った。意識して、一時的にでもフレームを替えることができれば、思いもかけなかった発想が現れる確率が高まると頭に留め、心がけたい。
また、西洋的な現代の思想の流れは片耳で追いつつ、西洋的でないもの、日本の古典を含め、アジアやアフリカ、各地の少数民族の思想を意識的に選んで読みたい。
2024年も良い本に出会えますように。

2023年、私の心に留まった本たち。
<人間は自然に敵わない>
 園芸家の一年 (平凡社ライブラリー)
園芸家の一年 (平凡社ライブラリー)カレル チャペック
 土を育てる: 自然をよみがえらせる土壌革命
土を育てる: 自然をよみがえらせる土壌革命ゲイブ・ブラウン
 土と内臓―微生物がつくる世界
土と内臓―微生物がつくる世界デイビッド・モントゴメリー,アン・ビクレー
 家は生態系―あなたは20万種の生き物と暮らしている
家は生態系―あなたは20万種の生き物と暮らしているロブ・ダン
 巨大津波は生態系をどう変えたか―生きものたちの東日本大震災 (ブルーバックス)
巨大津波は生態系をどう変えたか―生きものたちの東日本大震災 (ブルーバックス)永幡 嘉之
<西洋的なものへの違和感の自覚>
 いのちの教室
いのちの教室ライアル・ワトソン
 人類の星の時間
人類の星の時間シュテファン・ツヴァイク
<和への賛美>
 お茶人のための 茶花の野草大図鑑 改訂普及版
お茶人のための 茶花の野草大図鑑 改訂普及版宗匠

 新編 日本の面影 (角川ソフィア文庫)
新編 日本の面影 (角川ソフィア文庫)ラフカディオ・ハーン
<小説だから表現できるもの>
 楢山節考 (新潮文庫)
楢山節考 (新潮文庫)深沢 七郎
 シャンタラム(上) (新潮文庫)
シャンタラム(上) (新潮文庫)グレゴリー・デイヴィッド ロバーツ
 太陽の黄金(きん)の林檎〔新装版〕 (ハヤカワ文庫SF)
太陽の黄金(きん)の林檎〔新装版〕 (ハヤカワ文庫SF)レイ ブラッドベリ
2024年01月05日
2023年12月の記録
2023年の総括文をそろそろ考えなければと思い、
2022年の総括を読み返して腰を抜かしそうになった。
『月に1冊でいいから、古典、智の源と称される本に取り組むことを目標に』、
なんて3月の時点で忘れ果てている。
とりあえずショーペンハウアーで締めてみた。
忘却は加速度的に早まっている。
<今月のデータ>
購入12冊、購入費用8,844円。
読了15冊。
積読本320冊(うちKindle本157冊)。

 読書について (光文社古典新訳文庫)の感想
読書について (光文社古典新訳文庫)の感想
10年積んでいた。難解やろなあ、自省を迫られるんやろなと尻込みしていたからで、彼が19世紀のドイツ人であることも知らなかったのだ。さて、主著の注釈として書かれた論集の一部である。切れ味良くも深い類の文章で、わかりやすい。自分が誤りとする対象に対して手厳しい。というより最早罵っている。19世紀半ば、当地では通俗的で底の浅い娯楽本などが流行しており、真に良いものが廃れることを危惧していたと解説にある。今の日本でもありそうな現象を、「ドイツ人という国民はまったく」の調子で批判するあたりも面白い。多読の戒め。
読了日:12月29日 著者:アルトゥール ショーペンハウアー
 君が戦争を欲しないならば (岩波ブックレット)の感想
君が戦争を欲しないならば (岩波ブックレット)の感想
岡山県での講演から。高畑さんは9歳の時、岡山の大空襲に遭っていた。その体験が明瞭な表現で語られる。焼夷弾の落ちかたや焼けかたは「火垂るの墓」に正確に描かれた。しかし体験を語ってはこなかった。それは、自分たちが受けた悲惨な体験を語っても、これから突入していくかもしれない戦争を防止することにはならないから、と言う意味は深い。空襲が即ち一般人に対する無差別攻撃であることは、今のガザを見れば疑いない。だからと被害を強調するのではなく、平和を保つ努力、戦争をしない努力をひたすら続けるほうが、戦争を遠ざける道なのだ。
読了日:12月27日 著者:高畑 勲
 夜明け前(が一番暗い)の感想
夜明け前(が一番暗い)の感想
ひとつひとつ忘れている訳ではないが、この4年間に国政がしでかした数多の愚策失策奸策を一挙に並べると、奈落に臨む崖の縁が風化して大きく欠け落ちていくような寒々しい気分になった。しかし表題は「夜明け前(が一番暗い)」だ。今は暗くとも、ここから明るくなるのだよというニュアンスがある。長く生きれば「たいへんな時代」が前にもあったことを覚えているから絶望的にはならないのだと内田先生は言う。『歴史はそこそこ合理的に推移している』という経験が私には無い。だから個人レベルでくらいは親切な人であろうと思うのかもしれない。
読了日:12月26日 著者:内田 樹
 根に帰る落葉はの感想
根に帰る落葉はの感想
根に帰る落ち葉。南木さんは私の親の同世代だ。自身の人生の終いを意識した文章が多くなった。それでも私の行く先を照らしてくれる言葉は健在で、人間のからだというものは揺れるものだと、死に向けて絶え間なく老いていくもの、しかしつよいものだと教えてくれる。『記憶をおのれに都合よく改編しつつしたたかに生きのびている』。意に沿わない記憶の改ざんもまた、生き抜くためのスキルと受け入れていい。夫婦での登山の文章にある『人間ドックの検査結果説明では禁煙と歩くことの大切さ以外に、受診者に伝えることはほとんどない』も肝に銘ずる。
沁みた一文。『東京へ、東北へと帰る友の乗るタクシーを見送った夜空に膨らんだ月が重なって出ていた。あえて酔眼を凝らす必要もないので、二つの月をそのままにし、冷えた夜気を胸が痛くなるまで深く吸ってため息をつき、とりあえず今生きて在る事実を確認してみた』。
読了日:12月25日 著者:南木 佳士
 森の力 植物生態学者の理論と実践 (講談社現代新書)の感想
森の力 植物生態学者の理論と実践 (講談社現代新書)の感想
日本の本来の森(原植生)は現代の日本にほとんど残っておらず、あとは全て人間が改変したもの(現存植生)だという。少なくとも広葉樹林は、本物の森だと私は思っていたが、自然な森ではないと知った。著者は何十年も各地の現地植生調査を行ない、もともと生育していた土地本来の木(潜在自然植生)を突き止め、その苗を多層になるよう、また競争原理が働く形で密植することによって、「人間が管理せずとも維持できる森」を早く生育させる方式を編み出した。長期の観察から導かれる論理は強い。とりあえず神社の鎮守の森を見に行こう。それが本物。
読了日:12月23日 著者:宮脇 昭
 新ドリトル先生物語 ドリトル先生ガラパゴスを救うの感想
新ドリトル先生物語 ドリトル先生ガラパゴスを救うの感想
愛だなあ。福岡センセが好きなものをいっぱいに詰め込んだ物語。ドリトル先生とスタビンズ君たち、センスオブワンダーの数々、フェルメールとレーウェンフック、それに念願のガラパゴス諸島でのエピソードももちろんてんこ盛りだ。伝説のナチュラリスト、ダーウィンさんも出てきちゃうもんね。自然の不思議もいくつも出てきているので、興味を持って自然科学を志す子供がここから現れたら素敵だな。ガラパゴス諸島での活動はごく一部だけど、そこまでが大冒険だったし、その後もアッと驚く大冒険。ゾウガメを撫でたら10ペソのところが好き。
読了日:12月22日 著者:福岡伸一
 忘れる読書 (PHP新書)の感想
忘れる読書 (PHP新書)の感想
『むしろ忘れるために本を読んでいます』なんて格好いい。でもそれは、若い頃からそういう素地を養えたから。この人はほんとうに頭が良いのだと感じる一方、この人の本はこれ以上読まないでおこうと決める。この卓抜した頭脳が深く潜ろうとしているのは、イメージはできるが、私が全く関心を持てない方向だ。六本木から通学だったのか。それを読む時間に充てられたのはすごい。私なら寝る。ペデ沿いの古書店街で漁った、パラフィン紙に包まれた岩波文庫を思い出す。若造には理解できなかったものを、今ならきっと感じ取れる。読み返したくなった。
読了日:12月21日 著者:落合 陽一
 池上彰の世界の見方 インド: 混沌と発展のはざまでの感想
池上彰の世界の見方 インド: 混沌と発展のはざまでの感想
無駄にため込んだ断片的な知識を系統立てる、また増強するために。中学校での授業がベースだけあって平易でわかりやすい。宗教、識字率、人口分布を数字で見ることや、生活システムとしてのカースト制、ジャーティへの近代化の影響など、理解が深まる。差別や格差など課題が多い一方で、その多様さ、豊かさゆえの凄まじいエネルギーには期待せずにいられない。仏教はインドでは衰退しているが、日本の一部宗派のお経の詠唱には、インド映画で聴く音楽の節回しに似たものを感じるときがあって、ヒンドゥー教も多神教だし、勝手につながりを感じる。
イギリスはインドとパキスタンの間のみならず、インドと中国の間にも勝手に国境線を引いたのか。パレスチナ/イスラエルといい、なんと罪つくりな。近頃はアフリカからフランス軍が叩き出されているようで、こういう禍根を乗り越えながら、新しい和解が生まれるのだと信じたい。
理解が深まったメモ。「バジュランギおじさんと、小さな迷子」の、印パ問題の根深さ。「きっとうまくいく」の、IITのエリートさと厳しさ。「あなたの名前を呼べたなら」の、寡婦差別。「パドマーワト」の、ジャーハルの理不尽さ。もう一度映画を観直したくなる。そういえば「響け!情熱のムリダンガム」も確か、ジャーティが深くかかわったテーマだったはず。観たいなあ。そういえば池上さんは無いと言い切っていたけれど、映画カーストはあります。新しいカーストは生まれうるということか…。
読了日:12月20日 著者:池上 彰
 巡礼の家の感想
巡礼の家の感想
道後湯之町、道後温泉。先日泊まった旅館のそこここに、この小説が置いてあった。天童さんが高校時代まで暮らしただけでなく、その後今に至るまで交流を続けているからと知った。呑みながら読んでいたので、この世界はなんて残酷なんだろうと涙が止まらなくなった。事故も自然災害も民族紛争も、容赦なく大切な者を奪っていく。その傷んだ心が癒えるには、時間だけじゃ足りないのだ。人間同士の温かい気持ち、それが最高の手当てだ。身体も心も癒える場所としての道後。ユートピアのような遍路宿"さぎのや"に、天童さんの理想と願いをみる。
読了日:12月16日 著者:天童 荒太
 世界で一番美しい人体図鑑の感想
世界で一番美しい人体図鑑の感想
テレビで紹介されていて気になった図鑑。絵の精緻さ、人体の組織の精巧さが相まって溜息がこぼれる。スケルトンシートで重ねている部分が見どころで、表にめくったり裏にめくったり戻ったりと眺めて楽しい。各部位の名称や機能は、ビジュアルを損なわないようにかそれほど細かく書き込まれていない。そもそも、自分の身体に不調があるとき、それがどのあたりなのか見当をつけるために自宅に備えつけておくつもりだった。今朝は骨盤の内側に違和感があって、図鑑によると小腸から大腸につながるあたり。これはあれだなと、マッサージしておきました。
読了日:12月14日 著者:
 任せるコツの感想
任せるコツの感想
「正しい丸投げ」の方法論。使っている言葉は易しいが、実は深く、真面目なリーダーシップ論、マネジメント論として、わかりやすくて良かった。望まず中間管理職になった社員の目に触れるよう置いておこうと買い、読み出したら自分がひりひりする羽目になった。社員に仕事を任せるノウハウもそうだけど『育成の最終ゴールは、自分が不要になること』。あの人仕事してないんじゃね?と思われるような人にならないと実はぜんぜん安泰じゃない。未来工業の創業者は「社員には"餅"を与える」と言った。任せることも、"餅"のひとつなのだと思った。
読了日:12月13日 著者:山本 渉
 ゴリラからの警告「人間社会、ここがおかしい」の感想
ゴリラからの警告「人間社会、ここがおかしい」の感想
毎日新聞の連載、加筆修正。人間がゴリラやチンパンジー、サルとの共通祖先と分かれて700万年。その間にそれぞれ営みや集団のありかたを発達させてきた。彼らに関する知見をもって山極さんが見た人間社会の特性は、結論はごく良識的なものながら、切り口で新鮮に感じる。脳の大きさと、集団の平均サイズは相関する。人間の脳は格段に大きくなった。そこから導かれる適正な社会的集団の大きさは150人。深いやりとりをしながら維持できる共鳴集団では10~15人。これをより大人数で運営・管理しようとするから、無理や歪み、格差が出る訳だ。
読了日:12月12日 著者:山極 寿一
 シャンタラム(上) (新潮文庫)の感想
シャンタラム(上) (新潮文庫)の感想
夢中。オーヴァーアンダーパンツとかベアハグとか文化摩擦が面白過ぎる。なかでもインド映画でよく見る首振り×笑顔についての考察が大好きだ。自分でやってみると、肩から上の力を抜かないとできないのがわかる。スラムの人口密度は、他の国の都市とはけた違いに高い。欧米人をこの密度に詰め込んだら絶対やってゆけないという主旨の台詞がある。そうならない対人スキルや利他のシステムやがインド人にはあるのだ。ノワールな人生、なのに温かく笑顔に満ちて愛おしい。稚いタリク登場。この素敵なスラムの生活はまだ続いてくれるだろうか。中巻へ。養老先生が面白いと公言されていた小説。インドのスラムが舞台なのが珍しいだけではない。文化の違いに困惑したり、交流を楽しんでいるだけでもない。生まれや立場や来し方の違う人々が互いを受け入れる、理解し合う、愛おしい営みが描かれている。どういう経歴の人が書いているのだろうと奥付を見ると、ほとんど物語と一緒じゃん! どういうこと、これって実話なの?
読了日:12月09日 著者:グレゴリー・デイヴィッド ロバーツ
 笑いのある世界に生まれたということ (講談社+α新書)の感想
笑いのある世界に生まれたということ (講談社+α新書)の感想
兼近はなんか好きだ。中野信子も好きだ。二人のガチンコ対談は、とても面白かった。中野先生と生徒兼近。兼近先生と生徒中野。遠慮なしで釣り合って見えるのは絶妙だ。同時に、二人が慎重に狙い定めた戦略に、完全に自分がはめられていると気づいて笑ってしまう。笑う行為は人類が生き延びるために手に入れた特性、生来持っているHappy Pillsであり、人間社会を円滑にするための高度な技術でもある。その深遠を、彼は探っているのだな。それぞれのあとがきのちぐはぐ感がまた意外で、興味深い。同じ時代を生きる者として愛おしく思う。
読了日:12月06日 著者:中野 信子,兼近 大樹
 帝国の亡霊、そして殺人 (ハヤカワ・ミステリ)の感想
帝国の亡霊、そして殺人 (ハヤカワ・ミステリ)の感想
インド気分を味わうのにちょうどよいミステリ。イギリスからの独立、さらにパキスタン分離独立後のインドは、イギリスの失策ゆえに禍根を残し、恰好の不穏な舞台になる。著者はパキスタン出身の両親を持つイギリス人。インドは支配構造、身分、宗教、性別格差と複合的な社会なので、何からでも動機や障壁にできる。顔立ちが良いと設定されるキャラが多く、ラーム・チャラン、SRKなど脳内設定が忙しい。インドらしい小ネタは満載で楽しいけれど、ゾロアスター教徒設定の主人公といい、西洋的すぎるのが気になる。しゅっとしすぎているのが欠点。
読了日:12月04日 著者:ヴァシーム・カーン
注: は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。
2022年の総括を読み返して腰を抜かしそうになった。
『月に1冊でいいから、古典、智の源と称される本に取り組むことを目標に』、
なんて3月の時点で忘れ果てている。
とりあえずショーペンハウアーで締めてみた。
忘却は加速度的に早まっている。
<今月のデータ>
購入12冊、購入費用8,844円。
読了15冊。
積読本320冊(うちKindle本157冊)。

 読書について (光文社古典新訳文庫)の感想
読書について (光文社古典新訳文庫)の感想10年積んでいた。難解やろなあ、自省を迫られるんやろなと尻込みしていたからで、彼が19世紀のドイツ人であることも知らなかったのだ。さて、主著の注釈として書かれた論集の一部である。切れ味良くも深い類の文章で、わかりやすい。自分が誤りとする対象に対して手厳しい。というより最早罵っている。19世紀半ば、当地では通俗的で底の浅い娯楽本などが流行しており、真に良いものが廃れることを危惧していたと解説にある。今の日本でもありそうな現象を、「ドイツ人という国民はまったく」の調子で批判するあたりも面白い。多読の戒め。
読了日:12月29日 著者:アルトゥール ショーペンハウアー

 君が戦争を欲しないならば (岩波ブックレット)の感想
君が戦争を欲しないならば (岩波ブックレット)の感想岡山県での講演から。高畑さんは9歳の時、岡山の大空襲に遭っていた。その体験が明瞭な表現で語られる。焼夷弾の落ちかたや焼けかたは「火垂るの墓」に正確に描かれた。しかし体験を語ってはこなかった。それは、自分たちが受けた悲惨な体験を語っても、これから突入していくかもしれない戦争を防止することにはならないから、と言う意味は深い。空襲が即ち一般人に対する無差別攻撃であることは、今のガザを見れば疑いない。だからと被害を強調するのではなく、平和を保つ努力、戦争をしない努力をひたすら続けるほうが、戦争を遠ざける道なのだ。
読了日:12月27日 著者:高畑 勲

 夜明け前(が一番暗い)の感想
夜明け前(が一番暗い)の感想ひとつひとつ忘れている訳ではないが、この4年間に国政がしでかした数多の愚策失策奸策を一挙に並べると、奈落に臨む崖の縁が風化して大きく欠け落ちていくような寒々しい気分になった。しかし表題は「夜明け前(が一番暗い)」だ。今は暗くとも、ここから明るくなるのだよというニュアンスがある。長く生きれば「たいへんな時代」が前にもあったことを覚えているから絶望的にはならないのだと内田先生は言う。『歴史はそこそこ合理的に推移している』という経験が私には無い。だから個人レベルでくらいは親切な人であろうと思うのかもしれない。
読了日:12月26日 著者:内田 樹

 根に帰る落葉はの感想
根に帰る落葉はの感想根に帰る落ち葉。南木さんは私の親の同世代だ。自身の人生の終いを意識した文章が多くなった。それでも私の行く先を照らしてくれる言葉は健在で、人間のからだというものは揺れるものだと、死に向けて絶え間なく老いていくもの、しかしつよいものだと教えてくれる。『記憶をおのれに都合よく改編しつつしたたかに生きのびている』。意に沿わない記憶の改ざんもまた、生き抜くためのスキルと受け入れていい。夫婦での登山の文章にある『人間ドックの検査結果説明では禁煙と歩くことの大切さ以外に、受診者に伝えることはほとんどない』も肝に銘ずる。
沁みた一文。『東京へ、東北へと帰る友の乗るタクシーを見送った夜空に膨らんだ月が重なって出ていた。あえて酔眼を凝らす必要もないので、二つの月をそのままにし、冷えた夜気を胸が痛くなるまで深く吸ってため息をつき、とりあえず今生きて在る事実を確認してみた』。
読了日:12月25日 著者:南木 佳士
 森の力 植物生態学者の理論と実践 (講談社現代新書)の感想
森の力 植物生態学者の理論と実践 (講談社現代新書)の感想日本の本来の森(原植生)は現代の日本にほとんど残っておらず、あとは全て人間が改変したもの(現存植生)だという。少なくとも広葉樹林は、本物の森だと私は思っていたが、自然な森ではないと知った。著者は何十年も各地の現地植生調査を行ない、もともと生育していた土地本来の木(潜在自然植生)を突き止め、その苗を多層になるよう、また競争原理が働く形で密植することによって、「人間が管理せずとも維持できる森」を早く生育させる方式を編み出した。長期の観察から導かれる論理は強い。とりあえず神社の鎮守の森を見に行こう。それが本物。
読了日:12月23日 著者:宮脇 昭

 新ドリトル先生物語 ドリトル先生ガラパゴスを救うの感想
新ドリトル先生物語 ドリトル先生ガラパゴスを救うの感想愛だなあ。福岡センセが好きなものをいっぱいに詰め込んだ物語。ドリトル先生とスタビンズ君たち、センスオブワンダーの数々、フェルメールとレーウェンフック、それに念願のガラパゴス諸島でのエピソードももちろんてんこ盛りだ。伝説のナチュラリスト、ダーウィンさんも出てきちゃうもんね。自然の不思議もいくつも出てきているので、興味を持って自然科学を志す子供がここから現れたら素敵だな。ガラパゴス諸島での活動はごく一部だけど、そこまでが大冒険だったし、その後もアッと驚く大冒険。ゾウガメを撫でたら10ペソのところが好き。
読了日:12月22日 著者:福岡伸一
 忘れる読書 (PHP新書)の感想
忘れる読書 (PHP新書)の感想『むしろ忘れるために本を読んでいます』なんて格好いい。でもそれは、若い頃からそういう素地を養えたから。この人はほんとうに頭が良いのだと感じる一方、この人の本はこれ以上読まないでおこうと決める。この卓抜した頭脳が深く潜ろうとしているのは、イメージはできるが、私が全く関心を持てない方向だ。六本木から通学だったのか。それを読む時間に充てられたのはすごい。私なら寝る。ペデ沿いの古書店街で漁った、パラフィン紙に包まれた岩波文庫を思い出す。若造には理解できなかったものを、今ならきっと感じ取れる。読み返したくなった。
読了日:12月21日 著者:落合 陽一

 池上彰の世界の見方 インド: 混沌と発展のはざまでの感想
池上彰の世界の見方 インド: 混沌と発展のはざまでの感想無駄にため込んだ断片的な知識を系統立てる、また増強するために。中学校での授業がベースだけあって平易でわかりやすい。宗教、識字率、人口分布を数字で見ることや、生活システムとしてのカースト制、ジャーティへの近代化の影響など、理解が深まる。差別や格差など課題が多い一方で、その多様さ、豊かさゆえの凄まじいエネルギーには期待せずにいられない。仏教はインドでは衰退しているが、日本の一部宗派のお経の詠唱には、インド映画で聴く音楽の節回しに似たものを感じるときがあって、ヒンドゥー教も多神教だし、勝手につながりを感じる。
イギリスはインドとパキスタンの間のみならず、インドと中国の間にも勝手に国境線を引いたのか。パレスチナ/イスラエルといい、なんと罪つくりな。近頃はアフリカからフランス軍が叩き出されているようで、こういう禍根を乗り越えながら、新しい和解が生まれるのだと信じたい。
理解が深まったメモ。「バジュランギおじさんと、小さな迷子」の、印パ問題の根深さ。「きっとうまくいく」の、IITのエリートさと厳しさ。「あなたの名前を呼べたなら」の、寡婦差別。「パドマーワト」の、ジャーハルの理不尽さ。もう一度映画を観直したくなる。そういえば「響け!情熱のムリダンガム」も確か、ジャーティが深くかかわったテーマだったはず。観たいなあ。そういえば池上さんは無いと言い切っていたけれど、映画カーストはあります。新しいカーストは生まれうるということか…。
読了日:12月20日 著者:池上 彰

 巡礼の家の感想
巡礼の家の感想道後湯之町、道後温泉。先日泊まった旅館のそこここに、この小説が置いてあった。天童さんが高校時代まで暮らしただけでなく、その後今に至るまで交流を続けているからと知った。呑みながら読んでいたので、この世界はなんて残酷なんだろうと涙が止まらなくなった。事故も自然災害も民族紛争も、容赦なく大切な者を奪っていく。その傷んだ心が癒えるには、時間だけじゃ足りないのだ。人間同士の温かい気持ち、それが最高の手当てだ。身体も心も癒える場所としての道後。ユートピアのような遍路宿"さぎのや"に、天童さんの理想と願いをみる。
読了日:12月16日 著者:天童 荒太

 世界で一番美しい人体図鑑の感想
世界で一番美しい人体図鑑の感想テレビで紹介されていて気になった図鑑。絵の精緻さ、人体の組織の精巧さが相まって溜息がこぼれる。スケルトンシートで重ねている部分が見どころで、表にめくったり裏にめくったり戻ったりと眺めて楽しい。各部位の名称や機能は、ビジュアルを損なわないようにかそれほど細かく書き込まれていない。そもそも、自分の身体に不調があるとき、それがどのあたりなのか見当をつけるために自宅に備えつけておくつもりだった。今朝は骨盤の内側に違和感があって、図鑑によると小腸から大腸につながるあたり。これはあれだなと、マッサージしておきました。
読了日:12月14日 著者:
 任せるコツの感想
任せるコツの感想「正しい丸投げ」の方法論。使っている言葉は易しいが、実は深く、真面目なリーダーシップ論、マネジメント論として、わかりやすくて良かった。望まず中間管理職になった社員の目に触れるよう置いておこうと買い、読み出したら自分がひりひりする羽目になった。社員に仕事を任せるノウハウもそうだけど『育成の最終ゴールは、自分が不要になること』。あの人仕事してないんじゃね?と思われるような人にならないと実はぜんぜん安泰じゃない。未来工業の創業者は「社員には"餅"を与える」と言った。任せることも、"餅"のひとつなのだと思った。
読了日:12月13日 著者:山本 渉
 ゴリラからの警告「人間社会、ここがおかしい」の感想
ゴリラからの警告「人間社会、ここがおかしい」の感想毎日新聞の連載、加筆修正。人間がゴリラやチンパンジー、サルとの共通祖先と分かれて700万年。その間にそれぞれ営みや集団のありかたを発達させてきた。彼らに関する知見をもって山極さんが見た人間社会の特性は、結論はごく良識的なものながら、切り口で新鮮に感じる。脳の大きさと、集団の平均サイズは相関する。人間の脳は格段に大きくなった。そこから導かれる適正な社会的集団の大きさは150人。深いやりとりをしながら維持できる共鳴集団では10~15人。これをより大人数で運営・管理しようとするから、無理や歪み、格差が出る訳だ。
読了日:12月12日 著者:山極 寿一

 シャンタラム(上) (新潮文庫)の感想
シャンタラム(上) (新潮文庫)の感想夢中。オーヴァーアンダーパンツとかベアハグとか文化摩擦が面白過ぎる。なかでもインド映画でよく見る首振り×笑顔についての考察が大好きだ。自分でやってみると、肩から上の力を抜かないとできないのがわかる。スラムの人口密度は、他の国の都市とはけた違いに高い。欧米人をこの密度に詰め込んだら絶対やってゆけないという主旨の台詞がある。そうならない対人スキルや利他のシステムやがインド人にはあるのだ。ノワールな人生、なのに温かく笑顔に満ちて愛おしい。稚いタリク登場。この素敵なスラムの生活はまだ続いてくれるだろうか。中巻へ。養老先生が面白いと公言されていた小説。インドのスラムが舞台なのが珍しいだけではない。文化の違いに困惑したり、交流を楽しんでいるだけでもない。生まれや立場や来し方の違う人々が互いを受け入れる、理解し合う、愛おしい営みが描かれている。どういう経歴の人が書いているのだろうと奥付を見ると、ほとんど物語と一緒じゃん! どういうこと、これって実話なの?
読了日:12月09日 著者:グレゴリー・デイヴィッド ロバーツ
 笑いのある世界に生まれたということ (講談社+α新書)の感想
笑いのある世界に生まれたということ (講談社+α新書)の感想兼近はなんか好きだ。中野信子も好きだ。二人のガチンコ対談は、とても面白かった。中野先生と生徒兼近。兼近先生と生徒中野。遠慮なしで釣り合って見えるのは絶妙だ。同時に、二人が慎重に狙い定めた戦略に、完全に自分がはめられていると気づいて笑ってしまう。笑う行為は人類が生き延びるために手に入れた特性、生来持っているHappy Pillsであり、人間社会を円滑にするための高度な技術でもある。その深遠を、彼は探っているのだな。それぞれのあとがきのちぐはぐ感がまた意外で、興味深い。同じ時代を生きる者として愛おしく思う。
読了日:12月06日 著者:中野 信子,兼近 大樹

 帝国の亡霊、そして殺人 (ハヤカワ・ミステリ)の感想
帝国の亡霊、そして殺人 (ハヤカワ・ミステリ)の感想インド気分を味わうのにちょうどよいミステリ。イギリスからの独立、さらにパキスタン分離独立後のインドは、イギリスの失策ゆえに禍根を残し、恰好の不穏な舞台になる。著者はパキスタン出身の両親を持つイギリス人。インドは支配構造、身分、宗教、性別格差と複合的な社会なので、何からでも動機や障壁にできる。顔立ちが良いと設定されるキャラが多く、ラーム・チャラン、SRKなど脳内設定が忙しい。インドらしい小ネタは満載で楽しいけれど、ゾロアスター教徒設定の主人公といい、西洋的すぎるのが気になる。しゅっとしすぎているのが欠点。
読了日:12月04日 著者:ヴァシーム・カーン

注:
 は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。 2023年12月05日
2023年11月の記録
この季節。
エアコンをつけ始めると、部屋の開口部は閉めなければならない。
猫たちは主張する。
廊下へ出たい! 部屋へ入りたい! 廊下へ出たい! 部屋へ入りたい!
開けてくれなきゃドアに爪を立てて自分で開けてみせる!
都度、私は立ちあがってドアを開けることを繰り返す。
座ってもすぐに呼ばれるので集中できず、苛々と本を撫でまわしている。
<今月のデータ>
購入14冊、購入費用11,269円。
読了10冊。
積読本330冊(うちKindle本159冊、Honto本3冊)。
Honto本、ちびちびと消化していたけれど、Booxも捨て、スマホで読む気も起きず、
諦めて放棄することにした。
「月は無慈悲な夜の女王」、「死の鳥」、「シベリア追跡」。
Kindleでいずれ買い直すことになりそう。

 日本のコメ問題-5つの転換点と迫りくる最大の危機 (中公新書 2701)の感想
日本のコメ問題-5つの転換点と迫りくる最大の危機 (中公新書 2701)の感想
素人へのわかりやすさを心がけて書かれてはいるが、需給や政局により度重ねた政策変更には、素人の頭は追いつかない。つまり、技術の進歩に伴い、少ない労働力で多くの収穫が可能になった。需給から言えば米の収穫量はもう少し減ったほうが、米農家や米産業のためには良い、らしい。しかし余った田んぼをどうするか。小麦や大豆他への転作畑地化、また加工用米、飼料用米に切り替えてでも、いざというとき再び米をつくれる道が残された土地であってほしい。とは感傷か。そして飼料用米は経済的に成り立たない。補助金じゃぶじゃぶを是とするべきか。
田んぼとしての認定ルール。5年以内に、一度は水を張ること。それをしないと田んぼ認定が受けられず、補助金がもらえない。補助金は大きなインセンティヴとして機能してきた。だけど、余った田んぼの活用方法として植えた果樹や設置したビニールハウス、放牧した牛を除去するのは現実的でない。では何が田んぼで何が畑なのか?? もうわからん。補助金の問題が根深すぎて、にっちもさっちもいかない感じがする。とりあえず米も農作物も値上げしよう。スイーツに2,000円出せて、野菜の300円を高く感じるのは間違ってる。
読了日:11月29日 著者:小川 真如
 ゾンビ化するアメリカ 時代に逆行する最高裁、州法、そして大統領選の感想
ゾンビ化するアメリカ 時代に逆行する最高裁、州法、そして大統領選の感想
相変わらず日本人から見ると桁の外れた国だなあ。器がでかいようで、なんか生きにくそう。フロリダ州の「ザ・ヴィレッジズ」に度肝を抜かれる。高齢者限定の住宅を建ててつくった、裕福な高齢者限定のコミュニティ、住人は13万人。高齢者が余生を平穏に楽しく暮らすための街。そこまでやるのか。それって、欲求を純粋に求めた形とはいえ、人間社会としてすごく歪だと思う。幸せかな。政治ネタには溜息しか出ないけど、音楽や映画はそのさほど長くない歴史も多様性も映して、だから魅力的で、だから町山さんはアメリカが好きなんだろうと想像する。
「ガラスの天井」ならぬ「ガラスの崖(Glass Cliff)」が現れた。その企業が崖っぷちに追い詰められた時、女性や少数民族が経営陣に抜擢される現象とのこと。曰く、"独自の感性で画期的なアイデアが出ることを期待して"。それって、日本にも既にあるよな。今まで散々、男ばっかりで社会や会社を仕切ってきて、雲行きが怪しくなったら「女性の力」だの「女性らしい感性で」だの、調子の良い事この上ない。ましてや失敗したときには「ほらね」と言わんばかりに責任をなすりつけようとするとはどこまで女々しいのか。その手には乗らんぞ。
読了日:11月24日 著者:町山 智浩
 老後を動物と生きるの感想
老後を動物と生きるの感想
他者との交流や心身の自由が限られてくる老年期こそ、伴侶動物と暮らすべきだとずっと思ってきた。しかし日本では、安全面、衛生面、管理面などの障壁が先に立って、飼い犬/猫と一緒に入れる老人ホームなどは今も香川県内にはほぼ無い。この本は、老人福祉施設での動物飼育において、規定しておくべき要件のチェックリストや問題点についての論考集である。スイス、ドイツ、オーストリアにおいては、この本が出た2004年の時点で施設への動物受入れが格段に増えているとある。日本は訪問動物が限界だろうか。意地でも猫と離れず自宅で死にたい。
老年期に動物と暮らそうと思うと、人間が先に死んだ場合の備えがどうしたって必要になる。余生の飼養を引き受ける契約も民間団体レベルではあるが、システムとして不安定には違いなく、社会の仕組みとして確立できないものかと思う。外国ではティアハイムの延長として考える精神的素地があるが、日本ではブリーディングのように金儲け目的の悪徳業者がはびこりそうな気がして安心できない。うーん。
読了日:11月23日 著者:マリアンヌ ゲング,デニス・C. ターナー
 あなたが私を竹槍で突き殺す前にの感想
あなたが私を竹槍で突き殺す前にの感想
タイトルに負けず内容も衝撃的なディストピア小説。より右傾化した日本で総理大臣は小池百合子(推定)、日韓関係は断絶、ヘイトクライムは激増、悪質化の一途にある。在日韓国人の生きる場所を奪う政策が支持され、新大久保にもコリアンの居場所はほとんどない。怖いのは、これが少々過激すぎる設定ではあっても、現実と地続きに見えることだ。著者の来歴を検索したい気持ちを抑えて読み終えた。奥付、同い年の在日韓国人三世だった。同じ日本を生きてきて、私と彼に見える世界がどれだけ隔たっているか。片や強い怒り、片や深い諦めに息が止まる。
『日本国家に刃向かう不逞鮮人』って福田村事件からそのままスライドしてきたみたいな言葉だ。外国にルーツのある人々と共生するための社会制度がことごとく廃止される日本。マイナンバーカード提示義務化に伴う本名開示強制、通名禁止、ヘイトスピーチ解消法廃止、外国人への生活保護給付禁止、特別永住者制度廃止、外国人を対象外とするベーシックインカムの検討。そこまで積極的ではなくとも、そういう排他的な動きにひょっと繋がるのでは、と思ってしまう気配とか、実際に人権を侵害している法制とか、あるからフィクションだと割り切れない。
読了日:11月23日 著者:李龍徳
 海をあげる (単行本)の感想
海をあげる (単行本)の感想
海をもらう。絶望の海。海のような絶望。上間さんは穏やかな、柔らかい声で、相手に伝わるようゆっくり話す人だ。でも心の中にはこんなに憤りと悲しみを抱えていたのだと知る。米軍基地の爆音、水道水汚染や環境破壊、暴力。『いま、まっただなかで暮らしているひとは、どこに逃げたらいいのかわからない』。その深さを想い、言葉にならない。自身も普天間に暮らしながら、困難を抱える若者の、女性たちの言葉を聞く。受け止め、生きることを助ける。当事者でない私たちができることも、たぶん似ている。耳を澄まし、受け止めること。傍に立つこと。
沖縄県に顕著な、貧困状態にある人の多さを社会問題と大局的に捉え、解決方法を模索することも大事だ。しかしそのデータからは思い及ぶことの難しい、たくさんの若者、女性たちそれぞれの痛み、苦しみ、絶望と諦めがあることは見えづらい。ほんとうに酷い。実の親ですら、そして行政にも頼れない若者たちに差し伸べる手は必ず必要だ。その行為すら阻害されて、諦めて流される背中を見送るのはどんな思いだったろう。そこから、若い母親と乳児を保護し、節目を寿いで送り出すシェルター「おにわ」の立ち上げに繋がっていく。なんと尊い営みか。
沖縄に生まれてもいない、育ってもいない、暮らしてもいない私は徹底的に外野だ。むしろ加害者の側ですらある。その私が、沖縄に、沖縄の人々に対してどうあればよいのかは、ずっと考えていることだ。この本を読んで、書き上げた感想、自分で読んで「きれいごとだ」と感じる。とりあえず、読んで終わりにしないと決める。
読了日:11月13日 著者:上間 陽子
 おらおらでひとりいぐも (河出文庫)の感想
おらおらでひとりいぐも (河出文庫)の感想
脳内ひとりごとだだ洩れ系、大好き。止めどのない思考は、濁流となりせせらぎとなり奔流となり、そのときどきの思いに駆られてあっちこっち迷走しながら、人は生きている。辻褄?そんなもん合う訳ないやん。『おらの生ぎるはおらの裁量に任せられているのだな。おらはおらの人生を引き受げる』。女の業もちゃんと書いていて、傷つけた人のこと、離れてしまったきりの人のこと、悔やむけれど、しかたないやん、生きるしかないやん、という苦みも含め、東北弁で書ききったことに喝采をおくる。解説は町田康、これはもうね、当然すぎるね。
読了日:11月12日 著者:若竹千佐子
 福田村事件 -関東大震災・知られざる悲劇の感想
福田村事件 -関東大震災・知られざる悲劇の感想
関東大震災直後、デマに煽られて「朝鮮人」9人を虐殺したが、実は香川県からの行商人家族の集団だった。妊婦や幼児まで手にかけ、利根川に遺体を突き流した実在の事件だ。朝鮮人であるか否かの事実に関わらず数百人で少数を暴行のうえ虐殺したこと。国のためだったと言い張って悔いず、有罪判決は不服と上告までしたこと。村人から被告に見舞金を出したこと。歴史に残らないよう揃って口を閉ざしたこと。人間の、不変の愚かさがくっきり出ている。怖いのは事件そのものだけでなく、事件を無かったことのように忘れること。そこにぐらいは抗いたい。
被告のひとりの証言。『日本刀を持って出掛けると群衆のなかから、貴様は見物にきたのかと怒鳴りましたので、ついやったような訳です。私は実際相手を斬ったにもかかわらず、予審で三回も否認したのは、摂政宮殿下には玄米を召し上がられている際、不逞鮮人のために国家はどうなることかと憂れへの余りやったような次第ですが、監獄に入れられたので癪にさわったから、事実を否認したのです』。
被害者の地元の女性の証言。『日本人と朝鮮人とまちがえたということは、香川県の言葉と朝鮮の言葉はそんなに似とるんやろかなあ、なんでかしらんと思っておりました。こちらでは朝鮮の人はよくアメ売りに来ました。その人の言葉はなまりとかでわかりました。あの言葉と讃岐の言葉がなんでわからないのかなあ、関東の人ってひどい人やなあと私は思いました。罪のない人をまちがったか何か知らんけど殺すとはひどいとおもいましたよ。それが頭に残っています』。
香川県内には1990年代で46カ所同和地区があったと聞き、その多さに驚いた。瀬戸内海地方は温暖な気候や、人や物の往来の多さのわりに耕せる土地が少ないため、貧しかったと宮本常一も言っていた。面積が小さい香川県は特に、1軒当たりの農地が狭く、小作率も全国一高かった。そのことが、香川の売薬行商人が全国で2番目に多いなど、行商人が多かった理由だろう。「四国辺土」の遍路のことといい、香川県は災害が少なくて良いなど、わりとのほほんとした風土のように自称するが、なかなか深い闇を抱えているのだと最近になって戦慄している。
読了日:11月08日 著者:辻野弥生
 生命海流 GALAPAGOSの感想
生命海流 GALAPAGOSの感想
福岡センセイ、念願叶う。ダーウィンのマーベル号と同じ航路を取ってガラパゴスの島々を旅した記念の誌。装丁も豪華だ。船やコック、ガイドを雇った贅沢な旅とはいえ、自称ニセモノ・ナチュラリストの福岡先生には(きっと私にも)ガラパゴスの自然は厳しいのだろう。それこそ体験しなければわからない。釣竿を持って行ったくらいだから、獲ったり釣ったり生物を子細に観察する機会が全く禁じられたのは誤算だったのではないかしら。ダーウィンの頃は何でもやり放題、捕り放題で大量の標本や剥製を持ち帰ったのにとひき比べてみせるのが微笑ましい。
植物や微生物は『自分たちに必要な分だけ栄養分を作ったり、作ったアンモニアを独占するのではなく、いつも少しだけ多めに活動して、それを他の生命に分け与えてくれた。利己的にならず他を利することもつまり利他性があった。余裕があるところに利他性が生まれ、利他性が生まれると初めて共生が生まれる。利他性はめぐりめぐってまた自分のところに戻ってくる』。そうして何もなかった島に生命は満ちた。生命レベルの利他が無ければ、そもそも生命の繁栄は無かったとの指摘は、壮大で、考えてもみなかったことだった。
読了日:11月05日 著者:福岡 伸一
 オリガ・モリソヴナの反語法 (集英社文庫)の感想
オリガ・モリソヴナの反語法 (集英社文庫)の感想
初めての小説とは信じられない。実在するのは教師の存在と電信記録、自身の体験だけ。あとは時代の動乱に絡めた人々の受難の歴史、全て日露の膨大な文献にあたって創りあげた架空とは。ソ連という大きな枠組みの中での、女性たちの受難。子供も無縁でいられない。外国籍の人とのつき合いは用心しなさいと教えられ、キューバ危機の報に初恋の人への告白を決心する。人は時代とも世界とも無縁ではいられない。それがむき出しになるソ連と、何も知らないまま守られる日本のいずれが特別なのか、いずれにせよその落差が人の成熟を決するように感じた。
物語として、凄く面白かった。でもそれは米原さん自身がプラハで過ごした幼少期、そこで得た体験や学び方、知識無しにはあり得なくて、かの地の子どもたちがどのような常識と教養を身につけさせられるか、一方で日本の教育がどのような性質のものであるかを痛感せずにいられない。登場人物の痛みを想像する一方で、我が身のほうも苦いものが残る。よい読書体験でした。
読了日:11月03日 著者:米原 万里
 オーガニック植木屋の庭づくり: 暮らしが広がるガーデンデザインの感想
オーガニック植木屋の庭づくり: 暮らしが広がるガーデンデザインの感想
ひきちさんの本は4冊目。内容が劇的に違う訳ではないのだけれど、眺めてはイメージをつくり直す過程を繰り返すのが楽しい。今回は「オーガニックとはなにか」「自分の暮らしに合う庭とは」など大きな、かつ現実的な問い立てから、各アイテムの設置方法、望ましい仕様などを細かく書いている。低いレイズドベッド、バイオネスト、野外炉、インセクトホテル、排水用浸透層、睡蓮鉢、雨庭など、やってみたいけれど自分でやれるのかこれは。なものばかり挙げているな私。ま、実際にやってみるこったな。売っている堆肥の性質、注意点は憶えておきたい。
読了日:11月02日 著者:ひきちガーデンサービス 曳地トシ+曳地義治
注: は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。
エアコンをつけ始めると、部屋の開口部は閉めなければならない。
猫たちは主張する。
廊下へ出たい! 部屋へ入りたい! 廊下へ出たい! 部屋へ入りたい!
開けてくれなきゃドアに爪を立てて自分で開けてみせる!
都度、私は立ちあがってドアを開けることを繰り返す。
座ってもすぐに呼ばれるので集中できず、苛々と本を撫でまわしている。
<今月のデータ>
購入14冊、購入費用11,269円。
読了10冊。
積読本330冊(うちKindle本159冊、
Honto本、ちびちびと消化していたけれど、Booxも捨て、スマホで読む気も起きず、
諦めて放棄することにした。
「月は無慈悲な夜の女王」、「死の鳥」、「シベリア追跡」。
Kindleでいずれ買い直すことになりそう。

 日本のコメ問題-5つの転換点と迫りくる最大の危機 (中公新書 2701)の感想
日本のコメ問題-5つの転換点と迫りくる最大の危機 (中公新書 2701)の感想素人へのわかりやすさを心がけて書かれてはいるが、需給や政局により度重ねた政策変更には、素人の頭は追いつかない。つまり、技術の進歩に伴い、少ない労働力で多くの収穫が可能になった。需給から言えば米の収穫量はもう少し減ったほうが、米農家や米産業のためには良い、らしい。しかし余った田んぼをどうするか。小麦や大豆他への転作畑地化、また加工用米、飼料用米に切り替えてでも、いざというとき再び米をつくれる道が残された土地であってほしい。とは感傷か。そして飼料用米は経済的に成り立たない。補助金じゃぶじゃぶを是とするべきか。
田んぼとしての認定ルール。5年以内に、一度は水を張ること。それをしないと田んぼ認定が受けられず、補助金がもらえない。補助金は大きなインセンティヴとして機能してきた。だけど、余った田んぼの活用方法として植えた果樹や設置したビニールハウス、放牧した牛を除去するのは現実的でない。では何が田んぼで何が畑なのか?? もうわからん。補助金の問題が根深すぎて、にっちもさっちもいかない感じがする。とりあえず米も農作物も値上げしよう。スイーツに2,000円出せて、野菜の300円を高く感じるのは間違ってる。
読了日:11月29日 著者:小川 真如

 ゾンビ化するアメリカ 時代に逆行する最高裁、州法、そして大統領選の感想
ゾンビ化するアメリカ 時代に逆行する最高裁、州法、そして大統領選の感想相変わらず日本人から見ると桁の外れた国だなあ。器がでかいようで、なんか生きにくそう。フロリダ州の「ザ・ヴィレッジズ」に度肝を抜かれる。高齢者限定の住宅を建ててつくった、裕福な高齢者限定のコミュニティ、住人は13万人。高齢者が余生を平穏に楽しく暮らすための街。そこまでやるのか。それって、欲求を純粋に求めた形とはいえ、人間社会としてすごく歪だと思う。幸せかな。政治ネタには溜息しか出ないけど、音楽や映画はそのさほど長くない歴史も多様性も映して、だから魅力的で、だから町山さんはアメリカが好きなんだろうと想像する。
「ガラスの天井」ならぬ「ガラスの崖(Glass Cliff)」が現れた。その企業が崖っぷちに追い詰められた時、女性や少数民族が経営陣に抜擢される現象とのこと。曰く、"独自の感性で画期的なアイデアが出ることを期待して"。それって、日本にも既にあるよな。今まで散々、男ばっかりで社会や会社を仕切ってきて、雲行きが怪しくなったら「女性の力」だの「女性らしい感性で」だの、調子の良い事この上ない。ましてや失敗したときには「ほらね」と言わんばかりに責任をなすりつけようとするとはどこまで女々しいのか。その手には乗らんぞ。
読了日:11月24日 著者:町山 智浩

 老後を動物と生きるの感想
老後を動物と生きるの感想他者との交流や心身の自由が限られてくる老年期こそ、伴侶動物と暮らすべきだとずっと思ってきた。しかし日本では、安全面、衛生面、管理面などの障壁が先に立って、飼い犬/猫と一緒に入れる老人ホームなどは今も香川県内にはほぼ無い。この本は、老人福祉施設での動物飼育において、規定しておくべき要件のチェックリストや問題点についての論考集である。スイス、ドイツ、オーストリアにおいては、この本が出た2004年の時点で施設への動物受入れが格段に増えているとある。日本は訪問動物が限界だろうか。意地でも猫と離れず自宅で死にたい。
老年期に動物と暮らそうと思うと、人間が先に死んだ場合の備えがどうしたって必要になる。余生の飼養を引き受ける契約も民間団体レベルではあるが、システムとして不安定には違いなく、社会の仕組みとして確立できないものかと思う。外国ではティアハイムの延長として考える精神的素地があるが、日本ではブリーディングのように金儲け目的の悪徳業者がはびこりそうな気がして安心できない。うーん。
読了日:11月23日 著者:マリアンヌ ゲング,デニス・C. ターナー
 あなたが私を竹槍で突き殺す前にの感想
あなたが私を竹槍で突き殺す前にの感想タイトルに負けず内容も衝撃的なディストピア小説。より右傾化した日本で総理大臣は小池百合子(推定)、日韓関係は断絶、ヘイトクライムは激増、悪質化の一途にある。在日韓国人の生きる場所を奪う政策が支持され、新大久保にもコリアンの居場所はほとんどない。怖いのは、これが少々過激すぎる設定ではあっても、現実と地続きに見えることだ。著者の来歴を検索したい気持ちを抑えて読み終えた。奥付、同い年の在日韓国人三世だった。同じ日本を生きてきて、私と彼に見える世界がどれだけ隔たっているか。片や強い怒り、片や深い諦めに息が止まる。
『日本国家に刃向かう不逞鮮人』って福田村事件からそのままスライドしてきたみたいな言葉だ。外国にルーツのある人々と共生するための社会制度がことごとく廃止される日本。マイナンバーカード提示義務化に伴う本名開示強制、通名禁止、ヘイトスピーチ解消法廃止、外国人への生活保護給付禁止、特別永住者制度廃止、外国人を対象外とするベーシックインカムの検討。そこまで積極的ではなくとも、そういう排他的な動きにひょっと繋がるのでは、と思ってしまう気配とか、実際に人権を侵害している法制とか、あるからフィクションだと割り切れない。
読了日:11月23日 著者:李龍徳
 海をあげる (単行本)の感想
海をあげる (単行本)の感想海をもらう。絶望の海。海のような絶望。上間さんは穏やかな、柔らかい声で、相手に伝わるようゆっくり話す人だ。でも心の中にはこんなに憤りと悲しみを抱えていたのだと知る。米軍基地の爆音、水道水汚染や環境破壊、暴力。『いま、まっただなかで暮らしているひとは、どこに逃げたらいいのかわからない』。その深さを想い、言葉にならない。自身も普天間に暮らしながら、困難を抱える若者の、女性たちの言葉を聞く。受け止め、生きることを助ける。当事者でない私たちができることも、たぶん似ている。耳を澄まし、受け止めること。傍に立つこと。
沖縄県に顕著な、貧困状態にある人の多さを社会問題と大局的に捉え、解決方法を模索することも大事だ。しかしそのデータからは思い及ぶことの難しい、たくさんの若者、女性たちそれぞれの痛み、苦しみ、絶望と諦めがあることは見えづらい。ほんとうに酷い。実の親ですら、そして行政にも頼れない若者たちに差し伸べる手は必ず必要だ。その行為すら阻害されて、諦めて流される背中を見送るのはどんな思いだったろう。そこから、若い母親と乳児を保護し、節目を寿いで送り出すシェルター「おにわ」の立ち上げに繋がっていく。なんと尊い営みか。
沖縄に生まれてもいない、育ってもいない、暮らしてもいない私は徹底的に外野だ。むしろ加害者の側ですらある。その私が、沖縄に、沖縄の人々に対してどうあればよいのかは、ずっと考えていることだ。この本を読んで、書き上げた感想、自分で読んで「きれいごとだ」と感じる。とりあえず、読んで終わりにしないと決める。
読了日:11月13日 著者:上間 陽子

 おらおらでひとりいぐも (河出文庫)の感想
おらおらでひとりいぐも (河出文庫)の感想脳内ひとりごとだだ洩れ系、大好き。止めどのない思考は、濁流となりせせらぎとなり奔流となり、そのときどきの思いに駆られてあっちこっち迷走しながら、人は生きている。辻褄?そんなもん合う訳ないやん。『おらの生ぎるはおらの裁量に任せられているのだな。おらはおらの人生を引き受げる』。女の業もちゃんと書いていて、傷つけた人のこと、離れてしまったきりの人のこと、悔やむけれど、しかたないやん、生きるしかないやん、という苦みも含め、東北弁で書ききったことに喝采をおくる。解説は町田康、これはもうね、当然すぎるね。
読了日:11月12日 著者:若竹千佐子

 福田村事件 -関東大震災・知られざる悲劇の感想
福田村事件 -関東大震災・知られざる悲劇の感想関東大震災直後、デマに煽られて「朝鮮人」9人を虐殺したが、実は香川県からの行商人家族の集団だった。妊婦や幼児まで手にかけ、利根川に遺体を突き流した実在の事件だ。朝鮮人であるか否かの事実に関わらず数百人で少数を暴行のうえ虐殺したこと。国のためだったと言い張って悔いず、有罪判決は不服と上告までしたこと。村人から被告に見舞金を出したこと。歴史に残らないよう揃って口を閉ざしたこと。人間の、不変の愚かさがくっきり出ている。怖いのは事件そのものだけでなく、事件を無かったことのように忘れること。そこにぐらいは抗いたい。
被告のひとりの証言。『日本刀を持って出掛けると群衆のなかから、貴様は見物にきたのかと怒鳴りましたので、ついやったような訳です。私は実際相手を斬ったにもかかわらず、予審で三回も否認したのは、摂政宮殿下には玄米を召し上がられている際、不逞鮮人のために国家はどうなることかと憂れへの余りやったような次第ですが、監獄に入れられたので癪にさわったから、事実を否認したのです』。
被害者の地元の女性の証言。『日本人と朝鮮人とまちがえたということは、香川県の言葉と朝鮮の言葉はそんなに似とるんやろかなあ、なんでかしらんと思っておりました。こちらでは朝鮮の人はよくアメ売りに来ました。その人の言葉はなまりとかでわかりました。あの言葉と讃岐の言葉がなんでわからないのかなあ、関東の人ってひどい人やなあと私は思いました。罪のない人をまちがったか何か知らんけど殺すとはひどいとおもいましたよ。それが頭に残っています』。
香川県内には1990年代で46カ所同和地区があったと聞き、その多さに驚いた。瀬戸内海地方は温暖な気候や、人や物の往来の多さのわりに耕せる土地が少ないため、貧しかったと宮本常一も言っていた。面積が小さい香川県は特に、1軒当たりの農地が狭く、小作率も全国一高かった。そのことが、香川の売薬行商人が全国で2番目に多いなど、行商人が多かった理由だろう。「四国辺土」の遍路のことといい、香川県は災害が少なくて良いなど、わりとのほほんとした風土のように自称するが、なかなか深い闇を抱えているのだと最近になって戦慄している。
読了日:11月08日 著者:辻野弥生

 生命海流 GALAPAGOSの感想
生命海流 GALAPAGOSの感想福岡センセイ、念願叶う。ダーウィンのマーベル号と同じ航路を取ってガラパゴスの島々を旅した記念の誌。装丁も豪華だ。船やコック、ガイドを雇った贅沢な旅とはいえ、自称ニセモノ・ナチュラリストの福岡先生には(きっと私にも)ガラパゴスの自然は厳しいのだろう。それこそ体験しなければわからない。釣竿を持って行ったくらいだから、獲ったり釣ったり生物を子細に観察する機会が全く禁じられたのは誤算だったのではないかしら。ダーウィンの頃は何でもやり放題、捕り放題で大量の標本や剥製を持ち帰ったのにとひき比べてみせるのが微笑ましい。
植物や微生物は『自分たちに必要な分だけ栄養分を作ったり、作ったアンモニアを独占するのではなく、いつも少しだけ多めに活動して、それを他の生命に分け与えてくれた。利己的にならず他を利することもつまり利他性があった。余裕があるところに利他性が生まれ、利他性が生まれると初めて共生が生まれる。利他性はめぐりめぐってまた自分のところに戻ってくる』。そうして何もなかった島に生命は満ちた。生命レベルの利他が無ければ、そもそも生命の繁栄は無かったとの指摘は、壮大で、考えてもみなかったことだった。
読了日:11月05日 著者:福岡 伸一
 オリガ・モリソヴナの反語法 (集英社文庫)の感想
オリガ・モリソヴナの反語法 (集英社文庫)の感想初めての小説とは信じられない。実在するのは教師の存在と電信記録、自身の体験だけ。あとは時代の動乱に絡めた人々の受難の歴史、全て日露の膨大な文献にあたって創りあげた架空とは。ソ連という大きな枠組みの中での、女性たちの受難。子供も無縁でいられない。外国籍の人とのつき合いは用心しなさいと教えられ、キューバ危機の報に初恋の人への告白を決心する。人は時代とも世界とも無縁ではいられない。それがむき出しになるソ連と、何も知らないまま守られる日本のいずれが特別なのか、いずれにせよその落差が人の成熟を決するように感じた。
物語として、凄く面白かった。でもそれは米原さん自身がプラハで過ごした幼少期、そこで得た体験や学び方、知識無しにはあり得なくて、かの地の子どもたちがどのような常識と教養を身につけさせられるか、一方で日本の教育がどのような性質のものであるかを痛感せずにいられない。登場人物の痛みを想像する一方で、我が身のほうも苦いものが残る。よい読書体験でした。
読了日:11月03日 著者:米原 万里

 オーガニック植木屋の庭づくり: 暮らしが広がるガーデンデザインの感想
オーガニック植木屋の庭づくり: 暮らしが広がるガーデンデザインの感想ひきちさんの本は4冊目。内容が劇的に違う訳ではないのだけれど、眺めてはイメージをつくり直す過程を繰り返すのが楽しい。今回は「オーガニックとはなにか」「自分の暮らしに合う庭とは」など大きな、かつ現実的な問い立てから、各アイテムの設置方法、望ましい仕様などを細かく書いている。低いレイズドベッド、バイオネスト、野外炉、インセクトホテル、排水用浸透層、睡蓮鉢、雨庭など、やってみたいけれど自分でやれるのかこれは。なものばかり挙げているな私。ま、実際にやってみるこったな。売っている堆肥の性質、注意点は憶えておきたい。
読了日:11月02日 著者:ひきちガーデンサービス 曳地トシ+曳地義治
注:
 は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。 2023年11月01日
2023年10月の記録
ひと月にこれだけ読めているのに「読めてない!」と感じるのは、
積読の山に追い立てられているからだろう。
客観的には冊数は読めているし、読むべき本も数冊は読んでいる。
晩酌の量を減らせばもっと読めるかもよ、と自分を唆しておく。
一石二鳥。
<今月のデータ>
購入17冊、購入費用20,501円。
読了16冊。
積読本324冊(うちKindle本152冊、Honto本3冊)。

 太陽の黄金(きん)の林檎〔新装版〕 (ハヤカワ文庫SF)の感想
太陽の黄金(きん)の林檎〔新装版〕 (ハヤカワ文庫SF)の感想
皇帝の不興を買う「空飛ぶ機械」や、音を垂れ流す機械をアイスの海に沈める「殺人」など、それぞれテイストが違って凄い。なかでも断然「ぬいとり」が好き。女の手は家の内外に絶え間なく働き、心地よさを、生活を、自他の人生をつくりあげる。まるで意思を持っているかのように動き続ける。もし、明日世界が終わると知ったら、その手は働くことをやめるだろうか? 男の手がとっとと仕事を諦め、動きを止めたとしても、女の手は世界が燃え尽きるその瞬間まで働き続ける、その幻想的な様が素敵。こういうのに出会えるから、短編集は面白い。
読了日:10月29日 著者:レイ ブラッドベリ
 家は生態系―あなたは20万種の生き物と暮らしているの感想
家は生態系―あなたは20万種の生き物と暮らしているの感想
いやぁ面白かった。人間の住む環境は微生物だらけだと私は知っている。見えない微生物が世界に大きな役割を担っているとも知っている。しかし家の中に少なくとも8000種近くの生物がいると聞くとさすがにたじろいだ。布団やソファは無論、冷蔵庫にも給湯器にも水道水にも…? 読者の引きつった顔を想像して楽しむかのように、ロブ・ダンは研究の成果から話を展開していく。現代人はついそれらを殲滅できないかと考えるが、その大半は無害または有益で、殺菌は悪手。家の中も外と同様、多様性があってこそ人間の身体は健全に保たれると指摘する。
トキソプラズマの章が興味深い。人間を含む多くの哺乳類が感染するトキソプラズマ原虫の最終目的地は、ネコ科動物の腸管上皮の内層である。トキソプラズマ原虫は宿主にリスクテイキングな行動を促し、おそらくはネコ科動物に遭遇しやすく(捕食されやすく)していると考えられる。人間は操縦されているのだ。フランスでは全国民の50%以上に不顕性感染の証拠が見られた。アメリカで20%以上。感染率が生活や行動の様式によるなら日本はもっと低いか。自由や冒険への指向性、民族性と絡めると、人類の歴史をも左右し得る壮大なテーマではないか。
読了日:10月28日 著者:ロブ・ダン
 沖縄から貧困がなくならない本当の理由 (光文社新書)の感想
沖縄から貧困がなくならない本当の理由 (光文社新書)の感想
私が知らない沖縄が書かれている。米軍基地問題において、不満を抑え込むためのじゃぶじゃぶの補助金は、確かに自治体を自律失調に陥れているだろう。同調圧力という日本人特性を更に煮詰めたようなシマ社会も、沖縄県民を総じて幸せにはしていないように見える。「真面目(マーメー)」が最大級の侮辱言葉だと沖縄大学の学生は調査に回答したという。出る杭を折れるまでとことんブチのめすとあれば、どういうメンタリティだろう。全国に突出した貧困の原因を、著者は自尊心の低さに見出している。こういう見方があるととりあえず記憶しておく。
読了日:10月25日 著者:樋口 耕太郎
 薬膳ナムル手帖: 野菜のおいしい作りおきの感想
薬膳ナムル手帖: 野菜のおいしい作りおきの感想
ナムル好き。なぜなら手順が簡単。調味料の種類が少ない。野菜が摂れる。味つけに困らない。日持ちがする。そして野菜は1種類でいい。夫も喜んで食べる。それで薬膳?ええやん! というので飛びついた。通年ある野菜でもよし、旬の野菜はもっとよし。にんにくはたくさん刻んでオリーブオイル/ごま油に漬けておくと日持ちするしすぐに使える。オプションもナッツやきくらげなど常備しているようなものでよい。あとは、油を入れすぎてギトギトにして気持ち悪くならないようにつくるだけ。
読了日:10月23日 著者:植木もも子
 保育士よちよち日記――お散歩、お昼寝、おむつ替え…ぜんぜん人手が足りませんの感想
保育士よちよち日記――お散歩、お昼寝、おむつ替え…ぜんぜん人手が足りませんの感想
子どもって驚異だよなあ。毎日預かる大変さは想像を絶する。『保育士の仕事は感情労働だ』と著者は言う。予測不能の事態や理不尽な要求、業務過多といった要素は他の職業と変わらない。しかし危険回避と、子どもは大人の張りぼてを見抜くから、常に感情で向き合うのはしんどいという意味か。一方、園児の好意もストレートに得られて幸せホルモンどばどばなら、自尊心とか叱って思いどおりの行動をさせようとか、くだらなく思えないものだろうか。他職種からの転職組、数々の保育園を経験した派遣保育士だからこその構造的発見もあるとよかった。
園長をトップとした厳格なヒエラルキー組織。組織としては変革しにくいだろう。そうでなくても親や役所や世間に対して「なにかあったら大変」意識が強く、厳格化された統一ルールに従うことを求められる。強烈な閉鎖性と同調圧力を感じる。同僚にも干渉しない。有期契約の著者は「園によって違うよね」と肩をすくめて済ませるが、それではますます保育士のなり手も減り、しんどくなっていくだけなんじゃないか。と、親や祖父母の就労証明書を毎年手書きさせられる労務担当者は思う。
読了日:10月22日 著者:大原 綾希子
 新たなるインド映画の世界の感想
新たなるインド映画の世界の感想
再読。前回より観た本数も回数も増えて、ラーマ王子とシータ姫そうだったのか!などと瞠目すること多し。言語や宗教の多様ぶりもさながら、映画製作自体が各文化圏で独立していること、音楽も分業制になっていて、古典音楽の習得が必須なことなど、奥深くて面白過ぎる。ただし俳優の多くは映画カーストの出身とか、サルマーン・カーンはひき逃げ事件の悪印象を払拭するために「バジュランギおじさん~」で善い人を演じたとか、知りたくないこともままあるものだ。また知りすぎると感性で観られなくなってしまう部分もあるので、程々で。
読了日:10月19日 著者:夏目 深雪,松岡 環,高倉 嘉男,安宅 直子,岡本 敦史,浦川 留
 東京プリズン (河出文庫)の感想
東京プリズン (河出文庫)の感想
過去と現在、現実と幻想が入り交じって読みづらいが、ヘラジカもベトナムの双子も、最後の公開ディベートに向けて主人公を導く存在である。『日本の天皇ヒロヒトには、第二次世界大戦の戦争責任がある』。アメリカ人にこれを言われると、腹にずんと重い衝撃を感じ、反動でぐっとせり上がるものがある。じゃあ日本人は、いくつもの都市を絨毯爆撃し原発を落とし一方的に裁いたアメリカの所業を、どのように考え、何を求めるのか。あの戦争は加害と被害が両輪だ。今は"同盟国"だろうと、お互い何も思わないほど過去ではない。おそらくこれからも。
マッカーサーは昭和天皇に11回も直接会い、話し、天皇という人と在りかたに理解を深めたのだろう。しかし一般に、アメリカ人は大日本帝国憲法や訳語の定義に沿って昭和天皇こそ第一戦犯と捉え、断罪を求める。日本人にとっての天皇を、歴史の浅いアメリカ、さらに一神教を信仰する国民が大多数のアメリカで、理解することはかなり難しいだろう。そして日本人が自分たちにとっての天皇の存在を論理的に説明することもまた難しいことを自覚し、その双方を理解しておく必要がある。ということをこの小説は独特な形で描いている。
願わくば、日本の子供たちに戦争を起こした日本のことをちゃんと教えてください。拠って立つ自国の歴史の真実を知らないまま、心の備えを持たないまま諸外国の人と向き合うなんて、残酷で恥ずかしい事をさせるな。憲法をヘンな文章だねとか主語が無いのなんでとか言いながらでも、知って、考える素地を養うことは義務教育の義務だ。
読了日:10月14日 著者:赤坂 真理
 ひとはなぜ戦争をするのか (講談社学術文庫)の感想
ひとはなぜ戦争をするのか (講談社学術文庫)の感想
アインシュタインとフロイトの往復書簡。1932年、アインシュタインはフロイトなら戦争の問題解決を阻む障害を取り除く方法を示唆できるのではと問うた。手紙は1通ずつで長くはなく、後半は養老先生と斎藤環氏による解説である。アインシュタイン53歳、フロイト76歳、両者ともユダヤ人でナチスの興隆に伴い西側へ亡命した。フロイトは『文化の発展を促せば、戦争の終焉へ向けて歩み出すことができる』と手紙を締めたが、未だそうはならない。パレスチナ/イスラエル紛争の報道を見るにつけ、ユダヤ人すらそうなら、何が希望かと空を仰ぐ。
読了日:10月13日 著者:アルバート アインシュタイン,ジグムント フロイト
 給料の上げ方: 日本人みんなで豊かになるの感想
給料の上げ方: 日本人みんなで豊かになるの感想
「日本人の勝算」を読んだのが2019年。政府に直接働きかけ、大企業中小企業を叱咤し、しかし遅々として変わらない日本。ならばとアトキンソン氏は被雇用者に語りかけることにした。立ち上がれ、自己防衛せよと。経営者側の視点でも有用である。近く負担が重くなる日本で、氏の算出した給与上昇率はベア1.4%、定期昇給2.8%で年4.2%。提供するものに価値があるか。値上げにつながる付加価値を提供できるか、また目指しているか。そのうえで給料を上げ続けることができるか。氏が読者に問いかける要点は、即ち企業の課題である。
GDPや物価の上昇を是とする現状への懐疑心は暫時保留として。労働生産性について少しは理解が及んだように思う。「労働生産性が低い」とは個々人の働きの効率が悪いことではない。人の生みだしたものの価値は、不断の努力によってより高いものになるはずで、さすれば価格は上がるはずで、労働者への分配も上がるべきと考える。違っているかもしれないが、とりあえずそのように納得した。
氏は大企業寄りの論調だったように記憶していたが、今回「従業員100~300人の中堅企業がバランスが良い」としていて、目が留まった。労働分配率も、大企業や零細企業より程良いようだ。『厳しさが増すこれからの時代は、環境の変化を先取りし、その都度対応策を打ちながら規模を拡大させていくのが、もっとも現実的かつ有効な企業の成長の道筋のように感じます。つまり、重要なのは単純な規模の大小ではなく、適切なタイミングで適切な規模へ成長することなのです』。
読了日:10月11日 著者:デービッド・アトキンソン
 辺境の怪書、歴史の驚書、ハードボイルド読書合戦の感想
辺境の怪書、歴史の驚書、ハードボイルド読書合戦の感想
このお二人のセンスで選んだ課題図書を巡っての対談は面白い。辺境に住む民族は未開なのではなく、あえて稲作や道具を放棄した、とか、国境線近くは辺境だが交易の舞台でもある、とか、朝鮮出兵は文化を均質化する効果をもたらした、とか、数多の研究結果、見聞録から、自身の体験も含めて考え併せ、「世界の見方」をつくっていくのだ。点と点が繋がって"知の網"になる。高野さんはそれを「教養」の形成過程と感じたという。文明や豊かさについて考え直すことの知的興奮はこちらにも伝染して、自分がどんどん「常識」から外れていくのが楽しい。
読了日:10月10日 著者:高野 秀行,清水 克行
 ガルヴェイアスの犬 (新潮クレスト・ブックス)の感想
ガルヴェイアスの犬 (新潮クレスト・ブックス)の感想
小さな村、ガルヴェイアス。ある日宇宙から落ちてきた巨大な物の正体が何なのかは最後までわからない。ただ空気中に硫黄の臭いが満ち、パンは不味くなった。想像しただけでもしんどい。それでも人は弱くも、愚かにも、悲しくも、だましだまし生きていく。小さな村の人間関係は絡まり合っている。あるエピソードに登場する脇役が次のエピソードの主役になり、関係が輪郭を取りながら物語は進む。郵便配達人のジャネイロは、1年に1度訪れるギニアの地で人が変わったように生き生きとする。それでもガルヴェイアスに戻るのは、自分の場所だからか。
『誰にだって、運命の場所ってもんがあるのさ。誰の世界にも中心がある。あたしの場所はあんたのよりましだとか、そんなことは関係ないの。自分の場所ってのは他人のそれと比べるようなものじゃない。自分だけの大事なもんだからね。どこにあるかなんて、自分にしかわからないの。みんなの目に見える物にはその形の上に見えない層がいくつも重なっているんだ。自分の場所をだれかに説明しようったって無理だよ、わかっちゃもらえないからね』
読み終えたら、また最初から読みたくなる。ひとつには、人柄や人間関係がひととおりわかったから、改めてその人たちの行ないを違った目で見られること。ひとつには、一度気づいたからといって、小さな村の人々は暮らしかたを変えてしまえたりはしなくて、また同じループを数年ごと、数十年ごとに繰り返すだろうから。エンドレスなのだ。
読了日:10月09日 著者:ジョゼ・ルイス ペイショット
 「昭和天皇実録」の謎を解く (文春新書)の感想
「昭和天皇実録」の謎を解く (文春新書)の感想
宮内庁が編纂した昭和天皇の実録は61冊に及ぶという。生涯通じた記録の中でも、対談の焦点は戦前から戦後に集中する。最初から軍人として育てられた唯一の天皇。立憲君主として、神の子孫として、また軍の総統としてのお立場がある故の相克の深さを読み解く。止めることができない懊悩でやせ細る陛下の様子、実母である皇太后に疎開を拒否された日の苦しみなど、私には厳しそうで怖いおじいさんでしかなかった昭和天皇が一人の若い人間として像を結んだ。いたわしい、と思った。他方で、実録編纂の目的に天皇像の形成がある点も留めておきたい。
『我が国は軍事国家だったんだなあと、しみじみわかりました。もう、軍事のことばかりですよ』(半藤)。戦況が悪くなる前から、軍部は本当の戦況を陛下に報告しない。陛下にもそれがわかっていたから、アメリカの短波放送を頼りにご自身で情報を得、あるべき方向を模索していたという。担ぎ上げながら、天皇の意志を平然と無視する陸軍。『軍部にとって天皇とは、最高指揮官などではなく、神殿の壁のようなもの』だったとする半藤さんの評が印象深い。
読了日:10月07日 著者:半藤 一利,御厨 貴,磯田 道史,保阪 正康
 (074)船 (百年文庫)の感想
(074)船 (百年文庫)の感想
海。日本のまわりを囲む海。ある日は荒れ、ある日は凪ぐ水面の上で、隔絶された船の上では大漁に高揚したり漂流に絶望したりと、ぎゅっと濃縮された人間模様が展開される。なににしてもダイナミックな様相を見せる海の上だからだろうか、あるいは狭い船の上で強調して見えるからだろうか、人々の心の動きもダイナミックに描かれる3篇。なかでも「海神丸」は約2カ月もの太平洋漂流である。陸を離れて何千年も経ったようなと思われるほど、簡単には訪れない死、また一方で簡単に訪れる死。その非業の様相にもまた、海は何を思うことなく在るのみだ。
読了日:10月07日 著者:近藤 啓太郎,野上 弥生子,徳田 秋声
 新編 日本の面影 (2) (角川ソフィア文庫)の感想
新編 日本の面影 (2) (角川ソフィア文庫)の感想
『私この小泉八雲、日本人よりも本当の日本を愛するです』。引き続き日本愛に満ちた文章。雑誌に掲載する体裁ではなく、本当に愛していたのだとしみじみ読む。「伯耆から隠岐へ」は逸品だ。蒸気船に乗るくだりなどは、乗り心地の悪さに閉口したことを軽妙に書くのも楽しそうだ。一方、帰りの便では穏やかな憂鬱を描き切る、こちらも印象が深い。物質社会から離れた自然への敬慕。晩年に東京の西大久保に屋敷を買って住むのに、静かな環境と和の設えを喜んだという。『余り喜ぶの余りまた心配です。この家に住む事永いを喜びます』。2年余で死去。
読了日:10月03日 著者:ラフカディオ・ハーン
 サピエンス日本上陸 3万年前の大航海の感想
サピエンス日本上陸 3万年前の大航海の感想
人類は3万5000年前に琉球列島に到達し、5000年の間に日本列島全体に拡がったとされる。その過程を検証するプロジェクト。今の日本人の祖となるだけの人々が、広大な大陸から、島影の見えない海へ、漕ぎ出そうと考えたのはなぜか。海面下がどうなっているか、目指す地がどの方向にあるかわからない。失敗は死に直結した。著者は『海に立ち向かった挑戦者』と結論する。人類は直ちに必要のない事に挑む。命がけの遊びを面白がるのは現代も同じだ。拡大解釈すれば、人類が瞬く間に地球全体に拡がって支配者となった理由も。悪い気はしない。
狩猟採集民であった先祖は現代人よりも身体能力に優れ、生きるための必要以上のことに好奇心を持って挑み、技術は無くとも物を創る能力に長けていた。彼らを、現代の自分たちより劣ったものとして考える癖が染みついているのを自覚する。これを鮮やかに取り払いたいと考えている。その流れとしてグレーバーの新刊を読みたい。しかし5,500円か…。
読了日:10月01日 著者:海部 陽介
注: は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。
積読の山に追い立てられているからだろう。
客観的には冊数は読めているし、読むべき本も数冊は読んでいる。
晩酌の量を減らせばもっと読めるかもよ、と自分を唆しておく。
一石二鳥。
<今月のデータ>
購入17冊、購入費用20,501円。
読了16冊。
積読本324冊(うちKindle本152冊、Honto本3冊)。

 太陽の黄金(きん)の林檎〔新装版〕 (ハヤカワ文庫SF)の感想
太陽の黄金(きん)の林檎〔新装版〕 (ハヤカワ文庫SF)の感想皇帝の不興を買う「空飛ぶ機械」や、音を垂れ流す機械をアイスの海に沈める「殺人」など、それぞれテイストが違って凄い。なかでも断然「ぬいとり」が好き。女の手は家の内外に絶え間なく働き、心地よさを、生活を、自他の人生をつくりあげる。まるで意思を持っているかのように動き続ける。もし、明日世界が終わると知ったら、その手は働くことをやめるだろうか? 男の手がとっとと仕事を諦め、動きを止めたとしても、女の手は世界が燃え尽きるその瞬間まで働き続ける、その幻想的な様が素敵。こういうのに出会えるから、短編集は面白い。
読了日:10月29日 著者:レイ ブラッドベリ

 家は生態系―あなたは20万種の生き物と暮らしているの感想
家は生態系―あなたは20万種の生き物と暮らしているの感想いやぁ面白かった。人間の住む環境は微生物だらけだと私は知っている。見えない微生物が世界に大きな役割を担っているとも知っている。しかし家の中に少なくとも8000種近くの生物がいると聞くとさすがにたじろいだ。布団やソファは無論、冷蔵庫にも給湯器にも水道水にも…? 読者の引きつった顔を想像して楽しむかのように、ロブ・ダンは研究の成果から話を展開していく。現代人はついそれらを殲滅できないかと考えるが、その大半は無害または有益で、殺菌は悪手。家の中も外と同様、多様性があってこそ人間の身体は健全に保たれると指摘する。
トキソプラズマの章が興味深い。人間を含む多くの哺乳類が感染するトキソプラズマ原虫の最終目的地は、ネコ科動物の腸管上皮の内層である。トキソプラズマ原虫は宿主にリスクテイキングな行動を促し、おそらくはネコ科動物に遭遇しやすく(捕食されやすく)していると考えられる。人間は操縦されているのだ。フランスでは全国民の50%以上に不顕性感染の証拠が見られた。アメリカで20%以上。感染率が生活や行動の様式によるなら日本はもっと低いか。自由や冒険への指向性、民族性と絡めると、人類の歴史をも左右し得る壮大なテーマではないか。
読了日:10月28日 著者:ロブ・ダン
 沖縄から貧困がなくならない本当の理由 (光文社新書)の感想
沖縄から貧困がなくならない本当の理由 (光文社新書)の感想私が知らない沖縄が書かれている。米軍基地問題において、不満を抑え込むためのじゃぶじゃぶの補助金は、確かに自治体を自律失調に陥れているだろう。同調圧力という日本人特性を更に煮詰めたようなシマ社会も、沖縄県民を総じて幸せにはしていないように見える。「真面目(マーメー)」が最大級の侮辱言葉だと沖縄大学の学生は調査に回答したという。出る杭を折れるまでとことんブチのめすとあれば、どういうメンタリティだろう。全国に突出した貧困の原因を、著者は自尊心の低さに見出している。こういう見方があるととりあえず記憶しておく。
読了日:10月25日 著者:樋口 耕太郎

 薬膳ナムル手帖: 野菜のおいしい作りおきの感想
薬膳ナムル手帖: 野菜のおいしい作りおきの感想ナムル好き。なぜなら手順が簡単。調味料の種類が少ない。野菜が摂れる。味つけに困らない。日持ちがする。そして野菜は1種類でいい。夫も喜んで食べる。それで薬膳?ええやん! というので飛びついた。通年ある野菜でもよし、旬の野菜はもっとよし。にんにくはたくさん刻んでオリーブオイル/ごま油に漬けておくと日持ちするしすぐに使える。オプションもナッツやきくらげなど常備しているようなものでよい。あとは、油を入れすぎてギトギトにして気持ち悪くならないようにつくるだけ。
読了日:10月23日 著者:植木もも子
 保育士よちよち日記――お散歩、お昼寝、おむつ替え…ぜんぜん人手が足りませんの感想
保育士よちよち日記――お散歩、お昼寝、おむつ替え…ぜんぜん人手が足りませんの感想子どもって驚異だよなあ。毎日預かる大変さは想像を絶する。『保育士の仕事は感情労働だ』と著者は言う。予測不能の事態や理不尽な要求、業務過多といった要素は他の職業と変わらない。しかし危険回避と、子どもは大人の張りぼてを見抜くから、常に感情で向き合うのはしんどいという意味か。一方、園児の好意もストレートに得られて幸せホルモンどばどばなら、自尊心とか叱って思いどおりの行動をさせようとか、くだらなく思えないものだろうか。他職種からの転職組、数々の保育園を経験した派遣保育士だからこその構造的発見もあるとよかった。
園長をトップとした厳格なヒエラルキー組織。組織としては変革しにくいだろう。そうでなくても親や役所や世間に対して「なにかあったら大変」意識が強く、厳格化された統一ルールに従うことを求められる。強烈な閉鎖性と同調圧力を感じる。同僚にも干渉しない。有期契約の著者は「園によって違うよね」と肩をすくめて済ませるが、それではますます保育士のなり手も減り、しんどくなっていくだけなんじゃないか。と、親や祖父母の就労証明書を毎年手書きさせられる労務担当者は思う。
読了日:10月22日 著者:大原 綾希子

 新たなるインド映画の世界の感想
新たなるインド映画の世界の感想再読。前回より観た本数も回数も増えて、ラーマ王子とシータ姫そうだったのか!などと瞠目すること多し。言語や宗教の多様ぶりもさながら、映画製作自体が各文化圏で独立していること、音楽も分業制になっていて、古典音楽の習得が必須なことなど、奥深くて面白過ぎる。ただし俳優の多くは映画カーストの出身とか、サルマーン・カーンはひき逃げ事件の悪印象を払拭するために「バジュランギおじさん~」で善い人を演じたとか、知りたくないこともままあるものだ。また知りすぎると感性で観られなくなってしまう部分もあるので、程々で。
読了日:10月19日 著者:夏目 深雪,松岡 環,高倉 嘉男,安宅 直子,岡本 敦史,浦川 留
 東京プリズン (河出文庫)の感想
東京プリズン (河出文庫)の感想過去と現在、現実と幻想が入り交じって読みづらいが、ヘラジカもベトナムの双子も、最後の公開ディベートに向けて主人公を導く存在である。『日本の天皇ヒロヒトには、第二次世界大戦の戦争責任がある』。アメリカ人にこれを言われると、腹にずんと重い衝撃を感じ、反動でぐっとせり上がるものがある。じゃあ日本人は、いくつもの都市を絨毯爆撃し原発を落とし一方的に裁いたアメリカの所業を、どのように考え、何を求めるのか。あの戦争は加害と被害が両輪だ。今は"同盟国"だろうと、お互い何も思わないほど過去ではない。おそらくこれからも。
マッカーサーは昭和天皇に11回も直接会い、話し、天皇という人と在りかたに理解を深めたのだろう。しかし一般に、アメリカ人は大日本帝国憲法や訳語の定義に沿って昭和天皇こそ第一戦犯と捉え、断罪を求める。日本人にとっての天皇を、歴史の浅いアメリカ、さらに一神教を信仰する国民が大多数のアメリカで、理解することはかなり難しいだろう。そして日本人が自分たちにとっての天皇の存在を論理的に説明することもまた難しいことを自覚し、その双方を理解しておく必要がある。ということをこの小説は独特な形で描いている。
願わくば、日本の子供たちに戦争を起こした日本のことをちゃんと教えてください。拠って立つ自国の歴史の真実を知らないまま、心の備えを持たないまま諸外国の人と向き合うなんて、残酷で恥ずかしい事をさせるな。憲法をヘンな文章だねとか主語が無いのなんでとか言いながらでも、知って、考える素地を養うことは義務教育の義務だ。
読了日:10月14日 著者:赤坂 真理

 ひとはなぜ戦争をするのか (講談社学術文庫)の感想
ひとはなぜ戦争をするのか (講談社学術文庫)の感想アインシュタインとフロイトの往復書簡。1932年、アインシュタインはフロイトなら戦争の問題解決を阻む障害を取り除く方法を示唆できるのではと問うた。手紙は1通ずつで長くはなく、後半は養老先生と斎藤環氏による解説である。アインシュタイン53歳、フロイト76歳、両者ともユダヤ人でナチスの興隆に伴い西側へ亡命した。フロイトは『文化の発展を促せば、戦争の終焉へ向けて歩み出すことができる』と手紙を締めたが、未だそうはならない。パレスチナ/イスラエル紛争の報道を見るにつけ、ユダヤ人すらそうなら、何が希望かと空を仰ぐ。
読了日:10月13日 著者:アルバート アインシュタイン,ジグムント フロイト

 給料の上げ方: 日本人みんなで豊かになるの感想
給料の上げ方: 日本人みんなで豊かになるの感想「日本人の勝算」を読んだのが2019年。政府に直接働きかけ、大企業中小企業を叱咤し、しかし遅々として変わらない日本。ならばとアトキンソン氏は被雇用者に語りかけることにした。立ち上がれ、自己防衛せよと。経営者側の視点でも有用である。近く負担が重くなる日本で、氏の算出した給与上昇率はベア1.4%、定期昇給2.8%で年4.2%。提供するものに価値があるか。値上げにつながる付加価値を提供できるか、また目指しているか。そのうえで給料を上げ続けることができるか。氏が読者に問いかける要点は、即ち企業の課題である。
GDPや物価の上昇を是とする現状への懐疑心は暫時保留として。労働生産性について少しは理解が及んだように思う。「労働生産性が低い」とは個々人の働きの効率が悪いことではない。人の生みだしたものの価値は、不断の努力によってより高いものになるはずで、さすれば価格は上がるはずで、労働者への分配も上がるべきと考える。違っているかもしれないが、とりあえずそのように納得した。
氏は大企業寄りの論調だったように記憶していたが、今回「従業員100~300人の中堅企業がバランスが良い」としていて、目が留まった。労働分配率も、大企業や零細企業より程良いようだ。『厳しさが増すこれからの時代は、環境の変化を先取りし、その都度対応策を打ちながら規模を拡大させていくのが、もっとも現実的かつ有効な企業の成長の道筋のように感じます。つまり、重要なのは単純な規模の大小ではなく、適切なタイミングで適切な規模へ成長することなのです』。
読了日:10月11日 著者:デービッド・アトキンソン

 辺境の怪書、歴史の驚書、ハードボイルド読書合戦の感想
辺境の怪書、歴史の驚書、ハードボイルド読書合戦の感想このお二人のセンスで選んだ課題図書を巡っての対談は面白い。辺境に住む民族は未開なのではなく、あえて稲作や道具を放棄した、とか、国境線近くは辺境だが交易の舞台でもある、とか、朝鮮出兵は文化を均質化する効果をもたらした、とか、数多の研究結果、見聞録から、自身の体験も含めて考え併せ、「世界の見方」をつくっていくのだ。点と点が繋がって"知の網"になる。高野さんはそれを「教養」の形成過程と感じたという。文明や豊かさについて考え直すことの知的興奮はこちらにも伝染して、自分がどんどん「常識」から外れていくのが楽しい。
読了日:10月10日 著者:高野 秀行,清水 克行

 ガルヴェイアスの犬 (新潮クレスト・ブックス)の感想
ガルヴェイアスの犬 (新潮クレスト・ブックス)の感想小さな村、ガルヴェイアス。ある日宇宙から落ちてきた巨大な物の正体が何なのかは最後までわからない。ただ空気中に硫黄の臭いが満ち、パンは不味くなった。想像しただけでもしんどい。それでも人は弱くも、愚かにも、悲しくも、だましだまし生きていく。小さな村の人間関係は絡まり合っている。あるエピソードに登場する脇役が次のエピソードの主役になり、関係が輪郭を取りながら物語は進む。郵便配達人のジャネイロは、1年に1度訪れるギニアの地で人が変わったように生き生きとする。それでもガルヴェイアスに戻るのは、自分の場所だからか。
『誰にだって、運命の場所ってもんがあるのさ。誰の世界にも中心がある。あたしの場所はあんたのよりましだとか、そんなことは関係ないの。自分の場所ってのは他人のそれと比べるようなものじゃない。自分だけの大事なもんだからね。どこにあるかなんて、自分にしかわからないの。みんなの目に見える物にはその形の上に見えない層がいくつも重なっているんだ。自分の場所をだれかに説明しようったって無理だよ、わかっちゃもらえないからね』
読み終えたら、また最初から読みたくなる。ひとつには、人柄や人間関係がひととおりわかったから、改めてその人たちの行ないを違った目で見られること。ひとつには、一度気づいたからといって、小さな村の人々は暮らしかたを変えてしまえたりはしなくて、また同じループを数年ごと、数十年ごとに繰り返すだろうから。エンドレスなのだ。
読了日:10月09日 著者:ジョゼ・ルイス ペイショット
 「昭和天皇実録」の謎を解く (文春新書)の感想
「昭和天皇実録」の謎を解く (文春新書)の感想宮内庁が編纂した昭和天皇の実録は61冊に及ぶという。生涯通じた記録の中でも、対談の焦点は戦前から戦後に集中する。最初から軍人として育てられた唯一の天皇。立憲君主として、神の子孫として、また軍の総統としてのお立場がある故の相克の深さを読み解く。止めることができない懊悩でやせ細る陛下の様子、実母である皇太后に疎開を拒否された日の苦しみなど、私には厳しそうで怖いおじいさんでしかなかった昭和天皇が一人の若い人間として像を結んだ。いたわしい、と思った。他方で、実録編纂の目的に天皇像の形成がある点も留めておきたい。
『我が国は軍事国家だったんだなあと、しみじみわかりました。もう、軍事のことばかりですよ』(半藤)。戦況が悪くなる前から、軍部は本当の戦況を陛下に報告しない。陛下にもそれがわかっていたから、アメリカの短波放送を頼りにご自身で情報を得、あるべき方向を模索していたという。担ぎ上げながら、天皇の意志を平然と無視する陸軍。『軍部にとって天皇とは、最高指揮官などではなく、神殿の壁のようなもの』だったとする半藤さんの評が印象深い。
読了日:10月07日 著者:半藤 一利,御厨 貴,磯田 道史,保阪 正康

 (074)船 (百年文庫)の感想
(074)船 (百年文庫)の感想海。日本のまわりを囲む海。ある日は荒れ、ある日は凪ぐ水面の上で、隔絶された船の上では大漁に高揚したり漂流に絶望したりと、ぎゅっと濃縮された人間模様が展開される。なににしてもダイナミックな様相を見せる海の上だからだろうか、あるいは狭い船の上で強調して見えるからだろうか、人々の心の動きもダイナミックに描かれる3篇。なかでも「海神丸」は約2カ月もの太平洋漂流である。陸を離れて何千年も経ったようなと思われるほど、簡単には訪れない死、また一方で簡単に訪れる死。その非業の様相にもまた、海は何を思うことなく在るのみだ。
読了日:10月07日 著者:近藤 啓太郎,野上 弥生子,徳田 秋声
 新編 日本の面影 (2) (角川ソフィア文庫)の感想
新編 日本の面影 (2) (角川ソフィア文庫)の感想『私この小泉八雲、日本人よりも本当の日本を愛するです』。引き続き日本愛に満ちた文章。雑誌に掲載する体裁ではなく、本当に愛していたのだとしみじみ読む。「伯耆から隠岐へ」は逸品だ。蒸気船に乗るくだりなどは、乗り心地の悪さに閉口したことを軽妙に書くのも楽しそうだ。一方、帰りの便では穏やかな憂鬱を描き切る、こちらも印象が深い。物質社会から離れた自然への敬慕。晩年に東京の西大久保に屋敷を買って住むのに、静かな環境と和の設えを喜んだという。『余り喜ぶの余りまた心配です。この家に住む事永いを喜びます』。2年余で死去。
読了日:10月03日 著者:ラフカディオ・ハーン

 サピエンス日本上陸 3万年前の大航海の感想
サピエンス日本上陸 3万年前の大航海の感想人類は3万5000年前に琉球列島に到達し、5000年の間に日本列島全体に拡がったとされる。その過程を検証するプロジェクト。今の日本人の祖となるだけの人々が、広大な大陸から、島影の見えない海へ、漕ぎ出そうと考えたのはなぜか。海面下がどうなっているか、目指す地がどの方向にあるかわからない。失敗は死に直結した。著者は『海に立ち向かった挑戦者』と結論する。人類は直ちに必要のない事に挑む。命がけの遊びを面白がるのは現代も同じだ。拡大解釈すれば、人類が瞬く間に地球全体に拡がって支配者となった理由も。悪い気はしない。
狩猟採集民であった先祖は現代人よりも身体能力に優れ、生きるための必要以上のことに好奇心を持って挑み、技術は無くとも物を創る能力に長けていた。彼らを、現代の自分たちより劣ったものとして考える癖が染みついているのを自覚する。これを鮮やかに取り払いたいと考えている。その流れとしてグレーバーの新刊を読みたい。しかし5,500円か…。
読了日:10月01日 著者:海部 陽介

注:
 は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。 2023年10月02日
2023年9月の記録
こうして見ると先月はKindle本ばかり読んでいる。
細切れの読書が増えているということか。
そうすると「あんまり読めてない」感覚がして不満も高まりがちだ。
しかし実際は本腰で読む本も読めているので、意外に感じた。
<今月のデータ>
購入13冊、購入費用8,679円。
読了12冊。
積読本321冊(うちKindle本156冊、Honto本3冊)。

 怪談四代記 八雲のいたずら (講談社文庫)の感想
怪談四代記 八雲のいたずら (講談社文庫)の感想
ラフカディオ・ハーンを曾祖父に持つ学者の随筆。ハーンはギリシャとアイルランドにルーツがある。どちらも一神教一辺倒ではない国だ。神ではない、人に働きかける見えざる存在への親和性はありそうだ。もちろん日本も。私は彼を故国喪失者として見ている部分がある。ハーンは日本に渡って落ち着き、日本の暮らしを楽しんだ。しかし、明治の松江の人々は紅毛だ鬼だと疎み、盆踊りを観ているところへ砂を投げかけられたと記録が残っている。「日本の面影」にはそんな気配は露ほども見せない。仕方ないとはいえ、切ないことだ。
読了日:09月24日 著者:小泉 凡
 鬼はもとより (徳間文庫)の感想
鬼はもとより (徳間文庫)の感想
藩札という地域通貨のようなシステムを使って藩の財政を立て直すという、経済小説のような時代小説。池井戸潤の江戸時代版みたい。商人と武士の立ち位置の違いについて『利を生むための視野の広さを、国の成り立ちを考える際の視野の広さと混同してはならない。二つはまったく別物であり、そもそも見ている景色がちがう』って現代日本の政治経済を牛耳ってる奴らに聞かせてやりたいね。江戸はなぜ武士が為政者だったのだろうか。重たい覚悟を背負った、武士らしい施政。鬼を引き受ける。数多の命を預かるならば、国を治める者はそうあるべきかと。
読了日:09月23日 著者:青山 文平
 日本語の大疑問 眠れなくなるほど面白い ことばの世界 (幻冬舎新書)の感想
日本語の大疑問 眠れなくなるほど面白い ことばの世界 (幻冬舎新書)の感想
国立国語研究所の錚々たる研究者の方々が身近な質問に答える。「させていただいてもよろしいですか?」というややこしい言葉について、『非敬語ではより近い言葉へ、敬語ではより遠い言葉へ、というのが現在の日本語におけるポライトネス意識』としたうえで、距離感と敬意の度合い="遠近"をひとつの言葉にぶっこむ用法と説明する。ユピック・エスキモーの家族の概念や、下駄は外国語で男性名詞か女性名詞かなど、文化の違いにまで考えを及ばせるようなネタが興味深い。カンナダ語の歌を何度聞いても歌えず笑い出してしまう理由もよくわかった。
『拍感覚に慣れていない学習者にとっては、一拍を正しく聞き取ったり、発音したりすることが難しくなります。特に、促音や長音、撥音のリズムは、母語においてそれらを一拍として捉えることをしない多くの学習者にとって難しいのです』。
読了日:09月22日 著者:国立国語研究所編
 土と内臓―微生物がつくる世界 ( )の感想
土と内臓―微生物がつくる世界 ( )の感想
どわー、壮大な微生物の力に圧倒される。著者が『自然の隠れた半分』と呼ぶように、地球上の生物のほとんどは肉眼で見えない。植物と土壌生物、人間と腸内生物の共生。どちらにも言えることは、科学の力で人間にとっての栄養素、植物にとっての有益物質はわかってきているけれど、それが全てじゃない。だから、必要とわかっている栄養素だけ摂ったのではだめなのだ。目先ではよく効くサプリや肥料が喧伝されても、目に見えない部分をじっと想定する胆力が必要。ましてや安易に殺生物剤や抗生物質でマイクロバイオームを攪乱するべきではないだろう。
うちの猫のことを考える。不調があって獣医のところへ行くと、まず抗生物質を処方される。それでたいていの異変は治まる。だけど、その度彼らの腸内に起きていたことを想像すると心穏やかでない。せめてその後の食餌を心がけて整える必要がある。そう、食餌も。総合栄養食を定量与えるのが常識的な責務になっているが、それだけで良い訳がない。様々な食材が必要だ。魚、肉、欲しがるなら野菜、草。いずれは土の上を歩かせてやりたいなあ。そういえば人間や自分の尻を舐めたり、猫同士舐め合ったりするのも微生物の移動・交換にあたるのではないか。
読了日:09月21日 著者:デイビッド・モントゴメリー,アン・ビクレー
 図書館島 (海外文学セレクション)の感想
図書館島 (海外文学セレクション)の感想
島に育った少年は魔術のごとき異国の文字を学び、本から知った彼方の世界に憧れる。故郷を出て、本の中で読んだ都市の生活を見る。世界にはもっとたくさんの本があって、それも地域によって思想や文化、歴史は様々と知る。一方で、出会う人との関係が深くなるうち、ひとりの人の胸の奥にも物語があると知る。誰かがそれを文字に記すことで、物語は時代を超え、人の間を渡っていくことができる。だけど、記されないものも限りなくあるんだって気づくのだ。それも含めて「図書館」なのかな? 原題「A STRANGER IN OLONDRIA」。
『本とは砦であり、嘆きの場所であり、砂漠に至る鍵であり、橋のない川であり、槍の並ぶ庭なのだ』。この物語は長い。長い物語の先にこの言葉があって、沁みた。
読了日:09月18日 著者:ソフィア・サマター
 医療にたかるな (新潮新書)の感想
医療にたかるな (新潮新書)の感想
行政、職員、医者、住民、メディアの全員に財政破綻の原因と責任がある。夕張市の事例はわかりやすいし、総人口が減る一方で高齢者比率と社会保障費率が増大する日本では、明日は我が身だ。市民の要望を叶えるのではなく、どの施策が問題を解決するかを数値と検証で見極める必要がある。個人のモラルで軽々に医者にかからないのがいちばんと思っていたけれど、予防接種と検診の受診率は医療費に相関すること、口腔ケアも重要と知った。これから行政は間違いなく行き届かなくなる。頼らないだけではだめで、個人の自発性と工夫が問われると心得る。
目先の営利を求める医療機関と、不安がるくせに事実を見ない患者の共依存が医療費の増大を招く。自治体の『医療費が高いということは「住民の健康意識が低く、病人が多い」ということです』。住民の甘えに対して著者は厳しい。皆で払った税金を正しく使う方法を、私たちは解ってないんだろう。自身の健康を医者ではなく自らで管理し、一定のリスクはあるものと認め、QOLを考えること。小川淳也代議士が北欧の医療制度について視察をしてきて、似たようなことを言っていたと思い出す。それが自立ってことなんだろう。
読了日:09月13日 著者:村上 智彦
 ソロモンの指環―動物行動学入門 (ハヤカワ文庫NF)の感想
ソロモンの指環―動物行動学入門 (ハヤカワ文庫NF)の感想
ローレンツが初めて書いた本。楽しい読み物だ。世間でも興味から様々な動物を飼うことが珍しくなかった時代に、ローレンツは科学的な目で観察した。imprintingで有名だが、より動物の視点、論理に近づこうとする姿勢が新鮮だったのではないかと思う。主に『逃げようとすればいつでも逃げられるのに、私のそばにとどまっている』半分飼い馴らされた動物たちが主役で、特にコクマルガラスの章が興味深かった。動物本来の遺伝的行動と馴致の影響が葛藤する様もローレンツは観察している。原題は「彼、けものども、鳥ども、魚どもと語りき」。
ライアル・ワトソンがローレンツに師事するのを拒んだというのは前に知っていた。動物を意図的/非意図的に飼い馴らして観察したローレンツと、野性の中に人間がいる状態で育ったワトソンとでは、動物のあるべき姿への考え方も、アプローチも立ち位置も違いすぎて、聞きかじりながら、ワトソンは受け入れることができなかったのではと推測する。結局ワトソンはデズモンド・モリスに師事したのだったか。そちらも読まなければ。
読了日:09月11日 著者:コンラート ローレンツ
 瀬戸内文化誌の感想
瀬戸内文化誌の感想
海と海の民に焦点を当てた論考集。特に漁業の手法に詳しい。さて古来、瀬戸内海は日本各地から京阪への航路として要衝だった。人々はその時代の需要に合わせて、各地各島で様々な産業を手掛け、生計としてきた。しかし決して裕福ではなかったと宮本常一翁は言う。山地が多く、人が増えても養うための土地が少ない。土地の生産力が足りない。増えてはあぶれ、出稼ぎや海賊、遊女に身を落としたという。波のない内海を絶えず大小の船が航行する。潮や天候の具合によって走り、泊まり、名所を見物し、また無事を願う神事を行なう、歴史の末に今がある。
瀬戸内海を横断するフェリーに乗った。昔より少々視点が高いが、岸を離れたらちっぽけなもので、海、空、島、船が目まぐるしく移り変わっていくのを飽かずただ眺める。動く絵巻物のようだと言った旅行者の気持ちがわかる。美しい。もらった海図によると、安全に航行できるルートは非常に限られている。ざあざあ音を立てて流れる瀬戸は大きな船でも思うようには任せず、海底が浅くなっている難所も多い。こんなところで、島を回り込んだ途端にかがり火を焚いた海賊の小舟が一斉に飛び出してくる、なんて妄想をしては震えあがった事でした。
読了日:09月08日 著者:宮本常一
 満願 (新潮文庫)の感想
満願 (新潮文庫)の感想
売れに売れたと記憶している短編集。久しぶりの米澤穂信のミステリを、私は楽しみ切ったとはいえない。人の心に巣くう打算に興味がなくなったからだろうか。こちらも知識や経験を積み上げ、世にもっと不思議な事象や数奇があると知ってしまったからだろうか。意表を突かれる感覚がないまま淡々と読んでしまう。切ないことだ。こうなっては、「折れた竜骨」のようなファンタジー系の特殊設定か、「万灯」のように海外事情を織り込むとかいった奇策が必要かもしれない。といって、昨今は海外ミステリも各国からのが日本語で読めるから、難しいかな。
読了日:09月07日 著者:米澤 穂信
 地獄変の感想
地獄変の感想
これは立派にミステリ。深く読むほどに凄惨な絵図。猿が助けを求めたのは何故なのか。大殿様はなぜ顔色を変えたのか。なぜ良秀の娘が"罪人"なのか。仕掛けが細かい。伏線は回収されない。私は大殿様が最も恐ろしい。あれが正気の沙汰か。語り手は何も疑っていないが、読み手はそのとおり信じることができない。良秀の人間性を嫌っていた。のみならず、娘に思うところがあったとしか考えられないではないか。片や良秀は、おそらく結末をわかっていた。わかったうえで、大殿様に頼んだ。そして望んだものを得た。『奈落には己の娘が待っている』。
読了日:09月04日 著者:芥川 竜之介
 警視庁 生きものがかりの感想
警視庁 生きものがかりの感想
「生きものがかり」なんて優しそうな響きだから、迷子ペットの捜索するのかと思いきや、その実は希少野生動植物密売捜査。密輸入ブローカーが関西ルートで業者にだの、タイの密輸マーケットへの供給ルートを仕切る組織が国際テロ組織と連携だのと、ガチの警察組織だった。そもそもなぜ密輸するかと言えば、そこにカネが絡むからだ。愛じゃない。生きものを扱うゆえに環境省や動物園/水族館と連携したり、市民への啓発活動になりそうな事案を選んだりと、捜査する側によほど愛を感じる。ジーンズのポケットにスローロリス入れて飛行機に乗るなよ…。
一度密輸された動物を原産地へ戻すのは厳禁事項と知った。原産地に存在しない菌や病気をつけて戻したら、原産地の生態系に壊滅的な影響を与えかねないからだ。戻してやりたい気持ちはやまやまなんだけど、ごめんなあ、悪い人間のせいで。同じ種でも違う地域で生まれた雌雄を交配するのも、遺伝子の系列が交雑するのでタブー。そういうときに、動物園/水族館や研究機関は受け皿になるのだそうで。いろんな事情や役割があるのだなあ。
読了日:09月02日 著者:福原 秀一郎
 クマ問題を考える 野生動物生息域拡大期のリテラシー (ヤマケイ新書)の感想
クマ問題を考える 野生動物生息域拡大期のリテラシー (ヤマケイ新書)の感想
Oso18のニュースから。クマは雑食性なので肉を喰う。ただ、喰うために生きている人間や家畜を繰り返し襲うのは、リスクが比較的小さく、出産や冬眠のための栄養を貯めるのに効率的だと学習してしまったかららしい。人間が森林を開発して野生動物の生息域に干渉し、人間の居住地と森林の間に緩衝帯を維持せず、野生動物を森林に追い戻す行動を積極的に取らないことが事態を悪化させているという。飼い犬を外に放さなくなったのも大きい。犬による咬傷事故回避や狂犬病予防と、野生動物の市街地流入対策を天秤にかける日も近いのかなと思う。
『クマは、抵抗力のない、自分たちに圧力をかけてこない場所を選んでいるのである。それは市街地においても同様である。リアクションのない場所は、クマにとってはOKと受け止められている。さらにクマにとっては、人里に依存したほうが年間を通じてうま味がある。そのうま味のほうが、抱えるリスクよりも大きいと受け止められている。だから出没が絶えないのである。うま味をつくり出しているのも私たちである』。
読了日:09月01日 著者:田口 洋美
注: は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。
細切れの読書が増えているということか。
そうすると「あんまり読めてない」感覚がして不満も高まりがちだ。
しかし実際は本腰で読む本も読めているので、意外に感じた。
<今月のデータ>
購入13冊、購入費用8,679円。
読了12冊。
積読本321冊(うちKindle本156冊、Honto本3冊)。

 怪談四代記 八雲のいたずら (講談社文庫)の感想
怪談四代記 八雲のいたずら (講談社文庫)の感想ラフカディオ・ハーンを曾祖父に持つ学者の随筆。ハーンはギリシャとアイルランドにルーツがある。どちらも一神教一辺倒ではない国だ。神ではない、人に働きかける見えざる存在への親和性はありそうだ。もちろん日本も。私は彼を故国喪失者として見ている部分がある。ハーンは日本に渡って落ち着き、日本の暮らしを楽しんだ。しかし、明治の松江の人々は紅毛だ鬼だと疎み、盆踊りを観ているところへ砂を投げかけられたと記録が残っている。「日本の面影」にはそんな気配は露ほども見せない。仕方ないとはいえ、切ないことだ。
読了日:09月24日 著者:小泉 凡

 鬼はもとより (徳間文庫)の感想
鬼はもとより (徳間文庫)の感想藩札という地域通貨のようなシステムを使って藩の財政を立て直すという、経済小説のような時代小説。池井戸潤の江戸時代版みたい。商人と武士の立ち位置の違いについて『利を生むための視野の広さを、国の成り立ちを考える際の視野の広さと混同してはならない。二つはまったく別物であり、そもそも見ている景色がちがう』って現代日本の政治経済を牛耳ってる奴らに聞かせてやりたいね。江戸はなぜ武士が為政者だったのだろうか。重たい覚悟を背負った、武士らしい施政。鬼を引き受ける。数多の命を預かるならば、国を治める者はそうあるべきかと。
読了日:09月23日 著者:青山 文平

 日本語の大疑問 眠れなくなるほど面白い ことばの世界 (幻冬舎新書)の感想
日本語の大疑問 眠れなくなるほど面白い ことばの世界 (幻冬舎新書)の感想国立国語研究所の錚々たる研究者の方々が身近な質問に答える。「させていただいてもよろしいですか?」というややこしい言葉について、『非敬語ではより近い言葉へ、敬語ではより遠い言葉へ、というのが現在の日本語におけるポライトネス意識』としたうえで、距離感と敬意の度合い="遠近"をひとつの言葉にぶっこむ用法と説明する。ユピック・エスキモーの家族の概念や、下駄は外国語で男性名詞か女性名詞かなど、文化の違いにまで考えを及ばせるようなネタが興味深い。カンナダ語の歌を何度聞いても歌えず笑い出してしまう理由もよくわかった。
『拍感覚に慣れていない学習者にとっては、一拍を正しく聞き取ったり、発音したりすることが難しくなります。特に、促音や長音、撥音のリズムは、母語においてそれらを一拍として捉えることをしない多くの学習者にとって難しいのです』。
読了日:09月22日 著者:国立国語研究所編

 土と内臓―微生物がつくる世界 ( )の感想
土と内臓―微生物がつくる世界 ( )の感想どわー、壮大な微生物の力に圧倒される。著者が『自然の隠れた半分』と呼ぶように、地球上の生物のほとんどは肉眼で見えない。植物と土壌生物、人間と腸内生物の共生。どちらにも言えることは、科学の力で人間にとっての栄養素、植物にとっての有益物質はわかってきているけれど、それが全てじゃない。だから、必要とわかっている栄養素だけ摂ったのではだめなのだ。目先ではよく効くサプリや肥料が喧伝されても、目に見えない部分をじっと想定する胆力が必要。ましてや安易に殺生物剤や抗生物質でマイクロバイオームを攪乱するべきではないだろう。
うちの猫のことを考える。不調があって獣医のところへ行くと、まず抗生物質を処方される。それでたいていの異変は治まる。だけど、その度彼らの腸内に起きていたことを想像すると心穏やかでない。せめてその後の食餌を心がけて整える必要がある。そう、食餌も。総合栄養食を定量与えるのが常識的な責務になっているが、それだけで良い訳がない。様々な食材が必要だ。魚、肉、欲しがるなら野菜、草。いずれは土の上を歩かせてやりたいなあ。そういえば人間や自分の尻を舐めたり、猫同士舐め合ったりするのも微生物の移動・交換にあたるのではないか。
読了日:09月21日 著者:デイビッド・モントゴメリー,アン・ビクレー

 図書館島 (海外文学セレクション)の感想
図書館島 (海外文学セレクション)の感想島に育った少年は魔術のごとき異国の文字を学び、本から知った彼方の世界に憧れる。故郷を出て、本の中で読んだ都市の生活を見る。世界にはもっとたくさんの本があって、それも地域によって思想や文化、歴史は様々と知る。一方で、出会う人との関係が深くなるうち、ひとりの人の胸の奥にも物語があると知る。誰かがそれを文字に記すことで、物語は時代を超え、人の間を渡っていくことができる。だけど、記されないものも限りなくあるんだって気づくのだ。それも含めて「図書館」なのかな? 原題「A STRANGER IN OLONDRIA」。
『本とは砦であり、嘆きの場所であり、砂漠に至る鍵であり、橋のない川であり、槍の並ぶ庭なのだ』。この物語は長い。長い物語の先にこの言葉があって、沁みた。
読了日:09月18日 著者:ソフィア・サマター

 医療にたかるな (新潮新書)の感想
医療にたかるな (新潮新書)の感想行政、職員、医者、住民、メディアの全員に財政破綻の原因と責任がある。夕張市の事例はわかりやすいし、総人口が減る一方で高齢者比率と社会保障費率が増大する日本では、明日は我が身だ。市民の要望を叶えるのではなく、どの施策が問題を解決するかを数値と検証で見極める必要がある。個人のモラルで軽々に医者にかからないのがいちばんと思っていたけれど、予防接種と検診の受診率は医療費に相関すること、口腔ケアも重要と知った。これから行政は間違いなく行き届かなくなる。頼らないだけではだめで、個人の自発性と工夫が問われると心得る。
目先の営利を求める医療機関と、不安がるくせに事実を見ない患者の共依存が医療費の増大を招く。自治体の『医療費が高いということは「住民の健康意識が低く、病人が多い」ということです』。住民の甘えに対して著者は厳しい。皆で払った税金を正しく使う方法を、私たちは解ってないんだろう。自身の健康を医者ではなく自らで管理し、一定のリスクはあるものと認め、QOLを考えること。小川淳也代議士が北欧の医療制度について視察をしてきて、似たようなことを言っていたと思い出す。それが自立ってことなんだろう。
読了日:09月13日 著者:村上 智彦

 ソロモンの指環―動物行動学入門 (ハヤカワ文庫NF)の感想
ソロモンの指環―動物行動学入門 (ハヤカワ文庫NF)の感想ローレンツが初めて書いた本。楽しい読み物だ。世間でも興味から様々な動物を飼うことが珍しくなかった時代に、ローレンツは科学的な目で観察した。imprintingで有名だが、より動物の視点、論理に近づこうとする姿勢が新鮮だったのではないかと思う。主に『逃げようとすればいつでも逃げられるのに、私のそばにとどまっている』半分飼い馴らされた動物たちが主役で、特にコクマルガラスの章が興味深かった。動物本来の遺伝的行動と馴致の影響が葛藤する様もローレンツは観察している。原題は「彼、けものども、鳥ども、魚どもと語りき」。
ライアル・ワトソンがローレンツに師事するのを拒んだというのは前に知っていた。動物を意図的/非意図的に飼い馴らして観察したローレンツと、野性の中に人間がいる状態で育ったワトソンとでは、動物のあるべき姿への考え方も、アプローチも立ち位置も違いすぎて、聞きかじりながら、ワトソンは受け入れることができなかったのではと推測する。結局ワトソンはデズモンド・モリスに師事したのだったか。そちらも読まなければ。
読了日:09月11日 著者:コンラート ローレンツ

 瀬戸内文化誌の感想
瀬戸内文化誌の感想海と海の民に焦点を当てた論考集。特に漁業の手法に詳しい。さて古来、瀬戸内海は日本各地から京阪への航路として要衝だった。人々はその時代の需要に合わせて、各地各島で様々な産業を手掛け、生計としてきた。しかし決して裕福ではなかったと宮本常一翁は言う。山地が多く、人が増えても養うための土地が少ない。土地の生産力が足りない。増えてはあぶれ、出稼ぎや海賊、遊女に身を落としたという。波のない内海を絶えず大小の船が航行する。潮や天候の具合によって走り、泊まり、名所を見物し、また無事を願う神事を行なう、歴史の末に今がある。
瀬戸内海を横断するフェリーに乗った。昔より少々視点が高いが、岸を離れたらちっぽけなもので、海、空、島、船が目まぐるしく移り変わっていくのを飽かずただ眺める。動く絵巻物のようだと言った旅行者の気持ちがわかる。美しい。もらった海図によると、安全に航行できるルートは非常に限られている。ざあざあ音を立てて流れる瀬戸は大きな船でも思うようには任せず、海底が浅くなっている難所も多い。こんなところで、島を回り込んだ途端にかがり火を焚いた海賊の小舟が一斉に飛び出してくる、なんて妄想をしては震えあがった事でした。
読了日:09月08日 著者:宮本常一
 満願 (新潮文庫)の感想
満願 (新潮文庫)の感想売れに売れたと記憶している短編集。久しぶりの米澤穂信のミステリを、私は楽しみ切ったとはいえない。人の心に巣くう打算に興味がなくなったからだろうか。こちらも知識や経験を積み上げ、世にもっと不思議な事象や数奇があると知ってしまったからだろうか。意表を突かれる感覚がないまま淡々と読んでしまう。切ないことだ。こうなっては、「折れた竜骨」のようなファンタジー系の特殊設定か、「万灯」のように海外事情を織り込むとかいった奇策が必要かもしれない。といって、昨今は海外ミステリも各国からのが日本語で読めるから、難しいかな。
読了日:09月07日 著者:米澤 穂信

 地獄変の感想
地獄変の感想これは立派にミステリ。深く読むほどに凄惨な絵図。猿が助けを求めたのは何故なのか。大殿様はなぜ顔色を変えたのか。なぜ良秀の娘が"罪人"なのか。仕掛けが細かい。伏線は回収されない。私は大殿様が最も恐ろしい。あれが正気の沙汰か。語り手は何も疑っていないが、読み手はそのとおり信じることができない。良秀の人間性を嫌っていた。のみならず、娘に思うところがあったとしか考えられないではないか。片や良秀は、おそらく結末をわかっていた。わかったうえで、大殿様に頼んだ。そして望んだものを得た。『奈落には己の娘が待っている』。
読了日:09月04日 著者:芥川 竜之介

 警視庁 生きものがかりの感想
警視庁 生きものがかりの感想「生きものがかり」なんて優しそうな響きだから、迷子ペットの捜索するのかと思いきや、その実は希少野生動植物密売捜査。密輸入ブローカーが関西ルートで業者にだの、タイの密輸マーケットへの供給ルートを仕切る組織が国際テロ組織と連携だのと、ガチの警察組織だった。そもそもなぜ密輸するかと言えば、そこにカネが絡むからだ。愛じゃない。生きものを扱うゆえに環境省や動物園/水族館と連携したり、市民への啓発活動になりそうな事案を選んだりと、捜査する側によほど愛を感じる。ジーンズのポケットにスローロリス入れて飛行機に乗るなよ…。
一度密輸された動物を原産地へ戻すのは厳禁事項と知った。原産地に存在しない菌や病気をつけて戻したら、原産地の生態系に壊滅的な影響を与えかねないからだ。戻してやりたい気持ちはやまやまなんだけど、ごめんなあ、悪い人間のせいで。同じ種でも違う地域で生まれた雌雄を交配するのも、遺伝子の系列が交雑するのでタブー。そういうときに、動物園/水族館や研究機関は受け皿になるのだそうで。いろんな事情や役割があるのだなあ。
読了日:09月02日 著者:福原 秀一郎

 クマ問題を考える 野生動物生息域拡大期のリテラシー (ヤマケイ新書)の感想
クマ問題を考える 野生動物生息域拡大期のリテラシー (ヤマケイ新書)の感想Oso18のニュースから。クマは雑食性なので肉を喰う。ただ、喰うために生きている人間や家畜を繰り返し襲うのは、リスクが比較的小さく、出産や冬眠のための栄養を貯めるのに効率的だと学習してしまったかららしい。人間が森林を開発して野生動物の生息域に干渉し、人間の居住地と森林の間に緩衝帯を維持せず、野生動物を森林に追い戻す行動を積極的に取らないことが事態を悪化させているという。飼い犬を外に放さなくなったのも大きい。犬による咬傷事故回避や狂犬病予防と、野生動物の市街地流入対策を天秤にかける日も近いのかなと思う。
『クマは、抵抗力のない、自分たちに圧力をかけてこない場所を選んでいるのである。それは市街地においても同様である。リアクションのない場所は、クマにとってはOKと受け止められている。さらにクマにとっては、人里に依存したほうが年間を通じてうま味がある。そのうま味のほうが、抱えるリスクよりも大きいと受け止められている。だから出没が絶えないのである。うま味をつくり出しているのも私たちである』。
読了日:09月01日 著者:田口 洋美

注:
 は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。 2023年09月01日
2023年8月の記録
『これは日本の文化一般に通ずる思想ですが、私自身も年をとるということは、ある意味では生涯で一番楽しい時期ではないかと潜かに思っているんです。というのは若い時には知らないで過ごしたさまざまなものが見えてきますからね』。
今月読んだ白洲正子の言葉。
いやー、ほんとに。
時間が足りないよ困ったなあ、とすら思うくらい、年々どんどん楽しくなる。
先日、インド映画「K.G.F」を観に行った。
単なるバイオレンスエンタメでしょ、と思っていたところが、
社会構造や、宗教と母性のつながりなど、いくらでも深掘りしたくなる。
見えてくる、の意味をしみじみ思う。
<今月のデータ>
購入11冊、購入費用9,824円。
読了16冊。
積読本323冊(うちKindle本157冊、Honto本3冊)。

 文豪怪奇コレクション 恐怖と哀愁の内田百閒 (双葉文庫)の感想
文豪怪奇コレクション 恐怖と哀愁の内田百閒 (双葉文庫)の感想
内田百閒の作風を、そういえば知らなかった。怖いとか不思議とか感じる前に、呆気にとられる。怪異自体がわかりやすくないのだ。何が起きたのか、何を主人公が怖がっていたのか、わからないまま終わってしまうものも多い。だいたい主人公本人にもわかっていなかったりする。ただ、常ならざる雰囲気だったり、見えるものが異様だったり、気配がおかしかったり、形容しようのない状況の形容に巧みである。解りやすい「影」を好みと挙げておく。自身が疫病神なんじゃないかと、周りの人間の様子から察してゆく恐怖。次は「安房列車」を読みたい。
読了日:08月31日 著者:内田 百閒
 ゼロ時間へ (ハヤカワ文庫―クリスティー文庫)の感想
ゼロ時間へ (ハヤカワ文庫―クリスティー文庫)の感想
年々、小説を読みはじめるのが億劫になるようだ。人物を区別し、状況を把握するのが面倒で仕方ない。クリスティの凝った仕掛けとあらば気が抜けないから余計に。からの、一気読み。偶然の出来事も計算し尽くされた策略も、全てが集約される要の瞬間、それが"ゼロ時間"。ならば捜査や推理は時間を遡ってゼロ時間に到達する行為と言えるだろう。それにしてもたいした役者だった。読み返してみても言動に引っかかりが少なく、周りの人物のほうが余程不審な素振りを見せるのがクリスティの設定の妙。読むたび、クリスティ作品が好きだと思い出す。
読了日:08月30日 著者:アガサ・クリスティー
 サステイナブルに暮らしたい ―地球とつながる自由な生き方―の感想
サステイナブルに暮らしたい ―地球とつながる自由な生き方―の感想
できることならサステイナブルに暮らす人でありたい。できる範囲で。さほど無理せずに。心地よく。自分にできる/できない、向いている/向いていない、さらに好き/嫌いは人それぞれだから、こういう本は全てががっちりはまる、なんてことはないのだろうな。著者夫妻の言うように、「今日正しいと思ったこと」をやれる範囲で積み重ねていくのが正解だと思う。それは息苦しい縛りではなくて、ゴミ(と自責)からの解放、選ぶ自由なのだ。取り入れたいアイテムは蓋がガラスのWECK、竹ざる、自家製へちま。クロモジって庭に植えられるのだろうか。
読了日:08月27日 著者:服部雄一郎,服部麻子
 白い病 (岩波文庫)の感想
白い病 (岩波文庫)の感想
感染症を題材にした作品として、しかもチャペックで気になっていたのを、一箱古本市の店主から購入。こんなに短かく、また戯曲だったとは知らなかったと話したことだった。この物語は、悲惨な最期を迎える病そのものだけでなく、若い世代の行き詰まる世相や、為政者と軍需産業の戦争願望、さらに為政者の策略が大衆に飲み込まれ押し流されていく様子までを描いている。今と同じなのだ。戦争は狂った独裁者だけで始まるものではない。これを普遍と呼んでしまったら、人間はいつまでも愚かだと認めてしまうようじゃないかと狼狽える。希望ははかない。
読了日:08月26日 著者:カレル・チャペック
 あなたの会社、その働き方は幸せですか? (単行本)の感想
あなたの会社、その働き方は幸せですか? (単行本)の感想
このお二人が同級生とは、パワフルな組み合わせだ。二人とも数字とファクト、ロジックを持っているので、切れ味が良い。厚生年金保険の適用拡大や終身雇用の廃止、消費税の是非など、解説されると納得だった。労働が流動化することは企業のダイバーシティを促進する。すると人間の考える力が豊かになり新しい発想が生まれる。しかしうちのような、知識と技術だけでなく、特定現場経験の蓄積が物を言う業態である場合は、長く勤めてもらえるような待遇面のインセンティヴはやはり必要だろう。日本的経営が明文化されていないのは怠慢との指摘が痛い。
「育休中に浮いた人件費を他の社員に分与する」発想は私にも無かった。育休の間だけ臨時に人員を補充するのは、雇用管理面から言って面倒だし、中小企業ではまず無理。だったら、それ、やろう!
読了日:08月26日 著者:出口 治明,上野 千鶴子
 新編 日本の面影 (角川ソフィア文庫)の感想
新編 日本の面影 (角川ソフィア文庫)の感想
ラフカディオ・ハーン、明治23年来日、横浜から出雲へ旅立つ。イザベラ・バードの旅を連想するが、ハーンはもっと熱烈に、見聞きする全てを慈しみ、賛美する。いち日本人としては面映い。しかし観察する筆は写実かつ的確で、紛うかたなき日本の景色、風物、人である。出雲への旅、潜戸への旅、松江の居宅だった屋敷と庭の描写など、つられてうっとりしてしまう。文化や歴史にも造詣を深め、そこら辺の日本人では敵わない。出雲大社への昇殿を許された最初の西洋人として、ハーンほどふさわしい人物はいなかったんじゃないかと感服しきりだった。
『大橋から東の方角の地平線に、鋸の歯のような稜線を描く緑や青の美しい山々の連なりを望むと、神々しい幻影がひとつ空にそびえ立っているのが見える。山裾が遠くの霞に霞んで見えないので、空中にその幻影だけが浮かび上がっているようである。下の方は透き通った灰色で、上は白く霞み、夢かと見まがう万年雪をたたえた悠然たる、幻のような高嶺──それが、大山の雄姿である。』
読了日:08月24日 著者:ラフカディオ・ハーン
 世界まちかど地政学NEXTの感想
世界まちかど地政学NEXTの感想
藻谷さん相変わらずせわしない。Googleマップを駆使して追う私もへとへとである。この世界はどのように出来上がっているのか。重要なのは『何が「あるか」よりも、普通ならあるはずの何が「ないか」を探す観察力』と位置づけて世界を巡る。まさに百国百様、しかし違った中にも『同じ構造が繰り返し現れる』瞬間を追体験する。国内に産業が無いのに消費を煽る資本主義がねじ込まれている貧困国。歴史的条件と戦略の上に奇跡的な立ち位置を確立した小国。国体を維持することは、歴史の偶然と積み重ねのうえの奇跡を、智で先へ繋ぐ努力と見たり。
読了日:08月23日 著者:藻谷 浩介
 問題はロシアより、むしろアメリカだ 第三次世界大戦に突入した世界 (朝日新書)の感想
問題はロシアより、むしろアメリカだ 第三次世界大戦に突入した世界 (朝日新書)の感想
三次元の物体を、角度を変えて見ると別のもののように見える。それと同じで、アメリカを筆頭とする西側諸国が一枚岩には見えなくなった。アングロサクソン系の国と、ロシア、中国、中東などは、家族の形態も相続方式も違う。それが互いへの許容できなさに影響している可能性を指摘している。日本とドイツはその間の共同体家族構造を持っているので、実はロシア側にも親和性がある。たまたま大戦に負けたために西側についている「状態」は、必然ではないのだ。総じて世界の価値観は、西側的でない国のほうが多い。それが持つ意味をじっくり考えたい。
あとアメリカの衰退。アメリカは『他国を戦争に向かわせることをする国』だとの指摘を池上さんは否定しない。私もアメリカのウクライナや台湾、韓国へのやり口にそれを感じる。戦争はアメリカの存在を誇示できる。戦争は奪える。戦争は儲かる。一方で、軍需品をアメリカ国内で十分生産できなくなったら、生産力のあるドイツや日本に生産させるよう圧力をかけるという予測も、ありそうで怖い。安倍以降、せっせと武器輸出三原則をはずしにかかっているのは、すでにその方向でアメリカから圧がかかっているとみてそう的外れでないのかも。
読了日:08月17日 著者:エマニュエル・トッド,池上 彰
 悲しみの歌 (新潮文庫)の感想
悲しみの歌 (新潮文庫)の感想
その後30年経っても勝呂の懊悩は続いていた。善人であるところの勝呂が善で生きることができない世界。以前は、戦時下の非常、戦争の狂気ゆえと私は理由づけたのだった。ところが30年経ったって、多数の人々は自分の欲望や見栄ばかりで汚いことは他人に擦りつけている。本質は同じと著者は描き出す。どころか、平和ゆえの浅はかな正義感で人を簡単に糾弾するのだと。「くたびれていた」。言葉少なな勝呂の言葉から、他者が理解することは難しい。いつだって非難は簡単で、受容は難しい。『ほんとに、あの人、かなしかった。かなしい人でした』。
読了日:08月16日 著者:遠藤 周作
 ソングライン (series on the move)の感想
ソングライン (series on the move)の感想
ソングライン。白人が現れる前、オーストラリア全土にわたって巡らされた伝説の歌の道。言葉や血筋が違っても、アボリジニはその歌さえあれば通じ合うことができるという。アボリジニには"領土"と"道"が同じことばだ。乾燥した低木林や砂漠では降雨量が安定せず、定住できない。だから土地の保有ではなく、誰かに断りなく安心して居られる場所を道として保持しているというのは合理的なシステムだ。『歌われない土地は死んだ土地』。この物語は事実と虚構を織り交ぜて書いたものとあとがきで知った。ソングラインは実在するのか?と慌てた。
読了日:08月15日 著者:ブルース・チャトウィン
 山陰土産の感想
山陰土産の感想
遠出しない盆休みのお供に。島崎藤村は次男を連れ、山陰へ汽車の旅をした。当然、JR各駅停車よりさらに遅い汽車で、大阪から小郡まで10日余りかけた。東京とは比べるべくもない山野の"滴るばかりの緑"の深さに目を見張る描写など、街にも山野にも細やかな発見と描写をする様子は、列車が鈍行だからだけでなく、当時における旅行の珍しさと、持ち前の描写力だろう。土地土地の名士が訪れては親子をもてなし、名跡を案内する。羨ましいが忙しない。読もうと思ったのは、山陰の海岸の潜戸の描写があると聞いたからだったか。行くなら夏か。
読了日:08月15日 著者:島崎 藤村
 撤退論 歴史のパラダイム転換にむけて (犀の教室)の感想
撤退論 歴史のパラダイム転換にむけて (犀の教室)の感想
日頃の内田先生の撤退論に馴染んでいる身には、各論者の撤退論にぴんとこないものも多かった。各氏の専門分野を考えれば、撤退の意味もいろいろで当たり前である。なので、青木真兵氏の、資本に完全に包摂されないように常に距離感を計る必要性や、想田和弘氏の、非常識に思える選択肢を吟味する重要性、平川克美氏の、資本主義社会からの『撤退は敗北でも逃避でもなく、パラダイムの転換である』という実体験など、内田先生の論と親和性の高いものほど印象に強く、また即ち暮らしの中に取り込んでいかなければと私の心持ちを後押しした。
読了日:08月15日 著者:内田樹 編,堀田新五郎,斎藤幸平,白井聡,中田考,岩田健太郎,青木真兵,後藤正文,想田和弘,渡邉格,渡邉麻里子,平田オリザ,仲野徹,三砂ちづる,兪炳匡,平川克美
 タクシードライバーぐるぐる日記――朝7時から都内を周回中、営収5万円まで帰庫できませんの感想
タクシードライバーぐるぐる日記――朝7時から都内を周回中、営収5万円まで帰庫できませんの感想
今回は都内の大手タクシー会社に勤務するタクシー運転手。毎朝500台のタクシーが時間差で出ていくなんて、想像を絶する。職種柄、同僚や他社のドライバー、客と接触する人数は多いが、どこか淡泊で、意外に一人の時間が長い印象を受けた。心身ともに、自分を保つのが難しそうだ。「一番うまい店に連れてって」なんてテレビ番組があるが、それだって人によるよなあ。東日本大震災の直後。東京駅前には人が溢れ出し、人と車でみるみる渋滞して身動きが取れなくなって、「回送」表示にしても窓越しに乗車を懇願してくる人々の描写には鳥肌が立った。
読了日:08月14日 著者:内田正治
 天路の旅人の感想
天路の旅人の感想
戦時下、西川一三は密偵の命を受け、内蒙古から西へ向かった。それは敵地の情報を探るという任務、しかし元々は見知らぬ地を歩きたいという本人の情熱ゆえとわかる。蒙古人のラマ僧を装い、読経と御詠歌を会得してまで、そこに帰国や安住のチャンスがあってもあえて先へ先へとまだ見ぬ地を思い描く、その魂の自由さがまさに"天路の旅人"だと沢木さんは感じたのだろう。帰国後、苦行僧のように一心不乱に記録をまとめ続けた3年、その後数十年の淡々とした生活との落差はやはり際立つ。何が幸せだったかなど考えても詮無いことだけれど。
読了日:08月11日 著者:沢木 耕太郎
 日本の伝統美を訪ねて (河出文庫)の感想
日本の伝統美を訪ねて (河出文庫)の感想
白洲正子は好奇心旺盛な人だった。面白いと思ったら首を突っ込んでとことんはまる。結果として目が養われる。本質を掴む。あるいは自分の足で歩いて伊勢へ詣でる旅で、古人の実感を理解する。『だって、面白いんだもん。あたくし、いつでも面白いことが先に立つの』。だから彼女の言葉には惹かれる。着物、能、骨董など、長い伝統がある部類のものは素人が想像するよりずっと奥深い。知識だけでなく感覚で深く理解できるようになってはじめて、定石を踏まえたうえで拓ける境地というものがある、そのなにかひとつでも自分のものにしたいと憧れる。
『形がなかったら、心って表せないでしょ。心というのは、どっかにあるけれども、それを取り出して見せるといったら、やっぱり何かの形にしなくちゃならない。それは今も昔も同じだと思います』。『これは日本の文化一般に通ずる思想ですが、私自身も年をとるということは、ある意味では生涯で一番楽しい時期ではないかと潜かに思っているんです。というのは若い時には知らないで過ごしたさまざまなものが見えてきますからね』。
読了日:08月11日 著者:白洲 正子
 LISTEN――知性豊かで創造力がある人になれるの感想
LISTEN――知性豊かで創造力がある人になれるの感想
「きく」ことにまつわるあれこれ。『「話を聞く」とは相手のおしゃべりを待つことだと思っている人が多い』という見出しに、私は相手が話し始めるのを待ってしまうのでそのことかと思ったら、相手の話が終わるのを待つという意味だった。全体的に、聴く以外のことをしたがる人が多いわね。私は他人に関心が無いのが欠点であって、相手を決めつけている訳ではないと思っているけれど、引っ繰り返せばそういうことなんだろう。あと聴きかた。集中して聞くのではなく、意識を緊張させない状態で受け止める感じがいいのかな。それと沈黙を恐れないこと。
読了日:08月04日 著者:ケイト・マーフィ
注: は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。
今月読んだ白洲正子の言葉。
いやー、ほんとに。
時間が足りないよ困ったなあ、とすら思うくらい、年々どんどん楽しくなる。
先日、インド映画「K.G.F」を観に行った。
単なるバイオレンスエンタメでしょ、と思っていたところが、
社会構造や、宗教と母性のつながりなど、いくらでも深掘りしたくなる。
見えてくる、の意味をしみじみ思う。
<今月のデータ>
購入11冊、購入費用9,824円。
読了16冊。
積読本323冊(うちKindle本157冊、Honto本3冊)。

 文豪怪奇コレクション 恐怖と哀愁の内田百閒 (双葉文庫)の感想
文豪怪奇コレクション 恐怖と哀愁の内田百閒 (双葉文庫)の感想内田百閒の作風を、そういえば知らなかった。怖いとか不思議とか感じる前に、呆気にとられる。怪異自体がわかりやすくないのだ。何が起きたのか、何を主人公が怖がっていたのか、わからないまま終わってしまうものも多い。だいたい主人公本人にもわかっていなかったりする。ただ、常ならざる雰囲気だったり、見えるものが異様だったり、気配がおかしかったり、形容しようのない状況の形容に巧みである。解りやすい「影」を好みと挙げておく。自身が疫病神なんじゃないかと、周りの人間の様子から察してゆく恐怖。次は「安房列車」を読みたい。
読了日:08月31日 著者:内田 百閒

 ゼロ時間へ (ハヤカワ文庫―クリスティー文庫)の感想
ゼロ時間へ (ハヤカワ文庫―クリスティー文庫)の感想年々、小説を読みはじめるのが億劫になるようだ。人物を区別し、状況を把握するのが面倒で仕方ない。クリスティの凝った仕掛けとあらば気が抜けないから余計に。からの、一気読み。偶然の出来事も計算し尽くされた策略も、全てが集約される要の瞬間、それが"ゼロ時間"。ならば捜査や推理は時間を遡ってゼロ時間に到達する行為と言えるだろう。それにしてもたいした役者だった。読み返してみても言動に引っかかりが少なく、周りの人物のほうが余程不審な素振りを見せるのがクリスティの設定の妙。読むたび、クリスティ作品が好きだと思い出す。
読了日:08月30日 著者:アガサ・クリスティー

 サステイナブルに暮らしたい ―地球とつながる自由な生き方―の感想
サステイナブルに暮らしたい ―地球とつながる自由な生き方―の感想できることならサステイナブルに暮らす人でありたい。できる範囲で。さほど無理せずに。心地よく。自分にできる/できない、向いている/向いていない、さらに好き/嫌いは人それぞれだから、こういう本は全てががっちりはまる、なんてことはないのだろうな。著者夫妻の言うように、「今日正しいと思ったこと」をやれる範囲で積み重ねていくのが正解だと思う。それは息苦しい縛りではなくて、ゴミ(と自責)からの解放、選ぶ自由なのだ。取り入れたいアイテムは蓋がガラスのWECK、竹ざる、自家製へちま。クロモジって庭に植えられるのだろうか。
読了日:08月27日 著者:服部雄一郎,服部麻子
 白い病 (岩波文庫)の感想
白い病 (岩波文庫)の感想感染症を題材にした作品として、しかもチャペックで気になっていたのを、一箱古本市の店主から購入。こんなに短かく、また戯曲だったとは知らなかったと話したことだった。この物語は、悲惨な最期を迎える病そのものだけでなく、若い世代の行き詰まる世相や、為政者と軍需産業の戦争願望、さらに為政者の策略が大衆に飲み込まれ押し流されていく様子までを描いている。今と同じなのだ。戦争は狂った独裁者だけで始まるものではない。これを普遍と呼んでしまったら、人間はいつまでも愚かだと認めてしまうようじゃないかと狼狽える。希望ははかない。
読了日:08月26日 著者:カレル・チャペック
 あなたの会社、その働き方は幸せですか? (単行本)の感想
あなたの会社、その働き方は幸せですか? (単行本)の感想このお二人が同級生とは、パワフルな組み合わせだ。二人とも数字とファクト、ロジックを持っているので、切れ味が良い。厚生年金保険の適用拡大や終身雇用の廃止、消費税の是非など、解説されると納得だった。労働が流動化することは企業のダイバーシティを促進する。すると人間の考える力が豊かになり新しい発想が生まれる。しかしうちのような、知識と技術だけでなく、特定現場経験の蓄積が物を言う業態である場合は、長く勤めてもらえるような待遇面のインセンティヴはやはり必要だろう。日本的経営が明文化されていないのは怠慢との指摘が痛い。
「育休中に浮いた人件費を他の社員に分与する」発想は私にも無かった。育休の間だけ臨時に人員を補充するのは、雇用管理面から言って面倒だし、中小企業ではまず無理。だったら、それ、やろう!
読了日:08月26日 著者:出口 治明,上野 千鶴子

 新編 日本の面影 (角川ソフィア文庫)の感想
新編 日本の面影 (角川ソフィア文庫)の感想ラフカディオ・ハーン、明治23年来日、横浜から出雲へ旅立つ。イザベラ・バードの旅を連想するが、ハーンはもっと熱烈に、見聞きする全てを慈しみ、賛美する。いち日本人としては面映い。しかし観察する筆は写実かつ的確で、紛うかたなき日本の景色、風物、人である。出雲への旅、潜戸への旅、松江の居宅だった屋敷と庭の描写など、つられてうっとりしてしまう。文化や歴史にも造詣を深め、そこら辺の日本人では敵わない。出雲大社への昇殿を許された最初の西洋人として、ハーンほどふさわしい人物はいなかったんじゃないかと感服しきりだった。
『大橋から東の方角の地平線に、鋸の歯のような稜線を描く緑や青の美しい山々の連なりを望むと、神々しい幻影がひとつ空にそびえ立っているのが見える。山裾が遠くの霞に霞んで見えないので、空中にその幻影だけが浮かび上がっているようである。下の方は透き通った灰色で、上は白く霞み、夢かと見まがう万年雪をたたえた悠然たる、幻のような高嶺──それが、大山の雄姿である。』
読了日:08月24日 著者:ラフカディオ・ハーン

 世界まちかど地政学NEXTの感想
世界まちかど地政学NEXTの感想藻谷さん相変わらずせわしない。Googleマップを駆使して追う私もへとへとである。この世界はどのように出来上がっているのか。重要なのは『何が「あるか」よりも、普通ならあるはずの何が「ないか」を探す観察力』と位置づけて世界を巡る。まさに百国百様、しかし違った中にも『同じ構造が繰り返し現れる』瞬間を追体験する。国内に産業が無いのに消費を煽る資本主義がねじ込まれている貧困国。歴史的条件と戦略の上に奇跡的な立ち位置を確立した小国。国体を維持することは、歴史の偶然と積み重ねのうえの奇跡を、智で先へ繋ぐ努力と見たり。
読了日:08月23日 著者:藻谷 浩介

 問題はロシアより、むしろアメリカだ 第三次世界大戦に突入した世界 (朝日新書)の感想
問題はロシアより、むしろアメリカだ 第三次世界大戦に突入した世界 (朝日新書)の感想三次元の物体を、角度を変えて見ると別のもののように見える。それと同じで、アメリカを筆頭とする西側諸国が一枚岩には見えなくなった。アングロサクソン系の国と、ロシア、中国、中東などは、家族の形態も相続方式も違う。それが互いへの許容できなさに影響している可能性を指摘している。日本とドイツはその間の共同体家族構造を持っているので、実はロシア側にも親和性がある。たまたま大戦に負けたために西側についている「状態」は、必然ではないのだ。総じて世界の価値観は、西側的でない国のほうが多い。それが持つ意味をじっくり考えたい。
あとアメリカの衰退。アメリカは『他国を戦争に向かわせることをする国』だとの指摘を池上さんは否定しない。私もアメリカのウクライナや台湾、韓国へのやり口にそれを感じる。戦争はアメリカの存在を誇示できる。戦争は奪える。戦争は儲かる。一方で、軍需品をアメリカ国内で十分生産できなくなったら、生産力のあるドイツや日本に生産させるよう圧力をかけるという予測も、ありそうで怖い。安倍以降、せっせと武器輸出三原則をはずしにかかっているのは、すでにその方向でアメリカから圧がかかっているとみてそう的外れでないのかも。
読了日:08月17日 著者:エマニュエル・トッド,池上 彰

 悲しみの歌 (新潮文庫)の感想
悲しみの歌 (新潮文庫)の感想その後30年経っても勝呂の懊悩は続いていた。善人であるところの勝呂が善で生きることができない世界。以前は、戦時下の非常、戦争の狂気ゆえと私は理由づけたのだった。ところが30年経ったって、多数の人々は自分の欲望や見栄ばかりで汚いことは他人に擦りつけている。本質は同じと著者は描き出す。どころか、平和ゆえの浅はかな正義感で人を簡単に糾弾するのだと。「くたびれていた」。言葉少なな勝呂の言葉から、他者が理解することは難しい。いつだって非難は簡単で、受容は難しい。『ほんとに、あの人、かなしかった。かなしい人でした』。
読了日:08月16日 著者:遠藤 周作

 ソングライン (series on the move)の感想
ソングライン (series on the move)の感想ソングライン。白人が現れる前、オーストラリア全土にわたって巡らされた伝説の歌の道。言葉や血筋が違っても、アボリジニはその歌さえあれば通じ合うことができるという。アボリジニには"領土"と"道"が同じことばだ。乾燥した低木林や砂漠では降雨量が安定せず、定住できない。だから土地の保有ではなく、誰かに断りなく安心して居られる場所を道として保持しているというのは合理的なシステムだ。『歌われない土地は死んだ土地』。この物語は事実と虚構を織り交ぜて書いたものとあとがきで知った。ソングラインは実在するのか?と慌てた。
読了日:08月15日 著者:ブルース・チャトウィン

 山陰土産の感想
山陰土産の感想遠出しない盆休みのお供に。島崎藤村は次男を連れ、山陰へ汽車の旅をした。当然、JR各駅停車よりさらに遅い汽車で、大阪から小郡まで10日余りかけた。東京とは比べるべくもない山野の"滴るばかりの緑"の深さに目を見張る描写など、街にも山野にも細やかな発見と描写をする様子は、列車が鈍行だからだけでなく、当時における旅行の珍しさと、持ち前の描写力だろう。土地土地の名士が訪れては親子をもてなし、名跡を案内する。羨ましいが忙しない。読もうと思ったのは、山陰の海岸の潜戸の描写があると聞いたからだったか。行くなら夏か。
読了日:08月15日 著者:島崎 藤村

 撤退論 歴史のパラダイム転換にむけて (犀の教室)の感想
撤退論 歴史のパラダイム転換にむけて (犀の教室)の感想日頃の内田先生の撤退論に馴染んでいる身には、各論者の撤退論にぴんとこないものも多かった。各氏の専門分野を考えれば、撤退の意味もいろいろで当たり前である。なので、青木真兵氏の、資本に完全に包摂されないように常に距離感を計る必要性や、想田和弘氏の、非常識に思える選択肢を吟味する重要性、平川克美氏の、資本主義社会からの『撤退は敗北でも逃避でもなく、パラダイムの転換である』という実体験など、内田先生の論と親和性の高いものほど印象に強く、また即ち暮らしの中に取り込んでいかなければと私の心持ちを後押しした。
読了日:08月15日 著者:内田樹 編,堀田新五郎,斎藤幸平,白井聡,中田考,岩田健太郎,青木真兵,後藤正文,想田和弘,渡邉格,渡邉麻里子,平田オリザ,仲野徹,三砂ちづる,兪炳匡,平川克美
 タクシードライバーぐるぐる日記――朝7時から都内を周回中、営収5万円まで帰庫できませんの感想
タクシードライバーぐるぐる日記――朝7時から都内を周回中、営収5万円まで帰庫できませんの感想今回は都内の大手タクシー会社に勤務するタクシー運転手。毎朝500台のタクシーが時間差で出ていくなんて、想像を絶する。職種柄、同僚や他社のドライバー、客と接触する人数は多いが、どこか淡泊で、意外に一人の時間が長い印象を受けた。心身ともに、自分を保つのが難しそうだ。「一番うまい店に連れてって」なんてテレビ番組があるが、それだって人によるよなあ。東日本大震災の直後。東京駅前には人が溢れ出し、人と車でみるみる渋滞して身動きが取れなくなって、「回送」表示にしても窓越しに乗車を懇願してくる人々の描写には鳥肌が立った。
読了日:08月14日 著者:内田正治

 天路の旅人の感想
天路の旅人の感想戦時下、西川一三は密偵の命を受け、内蒙古から西へ向かった。それは敵地の情報を探るという任務、しかし元々は見知らぬ地を歩きたいという本人の情熱ゆえとわかる。蒙古人のラマ僧を装い、読経と御詠歌を会得してまで、そこに帰国や安住のチャンスがあってもあえて先へ先へとまだ見ぬ地を思い描く、その魂の自由さがまさに"天路の旅人"だと沢木さんは感じたのだろう。帰国後、苦行僧のように一心不乱に記録をまとめ続けた3年、その後数十年の淡々とした生活との落差はやはり際立つ。何が幸せだったかなど考えても詮無いことだけれど。
読了日:08月11日 著者:沢木 耕太郎
 日本の伝統美を訪ねて (河出文庫)の感想
日本の伝統美を訪ねて (河出文庫)の感想白洲正子は好奇心旺盛な人だった。面白いと思ったら首を突っ込んでとことんはまる。結果として目が養われる。本質を掴む。あるいは自分の足で歩いて伊勢へ詣でる旅で、古人の実感を理解する。『だって、面白いんだもん。あたくし、いつでも面白いことが先に立つの』。だから彼女の言葉には惹かれる。着物、能、骨董など、長い伝統がある部類のものは素人が想像するよりずっと奥深い。知識だけでなく感覚で深く理解できるようになってはじめて、定石を踏まえたうえで拓ける境地というものがある、そのなにかひとつでも自分のものにしたいと憧れる。
『形がなかったら、心って表せないでしょ。心というのは、どっかにあるけれども、それを取り出して見せるといったら、やっぱり何かの形にしなくちゃならない。それは今も昔も同じだと思います』。『これは日本の文化一般に通ずる思想ですが、私自身も年をとるということは、ある意味では生涯で一番楽しい時期ではないかと潜かに思っているんです。というのは若い時には知らないで過ごしたさまざまなものが見えてきますからね』。
読了日:08月11日 著者:白洲 正子
 LISTEN――知性豊かで創造力がある人になれるの感想
LISTEN――知性豊かで創造力がある人になれるの感想「きく」ことにまつわるあれこれ。『「話を聞く」とは相手のおしゃべりを待つことだと思っている人が多い』という見出しに、私は相手が話し始めるのを待ってしまうのでそのことかと思ったら、相手の話が終わるのを待つという意味だった。全体的に、聴く以外のことをしたがる人が多いわね。私は他人に関心が無いのが欠点であって、相手を決めつけている訳ではないと思っているけれど、引っ繰り返せばそういうことなんだろう。あと聴きかた。集中して聞くのではなく、意識を緊張させない状態で受け止める感じがいいのかな。それと沈黙を恐れないこと。
読了日:08月04日 著者:ケイト・マーフィ

注:
 は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。 2023年08月01日
2023年7月の記録
登山アプリ「ヤマップ」の社長がオフィスに備えつけているという本棚を見た。
人の偉さは読んだ本の冊数で測れないけれど。
若い頃から読み漁り、歩き、社会貢献の方法を考えてきたという言葉の裏打ち。
それだけの智を求めた足跡には違いない。
<今月のデータ>
購入16冊、購入費用14,890円。
読了18冊。
積読本329冊(うちKindle本161冊、Honto本3冊)。

 海獣学者、クジラを解剖する。~海の哺乳類の死体が教えてくれることの感想
海獣学者、クジラを解剖する。~海の哺乳類の死体が教えてくれることの感想
『本来、海にすんでいる哺乳類たちが、なぜ自ら海岸に打ち上がり、そして死んでしまうのか、その原因をただただ知りたいと思った』。クジラやイルカが陸に乗り上げて死ぬこと=ストランディングの報せを受けて全国を飛び回り、解剖調査や標本回収を重ねるお仕事。陸に乗り上げてしまうと、浮力が効かず、動けず、自重で自らの内臓を損傷して死ぬという事実に驚いた。それから、彼らの大きさ・重さね。そうか、重機で皮を引っ張らないとお腹の中を見ることができないのか。運ぶにも、埋めるにも、重機。泳いでいる彼らの美しさとのギャップが激しい。
読了日:07月30日 著者:田島 木綿子
 いのちのうちがわB面の感想
いのちのうちがわB面の感想
写真詩集。そうですか、詩がお好きでしたか。服部文祥の文章から丁寧や体裁という余分をそぎ落としたらこうなるのか、と唸った。余計な物を持たずに自分の身体だけで山野を進めば、思考もそぎ落とされるはずで、服部文祥は命を撃つたび、そぎ落とされた言葉でぐるぐる考えるのだろう。『だが銃弾が獲物を破壊し止め刺しで頸動脈を開き 命が絶えるまでの情景や感覚に「善」に分類されるものは何ひとつ見い出すことができない』。撃ち、喰い、考え込み、進む。ちょっと家族の前で読むのがはばかられる。だって写真が死骸とか内臓とかなんだもん。
石川氏と芸術祭に参加したときの、北海道の山旅。『他人の金でこんな旅して意味があるのかという思いも根底にはあるんだけど、アートや芸術祭が、この乞食みたいな山旅を表現として認めてサポートするっていうのは面白い』。
読了日:07月30日 著者:服部 文祥
 世界を売った男 (文春文庫)の感想
世界を売った男 (文春文庫)の感想
もう自分は現代ミステリをミステリとして楽しむことができなくなったのかと思っていた。でなければ、なぜ楽しんでいる自分が意外なのか。複層的な謎と、自信たっぷりに真相を決めつける人物たちのおかげで、事態は混沌を深める。PTSDやら記憶障害やらの説明口調がまどろっこしいが、それにしたってタイムトラベルかドッペルゲンガーかと、様々な可能性を当てはめてみる。鍵となる人物が現れてからはするするほどけて、そうか、第二回島田荘司推理小説賞か! 邦題も洒落てる。原題は「遺忘・刑警」。翻訳アプリによると「忘れる・刑事警察」…?
読了日:07月29日 著者:陳 浩基
 日本列島回復論 : この国で生き続けるために (新潮選書)の感想
日本列島回復論 : この国で生き続けるために (新潮選書)の感想
未来の日本人の回帰地点はどこにあるのだろう。日本人の未来という漠としたものを考えるのも飽きてきたが、確かなのは、減る一方の日本人が中央/地方の都市だけに集まって暮らすことが現実的でないことだ。国土やインフラを維持するためには辺境で山林の手入れをする人が必要で、辺境に生活する人がいれば交通網と通信網を含めたある程度のインフラは整備し続ける必要がある。金は無い。「ぽつんと一軒家」ではないが、傷みが進まないよう、ある程度自分たちで維持する努力は必要だろう。社会は自分の事だけをすればよいのではなくなっていくのだ。
読了日:07月29日 著者:井上 岳一
 未来の年表2 人口減少日本であなたに起きること (講談社現代新書)の感想
未来の年表2 人口減少日本であなたに起きること (講談社現代新書)の感想
日本の人口は減りすぎてしまうことが確定した。それは節操と想像力の無い政財界による当然の帰結ながら、なんでも値段が安くなることを歓迎した私たちも同罪である。甘い汁を吸ったジジイどもは逃げ切るつもりのようだが、私たち以降の世代は逃げられない。自分の老後をなんとかするための備えをと繰り返し考える。焦りつつ、年寄りが増えると街がスローダウンするというのは、悪くないとも思う。労働生産性が下がるというなら、一億(弱)総貧乏、皆がそこそこ貧乏になってのんびり暮らそう。曜日や時間限定で開く商店街って発想はなかなか好いな。
2018年の刊行。当時から既に変化は進んでいるので、読みながら現実でも似たような体感があって違和感がない。例えば外食は空席があるのに待たされ、親と同世代のような男性に配膳される。コンビニのガラス窓には年中求人告知が貼ってある。営業時間内のはずなのに閉まっているチェーン店にも慣れた。これからはもっともっと人が足りなくなる。そのときに、過剰なサービス業やブルシットジョブではなく、人が生きてゆくのにほんとうに必要な仕事に、労働力を集めることができる知恵を持ち合わせていることを、ささやかに願う。
読了日:07月27日 著者:河合 雅司
 よるねこ (集英社文庫)の感想
よるねこ (集英社文庫)の感想
姫野カオルコのホラー短編集。9篇てんでばらばらな、名づけようのない、あやかし。まさかね、と不安を誤魔化したがっているうちにがっつり顎に咥えこまれて動けない怖さもさながら、姫野カオルコ独特の文章に意地悪だなあとにやにやしてしまう。登場人物との絶妙な距離感、反復からの突き放しとか。その人物を描き、行為をディスっているようで、物語のゆくえを見守っているこちら側をも弄っているような共犯感とか。姫野カオルコの文章はホラーと相性が良いのかもしれん。『他人より自分がいちばん怖ろしいと申しますから……』。
読了日:07月27日 著者:姫野 カオルコ
 ヘンな科学 “イグノーベル賞" 研究40講の感想
ヘンな科学 “イグノーベル賞" 研究40講の感想
イグノーベル賞の受賞研究には発見編と問題解決編がある。その突拍子の無さと本人の真剣さの落差に、確かに笑えるんだけど、笑わせたくて研究の労を取ったわけでは当然なく、目的がある。感動したのは「ジェットコースターで尿路結石が通る」。ビッグサンダーマウンテン指定。ポイントは適度なスピード、細かい横振動、逆さま走行無し、石は6mm以下。で、なかなかの確率。私は結石を持っていないけど、読んだ瞬間に「人類の星の時間」ばりにきらめいて感じられた。AIが持たない好奇心、問題解決への希求、偶然への畏敬の念のなんと尊いことよ。
読了日:07月23日 著者:五十嵐 杏南
 〈効果的な利他主義〉宣言! ――慈善活動への科学的アプローチの感想
〈効果的な利他主義〉宣言! ――慈善活動への科学的アプローチの感想
世界をより良くするために、個々人は慈善活動の費用対効果の向上と公平性を求めるべきとする主旨。つまり富裕国よりも貧困国に寄付するほうが、また医者になるより稼いで寄付するほうがより多くの人を救えると説く。対照的な考え方は、身近または関心があるから援助する行為。それではだめですか?とあえて自分の中に問い立てして読んだ。結論から言うと、最終的にはその人の信条次第だ。しかし、その対象プログラムが実際に効果があるか、問題解決に貢献できるかを客観的に見定める姿勢は必要。評価団体が日本には無いので、見極めが難しいけれど。
エシカル商品やフェアトレード製品購入が搾取や貧困の撲滅に本当に貢献するか。著者は否定的だ。私は肯定派だが、フェアトレード認証を取得できるのは最貧困国ではない、また代金が労働従事者本人に届く証拠は無いとの指摘に反論できない。さらに、雑な考察ながら、家族のいない日本で技能実習生として月収10万円で暮らすのと、貧困国であっても母国の、設備の整った職場で年収10万円で暮らすのを比較して、日本産製品選択がすなわち是とも言いきれない。割増の対価を払うのなら正当性を自分自身で見極める、さもなくば逆効果もあり得るのだ。
『ファットテール分布は直感に反する』。1ドルの価値や所得の不均衡、格差などをグラフで見ると歪さに気づく。公正な数値化と比較はやっぱり大事だ。援助活動もファットテール分布を描く。つまりずば抜けて有効な援助だけに注力すれば絶大な効果を得られるのだが、機能するプログラムとそうでないプログラムを見極めるのは難しく、同時に効果的なプログラムの多くはきわめて効果的だという理由ですでに十分な資金提供を受けているのであり、ほんなんどないせえっちゅうねん。とぼやきたくはなる。これも"見極めが大事"案件。
読了日:07月20日 著者:ウィリアム・マッカスキル
 四国辺土 幻の草遍路と路地巡礼の感想
四国辺土 幻の草遍路と路地巡礼の感想
遍路道と被差別部落の分布が重なる点に着目した著者は四国を歩き始めた。遍路は重たいものを抱えた者、行き場のない者、逃げる者を受け止める。『遍路に出る人はみな何かあるから遍路をする』。そして遍路は、巡り続けることができるのだ。著者は遍路だけで暮らす草遍路に惹かれ、追い始める。それぞれの事情で、歩き続けることによって生きる人生を選ぶ人たち。やっぱり遍路には形式でない、深いなにかがある。山頭火や西行に比べ、現世生身の人間はどうしたって生臭さ金臭さが先に立つが、巡り続けるうちに至る境地は彼らに近づくのだと思った。
遍路つながり。こちらも香川県は手薄に終わるかと思いきや、福田村事件が大きく扱われている。しかしこの事件は最近出た新刊で深く読みたいので、軽く流す。宮本常一翁は書いた。『四国というところは、明治の終わりごろまではそういう遍路や乞食にみちみちたところであった』。たくさんの脱藩者を出した土佐がお遍路に厳しかったり、逆に道後の温泉はお遍路に料金を優遇したり、お遍路に多かったハンセン病者が大島青松園のような療養所に強制収容されたり、途切れなく続く歴史と文化の中に生きているんだなあと感じるところが多かった。
読了日:07月19日 著者:上原 善広
 作家の秘められた人生 (集英社文庫)の感想
作家の秘められた人生 (集英社文庫)の感想
フランスでの話題作ということだ。作家が作品を書くという行為について、少々ややこしい構造になったミステリ。作家になりたい。書きたい。だからといってなぜ尊敬する作家が隠遁している邸宅に忍び込んで、暴露本を書こうなんて動機が成立するのか。納得がいかない成り行きを保留にしながら探索は進み、達した結末は、それなりのものだった。世間離れした小さな離島の中だけで展開した事件は、20世紀末のバルカン半島の動乱へと広がりを見せる。その掘り進めていく感じが、この作家の持ち味か。物語の中に、幼い魂だけがきらめく。
読了日:07月17日 著者:ギヨーム・ミュッソ
 お遍路 (中公文庫)の感想
お遍路 (中公文庫)の感想
大正7年、うら若い女性が九州から単身歩き遍路に出る。現代でもよほどの決断だが、当時はもっと有り得ない行動と推測される。途中で会った見知らぬおじいさんと同行する。九州から船で八幡浜へ渡った人は、そこから巡礼を始めると知った。そして順打ちより逆打ちのほうが道が大変で、修行のためあえてそちらを選ぶことも。この記録は結願後、自らの記録と文献資料を併せて時系列に記述する形式。阿波や土佐、伊予に比べ讃岐の記述は薄い。高知から歩き始めたので、讃岐が無心になる頃合いなのか、それとも何も特筆すべきことが無かったのか。
目や足が不自由な人も遍路を巡った。むしろそのような困難を背負った人こそ遍路へ向かった。五体満足でも転がりそうな我らが国分寺の"遍路コロガシ"を皆上り下りしたそうだ。お互い助け合ってではあろうが、なんとも厳しい。善根宿、遍路宿、乞食宿、通夜、野宿。お接待は期待しないからありがたいのであって、迷惑がる人も多かったろう。この時代、国家権力による迫害も激しかったようだ。『幾ら身分はあっても遍路は遍路じゃないか。こら娘、その爺さんによく言ってきかせろ、分ったか。罪は成り立つのじゃが、特別をもって許しとくけに』。
読了日:07月16日 著者:高群 逸枝
 こんな一冊に出会いたい 本の道しるべ (NHK趣味どきっ!)の感想
こんな一冊に出会いたい 本の道しるべ (NHK趣味どきっ!)の感想
一箱古本市で、よその出店者さんに教えてもらって購入。前にも番組になっていたのだ。新しいほうの、立派な本棚に圧倒された後では確かに物足りない部分はある。収穫は橋本麻里さん。『全部を読破するのは不可能です。それでも本を所蔵し、棚に並べることには大きな意義があります』。橋本家ほどの本は収集できなくても、『本の向こうに広がる世界への入り口』はつくれると思う。前にもどこかに書いたけれど、読まなくても、背中を眺めているうちに得るものがある。橋本さんはそれを自分用の知識のマップと言う。本の処分も、よく吟味しなくては。
読了日:07月15日 著者:平松 洋子,矢部 太郎,渡辺 満里奈,祖父江 慎,橋本 麻里,穗村 弘,飛田 和緒,坂本 美雨,和氣 正幸,菊池 亜希子
 めんどくさいロシア人から日本人への感想
めんどくさいロシア人から日本人への感想
6歳からずっと日本で暮らしてればそりゃ日本人でしょ。ソ連時代の人々の暮らしの様子がなんでもカネカネでなかった頃の日本と似ていると気づいたり、帰化の条件に「日本国・日本政府・日本国憲法に反する思想を持っていた過去がないこと」という項目があると知ったり、いろいろ興味深い。「お付き合いする先のゴールがない」から恋愛に積極的になれないって言うのには、反射的にもったいないと思ってしまった。家族や子供を持つ未来は誰もが描けたほうがいいのにな。遺伝子的にどん詰まりなのは私も同じだし。それでもできれば楽しげなのがいいよ。
読了日:07月14日 著者:小原ブラス
 「その他の外国文学」の翻訳者の感想
「その他の外国文学」の翻訳者の感想
メジャーに扱われない言語で書かれた小説の翻訳者さんを取材した形式。おすすめ本や店頭など、どこかしらで私のアンテナにもかかっているようで、本棚や積読にちらほら見受けるのに気づいて驚いた。若い頃は海外小説ならアメリカと思い込んでいた節があり、またそれ以外は目に入らなかったのだが、最近は新潮クレストや白水社のような大手から小さな出版社まで、実は多く出版されていて有難いことだ。思うに、英語に代表される強者の言語フィルターを通さずに、原語から日本語で読めることは、贅沢でもあり、世界を見る目を養う肝要さを持っている。
読了日:07月10日 著者:
 本土の人間は知らないが、沖縄の人はみんな知っていること (ちくま文庫)の感想
本土の人間は知らないが、沖縄の人はみんな知っていること (ちくま文庫)の感想
沖縄は古来、覇権争いの要衝として望まずして権力争いに巻き込まれてきた。基地問題は今の沖縄にとって最たるもの、 アメリカと日本政府の動向は、知るも何も、生活を直接に左右する。敗戦以降、外務省や防衛省はアメリカの意に沿うことを最優先してきた。頻繁に開かれる在日米軍高官との機密会合、政治家は総理になって初めてその鉄の掟と密約を知らされ、背けない。主権国家として有り得ない、日本国民の意思がまるで通用しない領域。この歪みが本土にいるとなんでこんなに見えなくなるのか。「小指の痛み」はいずれ、全身の痛みになるのだろう。
東京南麻布の「ニュー山王ホテル」はアメリカ海軍の管轄下にある。ホテルとして泊まれるが、その実はニューサンノー米軍センター、一般日本人単独では泊まれない。観光協会のサイトでも「米国軍関係者向けの宿泊施設、保養所、社交場」とある。上記「日米地位協定各条に関する日米合同委員会」が開かれる場所でもある。当然治外法権。こういう事実にいちいち衝撃を受けているようでは、激甘の世間知らずなのだと、いったんは思うのに、自分の生活に実害が無いとすぐに忘れる。戦争に巻き込まれる羽目になって初めて、身に沁みるのだろう。
読了日:07月09日 著者:矢部 宏治
 ロビンソン・クルーソーを探して (新潮文庫)の感想
ロビンソン・クルーソーを探して (新潮文庫)の感想
デフォーの創作であるロビンソン・クルーソーのモデルであるところの船乗り、セルカークは確かにその島で生きていた。1721年に死去したセルカークの足跡は途切れがちでもちゃんと残っている。すり減りきったナイフとラストの大発見が読みどころではあるが、手がかりを追う探求の旅は、シーナさんや高野さんと違ってひたすら真面目な文章なので、少々退屈気味だった。クルーソーもセルカークも、見晴らしは良いが周りから見えにくい場所に住処を建てて、さらに木を植えた。ということは、デフォーはセルカークに直接会ったのだろうか?
読了日:07月08日 著者:高橋 大輔
 秘書綺譚―ブラックウッド幻想怪奇傑作集 (光文社古典新訳文庫)の感想
秘書綺譚―ブラックウッド幻想怪奇傑作集 (光文社古典新訳文庫)の感想
暗い夜の、人気のない家で、男が怪異に呑まれる。なにもそんなとこに行かなくてもいいのに、頼りがいがあるような無いようなMr.ショートハウスと共に乗り込んでもこちらはまったく安心できないという不思議な設定。その怪異はその人の咎ではなく、過去や他の住人や、つまり外部に由来するのが特徴である。勧善懲悪やら因果応報やら考えずに読めて楽しい。表題をひとつの山場に、その後はがらりと趣向が変わる。イギリスはヒースの野原、アメリカは荒野など、世界は常識ばかりでできてないと言いたげな自由な感じが良い。
読了日:07月07日 著者:アルジャーノン ブラックウッド
 こどもの一生 (集英社文庫)の感想
こどもの一生 (集英社文庫)の感想
らもさんの本で読んでいないものも残りわずか、と読み惜しんでいた小説。しかし読みながら、私は何を愛おしんでらもさんの本を読むのかが思い出せなくなってきてしまった。というわけで、いちばん心を動かされたのはあとがきである。これはらもさんが書いた脚本の舞台のノベライズだったのだ。笑う態勢万全で来る観客に、恐怖を。その思惑が成ったらもさんは劇場後部でほくそ笑んでいる。この物語は舞台に映える。その視覚を振り切って言葉で構築し直すのは難しかったと思う。失明したりしながらあえて小説として世に出したらもさんの姿を私は愛す。
読了日:07月03日 著者:中島 らも
注: は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。
人の偉さは読んだ本の冊数で測れないけれど。
若い頃から読み漁り、歩き、社会貢献の方法を考えてきたという言葉の裏打ち。
それだけの智を求めた足跡には違いない。
<今月のデータ>
購入16冊、購入費用14,890円。
読了18冊。
積読本329冊(うちKindle本161冊、Honto本3冊)。

 海獣学者、クジラを解剖する。~海の哺乳類の死体が教えてくれることの感想
海獣学者、クジラを解剖する。~海の哺乳類の死体が教えてくれることの感想『本来、海にすんでいる哺乳類たちが、なぜ自ら海岸に打ち上がり、そして死んでしまうのか、その原因をただただ知りたいと思った』。クジラやイルカが陸に乗り上げて死ぬこと=ストランディングの報せを受けて全国を飛び回り、解剖調査や標本回収を重ねるお仕事。陸に乗り上げてしまうと、浮力が効かず、動けず、自重で自らの内臓を損傷して死ぬという事実に驚いた。それから、彼らの大きさ・重さね。そうか、重機で皮を引っ張らないとお腹の中を見ることができないのか。運ぶにも、埋めるにも、重機。泳いでいる彼らの美しさとのギャップが激しい。
読了日:07月30日 著者:田島 木綿子

 いのちのうちがわB面の感想
いのちのうちがわB面の感想写真詩集。そうですか、詩がお好きでしたか。服部文祥の文章から丁寧や体裁という余分をそぎ落としたらこうなるのか、と唸った。余計な物を持たずに自分の身体だけで山野を進めば、思考もそぎ落とされるはずで、服部文祥は命を撃つたび、そぎ落とされた言葉でぐるぐる考えるのだろう。『だが銃弾が獲物を破壊し止め刺しで頸動脈を開き 命が絶えるまでの情景や感覚に「善」に分類されるものは何ひとつ見い出すことができない』。撃ち、喰い、考え込み、進む。ちょっと家族の前で読むのがはばかられる。だって写真が死骸とか内臓とかなんだもん。
石川氏と芸術祭に参加したときの、北海道の山旅。『他人の金でこんな旅して意味があるのかという思いも根底にはあるんだけど、アートや芸術祭が、この乞食みたいな山旅を表現として認めてサポートするっていうのは面白い』。
読了日:07月30日 著者:服部 文祥
 世界を売った男 (文春文庫)の感想
世界を売った男 (文春文庫)の感想もう自分は現代ミステリをミステリとして楽しむことができなくなったのかと思っていた。でなければ、なぜ楽しんでいる自分が意外なのか。複層的な謎と、自信たっぷりに真相を決めつける人物たちのおかげで、事態は混沌を深める。PTSDやら記憶障害やらの説明口調がまどろっこしいが、それにしたってタイムトラベルかドッペルゲンガーかと、様々な可能性を当てはめてみる。鍵となる人物が現れてからはするするほどけて、そうか、第二回島田荘司推理小説賞か! 邦題も洒落てる。原題は「遺忘・刑警」。翻訳アプリによると「忘れる・刑事警察」…?
読了日:07月29日 著者:陳 浩基

 日本列島回復論 : この国で生き続けるために (新潮選書)の感想
日本列島回復論 : この国で生き続けるために (新潮選書)の感想未来の日本人の回帰地点はどこにあるのだろう。日本人の未来という漠としたものを考えるのも飽きてきたが、確かなのは、減る一方の日本人が中央/地方の都市だけに集まって暮らすことが現実的でないことだ。国土やインフラを維持するためには辺境で山林の手入れをする人が必要で、辺境に生活する人がいれば交通網と通信網を含めたある程度のインフラは整備し続ける必要がある。金は無い。「ぽつんと一軒家」ではないが、傷みが進まないよう、ある程度自分たちで維持する努力は必要だろう。社会は自分の事だけをすればよいのではなくなっていくのだ。
読了日:07月29日 著者:井上 岳一

 未来の年表2 人口減少日本であなたに起きること (講談社現代新書)の感想
未来の年表2 人口減少日本であなたに起きること (講談社現代新書)の感想日本の人口は減りすぎてしまうことが確定した。それは節操と想像力の無い政財界による当然の帰結ながら、なんでも値段が安くなることを歓迎した私たちも同罪である。甘い汁を吸ったジジイどもは逃げ切るつもりのようだが、私たち以降の世代は逃げられない。自分の老後をなんとかするための備えをと繰り返し考える。焦りつつ、年寄りが増えると街がスローダウンするというのは、悪くないとも思う。労働生産性が下がるというなら、一億(弱)総貧乏、皆がそこそこ貧乏になってのんびり暮らそう。曜日や時間限定で開く商店街って発想はなかなか好いな。
2018年の刊行。当時から既に変化は進んでいるので、読みながら現実でも似たような体感があって違和感がない。例えば外食は空席があるのに待たされ、親と同世代のような男性に配膳される。コンビニのガラス窓には年中求人告知が貼ってある。営業時間内のはずなのに閉まっているチェーン店にも慣れた。これからはもっともっと人が足りなくなる。そのときに、過剰なサービス業やブルシットジョブではなく、人が生きてゆくのにほんとうに必要な仕事に、労働力を集めることができる知恵を持ち合わせていることを、ささやかに願う。
読了日:07月27日 著者:河合 雅司

 よるねこ (集英社文庫)の感想
よるねこ (集英社文庫)の感想姫野カオルコのホラー短編集。9篇てんでばらばらな、名づけようのない、あやかし。まさかね、と不安を誤魔化したがっているうちにがっつり顎に咥えこまれて動けない怖さもさながら、姫野カオルコ独特の文章に意地悪だなあとにやにやしてしまう。登場人物との絶妙な距離感、反復からの突き放しとか。その人物を描き、行為をディスっているようで、物語のゆくえを見守っているこちら側をも弄っているような共犯感とか。姫野カオルコの文章はホラーと相性が良いのかもしれん。『他人より自分がいちばん怖ろしいと申しますから……』。
読了日:07月27日 著者:姫野 カオルコ

 ヘンな科学 “イグノーベル賞" 研究40講の感想
ヘンな科学 “イグノーベル賞" 研究40講の感想イグノーベル賞の受賞研究には発見編と問題解決編がある。その突拍子の無さと本人の真剣さの落差に、確かに笑えるんだけど、笑わせたくて研究の労を取ったわけでは当然なく、目的がある。感動したのは「ジェットコースターで尿路結石が通る」。ビッグサンダーマウンテン指定。ポイントは適度なスピード、細かい横振動、逆さま走行無し、石は6mm以下。で、なかなかの確率。私は結石を持っていないけど、読んだ瞬間に「人類の星の時間」ばりにきらめいて感じられた。AIが持たない好奇心、問題解決への希求、偶然への畏敬の念のなんと尊いことよ。
読了日:07月23日 著者:五十嵐 杏南

 〈効果的な利他主義〉宣言! ――慈善活動への科学的アプローチの感想
〈効果的な利他主義〉宣言! ――慈善活動への科学的アプローチの感想世界をより良くするために、個々人は慈善活動の費用対効果の向上と公平性を求めるべきとする主旨。つまり富裕国よりも貧困国に寄付するほうが、また医者になるより稼いで寄付するほうがより多くの人を救えると説く。対照的な考え方は、身近または関心があるから援助する行為。それではだめですか?とあえて自分の中に問い立てして読んだ。結論から言うと、最終的にはその人の信条次第だ。しかし、その対象プログラムが実際に効果があるか、問題解決に貢献できるかを客観的に見定める姿勢は必要。評価団体が日本には無いので、見極めが難しいけれど。
エシカル商品やフェアトレード製品購入が搾取や貧困の撲滅に本当に貢献するか。著者は否定的だ。私は肯定派だが、フェアトレード認証を取得できるのは最貧困国ではない、また代金が労働従事者本人に届く証拠は無いとの指摘に反論できない。さらに、雑な考察ながら、家族のいない日本で技能実習生として月収10万円で暮らすのと、貧困国であっても母国の、設備の整った職場で年収10万円で暮らすのを比較して、日本産製品選択がすなわち是とも言いきれない。割増の対価を払うのなら正当性を自分自身で見極める、さもなくば逆効果もあり得るのだ。
『ファットテール分布は直感に反する』。1ドルの価値や所得の不均衡、格差などをグラフで見ると歪さに気づく。公正な数値化と比較はやっぱり大事だ。援助活動もファットテール分布を描く。つまりずば抜けて有効な援助だけに注力すれば絶大な効果を得られるのだが、機能するプログラムとそうでないプログラムを見極めるのは難しく、同時に効果的なプログラムの多くはきわめて効果的だという理由ですでに十分な資金提供を受けているのであり、ほんなんどないせえっちゅうねん。とぼやきたくはなる。これも"見極めが大事"案件。
読了日:07月20日 著者:ウィリアム・マッカスキル

 四国辺土 幻の草遍路と路地巡礼の感想
四国辺土 幻の草遍路と路地巡礼の感想遍路道と被差別部落の分布が重なる点に着目した著者は四国を歩き始めた。遍路は重たいものを抱えた者、行き場のない者、逃げる者を受け止める。『遍路に出る人はみな何かあるから遍路をする』。そして遍路は、巡り続けることができるのだ。著者は遍路だけで暮らす草遍路に惹かれ、追い始める。それぞれの事情で、歩き続けることによって生きる人生を選ぶ人たち。やっぱり遍路には形式でない、深いなにかがある。山頭火や西行に比べ、現世生身の人間はどうしたって生臭さ金臭さが先に立つが、巡り続けるうちに至る境地は彼らに近づくのだと思った。
遍路つながり。こちらも香川県は手薄に終わるかと思いきや、福田村事件が大きく扱われている。しかしこの事件は最近出た新刊で深く読みたいので、軽く流す。宮本常一翁は書いた。『四国というところは、明治の終わりごろまではそういう遍路や乞食にみちみちたところであった』。たくさんの脱藩者を出した土佐がお遍路に厳しかったり、逆に道後の温泉はお遍路に料金を優遇したり、お遍路に多かったハンセン病者が大島青松園のような療養所に強制収容されたり、途切れなく続く歴史と文化の中に生きているんだなあと感じるところが多かった。
読了日:07月19日 著者:上原 善広

 作家の秘められた人生 (集英社文庫)の感想
作家の秘められた人生 (集英社文庫)の感想フランスでの話題作ということだ。作家が作品を書くという行為について、少々ややこしい構造になったミステリ。作家になりたい。書きたい。だからといってなぜ尊敬する作家が隠遁している邸宅に忍び込んで、暴露本を書こうなんて動機が成立するのか。納得がいかない成り行きを保留にしながら探索は進み、達した結末は、それなりのものだった。世間離れした小さな離島の中だけで展開した事件は、20世紀末のバルカン半島の動乱へと広がりを見せる。その掘り進めていく感じが、この作家の持ち味か。物語の中に、幼い魂だけがきらめく。
読了日:07月17日 著者:ギヨーム・ミュッソ
 お遍路 (中公文庫)の感想
お遍路 (中公文庫)の感想大正7年、うら若い女性が九州から単身歩き遍路に出る。現代でもよほどの決断だが、当時はもっと有り得ない行動と推測される。途中で会った見知らぬおじいさんと同行する。九州から船で八幡浜へ渡った人は、そこから巡礼を始めると知った。そして順打ちより逆打ちのほうが道が大変で、修行のためあえてそちらを選ぶことも。この記録は結願後、自らの記録と文献資料を併せて時系列に記述する形式。阿波や土佐、伊予に比べ讃岐の記述は薄い。高知から歩き始めたので、讃岐が無心になる頃合いなのか、それとも何も特筆すべきことが無かったのか。
目や足が不自由な人も遍路を巡った。むしろそのような困難を背負った人こそ遍路へ向かった。五体満足でも転がりそうな我らが国分寺の"遍路コロガシ"を皆上り下りしたそうだ。お互い助け合ってではあろうが、なんとも厳しい。善根宿、遍路宿、乞食宿、通夜、野宿。お接待は期待しないからありがたいのであって、迷惑がる人も多かったろう。この時代、国家権力による迫害も激しかったようだ。『幾ら身分はあっても遍路は遍路じゃないか。こら娘、その爺さんによく言ってきかせろ、分ったか。罪は成り立つのじゃが、特別をもって許しとくけに』。
読了日:07月16日 著者:高群 逸枝

 こんな一冊に出会いたい 本の道しるべ (NHK趣味どきっ!)の感想
こんな一冊に出会いたい 本の道しるべ (NHK趣味どきっ!)の感想一箱古本市で、よその出店者さんに教えてもらって購入。前にも番組になっていたのだ。新しいほうの、立派な本棚に圧倒された後では確かに物足りない部分はある。収穫は橋本麻里さん。『全部を読破するのは不可能です。それでも本を所蔵し、棚に並べることには大きな意義があります』。橋本家ほどの本は収集できなくても、『本の向こうに広がる世界への入り口』はつくれると思う。前にもどこかに書いたけれど、読まなくても、背中を眺めているうちに得るものがある。橋本さんはそれを自分用の知識のマップと言う。本の処分も、よく吟味しなくては。
読了日:07月15日 著者:平松 洋子,矢部 太郎,渡辺 満里奈,祖父江 慎,橋本 麻里,穗村 弘,飛田 和緒,坂本 美雨,和氣 正幸,菊池 亜希子
 めんどくさいロシア人から日本人への感想
めんどくさいロシア人から日本人への感想6歳からずっと日本で暮らしてればそりゃ日本人でしょ。ソ連時代の人々の暮らしの様子がなんでもカネカネでなかった頃の日本と似ていると気づいたり、帰化の条件に「日本国・日本政府・日本国憲法に反する思想を持っていた過去がないこと」という項目があると知ったり、いろいろ興味深い。「お付き合いする先のゴールがない」から恋愛に積極的になれないって言うのには、反射的にもったいないと思ってしまった。家族や子供を持つ未来は誰もが描けたほうがいいのにな。遺伝子的にどん詰まりなのは私も同じだし。それでもできれば楽しげなのがいいよ。
読了日:07月14日 著者:小原ブラス

 「その他の外国文学」の翻訳者の感想
「その他の外国文学」の翻訳者の感想メジャーに扱われない言語で書かれた小説の翻訳者さんを取材した形式。おすすめ本や店頭など、どこかしらで私のアンテナにもかかっているようで、本棚や積読にちらほら見受けるのに気づいて驚いた。若い頃は海外小説ならアメリカと思い込んでいた節があり、またそれ以外は目に入らなかったのだが、最近は新潮クレストや白水社のような大手から小さな出版社まで、実は多く出版されていて有難いことだ。思うに、英語に代表される強者の言語フィルターを通さずに、原語から日本語で読めることは、贅沢でもあり、世界を見る目を養う肝要さを持っている。
読了日:07月10日 著者:
 本土の人間は知らないが、沖縄の人はみんな知っていること (ちくま文庫)の感想
本土の人間は知らないが、沖縄の人はみんな知っていること (ちくま文庫)の感想沖縄は古来、覇権争いの要衝として望まずして権力争いに巻き込まれてきた。基地問題は今の沖縄にとって最たるもの、 アメリカと日本政府の動向は、知るも何も、生活を直接に左右する。敗戦以降、外務省や防衛省はアメリカの意に沿うことを最優先してきた。頻繁に開かれる在日米軍高官との機密会合、政治家は総理になって初めてその鉄の掟と密約を知らされ、背けない。主権国家として有り得ない、日本国民の意思がまるで通用しない領域。この歪みが本土にいるとなんでこんなに見えなくなるのか。「小指の痛み」はいずれ、全身の痛みになるのだろう。
東京南麻布の「ニュー山王ホテル」はアメリカ海軍の管轄下にある。ホテルとして泊まれるが、その実はニューサンノー米軍センター、一般日本人単独では泊まれない。観光協会のサイトでも「米国軍関係者向けの宿泊施設、保養所、社交場」とある。上記「日米地位協定各条に関する日米合同委員会」が開かれる場所でもある。当然治外法権。こういう事実にいちいち衝撃を受けているようでは、激甘の世間知らずなのだと、いったんは思うのに、自分の生活に実害が無いとすぐに忘れる。戦争に巻き込まれる羽目になって初めて、身に沁みるのだろう。
読了日:07月09日 著者:矢部 宏治
 ロビンソン・クルーソーを探して (新潮文庫)の感想
ロビンソン・クルーソーを探して (新潮文庫)の感想デフォーの創作であるロビンソン・クルーソーのモデルであるところの船乗り、セルカークは確かにその島で生きていた。1721年に死去したセルカークの足跡は途切れがちでもちゃんと残っている。すり減りきったナイフとラストの大発見が読みどころではあるが、手がかりを追う探求の旅は、シーナさんや高野さんと違ってひたすら真面目な文章なので、少々退屈気味だった。クルーソーもセルカークも、見晴らしは良いが周りから見えにくい場所に住処を建てて、さらに木を植えた。ということは、デフォーはセルカークに直接会ったのだろうか?
読了日:07月08日 著者:高橋 大輔
 秘書綺譚―ブラックウッド幻想怪奇傑作集 (光文社古典新訳文庫)の感想
秘書綺譚―ブラックウッド幻想怪奇傑作集 (光文社古典新訳文庫)の感想暗い夜の、人気のない家で、男が怪異に呑まれる。なにもそんなとこに行かなくてもいいのに、頼りがいがあるような無いようなMr.ショートハウスと共に乗り込んでもこちらはまったく安心できないという不思議な設定。その怪異はその人の咎ではなく、過去や他の住人や、つまり外部に由来するのが特徴である。勧善懲悪やら因果応報やら考えずに読めて楽しい。表題をひとつの山場に、その後はがらりと趣向が変わる。イギリスはヒースの野原、アメリカは荒野など、世界は常識ばかりでできてないと言いたげな自由な感じが良い。
読了日:07月07日 著者:アルジャーノン ブラックウッド

 こどもの一生 (集英社文庫)の感想
こどもの一生 (集英社文庫)の感想らもさんの本で読んでいないものも残りわずか、と読み惜しんでいた小説。しかし読みながら、私は何を愛おしんでらもさんの本を読むのかが思い出せなくなってきてしまった。というわけで、いちばん心を動かされたのはあとがきである。これはらもさんが書いた脚本の舞台のノベライズだったのだ。笑う態勢万全で来る観客に、恐怖を。その思惑が成ったらもさんは劇場後部でほくそ笑んでいる。この物語は舞台に映える。その視覚を振り切って言葉で構築し直すのは難しかったと思う。失明したりしながらあえて小説として世に出したらもさんの姿を私は愛す。
読了日:07月03日 著者:中島 らも

注:
 は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。 2023年07月01日
2023年6月の記録
今年も海の見える一箱古本市&せとうちのみの市に参加することになりました。
読み終えて手放そうと思っている本はたくさんあるのでもうよいようなものの、
もう一冊でも多く読み終えておこうと息巻いてしまう。

<今月のデータ>
購入13冊、購入費用12,262円。
読了16冊。
積読本333冊(うちKindle本165冊、Honto本3冊)。

 NHK出版 学びのきほん フェミニズムがひらいた道 (教養・文化シリーズ)の感想
NHK出版 学びのきほん フェミニズムがひらいた道 (教養・文化シリーズ)の感想
ひとつには過去の話。私が社会へ出る少し前、男女雇用均等法が話題となり、女性も仕事を持ってバリバリ働くのだと素直に受け取った。社会に出て奮闘しているうちに、聡い同級生はとっとと寿退社して専業主婦になっていた。ひとつには現在の話。それでも女性の地位は過去の活動家の女性が勝ち得てきてくれた贈りものであり、今この時も心を傷だらけにして闘っている女性たちがいる。そのことに無感覚でいたくはない。団結して行動を起こすまでいかなくとも、「あれもまたムーブメントだった」と回顧できる、より良いほうへ向かう流れに沿っていたい。
読了日:06月30日 著者:上野 千鶴子
 いのちの教室の感想
いのちの教室の感想
ライアル・ワトソンは南アフリカ共和国に生まれ育った。白人に偏らない環境ゆえに、大地に足のついた言葉を語ることができる。だから「エレファントム」を読んだとき、フィクションかノンフィクションか迷うような独特な印象を受けたのだ。アフリカのブッシュに育つ感覚×動物行動学のハイブリッド。3代以上前に渡ったということは、彼の祖母であるオウマも生粋のアフリカ育ちである。地元の諸民族に一目置かれる特別な女性。コウノトリに縦縞ズボンを履かせ、オウパを大地に葬る。大地に根差す智を我がものとして羽ばたかせる生きかたに敬服する。
読了日:06月25日 著者:ライアル・ワトソン
 お茶人のための 茶花の野草大図鑑 改訂普及版の感想
お茶人のための 茶花の野草大図鑑 改訂普及版の感想
茶花の図鑑なら、日本らしい植物がたくさん載っているとふんで中古で入手。日本のどの地方に自生しているか、いつ頃舶来したか、名の由来など短くも興味深い記述満載で、写真も明瞭。音で聞くと洋物のように思っていた植物でも、漢字で書いて由来の古いものもたくさんあると知る。藪柑子、唐種小賀玉、酢漿草、射干、郁李、藺など、そう書くのか!と驚いたりうっとりしたり、いつまでも頁を繰っていたい満足感。私は茶人ではないので、活ける例は眺めて感心するばかり。花器の形や組み合わせにも定石のようなものがあるようで、茶の道の深さに慄く。
読了日:06月24日 著者:宗匠
 海洋プラスチック 永遠のごみの行方 (角川新書)の感想
海洋プラスチック 永遠のごみの行方 (角川新書)の感想
プラスチックごみ問題の事実を整理してある。熱回収、リサイクル、バイオプラ、いずれにせよ資源を消費することに変わりはない。さらに再生プラスチックの需要とコスト、資源回収時の汚れ問題、素材の複雑化で問題はさらに難解になる。使わないにこしたことはない。さて、海に浮いているはずのプラスチックごみの99%の行方が分からないという。マイクロプラスチックどころかナノプラスチックにまで細粒化されて人間が追跡できないのではと想像してみる。また、生分解性プラスチックは種類ごとに分解される環境が異なる。問題は解決しなさそうだ。
イケアの製品はプラスチックだらけである。環境先進国と呼ばれるスウェーデン発のこの企業は、どのようなスタンスでプラスチック製品を大量生産しているのかふと疑問に思い確認してみた。イケアは自社製品について目標を表明している。リサイクルプラスチックまたは再生可能なプラスチックのみを製品に使用すること。使い捨てプラスチックを廃止すること。リサイクルしやすいPETとPPを多く使うこと。有害成分を削減すること。まあ、そうなるしかないだろう。それを受け入れて購入し、使うかどうかは、こちら側の選択にかかっている。
読了日:06月24日 著者:保坂 直紀
 農は過去と未来をつなぐ――田んぼから考えたこと (岩波ジュニア新書)の感想
農は過去と未来をつなぐ――田んぼから考えたこと (岩波ジュニア新書)の感想
日本農業新聞のコラム執筆者。自らを"百姓"の代弁者と位置付ける。なるほど、農家があまりに当たり前と思って口に出さないことが、非農家の私にとっては未知であること、それ故に体感も考え方も違うという事実をお互いに知らないのだと知った。そして「自給」について。「買った方が安い」あるいは自分でつくれない種類の道具を必要と考えると、人は購入に依存した暮らし方へ移行してしまう。いろいろなものを自分でつくり工夫する生活をやめてしまう。農家でなくてもそうだ。やせ我慢でなく「効率を上げる道具」を否む生活をも、私たちは選べる。
読了日:06月22日 著者:宇根 豊
 楽園とは探偵の不在なり (ハヤカワ文庫JA)の感想
楽園とは探偵の不在なり (ハヤカワ文庫JA)の感想
自ら創作した謎解きルールの枠内で進行する本格推理ゲーム。設定はともかく「天使」の造形が、全編にわたって不気味な色調に染める。『私はあなたの助けを必要としています』。エラリイを想い出した。期待されようとされまいと、調べずにいられない、推理せずにいられない、探偵の「業」と呼んでよいのではないだろうか。表題はテッド・チャン「地獄とは神の不在なり」を踏まえる。テーマもインスパイアされていると著者があとがきに書いている。そちらも読んだはずだが、読んだときぴしっとこなかったものは片っ端から忘れるお歳頃である。
読了日:06月19日 著者:斜線堂 有紀
 すべての企業人のためのビジネスと人権入門の感想
すべての企業人のためのビジネスと人権入門の感想
大手企業を想定した内容。国内外の時事を耳に入れていれば常識的なことばかりである。しかし一方で、理解していない人が少なくないことも、社会を見ていれば判る。人権にはセンスが必要だ。社内のハラスメントや差別だけが人権ではない。そして『人権リスクのない企業など存在しない』。人権に限らず、自社の抱える課題に気づくことによって本業に新たな観点が生まれるのだけどね。著者は経産大臣のアドバイザーも務める。日本政府は経済に影響があるとなると重い腰を上げるが、女性や難民、LGBTQについてはずいぶん冷淡だ。ちぐはぐが目立つ。
煽り帯。『「脱炭素」の次は「人権」が来る!』なんてビジネスのネタみたいに言うなよ。と思ったらほんとに「人権ビジネスは未曽有のフロンティア」って章があってのけぞる。いやいや「環境ビジネス」もたいがい品性に欠けるし。「人権配慮型ビジネス」なら理解できないこともないが、人の多様性に配慮するとか社会課題を解決するとかって意味合いなら、んなたいそうな名前つけんでも企業の創意発案の範囲だし、営業をかける相手の企業に売り込むなどコンサルらしい押しつけがましさである。ビッグビジネスにとか勝機とか、そういうの無しで行こう。
読了日:06月17日 著者:羽生田 慶介
 謎のアジア納豆 そして帰ってきた〈日本納豆〉 (新潮文庫)の感想
謎のアジア納豆 そして帰ってきた〈日本納豆〉 (新潮文庫)の感想
やあ、快作。高野さんはムベンベではなく納豆で後世に名を遺すのだなあ。あちこちでつくった人脈がこの件にも怪しい情報や楽しい取材へと導いていくのが、高野さんの円熟味を顕しているようで、安心して読める。息もつかせぬ、アジアを股に掛けたオール納豆な展開。インドのシーク教徒が作る納豆チャーハンが好ましいと同時に、僻地に住むおばあさんが守っている伝統の製法もかけがえなく、食べる全ての人にそれぞれに手前納豆と流儀があるのは、まさに未来への希望だ。巻末解説の小倉ヒラク氏がディープさに追い打ちをかける。次作も見届けないと。
読了日:06月16日 著者:高野 秀行
 音楽と生命 (新書企画室単行本)の感想
音楽と生命 (新書企画室単行本)の感想
光沢のある装丁が美しくて手に取った本。元となるEテレ「SWITCHインタビュー」の対談は、そういえば観たのだったか。福岡センセと坂本龍一の静かで深い対話はまさに目前に見るようだと思ったのも当然である。二人の対話は、音楽と自然音、近代的医学と民間医療や漢方薬などテーマを変えながら、ロゴスとピュシスという主題を巡り、回帰していく。生きることや音楽の演奏が、そのとき一度きりの存在であるのと同様、このいくつかの対話もそれ自体が一度きりのものである。その尊さを想うと、表紙がますます白く見えるのは、感傷だろうけれど。
読了日:06月13日 著者:坂本 龍一,福岡 伸一
 DRAWDOWNドローダウン― 地球温暖化を逆転させる100の方法の感想
DRAWDOWNドローダウン― 地球温暖化を逆転させる100の方法の感想
地球温暖化こと気候変動は人為由来で二酸化炭素が犯人という前提なので、個人的に怪しいと感じるものを含め、その方向に沿った項目が並ぶ。「今後注目の解決策」は興味深いが、私でも革新的と思えるものは一部だった。分類すると、新しい科学技術の推進、教育・啓発の普及、動植物パワーの復古である。人間が地球にかけ続けている悪影響を逆転にしたいなら、例えば鉱物採掘で更なる環境負荷を増やしたり、遺伝子操作で捻じ曲げたりでなく、自然に沿うのが良い。新しい科学技術は必ずその生産や廃棄の部分で環境負荷や反動が大きくなるのが自明だ。
『大規模な電気事業者のビジネスモデルは分散型エネルギーや分散型ストレージとの共存が困難です。電気事業者は時代遅れになりつつある発電と送電のシステムに投資してきました。電気事業者が抵抗する場合、マイクログリッドにとって最大の壁は技術ではなく、独占です』。「ガイアの夜明け」で愛媛県西条市にできたマイクログリッド施設を取り上げていた。物販棟+ホテルで、電気は創エネ×蓄電池である。大手電気事業者や役所が動けないなら、民間がやるしかない。しかし蓄電池だけで数億! その実行力に敬服する。
紙はバージンパルプよりリサイクルパルプのほうが、森林伐採、水資源消費、化学物質流出すべてを抑える。温室効果ガスで言うなら、それもはるかに排出が少ないとの研究結果が出ている。
読了日:06月11日 著者:ポール・ホーケン
 堤未果のショック・ドクトリン 政府のやりたい放題から身を守る方法 (幻冬舎新書 690)の感想
堤未果のショック・ドクトリン 政府のやりたい放題から身を守る方法 (幻冬舎新書 690)の感想
日本で納税している人には読んでほしい。そして判断してほしい。なぜシステムが正常に働いていないのがわかっているのに為政者は止めようとしないか。止められたら困る人がいるからだ。政府や大企業が自分たちの利権優先で決めてしまう枠組みに、私たちは否応なく嵌められてしまう。お金だけでなく、生きる権利すら制限され始めているなかで、私たちはどのように抵抗できるのか。最後まで選択肢を手放さない事。まずはセキュリティや透明性が確立されるまでカードはつくらない、使わないという意思表示をすることだ。「100分de名著」が楽しみ。
『命に関わる感染症を理由に、政府が国民の不安につけこんできたとき、アラームが鳴ったんです。憲法を踏みにじるほど政府が暴走したときに立ち上がるのは、自分のためというより、この先を生きる子供たちに対する、私たち大人の責任ですからね。だから「ノー」と言ったんです。後悔しないために』。
『個人データは最大資産。リスクは極力分散し、安心できるルールができるまでは自己責任で死守せよ』。現代社会の一つの本質。それは今までも断片は見えていたから、不安は感じていた。でもオリンピックのような利権満載イベントだけじゃなく、脱炭素も新型コロナワクチンも復興事業も、全て誰かにとって都合の良い思惑だったようだ。政府とメディアが大手を振って推してくるものほどファクトチェックをしなければならない。ほぼほぼ、都合の悪いものが隠されているということだ。もちろん、堤さんの言葉を鵜呑みにするのではなく自分で確認する。
読了日:06月06日 著者:堤 未果
 迷蝶の島 (河出文庫)の感想
迷蝶の島 (河出文庫)の感想
海とヨットと島と。トリックが全てなので、もうなんにも言えません。浅はかな男には同情のかけらも覚えることができず、だからこそ彼女には、もっとやれーとばかり興が乗ってしまった。それだけに、最後は余計じゃなかったかしら。
読了日:06月04日 著者:泡坂妻夫
 季刊環境ビジネス2023年春号の感想
季刊環境ビジネス2023年春号の感想
"環境"をダシにしてがっつり稼ぐ気満々な企業の広告記事ばかりでげんなりする。風向きを知るために仕方ないが、この雑誌は後半が面白い。海外レポートは参考になる。ウクライナ・ロシア情勢を背景に、各国が国内再エネをリスク低減策と判断し切替を進めている。ドイツは再エネを他の電力源より優先すると法的に決めているので、再エネ化が進むのに対し、日本は値上げにしろ電力源の優先順位にしろ、国営みたいな電力会社が自社の収益都合で決めるので、これでは変われるはずがない。今日も天気が良すぎるので太陽光発電を止めるようお達しが来た。
『エネルギーが高いか安いかよりも、自国のエネルギーコストが相対的にどのような位置にあるのかを考えていくことが大切です』。『日本は再エネに振り切った方がいいのではないかと思います。少なくとも自国で供給できるエネルギーならば大きな価格の振れは少ないと思います。この不安定な世界の中で唯一リスクを減らす方策は国内の再エネではないかと考えます。(中略)輸入化石燃料のような不安定なものに頼ることは、経済的にはあまり合理的ではないはずです』。
読了日:06月03日 著者:
 風をつかまえた少年 14歳だったぼくはたったひとりで風力発電をつくった (文春文庫)の感想
風をつかまえた少年 14歳だったぼくはたったひとりで風力発電をつくった (文春文庫)の感想
マラウイで風車を立てて発電し、電気を手に入れる。その重要性を、読んで初めて理解した。この現代に、マラウイには干ばつで飢饉が起こる。食べものもお金も仕事もみるみる無くなり、なす術もなく痩せこけた体で飢えてさ迷う隣人たちを、私と世代の近いこの少年は克明に記憶している。学校にも行けず、同級生も犬も死んだ。電気でもっと簡便に水を手に入れられれば、その余った時間で他の生産的な作業ができる。家族が飢えずにすむようにできる。つまり自然エネルギーで電気をつくれれば、生活の質が桁違いに変わる。その欲求の切実さが胸に刺さる。
無いからこそ、自分の手でつくる。おもちゃも狩りの道具も、子供のときから他の用途に使っていた物や廃品を拾ってつくるのが当たり前という環境が、風力発電設備を自力でつくるという到達点につながっている。遊び方のあらかじめ決められた玩具や、お膳立ての整ったDIYで満足しているのが恥ずかしくなるような、人間の持つ能力の可能性において決定的な相違だ。この貪欲さとポテンシャルが相まって、かの国々は今後爆発的に伸びてゆくのだろう。楽しみだ。
『アフリカ人は毎日、手元にあるわずかなものを使って、なんとか自分の思いどおりのものをつくろうとしている。精いっぱいの想像力を駆使して、アフリカに課せられた難題を克服しようとしている。アフリカが世界がごみと思うものをリサイクルしている。アフリカは世界ががらくたと思うものを再生している』。
読了日:06月02日 著者:ウィリアム・カムクワンバ,ブライアン・ミーラー
 「惜別」の意図の感想
「惜別」の意図の感想
ええと。これを太宰は素面で書いたんやろか。当時、太宰は多忙だったという。それでも、情報局の要請とあらば拒めるものではなかろうと推察できるけれど、『日本人の生活には西洋文明と全く違つた獨自の凜乎たる犯しがたい品位』や清潔感があったなど、どこまで本気だったのだろうか。末尾の『現代の中國の若い智識人に讀ませて、日本にわれらの理解者ありの感懷を抱かしめ、百發の彈丸以上に日支全面和平に效力あらしめんとの意圖を存してゐます。』が全てを語っているのではないか。執筆を命じた向きへの宣言であり決意表明である。
今のきな臭い世界情勢にあって、ここは私がずっと考えているテーマの一つである。ある程度の正しい情報を得られる社会的位置にある者が、国家権力が旗を振って誘導する筋立てを本当に信じていたのか、信じないならばどのような態度を取り、どのような過程を経て破滅に突き進んだのか。
読了日:06月01日 著者:太宰 治
 惜別の感想
惜別の感想
太宰はなぜ魯迅を描こうとしたのか、純粋に疑問に思って。「藤野先生」の逸話への感動や、留学生である魯迅の、同級生から徹頭徹尾はみ出さざるをえない境遇、帰国前の「近代文明を病んで悩んだ」日々への共感あたりに熱を感じる。太宰に魯迅が憑依したというより、魯迅に太宰が憑依したかのような饒舌だったからだ。しかし、あとがきに太宰はこの小説が内閣情報局と文学報国会との依嘱であったと明かしている。文学報国会は情報局の実質的な外郭団体であるとのこと。戦局も悪化した時分でもあり、一挙に胡散臭さが充満するのはやむなしとする。
読了日:06月01日 著者:太宰 治
注: は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。
読み終えて手放そうと思っている本はたくさんあるのでもうよいようなものの、
もう一冊でも多く読み終えておこうと息巻いてしまう。
<今月のデータ>
購入13冊、購入費用12,262円。
読了16冊。
積読本333冊(うちKindle本165冊、Honto本3冊)。

 NHK出版 学びのきほん フェミニズムがひらいた道 (教養・文化シリーズ)の感想
NHK出版 学びのきほん フェミニズムがひらいた道 (教養・文化シリーズ)の感想ひとつには過去の話。私が社会へ出る少し前、男女雇用均等法が話題となり、女性も仕事を持ってバリバリ働くのだと素直に受け取った。社会に出て奮闘しているうちに、聡い同級生はとっとと寿退社して専業主婦になっていた。ひとつには現在の話。それでも女性の地位は過去の活動家の女性が勝ち得てきてくれた贈りものであり、今この時も心を傷だらけにして闘っている女性たちがいる。そのことに無感覚でいたくはない。団結して行動を起こすまでいかなくとも、「あれもまたムーブメントだった」と回顧できる、より良いほうへ向かう流れに沿っていたい。
読了日:06月30日 著者:上野 千鶴子

 いのちの教室の感想
いのちの教室の感想ライアル・ワトソンは南アフリカ共和国に生まれ育った。白人に偏らない環境ゆえに、大地に足のついた言葉を語ることができる。だから「エレファントム」を読んだとき、フィクションかノンフィクションか迷うような独特な印象を受けたのだ。アフリカのブッシュに育つ感覚×動物行動学のハイブリッド。3代以上前に渡ったということは、彼の祖母であるオウマも生粋のアフリカ育ちである。地元の諸民族に一目置かれる特別な女性。コウノトリに縦縞ズボンを履かせ、オウパを大地に葬る。大地に根差す智を我がものとして羽ばたかせる生きかたに敬服する。
読了日:06月25日 著者:ライアル・ワトソン
 お茶人のための 茶花の野草大図鑑 改訂普及版の感想
お茶人のための 茶花の野草大図鑑 改訂普及版の感想茶花の図鑑なら、日本らしい植物がたくさん載っているとふんで中古で入手。日本のどの地方に自生しているか、いつ頃舶来したか、名の由来など短くも興味深い記述満載で、写真も明瞭。音で聞くと洋物のように思っていた植物でも、漢字で書いて由来の古いものもたくさんあると知る。藪柑子、唐種小賀玉、酢漿草、射干、郁李、藺など、そう書くのか!と驚いたりうっとりしたり、いつまでも頁を繰っていたい満足感。私は茶人ではないので、活ける例は眺めて感心するばかり。花器の形や組み合わせにも定石のようなものがあるようで、茶の道の深さに慄く。
読了日:06月24日 著者:宗匠
 海洋プラスチック 永遠のごみの行方 (角川新書)の感想
海洋プラスチック 永遠のごみの行方 (角川新書)の感想プラスチックごみ問題の事実を整理してある。熱回収、リサイクル、バイオプラ、いずれにせよ資源を消費することに変わりはない。さらに再生プラスチックの需要とコスト、資源回収時の汚れ問題、素材の複雑化で問題はさらに難解になる。使わないにこしたことはない。さて、海に浮いているはずのプラスチックごみの99%の行方が分からないという。マイクロプラスチックどころかナノプラスチックにまで細粒化されて人間が追跡できないのではと想像してみる。また、生分解性プラスチックは種類ごとに分解される環境が異なる。問題は解決しなさそうだ。
イケアの製品はプラスチックだらけである。環境先進国と呼ばれるスウェーデン発のこの企業は、どのようなスタンスでプラスチック製品を大量生産しているのかふと疑問に思い確認してみた。イケアは自社製品について目標を表明している。リサイクルプラスチックまたは再生可能なプラスチックのみを製品に使用すること。使い捨てプラスチックを廃止すること。リサイクルしやすいPETとPPを多く使うこと。有害成分を削減すること。まあ、そうなるしかないだろう。それを受け入れて購入し、使うかどうかは、こちら側の選択にかかっている。
読了日:06月24日 著者:保坂 直紀

 農は過去と未来をつなぐ――田んぼから考えたこと (岩波ジュニア新書)の感想
農は過去と未来をつなぐ――田んぼから考えたこと (岩波ジュニア新書)の感想日本農業新聞のコラム執筆者。自らを"百姓"の代弁者と位置付ける。なるほど、農家があまりに当たり前と思って口に出さないことが、非農家の私にとっては未知であること、それ故に体感も考え方も違うという事実をお互いに知らないのだと知った。そして「自給」について。「買った方が安い」あるいは自分でつくれない種類の道具を必要と考えると、人は購入に依存した暮らし方へ移行してしまう。いろいろなものを自分でつくり工夫する生活をやめてしまう。農家でなくてもそうだ。やせ我慢でなく「効率を上げる道具」を否む生活をも、私たちは選べる。
読了日:06月22日 著者:宇根 豊

 楽園とは探偵の不在なり (ハヤカワ文庫JA)の感想
楽園とは探偵の不在なり (ハヤカワ文庫JA)の感想自ら創作した謎解きルールの枠内で進行する本格推理ゲーム。設定はともかく「天使」の造形が、全編にわたって不気味な色調に染める。『私はあなたの助けを必要としています』。エラリイを想い出した。期待されようとされまいと、調べずにいられない、推理せずにいられない、探偵の「業」と呼んでよいのではないだろうか。表題はテッド・チャン「地獄とは神の不在なり」を踏まえる。テーマもインスパイアされていると著者があとがきに書いている。そちらも読んだはずだが、読んだときぴしっとこなかったものは片っ端から忘れるお歳頃である。
読了日:06月19日 著者:斜線堂 有紀

 すべての企業人のためのビジネスと人権入門の感想
すべての企業人のためのビジネスと人権入門の感想大手企業を想定した内容。国内外の時事を耳に入れていれば常識的なことばかりである。しかし一方で、理解していない人が少なくないことも、社会を見ていれば判る。人権にはセンスが必要だ。社内のハラスメントや差別だけが人権ではない。そして『人権リスクのない企業など存在しない』。人権に限らず、自社の抱える課題に気づくことによって本業に新たな観点が生まれるのだけどね。著者は経産大臣のアドバイザーも務める。日本政府は経済に影響があるとなると重い腰を上げるが、女性や難民、LGBTQについてはずいぶん冷淡だ。ちぐはぐが目立つ。
煽り帯。『「脱炭素」の次は「人権」が来る!』なんてビジネスのネタみたいに言うなよ。と思ったらほんとに「人権ビジネスは未曽有のフロンティア」って章があってのけぞる。いやいや「環境ビジネス」もたいがい品性に欠けるし。「人権配慮型ビジネス」なら理解できないこともないが、人の多様性に配慮するとか社会課題を解決するとかって意味合いなら、んなたいそうな名前つけんでも企業の創意発案の範囲だし、営業をかける相手の企業に売り込むなどコンサルらしい押しつけがましさである。ビッグビジネスにとか勝機とか、そういうの無しで行こう。
読了日:06月17日 著者:羽生田 慶介

 謎のアジア納豆 そして帰ってきた〈日本納豆〉 (新潮文庫)の感想
謎のアジア納豆 そして帰ってきた〈日本納豆〉 (新潮文庫)の感想やあ、快作。高野さんはムベンベではなく納豆で後世に名を遺すのだなあ。あちこちでつくった人脈がこの件にも怪しい情報や楽しい取材へと導いていくのが、高野さんの円熟味を顕しているようで、安心して読める。息もつかせぬ、アジアを股に掛けたオール納豆な展開。インドのシーク教徒が作る納豆チャーハンが好ましいと同時に、僻地に住むおばあさんが守っている伝統の製法もかけがえなく、食べる全ての人にそれぞれに手前納豆と流儀があるのは、まさに未来への希望だ。巻末解説の小倉ヒラク氏がディープさに追い打ちをかける。次作も見届けないと。
読了日:06月16日 著者:高野 秀行

 音楽と生命 (新書企画室単行本)の感想
音楽と生命 (新書企画室単行本)の感想光沢のある装丁が美しくて手に取った本。元となるEテレ「SWITCHインタビュー」の対談は、そういえば観たのだったか。福岡センセと坂本龍一の静かで深い対話はまさに目前に見るようだと思ったのも当然である。二人の対話は、音楽と自然音、近代的医学と民間医療や漢方薬などテーマを変えながら、ロゴスとピュシスという主題を巡り、回帰していく。生きることや音楽の演奏が、そのとき一度きりの存在であるのと同様、このいくつかの対話もそれ自体が一度きりのものである。その尊さを想うと、表紙がますます白く見えるのは、感傷だろうけれど。
読了日:06月13日 著者:坂本 龍一,福岡 伸一

 DRAWDOWNドローダウン― 地球温暖化を逆転させる100の方法の感想
DRAWDOWNドローダウン― 地球温暖化を逆転させる100の方法の感想地球温暖化こと気候変動は人為由来で二酸化炭素が犯人という前提なので、個人的に怪しいと感じるものを含め、その方向に沿った項目が並ぶ。「今後注目の解決策」は興味深いが、私でも革新的と思えるものは一部だった。分類すると、新しい科学技術の推進、教育・啓発の普及、動植物パワーの復古である。人間が地球にかけ続けている悪影響を逆転にしたいなら、例えば鉱物採掘で更なる環境負荷を増やしたり、遺伝子操作で捻じ曲げたりでなく、自然に沿うのが良い。新しい科学技術は必ずその生産や廃棄の部分で環境負荷や反動が大きくなるのが自明だ。
『大規模な電気事業者のビジネスモデルは分散型エネルギーや分散型ストレージとの共存が困難です。電気事業者は時代遅れになりつつある発電と送電のシステムに投資してきました。電気事業者が抵抗する場合、マイクログリッドにとって最大の壁は技術ではなく、独占です』。「ガイアの夜明け」で愛媛県西条市にできたマイクログリッド施設を取り上げていた。物販棟+ホテルで、電気は創エネ×蓄電池である。大手電気事業者や役所が動けないなら、民間がやるしかない。しかし蓄電池だけで数億! その実行力に敬服する。
紙はバージンパルプよりリサイクルパルプのほうが、森林伐採、水資源消費、化学物質流出すべてを抑える。温室効果ガスで言うなら、それもはるかに排出が少ないとの研究結果が出ている。
読了日:06月11日 著者:ポール・ホーケン
 堤未果のショック・ドクトリン 政府のやりたい放題から身を守る方法 (幻冬舎新書 690)の感想
堤未果のショック・ドクトリン 政府のやりたい放題から身を守る方法 (幻冬舎新書 690)の感想日本で納税している人には読んでほしい。そして判断してほしい。なぜシステムが正常に働いていないのがわかっているのに為政者は止めようとしないか。止められたら困る人がいるからだ。政府や大企業が自分たちの利権優先で決めてしまう枠組みに、私たちは否応なく嵌められてしまう。お金だけでなく、生きる権利すら制限され始めているなかで、私たちはどのように抵抗できるのか。最後まで選択肢を手放さない事。まずはセキュリティや透明性が確立されるまでカードはつくらない、使わないという意思表示をすることだ。「100分de名著」が楽しみ。
『命に関わる感染症を理由に、政府が国民の不安につけこんできたとき、アラームが鳴ったんです。憲法を踏みにじるほど政府が暴走したときに立ち上がるのは、自分のためというより、この先を生きる子供たちに対する、私たち大人の責任ですからね。だから「ノー」と言ったんです。後悔しないために』。
『個人データは最大資産。リスクは極力分散し、安心できるルールができるまでは自己責任で死守せよ』。現代社会の一つの本質。それは今までも断片は見えていたから、不安は感じていた。でもオリンピックのような利権満載イベントだけじゃなく、脱炭素も新型コロナワクチンも復興事業も、全て誰かにとって都合の良い思惑だったようだ。政府とメディアが大手を振って推してくるものほどファクトチェックをしなければならない。ほぼほぼ、都合の悪いものが隠されているということだ。もちろん、堤さんの言葉を鵜呑みにするのではなく自分で確認する。
読了日:06月06日 著者:堤 未果

 迷蝶の島 (河出文庫)の感想
迷蝶の島 (河出文庫)の感想海とヨットと島と。トリックが全てなので、もうなんにも言えません。浅はかな男には同情のかけらも覚えることができず、だからこそ彼女には、もっとやれーとばかり興が乗ってしまった。それだけに、最後は余計じゃなかったかしら。
読了日:06月04日 著者:泡坂妻夫
 季刊環境ビジネス2023年春号の感想
季刊環境ビジネス2023年春号の感想"環境"をダシにしてがっつり稼ぐ気満々な企業の広告記事ばかりでげんなりする。風向きを知るために仕方ないが、この雑誌は後半が面白い。海外レポートは参考になる。ウクライナ・ロシア情勢を背景に、各国が国内再エネをリスク低減策と判断し切替を進めている。ドイツは再エネを他の電力源より優先すると法的に決めているので、再エネ化が進むのに対し、日本は値上げにしろ電力源の優先順位にしろ、国営みたいな電力会社が自社の収益都合で決めるので、これでは変われるはずがない。今日も天気が良すぎるので太陽光発電を止めるようお達しが来た。
『エネルギーが高いか安いかよりも、自国のエネルギーコストが相対的にどのような位置にあるのかを考えていくことが大切です』。『日本は再エネに振り切った方がいいのではないかと思います。少なくとも自国で供給できるエネルギーならば大きな価格の振れは少ないと思います。この不安定な世界の中で唯一リスクを減らす方策は国内の再エネではないかと考えます。(中略)輸入化石燃料のような不安定なものに頼ることは、経済的にはあまり合理的ではないはずです』。
読了日:06月03日 著者:
 風をつかまえた少年 14歳だったぼくはたったひとりで風力発電をつくった (文春文庫)の感想
風をつかまえた少年 14歳だったぼくはたったひとりで風力発電をつくった (文春文庫)の感想マラウイで風車を立てて発電し、電気を手に入れる。その重要性を、読んで初めて理解した。この現代に、マラウイには干ばつで飢饉が起こる。食べものもお金も仕事もみるみる無くなり、なす術もなく痩せこけた体で飢えてさ迷う隣人たちを、私と世代の近いこの少年は克明に記憶している。学校にも行けず、同級生も犬も死んだ。電気でもっと簡便に水を手に入れられれば、その余った時間で他の生産的な作業ができる。家族が飢えずにすむようにできる。つまり自然エネルギーで電気をつくれれば、生活の質が桁違いに変わる。その欲求の切実さが胸に刺さる。
無いからこそ、自分の手でつくる。おもちゃも狩りの道具も、子供のときから他の用途に使っていた物や廃品を拾ってつくるのが当たり前という環境が、風力発電設備を自力でつくるという到達点につながっている。遊び方のあらかじめ決められた玩具や、お膳立ての整ったDIYで満足しているのが恥ずかしくなるような、人間の持つ能力の可能性において決定的な相違だ。この貪欲さとポテンシャルが相まって、かの国々は今後爆発的に伸びてゆくのだろう。楽しみだ。
『アフリカ人は毎日、手元にあるわずかなものを使って、なんとか自分の思いどおりのものをつくろうとしている。精いっぱいの想像力を駆使して、アフリカに課せられた難題を克服しようとしている。アフリカが世界がごみと思うものをリサイクルしている。アフリカは世界ががらくたと思うものを再生している』。
読了日:06月02日 著者:ウィリアム・カムクワンバ,ブライアン・ミーラー

 「惜別」の意図の感想
「惜別」の意図の感想ええと。これを太宰は素面で書いたんやろか。当時、太宰は多忙だったという。それでも、情報局の要請とあらば拒めるものではなかろうと推察できるけれど、『日本人の生活には西洋文明と全く違つた獨自の凜乎たる犯しがたい品位』や清潔感があったなど、どこまで本気だったのだろうか。末尾の『現代の中國の若い智識人に讀ませて、日本にわれらの理解者ありの感懷を抱かしめ、百發の彈丸以上に日支全面和平に效力あらしめんとの意圖を存してゐます。』が全てを語っているのではないか。執筆を命じた向きへの宣言であり決意表明である。
今のきな臭い世界情勢にあって、ここは私がずっと考えているテーマの一つである。ある程度の正しい情報を得られる社会的位置にある者が、国家権力が旗を振って誘導する筋立てを本当に信じていたのか、信じないならばどのような態度を取り、どのような過程を経て破滅に突き進んだのか。
読了日:06月01日 著者:太宰 治

 惜別の感想
惜別の感想太宰はなぜ魯迅を描こうとしたのか、純粋に疑問に思って。「藤野先生」の逸話への感動や、留学生である魯迅の、同級生から徹頭徹尾はみ出さざるをえない境遇、帰国前の「近代文明を病んで悩んだ」日々への共感あたりに熱を感じる。太宰に魯迅が憑依したというより、魯迅に太宰が憑依したかのような饒舌だったからだ。しかし、あとがきに太宰はこの小説が内閣情報局と文学報国会との依嘱であったと明かしている。文学報国会は情報局の実質的な外郭団体であるとのこと。戦局も悪化した時分でもあり、一挙に胡散臭さが充満するのはやむなしとする。
読了日:06月01日 著者:太宰 治

注:
 は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。 2023年06月01日
2023年5月の記録
チャットGPTに、ある本の感想を255字以内で書けと指示すれば、一瞬にして滑らかにそれらしく書き上げるのだろう。
私が書く感想は、それに似ていないものでありたい。
後になって読んで、ほかならぬ自分が書いたものだと思えるものでありたい。
人が本を読んで感じたことを、何と結びつけ、何に例えて、どのような感情を覚えたかは必ず異なるはずだから。
<今月のデータ>
購入19冊、購入費用17,133円。
読了14冊。
積読本336冊(うちKindle本163冊、Honto本3冊)。

 ないもの、あります (ちくま文庫)の感想
ないもの、あります (ちくま文庫)の感想
この厚さの文庫本がもはや千円もするのか、と思ったところが、紙質にも凝った素敵な本だった。クラフト・エヴィング商會さんによる商品カタログである。どれを買おうか、行きつ戻りつ迷う。地獄耳は持っておきたいし、自分を上げる棚もあればいいよな。しかし持っていたらばこそ使いたくなるのも人情で、持っていることでかえって人生に難を呼び込んでしまうことも重々あり得るだろう。何かあったときのお助け用品がいいか。転ばぬ先の杖より、一筋縄のほうが握って心強い気もする。でもいちばんは堪忍袋の緒だなあ。私の堪忍袋のサイズ、ですか…。
読了日:05月31日 著者:クラフト・エヴィング商會
![時空旅人 2018年9月号 Vol.45 [ 台湾 見聞録 ー 日本が残した足跡を訪ねて ー]](https://m.media-amazon.com/images/I/61ozV7tdhLL._SL120_.jpg) 時空旅人 2018年9月号 Vol.45 [ 台湾 見聞録 ー 日本が残した足跡を訪ねて ー]の感想
時空旅人 2018年9月号 Vol.45 [ 台湾 見聞録 ー 日本が残した足跡を訪ねて ー]の感想
地に足の着いた案内誌。地域ごとに特筆すべき場所や来歴がバランスよく選び出されている印象。『台湾を見て歩くことは日本の歴史をたどること』。それもそうだけれど、台湾は、だけじゃない。大雑把に分類すると、古来からの多民族の暮らしと文化、中国からの流入、ポルトガル、清、日本による統治時代の遺物、その後の中国と混ざりあってある現代。支配の主体がどこであれ、その"統治"によって台湾はとても複雑である。その複雑を超えて、どのような関係が好ましいかが今後も課題だと思う。私が好きな光景は夜市と、その奥で出会った廟。
読了日:05月30日 著者:
 楢山節考 (新潮文庫)の感想
楢山節考 (新潮文庫)の感想
古い因習に縛られた村の物語。と言えばそれだけなのに、暮らしのふとしたタイミングでおりんの生きかたを想う。おりんは身の程を弁え、周りを思いやり、不測に備えられるだけ備えたうえで未練のかけらも無く旅立った。正しい生きかた、心安き生きかた、だろうか。若松英輔のツイートが折良くヒントをくれた。生きるのが下手な人たちには知識は無くても『語り得ない叡知』がある。だから生を肯定することができる。片や孫たちの不遜な在り様には叡智が見えない。先行きは暗い。おたまはどこへ行ったか。この問いに、なぜかある重みが、後を引く。
読了日:05月29日 著者:深沢 七郎
 果しなき流れの果に (角川文庫)の感想
果しなき流れの果に (角川文庫)の感想
全体像がおぼろげにも見えるまで我慢の子。しかし宇宙やら次元やらの観念的な説明に、意識が漂い始める。遅かれ早かれ、人間は地球に住み続けることができなくなる。それは太陽の異変より早く、人間側の所業に起因するのではないか。もし私たちがもっと賢かったなら、環境に害することなく地球上に平和裡に住み続けることができただろうか。小松左京の原風景は敗戦、廃墟の記憶という。鴨野の古家は私たちの豊かさの象徴だ。ノバ・ヤパナでなくここで死にたい。この物語は「日本沈没」と繋がってもいる。壮大な故国消滅、故国喪失の物語だった。
読了日:05月29日 著者:小松 左京
 故郷/阿Q正伝 (光文社古典新訳文庫)の感想
故郷/阿Q正伝 (光文社古典新訳文庫)の感想
魯迅。字面に怖気ず、早く読んでおくべきだった。青年期に抱えた葛藤と理想が届かぬ寂莫に共振したことだろう。といって、魯迅の青年期から壮年期は日本と中国の軋轢、中国国内の激動の最中だった。散文では日本留学を志向し、覚り、帰国した心の内が雄弁に語られ、それを知って読む小説は、なんのことない、可笑しみすら覚える日々の光景のようで、あからさまな批判にできない批判、表に出すことを躊躇われる哀しみが底流する。もっとも、大江健三郎は魯迅の小説が含むものを"捨て身の告発"と言い切るので、私の理解力が及んでいないことも解る。
読了日:05月26日 著者:魯迅
 柳田國男先生随行記の感想
柳田國男先生随行記の感想
柳田國男が講演で九州へ行く、その世話係として随行した記録。小型録音機などない時代、憶えて書き起こすのが当たり前だった。柳田國男は車窓の景色を見ながら当地の文化や事物、門人の話、新たな着想まで話題に事欠かない。著者は困り果てていたけれど、常人には難しいんじゃないか。一方、研究ばかりではなく、後進を育てることや、得た知識を書籍化して売ること、門人の集まりや入門書の構成にも心を配るなど、民俗学界を盛り立てる方向を考えていた人であったと窺える。真珠湾攻撃前夜のことでもあり、その頃の世相や一般人の心情も興味深い。
読了日:05月24日 著者:今野圓輔
 ディズニーキャストざわざわ日記――〝夢の国″にも☓☓☓☓ご指示のとおり掃除しますの感想
ディズニーキャストざわざわ日記――〝夢の国″にも☓☓☓☓ご指示のとおり掃除しますの感想
夢の国の"中の人"たちは当然ながら現実を生きている。ほとんどのスタッフは非正規雇用、そのシビアさをそーやろな、そーやろなと読むのは野次馬根性ゆえか、またはオリエンタルランドの労務管理への…野次馬根性ゆえか。本人たちはその事実もそれだけで食べていけないことも解っていて、それでも好きで働いている。著者が就いた職種は"カストーディアルキャスト"、その実は清掃員である。その立場だから見えることがある。夢の国では自分たちが排出した汚物を目にしたくない欲求も叶えられる。音や色彩が過剰なぶん、陰影は強調されて見える。
読了日:05月19日 著者:笠原一郎
 エフォートレス思考 努力を最小化して成果を最大化するの感想
エフォートレス思考 努力を最小化して成果を最大化するの感想
前作に続き、リソースを全力投入するのではなく、より少ない努力でより有効な成果を目指す。自律して自身を整えることや、仕事をする相手との関係性に言及したのが目新しいか。相手を信頼できれば、些末な確認作業や気遣いによる消耗を省ける。『あなたの判断を信頼する』と思えるか、また伝えられるか。その観点から相手を選ぶことも必要だと納得した。ワーキングメモリの容量不足は失敗のもとである。手順の簡略化や処理の機械化は当然ながら、他者のネガティブな表情がワーキングメモリに負荷をかけるとは、なかなか自覚しづらいところである。
『ゆっくり動けば、ものごとはスムーズになる。ものごとがスムーズであれば、より速く動ける』。『1日の仕事は、1日ですっかり疲れが取れる程度まで。1週間の仕事は、その週末ですっかり疲れが取れる程度までに制限する』。カフェインや糖分でごまかさない。
読了日:05月17日 著者:グレッグ・マキューン
 魂の退社の感想
魂の退社の感想
私もじきに著者が退職した歳になる。バブル期と就職氷河期という時代の差もあろうが、お金に対する感覚の隔絶感に目眩がした。この差はまま社会の格差につながる。「何もない」高松でお金を使わない暮らしに開眼し、大企業退職によって脱いだ下駄の高さや自身の無知に気づけたことは、大変良いことである。しかし新聞記者として社会のことを書いていても、自身が体感したのでなければ社会や中小企業というマジョリティのことを広く理解できているわけではないのだ。ぜひ大きめのカイシャにしか所属したことのないまま年を経た人に読んでみてほしい。
大学の先生や会社社長は生業が別にあるから原稿料は「ちょっとしたお小遣い」と表するのに違和感があった。本職があるから正当な原稿料が支払われなくてもいいことにはならないし、原稿料を経費と分類するなら、そこもお金についての考え方が大企業式じゃないかな。大企業勤務とはそんな余裕のあるものではないと言うかもしれないが、仮にも大企業と呼ばれる会社に所属して他より多めの報酬と待遇を得ているのなら、そちら側の人に、金銭的環境的理由で身動きの取れない人が置かれた状況を慮る努力をしてほしいと思うのは無理難題だろうか。
読了日:05月14日 著者:稲垣 えみ子
 土を育てる: 自然をよみがえらせる土壌革命の感想
土を育てる: 自然をよみがえらせる土壌革命の感想
胸がいっぱいだ。福岡正信翁とは思考の根っこが違う。なのに合理的な西洋式で辿り着いた結論が相似してくることに驚嘆する。『自然は耕さない』。人間は土から多くを得るために、自然の法則に反して土を殺すようなことばかりしている。リジェネラティブ農業は土の復権への賛歌である。植物の根は地中から養分や水分を吸い上げるだけでなく、土を耕し、かつ有機化合物を分泌する。土だけ、植物だけを見るのでは片手落ちで、その複雑な相互作用こそが大事。さらにカバークロップも、性質の異なる種を多種ブレンドすることによってより全きものになる。
アメリカという資本主義が強い社会で経済的に成功している点が心強い。それには作物の栽培・牛羊鶏他の飼養だけでなく経営や販売も自前で手掛けて収益を取りこぼさない必要があるが、リジェネラティブ農業なら家族+アルファの人員でこなせるという。希望そのものだと思うが、現在栽培される作物のほとんどは遺伝子組換で、農家は巨大企業の尻に敷かれて青息吐息という。『化学物質や、強欲な企業や、政府の認証や、思いやりのかけらもない市場への依存からの解放』、それに工夫する生業の楽しさ。隔てるのは、果てしない不安と現状依存なのだろう。
牛や肉食を悪者扱いする菜食主義者に向けての提言。『もし本当に地球環境のことを心配するなら、たとえあなた自身が肉を食べないとしても、反芻動物が草を食むことの重要性に目を向けるべきだ』。牛は本来食べる草以外のものを飼料として食べさせられては、メタンガスを放出すると非難されているのだ。
読了日:05月13日 著者:ゲイブ・ブラウン
 チャーメインと魔法の家: ハウルの動く城 3 (徳間文庫)の感想
チャーメインと魔法の家: ハウルの動く城 3 (徳間文庫)の感想
ああ、もう。先に部屋を片付けなさいよ。スーツケースの中を先に見てって言われたでしょ。なんにもしようとしない(できない)チャーメインにイライラする。私だって暇さえあれば本に鼻を突っ込んでいるのは同じだったはずなのに、人間はどこでどうやって大人になるのだろう。さてハウル一家。前回はすっかりだまされたので今回は眉に唾つけて読むも、堂々たる登場だった。すっかり歳相応になったソフィは感情を隠さない。片やハウルは、こりゃソフィに甘えてるんだろうなあ。ハウルの字が汚いとか細かいところでリアルなファンタジー。楽しかった。
読了日:05月13日 著者:ダイアナ・ウィン ジョーンズ
 ハウルの動く城2 アブダラと空飛ぶ絨毯 (徳間文庫)の感想
ハウルの動く城2 アブダラと空飛ぶ絨毯 (徳間文庫)の感想
アラビアンナイトめいたジンやジンニー、空飛ぶ絨毯が健気な主人公を窮地に陥れる物語。と言いたいくらい物事が真っ当に進まない。ハウルの城が舞台になるのは物語の折り返し地点を過ぎてからという、なんとも悠長な、まったく趣向を変えたお話なのね。終盤にハウルたちと合流したら上手くゆくのかしらと思ったら、なんと!まじか! 道理で物事が真っ直ぐ進まないわけだわ。『今まで、おいらにおせじを言ってくれたのは、この人だけだ』。できすぎなくらい物事が納まる場所に納まって、大団円となる。読み返したらまたにやにやしちゃうんだろうな。
読了日:05月07日 著者:ダイアナ・ウィン・ジョーンズ
 食べる つかう あそぶ 庭にほしい木と草の本: 散歩道でも楽しむの感想
食べる つかう あそぶ 庭にほしい木と草の本: 散歩道でも楽しむの感想
どんな植物でも、新芽は頼もしく、花は生命力に満ちて美しい。ならば、自分の好きなものを植えられるならば、眺める楽しみとは別に、役に立つものを植えたいと思うのは不純だろうか。食べる、漬ける、染める、遊ぶ。ニワトリとミツバチもいて、なんて羨ましい庭! たくさんの木や草が紹介されているが、どちらかというと子供と楽しむ目線が強め。私には“食べられる庭”のほうが読んでわくわくしたなあ。あ、でも、ヤマノイモは植えたい。食べられてものづくりにも使える。ムカゴを植えたらいいのね。とりあえず埋めてみよう〜♪
読了日:05月06日 著者:草木屋 著
 ハウルの動く城1 魔法使いハウルと火の悪魔 (徳間文庫)の感想
ハウルの動く城1 魔法使いハウルと火の悪魔 (徳間文庫)の感想
ジブリのハウルは大好きな映画だけれど、本家のソフィーとハウルの珍道中もめちゃめちゃ楽しい、新しい家族の物語。『ねえソフィー、出口をつなげる場所に注文はあるかい?』 映画にはなかった台詞やエピソードににやにやしてしまう。さらに続きを読めるなんて嬉しいな。ソフィーの、妹たちとのやりとりがいい。あたしは長女だから。その言葉がどれだけソフィーを縛っただろう。思えば、呪いをかけられて初めてソフィーは家を出ると決心できたのだ。思い切りが良くなるところも、力を発揮できるようになるところも、魔女の功か歳の功か。
読了日:05月03日 著者:ダイアナ・ウィン・ジョーンズ
注: は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。
私が書く感想は、それに似ていないものでありたい。
後になって読んで、ほかならぬ自分が書いたものだと思えるものでありたい。
人が本を読んで感じたことを、何と結びつけ、何に例えて、どのような感情を覚えたかは必ず異なるはずだから。
<今月のデータ>
購入19冊、購入費用17,133円。
読了14冊。
積読本336冊(うちKindle本163冊、Honto本3冊)。

 ないもの、あります (ちくま文庫)の感想
ないもの、あります (ちくま文庫)の感想この厚さの文庫本がもはや千円もするのか、と思ったところが、紙質にも凝った素敵な本だった。クラフト・エヴィング商會さんによる商品カタログである。どれを買おうか、行きつ戻りつ迷う。地獄耳は持っておきたいし、自分を上げる棚もあればいいよな。しかし持っていたらばこそ使いたくなるのも人情で、持っていることでかえって人生に難を呼び込んでしまうことも重々あり得るだろう。何かあったときのお助け用品がいいか。転ばぬ先の杖より、一筋縄のほうが握って心強い気もする。でもいちばんは堪忍袋の緒だなあ。私の堪忍袋のサイズ、ですか…。
読了日:05月31日 著者:クラフト・エヴィング商會
![時空旅人 2018年9月号 Vol.45 [ 台湾 見聞録 ー 日本が残した足跡を訪ねて ー]](https://m.media-amazon.com/images/I/61ozV7tdhLL._SL120_.jpg) 時空旅人 2018年9月号 Vol.45 [ 台湾 見聞録 ー 日本が残した足跡を訪ねて ー]の感想
時空旅人 2018年9月号 Vol.45 [ 台湾 見聞録 ー 日本が残した足跡を訪ねて ー]の感想地に足の着いた案内誌。地域ごとに特筆すべき場所や来歴がバランスよく選び出されている印象。『台湾を見て歩くことは日本の歴史をたどること』。それもそうだけれど、台湾は、だけじゃない。大雑把に分類すると、古来からの多民族の暮らしと文化、中国からの流入、ポルトガル、清、日本による統治時代の遺物、その後の中国と混ざりあってある現代。支配の主体がどこであれ、その"統治"によって台湾はとても複雑である。その複雑を超えて、どのような関係が好ましいかが今後も課題だと思う。私が好きな光景は夜市と、その奥で出会った廟。
読了日:05月30日 著者:
 楢山節考 (新潮文庫)の感想
楢山節考 (新潮文庫)の感想古い因習に縛られた村の物語。と言えばそれだけなのに、暮らしのふとしたタイミングでおりんの生きかたを想う。おりんは身の程を弁え、周りを思いやり、不測に備えられるだけ備えたうえで未練のかけらも無く旅立った。正しい生きかた、心安き生きかた、だろうか。若松英輔のツイートが折良くヒントをくれた。生きるのが下手な人たちには知識は無くても『語り得ない叡知』がある。だから生を肯定することができる。片や孫たちの不遜な在り様には叡智が見えない。先行きは暗い。おたまはどこへ行ったか。この問いに、なぜかある重みが、後を引く。
読了日:05月29日 著者:深沢 七郎
 果しなき流れの果に (角川文庫)の感想
果しなき流れの果に (角川文庫)の感想全体像がおぼろげにも見えるまで我慢の子。しかし宇宙やら次元やらの観念的な説明に、意識が漂い始める。遅かれ早かれ、人間は地球に住み続けることができなくなる。それは太陽の異変より早く、人間側の所業に起因するのではないか。もし私たちがもっと賢かったなら、環境に害することなく地球上に平和裡に住み続けることができただろうか。小松左京の原風景は敗戦、廃墟の記憶という。鴨野の古家は私たちの豊かさの象徴だ。ノバ・ヤパナでなくここで死にたい。この物語は「日本沈没」と繋がってもいる。壮大な故国消滅、故国喪失の物語だった。
読了日:05月29日 著者:小松 左京

 故郷/阿Q正伝 (光文社古典新訳文庫)の感想
故郷/阿Q正伝 (光文社古典新訳文庫)の感想魯迅。字面に怖気ず、早く読んでおくべきだった。青年期に抱えた葛藤と理想が届かぬ寂莫に共振したことだろう。といって、魯迅の青年期から壮年期は日本と中国の軋轢、中国国内の激動の最中だった。散文では日本留学を志向し、覚り、帰国した心の内が雄弁に語られ、それを知って読む小説は、なんのことない、可笑しみすら覚える日々の光景のようで、あからさまな批判にできない批判、表に出すことを躊躇われる哀しみが底流する。もっとも、大江健三郎は魯迅の小説が含むものを"捨て身の告発"と言い切るので、私の理解力が及んでいないことも解る。
読了日:05月26日 著者:魯迅

 柳田國男先生随行記の感想
柳田國男先生随行記の感想柳田國男が講演で九州へ行く、その世話係として随行した記録。小型録音機などない時代、憶えて書き起こすのが当たり前だった。柳田國男は車窓の景色を見ながら当地の文化や事物、門人の話、新たな着想まで話題に事欠かない。著者は困り果てていたけれど、常人には難しいんじゃないか。一方、研究ばかりではなく、後進を育てることや、得た知識を書籍化して売ること、門人の集まりや入門書の構成にも心を配るなど、民俗学界を盛り立てる方向を考えていた人であったと窺える。真珠湾攻撃前夜のことでもあり、その頃の世相や一般人の心情も興味深い。
読了日:05月24日 著者:今野圓輔
 ディズニーキャストざわざわ日記――〝夢の国″にも☓☓☓☓ご指示のとおり掃除しますの感想
ディズニーキャストざわざわ日記――〝夢の国″にも☓☓☓☓ご指示のとおり掃除しますの感想夢の国の"中の人"たちは当然ながら現実を生きている。ほとんどのスタッフは非正規雇用、そのシビアさをそーやろな、そーやろなと読むのは野次馬根性ゆえか、またはオリエンタルランドの労務管理への…野次馬根性ゆえか。本人たちはその事実もそれだけで食べていけないことも解っていて、それでも好きで働いている。著者が就いた職種は"カストーディアルキャスト"、その実は清掃員である。その立場だから見えることがある。夢の国では自分たちが排出した汚物を目にしたくない欲求も叶えられる。音や色彩が過剰なぶん、陰影は強調されて見える。
読了日:05月19日 著者:笠原一郎

 エフォートレス思考 努力を最小化して成果を最大化するの感想
エフォートレス思考 努力を最小化して成果を最大化するの感想前作に続き、リソースを全力投入するのではなく、より少ない努力でより有効な成果を目指す。自律して自身を整えることや、仕事をする相手との関係性に言及したのが目新しいか。相手を信頼できれば、些末な確認作業や気遣いによる消耗を省ける。『あなたの判断を信頼する』と思えるか、また伝えられるか。その観点から相手を選ぶことも必要だと納得した。ワーキングメモリの容量不足は失敗のもとである。手順の簡略化や処理の機械化は当然ながら、他者のネガティブな表情がワーキングメモリに負荷をかけるとは、なかなか自覚しづらいところである。
『ゆっくり動けば、ものごとはスムーズになる。ものごとがスムーズであれば、より速く動ける』。『1日の仕事は、1日ですっかり疲れが取れる程度まで。1週間の仕事は、その週末ですっかり疲れが取れる程度までに制限する』。カフェインや糖分でごまかさない。
読了日:05月17日 著者:グレッグ・マキューン

 魂の退社の感想
魂の退社の感想私もじきに著者が退職した歳になる。バブル期と就職氷河期という時代の差もあろうが、お金に対する感覚の隔絶感に目眩がした。この差はまま社会の格差につながる。「何もない」高松でお金を使わない暮らしに開眼し、大企業退職によって脱いだ下駄の高さや自身の無知に気づけたことは、大変良いことである。しかし新聞記者として社会のことを書いていても、自身が体感したのでなければ社会や中小企業というマジョリティのことを広く理解できているわけではないのだ。ぜひ大きめのカイシャにしか所属したことのないまま年を経た人に読んでみてほしい。
大学の先生や会社社長は生業が別にあるから原稿料は「ちょっとしたお小遣い」と表するのに違和感があった。本職があるから正当な原稿料が支払われなくてもいいことにはならないし、原稿料を経費と分類するなら、そこもお金についての考え方が大企業式じゃないかな。大企業勤務とはそんな余裕のあるものではないと言うかもしれないが、仮にも大企業と呼ばれる会社に所属して他より多めの報酬と待遇を得ているのなら、そちら側の人に、金銭的環境的理由で身動きの取れない人が置かれた状況を慮る努力をしてほしいと思うのは無理難題だろうか。
読了日:05月14日 著者:稲垣 えみ子

 土を育てる: 自然をよみがえらせる土壌革命の感想
土を育てる: 自然をよみがえらせる土壌革命の感想胸がいっぱいだ。福岡正信翁とは思考の根っこが違う。なのに合理的な西洋式で辿り着いた結論が相似してくることに驚嘆する。『自然は耕さない』。人間は土から多くを得るために、自然の法則に反して土を殺すようなことばかりしている。リジェネラティブ農業は土の復権への賛歌である。植物の根は地中から養分や水分を吸い上げるだけでなく、土を耕し、かつ有機化合物を分泌する。土だけ、植物だけを見るのでは片手落ちで、その複雑な相互作用こそが大事。さらにカバークロップも、性質の異なる種を多種ブレンドすることによってより全きものになる。
アメリカという資本主義が強い社会で経済的に成功している点が心強い。それには作物の栽培・牛羊鶏他の飼養だけでなく経営や販売も自前で手掛けて収益を取りこぼさない必要があるが、リジェネラティブ農業なら家族+アルファの人員でこなせるという。希望そのものだと思うが、現在栽培される作物のほとんどは遺伝子組換で、農家は巨大企業の尻に敷かれて青息吐息という。『化学物質や、強欲な企業や、政府の認証や、思いやりのかけらもない市場への依存からの解放』、それに工夫する生業の楽しさ。隔てるのは、果てしない不安と現状依存なのだろう。
牛や肉食を悪者扱いする菜食主義者に向けての提言。『もし本当に地球環境のことを心配するなら、たとえあなた自身が肉を食べないとしても、反芻動物が草を食むことの重要性に目を向けるべきだ』。牛は本来食べる草以外のものを飼料として食べさせられては、メタンガスを放出すると非難されているのだ。
読了日:05月13日 著者:ゲイブ・ブラウン
 チャーメインと魔法の家: ハウルの動く城 3 (徳間文庫)の感想
チャーメインと魔法の家: ハウルの動く城 3 (徳間文庫)の感想ああ、もう。先に部屋を片付けなさいよ。スーツケースの中を先に見てって言われたでしょ。なんにもしようとしない(できない)チャーメインにイライラする。私だって暇さえあれば本に鼻を突っ込んでいるのは同じだったはずなのに、人間はどこでどうやって大人になるのだろう。さてハウル一家。前回はすっかりだまされたので今回は眉に唾つけて読むも、堂々たる登場だった。すっかり歳相応になったソフィは感情を隠さない。片やハウルは、こりゃソフィに甘えてるんだろうなあ。ハウルの字が汚いとか細かいところでリアルなファンタジー。楽しかった。
読了日:05月13日 著者:ダイアナ・ウィン ジョーンズ

 ハウルの動く城2 アブダラと空飛ぶ絨毯 (徳間文庫)の感想
ハウルの動く城2 アブダラと空飛ぶ絨毯 (徳間文庫)の感想アラビアンナイトめいたジンやジンニー、空飛ぶ絨毯が健気な主人公を窮地に陥れる物語。と言いたいくらい物事が真っ当に進まない。ハウルの城が舞台になるのは物語の折り返し地点を過ぎてからという、なんとも悠長な、まったく趣向を変えたお話なのね。終盤にハウルたちと合流したら上手くゆくのかしらと思ったら、なんと!まじか! 道理で物事が真っ直ぐ進まないわけだわ。『今まで、おいらにおせじを言ってくれたのは、この人だけだ』。できすぎなくらい物事が納まる場所に納まって、大団円となる。読み返したらまたにやにやしちゃうんだろうな。
読了日:05月07日 著者:ダイアナ・ウィン・ジョーンズ

 食べる つかう あそぶ 庭にほしい木と草の本: 散歩道でも楽しむの感想
食べる つかう あそぶ 庭にほしい木と草の本: 散歩道でも楽しむの感想どんな植物でも、新芽は頼もしく、花は生命力に満ちて美しい。ならば、自分の好きなものを植えられるならば、眺める楽しみとは別に、役に立つものを植えたいと思うのは不純だろうか。食べる、漬ける、染める、遊ぶ。ニワトリとミツバチもいて、なんて羨ましい庭! たくさんの木や草が紹介されているが、どちらかというと子供と楽しむ目線が強め。私には“食べられる庭”のほうが読んでわくわくしたなあ。あ、でも、ヤマノイモは植えたい。食べられてものづくりにも使える。ムカゴを植えたらいいのね。とりあえず埋めてみよう〜♪
読了日:05月06日 著者:草木屋 著
 ハウルの動く城1 魔法使いハウルと火の悪魔 (徳間文庫)の感想
ハウルの動く城1 魔法使いハウルと火の悪魔 (徳間文庫)の感想ジブリのハウルは大好きな映画だけれど、本家のソフィーとハウルの珍道中もめちゃめちゃ楽しい、新しい家族の物語。『ねえソフィー、出口をつなげる場所に注文はあるかい?』 映画にはなかった台詞やエピソードににやにやしてしまう。さらに続きを読めるなんて嬉しいな。ソフィーの、妹たちとのやりとりがいい。あたしは長女だから。その言葉がどれだけソフィーを縛っただろう。思えば、呪いをかけられて初めてソフィーは家を出ると決心できたのだ。思い切りが良くなるところも、力を発揮できるようになるところも、魔女の功か歳の功か。
読了日:05月03日 著者:ダイアナ・ウィン・ジョーンズ

注:
 は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。 2023年05月02日
2023年4月の記録
10年来積読だったソローの「森の生活」読破を諦めた。
岩波文庫で字が小さいから…と電子書籍で買い直しもしたが、だめ。
有名な本は偉いと無条件に信じていた頃に勢いで読むのが正解だったか。
<今月のデータ>
購入11冊、購入費用13,832円。
読了12冊。
積読本330冊(うちKindle本158冊、Honto本3冊)。

 暗がり礼賛 明かりと電気の歴史と地球温暖化の感想
暗がり礼賛 明かりと電気の歴史と地球温暖化の感想
読む途中で「木綿リサイクル」の著者と気づいた。道理で、集めた情報の切り貼りである。著者ご本人は何の専門家でもない。ただ、火の発見から始まるエネルギーのエントロピー増大を現代の電力過剰消費につなげるところは上手い。この流れのいったいどこに人類が踏み止まれるポイントがあっただろうか。昔から学びつつ新しい暮らし方を生み出すことは、理性で考えれば可能だし、個人レベルではあり得る。しかし経済産業省も電力会社も、電力消費量を減らす方向性には全力で抵抗するだろう。今までもこれからも。私たちは、もう止まれない。
読了日:04月29日 著者:前田啓一
 雑草のくらし (福音館の科学シリーズ)の感想
雑草のくらし (福音館の科学シリーズ)の感想
今、ちょうど道端のスイバが色づいている。空き地に茂る草。まったく珍しくもない。なのに、なんて未知の世界なんだろう。それぞれが持てる武器を使って、しばしの栄華を極める。でもそれは毎年は続かなくって、次々と入れ替わっていくものだなんて、気づきもしなかった。ただし、人間が刈ったり抜いたり手を加えれば話は別で、たいてい毎年同じようなものが生えているように記憶している。何もしなければ、空き地は草むらから草藪へと変貌していく。地下の根っこの力は恐ろしいほどだ。地面は、人間がちょっとこま間借りしているようなものだなあ。
読了日:04月29日 著者:甲斐 信枝
 土を喰う日々: わが精進十二ヵ月 (新潮文庫)の感想
土を喰う日々: わが精進十二ヵ月 (新潮文庫)の感想
時短やタイパがもてはやされる時代ゆえに、氏のエッセイはより沁みる。丁寧な料理を、すなわち手間がかかることと認識するべきではない。その食材と正面から向き合うことで旬を捉え、滋味を味わい、味覚と記憶の繋がりに気づくことができる。『旬を喰うこととはつまり土を喰うこと』。その豊かさを我がものにしたいと願う。老人は季節の煮物を尊ぶとある。自分にあと何度季節が巡ってくるかに思いが至るとき、ようやくその時にしかできない作業や食事を愛おしく思えるのだろう。毎年読んでみたいような、そしたら少しはこの境地に近づけるだろうか。
こんにゃくは指でちぎる。豆腐はにぎりつぶす。味がしみやすいと同時に、その感触もまた食事の一部なんだなあと思う。そして自然と食事もつながっていて、山椒、 地梨子にスグリと、身近にないことが悔しく、きっと庭に植えようなど決め込んでみる。持てる時間が限られるなかで、他になにができるだろう。
読了日:04月27日 著者:水上 勉
 小説 不如帰 の感想
小説 不如帰 の感想
明治31年より「国民新聞」で連載の、文語体で書かれた小説。連続ドラマを観ているように面白かった。文語体ゆえに文を咀嚼しないと読めないのだが、慣れると美しい抑揚や流れに身を委ねるのが心地よい。かといって情景や心の機微を丁寧に味わっていると、これまた流れるように挟まれる皮肉や揶揄に吹き出してしまう。著者も楽しんで書いたと想像される。『この愛をば何人もつんざくあたわじ』。知人から耳にした実話を基にしたため、結末は最初から決まっていたようだ。当時の女性が置かれた立場もさることながら、浪子の悲運に涙が止まらない。
時は明治末期、日清戦争の前後。華族は資産や身分を保証された一方、士官として従軍もした。戦闘を野球のプレーに比べたり、戦艦の寄港地付で手紙や荷物を送るなど、先の戦争とは違った意味で日本人に戦争が身近だった時代である。徴兵ではない、職業軍人が戦地へ赴くことは任務であり責務であり、愛が危機に瀕しているからといって、征くのをやめて妻の元に戻るなどという感覚は皆無だよなあ。そして怪我が治りきらずともまた乗艦するのである。国民新聞が官僚や軍人寄りの立ち位置だった建前かとも考えたが、これは私のほうが平和ボケなのだろう。
読了日:04月26日 著者:徳冨 蘆花
 自然農・栽培の手引きの感想
自然農・栽培の手引きの感想
福岡正信翁の「何もしない農法」は必要十分以外を何もしないの意である。この本はその流れを汲む考え方と作業の実際を、優しい挿画も用いて細かく説明している。耕さない。できる限り土を動かさない。収穫後の作物の葉や茎も草も根から抜かない。刈り取り、土の上へ敷く。土に戻す。つまり土を裸にしないことで施肥や灌水の必要がなくなり、しかし土はどんどん豊かになっていくという。自然農を学び、実践する著者が、土や作物が変わっていった実感と感動を率直に綴っている。その体感が確信となって自然農への信頼が溢れている。まず大豆と落花生。
読了日:04月20日 著者:鏡山悦子
 台湾海峡一九四九の感想
台湾海峡一九四九の感想
満州事変勃発が1931年。侵略国日本が敗戦と共に退き、その後中国国内では国共内戦が起きた。隣人同士で殺し合いを続け、最終的に追い詰められた国民党が台湾へ渡ったのが1949年だった。膨大な資料や証言によって、著者は一人ひとりにとっての戦争を記録する。『人の頭蓋骨がどんな脆いか、どれくらいの大きさか、あなたは知らない』。それはアレクシェーヴィチの著作を読む感触に似ていた。しかしこちらの事実は、少なくとも半分がたは日本人の我が事のはずだ。彼らが何十年も身の内に留めて耐えた言葉を、受け取る義務があると私は思う。
ロシアの戦場で五百万人のドイツ兵が死に、捕虜収容所で百万人のドイツ兵が虐待を受けて死んだ。『ドイツ人が全世界に大きな災難をもたらしたことを知っていて、なお虐待を受けた百万人のドイツ人のために不平を訴える権利がある?』とドイツ人の若者が言う。この構図は日本にも当てはまる。日本人はアジア諸国や連合国軍の人々にどれほどの非道をしでかしたか知っているだろうか? 今の日本に生きていて、耳に入るのは原爆の悲劇であり、せいぜい大陸や南方で被った困苦である。被害のみを声高に語るのは片手落ちだと終戦の季節の来るたび思う。
日本陸軍は占領支配した朝鮮、中国、台湾の若者を募り、日本兵として南方へ送った。しかし日本出身の兵士と同等には扱わず、虐待し、現地民や連合国軍兵士の虐殺を強いた。敗戦後、上長である日本兵たちは生きろと彼らに言い置いて自決し、また処刑された。同じく日本軍の一兵卒であった私たちの祖父らは帰還し、戦地でどのような行為をしたかを妻子に語らなかった。今は日本を好意的に見てくれる人も多い。だからといって、祖父らの大陸での所業を無かったことにはしてはならない。その折り合いは私の中でつかない。つけずに、いつまでも抱く。
読了日:04月18日 著者:龍 應台
 その可能性はすでに考えた (講談社文庫)の感想
その可能性はすでに考えた (講談社文庫)の感想
『その可能性はすでに考えた。』は探偵の決め台詞である。全ての可能性を潰せばそれは「不可能」と呼べるのか。可能性が無限大であれば証明そのものが不可能だ。さらにひとつの可能性/不可能性が他の可能性を潰す自家撞着に陥る場合は深掘りするほど増える。底なしの論理遊び。しっかしまあ、ひとつの不可能事件の真相を究明するのに、ぎゅうぎゅうに要素を詰め込んだものだ。中国の四字熟語、言い廻し、拷問や宗教の蘊蓄。即アニメ化できそうなキャラ造形。国際色豊かなのも、百合も、きっと後々に勃発する何かの伏線なのだろう。気にはなる。
読了日:04月16日 著者:井上 真偽
 白昼夢の森の少女 (角川ホラー文庫)の感想
白昼夢の森の少女 (角川ホラー文庫)の感想
どれも面白い。するりと入り込む異界。『路地裏に人形を抱いた女がいた。』なんて書き出されるともうぞくぞくする。ホラーとは違う、ファンタジーでもない、恒川ワールドは年を経て様々な要素を加えてもぶれていない。こう言っては申し訳ないけれど、テーマに沿って編んだ短編集よりも、先入観なしに読めるばらばらなもののほうが、長さも趣向も展開も結末も見当がつかなくて、つまりまとまりなど考えすぎずに身を委ねられるので楽しい。「タイプライターズ」でテレビに初出演された恒川さんはとてもキュートでした。全部読み返したくなった。
読了日:04月15日 著者:恒川 光太郎
 わたしは英国王に給仕した (河出文庫)の感想
わたしは英国王に給仕した (河出文庫)の感想
あるチェコ人給仕の一生。彼の人生では次々と『信じられないことが現実にな』った。このしっちゃかめっちゃかがチェコの常識に照らしてどうかが私には判断がつかないことと、第二次世界大戦下で母国を占領したドイツ人を、抵抗せず受け入れる者の視点で描写していることを面白く感じた。そしてこれらが次元の異なる理不尽である点も。稼いだ紙幣を部屋中に敷き詰めて愛でる青年期から、巨万の富を得、失い、人里離れた荒野の肉体労働と孤独に身を埋める晩年へ。ドタバタから静寂へ。ズデニェクの存在によって対照的に浮かび上がる生き方もまた深い。
読了日:04月10日 著者:ボフミル フラバル
 山崎実業アイデアBOOKの感想
山崎実業アイデアBOOKの感想
好き。しゅっとしているところと、プラスチックでないところ、仕組みがシンプルであるところ、マグネット式やフック式で相手側に加工を要しないところ。今やアイテム数が増えすぎて、ネット上でラインナップが把握できないまでになっているので本刊行は嬉しい。以前から不便に思っていたあたりの解決法に留まらず、次々と繰り出されるアイデアに、ついそのアイテムを使うために自宅を改造したくなってくるという逆転現象が起きるのは、山崎実業ファンのあるある。待て!落ち着け! ここはという箇所から、ひとつずつ取り入れていこうではないか。
読了日:04月09日 著者:
 自然農法 わら一本の革命の感想
自然農法 わら一本の革命の感想
自然農法の祖、バイブルと目される本である。著者が編み出した肥料も農薬も耕うん機も使わない「何もしない農法」は人間の究極の知恵、ではなく、人間は絶対に自然には勝てないことの証と言いきる。それはもはや宗教じみて、だからこそ強い。著者の農法は欧米の有機農業にも影響を与えたと言われるが、それが単に方法論で留まるなら、自分の自然農法とは非なるものと切り捨てる。『仏教でいう大乗的な自然農法と、便宜的な小乗的な自然農法』との比喩は言い得て妙だ。わかりやすい。『人間は自然を壊せても、自然をつくることはできない』。
消費者の『少しでも外観のいいもの、きれいなもの、大きなものを買おうという、ほんのわずかの気持ちが、百姓をここまで追いこみ、苦しめている』。スーパーの売り場で、私だって選ぶ。同じ価格でも形のより良い玉ねぎを消費者が選べば、スーパーは形の悪い玉ねぎを事前に弾くだろう。しなびた小松菜を敬遠すれば、"長持ちさせることができる"パッケージを開発し、それはコスト増となる。過度な選別や無駄な品種改良、ひいては自然なものや適正な価格を外れていってしまう現象は私たちが招き、結果的に農家を苦しめていると鮮やかに糾弾する。
読了日:04月08日 著者:福岡 正信
 安曇野の白い庭 (新潮文庫)の感想
安曇野の白い庭 (新潮文庫)の感想
若い頃に読んだ氏の「白い庭」の経緯を確かめたかった。しかしやはり氏の傲慢さと他者蔑視に、嫌悪感を持て余す。350坪の土地に、俺は女や女みたいに軟弱な男にはできない仕事をやり上げたのだと自画自賛して憚らない。庭とは思いつきを手あたり次第に植えては挽き倒し植え直しを繰り返す自己満足である。自慢げに花の咲き誇る庭を眺めやるカラー写真。力と意志で現実を捻じ曲げられると信じている庭師の人間性がどうであれ、木は枝を高く伸ばし花は咲き誇る。それは逆に自然の持つ健やかさを、そして人間の小ささを証明しているように見えた。
読了日:04月01日 著者:丸山 健二
注: は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。
岩波文庫で字が小さいから…と電子書籍で買い直しもしたが、だめ。
有名な本は偉いと無条件に信じていた頃に勢いで読むのが正解だったか。
<今月のデータ>
購入11冊、購入費用13,832円。
読了12冊。
積読本330冊(うちKindle本158冊、Honto本3冊)。

 暗がり礼賛 明かりと電気の歴史と地球温暖化の感想
暗がり礼賛 明かりと電気の歴史と地球温暖化の感想読む途中で「木綿リサイクル」の著者と気づいた。道理で、集めた情報の切り貼りである。著者ご本人は何の専門家でもない。ただ、火の発見から始まるエネルギーのエントロピー増大を現代の電力過剰消費につなげるところは上手い。この流れのいったいどこに人類が踏み止まれるポイントがあっただろうか。昔から学びつつ新しい暮らし方を生み出すことは、理性で考えれば可能だし、個人レベルではあり得る。しかし経済産業省も電力会社も、電力消費量を減らす方向性には全力で抵抗するだろう。今までもこれからも。私たちは、もう止まれない。
読了日:04月29日 著者:前田啓一
 雑草のくらし (福音館の科学シリーズ)の感想
雑草のくらし (福音館の科学シリーズ)の感想今、ちょうど道端のスイバが色づいている。空き地に茂る草。まったく珍しくもない。なのに、なんて未知の世界なんだろう。それぞれが持てる武器を使って、しばしの栄華を極める。でもそれは毎年は続かなくって、次々と入れ替わっていくものだなんて、気づきもしなかった。ただし、人間が刈ったり抜いたり手を加えれば話は別で、たいてい毎年同じようなものが生えているように記憶している。何もしなければ、空き地は草むらから草藪へと変貌していく。地下の根っこの力は恐ろしいほどだ。地面は、人間がちょっとこま間借りしているようなものだなあ。
読了日:04月29日 著者:甲斐 信枝
 土を喰う日々: わが精進十二ヵ月 (新潮文庫)の感想
土を喰う日々: わが精進十二ヵ月 (新潮文庫)の感想時短やタイパがもてはやされる時代ゆえに、氏のエッセイはより沁みる。丁寧な料理を、すなわち手間がかかることと認識するべきではない。その食材と正面から向き合うことで旬を捉え、滋味を味わい、味覚と記憶の繋がりに気づくことができる。『旬を喰うこととはつまり土を喰うこと』。その豊かさを我がものにしたいと願う。老人は季節の煮物を尊ぶとある。自分にあと何度季節が巡ってくるかに思いが至るとき、ようやくその時にしかできない作業や食事を愛おしく思えるのだろう。毎年読んでみたいような、そしたら少しはこの境地に近づけるだろうか。
こんにゃくは指でちぎる。豆腐はにぎりつぶす。味がしみやすいと同時に、その感触もまた食事の一部なんだなあと思う。そして自然と食事もつながっていて、山椒、 地梨子にスグリと、身近にないことが悔しく、きっと庭に植えようなど決め込んでみる。持てる時間が限られるなかで、他になにができるだろう。
読了日:04月27日 著者:水上 勉

 小説 不如帰 の感想
小説 不如帰 の感想明治31年より「国民新聞」で連載の、文語体で書かれた小説。連続ドラマを観ているように面白かった。文語体ゆえに文を咀嚼しないと読めないのだが、慣れると美しい抑揚や流れに身を委ねるのが心地よい。かといって情景や心の機微を丁寧に味わっていると、これまた流れるように挟まれる皮肉や揶揄に吹き出してしまう。著者も楽しんで書いたと想像される。『この愛をば何人もつんざくあたわじ』。知人から耳にした実話を基にしたため、結末は最初から決まっていたようだ。当時の女性が置かれた立場もさることながら、浪子の悲運に涙が止まらない。
時は明治末期、日清戦争の前後。華族は資産や身分を保証された一方、士官として従軍もした。戦闘を野球のプレーに比べたり、戦艦の寄港地付で手紙や荷物を送るなど、先の戦争とは違った意味で日本人に戦争が身近だった時代である。徴兵ではない、職業軍人が戦地へ赴くことは任務であり責務であり、愛が危機に瀕しているからといって、征くのをやめて妻の元に戻るなどという感覚は皆無だよなあ。そして怪我が治りきらずともまた乗艦するのである。国民新聞が官僚や軍人寄りの立ち位置だった建前かとも考えたが、これは私のほうが平和ボケなのだろう。
読了日:04月26日 著者:徳冨 蘆花

 自然農・栽培の手引きの感想
自然農・栽培の手引きの感想福岡正信翁の「何もしない農法」は必要十分以外を何もしないの意である。この本はその流れを汲む考え方と作業の実際を、優しい挿画も用いて細かく説明している。耕さない。できる限り土を動かさない。収穫後の作物の葉や茎も草も根から抜かない。刈り取り、土の上へ敷く。土に戻す。つまり土を裸にしないことで施肥や灌水の必要がなくなり、しかし土はどんどん豊かになっていくという。自然農を学び、実践する著者が、土や作物が変わっていった実感と感動を率直に綴っている。その体感が確信となって自然農への信頼が溢れている。まず大豆と落花生。
読了日:04月20日 著者:鏡山悦子
 台湾海峡一九四九の感想
台湾海峡一九四九の感想満州事変勃発が1931年。侵略国日本が敗戦と共に退き、その後中国国内では国共内戦が起きた。隣人同士で殺し合いを続け、最終的に追い詰められた国民党が台湾へ渡ったのが1949年だった。膨大な資料や証言によって、著者は一人ひとりにとっての戦争を記録する。『人の頭蓋骨がどんな脆いか、どれくらいの大きさか、あなたは知らない』。それはアレクシェーヴィチの著作を読む感触に似ていた。しかしこちらの事実は、少なくとも半分がたは日本人の我が事のはずだ。彼らが何十年も身の内に留めて耐えた言葉を、受け取る義務があると私は思う。
ロシアの戦場で五百万人のドイツ兵が死に、捕虜収容所で百万人のドイツ兵が虐待を受けて死んだ。『ドイツ人が全世界に大きな災難をもたらしたことを知っていて、なお虐待を受けた百万人のドイツ人のために不平を訴える権利がある?』とドイツ人の若者が言う。この構図は日本にも当てはまる。日本人はアジア諸国や連合国軍の人々にどれほどの非道をしでかしたか知っているだろうか? 今の日本に生きていて、耳に入るのは原爆の悲劇であり、せいぜい大陸や南方で被った困苦である。被害のみを声高に語るのは片手落ちだと終戦の季節の来るたび思う。
日本陸軍は占領支配した朝鮮、中国、台湾の若者を募り、日本兵として南方へ送った。しかし日本出身の兵士と同等には扱わず、虐待し、現地民や連合国軍兵士の虐殺を強いた。敗戦後、上長である日本兵たちは生きろと彼らに言い置いて自決し、また処刑された。同じく日本軍の一兵卒であった私たちの祖父らは帰還し、戦地でどのような行為をしたかを妻子に語らなかった。今は日本を好意的に見てくれる人も多い。だからといって、祖父らの大陸での所業を無かったことにはしてはならない。その折り合いは私の中でつかない。つけずに、いつまでも抱く。
読了日:04月18日 著者:龍 應台
 その可能性はすでに考えた (講談社文庫)の感想
その可能性はすでに考えた (講談社文庫)の感想『その可能性はすでに考えた。』は探偵の決め台詞である。全ての可能性を潰せばそれは「不可能」と呼べるのか。可能性が無限大であれば証明そのものが不可能だ。さらにひとつの可能性/不可能性が他の可能性を潰す自家撞着に陥る場合は深掘りするほど増える。底なしの論理遊び。しっかしまあ、ひとつの不可能事件の真相を究明するのに、ぎゅうぎゅうに要素を詰め込んだものだ。中国の四字熟語、言い廻し、拷問や宗教の蘊蓄。即アニメ化できそうなキャラ造形。国際色豊かなのも、百合も、きっと後々に勃発する何かの伏線なのだろう。気にはなる。
読了日:04月16日 著者:井上 真偽

 白昼夢の森の少女 (角川ホラー文庫)の感想
白昼夢の森の少女 (角川ホラー文庫)の感想どれも面白い。するりと入り込む異界。『路地裏に人形を抱いた女がいた。』なんて書き出されるともうぞくぞくする。ホラーとは違う、ファンタジーでもない、恒川ワールドは年を経て様々な要素を加えてもぶれていない。こう言っては申し訳ないけれど、テーマに沿って編んだ短編集よりも、先入観なしに読めるばらばらなもののほうが、長さも趣向も展開も結末も見当がつかなくて、つまりまとまりなど考えすぎずに身を委ねられるので楽しい。「タイプライターズ」でテレビに初出演された恒川さんはとてもキュートでした。全部読み返したくなった。
読了日:04月15日 著者:恒川 光太郎

 わたしは英国王に給仕した (河出文庫)の感想
わたしは英国王に給仕した (河出文庫)の感想あるチェコ人給仕の一生。彼の人生では次々と『信じられないことが現実にな』った。このしっちゃかめっちゃかがチェコの常識に照らしてどうかが私には判断がつかないことと、第二次世界大戦下で母国を占領したドイツ人を、抵抗せず受け入れる者の視点で描写していることを面白く感じた。そしてこれらが次元の異なる理不尽である点も。稼いだ紙幣を部屋中に敷き詰めて愛でる青年期から、巨万の富を得、失い、人里離れた荒野の肉体労働と孤独に身を埋める晩年へ。ドタバタから静寂へ。ズデニェクの存在によって対照的に浮かび上がる生き方もまた深い。
読了日:04月10日 著者:ボフミル フラバル

 山崎実業アイデアBOOKの感想
山崎実業アイデアBOOKの感想好き。しゅっとしているところと、プラスチックでないところ、仕組みがシンプルであるところ、マグネット式やフック式で相手側に加工を要しないところ。今やアイテム数が増えすぎて、ネット上でラインナップが把握できないまでになっているので本刊行は嬉しい。以前から不便に思っていたあたりの解決法に留まらず、次々と繰り出されるアイデアに、ついそのアイテムを使うために自宅を改造したくなってくるという逆転現象が起きるのは、山崎実業ファンのあるある。待て!落ち着け! ここはという箇所から、ひとつずつ取り入れていこうではないか。
読了日:04月09日 著者:
 自然農法 わら一本の革命の感想
自然農法 わら一本の革命の感想自然農法の祖、バイブルと目される本である。著者が編み出した肥料も農薬も耕うん機も使わない「何もしない農法」は人間の究極の知恵、ではなく、人間は絶対に自然には勝てないことの証と言いきる。それはもはや宗教じみて、だからこそ強い。著者の農法は欧米の有機農業にも影響を与えたと言われるが、それが単に方法論で留まるなら、自分の自然農法とは非なるものと切り捨てる。『仏教でいう大乗的な自然農法と、便宜的な小乗的な自然農法』との比喩は言い得て妙だ。わかりやすい。『人間は自然を壊せても、自然をつくることはできない』。
消費者の『少しでも外観のいいもの、きれいなもの、大きなものを買おうという、ほんのわずかの気持ちが、百姓をここまで追いこみ、苦しめている』。スーパーの売り場で、私だって選ぶ。同じ価格でも形のより良い玉ねぎを消費者が選べば、スーパーは形の悪い玉ねぎを事前に弾くだろう。しなびた小松菜を敬遠すれば、"長持ちさせることができる"パッケージを開発し、それはコスト増となる。過度な選別や無駄な品種改良、ひいては自然なものや適正な価格を外れていってしまう現象は私たちが招き、結果的に農家を苦しめていると鮮やかに糾弾する。
読了日:04月08日 著者:福岡 正信
 安曇野の白い庭 (新潮文庫)の感想
安曇野の白い庭 (新潮文庫)の感想若い頃に読んだ氏の「白い庭」の経緯を確かめたかった。しかしやはり氏の傲慢さと他者蔑視に、嫌悪感を持て余す。350坪の土地に、俺は女や女みたいに軟弱な男にはできない仕事をやり上げたのだと自画自賛して憚らない。庭とは思いつきを手あたり次第に植えては挽き倒し植え直しを繰り返す自己満足である。自慢げに花の咲き誇る庭を眺めやるカラー写真。力と意志で現実を捻じ曲げられると信じている庭師の人間性がどうであれ、木は枝を高く伸ばし花は咲き誇る。それは逆に自然の持つ健やかさを、そして人間の小ささを証明しているように見えた。
読了日:04月01日 著者:丸山 健二
注:
 は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。 2023年04月01日
2023年3月の記録
はちみつを量り売りしてもらった。
注いだときにできた泡がまだ残って、陽に光る。
読書は娯楽であってよいけれど、いずれは暮らしと切り離せないもの。
はちみつの美味しさと、蜂や自然や商いのいろいろを想う。

<今月のデータ>
購入15冊、購入費用12,599円。
読了10冊。
積読本333冊(うちKindle本159冊、Honto本3冊)。

3月の読書メーター
読んだ本の数:10
 ルポ 誰が国語力を殺すのかの感想
ルポ 誰が国語力を殺すのかの感想
歳が離れゆくばかりの社員との対話について、時代や教育が変われば自分の年代とは前提条件が異なるだろうと、様子を知りたかったのが読む動機だった。まさか、日本に生まれ育った両親を持ちながら、母語である日本語を失った人たちがいるとは思わなかった。私たちは言葉のやりとりを通して他者とより深く意思疎通する。適切な言葉の力を持たなければ論理的に思考することはおろか、自らの気持ちを認識することもできないのだ。言語能力の個人差は以前からあることだし、機会があれば育てることができる。ただ、思っているより難しいと覚えておく。
読了日:03月26日 著者:石井 光太
 いい感じの石ころを拾いに (中公文庫)の感想
いい感じの石ころを拾いに (中公文庫)の感想
水辺で石を拾う夢を見た。その後、この本を見かけて買ったのは必然だった気がする。思うに、石は丸っこいのが好ましく、"なんかいい感じ"のものを全身で探したく、なにより無為なところがいい。とするとヒスイ海岸はいずれとして、より身近では川よりは河口、海、瀬戸内海よりは太平洋、日本海なのだな。『そんな石、どこにでも落ちてるだろ、と思う者には、今後おそろしい災禍がふりかからんことを』とか『このいまいましい女が、石の素晴らしさを目の当たりにして打ちのめされんことを願い』など、ダーク宮田が顔をのぞかせる。んんん。
読了日:03月26日 著者:宮田 珠己
 ルポ 食が壊れる 私たちは何を食べさせられるのか? (文春新書)の感想
ルポ 食が壊れる 私たちは何を食べさせられるのか? (文春新書)の感想
狂ってる。読むに堪えないと絶望しながら読み進めた。国家政府と巨大企業のタッグの前では、暮らしを守りたい個人の気持ちははあまりに無力に思える。このコロナ禍やウクライナ有事は、世界がこじらせた歪みを正す機会になるのだと私は思っていた。しかし世界のテクノロジー企業はほくそ笑んで着々と布石を打っていたのだ。私たちの「食べるものを選ぶ権利」は潰えるのか。終盤では癒され勇気づけられる思いがする。トップの姿勢がそれならば、私たちが正しい知識と倫理のもとにボトムアップでやっていくしかない。叡智がまだ残っているうちに。
『牛舎式だと4年と短い寿命が放牧だと3倍の12年に延びます(動物福祉)。次に草はタダなので、通常畜産で経費の半分を占めるエサ代や牛舎などの設備投資がかからない(経費削減)。牛をうまく使えば土壌の循環能力を再生させ温暖化ガスを土壌中に隔離できる(気候変動対策)。そして運動量も多くストレスが少ないため、牛たちの免疫力が圧倒的に高く、感染症などの病気にかかりにくいんです(病気対策)』。
『脱炭素なら牛と牧草のタッグが最強です』。牛の群れを自然の中を遊牧させる酪農は日本でもあちこちにある。正しく育てれば牛は救世主であると各国の人々が言う。誰が工場で培養された牛肉やら3Dプリンターで整形した寿司ネタやらコオロギやらを食べたいだろう。そして今生きている牛を潰せば補助金を出すと農水省は言うのだ。人工的な生産物で稼ごうとしている大企業の摺り込みは無視して、肚を据えて、正当に育てた野菜や肉を選ぼう。問題は、すでに食べ物の値段が狂っていて、これまでとの相対的な感覚で「高い」と感じてしまうこと。
『土の耕起は微生物の活動を活性化し、大切な土の有機物が分解されてしまった。さらに、休閑の間、作物の被覆がなくなるために、風雨による土壌侵食も深刻化した』。ここ、これから読む予定の本に繋がっていく予定。
読了日:03月25日 著者:堤 未果
 燃える秋 (角川文庫)の感想
燃える秋 (角川文庫)の感想
1977年の小説。主人公の言葉づかいも行動も現代からするとだいぶ違和感はあるも、時代も時代、女性が寿退社じゃなく退職して中東へ旅立つなんて、時代に先駆けた生き方を描いた。主人公の年齢設定は三十路。燃える「秋」って女性の年齢のことを暗喩しているのかな。この小説を手に取ったのは、私にもペルシャ絨毯に対する憧憬があるからだった。重量感のあるその存在を、見つめ、色に陶酔し、緻密さに驚愕し、携わる人々が費やした年月に尊崇の念を抱く。いいなあ、イラン行きたい。絨毯にまつわるイラン人の美学を想って、よしとする。
読了日:03月21日 著者:五木 寛之
 大地の五億年 せめぎあう土と生き物たち (ヤマケイ新書)の感想
大地の五億年 せめぎあう土と生き物たち (ヤマケイ新書)の感想
土についてもっと知りたくて2冊目。前作とアプローチが違う。地質や気候によって岩石から生まれた土が、少なくとも数百年の時間をかけて土壌になる。それは植物や昆虫、微生物、人間が足し算引き算でその土その土に適応してきたからなのだ。日本の土がどういうものか、なぜ山野は何もしなくても繁茂するのに畑には石灰を撒かなければならないか、ひいては農業、主食穀物と日本史、環境問題の根の深さなど、全てが繋がっていると理解できる。ここをふまえたほうが、本当に大事なものを見極められそう。「土」を考えるうえでの基本が理解できる良書。
読了日:03月20日 著者:藤井 一至
 メガバンク銀行員ぐだぐだ日記――このたびの件、深くお詫び申しあげます (日記シリーズ)の感想
メガバンク銀行員ぐだぐだ日記――このたびの件、深くお詫び申しあげます (日記シリーズ)の感想
メガバンク現職行員のぶっちゃけ話といえばシリーズとしては目玉かもしれないが、私にはシリーズで最もつまらなかった。なぜなら、銀行員は華々しい入社以来その世界に忙殺される。外界を知らない。支店の格とか出世レースとか俺の顔に泥とか、組織として病的とも思う。「客」の意味が他業種とは違うんじゃないか。他人様の制裁与奪の権利を握っていると誤解していると高慢さがにじみ出る。…私は銀行に恨みでもあるのか?あるんだろうな。真面目な銀行員の皆様、ごめんなさい。あなたに悪気が無いのは知っているんですけれど、共感はできません。
読了日:03月17日 著者:目黒冬弥
 NUDGE 実践 行動経済学 完全版の感想
NUDGE 実践 行動経済学 完全版の感想
現代社会のキーワードとしておさえておきたかった本。近接分野にも触れているぶん、厚い。さて、広義に捉えてナッジは人間が一人いれば発生するので、著者の言葉を借りれば、全てのヒューマンはキュレーターである。他人に働きかけをするとき、言い廻し、伝える順番、表現方法などナッジは意識しているつもりだ。働きかけを受け取る場合も、相手の意図や世間の潮流、経済行動学的側面を読み取ったうえで決断することは多々ある。しかしそれでも、自分の意識しない領分でナッジし、またナッジされていることはあるんだなと気づき考え込んでしまった。
『持続可能性の領域などで、新しい規範が生まれつつあると人びとに伝えると、その結果として予言が現実になることがある。多くの人は歴史の流れに逆らいたくないと思っている。あることをしている人が増えているのを目の当たりにすると、それまではむずかしいと思っていたこと、不可能だとすら思っていたことを実現できると考えるようになるかもしれない。実現しないわけがないとさえ考える人だって出てくるだろう』。これは根源的に重要なことを指摘している。社会を動かすのがなべてナッジなら、他者が受け取れる形での表明は人の義務ではないか?
読了日:03月15日 著者:リチャード・セイラー,キャス・サンスティーン
 乞食の名誉の感想
乞食の名誉の感想
「100分deフェミニズム論」で紹介された小説。引用された『不覚な違算』は、女性が自らの意志に反して背負わされる家庭内の責務を指している。先日内閣府が発表した調査結果で、育児と介護が女性の活躍を妨げる最たるものと発表していた。それは比重が大きく、挙げやすいだけであって、個人や身内で負担しなくてよい社会システムを構築するのは重要である一方、自身の愛着や同じ女性による反感の部分が小さくないことを伊藤野枝は指摘する。自分を活かしたい根源的な欲求を満たすことの障害を含め、変わっていかないかんだろうとは思うけれど。
読了日:03月15日 著者:伊 藤 野 枝
 ゼロエフの感想
ゼロエフの感想
『私が唾棄するのは紋切り型の理解である』。著者は福島を縦横に、歩きに歩く。人の声になった被災地の思いの聞き役に徹し、目に見えないものに耳を澄ます。一人の人の記憶にも年月の奥行きがあり、さらに先祖の記憶、集落の記憶も背負った言葉を、一人の身体で受け止められると思わない。我が事ではないゆえに感じる責務と無力感。しんどい。受け止められない事実を骨身に沁ませて、祈りはその先にあるのだろう。生き残った人間は何かをしたいと思うという。それぞれの鎮魂の作業。遺さなければ消える。だから碑であり野馬追であり紫陽花なのだ。
でも、碑すら人の都合で遷され忘れ去られるのだ。ではこの、作家の業みたいな、言葉にぐるぐる囚われたような文章なら遺るだろうか。何でもいい。大きなものじゃなくていいから、いろんなものを数多く遺しておけば、どれかは後世に伝わるのではないかと、これは複次的に言葉を受け取った者の、ささやかな祈り。
読了日:03月12日 著者:古川 日出男
 手のひらの京 (新潮文庫)の感想
手のひらの京 (新潮文庫)の感想
意外に、最近の作品である。年頃の三姉妹を中心とした、京都に暮らす人々の日常。凛が眺める冒頭の鴨川から始まり、そこここに描かれる情景は著者の記憶だろう。暮らす人だけが見る京都、観光客に交じって見る京都の風景は現代的だけど雅だ。愛おしさがにじむ。家から徒歩一時間以内にある神社すべてに初詣に行くのが趣味で、十以上回るとか、京都に暮らしたことがない者には想像もつかない。生まれてからずっと『身体の中へ蓄え続けた京都の息吹』が素敵ね。凛の東京行きを両親が頑強に反対する辺りで万城目学的展開を予想したが、普通に外れた。
読了日:03月02日 著者:綿矢 りさ
注: は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。
注いだときにできた泡がまだ残って、陽に光る。
読書は娯楽であってよいけれど、いずれは暮らしと切り離せないもの。
はちみつの美味しさと、蜂や自然や商いのいろいろを想う。

<今月のデータ>
購入15冊、購入費用12,599円。
読了10冊。
積読本333冊(うちKindle本159冊、Honto本3冊)。

3月の読書メーター
読んだ本の数:10
 ルポ 誰が国語力を殺すのかの感想
ルポ 誰が国語力を殺すのかの感想歳が離れゆくばかりの社員との対話について、時代や教育が変われば自分の年代とは前提条件が異なるだろうと、様子を知りたかったのが読む動機だった。まさか、日本に生まれ育った両親を持ちながら、母語である日本語を失った人たちがいるとは思わなかった。私たちは言葉のやりとりを通して他者とより深く意思疎通する。適切な言葉の力を持たなければ論理的に思考することはおろか、自らの気持ちを認識することもできないのだ。言語能力の個人差は以前からあることだし、機会があれば育てることができる。ただ、思っているより難しいと覚えておく。
読了日:03月26日 著者:石井 光太
 いい感じの石ころを拾いに (中公文庫)の感想
いい感じの石ころを拾いに (中公文庫)の感想水辺で石を拾う夢を見た。その後、この本を見かけて買ったのは必然だった気がする。思うに、石は丸っこいのが好ましく、"なんかいい感じ"のものを全身で探したく、なにより無為なところがいい。とするとヒスイ海岸はいずれとして、より身近では川よりは河口、海、瀬戸内海よりは太平洋、日本海なのだな。『そんな石、どこにでも落ちてるだろ、と思う者には、今後おそろしい災禍がふりかからんことを』とか『このいまいましい女が、石の素晴らしさを目の当たりにして打ちのめされんことを願い』など、ダーク宮田が顔をのぞかせる。んんん。
読了日:03月26日 著者:宮田 珠己
 ルポ 食が壊れる 私たちは何を食べさせられるのか? (文春新書)の感想
ルポ 食が壊れる 私たちは何を食べさせられるのか? (文春新書)の感想狂ってる。読むに堪えないと絶望しながら読み進めた。国家政府と巨大企業のタッグの前では、暮らしを守りたい個人の気持ちははあまりに無力に思える。このコロナ禍やウクライナ有事は、世界がこじらせた歪みを正す機会になるのだと私は思っていた。しかし世界のテクノロジー企業はほくそ笑んで着々と布石を打っていたのだ。私たちの「食べるものを選ぶ権利」は潰えるのか。終盤では癒され勇気づけられる思いがする。トップの姿勢がそれならば、私たちが正しい知識と倫理のもとにボトムアップでやっていくしかない。叡智がまだ残っているうちに。
『牛舎式だと4年と短い寿命が放牧だと3倍の12年に延びます(動物福祉)。次に草はタダなので、通常畜産で経費の半分を占めるエサ代や牛舎などの設備投資がかからない(経費削減)。牛をうまく使えば土壌の循環能力を再生させ温暖化ガスを土壌中に隔離できる(気候変動対策)。そして運動量も多くストレスが少ないため、牛たちの免疫力が圧倒的に高く、感染症などの病気にかかりにくいんです(病気対策)』。
『脱炭素なら牛と牧草のタッグが最強です』。牛の群れを自然の中を遊牧させる酪農は日本でもあちこちにある。正しく育てれば牛は救世主であると各国の人々が言う。誰が工場で培養された牛肉やら3Dプリンターで整形した寿司ネタやらコオロギやらを食べたいだろう。そして今生きている牛を潰せば補助金を出すと農水省は言うのだ。人工的な生産物で稼ごうとしている大企業の摺り込みは無視して、肚を据えて、正当に育てた野菜や肉を選ぼう。問題は、すでに食べ物の値段が狂っていて、これまでとの相対的な感覚で「高い」と感じてしまうこと。
『土の耕起は微生物の活動を活性化し、大切な土の有機物が分解されてしまった。さらに、休閑の間、作物の被覆がなくなるために、風雨による土壌侵食も深刻化した』。ここ、これから読む予定の本に繋がっていく予定。
読了日:03月25日 著者:堤 未果

 燃える秋 (角川文庫)の感想
燃える秋 (角川文庫)の感想1977年の小説。主人公の言葉づかいも行動も現代からするとだいぶ違和感はあるも、時代も時代、女性が寿退社じゃなく退職して中東へ旅立つなんて、時代に先駆けた生き方を描いた。主人公の年齢設定は三十路。燃える「秋」って女性の年齢のことを暗喩しているのかな。この小説を手に取ったのは、私にもペルシャ絨毯に対する憧憬があるからだった。重量感のあるその存在を、見つめ、色に陶酔し、緻密さに驚愕し、携わる人々が費やした年月に尊崇の念を抱く。いいなあ、イラン行きたい。絨毯にまつわるイラン人の美学を想って、よしとする。
読了日:03月21日 著者:五木 寛之

 大地の五億年 せめぎあう土と生き物たち (ヤマケイ新書)の感想
大地の五億年 せめぎあう土と生き物たち (ヤマケイ新書)の感想土についてもっと知りたくて2冊目。前作とアプローチが違う。地質や気候によって岩石から生まれた土が、少なくとも数百年の時間をかけて土壌になる。それは植物や昆虫、微生物、人間が足し算引き算でその土その土に適応してきたからなのだ。日本の土がどういうものか、なぜ山野は何もしなくても繁茂するのに畑には石灰を撒かなければならないか、ひいては農業、主食穀物と日本史、環境問題の根の深さなど、全てが繋がっていると理解できる。ここをふまえたほうが、本当に大事なものを見極められそう。「土」を考えるうえでの基本が理解できる良書。
読了日:03月20日 著者:藤井 一至

 メガバンク銀行員ぐだぐだ日記――このたびの件、深くお詫び申しあげます (日記シリーズ)の感想
メガバンク銀行員ぐだぐだ日記――このたびの件、深くお詫び申しあげます (日記シリーズ)の感想メガバンク現職行員のぶっちゃけ話といえばシリーズとしては目玉かもしれないが、私にはシリーズで最もつまらなかった。なぜなら、銀行員は華々しい入社以来その世界に忙殺される。外界を知らない。支店の格とか出世レースとか俺の顔に泥とか、組織として病的とも思う。「客」の意味が他業種とは違うんじゃないか。他人様の制裁与奪の権利を握っていると誤解していると高慢さがにじみ出る。…私は銀行に恨みでもあるのか?あるんだろうな。真面目な銀行員の皆様、ごめんなさい。あなたに悪気が無いのは知っているんですけれど、共感はできません。
読了日:03月17日 著者:目黒冬弥

 NUDGE 実践 行動経済学 完全版の感想
NUDGE 実践 行動経済学 完全版の感想現代社会のキーワードとしておさえておきたかった本。近接分野にも触れているぶん、厚い。さて、広義に捉えてナッジは人間が一人いれば発生するので、著者の言葉を借りれば、全てのヒューマンはキュレーターである。他人に働きかけをするとき、言い廻し、伝える順番、表現方法などナッジは意識しているつもりだ。働きかけを受け取る場合も、相手の意図や世間の潮流、経済行動学的側面を読み取ったうえで決断することは多々ある。しかしそれでも、自分の意識しない領分でナッジし、またナッジされていることはあるんだなと気づき考え込んでしまった。
『持続可能性の領域などで、新しい規範が生まれつつあると人びとに伝えると、その結果として予言が現実になることがある。多くの人は歴史の流れに逆らいたくないと思っている。あることをしている人が増えているのを目の当たりにすると、それまではむずかしいと思っていたこと、不可能だとすら思っていたことを実現できると考えるようになるかもしれない。実現しないわけがないとさえ考える人だって出てくるだろう』。これは根源的に重要なことを指摘している。社会を動かすのがなべてナッジなら、他者が受け取れる形での表明は人の義務ではないか?
読了日:03月15日 著者:リチャード・セイラー,キャス・サンスティーン

 乞食の名誉の感想
乞食の名誉の感想「100分deフェミニズム論」で紹介された小説。引用された『不覚な違算』は、女性が自らの意志に反して背負わされる家庭内の責務を指している。先日内閣府が発表した調査結果で、育児と介護が女性の活躍を妨げる最たるものと発表していた。それは比重が大きく、挙げやすいだけであって、個人や身内で負担しなくてよい社会システムを構築するのは重要である一方、自身の愛着や同じ女性による反感の部分が小さくないことを伊藤野枝は指摘する。自分を活かしたい根源的な欲求を満たすことの障害を含め、変わっていかないかんだろうとは思うけれど。
読了日:03月15日 著者:伊 藤 野 枝

 ゼロエフの感想
ゼロエフの感想『私が唾棄するのは紋切り型の理解である』。著者は福島を縦横に、歩きに歩く。人の声になった被災地の思いの聞き役に徹し、目に見えないものに耳を澄ます。一人の人の記憶にも年月の奥行きがあり、さらに先祖の記憶、集落の記憶も背負った言葉を、一人の身体で受け止められると思わない。我が事ではないゆえに感じる責務と無力感。しんどい。受け止められない事実を骨身に沁ませて、祈りはその先にあるのだろう。生き残った人間は何かをしたいと思うという。それぞれの鎮魂の作業。遺さなければ消える。だから碑であり野馬追であり紫陽花なのだ。
でも、碑すら人の都合で遷され忘れ去られるのだ。ではこの、作家の業みたいな、言葉にぐるぐる囚われたような文章なら遺るだろうか。何でもいい。大きなものじゃなくていいから、いろんなものを数多く遺しておけば、どれかは後世に伝わるのではないかと、これは複次的に言葉を受け取った者の、ささやかな祈り。
読了日:03月12日 著者:古川 日出男

 手のひらの京 (新潮文庫)の感想
手のひらの京 (新潮文庫)の感想意外に、最近の作品である。年頃の三姉妹を中心とした、京都に暮らす人々の日常。凛が眺める冒頭の鴨川から始まり、そこここに描かれる情景は著者の記憶だろう。暮らす人だけが見る京都、観光客に交じって見る京都の風景は現代的だけど雅だ。愛おしさがにじむ。家から徒歩一時間以内にある神社すべてに初詣に行くのが趣味で、十以上回るとか、京都に暮らしたことがない者には想像もつかない。生まれてからずっと『身体の中へ蓄え続けた京都の息吹』が素敵ね。凛の東京行きを両親が頑強に反対する辺りで万城目学的展開を予想したが、普通に外れた。
読了日:03月02日 著者:綿矢 りさ

注:
 は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。 2023年03月01日
2023年2月の記録
久しぶりに読んだ本が買った本を上回る。
それは端的に言って、AmazonのKindle本セールが刺さらないからである。
気になって古本屋から取り寄せる本は増えている気配。
<今月のデータ>
購入10冊、購入費用11,825円。
読了15冊。
積読本329冊(うちKindle本155冊、Honto本3冊)。

2月の読書メーター
読んだ本の数:15
 なんで家族を続けるの? (文春新書 1303)の感想
なんで家族を続けるの? (文春新書 1303)の感想
内田也哉子が中野信子にさまざま尋ねる対談。彼女の抱えてきたわだかまりは融けただろうか。中野信子も内田也哉子も特殊な家庭に育ったという自認があった。それは確実に「新しい家族を持つ」ときに影響した訳で、そこに関心を持つ私もまた自分の育った家庭を普通でないと思ってきた。中野信子の回答は端的だ。生物学的にまた脳科学的に見て、家族は何でもありで普通なんて無い。内田也哉子がほっとする気配が感じ取れて、こちらも緩む。本木雅弘も中野信子も姓を変えることに抵抗が無かった話から、自分を薄情だと自責しなくてよいのだと思えた。
読了日:02月28日 著者:内田 也哉子,中野 信子
 人類の星の時間の感想
人類の星の時間の感想
素晴らしい著作である。若い頃に読む機会と意欲に恵まれていれば人生の糧になったはずだ。歴史小説集という。ヨーロッパ中心にもかかわらず胸に重たく感じるのは、この選ばれた瞬間の多くが西洋人のみならず、極東の私にも人間の来し方として大きな転換点だったと感じられるからだ。凝縮された一瞬。それが他民族への虐殺と略奪であっても、金儲けや自尊心の為であっても、確かに煌めく。ツヴァイクがオーストリア人であると知ればロシアが3篇入っているのも納得だ。ドストエフスキーとトルストイのが好き。計り知れぬ哀しみ、これもまた煌めく。
読了日:02月27日 著者:シュテファン・ツヴァイク
 園芸家の一年 (平凡社ライブラリー)の感想
園芸家の一年 (平凡社ライブラリー)の感想
耕作すなわち文化。植物に飼いならされる人間の悲喜こもごもをユーモア満載で綴っている。当時は紳士が嗜む趣味であったようで、なるほど傍から見れば理解しがたい、滑稽ですらあろう姿だが、若い時分には解さない深い深い哲学が庭仕事にはあるからなのだ。そして『わたしたち園芸家は、未来に対して生きている』と断言する。花を植える瞬間はその花が咲いた姿を想うだろう。木を植える瞬間はその木が大きくなった10年後を、さらには見ることの叶わぬ50年後をも想うだろう。いつか自分の庭を得て、体感でわかるようになったら、また読みたい。
訳者あとがきに知った背景は覚えておきたい。チャペックはチェコ人である。この文章が連載された頃、ナチスドイツによる弾圧は既にチェコに及んでいた。兄ヨゼフは逮捕され、強制収容所で亡くなった。カレルはその直前に家で亡くなり、ナチの手を逃れている。そのような時世に、この平和で、笑いに満ちて、何気ない暮らしへの愛溢れる文章が書かれたのだ。それはチャペック兄弟が何を大切に思っていたかを、如実に表していると思った。そしたらその瞬間、とても深い思いが隠されたエッセイだったのだと悟って目が潤んでしまった。
読了日:02月25日 著者:カレル チャペック
 お金に頼らず 生きたい君へ: 廃村「自力」生活記 (14歳の世渡り術)の感想
お金に頼らず 生きたい君へ: 廃村「自力」生活記 (14歳の世渡り術)の感想
14歳の世渡り術というお題は半ばから踏み倒し、小蕗暮らし近況報告に突入していく。"エネルギーだだ漏れ生活"を脱却して、お金にも文明にも頼らない生活を実現すべく服部文祥は廃村の家と土地を手に入れた。電気、水、燃料を自力でなんとかする暮らし。食料は猟をし、野菜を植え、春を心待ちにする。手あたり次第に木の苗を植えて試せる土地の広大さが羨ましすぎる。服部文祥への私の恋心は差し引いても、胸が疼いた理由。そのキーワードは、桃源郷。人それぞれに違う、その理想郷を実現する一歩を踏み出した、その喜びが溢れているからだ。
人間がいる/いない、獣がいる/いないで村の自然の在りようが違ってくるあたりの観察が興味深い。獣に野菜や果樹の苗や芽を喰われては、労力と金と時間の喪失にがっかりしている。春は限られた回数しかその人に巡ってこない事実を想う。狩猟のときには決して言わなかった『鹿が憎い』にドキリとする。雌鹿を独りで仕留めた、愛すべきナツ(フィクションです)。面倒くさいと口では言いながら、服部文祥は溺愛していると感じる。久保俊治氏の猟犬フチを思い出した。女神だ。ナツの性別は知らんけど。
読了日:02月23日 著者:服部 文祥
 教養悪口本の感想
教養悪口本の感想
自称専業インテリ悪口作家。ジアタマのいい人の戯言って面白いな。それもこれくらいの分量に留めるからこそ。理系ながら文学のたしなみもあるので深みはそこそこでも幅広くて面白い。ってこれ悪口じゃありませんよ。プロールの餌もんやとか、あいつはラフレシアとか、毒舌っぽくない超毒舌が好き。すぐ使いたい。ああ、でも、自虐にこそ使いたいな。「重さがマイナス」とか言い出しかねない性格だし、車輪の再発明気質だし、スタックオーバーフローです!とか アセトアルデヒドふざけんな!とか、ユーモアで自分を許すってのも大事じゃね? 好い。
読了日:02月17日 著者:堀元 見
 サステイナブルに家を建てるの感想
サステイナブルに家を建てるの感想
家を建てる行為には、金銭面の制限と庶民的願望と環境負荷との板挟みで悩むプロセスがつきものだろう。環境に負荷をかけずに生きられない人間としては、設計士さんの一言が慰めではある。『自分のためだけでなく、次の住まい手のことまで考えて、日本に良質な家をひとつ増やしましょう』。自分の納得がゆく選択を重ねた先に、晴れやかな生活が待っている。現実に考えうる範囲で、自分たちの性格も考慮して、環境に掛ける負荷をできるだけ下げた家だと思う。分譲地を買い、ハウスメーカーの設定した枠の中で選択を重ねるのとは全然違うのだろうな。
読了日:02月16日 著者:服部雄一郎,服部麻子
 鳥・虫・草木と楽しむ オーガニック植木屋の剪定術の感想
鳥・虫・草木と楽しむ オーガニック植木屋の剪定術の感想
通りすがりに見る他所様の庭は、本職が剪定したようなものもあれば、自分でしていた剪定が歳取ってできなくなって巨木伸び放題になったようなものもある。今の私に手入れすべき庭はないけれど、自分で何とかできるような、心安らぐような、そんな庭ができたらと妄想する。曳地家メソッド本3冊目。好きなのだ。本書は木の維持管理を主に置いたもの。木が伸びるポテンシャルと、枝ぶり、樹形ごとにまとめられている。人間が見て気持ちのよい、木にとっても心地よい状態というのがあるのだな。全然かわいそうじゃない。「玉散らし」の呼び名を覚えた。
読了日:02月12日 著者:ひきちガーデンサービス(曳地トシ+曳地義治)
 (003)畳 (百年文庫)の感想
(003)畳 (百年文庫)の感想
私の畳生活への憧れはどこから来るんかなあ、と手に取った。しかしどの小説も、畳に明らかな焦点が当たることはなく、役割も存在感も無いに等しい。3篇目などむしろ「窓」なのだが、読み終えると、思い描く場面は畳の部屋でしかありえない、畳の上で展開した出来事であったと思い当たる。日本人の生活の匂い、なのだろう。『軍国歌謡集』が面白い。男は幻想を抱き、女も幻想も抱く。それは相似形でありながら、か弱いはずの女の心情の転換は素早く、強靭で、さらに勇敢だ。それ故に見事に粉砕される男たちの様子が小気味良くすらある、見事な構成。
読了日:02月12日 著者:林芙美子,獅子文六,山川方夫
 無農薬で安心・ラクラク はじめての手づくりオーガニック・ガーデン (PHPビジュアル実用BOOKS)の感想
無農薬で安心・ラクラク はじめての手づくりオーガニック・ガーデン (PHPビジュアル実用BOOKS)の感想
庭全体をバランスよく妄想できるのはこちら。好き。広い庭も狭い庭も、樹木、草花、アプローチ、水場、作業場所、雨水タンクまでいろんなパターンが細かく載っていて、シンボルツリーやその根元、壁際、半日蔭にはシランが素敵など妄想が広がる。木は冬に実のなるものを植えよう。ちなみに特に何も植えない場所、日陰にはドクダミ、日向にはシロツメクサの種をぶちまけることになっている。その土地に合うか合わないかは植えてみるしかないのね。人間だけの時間とは違う、うーんと伸ばしたような時間軸を楽しみたい。コンポストも曳地式がラクそう。
読了日:02月12日 著者:曳地 トシ,曳地 義治
 猫と住まいの解剖図鑑の感想
猫と住まいの解剖図鑑の感想
住まいを考えるとき、人間が困ることを猫にさせないつくりというものがある。猫に物事を禁止しても聴いてもらえないのだから、配置や素材など、人と猫の双方に無理のない妥協点を見出すのがお互いの為だと思うが、それを猫の要望ばかりを容れて俺は我慢かと態度を硬化されては困り果てる。ひいては人間の為だからと穏やかに説明を重ねながら、水を差さないように少しずつ修正を差し入れていくしかないのだろう。精神的に疲れる。そして大手は融通が効かない。助言をくれる専門家が猫エキスパートであったなら、どれだけ楽なことか。繰り返し見返す。
読了日:02月11日 著者:いしまるあきこ
 運動未満で体はととのうの感想
運動未満で体はととのうの感想
呼吸と重心。ここのところ忙しく、目と脳を絶え間なく朝から晩まで働かせるような日々を続けていたら、自分の身体を感じ取れなくなっていた。すっと立つことができなくて、中国武術の時間は目を閉じないと、脳みそで体を動かそうとしてしまう。呼吸と重心。ほんとうのことはシンプルだ。だからこそ効くのだけれど、現代のややこしげな"理論"にインパクト負けしがち。こんな整骨院&ジムが近くにあったら通うのになあ。舌トレーニングはこっそりやる。この動作は中国武術にもあるが、なかなか自分のものにできない。小顔効果もあるとか!
読了日:02月10日 著者:長島康之
 死ぬ気まんまん (光文社文庫)の感想
死ぬ気まんまん (光文社文庫)の感想
癌再発の告知を受けた足でジャガーを買ったのは有名な話。命も金も惜しまず暮らして、なのに宣告された余命2年を過ぎて周囲に愛想を尽かされたりする。70歳は死ぬのにちょうど良い、生き延びると困ると公言し、ホスピスに入院して14日で自ら退院してしまったりする。骨にも転移して砕けそうな痛みがあるのに。どどめ色になってしまったのに。私は自然の摂理として緩慢な死は受け入れられると思っている。でも、どどめ色は怖いな。私も立派に死ねるだろうか。洋子さんがホスピスから見たゴッホの夕陽を、私も見られるだろうか。対談がよい。
読了日:02月09日 著者:佐野 洋子
 生きのびるための流域思考 (ちくまプリマー新書)の感想
生きのびるための流域思考 (ちくまプリマー新書)の感想
水害を防ぐための方策は、排水機能強化やハザードマップ作成に限らず多岐にわたる。人の生活を守る取り組みは奥深い。さて、市街地化が進むと土地の保水・遊水力は低下する。その変化がハイドログラフに歴然と現れており、すなわちそれは豪雨災害の激甚化を意味する。温暖化による雨量の増加も考え合わせると、ますます事態は悪化すると予想される。治水(国土交通省)だけではない、環境保全(環境省)や農地保全(農林水産省)、森林保全(林野庁)も横断したグリーンインフラの構築が喫緊である。道筋はここに示された。あとはやるだけ。
読了日:02月08日 著者:岸 由二
 九尾の猫〔新訳版〕 (ハヤカワ・ミステリ文庫)の感想
九尾の猫〔新訳版〕 (ハヤカワ・ミステリ文庫)の感想
読む順番を違えているのはわかっていたのだけれど。前巻で生じた何かをエラリイは引きずっている。新たにニューヨークで起きた事件に首を突っ込むのを躊躇ったのもつかの間、俄然やる気になったエラリイに警視共々快哉を叫ぶ。ニューヨークにはライツヴィルに無いものがある。ニューヨーク市民による群舞、恐怖、混乱、妄動、からの暴動。警察が事件を解決しない限り理不尽な恐怖に向き合うしかない、都会の不穏な空気がなんとも言えない。手がかりを得てからの焦点を絞った心理戦パート、精神の迷宮パートと、がらりがらりと転換する趣向も魅力だ。
読了日:02月04日 著者:エラリイ・クイーン
 医療現場の行動経済学: すれ違う医者と患者の感想
医療現場の行動経済学: すれ違う医者と患者の感想
医療における医者と患者のやりとりのうまくいかない部分を、行動経済学の側面から分析する。患者は必ずしも医学的に望ましいと思える意思決定をしない。そりゃそうだ。命もかかりお金もかかり、しかもたいてい不意打ちだ。これまで言われてきたインフォームドコンセントの不全を補完する次段階の考え方として、シェアード・ディシジョン・メーキングが出てきた。そこに"ナッジ"することで齟齬や歪みの少ない決断を導く方法が試行錯誤されている。一方、意思決定が合理的でないのは医療者側も同じ。読んでいて息苦しい理由は、深く考えたくない。
読了日:02月02日 著者:大竹 文雄,平井 啓
注: は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。
それは端的に言って、AmazonのKindle本セールが刺さらないからである。
気になって古本屋から取り寄せる本は増えている気配。
<今月のデータ>
購入10冊、購入費用11,825円。
読了15冊。
積読本329冊(うちKindle本155冊、Honto本3冊)。

2月の読書メーター
読んだ本の数:15
 なんで家族を続けるの? (文春新書 1303)の感想
なんで家族を続けるの? (文春新書 1303)の感想内田也哉子が中野信子にさまざま尋ねる対談。彼女の抱えてきたわだかまりは融けただろうか。中野信子も内田也哉子も特殊な家庭に育ったという自認があった。それは確実に「新しい家族を持つ」ときに影響した訳で、そこに関心を持つ私もまた自分の育った家庭を普通でないと思ってきた。中野信子の回答は端的だ。生物学的にまた脳科学的に見て、家族は何でもありで普通なんて無い。内田也哉子がほっとする気配が感じ取れて、こちらも緩む。本木雅弘も中野信子も姓を変えることに抵抗が無かった話から、自分を薄情だと自責しなくてよいのだと思えた。
読了日:02月28日 著者:内田 也哉子,中野 信子

 人類の星の時間の感想
人類の星の時間の感想素晴らしい著作である。若い頃に読む機会と意欲に恵まれていれば人生の糧になったはずだ。歴史小説集という。ヨーロッパ中心にもかかわらず胸に重たく感じるのは、この選ばれた瞬間の多くが西洋人のみならず、極東の私にも人間の来し方として大きな転換点だったと感じられるからだ。凝縮された一瞬。それが他民族への虐殺と略奪であっても、金儲けや自尊心の為であっても、確かに煌めく。ツヴァイクがオーストリア人であると知ればロシアが3篇入っているのも納得だ。ドストエフスキーとトルストイのが好き。計り知れぬ哀しみ、これもまた煌めく。
読了日:02月27日 著者:シュテファン・ツヴァイク

 園芸家の一年 (平凡社ライブラリー)の感想
園芸家の一年 (平凡社ライブラリー)の感想耕作すなわち文化。植物に飼いならされる人間の悲喜こもごもをユーモア満載で綴っている。当時は紳士が嗜む趣味であったようで、なるほど傍から見れば理解しがたい、滑稽ですらあろう姿だが、若い時分には解さない深い深い哲学が庭仕事にはあるからなのだ。そして『わたしたち園芸家は、未来に対して生きている』と断言する。花を植える瞬間はその花が咲いた姿を想うだろう。木を植える瞬間はその木が大きくなった10年後を、さらには見ることの叶わぬ50年後をも想うだろう。いつか自分の庭を得て、体感でわかるようになったら、また読みたい。
訳者あとがきに知った背景は覚えておきたい。チャペックはチェコ人である。この文章が連載された頃、ナチスドイツによる弾圧は既にチェコに及んでいた。兄ヨゼフは逮捕され、強制収容所で亡くなった。カレルはその直前に家で亡くなり、ナチの手を逃れている。そのような時世に、この平和で、笑いに満ちて、何気ない暮らしへの愛溢れる文章が書かれたのだ。それはチャペック兄弟が何を大切に思っていたかを、如実に表していると思った。そしたらその瞬間、とても深い思いが隠されたエッセイだったのだと悟って目が潤んでしまった。
読了日:02月25日 著者:カレル チャペック

 お金に頼らず 生きたい君へ: 廃村「自力」生活記 (14歳の世渡り術)の感想
お金に頼らず 生きたい君へ: 廃村「自力」生活記 (14歳の世渡り術)の感想14歳の世渡り術というお題は半ばから踏み倒し、小蕗暮らし近況報告に突入していく。"エネルギーだだ漏れ生活"を脱却して、お金にも文明にも頼らない生活を実現すべく服部文祥は廃村の家と土地を手に入れた。電気、水、燃料を自力でなんとかする暮らし。食料は猟をし、野菜を植え、春を心待ちにする。手あたり次第に木の苗を植えて試せる土地の広大さが羨ましすぎる。服部文祥への私の恋心は差し引いても、胸が疼いた理由。そのキーワードは、桃源郷。人それぞれに違う、その理想郷を実現する一歩を踏み出した、その喜びが溢れているからだ。
人間がいる/いない、獣がいる/いないで村の自然の在りようが違ってくるあたりの観察が興味深い。獣に野菜や果樹の苗や芽を喰われては、労力と金と時間の喪失にがっかりしている。春は限られた回数しかその人に巡ってこない事実を想う。狩猟のときには決して言わなかった『鹿が憎い』にドキリとする。雌鹿を独りで仕留めた、愛すべきナツ(フィクションです)。面倒くさいと口では言いながら、服部文祥は溺愛していると感じる。久保俊治氏の猟犬フチを思い出した。女神だ。ナツの性別は知らんけど。
読了日:02月23日 著者:服部 文祥
 教養悪口本の感想
教養悪口本の感想自称専業インテリ悪口作家。ジアタマのいい人の戯言って面白いな。それもこれくらいの分量に留めるからこそ。理系ながら文学のたしなみもあるので深みはそこそこでも幅広くて面白い。ってこれ悪口じゃありませんよ。プロールの餌もんやとか、あいつはラフレシアとか、毒舌っぽくない超毒舌が好き。すぐ使いたい。ああ、でも、自虐にこそ使いたいな。「重さがマイナス」とか言い出しかねない性格だし、車輪の再発明気質だし、スタックオーバーフローです!とか アセトアルデヒドふざけんな!とか、ユーモアで自分を許すってのも大事じゃね? 好い。
読了日:02月17日 著者:堀元 見

 サステイナブルに家を建てるの感想
サステイナブルに家を建てるの感想家を建てる行為には、金銭面の制限と庶民的願望と環境負荷との板挟みで悩むプロセスがつきものだろう。環境に負荷をかけずに生きられない人間としては、設計士さんの一言が慰めではある。『自分のためだけでなく、次の住まい手のことまで考えて、日本に良質な家をひとつ増やしましょう』。自分の納得がゆく選択を重ねた先に、晴れやかな生活が待っている。現実に考えうる範囲で、自分たちの性格も考慮して、環境に掛ける負荷をできるだけ下げた家だと思う。分譲地を買い、ハウスメーカーの設定した枠の中で選択を重ねるのとは全然違うのだろうな。
読了日:02月16日 著者:服部雄一郎,服部麻子

 鳥・虫・草木と楽しむ オーガニック植木屋の剪定術の感想
鳥・虫・草木と楽しむ オーガニック植木屋の剪定術の感想通りすがりに見る他所様の庭は、本職が剪定したようなものもあれば、自分でしていた剪定が歳取ってできなくなって巨木伸び放題になったようなものもある。今の私に手入れすべき庭はないけれど、自分で何とかできるような、心安らぐような、そんな庭ができたらと妄想する。曳地家メソッド本3冊目。好きなのだ。本書は木の維持管理を主に置いたもの。木が伸びるポテンシャルと、枝ぶり、樹形ごとにまとめられている。人間が見て気持ちのよい、木にとっても心地よい状態というのがあるのだな。全然かわいそうじゃない。「玉散らし」の呼び名を覚えた。
読了日:02月12日 著者:ひきちガーデンサービス(曳地トシ+曳地義治)
 (003)畳 (百年文庫)の感想
(003)畳 (百年文庫)の感想私の畳生活への憧れはどこから来るんかなあ、と手に取った。しかしどの小説も、畳に明らかな焦点が当たることはなく、役割も存在感も無いに等しい。3篇目などむしろ「窓」なのだが、読み終えると、思い描く場面は畳の部屋でしかありえない、畳の上で展開した出来事であったと思い当たる。日本人の生活の匂い、なのだろう。『軍国歌謡集』が面白い。男は幻想を抱き、女も幻想も抱く。それは相似形でありながら、か弱いはずの女の心情の転換は素早く、強靭で、さらに勇敢だ。それ故に見事に粉砕される男たちの様子が小気味良くすらある、見事な構成。
読了日:02月12日 著者:林芙美子,獅子文六,山川方夫
 無農薬で安心・ラクラク はじめての手づくりオーガニック・ガーデン (PHPビジュアル実用BOOKS)の感想
無農薬で安心・ラクラク はじめての手づくりオーガニック・ガーデン (PHPビジュアル実用BOOKS)の感想庭全体をバランスよく妄想できるのはこちら。好き。広い庭も狭い庭も、樹木、草花、アプローチ、水場、作業場所、雨水タンクまでいろんなパターンが細かく載っていて、シンボルツリーやその根元、壁際、半日蔭にはシランが素敵など妄想が広がる。木は冬に実のなるものを植えよう。ちなみに特に何も植えない場所、日陰にはドクダミ、日向にはシロツメクサの種をぶちまけることになっている。その土地に合うか合わないかは植えてみるしかないのね。人間だけの時間とは違う、うーんと伸ばしたような時間軸を楽しみたい。コンポストも曳地式がラクそう。
読了日:02月12日 著者:曳地 トシ,曳地 義治
 猫と住まいの解剖図鑑の感想
猫と住まいの解剖図鑑の感想住まいを考えるとき、人間が困ることを猫にさせないつくりというものがある。猫に物事を禁止しても聴いてもらえないのだから、配置や素材など、人と猫の双方に無理のない妥協点を見出すのがお互いの為だと思うが、それを猫の要望ばかりを容れて俺は我慢かと態度を硬化されては困り果てる。ひいては人間の為だからと穏やかに説明を重ねながら、水を差さないように少しずつ修正を差し入れていくしかないのだろう。精神的に疲れる。そして大手は融通が効かない。助言をくれる専門家が猫エキスパートであったなら、どれだけ楽なことか。繰り返し見返す。
読了日:02月11日 著者:いしまるあきこ
 運動未満で体はととのうの感想
運動未満で体はととのうの感想呼吸と重心。ここのところ忙しく、目と脳を絶え間なく朝から晩まで働かせるような日々を続けていたら、自分の身体を感じ取れなくなっていた。すっと立つことができなくて、中国武術の時間は目を閉じないと、脳みそで体を動かそうとしてしまう。呼吸と重心。ほんとうのことはシンプルだ。だからこそ効くのだけれど、現代のややこしげな"理論"にインパクト負けしがち。こんな整骨院&ジムが近くにあったら通うのになあ。舌トレーニングはこっそりやる。この動作は中国武術にもあるが、なかなか自分のものにできない。小顔効果もあるとか!
読了日:02月10日 著者:長島康之

 死ぬ気まんまん (光文社文庫)の感想
死ぬ気まんまん (光文社文庫)の感想癌再発の告知を受けた足でジャガーを買ったのは有名な話。命も金も惜しまず暮らして、なのに宣告された余命2年を過ぎて周囲に愛想を尽かされたりする。70歳は死ぬのにちょうど良い、生き延びると困ると公言し、ホスピスに入院して14日で自ら退院してしまったりする。骨にも転移して砕けそうな痛みがあるのに。どどめ色になってしまったのに。私は自然の摂理として緩慢な死は受け入れられると思っている。でも、どどめ色は怖いな。私も立派に死ねるだろうか。洋子さんがホスピスから見たゴッホの夕陽を、私も見られるだろうか。対談がよい。
読了日:02月09日 著者:佐野 洋子

 生きのびるための流域思考 (ちくまプリマー新書)の感想
生きのびるための流域思考 (ちくまプリマー新書)の感想水害を防ぐための方策は、排水機能強化やハザードマップ作成に限らず多岐にわたる。人の生活を守る取り組みは奥深い。さて、市街地化が進むと土地の保水・遊水力は低下する。その変化がハイドログラフに歴然と現れており、すなわちそれは豪雨災害の激甚化を意味する。温暖化による雨量の増加も考え合わせると、ますます事態は悪化すると予想される。治水(国土交通省)だけではない、環境保全(環境省)や農地保全(農林水産省)、森林保全(林野庁)も横断したグリーンインフラの構築が喫緊である。道筋はここに示された。あとはやるだけ。
読了日:02月08日 著者:岸 由二

 九尾の猫〔新訳版〕 (ハヤカワ・ミステリ文庫)の感想
九尾の猫〔新訳版〕 (ハヤカワ・ミステリ文庫)の感想読む順番を違えているのはわかっていたのだけれど。前巻で生じた何かをエラリイは引きずっている。新たにニューヨークで起きた事件に首を突っ込むのを躊躇ったのもつかの間、俄然やる気になったエラリイに警視共々快哉を叫ぶ。ニューヨークにはライツヴィルに無いものがある。ニューヨーク市民による群舞、恐怖、混乱、妄動、からの暴動。警察が事件を解決しない限り理不尽な恐怖に向き合うしかない、都会の不穏な空気がなんとも言えない。手がかりを得てからの焦点を絞った心理戦パート、精神の迷宮パートと、がらりがらりと転換する趣向も魅力だ。
読了日:02月04日 著者:エラリイ・クイーン

 医療現場の行動経済学: すれ違う医者と患者の感想
医療現場の行動経済学: すれ違う医者と患者の感想医療における医者と患者のやりとりのうまくいかない部分を、行動経済学の側面から分析する。患者は必ずしも医学的に望ましいと思える意思決定をしない。そりゃそうだ。命もかかりお金もかかり、しかもたいてい不意打ちだ。これまで言われてきたインフォームドコンセントの不全を補完する次段階の考え方として、シェアード・ディシジョン・メーキングが出てきた。そこに"ナッジ"することで齟齬や歪みの少ない決断を導く方法が試行錯誤されている。一方、意思決定が合理的でないのは医療者側も同じ。読んでいて息苦しい理由は、深く考えたくない。
読了日:02月02日 著者:大竹 文雄,平井 啓

注:
 は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。 2023年02月02日
2023年1月の記録
理想の本棚を夢想しただけで積読本が増えるのはどうした現象だろう。
積読本の棚が本に申し訳ないような様相になってきた。
本が二列になると後ろの本の背表紙が見えなくてもやもやするのは私なのに。
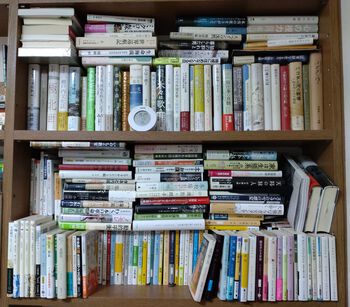
<今月のデータ>
購入18冊、購入費用14,992円。
読了14冊。
積読本332冊(うちKindle本157冊、Honto本4冊)。

 黒猫ルーイ、名探偵になる (ランダムハウス講談社文庫)の感想
黒猫ルーイ、名探偵になる (ランダムハウス講談社文庫)の感想
元気でキラキラした女性テンプルが主人公。相棒は堂々たる体躯の黒猫ルーイ…と言いたいところだが、ルーイは喋るでも主人公の腕を咥えてナビゲートするでもなく、仮にルーイの独白パートを除いても、最後のメッセージを除いてすら普通にミステリの起承転結が成立している。しかしルーイはテンプルを心配に思っていて、助けるために奔走した挙句収容されてしまうのだ。テンプルは姿を消したルーイが心配で事件解決に集中したい気持ちを乱されるのだ。そこが私は面白かった。そして二人はそれぞれ真相に辿り着く。そんなわけで、邦題はなんか違った。
読了日:01月27日 著者:キャロン ネルソン ダグラス
 SDGs投資 資産運用しながら社会貢献 (朝日新書)の感想
SDGs投資 資産運用しながら社会貢献 (朝日新書)の感想
もやもやが晴れない。説く対象は誰なのか、SDGsに絡めた投資が真に地球と人類の為になるのか。SDGsの有用性を祖父の「論語と算盤」に結びつけるのはずるくないか。と、ひねくれて思ってしまう。だって、良いと思う企業を応援したいなら購買なり寄付なりクラファンなりでお金を託せばいい。そこで常に見返りを求める投資という金融商品である必要性は無い。投資は社会貢献の一形態と主張する著者をポジショントークだと思ってしまうのは、株式会社という仕組みが企業の健全を阻害する側面をも持っていることへの疑念と切り離せないからだ。
しかし、素直に受け取るなら、つまり実際に現代の資本主義社会においてより善きものへ資本を注いでいこうとするなら、コモンズの投資信託は相対的に考えて好いとは思う。例えばコモンズ30の投資先は日本国内の「真のグローバル企業」と位置づけている。公開された組入銘柄は有名大手企業が多く、商社、製造業、サービス業と多岐にわたる。カネを稼ぐ力に加えて、経営者の意識や社内外への姿勢、企業文化をも評価基準としている点に特徴がある。そういう視点を持っているファンドを、資産を預ける相手を決める基準の一つにするのはありかと。
読了日:01月23日 著者:渋澤健
 巨大津波は生態系をどう変えたか―生きものたちの東日本大震災 (ブルーバックス)の感想
巨大津波は生態系をどう変えたか―生きものたちの東日本大震災 (ブルーバックス)の感想
人間の生活が優先と断わりながら、リアルタイムで記録しておく重要性を著者は訴え、調査を続けた。自身の生活も大変な中、記録しておいていただいてほんとうにありがたい。津波により沿岸の風景も地形も変わってしまった。しかし元は砂浜、湿地、広葉樹林であった地を人間が水田や農地に改変してきたのだ。それにより野性生物の生息域が分断された。津波の塩分は生物の多くを死滅させたが、雨のたびに洗い流され、徐々に生物が現れる。農地跡に咲いたミズアオイの清しさ、儚さに胸を衝かれる。写真が美しいので、カラーで読むことをお勧めします。
『生態系保全の観点からは、人為的にクロマツを植えるよりも、海岸本来の姿である草原や広葉樹の低木林に戻ることが最も望ましいのだが、内陸に宅地や農地があることから、飛砂防止にすぐれたクロマツ林がどうしても必要とされるだろう。海岸に瓦礫を埋め立てて、そこに広葉樹を植えるという案までが「森づくり」として大きく宣伝される例も見受けられるが、再生途上にある砂浜や湿地を埋め立てることは、生態系を根本から破壊してしまうので論外だ』。
読了日:01月22日 著者:永幡 嘉之
 本の雑誌476号2023年2月号の感想
本の雑誌476号2023年2月号の感想
「本を買う!」という特集は、企画する側も読む側も確信犯だろう。『いつか読む本を買いなさい』。『積みなさい、天に届くまで』。これでもかと煽る煽る。しかし1カ月に費やす本代が70万円越えの事例とまでくると、頭の芯がすーっと醒めてゆくのがわかる。特殊な職業であったり、買うことが目的化していたり、いやさ、自身のキャパとかスタンスとか、わきまえるべき"分"に思考が至ったのだった。とはいえ、読みたいと思った本が絶版になる速度は考えるべきで、遠からず絶版になる本は見極めて買っておきたい。と宣言してあれこれポチっと…。
読了日:01月20日 著者:
 やっぱり、このゴミは収集できません ~ゴミ清掃員がやばい現場で考えたことの感想
やっぱり、このゴミは収集できません ~ゴミ清掃員がやばい現場で考えたことの感想
ゴミ清掃員は世界の真実を直視する仕事。その仕事を続ける著者はいい顔をしている。動画配信で稼ぐと聞く芸人の水膨れしたような顔とは大違いだ。ゴミ回収しながらいろいろ考えるそうで、1個のポリバケツから人生の成功に思いを馳せるとはもはや詩人か哲学者の域だ。パッカー車で圧縮することによって一般人には想像不能な事態が多々発生する。見るも触れるも耐え難いモノに日々直面する。恥ずかしい仕事と考える風潮が世間にあるゆえに、それはなかなか伝わってきづらい。金持ち松竹梅のゴミ事情など、軽妙かつ熱く伝えてくれる存在は貴重である。
読了日:01月20日 著者:滝沢 秀一
 路 (文春文庫)の感想
路 (文春文庫)の感想
日本と台湾をまたいだ群像。目まぐるしく変転する視点と時間が最後に繋がり、一本の台湾高速鉄道に集束させる手腕は見事だ。日本と台湾の歴史は近代以降、陰に陽に絡まり合っている。引き揚げの日、基隆で別れた『昨日までの隣人たち』は、今もやはり隣人であると思う。ありたいと思う。吉田修一の思い入れも相まって、優しい気持ちになる物語だった。騒音や匂い、温度湿度と台湾の街が繰り返し描かれるなかで、何か物足りない。そうか、私は自分の足で台湾行きたいし街を歩きたいし美味しいもの食べたいし温泉入りたいし台湾高鉄に乗りたいのだ。
読了日:01月18日 著者:吉田 修一
 読書の森へ 本の道しるべ (NHKテキスト)の感想
読書の森へ 本の道しるべ (NHKテキスト)の感想
角田光代、福岡伸一、ヤマザキマリでもうお腹いっぱい。好きな作家の本棚を眺めるってなんて悦楽だろう。その人が大切にしている本、ルーツとなる作家は、必ず私にも響く気がする。知りたい。読みたい。そして絶版。「祖国地球」みたいに番組をきっかけに再版してくれないかしら。テレビは再生を一時停止して、写真はピンボケに目をすがめて、何の本があるか、どんな並べ方をしているか隅から隅まで眺め渡し、読みたい本の拾い出しと理想の本棚設計に余念がない。やっぱり本棚は重厚なのが良いなとか地震対策に造り付けで深めが良いとか。ああ至福。
読了日:01月17日 著者:角田 光代,福岡 伸一,ヤマザキマリ,町田 樹,平野 レミ,堀川 理万子,鹿島 茂,Aマッソ・加納
 人類が消えた世界の感想
人類が消えた世界の感想
突如地球上から人類が消えたら、地球は人類が誕生して経た変化を逆回しに復元するか。その糸口となるいくつかの事象。「すずめの戸締り」の"人の手で元に戻して"が幾度も思い出される。人の力で元に戻すことなど、どれひとつできやしない。ただ自然の持つレジリエンスが似て非なる均衡を見つけるだけなのだ。この本が出た直後の東日本大震災、原発事故後の福島に、人が突如いなくなった地を日本人は既に知っているではないか。湿地に還るマンハッタンが感傷を帯びて描かれているようで苛立つ。人間あってこその地球みたいな考え方は好かない。
読了日:01月17日 著者:アラン・ワイズマン
 陰翳礼讃 (角川ソフィア文庫)の感想
陰翳礼讃 (角川ソフィア文庫)の感想
かの有名な「陰翳礼讃」はたったこれだけのエッセイなのだ。文豪の有名な著作という摺り込みへのびびりっぷりに我ながら驚いた。明治からこちらを眺め渡すような他のエッセイも素敵に変態で楽しい。早く読めばよかった。この「陰翳礼讃」を私は宿で読んだ。現代へも続く欧米流と和風の綱引きは、この宿の障子を用いた間接照明や、落とした明かりに映える蒔絵風の椀を見るに、和のほうへ傾きつつあると言えるだろうか。照明や電飾の過剰を憂い、些事にもこだわる氏らの言は、私にも肯ずるところが多く、たぶん大事なのだと思う。この人好きだな。
旅や宿屋についての文章に、琴平のとらやが出てくる。『間口の長い店が街道に面していて、土間に入ると上り框の正面に幅の広い階段があり、二階の欄干からは町の人通りが見おろせるといった風の』宿だった名残は外観に見受けられたけれど、私が通い始めた頃にはただのうどん屋だった。そしてその由緒正しい建物も、今年の正月には解体されているのを見た。惜しい。あまりに惜しい。
読了日:01月16日 著者:谷崎 潤一郎
 「いい会社」ってどんな会社ですか? 社員の幸せについて語り合おうの感想
「いい会社」ってどんな会社ですか? 社員の幸せについて語り合おうの感想
会議で若い社員の昇給を主張していて感じたのは、経営者の考え方のブレである。私が様々に資料を用意して説得して、概ね賛同に傾いても、実際の数字を見ると迷う。『利益は残ったウンチにすぎない』。塚越氏や青野さんも散々迷ったはずだ。しかし検討と試行錯誤の末に自分の中に軸が持てれば、こんなに鮮やかに踏み切れるのだと目を見張った。性善説に立って社内制度を設計運営することは難しい。つい疑いの芽が出る。しかし疑い始めれば効率も人の心持ちも悪くなることは行政のやり方を見れば瞭然だ。自信をもって、思い切りよくいこう。
読了日:01月12日 著者:塚越 寛
 文学こそ最高の教養である (光文社新書)の感想
文学こそ最高の教養である (光文社新書)の感想
古典文学という領域の、自分の中での置き所を決めあぐねている。現代の作品や思想の前提となる古典をよむことは、今年の目標である「読書の深度を上げる」には有効な手段だ。新訳古典文庫は読みやすく、またこのような企画によって背景や作者の思想を知って読む利は大きい。しかし翻訳が読みやすい=理解しやすいではないのは翻訳者自ら語るとおりであり、限られた時間と他への興味との折り合いをつけるべく、始終唸りながら読んだ。落としどころはなんとなく見つかったので、それでOKとする。つまみ食い万歳、解れば良し、わからなくても良し。
読了日:01月09日 著者:駒井稔,光文社古典新訳文庫編集部
 現代中国・台湾ミステリビギナーズガイドブック (風狂推理新書)の感想
現代中国・台湾ミステリビギナーズガイドブック (風狂推理新書)の感想
ミステリはパズルだと思う。事件の大小不法合法を問わず、作者の企みをためつすがめつ、“真実”を得てすっきりする。ミス研は読んで楽しいを超えて、古今東西のミステリをトリックやパターンで類型化したり、整合性をつついて皆で盛り上がる場所なのね。座談会の皆さん、まあよく読んでおられること。私も所属したかったような、所属しなくてよかったような。いずれにせよ中国と台湾のミステリ、SFに負けず盛りあがって(翻訳されて)ほしい。あと、綾辻不由美が売れっ子マジシャンの犯人て、その筋から怒られなかったんですかね?
読了日:01月08日 著者:白樺香澄
 虚擬街頭漂流記 (文春e-book)の感想
虚擬街頭漂流記 (文春e-book)の感想
現代華文推理系列で読んだ籠物先生の長編ミステリ。『見るからに真実のような、そして触れてみても真実としか思えない、そして聞こえる音も真実のような』仮想現実世界における殺人。今よりIT技術が進んだSFテイスト、台北にある西門町の繁華を再現する設定も、伏線も、意欲的で好かった。人物の造形と翻訳にだいぶ難があるけれど、国を問わず若いミステリにはあるレベルだし、もっと読みたくなった。もっと人物が膨らめば東野圭吾みたいな感じになろうか。あるいは少し視点を引いて、ミステリアスな作風もいいなあ。そういや、あの人影ってさ…
読了日:01月08日 著者:寵物先生
 ぶらりユーラシア: 列車を乗り継ぎ大陸横断、72歳ひとり旅の感想
ぶらりユーラシア: 列車を乗り継ぎ大陸横断、72歳ひとり旅の感想
ロシア:ユジノ・サハリンスクからポルトガル:ポルトまで、大陸を横断する鉄道の旅。著者は写真のプロである。鉄道の進む速度で移り変わってゆく風土や文化のさまを眺めるのは楽しかった。イラン、トルコは特に、垣間見る豊かさに溜息が漏れる。美しい。行きたい。道中、国境をまたぐ鉄道は一本には繋がっておらず、かつてのオリエント急行の路線すら今は分断され、列車をいくつも乗り継がなければならないという。国家と国家の間の事情で、大地は繋がっているのに寂しいものだ。飛行機では見えないものを見られる鉄道の旅、素晴らしいと思った。
シベリアの夏。湿地帯の大地には果てしなく草木が生い茂り、水面には青空と白雲を映す、なんとも清涼な景色。ずっと寒くて凍っているという自分の頑なな思い込みにびっくりする。ウズベキスタン・ゼラフシャン川。山岳地帯から流れ下った雪解け水は、乾燥した大地に作物をつくるための灌漑用水として右に左に奪われ、そのうちに川そのものが地表から消えてしまうという。乾燥地帯の自然は、集めて早し最上川な日本の常識を引っ繰り返してくれる。
読了日:01月04日 著者:大木茂
注: は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。
積読本の棚が本に申し訳ないような様相になってきた。
本が二列になると後ろの本の背表紙が見えなくてもやもやするのは私なのに。
<今月のデータ>
購入18冊、購入費用14,992円。
読了14冊。
積読本332冊(うちKindle本157冊、Honto本4冊)。

 黒猫ルーイ、名探偵になる (ランダムハウス講談社文庫)の感想
黒猫ルーイ、名探偵になる (ランダムハウス講談社文庫)の感想元気でキラキラした女性テンプルが主人公。相棒は堂々たる体躯の黒猫ルーイ…と言いたいところだが、ルーイは喋るでも主人公の腕を咥えてナビゲートするでもなく、仮にルーイの独白パートを除いても、最後のメッセージを除いてすら普通にミステリの起承転結が成立している。しかしルーイはテンプルを心配に思っていて、助けるために奔走した挙句収容されてしまうのだ。テンプルは姿を消したルーイが心配で事件解決に集中したい気持ちを乱されるのだ。そこが私は面白かった。そして二人はそれぞれ真相に辿り着く。そんなわけで、邦題はなんか違った。
読了日:01月27日 著者:キャロン ネルソン ダグラス

 SDGs投資 資産運用しながら社会貢献 (朝日新書)の感想
SDGs投資 資産運用しながら社会貢献 (朝日新書)の感想もやもやが晴れない。説く対象は誰なのか、SDGsに絡めた投資が真に地球と人類の為になるのか。SDGsの有用性を祖父の「論語と算盤」に結びつけるのはずるくないか。と、ひねくれて思ってしまう。だって、良いと思う企業を応援したいなら購買なり寄付なりクラファンなりでお金を託せばいい。そこで常に見返りを求める投資という金融商品である必要性は無い。投資は社会貢献の一形態と主張する著者をポジショントークだと思ってしまうのは、株式会社という仕組みが企業の健全を阻害する側面をも持っていることへの疑念と切り離せないからだ。
しかし、素直に受け取るなら、つまり実際に現代の資本主義社会においてより善きものへ資本を注いでいこうとするなら、コモンズの投資信託は相対的に考えて好いとは思う。例えばコモンズ30の投資先は日本国内の「真のグローバル企業」と位置づけている。公開された組入銘柄は有名大手企業が多く、商社、製造業、サービス業と多岐にわたる。カネを稼ぐ力に加えて、経営者の意識や社内外への姿勢、企業文化をも評価基準としている点に特徴がある。そういう視点を持っているファンドを、資産を預ける相手を決める基準の一つにするのはありかと。
読了日:01月23日 著者:渋澤健

 巨大津波は生態系をどう変えたか―生きものたちの東日本大震災 (ブルーバックス)の感想
巨大津波は生態系をどう変えたか―生きものたちの東日本大震災 (ブルーバックス)の感想人間の生活が優先と断わりながら、リアルタイムで記録しておく重要性を著者は訴え、調査を続けた。自身の生活も大変な中、記録しておいていただいてほんとうにありがたい。津波により沿岸の風景も地形も変わってしまった。しかし元は砂浜、湿地、広葉樹林であった地を人間が水田や農地に改変してきたのだ。それにより野性生物の生息域が分断された。津波の塩分は生物の多くを死滅させたが、雨のたびに洗い流され、徐々に生物が現れる。農地跡に咲いたミズアオイの清しさ、儚さに胸を衝かれる。写真が美しいので、カラーで読むことをお勧めします。
『生態系保全の観点からは、人為的にクロマツを植えるよりも、海岸本来の姿である草原や広葉樹の低木林に戻ることが最も望ましいのだが、内陸に宅地や農地があることから、飛砂防止にすぐれたクロマツ林がどうしても必要とされるだろう。海岸に瓦礫を埋め立てて、そこに広葉樹を植えるという案までが「森づくり」として大きく宣伝される例も見受けられるが、再生途上にある砂浜や湿地を埋め立てることは、生態系を根本から破壊してしまうので論外だ』。
読了日:01月22日 著者:永幡 嘉之

 本の雑誌476号2023年2月号の感想
本の雑誌476号2023年2月号の感想「本を買う!」という特集は、企画する側も読む側も確信犯だろう。『いつか読む本を買いなさい』。『積みなさい、天に届くまで』。これでもかと煽る煽る。しかし1カ月に費やす本代が70万円越えの事例とまでくると、頭の芯がすーっと醒めてゆくのがわかる。特殊な職業であったり、買うことが目的化していたり、いやさ、自身のキャパとかスタンスとか、わきまえるべき"分"に思考が至ったのだった。とはいえ、読みたいと思った本が絶版になる速度は考えるべきで、遠からず絶版になる本は見極めて買っておきたい。と宣言してあれこれポチっと…。
読了日:01月20日 著者:
 やっぱり、このゴミは収集できません ~ゴミ清掃員がやばい現場で考えたことの感想
やっぱり、このゴミは収集できません ~ゴミ清掃員がやばい現場で考えたことの感想ゴミ清掃員は世界の真実を直視する仕事。その仕事を続ける著者はいい顔をしている。動画配信で稼ぐと聞く芸人の水膨れしたような顔とは大違いだ。ゴミ回収しながらいろいろ考えるそうで、1個のポリバケツから人生の成功に思いを馳せるとはもはや詩人か哲学者の域だ。パッカー車で圧縮することによって一般人には想像不能な事態が多々発生する。見るも触れるも耐え難いモノに日々直面する。恥ずかしい仕事と考える風潮が世間にあるゆえに、それはなかなか伝わってきづらい。金持ち松竹梅のゴミ事情など、軽妙かつ熱く伝えてくれる存在は貴重である。
読了日:01月20日 著者:滝沢 秀一

 路 (文春文庫)の感想
路 (文春文庫)の感想日本と台湾をまたいだ群像。目まぐるしく変転する視点と時間が最後に繋がり、一本の台湾高速鉄道に集束させる手腕は見事だ。日本と台湾の歴史は近代以降、陰に陽に絡まり合っている。引き揚げの日、基隆で別れた『昨日までの隣人たち』は、今もやはり隣人であると思う。ありたいと思う。吉田修一の思い入れも相まって、優しい気持ちになる物語だった。騒音や匂い、温度湿度と台湾の街が繰り返し描かれるなかで、何か物足りない。そうか、私は自分の足で台湾行きたいし街を歩きたいし美味しいもの食べたいし温泉入りたいし台湾高鉄に乗りたいのだ。
読了日:01月18日 著者:吉田 修一

 読書の森へ 本の道しるべ (NHKテキスト)の感想
読書の森へ 本の道しるべ (NHKテキスト)の感想角田光代、福岡伸一、ヤマザキマリでもうお腹いっぱい。好きな作家の本棚を眺めるってなんて悦楽だろう。その人が大切にしている本、ルーツとなる作家は、必ず私にも響く気がする。知りたい。読みたい。そして絶版。「祖国地球」みたいに番組をきっかけに再版してくれないかしら。テレビは再生を一時停止して、写真はピンボケに目をすがめて、何の本があるか、どんな並べ方をしているか隅から隅まで眺め渡し、読みたい本の拾い出しと理想の本棚設計に余念がない。やっぱり本棚は重厚なのが良いなとか地震対策に造り付けで深めが良いとか。ああ至福。
読了日:01月17日 著者:角田 光代,福岡 伸一,ヤマザキマリ,町田 樹,平野 レミ,堀川 理万子,鹿島 茂,Aマッソ・加納
 人類が消えた世界の感想
人類が消えた世界の感想突如地球上から人類が消えたら、地球は人類が誕生して経た変化を逆回しに復元するか。その糸口となるいくつかの事象。「すずめの戸締り」の"人の手で元に戻して"が幾度も思い出される。人の力で元に戻すことなど、どれひとつできやしない。ただ自然の持つレジリエンスが似て非なる均衡を見つけるだけなのだ。この本が出た直後の東日本大震災、原発事故後の福島に、人が突如いなくなった地を日本人は既に知っているではないか。湿地に還るマンハッタンが感傷を帯びて描かれているようで苛立つ。人間あってこその地球みたいな考え方は好かない。
読了日:01月17日 著者:アラン・ワイズマン
 陰翳礼讃 (角川ソフィア文庫)の感想
陰翳礼讃 (角川ソフィア文庫)の感想かの有名な「陰翳礼讃」はたったこれだけのエッセイなのだ。文豪の有名な著作という摺り込みへのびびりっぷりに我ながら驚いた。明治からこちらを眺め渡すような他のエッセイも素敵に変態で楽しい。早く読めばよかった。この「陰翳礼讃」を私は宿で読んだ。現代へも続く欧米流と和風の綱引きは、この宿の障子を用いた間接照明や、落とした明かりに映える蒔絵風の椀を見るに、和のほうへ傾きつつあると言えるだろうか。照明や電飾の過剰を憂い、些事にもこだわる氏らの言は、私にも肯ずるところが多く、たぶん大事なのだと思う。この人好きだな。
旅や宿屋についての文章に、琴平のとらやが出てくる。『間口の長い店が街道に面していて、土間に入ると上り框の正面に幅の広い階段があり、二階の欄干からは町の人通りが見おろせるといった風の』宿だった名残は外観に見受けられたけれど、私が通い始めた頃にはただのうどん屋だった。そしてその由緒正しい建物も、今年の正月には解体されているのを見た。惜しい。あまりに惜しい。
読了日:01月16日 著者:谷崎 潤一郎

 「いい会社」ってどんな会社ですか? 社員の幸せについて語り合おうの感想
「いい会社」ってどんな会社ですか? 社員の幸せについて語り合おうの感想会議で若い社員の昇給を主張していて感じたのは、経営者の考え方のブレである。私が様々に資料を用意して説得して、概ね賛同に傾いても、実際の数字を見ると迷う。『利益は残ったウンチにすぎない』。塚越氏や青野さんも散々迷ったはずだ。しかし検討と試行錯誤の末に自分の中に軸が持てれば、こんなに鮮やかに踏み切れるのだと目を見張った。性善説に立って社内制度を設計運営することは難しい。つい疑いの芽が出る。しかし疑い始めれば効率も人の心持ちも悪くなることは行政のやり方を見れば瞭然だ。自信をもって、思い切りよくいこう。
読了日:01月12日 著者:塚越 寛

 文学こそ最高の教養である (光文社新書)の感想
文学こそ最高の教養である (光文社新書)の感想古典文学という領域の、自分の中での置き所を決めあぐねている。現代の作品や思想の前提となる古典をよむことは、今年の目標である「読書の深度を上げる」には有効な手段だ。新訳古典文庫は読みやすく、またこのような企画によって背景や作者の思想を知って読む利は大きい。しかし翻訳が読みやすい=理解しやすいではないのは翻訳者自ら語るとおりであり、限られた時間と他への興味との折り合いをつけるべく、始終唸りながら読んだ。落としどころはなんとなく見つかったので、それでOKとする。つまみ食い万歳、解れば良し、わからなくても良し。
読了日:01月09日 著者:駒井稔,光文社古典新訳文庫編集部

 現代中国・台湾ミステリビギナーズガイドブック (風狂推理新書)の感想
現代中国・台湾ミステリビギナーズガイドブック (風狂推理新書)の感想ミステリはパズルだと思う。事件の大小不法合法を問わず、作者の企みをためつすがめつ、“真実”を得てすっきりする。ミス研は読んで楽しいを超えて、古今東西のミステリをトリックやパターンで類型化したり、整合性をつついて皆で盛り上がる場所なのね。座談会の皆さん、まあよく読んでおられること。私も所属したかったような、所属しなくてよかったような。いずれにせよ中国と台湾のミステリ、SFに負けず盛りあがって(翻訳されて)ほしい。あと、綾辻不由美が売れっ子マジシャンの犯人て、その筋から怒られなかったんですかね?
読了日:01月08日 著者:白樺香澄

 虚擬街頭漂流記 (文春e-book)の感想
虚擬街頭漂流記 (文春e-book)の感想現代華文推理系列で読んだ籠物先生の長編ミステリ。『見るからに真実のような、そして触れてみても真実としか思えない、そして聞こえる音も真実のような』仮想現実世界における殺人。今よりIT技術が進んだSFテイスト、台北にある西門町の繁華を再現する設定も、伏線も、意欲的で好かった。人物の造形と翻訳にだいぶ難があるけれど、国を問わず若いミステリにはあるレベルだし、もっと読みたくなった。もっと人物が膨らめば東野圭吾みたいな感じになろうか。あるいは少し視点を引いて、ミステリアスな作風もいいなあ。そういや、あの人影ってさ…
読了日:01月08日 著者:寵物先生

 ぶらりユーラシア: 列車を乗り継ぎ大陸横断、72歳ひとり旅の感想
ぶらりユーラシア: 列車を乗り継ぎ大陸横断、72歳ひとり旅の感想ロシア:ユジノ・サハリンスクからポルトガル:ポルトまで、大陸を横断する鉄道の旅。著者は写真のプロである。鉄道の進む速度で移り変わってゆく風土や文化のさまを眺めるのは楽しかった。イラン、トルコは特に、垣間見る豊かさに溜息が漏れる。美しい。行きたい。道中、国境をまたぐ鉄道は一本には繋がっておらず、かつてのオリエント急行の路線すら今は分断され、列車をいくつも乗り継がなければならないという。国家と国家の間の事情で、大地は繋がっているのに寂しいものだ。飛行機では見えないものを見られる鉄道の旅、素晴らしいと思った。
シベリアの夏。湿地帯の大地には果てしなく草木が生い茂り、水面には青空と白雲を映す、なんとも清涼な景色。ずっと寒くて凍っているという自分の頑なな思い込みにびっくりする。ウズベキスタン・ゼラフシャン川。山岳地帯から流れ下った雪解け水は、乾燥した大地に作物をつくるための灌漑用水として右に左に奪われ、そのうちに川そのものが地表から消えてしまうという。乾燥地帯の自然は、集めて早し最上川な日本の常識を引っ繰り返してくれる。
読了日:01月04日 著者:大木茂
注:
 は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。 2023年01月07日
2022年の総括
2022年、読んだ本の冊数は183冊。
購入費用198,691円。
積読本329冊(うちKindle本168冊、Honto本4冊)。
ヤマザキマリのNHK「読書の森へ 本の道しるべ」を呑みながら観たあと、
「これではいかん!」と急激に奮起した。
マリさん曰く、『読書は給油タンク、本は「ガソリン」』。
いわば燃焼効率の高い読書をせねばと思い立ったのだった。
目標は「読書の深度を上げる」。
セイゴオさんの網の論理で言えば、同じあたりに緩い結び目をやたらつくるより、
強靭な結び目をひとつつくるほうが、すっきりして美しい智の網になるだろう。
疲れている時だってあるから、月に1冊でいいから、
古典、智の源と称される本に取り組むことを目標にする。
先達が薦めて気になった本はとりあえず買う。
読めなかったら積読の山に戻すなり、諦めるなりすればいいのだ。
打率5割でも得るものは大きい。
2023年も良い本に出会えますように。


2022年、私に影響を与えた本たち。
<人間の業の深さよ>
 戦争は女の顔をしていない スヴェトラーナ アレクシエーヴィチ
戦争は女の顔をしていない スヴェトラーナ アレクシエーヴィチ
 マーシャル、父の戦場: ある日本兵の日記をめぐる歴史実践 大川 史織
マーシャル、父の戦場: ある日本兵の日記をめぐる歴史実践 大川 史織
 牙: アフリカゾウの「密猟組織」を追って 三浦 英之
牙: アフリカゾウの「密猟組織」を追って 三浦 英之

 Humankind 希望の歴史 人類が善き未来をつくるための18章 ルトガー・ブレグマン
Humankind 希望の歴史 人類が善き未来をつくるための18章 ルトガー・ブレグマン
<それでも世界は美しい>
 梅里雪山(メイリーシュエシャン)十七人の友を探して (ヤマケイ文庫) 小林尚礼
梅里雪山(メイリーシュエシャン)十七人の友を探して (ヤマケイ文庫) 小林尚礼
 アルハンブラ物語 (講談社文庫 あ 31-1) ワシントン・アービング
アルハンブラ物語 (講談社文庫 あ 31-1) ワシントン・アービング
 サマルカンドへ 〔ロング・マルシュ 長く歩く 2〕 ベルナール・オリヴィエ
サマルカンドへ 〔ロング・マルシュ 長く歩く 2〕 ベルナール・オリヴィエ
<真実を求める姿勢にブラボー!>
 エネルギーをめぐる旅――文明の歴史と私たちの未来 古舘 恒介
エネルギーをめぐる旅――文明の歴史と私たちの未来 古舘 恒介
 土 地球最後のナゾ 100億人を養う土壌を求めて (光文社新書) 藤井 一至
土 地球最後のナゾ 100億人を養う土壌を求めて (光文社新書) 藤井 一至
 塩の道 (講談社学術文庫) 宮本 常一
塩の道 (講談社学術文庫) 宮本 常一
 You are what you read あなたは読んだものに他ならない 服部文祥
You are what you read あなたは読んだものに他ならない 服部文祥
<もっと小説を読もう>

 プロジェクト・ヘイル・メアリー アンディ・ウィアー
プロジェクト・ヘイル・メアリー アンディ・ウィアー
 白の闇 (河出文庫) ジョゼ・サラマーゴ
白の闇 (河出文庫) ジョゼ・サラマーゴ
 ザリガニの鳴くところ ディーリア・オーエンズ
ザリガニの鳴くところ ディーリア・オーエンズ
 鷗外の怪談 永井 愛
鷗外の怪談 永井 愛
購入費用198,691円。
積読本329冊(うちKindle本168冊、Honto本4冊)。
ヤマザキマリのNHK「読書の森へ 本の道しるべ」を呑みながら観たあと、
「これではいかん!」と急激に奮起した。
マリさん曰く、『読書は給油タンク、本は「ガソリン」』。
いわば燃焼効率の高い読書をせねばと思い立ったのだった。
目標は「読書の深度を上げる」。
セイゴオさんの網の論理で言えば、同じあたりに緩い結び目をやたらつくるより、
強靭な結び目をひとつつくるほうが、すっきりして美しい智の網になるだろう。
疲れている時だってあるから、月に1冊でいいから、
古典、智の源と称される本に取り組むことを目標にする。
先達が薦めて気になった本はとりあえず買う。
読めなかったら積読の山に戻すなり、諦めるなりすればいいのだ。
打率5割でも得るものは大きい。
2023年も良い本に出会えますように。

2022年、私に影響を与えた本たち。
<人間の業の深さよ>
 戦争は女の顔をしていない スヴェトラーナ アレクシエーヴィチ
戦争は女の顔をしていない スヴェトラーナ アレクシエーヴィチ マーシャル、父の戦場: ある日本兵の日記をめぐる歴史実践 大川 史織
マーシャル、父の戦場: ある日本兵の日記をめぐる歴史実践 大川 史織 牙: アフリカゾウの「密猟組織」を追って 三浦 英之
牙: アフリカゾウの「密猟組織」を追って 三浦 英之
 Humankind 希望の歴史 人類が善き未来をつくるための18章 ルトガー・ブレグマン
Humankind 希望の歴史 人類が善き未来をつくるための18章 ルトガー・ブレグマン<それでも世界は美しい>
 梅里雪山(メイリーシュエシャン)十七人の友を探して (ヤマケイ文庫) 小林尚礼
梅里雪山(メイリーシュエシャン)十七人の友を探して (ヤマケイ文庫) 小林尚礼 アルハンブラ物語 (講談社文庫 あ 31-1) ワシントン・アービング
アルハンブラ物語 (講談社文庫 あ 31-1) ワシントン・アービング サマルカンドへ 〔ロング・マルシュ 長く歩く 2〕 ベルナール・オリヴィエ
サマルカンドへ 〔ロング・マルシュ 長く歩く 2〕 ベルナール・オリヴィエ<真実を求める姿勢にブラボー!>
 エネルギーをめぐる旅――文明の歴史と私たちの未来 古舘 恒介
エネルギーをめぐる旅――文明の歴史と私たちの未来 古舘 恒介 土 地球最後のナゾ 100億人を養う土壌を求めて (光文社新書) 藤井 一至
土 地球最後のナゾ 100億人を養う土壌を求めて (光文社新書) 藤井 一至 塩の道 (講談社学術文庫) 宮本 常一
塩の道 (講談社学術文庫) 宮本 常一 You are what you read あなたは読んだものに他ならない 服部文祥
You are what you read あなたは読んだものに他ならない 服部文祥<もっと小説を読もう>

 プロジェクト・ヘイル・メアリー アンディ・ウィアー
プロジェクト・ヘイル・メアリー アンディ・ウィアー 白の闇 (河出文庫) ジョゼ・サラマーゴ
白の闇 (河出文庫) ジョゼ・サラマーゴ ザリガニの鳴くところ ディーリア・オーエンズ
ザリガニの鳴くところ ディーリア・オーエンズ 鷗外の怪談 永井 愛
鷗外の怪談 永井 愛2023年01月05日
2022年12月の記録
2011年からこちら、その年に読んだ本ベスト20をつくっている。
スクショ保存してあるのを見返すと興味深い。
記憶にほとんど残っていない本がベスト3に入っていることもざらなら、
ベスト20のうち今も心のどこかで活きていると感じる本は5冊がいいところだったりする。
なにが根を生やし育つかわからないのだから、なんでも植えて(読んで)みるのが良いのだ。
とはいえ、私が気になった全ての本を読む時間は、私の人生にはもう無い。
なのに今月もたくさん買い込んだ。そろそろ読む本を選びなさいよという話である。
ちなみに今年のベスト20はこちら

<今月のデータ>
購入24冊、購入費用18,635円。
読了16冊。
積読本329冊(うちKindle本168冊、Honto本4冊)。

12月の読書メーター
読んだ本の数:16
 翻訳者による海外文学ブックガイド BOOKMARKの感想
翻訳者による海外文学ブックガイド BOOKMARKの感想
もとはフリーペーパー企画。表紙にあるとおりながら、小説を翻訳した本人による紹介というところがいちばんの魅力です。あと、各巻頭のエッセイは国内の作家さんによるもので、こちらもそうそうたる面々で嬉しい。若い読書が想定されているとのことでヤングアダルトや少年文庫も多いなか、大人向けの本格ものもたくさんあって鼻息荒く物色した。惜しむらくは、翻訳ものあるあるで、絶版の嵐。。。刊行されて数年で文庫にもならず消えてしまうのは余りにもったいないことだ。悔しい。ていうか早く読め私。次作はタイムリーに読みます。
読了日:12月30日 著者:金原 瑞人,三辺 律子
 僕らはソマリアギャングと夢を語る――「テロリストではない未来」をつくる挑戦の感想
僕らはソマリアギャングと夢を語る――「テロリストではない未来」をつくる挑戦の感想
永井陽右氏の活動の始まり。なぜ、国境なき医師団すら撤退したソマリアでなければならなかったか、という問いは既に無意味だろう。紛争解決の専門家の忠告よりも、渡航する度に得る手ごたえを糧に彼は前に進んだ。『ギャングと話せば話すほど、同じ時間を共有すればするほど、彼らが僕らと何も変わらない存在だと気づく』。信じた活動を10年続けた先に経験もスキルも学位も得た。彼は行けるところまで行くのだろう。自分が『人間としての責任』と認識する活動にどうすれば無関心な人たちを巻き込んでいけるのか、日々考える。真面目な人なのだ。
彼の論理では、ソマリアは世界でもっとも支援が必要な場所である。しかしそこは世界で最も死に近い場所である。死なずに続けられているのは幸運、だろう。内田先生との対談記事で、命を大事にと語りかける内田先生の言葉をスルーしているように読めるのが気にかかった。編集ならよいのだが。社会的な意義が大きいのは理解できる。ただ、殉教者にはなってほしくないと私も願っている。世界には、彼と同じように危険な地で活動に邁進する仲間がたくさんいるのだという。彼らや、ソマリアの仲間こそが、彼にとってのリアルなのだろうな。
知識もスキルも無い者が紛争地に行くべきではない。それが"常識的な"考え方だ。しかしそれに反して飛び込んでいく者たちがいて、私はそれを無謀と切って捨てるべきかと考え始める。そこには、人間が生きているのだ。例えば国内の活動で、政府も行政でもできないことを民間の有志が個人としてできる範囲のことをやっていくように、そこに人間が生きている限り、紛争地にも政府やNGOにはできないが個人にはできることがある、という考え方はできる。紛争自体は即時解決しなくても、何人かに生き延びる人生を生むことはできた、それが動力になる。
読了日:12月28日 著者:永井陽右
 その名にちなんで (新潮文庫)の感想
その名にちなんで (新潮文庫)の感想
物語を読み終えて、ほっと息を吐いた。家族2世代の歴史の物理的時間は40年もない。ただ彼らの綿々と抱える想いが重たいのだ。インド人が家族を単位に考えるのに対し、アメリカ人は個人を単位に考える。『アメリカというところは、何事も行き当たりばったりで、真実味がない』。インドからアメリカに移り住んだ一世が物事の捉え方の違いに戸惑い、一世同士で伴侶を見つけるのに対し、アメリカで生まれた二世は段違いにアメリカナイズされた考え方をする。しかし親親戚も自身の外見も完璧にベンガルである彼らの苦悩は、一世のものとは全く異なる。
母アショケはアメリカに渡った当初、家に引きこもりがちで、ベンガルの友人を得た後にインドの親戚のように招きもてなし合う関係を築いた。一方ゴーゴリたちは学校や職場で知り合うアメリカ人と集まって飲食や議論を共にするが、同じ賑やかなパーティーでもその本質は真逆だ。一見きらびやかなアメリカで、自身の中のインドとの折り合いをどこでつけるか、どちらを選ぶか、さらに異世界を選ぶか、その入り交じり具合も人によってほんとうに違っているのだということが、3代遡ってもみな日本生まれが当たり前の日常にいる私にはずっしりときた。
読了日:12月27日 著者:ジュンパ ラヒリ
 アラビア遊牧民 (講談社文庫)の感想
アラビア遊牧民 (講談社文庫)の感想
1965年のサウジアラビア。ベドウィンの人々や生活、ラクダやスカラベの観察も興味深い。さて、アラビア遊牧民が"見返りを求めず"旅人を歓待する話、その真実は「海老で鯛を釣る」慣習であるという。食事や接待それ自体のお礼は絶対に受け取らないが、その後は見返りをもっとよこせという態度に豹変する。不確実な善意に頼っていては死んでしまう土地、それは厳しい自然を指すのではなく、歴史的に侵略と強奪が繰り返された土地ゆえに根付いた、他人を信用しないことを前提にした民族の集積知であるという考え方は、胸に刻みつけたい。
読了日:12月27日 著者:本多勝一
 私の本棚 (新潮文庫)の感想
私の本棚 (新潮文庫)の感想
クリスマスイヴを小野さんのエッセイで過ごす。いやー、寄稿者の人選も好いし、本と本棚の話って熱いよな。本が身の周りに増えていくときの現象や、念願の本棚を手に入れて気づく真実はわりあい似ている。でもそこから導く在り様は人それぞれに多様だ。私は私がいつか手に入れる本棚の理想図を描きながら、本棚は読んだ本の背中でその人の姿を、積読本の山でその人の生きる望みを顕わすのだから、堂々といつも目に入るように手に取れるように置こうと決意した。今年の読書の締めくくりとしてふさわしかった。まだ読むけど。
今年の一箱古本市でお隣のブースになった方が、古書然とした本を並べておられたので、本職(古書店)の方ですかとお訊きしたら、「終活です」とお答えになったのが忘れられない。若い頃に大切に読んだ本も老眼が入れば読むものではなくもはや思い出であり、喜んでもらってくれるあてもない。1冊もらい受けようにもこちらも老眼に差し掛かる身で、当時の活字の小ささに怖じた。明日は我が身。溜め込むほど後が大変になるのは自明。それでも本にまつわる全ての記憶と、集めた本への執着、本を読む自分への希望は愛おしい。
読了日:12月25日 著者:
 豆腐屋の四季―ある青春の記録 (講談社文庫)の感想
豆腐屋の四季―ある青春の記録 (講談社文庫)の感想
豆腐屋を継いだ著者は、朝日歌壇に投稿する歌人である。その縁でエッセイもものする。決して余裕のない生活の中で、暮らしに根差した想いたちは、夜業に差す月の光、早暁の冴え冴えとした空気、極寒に大豆を絞る湯気の中にありありと立ちのぼる。生活詠と呼ぶそうだ。俳句を趣味にしていた亡き祖母を想う。遺品からはできた句を書き留め添削したノート、メモ綴じ、裏紙の類が膨大に出てきた。著者と同じ、無学な自営の妻だった。だからこそこの記を愛おしく思うのかもしれない。草木花歳時記数冊と広辞苑のような厚さの大歳時記は私が貰い受けた。
読了日:12月23日 著者:松下 竜一
 小説 すずめの戸締まり (角川文庫)の感想
小説 すずめの戸締まり (角川文庫)の感想
映画という表現方法を持つ新海誠が、なぜ同時進行で小説を書く必要があったかと訝しみつつ読んだ。理由はあとがきにあった。それはそれで納得である。視覚的な描写、静/動のメリハリの効いた描写の多い小説である。ダイジンの造形はわかりやすいけれど、その役割を知って読み返すとずるい。扉があるのは、かつて人間の活動が盛んだった場所であるようだ。『ひとのてで もとにもどして』。黒く塗りつぶされた3月11日。当事者でないからこそ、それを忘れかけていること、忘れてはいけないと自らに警告する術を、私たちは望んでいるのだろうか。
天災による被害という意味では、阪神大震災も同じはずだ。しかし、当時の私が哀しみや憤りのなんたるかも知らなかった年頃であったこと、東日本大震災の場合は地震と津波と、原発の人災が重なったことで、私にとっては太平洋戦争の敗戦に匹敵する重さで脳底に鎮座している。いつまでも割り切ることのできない出来事として抱えておきたい。
読了日:12月22日 著者:新海 誠
 日本の漁業が崩壊する本当の理由の感想
日本の漁業が崩壊する本当の理由の感想
これも日本ジリ貧案件。水産物生産量は世界では増えており、日本では減っている。魚種によって事情が違うし、外国との兼ね合いもあるが、主因は日本が科学的根拠に基づく分析・管理できずに乱獲する点である。例えば2011年の震災後、三陸沖の魚は増えた。人間が獲らなければ魚は繁殖し増える。しかしそれを豊漁と根こそぎ獲ってしまえば元の魚の減った海に戻るわけで。ならば養殖すればよいかといえば餌は高騰の一途。輸入すればよいかといえば円安で日本は買い負けし始めており、回転寿司屋が立ち行かなくなるのも時間の問題と予測してみる。
スーパーの鮮魚売り場で「ホッケ小さいな」「サンマ細いな」「高くなったな」は判るが、安く売られている魚が、旬だからではなく、不漁なのでしかたなく旬じゃないものや獲り頃よりまだ小さいものを獲ってきてるからだなんて、私は知らなかった。だから美味しくないのだと。海の生態系を破壊する底曳き網を規制するなどは国がするべきことだが、面倒なことはしたがらないのがお家芸。国民が現状や解決策を知り、世論を醸成して国を突き上げるしか、日本を変える方法はないのだろう。漁業にまつわる問題はそこらじゅうにあるようだ。読んで良かった。
とりあえず、メディアが今年は豊漁とか不漁とか高いとか安いとかだけ報道するのは害でしかない。もっとちゃんと取材してほんとうのところを知らしめていただきたい。
読了日:12月19日 著者:片野 歩
 アフリカ出身 サコ学長、日本を語るの感想
アフリカ出身 サコ学長、日本を語るの感想
自分の学生時代、その過ごし方を「あれで正しかったのだろうか」と私は時々思い返す。何か間違っていたから、本来得られたはずのものを逃して、いま見えない壁を越えられずにいるんじゃないかという気がずっとしていた。前半はサコ学長の来歴、後半は教育・教育システム論。サコ学長の現状概観を読むと、私は日本の教育システムが設計したとおりに正しく過ごしたとしか言えないことに驚いた。「良い子」だったんやなあ…と嘆息する。ならば、気づいた時点で若者に胸を張れる不良中年になるのが解決策じゃろなあ。今の若者は息苦しそうだもの。
サコ学長の学生時代を読みながら、多様性や異文化への理解は、直に接しないと絶対にわからないと痛感した。私は日本の教育の中で、小さい頃から「みんな同じ」「みんな平等」と教わってきた。私はうかつにも、高校生になっても大学生になっても文字どおり「人間は大同小異」だと思っていた節がある。でも実は、他人は皆能力も志向も違っていて、無限の方向性があって、手を伸ばして得るものなんだってことに気づいたのはほんとうに最近のことだ。
読了日:12月14日 著者:ウスビ・サコ
 体と心がラクになる「和」のウォーキング 芭蕉の“疲れない歩き方”でからだをゆるめて整える (祥伝社黄金文庫)の感想
体と心がラクになる「和」のウォーキング 芭蕉の“疲れない歩き方”でからだをゆるめて整える (祥伝社黄金文庫)の感想
安田先生の身体論×精神文化論とでも呼ぼうか。能やロルフィングの身体観に基づいた歩き方指南の本かと思いきや、日本人の身体の個性から話は古今の相撲における身体運用の違いへ、さらに「おくのほそ道」が"歌枕"を巡る歩き旅であったとの指摘、古典と現実を重ね合わせて楽しむ大名庭園の散歩法まで、安田先生のお話がいろいろ読めてお得。歳を取って能力に制限が加わることによってこそ、物事が新しく捉えられ、また興味深く感じることができる話が好きだが、元大相撲力士の一ノ矢さんも同意とか。歳を取ることが楽しみになってくる嬉しさよ。
読了日:12月12日 著者:安田登
 その農地、私が買います 高橋さん家の次女の乱の感想
その農地、私が買います 高橋さん家の次女の乱の感想
黒糖づくりや百姓、猟師など、現状を憂え、自身が信じたように行動する人たちが、ここには何人も出てくる。こういう動きを内田先生は希望と呼ぶのかな。農地付きの土地をなんとか買えないかと考えていた私にも参考になった(諦めた)。しかし後味は悪い。ここにはふたつ大きな問題があって、ひとつは農業を諦める人の土地売買の問題、ひとつは日本人らしい自治、日本的民主主義とは何かという問題である。妨害行為は違法だが、著者のやり方は褒められたもんじゃないとも私は思って、考え込んだ。唯一無二のお母さんの土がなんとか守られますように。
農地は農業従事者以外が買うことはできないし、買ったらそこには販売用の農作物をつくらなければならない。かといって農地転用した土地は宅地分の固定資産税を払えば自由になる訳ではなく、農作物をつくったり木を植えたりして住宅を建てずにいると指導される。これでは、放置か分譲住宅にするか太陽光パネルを敷き詰めるかしかないだろう。農地を農地として守る規制は大事だけれど、農地なり緑地なり他の方法でも、土のまま繋いでいくことはできないのだろうか。この仕組みは待った無しで変えていかなければ、ますます失われるばかりだ。
著者の行動は"筋"が通ってない。「男でないと」とあるが、性別の話ではない。さらに、住んでもいない、これまでに合議に参加したこともない若いもんが、経緯を脇に置いて論を吹っかけるなど、私でも鼻白む。それがわからない者が一人前に認められないのは当然すぎる。日本人の自治は、宮本常一が書いたように、古来定式がある。それを経た結論は、既に集団の総意だ。一方で、男ばかりの団体に所属している経験から言うと、男偏重の合議には変な暗黙の了解みたいなのもあって、健全な議論を阻害しがちなのも確かなので、変わっていくべきとも思う。
読了日:12月11日 著者:高橋久美子
 また 身の下相談にお答えします (朝日文庫)の感想
また 身の下相談にお答えします (朝日文庫)の感想
にやにやと読む。家族の話題が多いなかでも夫婦の話が気に留まる。夫を『上下関係のもとで命令されつけているので、ことほどさように自発性のない生きもの』とまでは思わないが、旅行やゴルフのようなイベントを除くと、わりと画面の前で完結しているようにも思える。地域や趣味での居場所づくりのお膳立てはせっせと励んでおこう。また、生活を共にして何年も経つと同化してきたような気にもなるが、夫婦とは異文化共存、『異文化と共存するのは実は不愉快なもの』。諦めや苛立ちを抑えるんじゃなく、そこんとこ肚に落として向かい合いたいものだ。
読了日:12月10日 著者:上野千鶴子
 白の闇 (河出文庫)の感想
白の闇 (河出文庫)の感想
視界が真っ白な闇に閉ざされる感染症が蔓延する。都市に暮らす者が皆盲目になったらどうなるかという思考実験である。閉ざされた集団で起こる事態はさもありうべき悲惨だが、では街は。社会システムの崩壊、物質社会の崩壊、モラルの崩壊、なにも生み出すことができない世界。視覚に頼って生きてきた人間は、目が見えないというそれだけで、自然に還ることもできずに汚穢をこびりつかせたまま残されたものを奪い合う。全ての目撃者であり、引率者としての役割を果たす医者の妻が、全てを引き受けてなお生きるしたたさの象徴として強い印象を残した。
荒廃しきった街。仮に再び目が見えるようになったとして、元に戻れるか。戻れるだろう。戻るのだ。人間のレジリエンス。生き残った者たちで、生きてゆくための社会をまた築く。それは、ただ今戦禍の下で生を繋ごうとしている人たちの姿、また戦争を経た後の国の姿として歴史に残されているとおりなのだと、現代を生きる私たちは知っている。
読了日:12月10日 著者:ジョゼ・サラマーゴ
 比類なきジーヴス (ウッドハウス・コレクション)の感想
比類なきジーヴス (ウッドハウス・コレクション)の感想
なんて一流な執事、ジーヴス。さらりと手をまわしてごたごたを解決してしまう手並みが楽しい。でも執事って隠居みたいな生活の若主人やその友人の窮地を救って小金をもらったり競馬や賭け事で儲けたり、するものだっけ? くすっと笑える、19世紀の手軽なシリーズ。しかしこれ、オーウェルもエリオットもクリスティも吉田健一も美智子上皇后さまも愛読者という有名なもの。実は深い教養が織り込まれているとか、毒がないとか、イギリス流のユーモアが楽しめるとか…? cozyな読み物の古典、といったところかな?
読了日:12月08日 著者:P.G. ウッドハウス
 牙: アフリカゾウの「密猟組織」を追っての感想
牙: アフリカゾウの「密猟組織」を追っての感想
辛い読書。サタオの雄姿と骸の写真を私は忘れまい。辛いのは、人間が今もカネのために、生態系循環に大きな役割を担うゾウを、生きたまま顔ごとえぐり取るようなやり方で虐殺し続けている事実。そして日本が今もアフリカゾウの絶滅過程に加担し続けている事実を突きつけられたからだ。ゾウから象牙を奪う行為はゾウを殺すことと同義。日本人がハンコにする象牙のために、アフリカゾウは絶滅しようとしている。その事実が世界の知るところとなった2016年の会議を経て2022年のワシントン条約締約国会議、日本は変わらず汚い主張を繰り広げた。
『一国でも象牙市場が存続し続ける限り、密猟者たちはアフリカゾウの虐殺を止めない。その存在を免罪符にして彼らはいつまでもゾウを殺すだろうし、象牙が生産される限り、中国はいくらでもそれらを買うだろう。日本人はそんな簡単なこともわからないのか』と関係者に言わしめたのが2016年。認定NPO法人トラ・ゾウ保護基金による2022年11月のワシントン条約締約国会議@パナマのTwitterレポートを読む限り、全象牙市場の閉鎖を求める世界的な方向性に逆らい、日本政府は"徹底抗戦"し、日本市場は閉鎖していない。恥ずかしい。
読了日:12月05日 著者:三浦 英之
 NORTH 北へ―アパラチアン・トレイルを踏破して見つけた僕の道の感想
NORTH 北へ―アパラチアン・トレイルを踏破して見つけた僕の道の感想
アパラチアントレイルを南から北へ踏破する。平地ではなく山道を走りたい、あるいは長く走りたい欲求は想像できなくもないが、のみならず、レース優勝や最速踏破記録更新への欲望は、とうてい理解できない。さらにジャーカーはヴィーガンだ。生体維持に必要なカロリーと走って消費するカロリーを食事でまかないきれない。みるみる痩せ、走るのに必要外の生体機能が低下し、やがて自分自身を食い尽くし始める。それでも走り続けるのは、曰く「闘いつづける自分への欲求」。そういえばトレランレースの出場者は、テレビ番組で見る限り年齢層が高めだ。
読了日:12月03日 著者:スコット・ジュレク
注: は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。
スクショ保存してあるのを見返すと興味深い。
記憶にほとんど残っていない本がベスト3に入っていることもざらなら、
ベスト20のうち今も心のどこかで活きていると感じる本は5冊がいいところだったりする。
なにが根を生やし育つかわからないのだから、なんでも植えて(読んで)みるのが良いのだ。
とはいえ、私が気になった全ての本を読む時間は、私の人生にはもう無い。
なのに今月もたくさん買い込んだ。そろそろ読む本を選びなさいよという話である。
ちなみに今年のベスト20はこちら

<今月のデータ>
購入24冊、購入費用18,635円。
読了16冊。
積読本329冊(うちKindle本168冊、Honto本4冊)。

12月の読書メーター
読んだ本の数:16
 翻訳者による海外文学ブックガイド BOOKMARKの感想
翻訳者による海外文学ブックガイド BOOKMARKの感想もとはフリーペーパー企画。表紙にあるとおりながら、小説を翻訳した本人による紹介というところがいちばんの魅力です。あと、各巻頭のエッセイは国内の作家さんによるもので、こちらもそうそうたる面々で嬉しい。若い読書が想定されているとのことでヤングアダルトや少年文庫も多いなか、大人向けの本格ものもたくさんあって鼻息荒く物色した。惜しむらくは、翻訳ものあるあるで、絶版の嵐。。。刊行されて数年で文庫にもならず消えてしまうのは余りにもったいないことだ。悔しい。ていうか早く読め私。次作はタイムリーに読みます。
読了日:12月30日 著者:金原 瑞人,三辺 律子

 僕らはソマリアギャングと夢を語る――「テロリストではない未来」をつくる挑戦の感想
僕らはソマリアギャングと夢を語る――「テロリストではない未来」をつくる挑戦の感想永井陽右氏の活動の始まり。なぜ、国境なき医師団すら撤退したソマリアでなければならなかったか、という問いは既に無意味だろう。紛争解決の専門家の忠告よりも、渡航する度に得る手ごたえを糧に彼は前に進んだ。『ギャングと話せば話すほど、同じ時間を共有すればするほど、彼らが僕らと何も変わらない存在だと気づく』。信じた活動を10年続けた先に経験もスキルも学位も得た。彼は行けるところまで行くのだろう。自分が『人間としての責任』と認識する活動にどうすれば無関心な人たちを巻き込んでいけるのか、日々考える。真面目な人なのだ。
彼の論理では、ソマリアは世界でもっとも支援が必要な場所である。しかしそこは世界で最も死に近い場所である。死なずに続けられているのは幸運、だろう。内田先生との対談記事で、命を大事にと語りかける内田先生の言葉をスルーしているように読めるのが気にかかった。編集ならよいのだが。社会的な意義が大きいのは理解できる。ただ、殉教者にはなってほしくないと私も願っている。世界には、彼と同じように危険な地で活動に邁進する仲間がたくさんいるのだという。彼らや、ソマリアの仲間こそが、彼にとってのリアルなのだろうな。
知識もスキルも無い者が紛争地に行くべきではない。それが"常識的な"考え方だ。しかしそれに反して飛び込んでいく者たちがいて、私はそれを無謀と切って捨てるべきかと考え始める。そこには、人間が生きているのだ。例えば国内の活動で、政府も行政でもできないことを民間の有志が個人としてできる範囲のことをやっていくように、そこに人間が生きている限り、紛争地にも政府やNGOにはできないが個人にはできることがある、という考え方はできる。紛争自体は即時解決しなくても、何人かに生き延びる人生を生むことはできた、それが動力になる。
読了日:12月28日 著者:永井陽右

 その名にちなんで (新潮文庫)の感想
その名にちなんで (新潮文庫)の感想物語を読み終えて、ほっと息を吐いた。家族2世代の歴史の物理的時間は40年もない。ただ彼らの綿々と抱える想いが重たいのだ。インド人が家族を単位に考えるのに対し、アメリカ人は個人を単位に考える。『アメリカというところは、何事も行き当たりばったりで、真実味がない』。インドからアメリカに移り住んだ一世が物事の捉え方の違いに戸惑い、一世同士で伴侶を見つけるのに対し、アメリカで生まれた二世は段違いにアメリカナイズされた考え方をする。しかし親親戚も自身の外見も完璧にベンガルである彼らの苦悩は、一世のものとは全く異なる。
母アショケはアメリカに渡った当初、家に引きこもりがちで、ベンガルの友人を得た後にインドの親戚のように招きもてなし合う関係を築いた。一方ゴーゴリたちは学校や職場で知り合うアメリカ人と集まって飲食や議論を共にするが、同じ賑やかなパーティーでもその本質は真逆だ。一見きらびやかなアメリカで、自身の中のインドとの折り合いをどこでつけるか、どちらを選ぶか、さらに異世界を選ぶか、その入り交じり具合も人によってほんとうに違っているのだということが、3代遡ってもみな日本生まれが当たり前の日常にいる私にはずっしりときた。
読了日:12月27日 著者:ジュンパ ラヒリ
 アラビア遊牧民 (講談社文庫)の感想
アラビア遊牧民 (講談社文庫)の感想1965年のサウジアラビア。ベドウィンの人々や生活、ラクダやスカラベの観察も興味深い。さて、アラビア遊牧民が"見返りを求めず"旅人を歓待する話、その真実は「海老で鯛を釣る」慣習であるという。食事や接待それ自体のお礼は絶対に受け取らないが、その後は見返りをもっとよこせという態度に豹変する。不確実な善意に頼っていては死んでしまう土地、それは厳しい自然を指すのではなく、歴史的に侵略と強奪が繰り返された土地ゆえに根付いた、他人を信用しないことを前提にした民族の集積知であるという考え方は、胸に刻みつけたい。
読了日:12月27日 著者:本多勝一

 私の本棚 (新潮文庫)の感想
私の本棚 (新潮文庫)の感想クリスマスイヴを小野さんのエッセイで過ごす。いやー、寄稿者の人選も好いし、本と本棚の話って熱いよな。本が身の周りに増えていくときの現象や、念願の本棚を手に入れて気づく真実はわりあい似ている。でもそこから導く在り様は人それぞれに多様だ。私は私がいつか手に入れる本棚の理想図を描きながら、本棚は読んだ本の背中でその人の姿を、積読本の山でその人の生きる望みを顕わすのだから、堂々といつも目に入るように手に取れるように置こうと決意した。今年の読書の締めくくりとしてふさわしかった。まだ読むけど。
今年の一箱古本市でお隣のブースになった方が、古書然とした本を並べておられたので、本職(古書店)の方ですかとお訊きしたら、「終活です」とお答えになったのが忘れられない。若い頃に大切に読んだ本も老眼が入れば読むものではなくもはや思い出であり、喜んでもらってくれるあてもない。1冊もらい受けようにもこちらも老眼に差し掛かる身で、当時の活字の小ささに怖じた。明日は我が身。溜め込むほど後が大変になるのは自明。それでも本にまつわる全ての記憶と、集めた本への執着、本を読む自分への希望は愛おしい。
読了日:12月25日 著者:

 豆腐屋の四季―ある青春の記録 (講談社文庫)の感想
豆腐屋の四季―ある青春の記録 (講談社文庫)の感想豆腐屋を継いだ著者は、朝日歌壇に投稿する歌人である。その縁でエッセイもものする。決して余裕のない生活の中で、暮らしに根差した想いたちは、夜業に差す月の光、早暁の冴え冴えとした空気、極寒に大豆を絞る湯気の中にありありと立ちのぼる。生活詠と呼ぶそうだ。俳句を趣味にしていた亡き祖母を想う。遺品からはできた句を書き留め添削したノート、メモ綴じ、裏紙の類が膨大に出てきた。著者と同じ、無学な自営の妻だった。だからこそこの記を愛おしく思うのかもしれない。草木花歳時記数冊と広辞苑のような厚さの大歳時記は私が貰い受けた。
読了日:12月23日 著者:松下 竜一

 小説 すずめの戸締まり (角川文庫)の感想
小説 すずめの戸締まり (角川文庫)の感想映画という表現方法を持つ新海誠が、なぜ同時進行で小説を書く必要があったかと訝しみつつ読んだ。理由はあとがきにあった。それはそれで納得である。視覚的な描写、静/動のメリハリの効いた描写の多い小説である。ダイジンの造形はわかりやすいけれど、その役割を知って読み返すとずるい。扉があるのは、かつて人間の活動が盛んだった場所であるようだ。『ひとのてで もとにもどして』。黒く塗りつぶされた3月11日。当事者でないからこそ、それを忘れかけていること、忘れてはいけないと自らに警告する術を、私たちは望んでいるのだろうか。
天災による被害という意味では、阪神大震災も同じはずだ。しかし、当時の私が哀しみや憤りのなんたるかも知らなかった年頃であったこと、東日本大震災の場合は地震と津波と、原発の人災が重なったことで、私にとっては太平洋戦争の敗戦に匹敵する重さで脳底に鎮座している。いつまでも割り切ることのできない出来事として抱えておきたい。
読了日:12月22日 著者:新海 誠
 日本の漁業が崩壊する本当の理由の感想
日本の漁業が崩壊する本当の理由の感想これも日本ジリ貧案件。水産物生産量は世界では増えており、日本では減っている。魚種によって事情が違うし、外国との兼ね合いもあるが、主因は日本が科学的根拠に基づく分析・管理できずに乱獲する点である。例えば2011年の震災後、三陸沖の魚は増えた。人間が獲らなければ魚は繁殖し増える。しかしそれを豊漁と根こそぎ獲ってしまえば元の魚の減った海に戻るわけで。ならば養殖すればよいかといえば餌は高騰の一途。輸入すればよいかといえば円安で日本は買い負けし始めており、回転寿司屋が立ち行かなくなるのも時間の問題と予測してみる。
スーパーの鮮魚売り場で「ホッケ小さいな」「サンマ細いな」「高くなったな」は判るが、安く売られている魚が、旬だからではなく、不漁なのでしかたなく旬じゃないものや獲り頃よりまだ小さいものを獲ってきてるからだなんて、私は知らなかった。だから美味しくないのだと。海の生態系を破壊する底曳き網を規制するなどは国がするべきことだが、面倒なことはしたがらないのがお家芸。国民が現状や解決策を知り、世論を醸成して国を突き上げるしか、日本を変える方法はないのだろう。漁業にまつわる問題はそこらじゅうにあるようだ。読んで良かった。
とりあえず、メディアが今年は豊漁とか不漁とか高いとか安いとかだけ報道するのは害でしかない。もっとちゃんと取材してほんとうのところを知らしめていただきたい。
読了日:12月19日 著者:片野 歩

 アフリカ出身 サコ学長、日本を語るの感想
アフリカ出身 サコ学長、日本を語るの感想自分の学生時代、その過ごし方を「あれで正しかったのだろうか」と私は時々思い返す。何か間違っていたから、本来得られたはずのものを逃して、いま見えない壁を越えられずにいるんじゃないかという気がずっとしていた。前半はサコ学長の来歴、後半は教育・教育システム論。サコ学長の現状概観を読むと、私は日本の教育システムが設計したとおりに正しく過ごしたとしか言えないことに驚いた。「良い子」だったんやなあ…と嘆息する。ならば、気づいた時点で若者に胸を張れる不良中年になるのが解決策じゃろなあ。今の若者は息苦しそうだもの。
サコ学長の学生時代を読みながら、多様性や異文化への理解は、直に接しないと絶対にわからないと痛感した。私は日本の教育の中で、小さい頃から「みんな同じ」「みんな平等」と教わってきた。私はうかつにも、高校生になっても大学生になっても文字どおり「人間は大同小異」だと思っていた節がある。でも実は、他人は皆能力も志向も違っていて、無限の方向性があって、手を伸ばして得るものなんだってことに気づいたのはほんとうに最近のことだ。
読了日:12月14日 著者:ウスビ・サコ

 体と心がラクになる「和」のウォーキング 芭蕉の“疲れない歩き方”でからだをゆるめて整える (祥伝社黄金文庫)の感想
体と心がラクになる「和」のウォーキング 芭蕉の“疲れない歩き方”でからだをゆるめて整える (祥伝社黄金文庫)の感想安田先生の身体論×精神文化論とでも呼ぼうか。能やロルフィングの身体観に基づいた歩き方指南の本かと思いきや、日本人の身体の個性から話は古今の相撲における身体運用の違いへ、さらに「おくのほそ道」が"歌枕"を巡る歩き旅であったとの指摘、古典と現実を重ね合わせて楽しむ大名庭園の散歩法まで、安田先生のお話がいろいろ読めてお得。歳を取って能力に制限が加わることによってこそ、物事が新しく捉えられ、また興味深く感じることができる話が好きだが、元大相撲力士の一ノ矢さんも同意とか。歳を取ることが楽しみになってくる嬉しさよ。
読了日:12月12日 著者:安田登
 その農地、私が買います 高橋さん家の次女の乱の感想
その農地、私が買います 高橋さん家の次女の乱の感想黒糖づくりや百姓、猟師など、現状を憂え、自身が信じたように行動する人たちが、ここには何人も出てくる。こういう動きを内田先生は希望と呼ぶのかな。農地付きの土地をなんとか買えないかと考えていた私にも参考になった(諦めた)。しかし後味は悪い。ここにはふたつ大きな問題があって、ひとつは農業を諦める人の土地売買の問題、ひとつは日本人らしい自治、日本的民主主義とは何かという問題である。妨害行為は違法だが、著者のやり方は褒められたもんじゃないとも私は思って、考え込んだ。唯一無二のお母さんの土がなんとか守られますように。
農地は農業従事者以外が買うことはできないし、買ったらそこには販売用の農作物をつくらなければならない。かといって農地転用した土地は宅地分の固定資産税を払えば自由になる訳ではなく、農作物をつくったり木を植えたりして住宅を建てずにいると指導される。これでは、放置か分譲住宅にするか太陽光パネルを敷き詰めるかしかないだろう。農地を農地として守る規制は大事だけれど、農地なり緑地なり他の方法でも、土のまま繋いでいくことはできないのだろうか。この仕組みは待った無しで変えていかなければ、ますます失われるばかりだ。
著者の行動は"筋"が通ってない。「男でないと」とあるが、性別の話ではない。さらに、住んでもいない、これまでに合議に参加したこともない若いもんが、経緯を脇に置いて論を吹っかけるなど、私でも鼻白む。それがわからない者が一人前に認められないのは当然すぎる。日本人の自治は、宮本常一が書いたように、古来定式がある。それを経た結論は、既に集団の総意だ。一方で、男ばかりの団体に所属している経験から言うと、男偏重の合議には変な暗黙の了解みたいなのもあって、健全な議論を阻害しがちなのも確かなので、変わっていくべきとも思う。
読了日:12月11日 著者:高橋久美子

 また 身の下相談にお答えします (朝日文庫)の感想
また 身の下相談にお答えします (朝日文庫)の感想にやにやと読む。家族の話題が多いなかでも夫婦の話が気に留まる。夫を『上下関係のもとで命令されつけているので、ことほどさように自発性のない生きもの』とまでは思わないが、旅行やゴルフのようなイベントを除くと、わりと画面の前で完結しているようにも思える。地域や趣味での居場所づくりのお膳立てはせっせと励んでおこう。また、生活を共にして何年も経つと同化してきたような気にもなるが、夫婦とは異文化共存、『異文化と共存するのは実は不愉快なもの』。諦めや苛立ちを抑えるんじゃなく、そこんとこ肚に落として向かい合いたいものだ。
読了日:12月10日 著者:上野千鶴子

 白の闇 (河出文庫)の感想
白の闇 (河出文庫)の感想視界が真っ白な闇に閉ざされる感染症が蔓延する。都市に暮らす者が皆盲目になったらどうなるかという思考実験である。閉ざされた集団で起こる事態はさもありうべき悲惨だが、では街は。社会システムの崩壊、物質社会の崩壊、モラルの崩壊、なにも生み出すことができない世界。視覚に頼って生きてきた人間は、目が見えないというそれだけで、自然に還ることもできずに汚穢をこびりつかせたまま残されたものを奪い合う。全ての目撃者であり、引率者としての役割を果たす医者の妻が、全てを引き受けてなお生きるしたたさの象徴として強い印象を残した。
荒廃しきった街。仮に再び目が見えるようになったとして、元に戻れるか。戻れるだろう。戻るのだ。人間のレジリエンス。生き残った者たちで、生きてゆくための社会をまた築く。それは、ただ今戦禍の下で生を繋ごうとしている人たちの姿、また戦争を経た後の国の姿として歴史に残されているとおりなのだと、現代を生きる私たちは知っている。
読了日:12月10日 著者:ジョゼ・サラマーゴ
 比類なきジーヴス (ウッドハウス・コレクション)の感想
比類なきジーヴス (ウッドハウス・コレクション)の感想なんて一流な執事、ジーヴス。さらりと手をまわしてごたごたを解決してしまう手並みが楽しい。でも執事って隠居みたいな生活の若主人やその友人の窮地を救って小金をもらったり競馬や賭け事で儲けたり、するものだっけ? くすっと笑える、19世紀の手軽なシリーズ。しかしこれ、オーウェルもエリオットもクリスティも吉田健一も美智子上皇后さまも愛読者という有名なもの。実は深い教養が織り込まれているとか、毒がないとか、イギリス流のユーモアが楽しめるとか…? cozyな読み物の古典、といったところかな?
読了日:12月08日 著者:P.G. ウッドハウス

 牙: アフリカゾウの「密猟組織」を追っての感想
牙: アフリカゾウの「密猟組織」を追っての感想辛い読書。サタオの雄姿と骸の写真を私は忘れまい。辛いのは、人間が今もカネのために、生態系循環に大きな役割を担うゾウを、生きたまま顔ごとえぐり取るようなやり方で虐殺し続けている事実。そして日本が今もアフリカゾウの絶滅過程に加担し続けている事実を突きつけられたからだ。ゾウから象牙を奪う行為はゾウを殺すことと同義。日本人がハンコにする象牙のために、アフリカゾウは絶滅しようとしている。その事実が世界の知るところとなった2016年の会議を経て2022年のワシントン条約締約国会議、日本は変わらず汚い主張を繰り広げた。
『一国でも象牙市場が存続し続ける限り、密猟者たちはアフリカゾウの虐殺を止めない。その存在を免罪符にして彼らはいつまでもゾウを殺すだろうし、象牙が生産される限り、中国はいくらでもそれらを買うだろう。日本人はそんな簡単なこともわからないのか』と関係者に言わしめたのが2016年。認定NPO法人トラ・ゾウ保護基金による2022年11月のワシントン条約締約国会議@パナマのTwitterレポートを読む限り、全象牙市場の閉鎖を求める世界的な方向性に逆らい、日本政府は"徹底抗戦"し、日本市場は閉鎖していない。恥ずかしい。
読了日:12月05日 著者:三浦 英之

 NORTH 北へ―アパラチアン・トレイルを踏破して見つけた僕の道の感想
NORTH 北へ―アパラチアン・トレイルを踏破して見つけた僕の道の感想アパラチアントレイルを南から北へ踏破する。平地ではなく山道を走りたい、あるいは長く走りたい欲求は想像できなくもないが、のみならず、レース優勝や最速踏破記録更新への欲望は、とうてい理解できない。さらにジャーカーはヴィーガンだ。生体維持に必要なカロリーと走って消費するカロリーを食事でまかないきれない。みるみる痩せ、走るのに必要外の生体機能が低下し、やがて自分自身を食い尽くし始める。それでも走り続けるのは、曰く「闘いつづける自分への欲求」。そういえばトレランレースの出場者は、テレビ番組で見る限り年齢層が高めだ。
読了日:12月03日 著者:スコット・ジュレク

注:
 は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。 






