2022年12月01日
2022年11月の記録
すごい! 本が読めない! この私が!
溜まった疲れのうえに家の中の諸雑用で忙殺され、
ようやく本を手に取っても並ぶ文字を理解できない日が続く。
この感覚のまあ新鮮なこと。
ようやく休息も足り、時間ができ、ソファに寝そべって本を手に取ったのに、
それがハズレだったときのがっかり感よ。
<今月のデータ>
購入16冊、購入費用14,860円。
読了11冊。
積読本324冊(うちKindle本160冊、Honto本6冊)。

11月の読書メーター
読んだ本の数:11
 スタッキング可能の感想
スタッキング可能の感想
『嘘ばっかり! 嘘ばっかり! ウォータープルーフ嘘ばっかり!』 ああもうすんごい生きづらそう。そんな不毛でしんどい日々をなんとか過ごしている人たちが今もいるんだなあ、と思って気づくのは、自分もそういう時期を経たのであり、歳を重ねるうちにようやく手放し、平和を手に入れた事実である。しかし今も都会のビル街でホワイトカラーとして働いていたなら、手放すこともできずに悶々と抱えていなきゃならんのかなあと思うと、やはり同情しきりだった。ここ10年を超えて化粧品売り場に足を踏み入れることのなかった、この平和を愛する。
読了日:11月27日 著者:松田 青子
 ぼくの旅のあと先 (角川文庫)の感想
ぼくの旅のあと先 (角川文庫)の感想
「本の旅人」連載。シーナさんが新たにどこかへ旅した、みたいな話ではなくて、これまで行った土地やエピソードを回顧するような、言ってみれば人生の総括に差しかかっているのかと寂しさを覚えた。さすがのシーナさんも痛風を患い、機内の小さなライトでは文庫本を読めなくなり、小樽の家も仕舞を余儀なくされた。少年すぎるエピソードも陰を帯びる。だけど積み重ねたものの趣は深く、読んで良かった。インドで牛肉に人気が無いからスパイスカレーに牛肉は入らないとか、人間はその土地に合った埋葬方法を編み出し儀式を整えるとか、なるほど納得。
読了日:11月27日 著者:椎名 誠
 黒猫ネロの帰郷の感想
黒猫ネロの帰郷の感想
原題「ネロ・コルレオーネ」。生後6週目にしてこの傍若無人な振舞いよう、ネロの名は黒いからではなく暴君からのほうがしっくりくる。私の経験上(サンプル数3)、人間と暮らす黒猫は天然気質で愛くるしい性格なものだけど、著者の家の黒猫はそんなだったのかしらん。ネロはイタリアからドイツへ、ドイツからイタリアへと移住する。最後の老農夫とじっと見つめあう場面がとても好い。この老農夫、なんだかんだ言って面倒見が良くて、実はちゃんとわかってるんだなあ。農家の猫って猫の暮らしとしては理想的なんじゃないかしら。
読了日:11月27日 著者:エルケ ハイデンライヒ
 瀬戸内海の発見―意味の風景から視覚の風景へ (中公新書)の感想
瀬戸内海の発見―意味の風景から視覚の風景へ (中公新書)の感想
近代初頭、来日した西洋人たちは瀬戸内海を絶賛した。なかでも瀬戸内海を航行する船の上から見える景色を称賛したという。陸路より海路のほうが発達が早かった。波が穏やかなだけでなく、大小の島々、潮の流れる瀬戸、港町、段々畑、小舟が移ろいゆくのを船上から「動く風景」として愛でた。だから初まりは陸からの展望景や山上からの俯瞰景ではなかったのだ。『すべて島々の海中に浮てみゆるは、盆に水を湛へておもしろき石どもを入れをける如くにて』とは日本人の評だが、京都の石庭に通じるものがある。それが自ら動いたらそれは興深かろう。
近世までは、古典文学、また俳句や和歌に詠い継がれた地が日本人の見るすべき"観光地"であり、その様式化された風景を踏まえて表現をすることがステイタスだったのだろう。それ以外の景色は見向きされなかった。朝鮮通信使もまた九州から近畿へ抜ける航行で、中国文化に由来する漢詩チックな風景をもて囃した。だから、瀬戸内海の自然の風景が称賛されたというのは地学・地理学的知識を持った西洋人が来航し、国内を行き来するようになってからの話であり、日本の知識人がそれに影響され、広がったというのが実のところではないかと思う。
地元民にとって瀬戸内海は、愛着はあれど「ほんまに海か?」と茶化すような当たり前の存在である。私は長年、太平洋のほうが雄大で偉いと思ってきた。しかしこうまで評されると、なにやらかけがえのないものに思われてきた。料金の馬鹿高いガンツウも、インバウンド狙いの時代になるほどそういった客層を狙ってのものなのだと理解した。そのガンツウには乗れそうもない庶民である私は、年に一日だけ近畿から九州へ航行している「昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ」を発見し、来年狙うことにした。わくわくする。読んでよかった。
読了日:11月26日 著者:西田 正憲
 日本人の給料 (宝島社新書)の感想
日本人の給料 (宝島社新書)の感想
専門家が解析してみせる日本の経済や政策の如何は理解しきれないのだが、政財界や外資系コンサルなどが煽ってなんとなく日本に充満している「今の常識」は耳に入れなくていいということはわかった。時代が変わろうと、日本の「良い企業」の条件は変わらない。肌感覚を鋭敏にし、世間の潮流には馬耳東風で構わない。とはいえ、資本主義による弊害と日本政府の失策による弊害は混然として、法律で雁字搦めになっている地方の中小企業にとって、これが会社にも従業員にもひいては客にも良いと言える仕組みはなかなか難しい。結局悩むしかないのだが。
読了日:11月25日 著者:浜 矩子,城 繁幸,野口 悠紀雄,ほか
 ワニの町へ来たスパイ (創元推理文庫)の感想
ワニの町へ来たスパイ (創元推理文庫)の感想
評判通りの面白さであっという間に読み終わってしまった。老いた男が元気なのは微笑ましいが、老いた女が元気なのは痛快だ。こんな老後を過ごしたい。無理だけど。あり得ないけど。舞台がディープサウスってのも、都会とは違った未知の要素てんこ盛りでわくわくする。ロマンス要素ももれなくついてて、続き読んじゃうなあ、これ。この調子で続々仕留めてたら、シリーズ終盤には町の人口半減してるんじゃないかと心配。
読了日:11月19日 著者:ジャナ・デリオン
 ぼくはウーバーで捻挫し、山でシカと闘い、水俣で泣いたの感想
ぼくはウーバーで捻挫し、山でシカと闘い、水俣で泣いたの感想
「アマゾンの倉庫で絶望し、~」をふまえたようなタイトル。こちらは潜入ではなく取材、毎日新聞の連載だ。枚挙に暇無い社会問題の現地に斎藤幸平は出かけて行く。字数制限もあり、各々への所感はあっさりしている。思想家と自称する斎藤幸平は、自分が当事者でない、理不尽を振りかざす立場にないと自覚している。それでもこうして書く、自身の立ち位置への逡巡が巻末で吐露される。しかし自身結論するとおり、直接取材することで肌に感じ共有することには意味がある。加えて、実経験の積み重ねは斎藤幸平の言霊を育てるだろう。次作が楽しみです。
読了日:11月17日 著者:斎藤 幸平
 ねじねじ録の感想
ねじねじ録の感想
藤崎彩織はごく平均的な家庭で育った女性だ。学生時代や新しい家族の日々を描き、女性が抱える諸問題を考え、セカオワの裏話も書く。話題のバランスを配慮しているのが窺える。孤独を抱え、不眠に悩んだ時期が彼女にもある。負けず嫌いなのに悩み性だから今もねじねじする。それらがセカオワの曲に通底する祈りと希望に昇華しているのだと納得。ライブでのあの満ち足りた笑顔の裏側に数えきれない涙があると知れば、大切に思える曲も新たに増えたのは嬉しいボーナスだった。2019年のライブ前が実は解散の危機崖っぷちだった、なんて心臓に悪い。
読了日:11月12日 著者:藤崎 彩織
 脳科学者の母が、認知症になる: 記憶を失うと、その人は“その人"でなくなるのか?の感想
脳科学者の母が、認知症になる: 記憶を失うと、その人は“その人"でなくなるのか?の感想
認知症がいかに今の生活から地続きであることか。「認知症世界の歩き方」が、認知症を患った本人にとって世界がどのように変貌して見えるかだったのに対し、こちらは認知症と診断された家族が呈する症状への解釈の実践である。人間が知覚する情報量は膨大だ。それを取捨選択し、絞り込み、処理する能力は、脳機能の経年減退に伴い低減する。それは過度な疲労や泥酔時の自分のそれと同種ではないのか。泥酔と違い、回復することなく緩慢に進む症状と折り合うには、できることを自分のペースでやれている実感を本人に維持するのが大事と憶えておく。
『感情は、理性だけではとても対応できないような、不確実な状況で、なんとか人間を動かしてくれるシステム、意思決定をさせてくれるシステムなのである』。物事の理解能力が衰えても、感情的判断は正しいと著者は言う。理性よりも原始的な能力であるところの感情は、人間の生存を助けてきたからだ。健康な人と同じように尊重すべきだし、感情こそその人らしさと結論づけている。『感情は、生まれつきの個性であり、また、認知機能と同じように、その人の人生経験によって発達してきた能力であり、いまだに発達し続けている能力である』。
読了日:11月11日 著者:恩蔵絢子
 化物園 (単行本)の感想
化物園 (単行本)の感想
ん。これも、一貫した主題あって書かれた短編集じゃない感じ。ケシヨウ(化生?)の気配を感じるもの、感じないもの、人の性悪、ファンタジー、因果応報、ぶれぶれ。そのケシヨウすら、読みながら存在を忘れてしまうほどの存在感の薄さが、恒川さんの迷走を思わせる。「胡乱の山犬」が好きかな。そこここに暗闇と曖昧があった時代設定もさながら、「彼」の生涯が自然に呑まれる時を迎える展開が好きなのだ。恒川光太郎のなにが好きといって、単なる怪異譚ではない。現実とのズレ感が、空間的時間的に拡がりを持つとき、物語は永遠の性質を帯びる。
読了日:11月10日 著者:恒川 光太郎
 ケアマネジャーはらはら日記の感想
ケアマネジャーはらはら日記の感想
先日祖母を見送った。施設に10年近く入っていた。5年前には娘の顔も忘れた。葬儀で伯母たちは「ケアマネさんが良い人でよかった」と言い合った。ケアマネージャーという仕事は小回りの効いた動きを求められ、精神的負担は想像をはるかに超えた。"目配り、気配り、心配り"。不安や困窮を抱えた老人やその家族が、生活に差配する他人に穏やかに接せるとは限らない。その心のケアもなんて大変すぎる。かつその報酬がケアプランの作成料だけとか。ケアする側も全員が心映えや各種処理能力のよくできた聖人ではなく、全てで当たり前ではないと自戒。
読了日:11月02日 著者:岸山真理子
注: は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。
溜まった疲れのうえに家の中の諸雑用で忙殺され、
ようやく本を手に取っても並ぶ文字を理解できない日が続く。
この感覚のまあ新鮮なこと。
ようやく休息も足り、時間ができ、ソファに寝そべって本を手に取ったのに、
それがハズレだったときのがっかり感よ。
<今月のデータ>
購入16冊、購入費用14,860円。
読了11冊。
積読本324冊(うちKindle本160冊、Honto本6冊)。

11月の読書メーター
読んだ本の数:11
 スタッキング可能の感想
スタッキング可能の感想『嘘ばっかり! 嘘ばっかり! ウォータープルーフ嘘ばっかり!』 ああもうすんごい生きづらそう。そんな不毛でしんどい日々をなんとか過ごしている人たちが今もいるんだなあ、と思って気づくのは、自分もそういう時期を経たのであり、歳を重ねるうちにようやく手放し、平和を手に入れた事実である。しかし今も都会のビル街でホワイトカラーとして働いていたなら、手放すこともできずに悶々と抱えていなきゃならんのかなあと思うと、やはり同情しきりだった。ここ10年を超えて化粧品売り場に足を踏み入れることのなかった、この平和を愛する。
読了日:11月27日 著者:松田 青子

 ぼくの旅のあと先 (角川文庫)の感想
ぼくの旅のあと先 (角川文庫)の感想「本の旅人」連載。シーナさんが新たにどこかへ旅した、みたいな話ではなくて、これまで行った土地やエピソードを回顧するような、言ってみれば人生の総括に差しかかっているのかと寂しさを覚えた。さすがのシーナさんも痛風を患い、機内の小さなライトでは文庫本を読めなくなり、小樽の家も仕舞を余儀なくされた。少年すぎるエピソードも陰を帯びる。だけど積み重ねたものの趣は深く、読んで良かった。インドで牛肉に人気が無いからスパイスカレーに牛肉は入らないとか、人間はその土地に合った埋葬方法を編み出し儀式を整えるとか、なるほど納得。
読了日:11月27日 著者:椎名 誠

 黒猫ネロの帰郷の感想
黒猫ネロの帰郷の感想原題「ネロ・コルレオーネ」。生後6週目にしてこの傍若無人な振舞いよう、ネロの名は黒いからではなく暴君からのほうがしっくりくる。私の経験上(サンプル数3)、人間と暮らす黒猫は天然気質で愛くるしい性格なものだけど、著者の家の黒猫はそんなだったのかしらん。ネロはイタリアからドイツへ、ドイツからイタリアへと移住する。最後の老農夫とじっと見つめあう場面がとても好い。この老農夫、なんだかんだ言って面倒見が良くて、実はちゃんとわかってるんだなあ。農家の猫って猫の暮らしとしては理想的なんじゃないかしら。
読了日:11月27日 著者:エルケ ハイデンライヒ
 瀬戸内海の発見―意味の風景から視覚の風景へ (中公新書)の感想
瀬戸内海の発見―意味の風景から視覚の風景へ (中公新書)の感想近代初頭、来日した西洋人たちは瀬戸内海を絶賛した。なかでも瀬戸内海を航行する船の上から見える景色を称賛したという。陸路より海路のほうが発達が早かった。波が穏やかなだけでなく、大小の島々、潮の流れる瀬戸、港町、段々畑、小舟が移ろいゆくのを船上から「動く風景」として愛でた。だから初まりは陸からの展望景や山上からの俯瞰景ではなかったのだ。『すべて島々の海中に浮てみゆるは、盆に水を湛へておもしろき石どもを入れをける如くにて』とは日本人の評だが、京都の石庭に通じるものがある。それが自ら動いたらそれは興深かろう。
近世までは、古典文学、また俳句や和歌に詠い継がれた地が日本人の見るすべき"観光地"であり、その様式化された風景を踏まえて表現をすることがステイタスだったのだろう。それ以外の景色は見向きされなかった。朝鮮通信使もまた九州から近畿へ抜ける航行で、中国文化に由来する漢詩チックな風景をもて囃した。だから、瀬戸内海の自然の風景が称賛されたというのは地学・地理学的知識を持った西洋人が来航し、国内を行き来するようになってからの話であり、日本の知識人がそれに影響され、広がったというのが実のところではないかと思う。
地元民にとって瀬戸内海は、愛着はあれど「ほんまに海か?」と茶化すような当たり前の存在である。私は長年、太平洋のほうが雄大で偉いと思ってきた。しかしこうまで評されると、なにやらかけがえのないものに思われてきた。料金の馬鹿高いガンツウも、インバウンド狙いの時代になるほどそういった客層を狙ってのものなのだと理解した。そのガンツウには乗れそうもない庶民である私は、年に一日だけ近畿から九州へ航行している「昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ」を発見し、来年狙うことにした。わくわくする。読んでよかった。
読了日:11月26日 著者:西田 正憲
 日本人の給料 (宝島社新書)の感想
日本人の給料 (宝島社新書)の感想専門家が解析してみせる日本の経済や政策の如何は理解しきれないのだが、政財界や外資系コンサルなどが煽ってなんとなく日本に充満している「今の常識」は耳に入れなくていいということはわかった。時代が変わろうと、日本の「良い企業」の条件は変わらない。肌感覚を鋭敏にし、世間の潮流には馬耳東風で構わない。とはいえ、資本主義による弊害と日本政府の失策による弊害は混然として、法律で雁字搦めになっている地方の中小企業にとって、これが会社にも従業員にもひいては客にも良いと言える仕組みはなかなか難しい。結局悩むしかないのだが。
読了日:11月25日 著者:浜 矩子,城 繁幸,野口 悠紀雄,ほか

 ワニの町へ来たスパイ (創元推理文庫)の感想
ワニの町へ来たスパイ (創元推理文庫)の感想評判通りの面白さであっという間に読み終わってしまった。老いた男が元気なのは微笑ましいが、老いた女が元気なのは痛快だ。こんな老後を過ごしたい。無理だけど。あり得ないけど。舞台がディープサウスってのも、都会とは違った未知の要素てんこ盛りでわくわくする。ロマンス要素ももれなくついてて、続き読んじゃうなあ、これ。この調子で続々仕留めてたら、シリーズ終盤には町の人口半減してるんじゃないかと心配。
読了日:11月19日 著者:ジャナ・デリオン

 ぼくはウーバーで捻挫し、山でシカと闘い、水俣で泣いたの感想
ぼくはウーバーで捻挫し、山でシカと闘い、水俣で泣いたの感想「アマゾンの倉庫で絶望し、~」をふまえたようなタイトル。こちらは潜入ではなく取材、毎日新聞の連載だ。枚挙に暇無い社会問題の現地に斎藤幸平は出かけて行く。字数制限もあり、各々への所感はあっさりしている。思想家と自称する斎藤幸平は、自分が当事者でない、理不尽を振りかざす立場にないと自覚している。それでもこうして書く、自身の立ち位置への逡巡が巻末で吐露される。しかし自身結論するとおり、直接取材することで肌に感じ共有することには意味がある。加えて、実経験の積み重ねは斎藤幸平の言霊を育てるだろう。次作が楽しみです。
読了日:11月17日 著者:斎藤 幸平

 ねじねじ録の感想
ねじねじ録の感想藤崎彩織はごく平均的な家庭で育った女性だ。学生時代や新しい家族の日々を描き、女性が抱える諸問題を考え、セカオワの裏話も書く。話題のバランスを配慮しているのが窺える。孤独を抱え、不眠に悩んだ時期が彼女にもある。負けず嫌いなのに悩み性だから今もねじねじする。それらがセカオワの曲に通底する祈りと希望に昇華しているのだと納得。ライブでのあの満ち足りた笑顔の裏側に数えきれない涙があると知れば、大切に思える曲も新たに増えたのは嬉しいボーナスだった。2019年のライブ前が実は解散の危機崖っぷちだった、なんて心臓に悪い。
読了日:11月12日 著者:藤崎 彩織

 脳科学者の母が、認知症になる: 記憶を失うと、その人は“その人"でなくなるのか?の感想
脳科学者の母が、認知症になる: 記憶を失うと、その人は“その人"でなくなるのか?の感想認知症がいかに今の生活から地続きであることか。「認知症世界の歩き方」が、認知症を患った本人にとって世界がどのように変貌して見えるかだったのに対し、こちらは認知症と診断された家族が呈する症状への解釈の実践である。人間が知覚する情報量は膨大だ。それを取捨選択し、絞り込み、処理する能力は、脳機能の経年減退に伴い低減する。それは過度な疲労や泥酔時の自分のそれと同種ではないのか。泥酔と違い、回復することなく緩慢に進む症状と折り合うには、できることを自分のペースでやれている実感を本人に維持するのが大事と憶えておく。
『感情は、理性だけではとても対応できないような、不確実な状況で、なんとか人間を動かしてくれるシステム、意思決定をさせてくれるシステムなのである』。物事の理解能力が衰えても、感情的判断は正しいと著者は言う。理性よりも原始的な能力であるところの感情は、人間の生存を助けてきたからだ。健康な人と同じように尊重すべきだし、感情こそその人らしさと結論づけている。『感情は、生まれつきの個性であり、また、認知機能と同じように、その人の人生経験によって発達してきた能力であり、いまだに発達し続けている能力である』。
読了日:11月11日 著者:恩蔵絢子

 化物園 (単行本)の感想
化物園 (単行本)の感想ん。これも、一貫した主題あって書かれた短編集じゃない感じ。ケシヨウ(化生?)の気配を感じるもの、感じないもの、人の性悪、ファンタジー、因果応報、ぶれぶれ。そのケシヨウすら、読みながら存在を忘れてしまうほどの存在感の薄さが、恒川さんの迷走を思わせる。「胡乱の山犬」が好きかな。そこここに暗闇と曖昧があった時代設定もさながら、「彼」の生涯が自然に呑まれる時を迎える展開が好きなのだ。恒川光太郎のなにが好きといって、単なる怪異譚ではない。現実とのズレ感が、空間的時間的に拡がりを持つとき、物語は永遠の性質を帯びる。
読了日:11月10日 著者:恒川 光太郎
 ケアマネジャーはらはら日記の感想
ケアマネジャーはらはら日記の感想先日祖母を見送った。施設に10年近く入っていた。5年前には娘の顔も忘れた。葬儀で伯母たちは「ケアマネさんが良い人でよかった」と言い合った。ケアマネージャーという仕事は小回りの効いた動きを求められ、精神的負担は想像をはるかに超えた。"目配り、気配り、心配り"。不安や困窮を抱えた老人やその家族が、生活に差配する他人に穏やかに接せるとは限らない。その心のケアもなんて大変すぎる。かつその報酬がケアプランの作成料だけとか。ケアする側も全員が心映えや各種処理能力のよくできた聖人ではなく、全てで当たり前ではないと自戒。
読了日:11月02日 著者:岸山真理子

注:
 は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。 2022年11月02日
2022年10月の記録
あらゆることが「大きく、早く」がよしとされる時代に、
読書も「たくさん、早く」と追い立てられているような気がする。
メディアやSNSであれば一歩引いて構えられる私も読書は例外である。
そうでなくても歳と共に時間の流れが速く感じられるようになってきている。
ゆっくり深く読むのが読書の醍醐味と知っていても、
飢えたように紙面に食い入ってしまう秋。
<今月のデータ>
購入9冊、購入費用6,496円。
読了17冊。
積読本319冊(うちKindle本156冊、Honto本6冊)。

10月の読書メーター
読んだ本の数:17
 アメリカがカルトに乗っ取られた! 中絶禁止、銃は野放し、暴走する政教分離の感想
アメリカがカルトに乗っ取られた! 中絶禁止、銃は野放し、暴走する政教分離の感想
ドラマ「SWAT」を観ていると、社会の諸問題が日本にあり得ないレベルで盛り込まれていて、そういえば町山さんが言ってたよなあ、と思い出す。多様ゆえの摩擦を直視し、より公平であろうとする人々と、貧困や教育を受ける権利のはく奪によりそれを受け入れることができない人々、多様性に飲み込まれまいと既得権益を振りかざす人々が取り上げられている。町山さん自身のSFとの出会いから始まる「オタク差別をやめろ」がエッセイとして秀逸。何かを深く愛するって素敵なことだ。笑いに乗せて伝えるって高度な技だ。聞こえましたか、文春さん?
アメリカの民主党と共和党の関係を、日本の自民党と野党の関係に照らし合わせてみると、民主主義の制度を基盤とする限り同じ問題を抱えているとわかる。しかし、今の世界的なインフレ圧力下において、なにもかもが極端な方向に動こうとするなかで、アメリカでは民主党から共和党に主導権が移行しそうなのに対し、日本では自民党が劣勢に立たされつつも野党が常軌を逸した動きで支持を失っているように見え、結果自民党優位が保たれるのではないかと危惧される。総じて、未来が明るいとは、どうしても思えないのだ。
読了日:10月31日 著者:町山 智浩
 すばらしい新世界 (光文社古典新訳文庫)の感想
すばらしい新世界 (光文社古典新訳文庫)の感想
この世界に登場したジョンが好ましく見える。それは一見ユートピアを模しながら、かつ人々が別段不満を持っていないにもかかわらず、読む私が息苦しさを感じる性質のものだからだろう。私はディストピア小説を街中で読むのが好きだ。現実の世界が小説の世界のようではないことにほっとすると同時に、現実の世界に小説の世界の要素を感じ取って眩惑するのを好む。自然、揺らぎ、不確定さ、自ら何かを創り上げることの達成感、喜び。そういった実感を深く味わって私たちは生きているだろうか? 覚悟を持ち得なかったバーナードのふるまいを笑えるか?
読了日:10月30日 著者:オルダス ハクスリー
 古(いにしえ)の武術に学ぶ無意識のちから - 広大な潜在能力の世界にアクセスする“フロー"への入り口 - (ワニプラス)の感想
古(いにしえ)の武術に学ぶ無意識のちから - 広大な潜在能力の世界にアクセスする“フロー"への入り口 - (ワニプラス)の感想
『人間の運命は完ぺきに決まっていて、完璧に自由である』。若い頃に得た直観以降、求道者として甲野先生の気に留まった世間の事柄や、一般的な認識に反する事象、身体のありようについてたくさんの所見が述べられている。武術に限らない。自分の意志では発揮できない能力や、意識で知覚できないために現実を超越したもののように感じられる事象が遍在すると知ること、それを拡げる方向へ自分の身体を置くようにすることは大事だ。人間即ち自然の摂理。「三脈」は憶えておいて、なんかヤバいなと思ったら必ずやる。ズレたら駄目。念のため。
読了日:10月28日 著者:甲野 善紀,前野 隆司
 植物はそこまで知っている: 感覚に満ちた世界に生きる植物たち (河出文庫)の感想
植物はそこまで知っている: 感覚に満ちた世界に生きる植物たち (河出文庫)の感想
植物には脳も神経もない。だからといって、芽を出し、生長し、花を咲かせ、種をつくって枯れる機能を持った機械ではない。植物は…人間が生体を表わす言葉では表現しづらい。擬人化では、誤ったニュアンスが人間側に返ってくる。だからこの本の「知っている(know)」は言い得て妙だと感心した。研究では植物の持つ能力を知るために、通常の植物のほか、化学薬品に晒してDNA変異を誘発した植物を用いて比較検証などの実験をするそうだ。見る、嗅ぐ、感じる、聞く、憶える…。彼らが生きるために、必要な能力だ。でも、やっぱり不思議な感じ。
読了日:10月22日 著者:ダニエル・チャモヴィッツ
 トラックドライバーにも言わせて (新潮新書)の感想
トラックドライバーにも言わせて (新潮新書)の感想
聞いて初めて、知らなかったと自覚する事柄が世界にはたくさんある。日本の運送業界は需要の増大につれて問題を混迷させている。これを読んでからというもの数日、道行く大型トラックを珍しいものでも見つけたかのように観察してしまう。そもそもの大型トラックの仕組みすら知らなかったのだ。エアブレーキの特性、荷積みの難しさ、車体を止める技術、死角。急ブレーキをかければとんでもない破壊力を持つからこそ、ドライバーは客や周りの自家用車らの無理解と横暴にブチ切れることなく、マナーを守り、命を削る。これはなんとかせんといかんで。
読了日:10月20日 著者:橋本 愛喜(はしもと あいき)
 半農半林で暮らしを立てる―資金ゼロからのIターン田舎暮らし入門の感想
半農半林で暮らしを立てる―資金ゼロからのIターン田舎暮らし入門の感想
何の技能も持たないまま、人間社会の行く末を憂えて、農林業従事者へ転身。人が事を始めるのに遅すぎることはないという考えに賛成だが、無鉄砲という名の踏み切りの良さを体力気力で補える若さはこのケースには必要である。林業、除雪、米づくりを柱にした設計。意識高いところから入っているので、米づくりは手植え・手刈りから入り、必要を実感しては小型、より大型の農機具へ切り替える遠回り加減に好感。これは売る米の量など、本人の目的と農地面積によって違ってくるだろう。自分の身体を使って、改めて得る種苗法や農薬への考えが興味深い。
読了日:10月17日 著者:市井 晴也
 【2021年本屋大賞 翻訳小説部門 第1位】ザリガニの鳴くところの感想
【2021年本屋大賞 翻訳小説部門 第1位】ザリガニの鳴くところの感想
カイアとテイト。カイアとチェイス。あるいはジャンピン。人が他者に近づく、人が他者を受け入れる、人が他者と生きていくとは、と原初的な問いが絶えず浮かぶのは、カイアの孤独ゆえである。あまりに切ない境遇と引き換えにカイアが得たのは大いなる自然との一体感。潟湖の生態系がこんなに豊かとは知らなかった。自然の中にいるカイアはずっと見ていたいほど自由で美しかった。潟湖や海の景色が心象と寄り添ったり歯向かったりと、雄大に物語る。カイアは40年近くをこのうえなく幸せに生きた。そう信じることが、私にいちばんの満足感を与える。
貝殻の伏線も劇的に回収される。カイアがしたことは裏切りだろうか? カイアが独学で得た生物学の知識が、彼女の行動を方向づけたことは間違いない。『命の時計の針が動きつづけている限り、そこには醜いものなど何ひとつないように思えた。これは自然界の暗い側面などではなく、何としても困難を乗り越えるために編み出された方策なのだ。それが人間となれば、もっとたくさんの策を講じたとしても不思議はないだろう』。絵も詩も、得たものは全て生きることを助けた。それが人間社会のルールに沿うかどうかは、結果論なのだと思った。
「潟湖」が何回辞書で確認しても読み方を憶えられず、読み終えた今も怪しいので書いておく。"せきこ"。つい"かたこ"と読んでしまう…。
読了日:10月16日 著者:ディーリア・オーエンズ
 アジア未知動物紀行 ベトナム・奄美・アフガニスタン (講談社文庫)の感想
アジア未知動物紀行 ベトナム・奄美・アフガニスタン (講談社文庫)の感想
あれれ。私、これ好きだな。いつも高野さんが探しに出かけている外国のだと、「ああ、未知生物ね。UMAね。」とそのまんま受け取ってしまうのだけれど、奄美となると生物のような精霊のようなあやかしのような、微妙な差を肌に感じる(気がする)のは不思議な現象だ。キジムナーもケンモンもいるよ。だって会った人がいるんだしさ。白いヤギもそうじゃない?と信じる人の気持ちにぐっと近づくことができる(気がする)。それでいて、奄美方言は異国的でもあって、ぞくっとする。アフガニスタンもこれはこれで鮮やかな視界の転回が興味深い。
読了日:10月13日 著者:高野 秀行
 母の記憶に (ケン・リュウ短篇傑作集3)の感想
母の記憶に (ケン・リュウ短篇傑作集3)の感想
ハードボイルドなSFも書けるケン・リュウいいね! こちらは東洋風味控えめの短編集。来たるべき未来への不安を突くような「ループの中で」と「残されし者」を印象深く受け取る自分を憂鬱に眺める。一方は戦争。科学技術が進んでも人間が攻撃するのは人間。人殺しに加担した呵責は、相対した者にも、安全な場所から無人機を操る者にも、遠隔操作するAIを設計した者にも等しく圧しかかる。無間地獄。他方は未来潰えた人類の姿。技術進歩はおろか退却しかない暗黒世界に子孫を遺して、私たちは死ぬのか。子孫の賢さ? 問題はそこではない。
読了日:10月11日 著者:ケン リュウ
 鶴川日記 (PHP文芸文庫)の感想
鶴川日記 (PHP文芸文庫)の感想
夫妻が鶴川村の武相荘を入手したいきさつや暮らしを知りたくて。少しなのが残念。正子さんは田舎暮らしを愛しており、夫君も自らあれこれ手掛け、近隣の人々の助けをも得、さほどの波風なく収まったように受け取れる。戦時下でもあり、華族も農民も現代人とは胆力の桁が違う、と言うべきか。日本において華族の人々が日本文化に果たす役割を思う。富と時間と教養を持った好事家、また研究者として、技術や知識を次世代に伝えねば、日本の価値あるものはぼろぼろと失われてしまう。役割なのだ。また、祖父母の逸話が印象深い。まさしく激動の時代。
『おもうに、維新と名づける破天荒な事業は、祖父が封建武士から陸軍の将官へ、更に海軍提督へと何の躊躇もなく転身したように、過去も未来も打ち捨てて、ひたすら現実の中に飛びこむことのできた人々だけに可能な革命であった。悲しいことに、それは為しとげなければ国が危うい止むに止まれぬ勢いであった。』
読了日:10月11日 著者:白洲 正子
 食べられる庭図鑑の感想
食べられる庭図鑑の感想
この気軽さが好み。庭と畑を区別しない混植スタイル、雑草は抜きすぎないし落ち葉は春まで除かない。気軽に植え、育つものは育て、失敗したら試行錯誤して、その植物とのつき合いかたは自分が決める方式。種は必要なぶんを採取し、残りは庭にばらまくか人にあげる。思わぬところから芽が出るの、いいよなあ。根っこ付きの細ネギや豆苗を植えるのははもちろん、食べた野菜や果物から出てきた種もぽいっと庭に投げて、『種は芽を出したいはず』と待つ。家庭菜園は本職の農家とは違うのだから、きれいな実をたくさんなんて肩肘張らずに楽しめるといい。
読了日:10月10日 著者:良原リエ
 入れ子の水は月に轢かれ (ハヤカワ文庫JA JAオ 16-1)の感想
入れ子の水は月に轢かれ (ハヤカワ文庫JA JAオ 16-1)の感想
沖縄復帰50周年に、沖縄ミステリ。沖縄には地上だけでなく地下にも、複雑で根深い歴史が絡みついている。米軍と日本政府に翻弄された時代と、毎年台風に晒される沖縄、生き抜いたおじいやおばあの過去が事件のベースとなる。『国って平気でグァーシーするのさ』。鶴子おばあは喋りに喋る。ところどころ何を言っているか私にはわからない言葉の奥に、不屈のエネルギーを感じる。著者が妙齢の女性と知って驚いた。謎の性質上、意外だったのだが、女だってしたたかでなければ生き抜けなかった時代のことは、そら書いとかななあ。
読了日:10月08日 著者:オーガニック ゆうき
 小さな声、光る棚 新刊書店Titleの日常の感想
小さな声、光る棚 新刊書店Titleの日常の感想
小さな本屋さんの存在感が年々増していると感じる。店なんて物と金が出入りするだけの場所だと思ってきたからか、この歳になって小さな本屋さんに出会って、本屋という静かな磁場に、変わらず迎えてくれる店主がいることを、ありがたいことだなあと思う。知らない本が並んでいる棚、という意味では、我が家の積読棚も同じだ。本屋さんと同じように静かで豊かで魅力的かと目を遣り、安心する。眺めているだけで知らず時が経つ。まだ読んでいない本でも今必要でない本でも、そこにあるだけで既に仕事をはたしているという言葉に同意して満ち足りる。
読了日:10月04日 著者:辻山 良雄
 認知症世界の歩き方の感想
認知症世界の歩き方の感想
母が認知症に足を突っ込みかけているので、先回りして知っておこうと思った。なにぶん自分の非を認めることができず、私のせいにする習慣が既に構築されている。確認できたのは、症状は人によって違うこと。周りが違和感を持つ行動には理由があること。本人が誰より混乱していること。かといって理不尽になじられて腹を立てないほど人間出来ていないので処しようを知りたかったが、本人の中で起きる事象がメイン。本人が混乱を起こしにくい環境を整えること。いずれ、本人も家族も知っている方がより良い。本人含め、家族で回し読みすることにした。
読了日:10月04日 著者:筧 裕介
 新・台湾の主張 (PHP新書)の感想
新・台湾の主張 (PHP新書)の感想
2016年、蔡英文が総統に選ばれる直前の著。台湾の戦後史と、台湾という国家の形態、日本との関係について。50年間の統治という名の占領をしでかした日本を、好意的に扱ってくれる台湾人は少なくない。"犬"の後に"豚"が来たから相対的に評価が上がったのもあろうが、それだけじゃない、それはいったい何だろうと考え続けている。李登輝は新渡戸稲造の産業振興と八田與一の治水事業、後藤新平の統治運営改革が台湾を底上げしたと評している。その李登輝の政治的手腕、心理的誘導による部分は大きいと察せられるが、それだけが真実ではない。
読了日:10月03日 著者:李 登輝
 日本のヤバい女の子 覚醒編 (角川文庫)の感想
日本のヤバい女の子 覚醒編 (角川文庫)の感想
日本の古典文学や説話に登場する女性の、置かれた立場や投げ込まれる理不尽を、当人の気持ちを想像して味わう趣向。著者は文学や文化の研究者ではない。しかしずらりと並ぶ巻末の参考文献を見るに、読みはじめたら面白かったんだろうなあ。古代・中世の日本人は、現代人と違う発声で意思疎通したと聞く。私が古典に手が出ないのは、今生きている私と隔絶された「日本」の人々に、理解や共感を持つことが難しいと思っているからだ。習俗も隣国並みに違う。その段差を踏み倒して彼女ら"ヤバい女の子"に想いを寄せる著者は、パワフルかつ情緒豊かだ。
読了日:10月02日 著者:はらだ 有彩
 皮膚の下の頭蓋骨 (ハヤカワ・ミステリ文庫 129-2)の感想
皮膚の下の頭蓋骨 (ハヤカワ・ミステリ文庫 129-2)の感想
孤島の城、クローズドサークル。前作は序章だったのか。と納得しかける程、バーニイの遺したものや革ベルトを糧として、若きコーデリアが本領を発揮する。すなわち観察力の高さもさながら、臆することなく年輩と対等に渡り合い、楽しませることができる知性と教養の発露が眩しい。読むこちらにまったく教養が足りてないのが残念なれど、アイヴォとの対話など読んでいて楽しい。紋切り型の対応と質問でしか事件と相対することができない警察とは対照的である。アクションシーンあり、漁師の男の子との胸キュンシーンあり、良いミステリでした。
読了日:10月01日 著者:P.D.ジェイムズ
注: は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。
読書も「たくさん、早く」と追い立てられているような気がする。
メディアやSNSであれば一歩引いて構えられる私も読書は例外である。
そうでなくても歳と共に時間の流れが速く感じられるようになってきている。
ゆっくり深く読むのが読書の醍醐味と知っていても、
飢えたように紙面に食い入ってしまう秋。
<今月のデータ>
購入9冊、購入費用6,496円。
読了17冊。
積読本319冊(うちKindle本156冊、Honto本6冊)。

10月の読書メーター
読んだ本の数:17
 アメリカがカルトに乗っ取られた! 中絶禁止、銃は野放し、暴走する政教分離の感想
アメリカがカルトに乗っ取られた! 中絶禁止、銃は野放し、暴走する政教分離の感想ドラマ「SWAT」を観ていると、社会の諸問題が日本にあり得ないレベルで盛り込まれていて、そういえば町山さんが言ってたよなあ、と思い出す。多様ゆえの摩擦を直視し、より公平であろうとする人々と、貧困や教育を受ける権利のはく奪によりそれを受け入れることができない人々、多様性に飲み込まれまいと既得権益を振りかざす人々が取り上げられている。町山さん自身のSFとの出会いから始まる「オタク差別をやめろ」がエッセイとして秀逸。何かを深く愛するって素敵なことだ。笑いに乗せて伝えるって高度な技だ。聞こえましたか、文春さん?
アメリカの民主党と共和党の関係を、日本の自民党と野党の関係に照らし合わせてみると、民主主義の制度を基盤とする限り同じ問題を抱えているとわかる。しかし、今の世界的なインフレ圧力下において、なにもかもが極端な方向に動こうとするなかで、アメリカでは民主党から共和党に主導権が移行しそうなのに対し、日本では自民党が劣勢に立たされつつも野党が常軌を逸した動きで支持を失っているように見え、結果自民党優位が保たれるのではないかと危惧される。総じて、未来が明るいとは、どうしても思えないのだ。
読了日:10月31日 著者:町山 智浩

 すばらしい新世界 (光文社古典新訳文庫)の感想
すばらしい新世界 (光文社古典新訳文庫)の感想この世界に登場したジョンが好ましく見える。それは一見ユートピアを模しながら、かつ人々が別段不満を持っていないにもかかわらず、読む私が息苦しさを感じる性質のものだからだろう。私はディストピア小説を街中で読むのが好きだ。現実の世界が小説の世界のようではないことにほっとすると同時に、現実の世界に小説の世界の要素を感じ取って眩惑するのを好む。自然、揺らぎ、不確定さ、自ら何かを創り上げることの達成感、喜び。そういった実感を深く味わって私たちは生きているだろうか? 覚悟を持ち得なかったバーナードのふるまいを笑えるか?
読了日:10月30日 著者:オルダス ハクスリー

 古(いにしえ)の武術に学ぶ無意識のちから - 広大な潜在能力の世界にアクセスする“フロー"への入り口 - (ワニプラス)の感想
古(いにしえ)の武術に学ぶ無意識のちから - 広大な潜在能力の世界にアクセスする“フロー"への入り口 - (ワニプラス)の感想『人間の運命は完ぺきに決まっていて、完璧に自由である』。若い頃に得た直観以降、求道者として甲野先生の気に留まった世間の事柄や、一般的な認識に反する事象、身体のありようについてたくさんの所見が述べられている。武術に限らない。自分の意志では発揮できない能力や、意識で知覚できないために現実を超越したもののように感じられる事象が遍在すると知ること、それを拡げる方向へ自分の身体を置くようにすることは大事だ。人間即ち自然の摂理。「三脈」は憶えておいて、なんかヤバいなと思ったら必ずやる。ズレたら駄目。念のため。
読了日:10月28日 著者:甲野 善紀,前野 隆司
 植物はそこまで知っている: 感覚に満ちた世界に生きる植物たち (河出文庫)の感想
植物はそこまで知っている: 感覚に満ちた世界に生きる植物たち (河出文庫)の感想植物には脳も神経もない。だからといって、芽を出し、生長し、花を咲かせ、種をつくって枯れる機能を持った機械ではない。植物は…人間が生体を表わす言葉では表現しづらい。擬人化では、誤ったニュアンスが人間側に返ってくる。だからこの本の「知っている(know)」は言い得て妙だと感心した。研究では植物の持つ能力を知るために、通常の植物のほか、化学薬品に晒してDNA変異を誘発した植物を用いて比較検証などの実験をするそうだ。見る、嗅ぐ、感じる、聞く、憶える…。彼らが生きるために、必要な能力だ。でも、やっぱり不思議な感じ。
読了日:10月22日 著者:ダニエル・チャモヴィッツ

 トラックドライバーにも言わせて (新潮新書)の感想
トラックドライバーにも言わせて (新潮新書)の感想聞いて初めて、知らなかったと自覚する事柄が世界にはたくさんある。日本の運送業界は需要の増大につれて問題を混迷させている。これを読んでからというもの数日、道行く大型トラックを珍しいものでも見つけたかのように観察してしまう。そもそもの大型トラックの仕組みすら知らなかったのだ。エアブレーキの特性、荷積みの難しさ、車体を止める技術、死角。急ブレーキをかければとんでもない破壊力を持つからこそ、ドライバーは客や周りの自家用車らの無理解と横暴にブチ切れることなく、マナーを守り、命を削る。これはなんとかせんといかんで。
読了日:10月20日 著者:橋本 愛喜(はしもと あいき)

 半農半林で暮らしを立てる―資金ゼロからのIターン田舎暮らし入門の感想
半農半林で暮らしを立てる―資金ゼロからのIターン田舎暮らし入門の感想何の技能も持たないまま、人間社会の行く末を憂えて、農林業従事者へ転身。人が事を始めるのに遅すぎることはないという考えに賛成だが、無鉄砲という名の踏み切りの良さを体力気力で補える若さはこのケースには必要である。林業、除雪、米づくりを柱にした設計。意識高いところから入っているので、米づくりは手植え・手刈りから入り、必要を実感しては小型、より大型の農機具へ切り替える遠回り加減に好感。これは売る米の量など、本人の目的と農地面積によって違ってくるだろう。自分の身体を使って、改めて得る種苗法や農薬への考えが興味深い。
読了日:10月17日 著者:市井 晴也
 【2021年本屋大賞 翻訳小説部門 第1位】ザリガニの鳴くところの感想
【2021年本屋大賞 翻訳小説部門 第1位】ザリガニの鳴くところの感想カイアとテイト。カイアとチェイス。あるいはジャンピン。人が他者に近づく、人が他者を受け入れる、人が他者と生きていくとは、と原初的な問いが絶えず浮かぶのは、カイアの孤独ゆえである。あまりに切ない境遇と引き換えにカイアが得たのは大いなる自然との一体感。潟湖の生態系がこんなに豊かとは知らなかった。自然の中にいるカイアはずっと見ていたいほど自由で美しかった。潟湖や海の景色が心象と寄り添ったり歯向かったりと、雄大に物語る。カイアは40年近くをこのうえなく幸せに生きた。そう信じることが、私にいちばんの満足感を与える。
貝殻の伏線も劇的に回収される。カイアがしたことは裏切りだろうか? カイアが独学で得た生物学の知識が、彼女の行動を方向づけたことは間違いない。『命の時計の針が動きつづけている限り、そこには醜いものなど何ひとつないように思えた。これは自然界の暗い側面などではなく、何としても困難を乗り越えるために編み出された方策なのだ。それが人間となれば、もっとたくさんの策を講じたとしても不思議はないだろう』。絵も詩も、得たものは全て生きることを助けた。それが人間社会のルールに沿うかどうかは、結果論なのだと思った。
「潟湖」が何回辞書で確認しても読み方を憶えられず、読み終えた今も怪しいので書いておく。"せきこ"。つい"かたこ"と読んでしまう…。
読了日:10月16日 著者:ディーリア・オーエンズ

 アジア未知動物紀行 ベトナム・奄美・アフガニスタン (講談社文庫)の感想
アジア未知動物紀行 ベトナム・奄美・アフガニスタン (講談社文庫)の感想あれれ。私、これ好きだな。いつも高野さんが探しに出かけている外国のだと、「ああ、未知生物ね。UMAね。」とそのまんま受け取ってしまうのだけれど、奄美となると生物のような精霊のようなあやかしのような、微妙な差を肌に感じる(気がする)のは不思議な現象だ。キジムナーもケンモンもいるよ。だって会った人がいるんだしさ。白いヤギもそうじゃない?と信じる人の気持ちにぐっと近づくことができる(気がする)。それでいて、奄美方言は異国的でもあって、ぞくっとする。アフガニスタンもこれはこれで鮮やかな視界の転回が興味深い。
読了日:10月13日 著者:高野 秀行

 母の記憶に (ケン・リュウ短篇傑作集3)の感想
母の記憶に (ケン・リュウ短篇傑作集3)の感想ハードボイルドなSFも書けるケン・リュウいいね! こちらは東洋風味控えめの短編集。来たるべき未来への不安を突くような「ループの中で」と「残されし者」を印象深く受け取る自分を憂鬱に眺める。一方は戦争。科学技術が進んでも人間が攻撃するのは人間。人殺しに加担した呵責は、相対した者にも、安全な場所から無人機を操る者にも、遠隔操作するAIを設計した者にも等しく圧しかかる。無間地獄。他方は未来潰えた人類の姿。技術進歩はおろか退却しかない暗黒世界に子孫を遺して、私たちは死ぬのか。子孫の賢さ? 問題はそこではない。
読了日:10月11日 著者:ケン リュウ
 鶴川日記 (PHP文芸文庫)の感想
鶴川日記 (PHP文芸文庫)の感想夫妻が鶴川村の武相荘を入手したいきさつや暮らしを知りたくて。少しなのが残念。正子さんは田舎暮らしを愛しており、夫君も自らあれこれ手掛け、近隣の人々の助けをも得、さほどの波風なく収まったように受け取れる。戦時下でもあり、華族も農民も現代人とは胆力の桁が違う、と言うべきか。日本において華族の人々が日本文化に果たす役割を思う。富と時間と教養を持った好事家、また研究者として、技術や知識を次世代に伝えねば、日本の価値あるものはぼろぼろと失われてしまう。役割なのだ。また、祖父母の逸話が印象深い。まさしく激動の時代。
『おもうに、維新と名づける破天荒な事業は、祖父が封建武士から陸軍の将官へ、更に海軍提督へと何の躊躇もなく転身したように、過去も未来も打ち捨てて、ひたすら現実の中に飛びこむことのできた人々だけに可能な革命であった。悲しいことに、それは為しとげなければ国が危うい止むに止まれぬ勢いであった。』
読了日:10月11日 著者:白洲 正子

 食べられる庭図鑑の感想
食べられる庭図鑑の感想この気軽さが好み。庭と畑を区別しない混植スタイル、雑草は抜きすぎないし落ち葉は春まで除かない。気軽に植え、育つものは育て、失敗したら試行錯誤して、その植物とのつき合いかたは自分が決める方式。種は必要なぶんを採取し、残りは庭にばらまくか人にあげる。思わぬところから芽が出るの、いいよなあ。根っこ付きの細ネギや豆苗を植えるのははもちろん、食べた野菜や果物から出てきた種もぽいっと庭に投げて、『種は芽を出したいはず』と待つ。家庭菜園は本職の農家とは違うのだから、きれいな実をたくさんなんて肩肘張らずに楽しめるといい。
読了日:10月10日 著者:良原リエ
 入れ子の水は月に轢かれ (ハヤカワ文庫JA JAオ 16-1)の感想
入れ子の水は月に轢かれ (ハヤカワ文庫JA JAオ 16-1)の感想沖縄復帰50周年に、沖縄ミステリ。沖縄には地上だけでなく地下にも、複雑で根深い歴史が絡みついている。米軍と日本政府に翻弄された時代と、毎年台風に晒される沖縄、生き抜いたおじいやおばあの過去が事件のベースとなる。『国って平気でグァーシーするのさ』。鶴子おばあは喋りに喋る。ところどころ何を言っているか私にはわからない言葉の奥に、不屈のエネルギーを感じる。著者が妙齢の女性と知って驚いた。謎の性質上、意外だったのだが、女だってしたたかでなければ生き抜けなかった時代のことは、そら書いとかななあ。
読了日:10月08日 著者:オーガニック ゆうき

 小さな声、光る棚 新刊書店Titleの日常の感想
小さな声、光る棚 新刊書店Titleの日常の感想小さな本屋さんの存在感が年々増していると感じる。店なんて物と金が出入りするだけの場所だと思ってきたからか、この歳になって小さな本屋さんに出会って、本屋という静かな磁場に、変わらず迎えてくれる店主がいることを、ありがたいことだなあと思う。知らない本が並んでいる棚、という意味では、我が家の積読棚も同じだ。本屋さんと同じように静かで豊かで魅力的かと目を遣り、安心する。眺めているだけで知らず時が経つ。まだ読んでいない本でも今必要でない本でも、そこにあるだけで既に仕事をはたしているという言葉に同意して満ち足りる。
読了日:10月04日 著者:辻山 良雄

 認知症世界の歩き方の感想
認知症世界の歩き方の感想母が認知症に足を突っ込みかけているので、先回りして知っておこうと思った。なにぶん自分の非を認めることができず、私のせいにする習慣が既に構築されている。確認できたのは、症状は人によって違うこと。周りが違和感を持つ行動には理由があること。本人が誰より混乱していること。かといって理不尽になじられて腹を立てないほど人間出来ていないので処しようを知りたかったが、本人の中で起きる事象がメイン。本人が混乱を起こしにくい環境を整えること。いずれ、本人も家族も知っている方がより良い。本人含め、家族で回し読みすることにした。
読了日:10月04日 著者:筧 裕介
 新・台湾の主張 (PHP新書)の感想
新・台湾の主張 (PHP新書)の感想2016年、蔡英文が総統に選ばれる直前の著。台湾の戦後史と、台湾という国家の形態、日本との関係について。50年間の統治という名の占領をしでかした日本を、好意的に扱ってくれる台湾人は少なくない。"犬"の後に"豚"が来たから相対的に評価が上がったのもあろうが、それだけじゃない、それはいったい何だろうと考え続けている。李登輝は新渡戸稲造の産業振興と八田與一の治水事業、後藤新平の統治運営改革が台湾を底上げしたと評している。その李登輝の政治的手腕、心理的誘導による部分は大きいと察せられるが、それだけが真実ではない。
読了日:10月03日 著者:李 登輝

 日本のヤバい女の子 覚醒編 (角川文庫)の感想
日本のヤバい女の子 覚醒編 (角川文庫)の感想日本の古典文学や説話に登場する女性の、置かれた立場や投げ込まれる理不尽を、当人の気持ちを想像して味わう趣向。著者は文学や文化の研究者ではない。しかしずらりと並ぶ巻末の参考文献を見るに、読みはじめたら面白かったんだろうなあ。古代・中世の日本人は、現代人と違う発声で意思疎通したと聞く。私が古典に手が出ないのは、今生きている私と隔絶された「日本」の人々に、理解や共感を持つことが難しいと思っているからだ。習俗も隣国並みに違う。その段差を踏み倒して彼女ら"ヤバい女の子"に想いを寄せる著者は、パワフルかつ情緒豊かだ。
読了日:10月02日 著者:はらだ 有彩

 皮膚の下の頭蓋骨 (ハヤカワ・ミステリ文庫 129-2)の感想
皮膚の下の頭蓋骨 (ハヤカワ・ミステリ文庫 129-2)の感想孤島の城、クローズドサークル。前作は序章だったのか。と納得しかける程、バーニイの遺したものや革ベルトを糧として、若きコーデリアが本領を発揮する。すなわち観察力の高さもさながら、臆することなく年輩と対等に渡り合い、楽しませることができる知性と教養の発露が眩しい。読むこちらにまったく教養が足りてないのが残念なれど、アイヴォとの対話など読んでいて楽しい。紋切り型の対応と質問でしか事件と相対することができない警察とは対照的である。アクションシーンあり、漁師の男の子との胸キュンシーンあり、良いミステリでした。
読了日:10月01日 著者:P.D.ジェイムズ

注:
 は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。 2022年10月01日
2022年9月の記録
内田樹先生の講演を聴きに行った。
初めて聞く先生の声は柔らかかった。意外に感じた。
ルヌガンガさんが内田先生の本を持って来ていて、サインが頂けるということで1冊を急いで選んだ。
ちらと危惧したとおり、1年前に既に読んでおり、しかも比較的気に入らなかったものだった。
安田先生との対談本にすればよかった。
しかし内田先生に私の言葉を伝えて、にっこり笑っていただいたことは忘れない。
<今月のデータ>
購入19冊、購入費用21,977円。
読了15冊。
積読本328冊(うちKindle本161冊、Honto本6冊)。

9月の読書メーター
 女には向かない職業 (ハヤカワ・ミステリ文庫)の感想
女には向かない職業 (ハヤカワ・ミステリ文庫)の感想
修道院で暮らした過去や、他人を安易に容れない性格による、ドライな世界観を持った若い探偵という設定。若干こなれない、上滑りな印象を受けるのは、シリーズ初作だからか。依頼を受け、予想外に淡々と乗り込んだカテージは、真実が明るみに出るにつれて穏やかな明るい隠れ家からおぞましい悪意に浸食された空き家へ変貌する。その過程もどこかしっくりこない感触だが、この物語の読みどころは事件解決後、ダルグリッシュ警視との攻防戦なのだ。このダルグリッシュ警視がシリーズ本流らしく、引力のある登場人物。買っちゃってるので続編を読む。
読了日:09月25日 著者:P.D.ジェイムズ
 営繕かるかや怪異譚 その弐 (角川文庫)の感想
営繕かるかや怪異譚 その弐 (角川文庫)の感想
違和感、気配と経て、怪異は凝って視覚化する。その経緯を書くのが小野さんは上手いのである。ていうか、今回は具現化しすぎて、これはこれで怖い。紐とか鎌とか、悪霊シリーズの再現である。中では、物と、人の思いが絡んだ怪異が印象に残った。物に残る魂。リサイクルや古物を取り入れた暮らしは流行りとて、物を大切に使う暮らしとは同義でない。逆に粗末にすることもある例である。工夫と横着は違う。『ものを作るのは手間暇かかるものよ。手間暇を惜しむから、あなたはすぐ奇抜なことに走るの』。隅田さんが素敵なキャラになってきた。
読了日:09月22日 著者:小野 不由美
 ビーグル号世界周航記 ダーウィンは何をみたか (講談社学術文庫)の感想
ビーグル号世界周航記 ダーウィンは何をみたか (講談社学術文庫)の感想
航海記そのものではなく、著書からの抜粋を子供向けに編集した本「ビーグル号で世界を巡る旅の中でダーウィン氏が見たもの」の翻訳である。19世紀、ダーウィンが体験した事物が事細かに記録されている。各地の民族や土地の描写を読むのは楽しい。なぜなら、乗馬でボラスの扱いを失敗して南米ガウーチョ人に笑われた逸話や、タヒチ人への開けっぴろげな賛美など、西洋人らしからぬ偏りのない観察眼、旺盛な好奇心と道義心は、正直で愛すべき人物と認定するにじゅうぶんだからだ。原始林を「"自然という神"が生み出した殿堂」と呼ぶのも好ましい。
1835年2月20日11時半、ダーウィンはチリで地震に遭遇する。『ひどい地震はたちまちわれわれの古い連想を破ってしまう。堅固そのものを象徴するような大地が、流体の上のうすい皮のようにわれわれの足元で動いた。地震は一秒で、何時間の反省によっても産みだせないような奇妙な不安な心持を、心の中につくりあげてしまった』。そしてもしイギリスが地震の暴威にさらされたらどのような事態になるかと震撼している。地震に遭ったことがなかったと見える。地震は、地震が頻発する地に生きる民族の精神性に大きな影響を与えているのだろうな。
読了日:09月21日 著者:チャールズ・ロバート・ダーウィン
 おくのほそ道(全) ビギナーズ・クラシックス 日本の古典 (角川ソフィア文庫―ビギナーズ・クラシックス)の感想
おくのほそ道(全) ビギナーズ・クラシックス 日本の古典 (角川ソフィア文庫―ビギナーズ・クラシックス)の感想
ある本を読もうと思って、そういえば原本を読んでいないことに思い至り、さらりと読んでみる。深川の草庵から、芭蕉は自ら荷物を担いで旅に出る。笠敷いたり賽銭踏んだりしては、泣く。感動の誇張表現なのか、あるいは歩いて旅をするという行為が当たり前でも安全でもないゆえに、感情が増幅されるのだろうか。実際に歩いてみたらわかるのだろうか。先達の詠んだ和歌や俳句への知識が深い。当然、記憶している。この旅は、知己を訪ねる旅でもなく、名所巡りでもなく、先達の足跡を辿る旅だったのだろう。安田先生の芭蕉を歩く旅の、あれも読もう。
読了日:09月19日 著者:松尾芭蕉
 「十二国記」30周年記念ガイドブックの感想
「十二国記」30周年記念ガイドブックの感想
もうガイドブックなんて読んでも目新しい発見は無いくらい繰り返し読んできたと自信はありつつ、小野主上のインタビューと短編はやはり逃がせないと購入。辻村深月のエッセイが上手くて、同じ時間を共有した者としてじんと震える。そしてなんといっても小野さんの肉声である。悪霊シリーズ以来、自らの言葉で語られる場がほとんどなくなって、綾辻さんから漏れ聞くだけだったから、、、あれ、そういえば何年か前のインタビュー誌はどこへいったっけ? ともかくお身体を大事にしていただきたい。あと、A0サイズの十二国記の地図見てみたいです。
読了日:09月18日 著者:
 これは、アレだなの感想
これは、アレだなの感想
テレビの普及期からよほどメディア漬けでこられたんじゃないかと想像するほど、テレビ、漫画、本、音楽、映画、今はネトフリ他ストリーミング配信まで、あらゆる媒体で発表される作品を渉猟されてきたようだ。そのデータベースを 「これ」から「アレ」へと、古今東西思いのままに発想を飛ばされるのを、こちらは口をぽかんと開けて拝聴していればよいだけだが、ご本人にはかなり大変な作業になったらしい。たくさんの作品の「これ」と「アレ」を見定めてゆけば、生まれる感動が薄れるかと思えばそうではないらしく、「鬼滅の刃」は泣くらしい。
読了日:09月17日 著者:高橋 源一郎
 破船 (新潮文庫)の感想
破船 (新潮文庫)の感想
極貧の漁村。タコ、イワシ、サンマ、塩と、自然の恵みに依存した営みは季節に沿い正しく繰り返される。漁獲は村人の糧の多寡に直結し、頻繁に身売りが行われる。物語の中で季節は執拗に繰り返され、お船様が現れた頃には読み手も生き延びるためのムラの論理をやむなく思い始める。しかしそれは、村外の人間の死と表裏だ。著者が描きたかったのは、その貧しき人の心のさもしさと生々しい生への執着の捻じれなのだろう。幼い伊作は父親に代わり、漁に出る。年ごとに上手くなり、家の母や弟妹を想う。そんな日々の積み重ねも疫病によって無に帰すのだ。
この村は、穀物の栽培もおぼつかず、漁獲が少なければ即、飢えてしまう。数年に一度の破船から奪ったもので数年を食いつなぐ、つまり破船が無ければ生きていけないから、破船をお船様と呼んで乞い願うようになる。この村には、未来があってはならないのだ。病んだ者ではなく、病まなかった者が出て行けばよかったのに。
読了日:09月15日 著者:吉村 昭
 エネルギーをめぐる旅――文明の歴史と私たちの未来の感想
エネルギーをめぐる旅――文明の歴史と私たちの未来の感想
ブラボー! 感動未だ冷めやらず。石油会社の一社員の立ち位置にありながら、偏らない姿勢でエネルギーという巨大テーマに深い関心を持ち続ける意志がすごい。そして人がライフワークを抱いていると、様々な方面から知は集まってくる。すなわち、専攻の化学分野に留まらず、科学、哲学、歴史、地学と多角的に情報を整理し、エネルギーという抽象的な存在の本質に迫ることで人類の未来に希望を見出そうとする著者の誠実な試みは、人間の英知そのものと呼びたい。さらにそれを他者に分け与えんと執筆の労を担ってくださった著者に心から敬意を表する。
『エネルギー問題とは、単に技術革新に期待するだけでは解決できない複雑な問題』『安易な技術革新信仰を捨て、より深いところでエネルギー問題に正対すること』『環境負荷を全く気にすることなく人類が好き勝手に使ってよいような完璧なエネルギー源など、そもそもこの世には存在しない』『個々の省エネ技術はむしろ社会全体のエネルギー消費量を増やす傾向があるとなると、知識の蓄積で成り立っている現代文明を維持・発展させていくためには、エネルギー消費量を引き続き増やし続けていくほか手立てがなくなってしまいます。』
著者は核融合反応による原子力発電を希望の発電システムと見定めている。しかしその実現には世界中の英知と資本を結集した開発によって、今の人類の技術からはずっと先の技術革新を成さなければならない。目下としては、ヒトの脳が持つ際限のないエネルギー獲得への欲求を自覚し、太陽光エネルギー、水素、省エネ、地産地消を前提とした分散型システムなど、できること全てをやらなければならないとしている。『何もないところからエネルギーを作り出す技術、ないしはエネルギーの質の劣化を逆転させる技術、そのいずれもが実現不可能なのです』。
「旅のおわりに」と「謝辞」の真摯さ率直さは好ましく、「謝辞」の締めくくりにはほろりとしてしまった。英治出版の社長の心意気にも感謝したい。おかげで著者の英知を私が受け取ることができたのだから。電子書籍の末尾も末尾、いつもなら本を閉じてしまうところに文字を発見。"TO MAKE THE WORLD A BETTER PLACE - Eiji Press, Inc." かっこいい!
読了日:09月15日 著者:古舘 恒介
 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー (新潮文庫)の感想
ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー (新潮文庫)の感想
カトリック系の私立小学校から、公立の"元底辺中学校"へ進学。息子君と家族の日々遭遇する事件は、持っている歴史や文化の相違上、日本ではありえず、同時にイギリスの内側でずっと同じ階級にいては当たり前すぎて気づけない種類の問題を可視化する。著者持ち前の元気でパンクな語り口と、社会制度への知識が読み応えに繋がっている。ボランティアの感覚が日本と絶対的に違う。相互扶助の精神が遍在する社会の姿や、多様な人々が共生するにあたって避けられない摩擦の例、それをより良い方向へ変えていこうと組まれる教育の在りかたが興味深い。
読了日:09月12日 著者:ブレイディみかこ
 独りでいるより優しくての感想
独りでいるより優しくての感想
ミステリのようで、つまるところ、黙然の物語であると私は思う。素直でよく笑う少女。泊陽の薄情や、如玉の拒絶に戸惑い、結果として犯罪に加担した苦しさはいかばかりか。それから渡米までの数年間については結局触れられていないが、その後の挙動には影が残る。相手は訳わからんだろう。だから、ジョセフとの関係を取り戻せたことはすごく良かったと感じるのだ。『先へ進む? それはアメリカのもので、私はそれをいいこととは思ってないよ』。芯からアメリカナイズされるのではなく、黙然が黙然であるところの女性で在れる結末を好ましく思った。
読了日:09月10日 著者:イーユン リー
 にごりえの感想
にごりえの感想
文体が好きで、何度か読んでいたはずなのに、「文人悪妻」にちらりと出た結末に覚えがなかった自分に驚く。いやー、お力が健気で、かわいらしいやらいたわしいやらで、そちらが印象に強くて、最終章のがらりと展開してチョンと終わる、テンポの加減のせいかしら。「曽根崎心中」とやや混同している向きもあり。刀傷の描写をじっくりと読むと、お力の振舞いがまざまざと見えるようであり、やっぱりなんとも痛ましい物語である。
読了日:09月06日 著者:樋口 一葉
 文人悪妻 (新潮文庫)の感想
文人悪妻 (新潮文庫)の感想
男性向け週刊誌の連載かと勘繰るノリと、女性たちの精気と色気に中てられてクラクラしてくる。流れでたまたま「文人」と題しただけで、さして「悪」妻でもない。森しげでもさほど悪く書かれていない。むしろ、妻の役目を務め上げた、あるいは強かに生き抜いた明治~昭和時代の著名な男性の伴侶、または自身が著名な女性への賛歌である。男性にしろ女性にしろ、文人という人種の伴侶は難しい。しかし、その人生経験を見事に文学作品に昇華する姿には、「まじか…」しか出ない。著者の文学への造詣ゆえ、混ぜ込まれる作品を片っ端から漁りたくなる。
読了日:09月06日 著者:嵐山 光三郎
 ウルフ・ウォーズ オオカミはこうしてイエローストーンに復活したの感想
ウルフ・ウォーズ オオカミはこうしてイエローストーンに復活したの感想
オオカミ再導入をいかに成し得たかの記録。野性大型動物の乱獲による急減と、人間と家畜動物の急増が、オオカミによる"被害"を増やした点は同じである。しかし"絶滅"させた日本と違い、アメリカでは国境の向こう側や隣州に同種がいるので、民間人による殺戮と家畜被害の補償の法制化が主である。先にニホンオオカミの本を読んだせいで熱が入らない頭で考える。ある種が100年を生き繋ぐのに、そもそも何頭残っていれば可能だろうか。その頭数のオオカミが、いくら人間の脚が山中で不自由といえ、発見されず生き延びられるか疑問に思えてきた。
先日、鴻池朋子の「みる誕生」を観に行った。知らなかったのだが、鴻池さんはオオカミやキツネの毛皮をいくつも吊るす展示をする。顔も足指もある毛皮に私が動揺していると、学芸員さんが近づいて、「オオカミの毛皮です。日本はいませんが、外国では害獣なので。インターネットで販売されていて、買えるそうです。」と説明した。冬毛だろうか、毒殺だろうか、手の甲で触れたハイイロオオカミの深い毛並みは、名状し難い激情を生んだ。泣きたかった。
読了日:09月04日 著者:ハンク・フィッシャー
 貧困パンデミック――寝ている『公助』を叩き起こすの感想
貧困パンデミック――寝ている『公助』を叩き起こすの感想
2020~2021年の、各支援団体の状況がわかる。新型コロナでもともと不安定だった雇用が奪われ、困窮の末住まいも失った人が急増した。そして福祉崩壊、相談崩壊。支援団体の人々は支援をしながら行政に申入れし、抗議し、地道に変えていく。一方で政治家によるネガキャンは大々的に報道され、確実に人々の心を侵食していく。国の組織としてのしなやかさの欠如が、日本をますます生きづらい場所にする。行政の支援を受けるのに、やりとりを録音しておくべきだなんて常態は酷すぎる。「自助も共助も限界に来ている。今こそ、公助の出番だ」。
読了日:09月03日 著者:稲葉 剛
 「身体」を忘れた日本人 JAPANESE, AND THE LOSS OF PHYSICAL SENSESの感想
「身体」を忘れた日本人 JAPANESE, AND THE LOSS OF PHYSICAL SENSESの感想
2020年に亡くなったC.W.ニコル氏と養老先生の対談、2014年。ニコル氏はアファンの森をつくったり馬を使役したり学校創設に関わったりと活動の幅広く、養老先生も保育園の理事長を引き受けたりされているので、日本の未来を想って、日本の自然や子供のために尽力している共通点がある。"We have to be gardeners"。感覚は違いを発見するもの。意識は同じを見つけるもの。どちらに傾きすぎても生きづらいけれど、感覚の世界の奥深さを忘れては人は生きられないのだよという大切なメッセージ。広い土地欲しい。
読了日:09月03日 著者:養老孟司,C.W.ニコル
注: は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。
初めて聞く先生の声は柔らかかった。意外に感じた。
ルヌガンガさんが内田先生の本を持って来ていて、サインが頂けるということで1冊を急いで選んだ。
ちらと危惧したとおり、1年前に既に読んでおり、しかも比較的気に入らなかったものだった。
安田先生との対談本にすればよかった。
しかし内田先生に私の言葉を伝えて、にっこり笑っていただいたことは忘れない。
<今月のデータ>
購入19冊、購入費用21,977円。
読了15冊。
積読本328冊(うちKindle本161冊、Honto本6冊)。

9月の読書メーター
 女には向かない職業 (ハヤカワ・ミステリ文庫)の感想
女には向かない職業 (ハヤカワ・ミステリ文庫)の感想修道院で暮らした過去や、他人を安易に容れない性格による、ドライな世界観を持った若い探偵という設定。若干こなれない、上滑りな印象を受けるのは、シリーズ初作だからか。依頼を受け、予想外に淡々と乗り込んだカテージは、真実が明るみに出るにつれて穏やかな明るい隠れ家からおぞましい悪意に浸食された空き家へ変貌する。その過程もどこかしっくりこない感触だが、この物語の読みどころは事件解決後、ダルグリッシュ警視との攻防戦なのだ。このダルグリッシュ警視がシリーズ本流らしく、引力のある登場人物。買っちゃってるので続編を読む。
読了日:09月25日 著者:P.D.ジェイムズ

 営繕かるかや怪異譚 その弐 (角川文庫)の感想
営繕かるかや怪異譚 その弐 (角川文庫)の感想違和感、気配と経て、怪異は凝って視覚化する。その経緯を書くのが小野さんは上手いのである。ていうか、今回は具現化しすぎて、これはこれで怖い。紐とか鎌とか、悪霊シリーズの再現である。中では、物と、人の思いが絡んだ怪異が印象に残った。物に残る魂。リサイクルや古物を取り入れた暮らしは流行りとて、物を大切に使う暮らしとは同義でない。逆に粗末にすることもある例である。工夫と横着は違う。『ものを作るのは手間暇かかるものよ。手間暇を惜しむから、あなたはすぐ奇抜なことに走るの』。隅田さんが素敵なキャラになってきた。
読了日:09月22日 著者:小野 不由美
 ビーグル号世界周航記 ダーウィンは何をみたか (講談社学術文庫)の感想
ビーグル号世界周航記 ダーウィンは何をみたか (講談社学術文庫)の感想航海記そのものではなく、著書からの抜粋を子供向けに編集した本「ビーグル号で世界を巡る旅の中でダーウィン氏が見たもの」の翻訳である。19世紀、ダーウィンが体験した事物が事細かに記録されている。各地の民族や土地の描写を読むのは楽しい。なぜなら、乗馬でボラスの扱いを失敗して南米ガウーチョ人に笑われた逸話や、タヒチ人への開けっぴろげな賛美など、西洋人らしからぬ偏りのない観察眼、旺盛な好奇心と道義心は、正直で愛すべき人物と認定するにじゅうぶんだからだ。原始林を「"自然という神"が生み出した殿堂」と呼ぶのも好ましい。
1835年2月20日11時半、ダーウィンはチリで地震に遭遇する。『ひどい地震はたちまちわれわれの古い連想を破ってしまう。堅固そのものを象徴するような大地が、流体の上のうすい皮のようにわれわれの足元で動いた。地震は一秒で、何時間の反省によっても産みだせないような奇妙な不安な心持を、心の中につくりあげてしまった』。そしてもしイギリスが地震の暴威にさらされたらどのような事態になるかと震撼している。地震に遭ったことがなかったと見える。地震は、地震が頻発する地に生きる民族の精神性に大きな影響を与えているのだろうな。
読了日:09月21日 著者:チャールズ・ロバート・ダーウィン

 おくのほそ道(全) ビギナーズ・クラシックス 日本の古典 (角川ソフィア文庫―ビギナーズ・クラシックス)の感想
おくのほそ道(全) ビギナーズ・クラシックス 日本の古典 (角川ソフィア文庫―ビギナーズ・クラシックス)の感想ある本を読もうと思って、そういえば原本を読んでいないことに思い至り、さらりと読んでみる。深川の草庵から、芭蕉は自ら荷物を担いで旅に出る。笠敷いたり賽銭踏んだりしては、泣く。感動の誇張表現なのか、あるいは歩いて旅をするという行為が当たり前でも安全でもないゆえに、感情が増幅されるのだろうか。実際に歩いてみたらわかるのだろうか。先達の詠んだ和歌や俳句への知識が深い。当然、記憶している。この旅は、知己を訪ねる旅でもなく、名所巡りでもなく、先達の足跡を辿る旅だったのだろう。安田先生の芭蕉を歩く旅の、あれも読もう。
読了日:09月19日 著者:松尾芭蕉

 「十二国記」30周年記念ガイドブックの感想
「十二国記」30周年記念ガイドブックの感想もうガイドブックなんて読んでも目新しい発見は無いくらい繰り返し読んできたと自信はありつつ、小野主上のインタビューと短編はやはり逃がせないと購入。辻村深月のエッセイが上手くて、同じ時間を共有した者としてじんと震える。そしてなんといっても小野さんの肉声である。悪霊シリーズ以来、自らの言葉で語られる場がほとんどなくなって、綾辻さんから漏れ聞くだけだったから、、、あれ、そういえば何年か前のインタビュー誌はどこへいったっけ? ともかくお身体を大事にしていただきたい。あと、A0サイズの十二国記の地図見てみたいです。
読了日:09月18日 著者:
 これは、アレだなの感想
これは、アレだなの感想テレビの普及期からよほどメディア漬けでこられたんじゃないかと想像するほど、テレビ、漫画、本、音楽、映画、今はネトフリ他ストリーミング配信まで、あらゆる媒体で発表される作品を渉猟されてきたようだ。そのデータベースを 「これ」から「アレ」へと、古今東西思いのままに発想を飛ばされるのを、こちらは口をぽかんと開けて拝聴していればよいだけだが、ご本人にはかなり大変な作業になったらしい。たくさんの作品の「これ」と「アレ」を見定めてゆけば、生まれる感動が薄れるかと思えばそうではないらしく、「鬼滅の刃」は泣くらしい。
読了日:09月17日 著者:高橋 源一郎

 破船 (新潮文庫)の感想
破船 (新潮文庫)の感想極貧の漁村。タコ、イワシ、サンマ、塩と、自然の恵みに依存した営みは季節に沿い正しく繰り返される。漁獲は村人の糧の多寡に直結し、頻繁に身売りが行われる。物語の中で季節は執拗に繰り返され、お船様が現れた頃には読み手も生き延びるためのムラの論理をやむなく思い始める。しかしそれは、村外の人間の死と表裏だ。著者が描きたかったのは、その貧しき人の心のさもしさと生々しい生への執着の捻じれなのだろう。幼い伊作は父親に代わり、漁に出る。年ごとに上手くなり、家の母や弟妹を想う。そんな日々の積み重ねも疫病によって無に帰すのだ。
この村は、穀物の栽培もおぼつかず、漁獲が少なければ即、飢えてしまう。数年に一度の破船から奪ったもので数年を食いつなぐ、つまり破船が無ければ生きていけないから、破船をお船様と呼んで乞い願うようになる。この村には、未来があってはならないのだ。病んだ者ではなく、病まなかった者が出て行けばよかったのに。
読了日:09月15日 著者:吉村 昭
 エネルギーをめぐる旅――文明の歴史と私たちの未来の感想
エネルギーをめぐる旅――文明の歴史と私たちの未来の感想ブラボー! 感動未だ冷めやらず。石油会社の一社員の立ち位置にありながら、偏らない姿勢でエネルギーという巨大テーマに深い関心を持ち続ける意志がすごい。そして人がライフワークを抱いていると、様々な方面から知は集まってくる。すなわち、専攻の化学分野に留まらず、科学、哲学、歴史、地学と多角的に情報を整理し、エネルギーという抽象的な存在の本質に迫ることで人類の未来に希望を見出そうとする著者の誠実な試みは、人間の英知そのものと呼びたい。さらにそれを他者に分け与えんと執筆の労を担ってくださった著者に心から敬意を表する。
『エネルギー問題とは、単に技術革新に期待するだけでは解決できない複雑な問題』『安易な技術革新信仰を捨て、より深いところでエネルギー問題に正対すること』『環境負荷を全く気にすることなく人類が好き勝手に使ってよいような完璧なエネルギー源など、そもそもこの世には存在しない』『個々の省エネ技術はむしろ社会全体のエネルギー消費量を増やす傾向があるとなると、知識の蓄積で成り立っている現代文明を維持・発展させていくためには、エネルギー消費量を引き続き増やし続けていくほか手立てがなくなってしまいます。』
著者は核融合反応による原子力発電を希望の発電システムと見定めている。しかしその実現には世界中の英知と資本を結集した開発によって、今の人類の技術からはずっと先の技術革新を成さなければならない。目下としては、ヒトの脳が持つ際限のないエネルギー獲得への欲求を自覚し、太陽光エネルギー、水素、省エネ、地産地消を前提とした分散型システムなど、できること全てをやらなければならないとしている。『何もないところからエネルギーを作り出す技術、ないしはエネルギーの質の劣化を逆転させる技術、そのいずれもが実現不可能なのです』。
「旅のおわりに」と「謝辞」の真摯さ率直さは好ましく、「謝辞」の締めくくりにはほろりとしてしまった。英治出版の社長の心意気にも感謝したい。おかげで著者の英知を私が受け取ることができたのだから。電子書籍の末尾も末尾、いつもなら本を閉じてしまうところに文字を発見。"TO MAKE THE WORLD A BETTER PLACE - Eiji Press, Inc." かっこいい!
読了日:09月15日 著者:古舘 恒介

 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー (新潮文庫)の感想
ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー (新潮文庫)の感想カトリック系の私立小学校から、公立の"元底辺中学校"へ進学。息子君と家族の日々遭遇する事件は、持っている歴史や文化の相違上、日本ではありえず、同時にイギリスの内側でずっと同じ階級にいては当たり前すぎて気づけない種類の問題を可視化する。著者持ち前の元気でパンクな語り口と、社会制度への知識が読み応えに繋がっている。ボランティアの感覚が日本と絶対的に違う。相互扶助の精神が遍在する社会の姿や、多様な人々が共生するにあたって避けられない摩擦の例、それをより良い方向へ変えていこうと組まれる教育の在りかたが興味深い。
読了日:09月12日 著者:ブレイディみかこ
 独りでいるより優しくての感想
独りでいるより優しくての感想ミステリのようで、つまるところ、黙然の物語であると私は思う。素直でよく笑う少女。泊陽の薄情や、如玉の拒絶に戸惑い、結果として犯罪に加担した苦しさはいかばかりか。それから渡米までの数年間については結局触れられていないが、その後の挙動には影が残る。相手は訳わからんだろう。だから、ジョセフとの関係を取り戻せたことはすごく良かったと感じるのだ。『先へ進む? それはアメリカのもので、私はそれをいいこととは思ってないよ』。芯からアメリカナイズされるのではなく、黙然が黙然であるところの女性で在れる結末を好ましく思った。
読了日:09月10日 著者:イーユン リー
 にごりえの感想
にごりえの感想文体が好きで、何度か読んでいたはずなのに、「文人悪妻」にちらりと出た結末に覚えがなかった自分に驚く。いやー、お力が健気で、かわいらしいやらいたわしいやらで、そちらが印象に強くて、最終章のがらりと展開してチョンと終わる、テンポの加減のせいかしら。「曽根崎心中」とやや混同している向きもあり。刀傷の描写をじっくりと読むと、お力の振舞いがまざまざと見えるようであり、やっぱりなんとも痛ましい物語である。
読了日:09月06日 著者:樋口 一葉

 文人悪妻 (新潮文庫)の感想
文人悪妻 (新潮文庫)の感想男性向け週刊誌の連載かと勘繰るノリと、女性たちの精気と色気に中てられてクラクラしてくる。流れでたまたま「文人」と題しただけで、さして「悪」妻でもない。森しげでもさほど悪く書かれていない。むしろ、妻の役目を務め上げた、あるいは強かに生き抜いた明治~昭和時代の著名な男性の伴侶、または自身が著名な女性への賛歌である。男性にしろ女性にしろ、文人という人種の伴侶は難しい。しかし、その人生経験を見事に文学作品に昇華する姿には、「まじか…」しか出ない。著者の文学への造詣ゆえ、混ぜ込まれる作品を片っ端から漁りたくなる。
読了日:09月06日 著者:嵐山 光三郎

 ウルフ・ウォーズ オオカミはこうしてイエローストーンに復活したの感想
ウルフ・ウォーズ オオカミはこうしてイエローストーンに復活したの感想オオカミ再導入をいかに成し得たかの記録。野性大型動物の乱獲による急減と、人間と家畜動物の急増が、オオカミによる"被害"を増やした点は同じである。しかし"絶滅"させた日本と違い、アメリカでは国境の向こう側や隣州に同種がいるので、民間人による殺戮と家畜被害の補償の法制化が主である。先にニホンオオカミの本を読んだせいで熱が入らない頭で考える。ある種が100年を生き繋ぐのに、そもそも何頭残っていれば可能だろうか。その頭数のオオカミが、いくら人間の脚が山中で不自由といえ、発見されず生き延びられるか疑問に思えてきた。
先日、鴻池朋子の「みる誕生」を観に行った。知らなかったのだが、鴻池さんはオオカミやキツネの毛皮をいくつも吊るす展示をする。顔も足指もある毛皮に私が動揺していると、学芸員さんが近づいて、「オオカミの毛皮です。日本はいませんが、外国では害獣なので。インターネットで販売されていて、買えるそうです。」と説明した。冬毛だろうか、毒殺だろうか、手の甲で触れたハイイロオオカミの深い毛並みは、名状し難い激情を生んだ。泣きたかった。
読了日:09月04日 著者:ハンク・フィッシャー
 貧困パンデミック――寝ている『公助』を叩き起こすの感想
貧困パンデミック――寝ている『公助』を叩き起こすの感想2020~2021年の、各支援団体の状況がわかる。新型コロナでもともと不安定だった雇用が奪われ、困窮の末住まいも失った人が急増した。そして福祉崩壊、相談崩壊。支援団体の人々は支援をしながら行政に申入れし、抗議し、地道に変えていく。一方で政治家によるネガキャンは大々的に報道され、確実に人々の心を侵食していく。国の組織としてのしなやかさの欠如が、日本をますます生きづらい場所にする。行政の支援を受けるのに、やりとりを録音しておくべきだなんて常態は酷すぎる。「自助も共助も限界に来ている。今こそ、公助の出番だ」。
読了日:09月03日 著者:稲葉 剛

 「身体」を忘れた日本人 JAPANESE, AND THE LOSS OF PHYSICAL SENSESの感想
「身体」を忘れた日本人 JAPANESE, AND THE LOSS OF PHYSICAL SENSESの感想2020年に亡くなったC.W.ニコル氏と養老先生の対談、2014年。ニコル氏はアファンの森をつくったり馬を使役したり学校創設に関わったりと活動の幅広く、養老先生も保育園の理事長を引き受けたりされているので、日本の未来を想って、日本の自然や子供のために尽力している共通点がある。"We have to be gardeners"。感覚は違いを発見するもの。意識は同じを見つけるもの。どちらに傾きすぎても生きづらいけれど、感覚の世界の奥深さを忘れては人は生きられないのだよという大切なメッセージ。広い土地欲しい。
読了日:09月03日 著者:養老孟司,C.W.ニコル

注:
 は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。 2022年09月02日
2022年8月の記録
食べた言葉を消化するには、なかなかのエネルギーを要するらしい。
食べる言葉の量を減らせば思考の量も減らせるらしいが、
ついアルコールと一緒に流し込んでオーバーフローに陥ってしまう。
「忘れる」はサーキットブレーカーみたいなものなんだろう。
<今月のデータ>
購入18冊、購入費用17,608円。
読了18冊。
積読本325冊(うちKindle本160冊、Honto本8冊)。

8月の読書メーター
読んだ本の数:17
 コンビニ人間 (文春文庫)の感想
コンビニ人間 (文春文庫)の感想
何気なく読んだら面白かった。でもメンタル引きずり込まれて困ってもいる。私のコンビニの記憶。雇い主や同僚には嫌な記憶ばかりだ。コンビニは社会の底辺だと割り切ってきた。しかしほんとうは私が徹底的に弾かれたのだよな。遡って、勉強さえしていれば挙動の怪しさは免罪されると思っていた子供時代、さらに親戚づきあいから逃げ回る現在へと、記憶たちがざわざわする。人は想像する以上にみな違うもんだよ治るとかよかったとかってなんですか。妹の「治らないの?」の涙に別の意味で動揺しない主人公が心強い。彼女がコンビニに戻れてよかった。
読了日:08月31日 著者:村田 沙耶香
 ほの暗い永久から出でて 生と死を巡る対話 (文春文庫)の感想
ほの暗い永久から出でて 生と死を巡る対話 (文春文庫)の感想
目には見えないもののことをじっくり考える習慣は、人を強くする。人間の身体は遺伝子を繋ぐため、生命を存続させる必要がある間は生きたいと思わせ、時が来れば容赦なく壊れるようできている。対して、感情は振りほどきようがない強さで、いつもあとから湧いてくる。その落差を埋めるために、人は熱意を傾けて知を育むのではないだろうか。『自分が直面している状況に関して、切り口を変えると、全く見方が変わってくる』。"気配"の概念を理解できない西洋人の話が出てくる。東洋の思考は見えないものを捉える切り口を増やす利があると思い至る。
読了日:08月30日 著者:上橋 菜穂子,津田 篤太郎
 読み解き!『裸の大地 第一部 狩りと漂泊』 対談 不確実性(ナルホイヤ)のなかで見出す解(角幡唯介トークス) (集英社e選書トークス)の感想
読み解き!『裸の大地 第一部 狩りと漂泊』 対談 不確実性(ナルホイヤ)のなかで見出す解(角幡唯介トークス) (集英社e選書トークス)の感想
2021年、服部文祥の小屋で。この二人の対談が面白くないはずがない。本人たちは、こんなの読者は読んで面白いか?とか売れないんじゃないか?とかじゃあ俺はどうしたらいいんだよとか、文章を書くってたいへんな作業なんだ。私はあなたたちの書くものなら何でも読みたい。それだって丸投げだし。歳と共に表現欲が減退して、モチベーションが下がっているとも言う。嫌だ、YouTuberになんかならないで、文章を書くのやめないで、想像するだけで泣きそうだ…。俺は文章表現が好きだから、と衒いなく言っちゃう服部文祥が私は大好きなんだ。
読了日:08月30日 著者:角幡唯介,服部文祥
 ニホンオオカミは消えたか?の感想
ニホンオオカミは消えたか?の感想
オオカミはかつて食物連鎖の頂点に君臨したがゆえに、難しい立ち位置に置かれている。今世紀に入ってもイヌでもキツネでもない獣の目撃報告は続いている。目撃してしまった人の中では、最早オオカミがいないことにはできない。しかし生きている証明ができない。国による本格調査無き絶滅宣言は信用できない。ニホンオオカミが生きているならタイリクオオカミを日本に導入することはできない。八方塞がりだ。オオカミ信仰の残る秩父地方で目撃報告が多いのは示唆的である。日本の森には人間が知り得ない真実が今もあると信じる側に私は立ちたい。
読了日:08月29日 著者:宗像 充
 会社というモンスターが、僕たちを不幸にしているのかもしれない。の感想
会社というモンスターが、僕たちを不幸にしているのかもしれない。の感想
社員に会社辞めると言われると、落ち込むことにしている。言い直すと、その辞めたいと思った動機が、本人の軽挙妄動と即割りきるのではなく、なにか会社の側の至らなさにあったのではないかと省みることにしている。ただ今回は落ち込み過ぎたので、青野さんの本を再読してみた。サイボウズと同じにはいかなくも、令和を生き残る企業として必要なのはどのような姿勢か、方向性の確認をしたかったのだと思う。これからの社会では給料は成果への報酬ではなく、未来の期待値という考えは、希望があっていいなあ。さあ、やるべきことは山積みだー。
読了日:08月28日 著者:青野 慶久
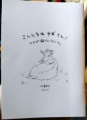 こんにちはヤギさん!の感想
こんにちはヤギさん!の感想
で、意識的にか無意識にか本編では省かれていた、ヤギを飼ううえで「役に立つ」情報を詰め込んだのがこのヤギZINE。本編を読んでヤギを飼いたい人が増えたらと内澤さんは心配しておいでる。いやー、本編に獣医とか出てこないし、いやにさらりとしていると思ったが、蹄の手入れもたいへんだし、もっと日常なところで、ヤギが好んで食べる草と食べられる草と食べてはいけない草がこんなにシビアとは知らなかった。ヤギは寂しがりで、独りでも寂しければ、仲の良いヤギ伴侶が死んだら鬱になるほどとも内澤さんは心配している。イラストが素敵すぎ。
読了日:08月27日 著者:内澤 旬子
 カヨと私の感想
カヨと私の感想
今作の内澤さんの文章は今までよりもたおやかな、やわらかい感触がしていた。昨日のルヌガンガでの内澤さんのお話会にサプライズ登場した杉江さんとの遣り取りによると、内澤さんはこれまで本を書くときは、誰かの役に立つ内容を届ける前提で、そうでなければ本を手に取ってもらえないと思って企画・執筆していたのだそうだ。今回は、書きたいことを書いた。たいへんだけど愛おしい日々を、言葉を介さない深い交流を、ヤギ愛全開で書いたから、私はそう感じたのだ。役に立たなくたって、もう胸いっぱいである。内澤さん、カヨと出会って良かった。
家の中に人間より動物の数が多い場合、生じる現象はヤギでも猫でも似ている。生命力は常に人間の想定を超えてくる。刹那を生きる動物の望みどおりにしてやりたい思いと、人間の居住地域内にいるがゆえに限られる選択肢、その板挟みで途方に暮れる人間に向かって全身で鳴き叫ぶ姿は想像するだに身もだえしてしまう。さらに個体同士の関係性は刻々変わっていく。動物には動物の理がある。急に嫌ったり攻撃したり仲間外れにしたり、人間の関われる範疇ではない。人間の都合よいとおりにはならないけれど、全き理解は成り立つと私は信じる。
読了日:08月26日 著者:内澤旬子
 人、イヌと暮らすー進化、愛情、社会 (教養みらい選書)の感想
人、イヌと暮らすー進化、愛情、社会 (教養みらい選書)の感想
理知めな犬エッセイ。ヒトーイヌ関係や、イヌを介在したヒトーヒト関係についての考察。ヒトーイヌ関係もイヌを介在したヒトーヒト関係も、ネコとのそれよりも相互作用が豊かであるというのは、どうやら確かだ。ネコとヒトもアイコンタクトは取れるが、そこに共感は発生しない。またネコと暮らす人同士にイヌ友のような友情は発生せず、それをきっかけとする地域の人間関係も生じ得ない。これは人生すら左右する現象だ。素晴らしい。だからといってイヌをうちに迎えようとはならないのは、私の中のネコ的要素がそれを求めないのだから仕方ないよな。
読了日:08月25日 著者:長谷川 眞理子
 野ざらし紀行 現代語訳付の感想
野ざらし紀行 現代語訳付の感想
「おくのほそ道」の旅に出るより前、庵から西方面へ。備忘録程度の短い文章+句という構成で、その短い文章すら途中からは省くから残ったのは地名だけという、ミニマムな紀行文?である。句は、ふと思いついたことを句に仕立てた感じ。特に感慨深かったわけでもないけど風物が目の前にあるからひねってみた、みたいなものも多い。山頭火や放哉の、四六時中落涙か流血しているような句を魂の句だと思っている節がある私には拍子抜けだった。現代語訳に句の意味も書かれているのだが、句に書かれていない背景込みで説明されるあたり、ずるい。
読了日:08月21日 著者:松尾芭蕉
 コールセンターもしもし日記の感想
コールセンターもしもし日記の感想
コールセンターってこういう仕組みなのか。マニュアルで対応する派遣、上にSV、管理職がいる。かける専門と受ける専門、単なる事務処理から問題解決まで難易度も客の経済水準もピンキリだが、派遣される側は業務内容を知らされず、勤務地と時給だけで選ぶ。携帯の代金を払わなくて電話を止められたからとコールセンターのオペレーターを怒鳴り倒す客の応対と、高めな時給の天秤は釣り合うのだろうか。かかってくる営業の電話も、たどたどしいのは派遣だろうか。詐欺まがいのマニュアルで相手にキレられる、そんな仕事はお辞めなさいと説得したい。
読了日:08月21日 著者:吉川 徹
 アルハンブラ物語 (講談社文庫 あ 31-1)の感想
アルハンブラ物語 (講談社文庫 あ 31-1)の感想
1829年、著者は総督からアルハンブラ宮殿内の空き部屋に住む許可を得る。今のように観光地化される前、アルハンブラは荒れ放題で、出入り自由、貧民が住みついたりもしていた。それにしたってムーアの遺した造形物の美しさは紛う方ない。「月光を浴びるアルハンブラ」が好きだ。当然、ライトアップなどされていないので夜は暗闇である。ひと気のない宮殿は怖くもあろうけれど、手燭が揺らす彫刻や柱の陰影は目を奪おう。月が出れば乳白の大理石が白く浮かぶ。夜な夜な歩き、物思いに耽り、昼間はバルコニーの手すりに持たれてまどろむ贅沢さよ。
読了日:08月19日 著者:ワシントン・アービング
 プロジェクト・ヘイル・メアリー 下の感想
プロジェクト・ヘイル・メアリー 下の感想
よい、よい、よい! しあわせ! 人類やけっぱち作戦の顛末。ウィアーの小説ならば、バッドエンドは無い。しかし読み終えて覚えるのは、「結末はこれ以外に有り得なかった」という満足感だ。究極の二択で彼が選んだ世界は、彼だから選んだ世界。人類は愚かだ。いつも愚かな道を選ばずにいられない。しかしそれはそれとして、隣人を大切にする気持ちは信じる。意思疎通を図り、情報を共有し、だからこそ宇宙を航行できるほどの技術を人類は手にすることができた。そして科学のたゆまぬ探求、新たな発見が未来を拓く可能性は、信じてもいいと思った。
読了日:08月18日 著者:アンディ・ウィアー
 プロジェクト・ヘイル・メアリー 上の感想
プロジェクト・ヘイル・メアリー 上の感想
今回は宇宙で、宇宙船の中で独りぼっち。理系の人って、こんなふうに次々と問題解決できる引き出しを素養として身に着けてるのか。すごい。しかし今回は地球の命運がかかっている。独りではどこまで…と思ってたら独りぼっちじゃなくなった! アストロファージの設定が細かい。やつらの持っている性質、それによっていろいろな使いでが導かれて、物語を盛り上げる。専門的な説明描写に浮遊しだす意識を引き戻しながら、私はユーグレナを連想していた。巷の資本主義的喧伝に幻滅しそうになるけど、新しい発見には地球を救うチカラがあるのかな?
読了日:08月12日 著者:アンディ・ウィアー
 「日本の伝統」の正体 (新潮文庫)の感想
「日本の伝統」の正体 (新潮文庫)の感想
私が知る伝統に偽物が混じっていないか確認するため。いわゆる雑学本だが、雑学本としての事実確認の深さがちょうどよい。さて、意図的につくられた「伝統」は多くて、商売繁盛のために商売人が仕掛けたもの、また政府や寺社仏閣が自らの存在に箔をつけるため、正当化するために謳ったものが多い。加えて著者が指摘しているのは、明治時代と戦後に「伝統」が量産された点だ。それは大きな断絶の後なのだ。断絶を感じ取り、新しい時代への変化を望みながら、同時に長い日本の歴史を誇ってもいたい気持ちが、「伝統」を創らせたのだろうと想像した。
高松まつりの総おどりを観に行った。四国で言うと伝統が長いのは徳島の阿波踊りで400年程度、それを羨んで創った高知のよさこいが70年程度。江戸時代からあった"よさこい節"に踊りをつけ、アレンジを加えて今がある。観ていると、俺たちは踊りたくて仕方ないんだ!と内から発散する熱にこちらが焦がされそうなほどで心掴まれる。よさこいソーランつくりたくなるのわかる。片や高松の"一合まいた"は室町小唄起源を力説しようと、もはや形骸感が半端ない。この先、伝統になっていくのはよさこいだわなと思わずにいられない。よさこい観たい。
読了日:08月11日 著者:藤井 青銅
 マーシャル、父の戦場: ある日本兵の日記をめぐる歴史実践の感想
マーシャル、父の戦場: ある日本兵の日記をめぐる歴史実践の感想
マーシャル諸島で餓死した一人の日本兵。遺された手帳をその息子から託され、解読する作業から始まった企画である。そこには援軍の到来を待ち望みながら、空腹を耐え、機銃掃射から逃れ、作物を自給し、仲間を日々見送り、ついには自らの死を自覚する心中が綴られていた。『最後カナ』の絶筆。時系列からは、東京や大阪が空襲を受け、米軍が沖縄に上陸した、その事実も知らないまま床に臥していた事がわかる。しかし生き延びることは、ついぞ諦めなかった。37歳の出征当初から日本の敗戦は覚っていたという。還れなかった、その無念を思う。
読了日:08月11日 著者:大川 史織
 ストーカー (ハヤカワ文庫 SF 504)の感想
ストーカー (ハヤカワ文庫 SF 504)の感想
なにやらわからないが、異世界との接点が地球上に表れた。そこへ忍び込んで未知の知的存在が造った未知の物体を持ち帰る者が「ストーカー」である。人間の心身を害する要素もあるらしく、何人ものストーカーが斃れた。ホラー映画のように、正体が見えないまま危害が加えられるあたりも理不尽である。それでも忍び込むのは金になるから、つまりその未知の物体の構造や機能が、人間の好奇心を刺激してやまないからだ。未知の存在は、いっさい姿を現さない。あるのは、当たり前の人間の暮らし、変異した街に暮らす人々の殺伐とした心象、自滅への願望。
読了日:08月04日 著者:アルカジイ ストルガツキー,ボリス ストルガツキー
 半日の感想
半日の感想
ああ、典型的な悪妻。自分がやりたくないことは絶対したくない。そのためには事実を捻じ曲げる。筋道が通るまいが反駁する。おるなあ、そういうひと。生命力削られるんよなあ。自分の妻がそういう女であったと気付いて、論理思考な性質の男はどう思うのだろう。たとえば鴎外は。後悔するのか、愛おしく思うのか。ちなみに文中に妻を褒める言葉は顔立ちについてのみである。なだめ、すかし、エンドレスな諍いに諦観の匂いがする。真偽のほどは知らないけれど、この女性のモデルは自分だと知らされたら、鴎外の妻はそりゃ憤激するだろうな。
読了日:08月01日 著者:森 鴎外
注: は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。
食べる言葉の量を減らせば思考の量も減らせるらしいが、
ついアルコールと一緒に流し込んでオーバーフローに陥ってしまう。
「忘れる」はサーキットブレーカーみたいなものなんだろう。
<今月のデータ>
購入18冊、購入費用17,608円。
読了18冊。
積読本325冊(うちKindle本160冊、Honto本8冊)。

8月の読書メーター
読んだ本の数:17
 コンビニ人間 (文春文庫)の感想
コンビニ人間 (文春文庫)の感想何気なく読んだら面白かった。でもメンタル引きずり込まれて困ってもいる。私のコンビニの記憶。雇い主や同僚には嫌な記憶ばかりだ。コンビニは社会の底辺だと割り切ってきた。しかしほんとうは私が徹底的に弾かれたのだよな。遡って、勉強さえしていれば挙動の怪しさは免罪されると思っていた子供時代、さらに親戚づきあいから逃げ回る現在へと、記憶たちがざわざわする。人は想像する以上にみな違うもんだよ治るとかよかったとかってなんですか。妹の「治らないの?」の涙に別の意味で動揺しない主人公が心強い。彼女がコンビニに戻れてよかった。
読了日:08月31日 著者:村田 沙耶香

 ほの暗い永久から出でて 生と死を巡る対話 (文春文庫)の感想
ほの暗い永久から出でて 生と死を巡る対話 (文春文庫)の感想目には見えないもののことをじっくり考える習慣は、人を強くする。人間の身体は遺伝子を繋ぐため、生命を存続させる必要がある間は生きたいと思わせ、時が来れば容赦なく壊れるようできている。対して、感情は振りほどきようがない強さで、いつもあとから湧いてくる。その落差を埋めるために、人は熱意を傾けて知を育むのではないだろうか。『自分が直面している状況に関して、切り口を変えると、全く見方が変わってくる』。"気配"の概念を理解できない西洋人の話が出てくる。東洋の思考は見えないものを捉える切り口を増やす利があると思い至る。
読了日:08月30日 著者:上橋 菜穂子,津田 篤太郎

 読み解き!『裸の大地 第一部 狩りと漂泊』 対談 不確実性(ナルホイヤ)のなかで見出す解(角幡唯介トークス) (集英社e選書トークス)の感想
読み解き!『裸の大地 第一部 狩りと漂泊』 対談 不確実性(ナルホイヤ)のなかで見出す解(角幡唯介トークス) (集英社e選書トークス)の感想2021年、服部文祥の小屋で。この二人の対談が面白くないはずがない。本人たちは、こんなの読者は読んで面白いか?とか売れないんじゃないか?とかじゃあ俺はどうしたらいいんだよとか、文章を書くってたいへんな作業なんだ。私はあなたたちの書くものなら何でも読みたい。それだって丸投げだし。歳と共に表現欲が減退して、モチベーションが下がっているとも言う。嫌だ、YouTuberになんかならないで、文章を書くのやめないで、想像するだけで泣きそうだ…。俺は文章表現が好きだから、と衒いなく言っちゃう服部文祥が私は大好きなんだ。
読了日:08月30日 著者:角幡唯介,服部文祥

 ニホンオオカミは消えたか?の感想
ニホンオオカミは消えたか?の感想オオカミはかつて食物連鎖の頂点に君臨したがゆえに、難しい立ち位置に置かれている。今世紀に入ってもイヌでもキツネでもない獣の目撃報告は続いている。目撃してしまった人の中では、最早オオカミがいないことにはできない。しかし生きている証明ができない。国による本格調査無き絶滅宣言は信用できない。ニホンオオカミが生きているならタイリクオオカミを日本に導入することはできない。八方塞がりだ。オオカミ信仰の残る秩父地方で目撃報告が多いのは示唆的である。日本の森には人間が知り得ない真実が今もあると信じる側に私は立ちたい。
読了日:08月29日 著者:宗像 充

 会社というモンスターが、僕たちを不幸にしているのかもしれない。の感想
会社というモンスターが、僕たちを不幸にしているのかもしれない。の感想社員に会社辞めると言われると、落ち込むことにしている。言い直すと、その辞めたいと思った動機が、本人の軽挙妄動と即割りきるのではなく、なにか会社の側の至らなさにあったのではないかと省みることにしている。ただ今回は落ち込み過ぎたので、青野さんの本を再読してみた。サイボウズと同じにはいかなくも、令和を生き残る企業として必要なのはどのような姿勢か、方向性の確認をしたかったのだと思う。これからの社会では給料は成果への報酬ではなく、未来の期待値という考えは、希望があっていいなあ。さあ、やるべきことは山積みだー。
読了日:08月28日 著者:青野 慶久
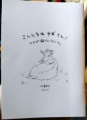 こんにちはヤギさん!の感想
こんにちはヤギさん!の感想で、意識的にか無意識にか本編では省かれていた、ヤギを飼ううえで「役に立つ」情報を詰め込んだのがこのヤギZINE。本編を読んでヤギを飼いたい人が増えたらと内澤さんは心配しておいでる。いやー、本編に獣医とか出てこないし、いやにさらりとしていると思ったが、蹄の手入れもたいへんだし、もっと日常なところで、ヤギが好んで食べる草と食べられる草と食べてはいけない草がこんなにシビアとは知らなかった。ヤギは寂しがりで、独りでも寂しければ、仲の良いヤギ伴侶が死んだら鬱になるほどとも内澤さんは心配している。イラストが素敵すぎ。
読了日:08月27日 著者:内澤 旬子
 カヨと私の感想
カヨと私の感想今作の内澤さんの文章は今までよりもたおやかな、やわらかい感触がしていた。昨日のルヌガンガでの内澤さんのお話会にサプライズ登場した杉江さんとの遣り取りによると、内澤さんはこれまで本を書くときは、誰かの役に立つ内容を届ける前提で、そうでなければ本を手に取ってもらえないと思って企画・執筆していたのだそうだ。今回は、書きたいことを書いた。たいへんだけど愛おしい日々を、言葉を介さない深い交流を、ヤギ愛全開で書いたから、私はそう感じたのだ。役に立たなくたって、もう胸いっぱいである。内澤さん、カヨと出会って良かった。
家の中に人間より動物の数が多い場合、生じる現象はヤギでも猫でも似ている。生命力は常に人間の想定を超えてくる。刹那を生きる動物の望みどおりにしてやりたい思いと、人間の居住地域内にいるがゆえに限られる選択肢、その板挟みで途方に暮れる人間に向かって全身で鳴き叫ぶ姿は想像するだに身もだえしてしまう。さらに個体同士の関係性は刻々変わっていく。動物には動物の理がある。急に嫌ったり攻撃したり仲間外れにしたり、人間の関われる範疇ではない。人間の都合よいとおりにはならないけれど、全き理解は成り立つと私は信じる。
読了日:08月26日 著者:内澤旬子
 人、イヌと暮らすー進化、愛情、社会 (教養みらい選書)の感想
人、イヌと暮らすー進化、愛情、社会 (教養みらい選書)の感想理知めな犬エッセイ。ヒトーイヌ関係や、イヌを介在したヒトーヒト関係についての考察。ヒトーイヌ関係もイヌを介在したヒトーヒト関係も、ネコとのそれよりも相互作用が豊かであるというのは、どうやら確かだ。ネコとヒトもアイコンタクトは取れるが、そこに共感は発生しない。またネコと暮らす人同士にイヌ友のような友情は発生せず、それをきっかけとする地域の人間関係も生じ得ない。これは人生すら左右する現象だ。素晴らしい。だからといってイヌをうちに迎えようとはならないのは、私の中のネコ的要素がそれを求めないのだから仕方ないよな。
読了日:08月25日 著者:長谷川 眞理子

 野ざらし紀行 現代語訳付の感想
野ざらし紀行 現代語訳付の感想「おくのほそ道」の旅に出るより前、庵から西方面へ。備忘録程度の短い文章+句という構成で、その短い文章すら途中からは省くから残ったのは地名だけという、ミニマムな紀行文?である。句は、ふと思いついたことを句に仕立てた感じ。特に感慨深かったわけでもないけど風物が目の前にあるからひねってみた、みたいなものも多い。山頭火や放哉の、四六時中落涙か流血しているような句を魂の句だと思っている節がある私には拍子抜けだった。現代語訳に句の意味も書かれているのだが、句に書かれていない背景込みで説明されるあたり、ずるい。
読了日:08月21日 著者:松尾芭蕉

 コールセンターもしもし日記の感想
コールセンターもしもし日記の感想コールセンターってこういう仕組みなのか。マニュアルで対応する派遣、上にSV、管理職がいる。かける専門と受ける専門、単なる事務処理から問題解決まで難易度も客の経済水準もピンキリだが、派遣される側は業務内容を知らされず、勤務地と時給だけで選ぶ。携帯の代金を払わなくて電話を止められたからとコールセンターのオペレーターを怒鳴り倒す客の応対と、高めな時給の天秤は釣り合うのだろうか。かかってくる営業の電話も、たどたどしいのは派遣だろうか。詐欺まがいのマニュアルで相手にキレられる、そんな仕事はお辞めなさいと説得したい。
読了日:08月21日 著者:吉川 徹

 アルハンブラ物語 (講談社文庫 あ 31-1)の感想
アルハンブラ物語 (講談社文庫 あ 31-1)の感想1829年、著者は総督からアルハンブラ宮殿内の空き部屋に住む許可を得る。今のように観光地化される前、アルハンブラは荒れ放題で、出入り自由、貧民が住みついたりもしていた。それにしたってムーアの遺した造形物の美しさは紛う方ない。「月光を浴びるアルハンブラ」が好きだ。当然、ライトアップなどされていないので夜は暗闇である。ひと気のない宮殿は怖くもあろうけれど、手燭が揺らす彫刻や柱の陰影は目を奪おう。月が出れば乳白の大理石が白く浮かぶ。夜な夜な歩き、物思いに耽り、昼間はバルコニーの手すりに持たれてまどろむ贅沢さよ。
読了日:08月19日 著者:ワシントン・アービング

 プロジェクト・ヘイル・メアリー 下の感想
プロジェクト・ヘイル・メアリー 下の感想よい、よい、よい! しあわせ! 人類やけっぱち作戦の顛末。ウィアーの小説ならば、バッドエンドは無い。しかし読み終えて覚えるのは、「結末はこれ以外に有り得なかった」という満足感だ。究極の二択で彼が選んだ世界は、彼だから選んだ世界。人類は愚かだ。いつも愚かな道を選ばずにいられない。しかしそれはそれとして、隣人を大切にする気持ちは信じる。意思疎通を図り、情報を共有し、だからこそ宇宙を航行できるほどの技術を人類は手にすることができた。そして科学のたゆまぬ探求、新たな発見が未来を拓く可能性は、信じてもいいと思った。
読了日:08月18日 著者:アンディ・ウィアー

 プロジェクト・ヘイル・メアリー 上の感想
プロジェクト・ヘイル・メアリー 上の感想今回は宇宙で、宇宙船の中で独りぼっち。理系の人って、こんなふうに次々と問題解決できる引き出しを素養として身に着けてるのか。すごい。しかし今回は地球の命運がかかっている。独りではどこまで…と思ってたら独りぼっちじゃなくなった! アストロファージの設定が細かい。やつらの持っている性質、それによっていろいろな使いでが導かれて、物語を盛り上げる。専門的な説明描写に浮遊しだす意識を引き戻しながら、私はユーグレナを連想していた。巷の資本主義的喧伝に幻滅しそうになるけど、新しい発見には地球を救うチカラがあるのかな?
読了日:08月12日 著者:アンディ・ウィアー

 「日本の伝統」の正体 (新潮文庫)の感想
「日本の伝統」の正体 (新潮文庫)の感想私が知る伝統に偽物が混じっていないか確認するため。いわゆる雑学本だが、雑学本としての事実確認の深さがちょうどよい。さて、意図的につくられた「伝統」は多くて、商売繁盛のために商売人が仕掛けたもの、また政府や寺社仏閣が自らの存在に箔をつけるため、正当化するために謳ったものが多い。加えて著者が指摘しているのは、明治時代と戦後に「伝統」が量産された点だ。それは大きな断絶の後なのだ。断絶を感じ取り、新しい時代への変化を望みながら、同時に長い日本の歴史を誇ってもいたい気持ちが、「伝統」を創らせたのだろうと想像した。
高松まつりの総おどりを観に行った。四国で言うと伝統が長いのは徳島の阿波踊りで400年程度、それを羨んで創った高知のよさこいが70年程度。江戸時代からあった"よさこい節"に踊りをつけ、アレンジを加えて今がある。観ていると、俺たちは踊りたくて仕方ないんだ!と内から発散する熱にこちらが焦がされそうなほどで心掴まれる。よさこいソーランつくりたくなるのわかる。片や高松の"一合まいた"は室町小唄起源を力説しようと、もはや形骸感が半端ない。この先、伝統になっていくのはよさこいだわなと思わずにいられない。よさこい観たい。
読了日:08月11日 著者:藤井 青銅

 マーシャル、父の戦場: ある日本兵の日記をめぐる歴史実践の感想
マーシャル、父の戦場: ある日本兵の日記をめぐる歴史実践の感想マーシャル諸島で餓死した一人の日本兵。遺された手帳をその息子から託され、解読する作業から始まった企画である。そこには援軍の到来を待ち望みながら、空腹を耐え、機銃掃射から逃れ、作物を自給し、仲間を日々見送り、ついには自らの死を自覚する心中が綴られていた。『最後カナ』の絶筆。時系列からは、東京や大阪が空襲を受け、米軍が沖縄に上陸した、その事実も知らないまま床に臥していた事がわかる。しかし生き延びることは、ついぞ諦めなかった。37歳の出征当初から日本の敗戦は覚っていたという。還れなかった、その無念を思う。
読了日:08月11日 著者:大川 史織
 ストーカー (ハヤカワ文庫 SF 504)の感想
ストーカー (ハヤカワ文庫 SF 504)の感想なにやらわからないが、異世界との接点が地球上に表れた。そこへ忍び込んで未知の知的存在が造った未知の物体を持ち帰る者が「ストーカー」である。人間の心身を害する要素もあるらしく、何人ものストーカーが斃れた。ホラー映画のように、正体が見えないまま危害が加えられるあたりも理不尽である。それでも忍び込むのは金になるから、つまりその未知の物体の構造や機能が、人間の好奇心を刺激してやまないからだ。未知の存在は、いっさい姿を現さない。あるのは、当たり前の人間の暮らし、変異した街に暮らす人々の殺伐とした心象、自滅への願望。
読了日:08月04日 著者:アルカジイ ストルガツキー,ボリス ストルガツキー

 半日の感想
半日の感想ああ、典型的な悪妻。自分がやりたくないことは絶対したくない。そのためには事実を捻じ曲げる。筋道が通るまいが反駁する。おるなあ、そういうひと。生命力削られるんよなあ。自分の妻がそういう女であったと気付いて、論理思考な性質の男はどう思うのだろう。たとえば鴎外は。後悔するのか、愛おしく思うのか。ちなみに文中に妻を褒める言葉は顔立ちについてのみである。なだめ、すかし、エンドレスな諍いに諦観の匂いがする。真偽のほどは知らないけれど、この女性のモデルは自分だと知らされたら、鴎外の妻はそりゃ憤激するだろうな。
読了日:08月01日 著者:森 鴎外

注:
 は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。 2022年08月01日
2022年7月の記録
宮田珠己氏が「めちゃめちゃ好みだ、どストライクだという本と、これはなかなか面白そうだという本と、これは読んでおかないという本がある場合、まず読んでおかないと本から読んでしまう癖をやめたい。どストライク本までなかなかたどり着かない。」とつぶやいておられて、まったく同意する。
読んでくれる人も稀であろうこのブログの意義といって、月に一度自分の読んだ本を眺め渡すことにもある。
これといって重みのある本は読んでいないな、また特に響く本は無かったな、と思うけれど、なんらかの糧にはなっているのだ。
特に社会を見る目がまた転換期にあると思う。
<今月のデータ>
購入21冊、購入費用14,994円。
読了12冊。
積読本320冊(うちKindle本156冊、Honto本9冊)。

7月の読書メーター
読んだ本の数:12
 吉田茂 ポピュリズムに背を向けて<下> (講談社文庫)の感想
吉田茂 ポピュリズムに背を向けて<下> (講談社文庫)の感想
吉田茂の大舞台。サンフランシスコでの講和へ向かう場面はとかく目が潤んでしまって、未来の日本を想う先人たちの気持ちに感じ入った。政治家の在るべき姿について考えた。しかし一転、あとがきで感傷は吹っ飛ぶ。国民は政治を見る目を養えと著者は言う。政治家の本当の仕事は、一般人には見えない事の方が多いのだろう。そして政治の様相は、当時と今と違わない点も多い。それにしたって、小手先の人気取りだったり、粗忽な政策を議論を拒んで拙速に通したり、そんな教養も矜持も目減りが明らかな政治家がのさばる今の政治をどう信頼しろと。
読了日:07月28日 著者:北 康利
 美貌のひと 歴史に名を刻んだ顔 (PHP新書)の感想
美貌のひと 歴史に名を刻んだ顔 (PHP新書)の感想
中野さんの本を読むのは好きだ。しかし絵を眺める時間は、3回くらい見返したとしてもそう長くない。きれいだなぁ、とか気味悪いなぁ、とか思うくらいで、どこがすごいのか探る気がさっぱり無い。私にとって中野さんの本は、ミニミステリだ。絵の裏に隠れた物語、壮大な、あるいは謎に満ちた、絵はその手がかり。もっと面白い話を聞きたくてずるずる読んでしまう。ユトリロにせよトルストイにせよ、ほう!と感嘆したことばかり印象に残って、絵も画家の名も覚えちゃいないのだ。でもアルテミジアは覚えておきたいな。かっこいいから。
読了日:07月23日 著者:中野 京子
 無敵の読解力 (文春新書 1341)の感想
無敵の読解力 (文春新書 1341)の感想
素地の全く違う二人の対談本も早や何冊目か。しかし慣れ合うのではなく、敢えて異なる見方を相手の見解の横に並べてみせるところが面白い。相手を驚かせるための隠し玉を事前に仕込んだりしていそうだ。さて、政治家の教養について。為政者を志すなら、質と量ともに一般人のそれでは足りない。頼るべきは先人の知恵たる古典で、その道を進むなら読んでおくべき類のものが底力となる。若い頃に重厚なものを読む力をつけてそこまで辿り着くには、天賦の嗅覚か、身近な者の誘導が必要だろう。あるいは素養が足りないと自覚して誰か教師役を捕まえるか。
しかし「きちんとした読書の基盤がある政治家」は与野党共に減っているという。松岡正剛氏のエピソードが興味深い。ある政治家に本の読み方を教えてやってほしいと請われ、試みたが全くうまくいかなかったという。そもそも読む必要が理解できない者には、馬を水辺に連れて行くことはできても、である。テレビでは政権に対する忖度とも取れる発言に留める池上さんだが、本書では日本の元首相や政治家に対して、佐藤氏と毒舌の応酬である。ということは、局側からNGがかかっているのだろう。知識と毒舌がぽんぽん飛び出す池上さんは格好好いぞ。
佐藤氏:古代ローマの詩人ホラティウスの頌歌を引いた一節です。「祖父母に劣れる父母/さらに劣れるわれらを生めり、/われら遠からずして/より劣悪なる子孫を儲けん」。
読了日:07月22日 著者:池上 彰,佐藤 優
 吉田茂 ポピュリズムに背を向けて<上> (講談社文庫)の感想
吉田茂 ポピュリズムに背を向けて<上> (講談社文庫)の感想
日本が敗戦に向かって転げ落ちている時分、政府や官僚は何をしていたのかと以前の私は鼻白んだものだったが、今よりも胆力があって優秀な政治家や外務省官僚でも止めることができないほど、陸軍や親独派政治家の勢いが急速についてしまっていた。なんとか戦争回避、早期終結に奮闘していたのが、あの首相の入替りの激しさ、内閣の短命に表れていたと知る。水面下で流れた組閣も多かった由。結局、戦争に積極的な態度を取った首相は東条だけだったようだ。吉田茂も切歯扼腕、陰で奔走していた一人。憲兵隊コード"ヨハンセン"とは「吉田反戦」の意。
降伏文書に誤りがあり、アメリカの担当者がそのままにしようとしたことに日本側は抗議、訂正を求める。『この期に及んでささやかな抵抗を試みた彼らのことを滑稽だと感じる人は、感情の襞のいささか少ない人だと言わざるを得ない。この時の彼らの立場に自らを置いてみる努力を、今の日本人はすべきであろう。戦いに敗れてなお、彼らのような矜持ある日本人が残っていたからこそ、この国は奇跡の回復をなしえたのである』。上巻の終りに近い箇所のエピソードだが、ずっと読み進めた後のこれは、じんときた。
読了日:07月19日 著者:北 康利
 鷗外の怪談の感想
鷗外の怪談の感想
戯曲は面白いなあ。心に秘めたものまでが、台詞にほとんど詰め込まれている。主張も迷いも絶望も吐露され、揺れる。この永井荷風が私は大好きだ。身をもって、信念にかけて守ろうとするものが、日本という国家に阻まれ守ることができなかった、落胆、悲嘆。それは現代の私たちがあからさまな政治の逸脱を糾弾することができなかった、改憲勢力の増長を選挙で止めることができなかった、悪政を通した元首相を国葬にするなどという茶番を止めることができない予感、そのたびに味わう挫折感に似ているだろうか。これらは確実に、人の心をくじいてゆく。
読了日:07月14日 著者:永井 愛
 木綿リサイクルの衰退と復活 ―大阪八尾を中心とする木綿の経済史―〈発行:ブックウェイ〉の感想
木綿リサイクルの衰退と復活 ―大阪八尾を中心とする木綿の経済史―〈発行:ブックウェイ〉の感想
木綿は温暖な地で江戸時代に栽培が盛んになった。しかし開国と共に輸入品に押される。明治16年、渋沢栄一が紡績会社設立。国産の綿でも試行錯誤したが、輸入品の綿糸のほうが良質だったため、明治19年以降中国産、インド産で操業。大正5年には河内の木綿栽培は壊滅した由。合成繊維が現れるまでもなかったようだ。なお、私の興味を引いた「リサイクル」とは、以前においては布地をボロボロになるまで使い倒した後、肥やしとして畑に鋤き込むことであり、現代においては"自然に優しい"に同義と扱われているあたり、不満と言わざるを得ない。
読了日:07月13日 著者:前田啓一
 壊れた脳 生存する知の感想
壊れた脳 生存する知の感想
「奇跡の脳」の脳神経科学者ジル・ボルト・テイラーや、「脳はすごい」の人工知能研究者クラーク・エリオットなど、脳の専門家本人による脳損傷、負った高次脳機能障害とその回復の記録は、人知を超えたような、畏敬の念を読み手に与えてくれたものだったが、我が香川県にも脳損傷からの回復の経緯を記した医師があったのだ。脳の損傷によって起きる行動の変異。障害による消耗も激しいが、周囲の、特に医療従事者の無理解がずいぶんダメージになる。熱心に回復に取り組むほど、脳の自ら機能を再生する力も強まる。脳も凄いが、人間って凄いな。
読了日:07月12日 著者:山田 規畝子
 住宅営業マンぺこぺこ日記――「今月2件5000万! 」死にもの狂いでノルマこなしますの感想
住宅営業マンぺこぺこ日記――「今月2件5000万! 」死にもの狂いでノルマこなしますの感想
フィリピンパブ接待だノルマだ気合だって、昭和なのはタマ…ホームだけだろうか。ローコスト住宅メーカーの内部事情。営業の悲哀はともかく、売り物が住まいである今作は買う側の悲哀が強い。手付金に100万円はおろか、10万円さえ払えず、それを営業担当が自腹で無利子で貸すのである。家賃並みの支払額で買えるとの宣伝を真に受け、月々1万5千円のローンを組めると考えるのである。安くても隣と見た目同じはイヤなのである。安住できるマイホームへの信仰は、建ち続ける戸建て住宅を見れば明らかなとおり、令和の時代も現役だ。私も含め。
読了日:07月12日 著者:屋敷康蔵
 焔の感想
焔の感想
末世の百物語。ディストピア、そして人ならぬものへの変転が語られる。人間が減ってゆく。それぞれの短編は独立しているのでそれぞれに楽しめ、人間バンクとか、星野智幸らしい視点と展開で興味深い。どう結末するのかと期待したのに、なぜこうなったのでしょうか。最後の角力に喰われ、私の中に想像された均衡はだだ崩れ、こうなっては書き溜めた短編を単行本らしく整えるためにひねり出した趣向みたいな…いや、違うんだろうけども。希望が私には場違いに感じられて仕方ないからだな。単行本の表紙も好いが文庫本のも好い。
読了日:07月11日 著者:星野 智幸
 トマト缶の黒い真実 (ヒストリカル・スタディーズ)の感想
トマト缶の黒い真実 (ヒストリカル・スタディーズ)の感想
トマト缶は便利だ。手元のトマト缶には、イタリア国内の産地、品種、有機栽培であるとも書かれている。この本を読んで、抜け穴がそこら中にあることを知った後では全てが疑わしい。さすがにブラックインクとは思わないが、ウイグルの強制労働で収穫された戦闘用トマトでないと誰が保証できるだろう。クエン酸不使用、では他の添加物は? 品質保証マークにどれだけの信頼性が? 加工製品はもっとだし、トマトだけじゃない。ネオリベやグローバリズムの成れの果てに、知らずに騙されていたほうが幸せみたいな世界になっている証拠を突きつけられる。
読了日:07月10日 著者:ジャン=バティスト・マレ
 ドリトル先生航海記 (新潮文庫)の感想
ドリトル先生航海記 (新潮文庫)の感想
これも幼い頃に出会っておきたかった物語。感受性が強い年頃に読んで、どこが心に響くかはその子次第で分かれそうだ。ドリトル先生やスタビンズ君の魅力はさておいても、自然の学問の幅広いワンダーが散りばめられている。今の私には、初めて航海に出たときの心踊る感覚、ロング・アローが集めた標本の不思議、海カタツムリの殻を通して見た世界の美しさ、バンポ王子のキュートさが胸に残る。さらに訳した福岡先生の思い入れで、物語の力は2割増しじゃないかしら。Do a little,think a lot.の言葉遊びが素敵。
読了日:07月07日 著者:ヒュー ロフティング
 いのちをもてなす―環境と医療の現場からの感想
いのちをもてなす―環境と医療の現場からの感想
環境問題から終末期医療まで語れる珍しい経歴をお持ちの医師の著述集である。医師である人に「ペンタゴン・レポートが」なんて言われると面食らってしまった。しかし当然ながら、環境と人体は無関係ではない。流入流域の灌漑工事によるアラル海の縮小や日本の公害などは、人間による環境破壊と周辺住民の健康被害が関連する問題であり、医師の知見の生きる社会医学という分野なのだと知った。限られた資源を収奪する技術が進歩するほど、人間のこころの未熟さは強調されるとの指摘が鋭い。まさに歴史の全ては我れが我れがの帰結である。
読了日:07月04日 著者:大井 玄
注: は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。
読んでくれる人も稀であろうこのブログの意義といって、月に一度自分の読んだ本を眺め渡すことにもある。
これといって重みのある本は読んでいないな、また特に響く本は無かったな、と思うけれど、なんらかの糧にはなっているのだ。
特に社会を見る目がまた転換期にあると思う。
<今月のデータ>
購入21冊、購入費用14,994円。
読了12冊。
積読本320冊(うちKindle本156冊、Honto本9冊)。

7月の読書メーター
読んだ本の数:12
 吉田茂 ポピュリズムに背を向けて<下> (講談社文庫)の感想
吉田茂 ポピュリズムに背を向けて<下> (講談社文庫)の感想吉田茂の大舞台。サンフランシスコでの講和へ向かう場面はとかく目が潤んでしまって、未来の日本を想う先人たちの気持ちに感じ入った。政治家の在るべき姿について考えた。しかし一転、あとがきで感傷は吹っ飛ぶ。国民は政治を見る目を養えと著者は言う。政治家の本当の仕事は、一般人には見えない事の方が多いのだろう。そして政治の様相は、当時と今と違わない点も多い。それにしたって、小手先の人気取りだったり、粗忽な政策を議論を拒んで拙速に通したり、そんな教養も矜持も目減りが明らかな政治家がのさばる今の政治をどう信頼しろと。
読了日:07月28日 著者:北 康利

 美貌のひと 歴史に名を刻んだ顔 (PHP新書)の感想
美貌のひと 歴史に名を刻んだ顔 (PHP新書)の感想中野さんの本を読むのは好きだ。しかし絵を眺める時間は、3回くらい見返したとしてもそう長くない。きれいだなぁ、とか気味悪いなぁ、とか思うくらいで、どこがすごいのか探る気がさっぱり無い。私にとって中野さんの本は、ミニミステリだ。絵の裏に隠れた物語、壮大な、あるいは謎に満ちた、絵はその手がかり。もっと面白い話を聞きたくてずるずる読んでしまう。ユトリロにせよトルストイにせよ、ほう!と感嘆したことばかり印象に残って、絵も画家の名も覚えちゃいないのだ。でもアルテミジアは覚えておきたいな。かっこいいから。
読了日:07月23日 著者:中野 京子
 無敵の読解力 (文春新書 1341)の感想
無敵の読解力 (文春新書 1341)の感想素地の全く違う二人の対談本も早や何冊目か。しかし慣れ合うのではなく、敢えて異なる見方を相手の見解の横に並べてみせるところが面白い。相手を驚かせるための隠し玉を事前に仕込んだりしていそうだ。さて、政治家の教養について。為政者を志すなら、質と量ともに一般人のそれでは足りない。頼るべきは先人の知恵たる古典で、その道を進むなら読んでおくべき類のものが底力となる。若い頃に重厚なものを読む力をつけてそこまで辿り着くには、天賦の嗅覚か、身近な者の誘導が必要だろう。あるいは素養が足りないと自覚して誰か教師役を捕まえるか。
しかし「きちんとした読書の基盤がある政治家」は与野党共に減っているという。松岡正剛氏のエピソードが興味深い。ある政治家に本の読み方を教えてやってほしいと請われ、試みたが全くうまくいかなかったという。そもそも読む必要が理解できない者には、馬を水辺に連れて行くことはできても、である。テレビでは政権に対する忖度とも取れる発言に留める池上さんだが、本書では日本の元首相や政治家に対して、佐藤氏と毒舌の応酬である。ということは、局側からNGがかかっているのだろう。知識と毒舌がぽんぽん飛び出す池上さんは格好好いぞ。
佐藤氏:古代ローマの詩人ホラティウスの頌歌を引いた一節です。「祖父母に劣れる父母/さらに劣れるわれらを生めり、/われら遠からずして/より劣悪なる子孫を儲けん」。
読了日:07月22日 著者:池上 彰,佐藤 優

 吉田茂 ポピュリズムに背を向けて<上> (講談社文庫)の感想
吉田茂 ポピュリズムに背を向けて<上> (講談社文庫)の感想日本が敗戦に向かって転げ落ちている時分、政府や官僚は何をしていたのかと以前の私は鼻白んだものだったが、今よりも胆力があって優秀な政治家や外務省官僚でも止めることができないほど、陸軍や親独派政治家の勢いが急速についてしまっていた。なんとか戦争回避、早期終結に奮闘していたのが、あの首相の入替りの激しさ、内閣の短命に表れていたと知る。水面下で流れた組閣も多かった由。結局、戦争に積極的な態度を取った首相は東条だけだったようだ。吉田茂も切歯扼腕、陰で奔走していた一人。憲兵隊コード"ヨハンセン"とは「吉田反戦」の意。
降伏文書に誤りがあり、アメリカの担当者がそのままにしようとしたことに日本側は抗議、訂正を求める。『この期に及んでささやかな抵抗を試みた彼らのことを滑稽だと感じる人は、感情の襞のいささか少ない人だと言わざるを得ない。この時の彼らの立場に自らを置いてみる努力を、今の日本人はすべきであろう。戦いに敗れてなお、彼らのような矜持ある日本人が残っていたからこそ、この国は奇跡の回復をなしえたのである』。上巻の終りに近い箇所のエピソードだが、ずっと読み進めた後のこれは、じんときた。
読了日:07月19日 著者:北 康利

 鷗外の怪談の感想
鷗外の怪談の感想戯曲は面白いなあ。心に秘めたものまでが、台詞にほとんど詰め込まれている。主張も迷いも絶望も吐露され、揺れる。この永井荷風が私は大好きだ。身をもって、信念にかけて守ろうとするものが、日本という国家に阻まれ守ることができなかった、落胆、悲嘆。それは現代の私たちがあからさまな政治の逸脱を糾弾することができなかった、改憲勢力の増長を選挙で止めることができなかった、悪政を通した元首相を国葬にするなどという茶番を止めることができない予感、そのたびに味わう挫折感に似ているだろうか。これらは確実に、人の心をくじいてゆく。
読了日:07月14日 著者:永井 愛
 木綿リサイクルの衰退と復活 ―大阪八尾を中心とする木綿の経済史―〈発行:ブックウェイ〉の感想
木綿リサイクルの衰退と復活 ―大阪八尾を中心とする木綿の経済史―〈発行:ブックウェイ〉の感想木綿は温暖な地で江戸時代に栽培が盛んになった。しかし開国と共に輸入品に押される。明治16年、渋沢栄一が紡績会社設立。国産の綿でも試行錯誤したが、輸入品の綿糸のほうが良質だったため、明治19年以降中国産、インド産で操業。大正5年には河内の木綿栽培は壊滅した由。合成繊維が現れるまでもなかったようだ。なお、私の興味を引いた「リサイクル」とは、以前においては布地をボロボロになるまで使い倒した後、肥やしとして畑に鋤き込むことであり、現代においては"自然に優しい"に同義と扱われているあたり、不満と言わざるを得ない。
読了日:07月13日 著者:前田啓一
 壊れた脳 生存する知の感想
壊れた脳 生存する知の感想「奇跡の脳」の脳神経科学者ジル・ボルト・テイラーや、「脳はすごい」の人工知能研究者クラーク・エリオットなど、脳の専門家本人による脳損傷、負った高次脳機能障害とその回復の記録は、人知を超えたような、畏敬の念を読み手に与えてくれたものだったが、我が香川県にも脳損傷からの回復の経緯を記した医師があったのだ。脳の損傷によって起きる行動の変異。障害による消耗も激しいが、周囲の、特に医療従事者の無理解がずいぶんダメージになる。熱心に回復に取り組むほど、脳の自ら機能を再生する力も強まる。脳も凄いが、人間って凄いな。
読了日:07月12日 著者:山田 規畝子
 住宅営業マンぺこぺこ日記――「今月2件5000万! 」死にもの狂いでノルマこなしますの感想
住宅営業マンぺこぺこ日記――「今月2件5000万! 」死にもの狂いでノルマこなしますの感想フィリピンパブ接待だノルマだ気合だって、昭和なのはタマ…ホームだけだろうか。ローコスト住宅メーカーの内部事情。営業の悲哀はともかく、売り物が住まいである今作は買う側の悲哀が強い。手付金に100万円はおろか、10万円さえ払えず、それを営業担当が自腹で無利子で貸すのである。家賃並みの支払額で買えるとの宣伝を真に受け、月々1万5千円のローンを組めると考えるのである。安くても隣と見た目同じはイヤなのである。安住できるマイホームへの信仰は、建ち続ける戸建て住宅を見れば明らかなとおり、令和の時代も現役だ。私も含め。
読了日:07月12日 著者:屋敷康蔵

 焔の感想
焔の感想末世の百物語。ディストピア、そして人ならぬものへの変転が語られる。人間が減ってゆく。それぞれの短編は独立しているのでそれぞれに楽しめ、人間バンクとか、星野智幸らしい視点と展開で興味深い。どう結末するのかと期待したのに、なぜこうなったのでしょうか。最後の角力に喰われ、私の中に想像された均衡はだだ崩れ、こうなっては書き溜めた短編を単行本らしく整えるためにひねり出した趣向みたいな…いや、違うんだろうけども。希望が私には場違いに感じられて仕方ないからだな。単行本の表紙も好いが文庫本のも好い。
読了日:07月11日 著者:星野 智幸
 トマト缶の黒い真実 (ヒストリカル・スタディーズ)の感想
トマト缶の黒い真実 (ヒストリカル・スタディーズ)の感想トマト缶は便利だ。手元のトマト缶には、イタリア国内の産地、品種、有機栽培であるとも書かれている。この本を読んで、抜け穴がそこら中にあることを知った後では全てが疑わしい。さすがにブラックインクとは思わないが、ウイグルの強制労働で収穫された戦闘用トマトでないと誰が保証できるだろう。クエン酸不使用、では他の添加物は? 品質保証マークにどれだけの信頼性が? 加工製品はもっとだし、トマトだけじゃない。ネオリベやグローバリズムの成れの果てに、知らずに騙されていたほうが幸せみたいな世界になっている証拠を突きつけられる。
読了日:07月10日 著者:ジャン=バティスト・マレ

 ドリトル先生航海記 (新潮文庫)の感想
ドリトル先生航海記 (新潮文庫)の感想これも幼い頃に出会っておきたかった物語。感受性が強い年頃に読んで、どこが心に響くかはその子次第で分かれそうだ。ドリトル先生やスタビンズ君の魅力はさておいても、自然の学問の幅広いワンダーが散りばめられている。今の私には、初めて航海に出たときの心踊る感覚、ロング・アローが集めた標本の不思議、海カタツムリの殻を通して見た世界の美しさ、バンポ王子のキュートさが胸に残る。さらに訳した福岡先生の思い入れで、物語の力は2割増しじゃないかしら。Do a little,think a lot.の言葉遊びが素敵。
読了日:07月07日 著者:ヒュー ロフティング
 いのちをもてなす―環境と医療の現場からの感想
いのちをもてなす―環境と医療の現場からの感想環境問題から終末期医療まで語れる珍しい経歴をお持ちの医師の著述集である。医師である人に「ペンタゴン・レポートが」なんて言われると面食らってしまった。しかし当然ながら、環境と人体は無関係ではない。流入流域の灌漑工事によるアラル海の縮小や日本の公害などは、人間による環境破壊と周辺住民の健康被害が関連する問題であり、医師の知見の生きる社会医学という分野なのだと知った。限られた資源を収奪する技術が進歩するほど、人間のこころの未熟さは強調されるとの指摘が鋭い。まさに歴史の全ては我れが我れがの帰結である。
読了日:07月04日 著者:大井 玄

注:
 は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。 2022年07月01日
2022年6月の記録
つまり、易しいノンフィクションで興味の範囲を拡げたり、優れたノンフィクションで事物を深く理解したり、よく練られた物語で活劇を楽しんだりすることとは、根本的に目的が異なるのだ。優れた文学作品を読むことは、絵画や音楽など他の芸術鑑賞のように、現実を写実とは違ったやりかたで捉えることで、厳しい現実の人生に、新たな色彩や揺らぎを与え、息苦しさをつかのま逸らすことができる。
話題の本も読みたいものは読めばいいけれど、並行して古典や文学を味わうことも、私を救うんではないかな。サプリや流動食はほどほどに。
<今月のデータ>
購入10冊、購入費用15,196円。
読了17冊。
積読本312冊(うちKindle本147冊、Honto本9冊)。

6月の読書メーター
読んだ本の数:16
 頁をめくる音で息をするの感想
頁をめくる音で息をするの感想
高校時代の同級生が古本屋を営んでいるのだが、どうにもとらえどころのない人で、古本屋を営む理由を問うたところで理解できる返答が返ってくる気がしない。これしかないから。これしかできないから。とこの本の著者は古本屋を営む理由を語る。古本屋を営む理由というのは、飲食店や工事店のように明確に相手に訴求することばになるとは限らないのかもしれない。形ある物の売買でありながら形のない思いや気持ちが行き交う。古本屋でコーヒーやビールを飲みながらも好い。今は無きリバー書房の店主の淹れたコーヒー、ゆっくりいただけばよかった。
読了日:06月28日 著者:藤井基二
 隣の家の少女 (扶桑社ミステリー)の感想
隣の家の少女 (扶桑社ミステリー)の感想
けったくそ悪い物語だ。14歳だぞ。悪意、弱さ、卑怯さ。この事件に関わった少年ども皆、のたうち回って苦しんでくたばりますようにと祈る。デイヴィッドも例外ではない。悪夢など生ぬるい。この胸糞悪さは、このような事件が現実にもありふれて起こり得るからでもある。つい数年前、旭川でも「いじめによる自殺」事件があったはずだ。犠牲者になりかわり、私が呪いをかけてやる。キングがこの作品を褒めたのは1995年。頭おかしいんじゃないの。と毒づいておく。
読了日:06月25日 著者:ジャック ケッチャム
 第三の脳――皮膚から考える命、こころ、世界の感想
第三の脳――皮膚から考える命、こころ、世界の感想
皮膚の構造から、研究者がそんなこと書いていいのか級の仮説まで、幅広いトピック。しかし目下肌トラブルを抱える身としては、皮膚と精神の関わりについて知りたいのだ。『表皮が「興奮」するとバリアの回復が遅れ、肌荒れもひどくなり、「抑制」するとバリアの回復が促進され、肌荒れも治る』。痒さが痒さを呼び、「ここもかゆいよ」コールがやまない状態を私は「ケラチノサイトの大暴走」と呼んでいる。恒常的に放出されるサイトカインを鎮めるには何が良いか。精神よりも五感に心地良いことを心がけるのが実は最も効果的ではないかと思った次第。
マグネシウム塩やカルシウム塩は、角層のバリア回復を促進する。入浴剤としても使われるにがりの主成分はマグネシウム塩とカルシウム塩であり、またアトピーには海水浴が良いなんてこのような研究結果が出る前から言われていたのは、先人の知恵であるよなあ。マスクによる頬への摩擦や空気の乾燥、体重増加による衣服との摩擦、ストレスなど、肌の状態が悪化する要素には事欠かない。汗をかいて代謝を上げ、皮膚のバリア回復を図ろうと熱めの風呂に頑張って浸かっていたのは逆効果だったようだから、ぬるめのにがり湯に浸かって本を読むことにする。
読了日:06月24日 著者:傳田光洋
 ボーヴォワール『老い』 2021年7月 (NHK100分de名著)の感想
ボーヴォワール『老い』 2021年7月 (NHK100分de名著)の感想
ボーヴォワールは現実を直視できる目を持った人であるとともに、自由の良い面も悪い面も体現する生き方を貫いた女性であった。それは女性性、老いを取り上げた著作に見ることができる。ボーヴォワールを語る上野さんの口ぶりに称賛の響きがあるように感じた。彼女のように徹底した生き方はできないけれど、生物学的に遺伝子を繋がずとも、身を投げうつような献身でなくとも、なお後から来る人々に明かりを差し出す人でありたし。気になるぞボーヴォワール。読んでみたいがなあ。光文社さん、古典新訳文庫で出してくれないだろうか。
読了日:06月24日 著者:上野 千鶴子
 梅里雪山(メイリーシュエシャン)十七人の友を探して (ヤマケイ文庫)の感想
梅里雪山(メイリーシュエシャン)十七人の友を探して (ヤマケイ文庫)の感想
素敵な響きだ。地元の村人は聖なる山"カワカブ"と崇め、毎朝祈り、亡くなった家族や仲間を想って巡礼に出る。ひっくるめて信仰とし、平穏に暮らす。美しい自然、雪解け水が農作物を実らせ、牛や豚を育てる。こんなに豊かな生き方が現代にあるだろうか。その山の登頂を日中合同登山隊が目指し、全17人が遭難した。地元の村人たちは、聖山だから登らないでくれと繰り返し訴えた。なぜ現代人は未踏の高山に登りたがるのだろう。刹那に生命を賭けて山頂を征服するのが自然に逆らう行為なら、自然に命を預けて平穏に暮らすほうが気高いように思う。
読了日:06月21日 著者:小林尚礼
 82年生まれ、キム・ジヨン (単行本)の感想
82年生まれ、キム・ジヨン (単行本)の感想
同じ時代を生きる女性たちに思いを重ねる。憑依じみた行動は奇異だけど、それが母と先輩であったのには意味があって、女性は身近な女性の有形無形の助けによって支えられているのだと暗示する。韓国と日本はやはり似ている。それでも韓国の方が、男子を表立って優遇するぶん、酷いかな。男性を増長させる社会の仕組みにぞっとする。それは同時に弱い男性を疲弊させ、反動で女性を敵視させるのだ。でも男優遇な現実に気づかされて女性が水面下でうんざりしている日本よりも、女性がはっきり意思や怒りを表明する韓国の方が、変革は早いかもしれない。
ジヨンの母が素敵。耐えてきた自分の苦しみを娘たちに引き継がせることの残酷さへの自覚が、世代ごとに事をより良くしていると思う。ならば私たちも、子があろうとなかろうと、次の世代をより良い方向に押してあげる義務があるのだ。
読了日:06月20日 著者:チョ・ナムジュ
 ファインダーズ・キーパーズ 下 (文春文庫)の感想
ファインダーズ・キーパーズ 下 (文春文庫)の感想
物語の持つ力は大きい。物語という液体の中に頭の先まで沈み込めるような体験は稀で、そのような物語に出会えたことは身一つしかない人の生にとって祝福とも呼べるような出来事だ。でもどれだけ物語を現実のように感じられたとしても、目の前に生きている人を見失うことはあってはならんとわかっているかどうか。さて、キングの作品にシリーズ物は珍しい。だから、今作が前作のキャラクターを踏まえていることに戸惑った。しかも、当たり前だが、時間も人間関係も進展している。これはジミー・ゴールドものと同様、円環を描くと期待してよいのかな?
読了日:06月18日 著者:スティーヴン キング
 土 地球最後のナゾ 100億人を養う土壌を求めて (光文社新書)の感想
土 地球最後のナゾ 100億人を養う土壌を求めて (光文社新書)の感想
土って面白い。毎日目にするものなのに、眼から鱗がぼろぼろ落ちた。気候や地面の成り立ちによって、土は違った様相を見せる。農作物や特産品も、その地の土や水に因って生まれる。人はその土に合う作物を見つけ、またより豊かになるよう改良を重ねて食物を手に入れる。日本は豊かな土壌だと思っていたけれど、火山灰土壌や未熟土は、世界の中で見れば土としてはそうでもない。でも日本には豊かな水と農耕のノウハウがある。だから豊かなのだ。パンを食べるからじゃあ小麦をという訳にはいかないとわかった。日本には日本の豊穣、失いたくないなあ。
世界で最も豊かな性質を持った土は、チェルノーゼム。その土壌を持つ代表として、ウクライナに度々言及している。小麦を生産する広大な畑。収穫した小麦やトウモロコシを輸出できない、長年耕作してきた農地に植え付けできなかった、また砲弾だらけになった、ダメージは思うより甚大になるだろう。そしてウクライナ兵の捕虜や住民が貧しい土壌の極東に送られていると聞く。土が変われば作物も農法もまるで変ってしまう。そもそも農耕可能な土地があてがわれるかもわからない。かの人たちは、生きてゆけるだろうか。どうか恵みがありますように。
『我々は天体の動きについての方が分かっている、足元にある土よりも』 by レオナルド・ダ・ヴィンチ。不耕起栽培とか無農薬とか聞きかじったものに私は真実を見出したがるけれど、きっとそこには想像よりずっと奥深く、いろいろな真実があるのだろうな。日本の土は農耕や水によって酸性に傾きがちだ。日本の農地に石灰を撒きまわるのはそういうことかと納得もした。私はそのあたりを知らないに等しいので、わくわくしながら多面的に掘り返して、土、微生物、農作物、腸内環境、人間と関心をつなげ拡げてゆく予定。
読了日:06月14日 著者:藤井 一至
 ファインダーズ・キーパーズ 上 (文春文庫 キ 2-57)の感想
ファインダーズ・キーパーズ 上 (文春文庫 キ 2-57)の感想
キングが社会問題を背景に入れ込むようになったのはいつ頃だったか。経済破綻や再び描写された無差別犯罪によって窮地に置かれた罪なき人々。格差を背景に、人々はより金銭にがめつくなり、主人公の家では<うちの一家はどんづまり>が頻繁に上演される。今回被害者を作家としたのはキングの企みだ。キングが教師として教えていた頃のことや「書くことについて」を彷彿とする。物語をつくりあげるものの『見た目はオートミールそっくり』ににやり。ホッジズ&ホリーの出番は終盤にちょっぴり。前作のキャラをあらかた忘れてしまっている自分が残念。
読了日:06月12日 著者:スティーヴン キング
 ココアどこ わたしはゴマだれの感想
ココアどこ わたしはゴマだれの感想
表紙のつくりにスイセイさんのこだわりが炸裂している。スナックたかやまが好い。ゲストとスイセイさんが話し、高山さんも料理を出しながら参加する感じが、そんなスナック行きたい。でも高山さんとスイセイさんがディープに話しているのはよくわからん。『生キルノ手帖』はもっとわからん。あと、どれだけ高山さんが神経を逆なでしたのだとしても、怒鳴りつけるスイセイさんは嫌だ。高山さんはスイセイさんに問いかけ、対話することによって、生きることの解釈や指針を引き出していた。これだけ深く話しあえる二人なのに、なぜなんだろう。
読了日:06月10日 著者:高山 なおみ,スイセイ
 快楽としての動物保護 『シートン動物記』から『ザ・コーヴ』へ (講談社選書メチエ)の感想
快楽としての動物保護 『シートン動物記』から『ザ・コーヴ』へ (講談社選書メチエ)の感想
そもそも人間の集団がさほど大きくなかった頃までは、民族と動物の間に古来より時間をかけて培った関係は文化や思想として、節度を持った均衡点を持っていた。他者のそれを想像する必要をはじめ、住みついてさえ会得することのできない微細の感覚があることは、前提としたい。思うに、人間は21世紀になってなお、自然のことも動物のことも理解しきれてなどいないのだ。加えて、一義的な「正しさ」を振りかざして、「野蛮」と決めつけた相手を糾弾する行為が快感と知覚される現象は想像に難くない。そしてそれは物事をより良くする結果は生まない。
去年亡くした猫のこと。彼は食欲を無くした後、ベランダの地面のコンクリートを熱心に舐めていた。その理由、そこにある真実を、インターネットでも獣医でも本でも私は見つけることができなかった。もしこれが外に自由に出られて、草むらや里山を出歩ける生活なら、彼は自分で自らを癒す植物なりを見つけに行くことができたはずなのだ。「猫は室内で飼うのが良いのです」としたり顔で説明していた自分の顔を平手打ちにしたかった。それは、100%人間都合の論理だ。私は知っているとばかり得意になって話す、そこに快感がなかったとは言わない。
イルカ(とクジラ)を特別視する風潮の生まれた経緯にも詳しい。ある研究者の描いたイルカについての論文(ポエム)が膨張し、到達点としてシー・シェパードは「ザ・コーヴ」で太地町の漁従事者の野蛮を糾弾するパフォーマンスを成し遂げた。イルカを自然のアイコン、特別愛すべき存在と位置付ける流れは「グランブルー」、「フィリー・ウィリー」、ラッセンの絵画など、1980年代以降の流行に表象されていたと著者は指摘する。知らず喜んで観ていた過去の自分を振り返ると、そのような「正しさ」の波がどれだけ人を呑み込みやすいものかと驚く。
読了日:06月08日 著者:信岡 朝子
 非正規介護職員ヨボヨボ日記――当年60歳、排泄も入浴もお世話させていただきますの感想
非正規介護職員ヨボヨボ日記――当年60歳、排泄も入浴もお世話させていただきますの感想
祖母の葬儀を思い出す。通っていたデイサービスの職員5、6人が焼香に来てくれた。見慣れた色の作業服を見た時に気づいたのは、祖母が晩年楽しみにしていたのが、なんでもない会話でも児戯じみた遊びでも、職員との軽やかなやりとりに違いなかったことだ。この著者は長期入所施設の職員ということもあり、情を入れすぎては身が持たないと、全編にわたって淡々とした印象を受ける。それでも、面白がったり憤慨したりしながらでも人間と人間の付き合いをすることは、専門職としての身体のケアと同じようにこの仕事の大切な部分なのだと感じた。
読了日:06月07日 著者:真山 剛
 古来種野菜を食べてください。の感想
古来種野菜を食べてください。の感想
日本農業新聞など読みながら釈然としなかったものが晴れた。今、国が推進している農作物の有機化は、ぱっと見に必要なことなのだけれど、思想が伴っていない。それはトップダウンなせいらしい。著者は「農業」と「農」を別と捉える。国民に食べさせるだけの農作物を確保するためには、化学肥料も最新技術もAIも使って、量を確保する、それが「農業」で、一方の「農」は古来の知恵や自然の持つ力を信じ、少量でも守っていく思想ありきだ。どちらも必要と捉えつつ、双方寄せ合っていけたらいい。『農法は生き方』。ならば、食べ方も生き方だなあ。
読了日:06月06日 著者:高橋 一也
 ホビットの冒険 (全1冊) (岩波少年文庫)の感想
ホビットの冒険 (全1冊) (岩波少年文庫)の感想
ホビットなんて見たこともない生き物、少ない挿絵をヒントに家も風景も全て想像するしかない。その彼らの世界に入り込み、冒険を共にする。なんと豊かな愉しみだろう。ビルボが能動的に冒険を想ったのはほんの一瞬で、あとは巻き込まれなされるがままの流れの中で 思い、考え、選ぶ。道を進み続けるのは大変なこと、世界にはいろんな人がいること、「自分ひとりのはげしい心の戦い」を戦わなければならない時があること。子供への贈り物としての物語は、大人が読んでも面白いけれど、やはり感性の鈍りは否めず、味わいきれなさが残念。姪に贈る。
ビルボの台詞。『ああ、やりきれない! わたしは今まで、かずかずの戦のほめ歌をきかされてきた。そしていつも、ほろびる者に栄光があると思ってきた。だが戦とは、ひさんなばかりでなく、まことにやりきれないものだ。この戦に加わらなかったらなあ!』 1937年の作品だから、ヨーロッパの戦争は無関係ではない。父から子供たちへの物語。ドワーフや人間、エルフ、ワシ族ほかの者たちは友好と均衡を取り戻すが、スマウグは滅び、ゴブリンとアクマイヌは叩きのめされる。平和。物語の中ですらかくも難しきもの。
読了日:06月05日 著者:J.R.R.トールキン
 ある人殺しの物語 香水 (文春文庫)の感想
ある人殺しの物語 香水 (文春文庫)の感想
のっけからものすごい臭気に襲われる。近世フランスの街に充満する種々の臭い、その臭いを消すための匂い。なので臭いも匂いも持たない体質の主人公は、醜くも透明さを併せ持った者のようにもあるが、人間らしいにおいをつけるための香水を身につけた瞬間から、身の内に凝った情念を一気に発散させる。彼が善悪の判断を持たなかったのはにおいとは関係ないだろうし、モラルも善意もあったもんじゃない時代の人々の行為には親愛の情も持ちようがない。そして後味がどうとか評しようのない幕切れ。これがそれほどの話題作になった理由が知りたし。
読了日:06月02日 著者:パトリック ジュースキント
 ペルソナ 脳に潜む闇 (講談社現代新書)の感想
ペルソナ 脳に潜む闇 (講談社現代新書)の感想
理知的な中野信子と辛辣な中野信子が波のように入れ替わる。"私の毒々しい感情"と称するところの主観を露わにするには、公的な場でまとう鎧をある程度削り落とさなければならず、その真っ当な防衛反応として、表れる棘は鋭い。中野信子にすれば他人の同調など鬱陶しいだけだろうけれど、本気で読みたければこちらも多かれ少なかれ血を流す覚悟で武装せざるを得ず、ふと気を抜くとつい「わかるよ。。。」とつぶやいてしまう。「ホンマでっか!?TV」との出会いは良かったのだなあ。あの番組に出ている中野信子はとても楽しんでいるように見える。
読者が何のために中野信子の書く本を読むのかを自ら分析するくだりがある。私は何故読みたかったのだろう? もちろん金を恵みたいのではない。完全に同世代である中野信子に共感したいという動機は認めざるを得ない。役に立てたかったのだろうか? 様々な事象を「理解しすぎてしまう」彼女が、このややこしい時代を、理不尽な人生というものを、どんなふうに処理しているのか知りたかった。クレバーな処しようがあるなら知りたかった。中野信子には論理的な頭脳と共に、芸術的な感性がある。それがこれだ。そしてそれは私には、文学と自然だろう。
『時間は、ただの時の流れではなくて、寿命の一部である。一部とはいえ、こんな闘争に、命を懸けて取り組む価値など、欠片もない。過去のよく知りもしない人が勝手に作り上げてきた男性原理を覆すなんていうことのために、自分の、有限でしかない時間を、惜しみなく注ぐ気になど到底なれない』。中野信子独特の言いように、声を出して笑ってしまった。遺伝子を残さない自分の引け目もあり、男性優位なこの社会で、後に続く女性たちのために抵抗し闘う義務が自分にあるように思っている私にはちょっと快感。それもまたよし。気張りすぎなさんな、私。
読了日:06月01日 著者:中野 信子
注: は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。
話題の本も読みたいものは読めばいいけれど、並行して古典や文学を味わうことも、私を救うんではないかな。サプリや流動食はほどほどに。
<今月のデータ>
購入10冊、購入費用15,196円。
読了17冊。
積読本312冊(うちKindle本147冊、Honto本9冊)。

6月の読書メーター
読んだ本の数:16
 頁をめくる音で息をするの感想
頁をめくる音で息をするの感想高校時代の同級生が古本屋を営んでいるのだが、どうにもとらえどころのない人で、古本屋を営む理由を問うたところで理解できる返答が返ってくる気がしない。これしかないから。これしかできないから。とこの本の著者は古本屋を営む理由を語る。古本屋を営む理由というのは、飲食店や工事店のように明確に相手に訴求することばになるとは限らないのかもしれない。形ある物の売買でありながら形のない思いや気持ちが行き交う。古本屋でコーヒーやビールを飲みながらも好い。今は無きリバー書房の店主の淹れたコーヒー、ゆっくりいただけばよかった。
読了日:06月28日 著者:藤井基二
 隣の家の少女 (扶桑社ミステリー)の感想
隣の家の少女 (扶桑社ミステリー)の感想けったくそ悪い物語だ。14歳だぞ。悪意、弱さ、卑怯さ。この事件に関わった少年ども皆、のたうち回って苦しんでくたばりますようにと祈る。デイヴィッドも例外ではない。悪夢など生ぬるい。この胸糞悪さは、このような事件が現実にもありふれて起こり得るからでもある。つい数年前、旭川でも「いじめによる自殺」事件があったはずだ。犠牲者になりかわり、私が呪いをかけてやる。キングがこの作品を褒めたのは1995年。頭おかしいんじゃないの。と毒づいておく。
読了日:06月25日 著者:ジャック ケッチャム

 第三の脳――皮膚から考える命、こころ、世界の感想
第三の脳――皮膚から考える命、こころ、世界の感想皮膚の構造から、研究者がそんなこと書いていいのか級の仮説まで、幅広いトピック。しかし目下肌トラブルを抱える身としては、皮膚と精神の関わりについて知りたいのだ。『表皮が「興奮」するとバリアの回復が遅れ、肌荒れもひどくなり、「抑制」するとバリアの回復が促進され、肌荒れも治る』。痒さが痒さを呼び、「ここもかゆいよ」コールがやまない状態を私は「ケラチノサイトの大暴走」と呼んでいる。恒常的に放出されるサイトカインを鎮めるには何が良いか。精神よりも五感に心地良いことを心がけるのが実は最も効果的ではないかと思った次第。
マグネシウム塩やカルシウム塩は、角層のバリア回復を促進する。入浴剤としても使われるにがりの主成分はマグネシウム塩とカルシウム塩であり、またアトピーには海水浴が良いなんてこのような研究結果が出る前から言われていたのは、先人の知恵であるよなあ。マスクによる頬への摩擦や空気の乾燥、体重増加による衣服との摩擦、ストレスなど、肌の状態が悪化する要素には事欠かない。汗をかいて代謝を上げ、皮膚のバリア回復を図ろうと熱めの風呂に頑張って浸かっていたのは逆効果だったようだから、ぬるめのにがり湯に浸かって本を読むことにする。
読了日:06月24日 著者:傳田光洋
 ボーヴォワール『老い』 2021年7月 (NHK100分de名著)の感想
ボーヴォワール『老い』 2021年7月 (NHK100分de名著)の感想ボーヴォワールは現実を直視できる目を持った人であるとともに、自由の良い面も悪い面も体現する生き方を貫いた女性であった。それは女性性、老いを取り上げた著作に見ることができる。ボーヴォワールを語る上野さんの口ぶりに称賛の響きがあるように感じた。彼女のように徹底した生き方はできないけれど、生物学的に遺伝子を繋がずとも、身を投げうつような献身でなくとも、なお後から来る人々に明かりを差し出す人でありたし。気になるぞボーヴォワール。読んでみたいがなあ。光文社さん、古典新訳文庫で出してくれないだろうか。
読了日:06月24日 著者:上野 千鶴子

 梅里雪山(メイリーシュエシャン)十七人の友を探して (ヤマケイ文庫)の感想
梅里雪山(メイリーシュエシャン)十七人の友を探して (ヤマケイ文庫)の感想素敵な響きだ。地元の村人は聖なる山"カワカブ"と崇め、毎朝祈り、亡くなった家族や仲間を想って巡礼に出る。ひっくるめて信仰とし、平穏に暮らす。美しい自然、雪解け水が農作物を実らせ、牛や豚を育てる。こんなに豊かな生き方が現代にあるだろうか。その山の登頂を日中合同登山隊が目指し、全17人が遭難した。地元の村人たちは、聖山だから登らないでくれと繰り返し訴えた。なぜ現代人は未踏の高山に登りたがるのだろう。刹那に生命を賭けて山頂を征服するのが自然に逆らう行為なら、自然に命を預けて平穏に暮らすほうが気高いように思う。
読了日:06月21日 著者:小林尚礼

 82年生まれ、キム・ジヨン (単行本)の感想
82年生まれ、キム・ジヨン (単行本)の感想同じ時代を生きる女性たちに思いを重ねる。憑依じみた行動は奇異だけど、それが母と先輩であったのには意味があって、女性は身近な女性の有形無形の助けによって支えられているのだと暗示する。韓国と日本はやはり似ている。それでも韓国の方が、男子を表立って優遇するぶん、酷いかな。男性を増長させる社会の仕組みにぞっとする。それは同時に弱い男性を疲弊させ、反動で女性を敵視させるのだ。でも男優遇な現実に気づかされて女性が水面下でうんざりしている日本よりも、女性がはっきり意思や怒りを表明する韓国の方が、変革は早いかもしれない。
ジヨンの母が素敵。耐えてきた自分の苦しみを娘たちに引き継がせることの残酷さへの自覚が、世代ごとに事をより良くしていると思う。ならば私たちも、子があろうとなかろうと、次の世代をより良い方向に押してあげる義務があるのだ。
読了日:06月20日 著者:チョ・ナムジュ
 ファインダーズ・キーパーズ 下 (文春文庫)の感想
ファインダーズ・キーパーズ 下 (文春文庫)の感想物語の持つ力は大きい。物語という液体の中に頭の先まで沈み込めるような体験は稀で、そのような物語に出会えたことは身一つしかない人の生にとって祝福とも呼べるような出来事だ。でもどれだけ物語を現実のように感じられたとしても、目の前に生きている人を見失うことはあってはならんとわかっているかどうか。さて、キングの作品にシリーズ物は珍しい。だから、今作が前作のキャラクターを踏まえていることに戸惑った。しかも、当たり前だが、時間も人間関係も進展している。これはジミー・ゴールドものと同様、円環を描くと期待してよいのかな?
読了日:06月18日 著者:スティーヴン キング
 土 地球最後のナゾ 100億人を養う土壌を求めて (光文社新書)の感想
土 地球最後のナゾ 100億人を養う土壌を求めて (光文社新書)の感想土って面白い。毎日目にするものなのに、眼から鱗がぼろぼろ落ちた。気候や地面の成り立ちによって、土は違った様相を見せる。農作物や特産品も、その地の土や水に因って生まれる。人はその土に合う作物を見つけ、またより豊かになるよう改良を重ねて食物を手に入れる。日本は豊かな土壌だと思っていたけれど、火山灰土壌や未熟土は、世界の中で見れば土としてはそうでもない。でも日本には豊かな水と農耕のノウハウがある。だから豊かなのだ。パンを食べるからじゃあ小麦をという訳にはいかないとわかった。日本には日本の豊穣、失いたくないなあ。
世界で最も豊かな性質を持った土は、チェルノーゼム。その土壌を持つ代表として、ウクライナに度々言及している。小麦を生産する広大な畑。収穫した小麦やトウモロコシを輸出できない、長年耕作してきた農地に植え付けできなかった、また砲弾だらけになった、ダメージは思うより甚大になるだろう。そしてウクライナ兵の捕虜や住民が貧しい土壌の極東に送られていると聞く。土が変われば作物も農法もまるで変ってしまう。そもそも農耕可能な土地があてがわれるかもわからない。かの人たちは、生きてゆけるだろうか。どうか恵みがありますように。
『我々は天体の動きについての方が分かっている、足元にある土よりも』 by レオナルド・ダ・ヴィンチ。不耕起栽培とか無農薬とか聞きかじったものに私は真実を見出したがるけれど、きっとそこには想像よりずっと奥深く、いろいろな真実があるのだろうな。日本の土は農耕や水によって酸性に傾きがちだ。日本の農地に石灰を撒きまわるのはそういうことかと納得もした。私はそのあたりを知らないに等しいので、わくわくしながら多面的に掘り返して、土、微生物、農作物、腸内環境、人間と関心をつなげ拡げてゆく予定。
読了日:06月14日 著者:藤井 一至

 ファインダーズ・キーパーズ 上 (文春文庫 キ 2-57)の感想
ファインダーズ・キーパーズ 上 (文春文庫 キ 2-57)の感想キングが社会問題を背景に入れ込むようになったのはいつ頃だったか。経済破綻や再び描写された無差別犯罪によって窮地に置かれた罪なき人々。格差を背景に、人々はより金銭にがめつくなり、主人公の家では<うちの一家はどんづまり>が頻繁に上演される。今回被害者を作家としたのはキングの企みだ。キングが教師として教えていた頃のことや「書くことについて」を彷彿とする。物語をつくりあげるものの『見た目はオートミールそっくり』ににやり。ホッジズ&ホリーの出番は終盤にちょっぴり。前作のキャラをあらかた忘れてしまっている自分が残念。
読了日:06月12日 著者:スティーヴン キング
 ココアどこ わたしはゴマだれの感想
ココアどこ わたしはゴマだれの感想表紙のつくりにスイセイさんのこだわりが炸裂している。スナックたかやまが好い。ゲストとスイセイさんが話し、高山さんも料理を出しながら参加する感じが、そんなスナック行きたい。でも高山さんとスイセイさんがディープに話しているのはよくわからん。『生キルノ手帖』はもっとわからん。あと、どれだけ高山さんが神経を逆なでしたのだとしても、怒鳴りつけるスイセイさんは嫌だ。高山さんはスイセイさんに問いかけ、対話することによって、生きることの解釈や指針を引き出していた。これだけ深く話しあえる二人なのに、なぜなんだろう。
読了日:06月10日 著者:高山 なおみ,スイセイ
 快楽としての動物保護 『シートン動物記』から『ザ・コーヴ』へ (講談社選書メチエ)の感想
快楽としての動物保護 『シートン動物記』から『ザ・コーヴ』へ (講談社選書メチエ)の感想そもそも人間の集団がさほど大きくなかった頃までは、民族と動物の間に古来より時間をかけて培った関係は文化や思想として、節度を持った均衡点を持っていた。他者のそれを想像する必要をはじめ、住みついてさえ会得することのできない微細の感覚があることは、前提としたい。思うに、人間は21世紀になってなお、自然のことも動物のことも理解しきれてなどいないのだ。加えて、一義的な「正しさ」を振りかざして、「野蛮」と決めつけた相手を糾弾する行為が快感と知覚される現象は想像に難くない。そしてそれは物事をより良くする結果は生まない。
去年亡くした猫のこと。彼は食欲を無くした後、ベランダの地面のコンクリートを熱心に舐めていた。その理由、そこにある真実を、インターネットでも獣医でも本でも私は見つけることができなかった。もしこれが外に自由に出られて、草むらや里山を出歩ける生活なら、彼は自分で自らを癒す植物なりを見つけに行くことができたはずなのだ。「猫は室内で飼うのが良いのです」としたり顔で説明していた自分の顔を平手打ちにしたかった。それは、100%人間都合の論理だ。私は知っているとばかり得意になって話す、そこに快感がなかったとは言わない。
イルカ(とクジラ)を特別視する風潮の生まれた経緯にも詳しい。ある研究者の描いたイルカについての論文(ポエム)が膨張し、到達点としてシー・シェパードは「ザ・コーヴ」で太地町の漁従事者の野蛮を糾弾するパフォーマンスを成し遂げた。イルカを自然のアイコン、特別愛すべき存在と位置付ける流れは「グランブルー」、「フィリー・ウィリー」、ラッセンの絵画など、1980年代以降の流行に表象されていたと著者は指摘する。知らず喜んで観ていた過去の自分を振り返ると、そのような「正しさ」の波がどれだけ人を呑み込みやすいものかと驚く。
読了日:06月08日 著者:信岡 朝子

 非正規介護職員ヨボヨボ日記――当年60歳、排泄も入浴もお世話させていただきますの感想
非正規介護職員ヨボヨボ日記――当年60歳、排泄も入浴もお世話させていただきますの感想祖母の葬儀を思い出す。通っていたデイサービスの職員5、6人が焼香に来てくれた。見慣れた色の作業服を見た時に気づいたのは、祖母が晩年楽しみにしていたのが、なんでもない会話でも児戯じみた遊びでも、職員との軽やかなやりとりに違いなかったことだ。この著者は長期入所施設の職員ということもあり、情を入れすぎては身が持たないと、全編にわたって淡々とした印象を受ける。それでも、面白がったり憤慨したりしながらでも人間と人間の付き合いをすることは、専門職としての身体のケアと同じようにこの仕事の大切な部分なのだと感じた。
読了日:06月07日 著者:真山 剛

 古来種野菜を食べてください。の感想
古来種野菜を食べてください。の感想日本農業新聞など読みながら釈然としなかったものが晴れた。今、国が推進している農作物の有機化は、ぱっと見に必要なことなのだけれど、思想が伴っていない。それはトップダウンなせいらしい。著者は「農業」と「農」を別と捉える。国民に食べさせるだけの農作物を確保するためには、化学肥料も最新技術もAIも使って、量を確保する、それが「農業」で、一方の「農」は古来の知恵や自然の持つ力を信じ、少量でも守っていく思想ありきだ。どちらも必要と捉えつつ、双方寄せ合っていけたらいい。『農法は生き方』。ならば、食べ方も生き方だなあ。
読了日:06月06日 著者:高橋 一也
 ホビットの冒険 (全1冊) (岩波少年文庫)の感想
ホビットの冒険 (全1冊) (岩波少年文庫)の感想ホビットなんて見たこともない生き物、少ない挿絵をヒントに家も風景も全て想像するしかない。その彼らの世界に入り込み、冒険を共にする。なんと豊かな愉しみだろう。ビルボが能動的に冒険を想ったのはほんの一瞬で、あとは巻き込まれなされるがままの流れの中で 思い、考え、選ぶ。道を進み続けるのは大変なこと、世界にはいろんな人がいること、「自分ひとりのはげしい心の戦い」を戦わなければならない時があること。子供への贈り物としての物語は、大人が読んでも面白いけれど、やはり感性の鈍りは否めず、味わいきれなさが残念。姪に贈る。
ビルボの台詞。『ああ、やりきれない! わたしは今まで、かずかずの戦のほめ歌をきかされてきた。そしていつも、ほろびる者に栄光があると思ってきた。だが戦とは、ひさんなばかりでなく、まことにやりきれないものだ。この戦に加わらなかったらなあ!』 1937年の作品だから、ヨーロッパの戦争は無関係ではない。父から子供たちへの物語。ドワーフや人間、エルフ、ワシ族ほかの者たちは友好と均衡を取り戻すが、スマウグは滅び、ゴブリンとアクマイヌは叩きのめされる。平和。物語の中ですらかくも難しきもの。
読了日:06月05日 著者:J.R.R.トールキン

 ある人殺しの物語 香水 (文春文庫)の感想
ある人殺しの物語 香水 (文春文庫)の感想のっけからものすごい臭気に襲われる。近世フランスの街に充満する種々の臭い、その臭いを消すための匂い。なので臭いも匂いも持たない体質の主人公は、醜くも透明さを併せ持った者のようにもあるが、人間らしいにおいをつけるための香水を身につけた瞬間から、身の内に凝った情念を一気に発散させる。彼が善悪の判断を持たなかったのはにおいとは関係ないだろうし、モラルも善意もあったもんじゃない時代の人々の行為には親愛の情も持ちようがない。そして後味がどうとか評しようのない幕切れ。これがそれほどの話題作になった理由が知りたし。
読了日:06月02日 著者:パトリック ジュースキント
 ペルソナ 脳に潜む闇 (講談社現代新書)の感想
ペルソナ 脳に潜む闇 (講談社現代新書)の感想理知的な中野信子と辛辣な中野信子が波のように入れ替わる。"私の毒々しい感情"と称するところの主観を露わにするには、公的な場でまとう鎧をある程度削り落とさなければならず、その真っ当な防衛反応として、表れる棘は鋭い。中野信子にすれば他人の同調など鬱陶しいだけだろうけれど、本気で読みたければこちらも多かれ少なかれ血を流す覚悟で武装せざるを得ず、ふと気を抜くとつい「わかるよ。。。」とつぶやいてしまう。「ホンマでっか!?TV」との出会いは良かったのだなあ。あの番組に出ている中野信子はとても楽しんでいるように見える。
読者が何のために中野信子の書く本を読むのかを自ら分析するくだりがある。私は何故読みたかったのだろう? もちろん金を恵みたいのではない。完全に同世代である中野信子に共感したいという動機は認めざるを得ない。役に立てたかったのだろうか? 様々な事象を「理解しすぎてしまう」彼女が、このややこしい時代を、理不尽な人生というものを、どんなふうに処理しているのか知りたかった。クレバーな処しようがあるなら知りたかった。中野信子には論理的な頭脳と共に、芸術的な感性がある。それがこれだ。そしてそれは私には、文学と自然だろう。
『時間は、ただの時の流れではなくて、寿命の一部である。一部とはいえ、こんな闘争に、命を懸けて取り組む価値など、欠片もない。過去のよく知りもしない人が勝手に作り上げてきた男性原理を覆すなんていうことのために、自分の、有限でしかない時間を、惜しみなく注ぐ気になど到底なれない』。中野信子独特の言いように、声を出して笑ってしまった。遺伝子を残さない自分の引け目もあり、男性優位なこの社会で、後に続く女性たちのために抵抗し闘う義務が自分にあるように思っている私にはちょっと快感。それもまたよし。気張りすぎなさんな、私。
読了日:06月01日 著者:中野 信子

注:
 は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。 2022年06月01日
2022年5月の記録
SNSに登録している、読んだ本の冊数が2000冊目を超えたのだとか。
感想も1700冊以上書いているそうだから、1冊255字とはいえなかなかの量になった。
自分の書いた感想に感じ入ることも少なくない。
さらに以前の、幼少の頃に読んだ本たちや何度も読み返した本たちに思いを馳せる。
もう思い出せなかったりするそれらすべてを糧にして今の私がある。
<今月のデータ>
購入28冊、購入費用23,490円。
読了16冊。
積読本321冊(うちKindle本154冊、Honto本11冊)。

5月の読書メーター
読んだ本の数:16
 桃 もうひとつのツ、イ、ラ、ク (角川文庫)の感想
桃 もうひとつのツ、イ、ラ、ク (角川文庫)の感想
「ツ、イ、ラ、ク」から間を置かずに読めばもっとヒリヒリできたかもしれない。彼女の周りにいた「普通の」生徒たち。彼/彼女らに対して私の感じていた嫌らしさは、本人が意識的に選択して行動した/行動しなかったからではなく、生物的スキルによって自動選択されたもの故であった。一方で彼/彼女らもまた熟し始めた個体としての衝動を隠し持っていたのであり、彼女のみを異質物のように浮かせた一方、彼女から少なからず影響を受けていた出来事がこれらの短編では明らかにされる、そのお互い知り得ない他者の内部の底知れなさがじわじわくる。
読了日:05月27日 著者:姫野 カオルコ
 現代華文推理系列 第一集の感想
現代華文推理系列 第一集の感想
若手作家による華文ミステリ集。外国ミステリとはいえ、学校のようなクローズド設定で、論理を詰めて進める類の謎解きミステリは日本のそれと何も変わらないのでつまらない。面白いのは、社会性や叙情性を持ち込むのみならず、それらを巧く利用した作品だ。水天一色「おれみたいな奴が」では社会的底辺者の鬱屈やユーモアがプーアル茶のくだりに現れ、寵物先生「犯罪の赤い糸」には『神経がサトウキビぐらい図太くないと』や『節のほかから枝が生えないように』のような独特の言い回しが興を添える。先入観が無いから楽しめる。はまりそうな予感!
読了日:05月24日 著者:御手洗熊猫,水天一色,林斯諺,寵物先生
 くそつまらない未来を変えられるかもしれない投資の話 (シリーズ3/4)の感想
くそつまらない未来を変えられるかもしれない投資の話 (シリーズ3/4)の感想
パンクな個人投資家によるお金の使いかた指南。金融リテラシーを得る入門書として楽しく読める。なんて言うと軽い啓発本みたいだけど、ちゃんとした知識に根差した哲学がある。今遊ぶことを諦めず、将来のことも捨てない生き方。あと、金融商品でも生活に必要な品物でも、応援したい、ずっと残ってほしい、社会の役に立つと思えるお店の商品を選んで買おうよという話。これはこれで、自分たちの行動次第で未来を自分好みに変えられると考え行動する意味においては未来を拓く動きであり、例えば渋沢健氏の投資哲学とは違った知性の表れだと思う。
読了日:05月21日 著者:ヤマザキOKコンピュータ
 カラスをだます (NHK出版新書 646)の感想
カラスをだます (NHK出版新書 646)の感想
研究者からのベンチャー起業家、自称"カラス・ソリューショニスト"。カラスが好きで研究者になったわけでない人もいる。さて、カラスをだます。カラスを食べる。どちらも人間社会とカラスの摩擦を解消する試みだ。しかし視覚優位で記憶力にも優れるカラスを人間の意に沿わせるのは大変と知る。カラス剥製ロボットの首がもげたところは笑いすぎて涙が出た。カラスが人間の出すゴミを漁って、プラスチックを大量に食べてしまわないか心配だったが、カラスは消化できないものを体内に溜めず、ペリットと呼ばれる塊にして吐き出すと知って安心した。
読了日:05月20日 著者:塚原 直樹
 僕たちはどう生きるか 言葉と思考のエコロジカルな転回の感想
僕たちはどう生きるか 言葉と思考のエコロジカルな転回の感想
日本の若き知性として注目される、森田真生氏のエッセイ。書店で手に取った瞬間、やられたと思った。なにかここにある、と予感した。『このままではいけない。いままでとは別の、生き方を探しなさい』。感染症による活動縮小を契機に、新しいセンサを働かせて取り組む活動のセンスが好い。通底するのは、人間が人間でないものたちと同じ地平に降り立とうとする意思だ。『人間はもっと humiliate されていい』と言う。これまでと同じようには生きていくことができなくなった世界では、思考より肌感覚に従う、柔軟な行動こそ生き抜く術。
舩橋真俊氏の提唱する「協生農法」が気になる。無耕起、無施肥、無農薬の流れの一手法というだけではないようだ。国内外の実績もあるとのことだが、私の胸を突いたのは『人間がかかわることで、人間がいないよりも高い生物多様性を実現する』というヴィジョンである。できるだけ環境を壊さない、という消極的な環境活動とはベクトルの強さが違う。その圧倒的な突破力こそ、私が求めることのできる最強到達点ではないかと鼻息荒くなってしまう。もっと知りたい。
読了日:05月19日 著者:森田 真生
 塩の道 (講談社学術文庫)の感想
塩の道 (講談社学術文庫)の感想
宮本常一翁晩年の講演録「塩の道」「日本人と食べもの」「暮らしの形と美」。加速度的に転がる話に、ぽかんと口を開けてただ聴き入る。ほうほう。ああ、そういうことでしたか、そう考えたほうが自然ですね、なるほどなるほど。知らなかった事実を知るというだけではなくて、翁自身の脚で集められた情報量の凄みと、翁の中で見出された様々の事物が繋がる自在さがもはや小宇宙のようで心地よいのだ。人や獣に必須の塩について、塩を中心に見た歴史がこんなに奥深いとは思わなんだ。塩と醤油、味噌には、ぜひとも産地・製法にこだわって比べてみたい。
日本人には山間地や平地、海べりなど各地でそれぞれ為すべき生業があって、そのためには住まい作業するその土地に合わせた作物を見つけ、つくり、食べる必要があった。そのうちによりつくりやすい作物が流入し、また改良し、食が豊かになったぶん、また人が増え、産業が盛んになる、その繰り返しだった。日本では戦に加わる人と、作物をつくる人が別だったから、中国のようには人口変動の振れ幅が大きくなかったのだという指摘が興味深かった。
読了日:05月19日 著者:宮本 常一
 ヒトの壁 (新潮新書)の感想
ヒトの壁 (新潮新書)の感想
読み進まなかったのはお風呂で読んでいたせいか、養老先生の言うように日常と同時進行で書かれたからか、病や別離のゆえに難しいご気分であったせいか。気の赴くままにこぼれるぼやきに近いのかもしれない。心に留めておきたいのは昭和天皇の開戦の詔勅『まことに已むを得ざるものあり、あに朕が志ならんや』。陛下の真情がどのようにあったかは別にして、当時の為政者や軍属の人々にも受け入れられるメンタリティーであったのだなあ。「なるべくしてなる」という日本人の感覚は、外国から見たら無責任に取られたりもするのだろうか。
読了日:05月18日 著者:養老 孟司
 兄の終いの感想
兄の終いの感想
いうなれば「毒兄」。よく聞くお名前なので、恥ずかしながらてっきり小説だと思って読み始め、同じ苗字の主人公に、どうやらノンフィクションらしいと気づいて動揺した。なんとトーマス・トウェイツ本の翻訳者さんでした。さて、生前いくら怒りを覚え、拒絶し倒すしか処しようのなかった相手でも、死後もずっと憎み続けることは、人にはできないのだろう。相手の精神の消滅と同時に、脅威は消え、自らの中で何かが変わり始める。こちらに真実に向き合おうなんて気持ちが欠片でも浮かぶ場合は特に。悔いも生まれる。きっとそれが「弔う」ことなのだ。
読了日:05月17日 著者:村井 理子
 佐藤優の裏読み! 国際関係論の感想
佐藤優の裏読み! 国際関係論の感想
約1年前の著作であり、残念ながらウクライナには触れていないが、ロシアの北方領土交渉や地球温暖化についての見解は興味深い。読みどころは、氏の珍しく感情の混じる文章である。沖縄人としての強い思いと元外交官としての判断が相克している。本土人として胸に手を当てずにいられない。また、どうやら私たちは新型コロナやらウクライナ動乱やらを機にますます危うい情勢に巻き込まれつつある。自発性を重んじる"翼賛"の思想が同調圧力という強制に転じるのは、日本の政治文化であるという。恐怖政治の気配といい、どちらを向いても恐ろしい。
氏は、当時の菅政権の外交が満点に近いと評価する。外務省のトップが優秀である点と、政権が任せた点が良かったとのことだ。つまり、政権が無能のポンコツでも、外務省の要がしっかりしていればきちんと折り合いをつける外交ができるということだと理解した。極右政治家がわあわあ騒いでも、脊髄反射的に罵ったりせず、じっと見定める姿勢が大事である。戦闘能力や憲法を云々する前に、非常事態を回避する外交が必要。
読了日:05月16日 著者:佐藤 優
 限りなく完璧に近い人々 なぜ北欧の暮らしは世界一幸せなのか?の感想
限りなく完璧に近い人々 なぜ北欧の暮らしは世界一幸せなのか?の感想
フィンランドの章。ソ連との浅からぬ因縁が書かれていたと記憶していたので再読。西欧と東欧のはざまに位置するのはウクライナと同じである。ロシア帝国からの独立後、1939-40年のソ連との冬戦争により賠償金と領土を失い、第二次世界大戦で敵(ソ連)の敵=ドイツに与したことで敗戦、再びソ連に領土のうち豊かな農地や発電所、港を割譲させられている。しかしアメリカやNATOには頼らず基地もつくらせない方針で、ソ連との折り合いをつけてきた国だ。それがその方針を転換しようとしているのは、歴史的な事件なのだと、改めて確認した。
読了日:05月15日 著者:マイケル・ブース
 「十五少年漂流記」への旅 ―幻の島を探して (新潮文庫)の感想
「十五少年漂流記」への旅 ―幻の島を探して (新潮文庫)の感想
「十五少年漂流記」は少年シーナマコトの冒険心の芽を育んだ。そのモデルとなった無人島へ上陸する企画。とはいえ、現地の描写は数ページである。脱線のように過去の旅での体験や知識が披瀝されるので、意図を計りかねて置き去りにされそうになる。もちろん適当な紙面埋めなどではなく、言わんとすることがあるのだ。椎名家の書棚にはフィクション・ノンフィクションを問わず、冒険記や漂流記が膨大に並んでいると推察される。経験と知識が合わさって初めて立つ仮説、実感があるのだなあ。シーナ級でないとできない偉業である。珍しくちょい辛口。
読了日:05月14日 著者:椎名 誠
 言壺 (ハヤカワ文庫JA)の感想
言壺 (ハヤカワ文庫JA)の感想
面白い面白い。言葉にまつわるSF短編集。言葉そのものの在りかたが変化してしまった世界は、スイッチ一つで小説が目の前から消え去ってしまう電子書籍や、スマホの予測機能で出る単語をつないで他者とやり取りするスマホネイティブの、延長線上にあるかもしれない世界だ。文字ができ、印刷技術が発達し、手書きしなくなり、そのたび言葉の機能も変わってきたはずで、さらに身体性が弱り、言葉にどっぷり浸かっていると、どちらがどちらを支配しているのかわからない感じとか、言葉の破壊が社会や人間をも破壊してしまう想像とか、脳内に遊ばせる。
「栽培文」が幻想的で好い。映像化できそう。『その言葉を枯葉の状態からよみがえらせるには、それを生んだときの気分が必要らしい。その言葉を読むと、その気持ちがよみがえるのか、その気持ちを忘れないでいるから、その枯葉がよみがえるのか、どちらなのか、と娘は考えた。言葉が先か、気持ちが先か、どちらなのだろう。』彼女の素朴な疑問は、実は深い意味を湛えてこちらの気持ちをゆらゆら揺らす。
1994年の刊行と聞いて腰を抜かしそうになる。1994年と言えばWindowsは95以前で、電子書籍もスマホもありゃしない。オフコンからワーカムを発想する凄さたるや。…しかし、ワーカムを今のWindows11よりもすごげな、VRみたいなガジェットに想像したのは、著者ではなく私の脳みそなのである。言葉。その威力をまざまざと感じる。
読了日:05月12日 著者:神林長平
 日本でわたしも考えた:インド人ジャーナリストが体感した禅とトイレと温泉との感想
日本でわたしも考えた:インド人ジャーナリストが体感した禅とトイレと温泉との感想
インド人というより、インド生まれの国際人であるジャーナリストの日本滞在記として、インドで刊行された書籍の翻訳本。著者は日本を気に入っているが、日本礼賛本ではなく、社会や政治の在り様への辛辣な指摘も多い。これが何度も来日してくれる人々の本音だろう。切り口が面白い。子供が独りで通学するのは、コミュニティへの信頼が生きている証と洞察する。自分で掃除するのは自ら清潔にするための手段であって、罰でも人の尊厳を損なうものでない。私たちには当たり前のことが外国ではそうではないと気づく瞬間は、やはり醍醐味である。
読了日:05月10日 著者:パーラヴィ・アイヤール
 特殊清掃 (ディスカヴァー携書)の感想
特殊清掃 (ディスカヴァー携書)の感想
一人身の人間が増えれば孤独死も増える。孤独死に心理的拒否感は無いけれど、まあ、その後は問題よね。死は現代社会では表向き異質なものだ。存命中の姿を知らず、三人称の死と割り切れれば、モノの始末と処理をこなすことはできるのではと想像していたが、人体が腐乱し融解する過程は、プロでも抑えきれない拒否感を生じさせるようだ。この本能レベルの反応は、同様に死体を扱う例えば納棺師のような職業では聞かない。自然に還ることもできない人体を汚物として扱うしかない点が、人間の脳が持つバグを突く。ここがこの職業の特殊さかと想像した。
読了日:05月08日 著者:特掃隊長
 最後の講義 完全版 上野千鶴子 これからの時代を生きるあなたへ安心して弱者になれる社会をつくりたいの感想
最後の講義 完全版 上野千鶴子 これからの時代を生きるあなたへ安心して弱者になれる社会をつくりたいの感想
NHKの番組はつまみぐいだったようだ。記憶より分量がある。講義は無論、対話も各々がどういう生き方を選んで、課題を抱え、どのような社会システムを望んでいるか知れて良い。日本は子育ても介護も家事も、公助/共助とも絶対的に足りない。今まで女がタダでやってきたから、そんなことにおカネを払う理由がないと誰かが考えている。私の夫はリベラルな方だが、それらにさほどの対価は払えないなどと考えるようになったとしたら、それは私のせいだなと自戒。『こんな世の中にしてごめんなさいと言わなくてすむ社会を手渡したい』の言葉が温かい。
観て好きだった講義。女が親になったら、子供に対して人生最大の権力者になる、という発言を鮮烈に記憶している。自らの体感は確実に人の人生の軌道を左右する。上野さんの切れの良い話しかたが好きだ。全てを抱え込んで途方に暮れている受講者には優しく助言する。一方、無神経に懐古的な発言をする受講者には間髪入れずぴしゃりと批判する。『年を取るっていうのは、現実の多様性にぶつかって、脱洗脳、つまり洗脳が解けていく過程なので、わたしは年を取ったほうがはるかに柔軟になって、寛容になりました』。まさに。
読了日:05月07日 著者:上野 千鶴子,NHKグローバルメディアサービス,テレビマンユニオン
 宮辻薬東宮 (講談社文庫)の感想
宮辻薬東宮 (講談社文庫)の感想
妹本。そうそうたる面々の短編リレー。最初に宮部さんがちょいホラーで縛ってしまった流れなのだろうか。それぞれの作家のカラーが出ておもしろかった。タイトルも意味深なニュアンスが中黒で表されていて、読後になるほどなあ、と作家の創意に唸ったものだが、うしろ2編はよくわからなかった。なにかダブルミーニングのようなひねりはあったのだろうか。そこも解説が欲しかった。記念撮影はどないことなったんかな。
読了日:05月02日 著者:宮部 みゆき,辻村 深月,薬丸 岳,東山 彰良,宮内 悠介
注: は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。
感想も1700冊以上書いているそうだから、1冊255字とはいえなかなかの量になった。
自分の書いた感想に感じ入ることも少なくない。
さらに以前の、幼少の頃に読んだ本たちや何度も読み返した本たちに思いを馳せる。
もう思い出せなかったりするそれらすべてを糧にして今の私がある。
<今月のデータ>
購入28冊、購入費用23,490円。
読了16冊。
積読本321冊(うちKindle本154冊、Honto本11冊)。

5月の読書メーター
読んだ本の数:16
 桃 もうひとつのツ、イ、ラ、ク (角川文庫)の感想
桃 もうひとつのツ、イ、ラ、ク (角川文庫)の感想「ツ、イ、ラ、ク」から間を置かずに読めばもっとヒリヒリできたかもしれない。彼女の周りにいた「普通の」生徒たち。彼/彼女らに対して私の感じていた嫌らしさは、本人が意識的に選択して行動した/行動しなかったからではなく、生物的スキルによって自動選択されたもの故であった。一方で彼/彼女らもまた熟し始めた個体としての衝動を隠し持っていたのであり、彼女のみを異質物のように浮かせた一方、彼女から少なからず影響を受けていた出来事がこれらの短編では明らかにされる、そのお互い知り得ない他者の内部の底知れなさがじわじわくる。
読了日:05月27日 著者:姫野 カオルコ
 現代華文推理系列 第一集の感想
現代華文推理系列 第一集の感想若手作家による華文ミステリ集。外国ミステリとはいえ、学校のようなクローズド設定で、論理を詰めて進める類の謎解きミステリは日本のそれと何も変わらないのでつまらない。面白いのは、社会性や叙情性を持ち込むのみならず、それらを巧く利用した作品だ。水天一色「おれみたいな奴が」では社会的底辺者の鬱屈やユーモアがプーアル茶のくだりに現れ、寵物先生「犯罪の赤い糸」には『神経がサトウキビぐらい図太くないと』や『節のほかから枝が生えないように』のような独特の言い回しが興を添える。先入観が無いから楽しめる。はまりそうな予感!
読了日:05月24日 著者:御手洗熊猫,水天一色,林斯諺,寵物先生

 くそつまらない未来を変えられるかもしれない投資の話 (シリーズ3/4)の感想
くそつまらない未来を変えられるかもしれない投資の話 (シリーズ3/4)の感想パンクな個人投資家によるお金の使いかた指南。金融リテラシーを得る入門書として楽しく読める。なんて言うと軽い啓発本みたいだけど、ちゃんとした知識に根差した哲学がある。今遊ぶことを諦めず、将来のことも捨てない生き方。あと、金融商品でも生活に必要な品物でも、応援したい、ずっと残ってほしい、社会の役に立つと思えるお店の商品を選んで買おうよという話。これはこれで、自分たちの行動次第で未来を自分好みに変えられると考え行動する意味においては未来を拓く動きであり、例えば渋沢健氏の投資哲学とは違った知性の表れだと思う。
読了日:05月21日 著者:ヤマザキOKコンピュータ

 カラスをだます (NHK出版新書 646)の感想
カラスをだます (NHK出版新書 646)の感想研究者からのベンチャー起業家、自称"カラス・ソリューショニスト"。カラスが好きで研究者になったわけでない人もいる。さて、カラスをだます。カラスを食べる。どちらも人間社会とカラスの摩擦を解消する試みだ。しかし視覚優位で記憶力にも優れるカラスを人間の意に沿わせるのは大変と知る。カラス剥製ロボットの首がもげたところは笑いすぎて涙が出た。カラスが人間の出すゴミを漁って、プラスチックを大量に食べてしまわないか心配だったが、カラスは消化できないものを体内に溜めず、ペリットと呼ばれる塊にして吐き出すと知って安心した。
読了日:05月20日 著者:塚原 直樹

 僕たちはどう生きるか 言葉と思考のエコロジカルな転回の感想
僕たちはどう生きるか 言葉と思考のエコロジカルな転回の感想日本の若き知性として注目される、森田真生氏のエッセイ。書店で手に取った瞬間、やられたと思った。なにかここにある、と予感した。『このままではいけない。いままでとは別の、生き方を探しなさい』。感染症による活動縮小を契機に、新しいセンサを働かせて取り組む活動のセンスが好い。通底するのは、人間が人間でないものたちと同じ地平に降り立とうとする意思だ。『人間はもっと humiliate されていい』と言う。これまでと同じようには生きていくことができなくなった世界では、思考より肌感覚に従う、柔軟な行動こそ生き抜く術。
舩橋真俊氏の提唱する「協生農法」が気になる。無耕起、無施肥、無農薬の流れの一手法というだけではないようだ。国内外の実績もあるとのことだが、私の胸を突いたのは『人間がかかわることで、人間がいないよりも高い生物多様性を実現する』というヴィジョンである。できるだけ環境を壊さない、という消極的な環境活動とはベクトルの強さが違う。その圧倒的な突破力こそ、私が求めることのできる最強到達点ではないかと鼻息荒くなってしまう。もっと知りたい。
読了日:05月19日 著者:森田 真生
 塩の道 (講談社学術文庫)の感想
塩の道 (講談社学術文庫)の感想宮本常一翁晩年の講演録「塩の道」「日本人と食べもの」「暮らしの形と美」。加速度的に転がる話に、ぽかんと口を開けてただ聴き入る。ほうほう。ああ、そういうことでしたか、そう考えたほうが自然ですね、なるほどなるほど。知らなかった事実を知るというだけではなくて、翁自身の脚で集められた情報量の凄みと、翁の中で見出された様々の事物が繋がる自在さがもはや小宇宙のようで心地よいのだ。人や獣に必須の塩について、塩を中心に見た歴史がこんなに奥深いとは思わなんだ。塩と醤油、味噌には、ぜひとも産地・製法にこだわって比べてみたい。
日本人には山間地や平地、海べりなど各地でそれぞれ為すべき生業があって、そのためには住まい作業するその土地に合わせた作物を見つけ、つくり、食べる必要があった。そのうちによりつくりやすい作物が流入し、また改良し、食が豊かになったぶん、また人が増え、産業が盛んになる、その繰り返しだった。日本では戦に加わる人と、作物をつくる人が別だったから、中国のようには人口変動の振れ幅が大きくなかったのだという指摘が興味深かった。
読了日:05月19日 著者:宮本 常一

 ヒトの壁 (新潮新書)の感想
ヒトの壁 (新潮新書)の感想読み進まなかったのはお風呂で読んでいたせいか、養老先生の言うように日常と同時進行で書かれたからか、病や別離のゆえに難しいご気分であったせいか。気の赴くままにこぼれるぼやきに近いのかもしれない。心に留めておきたいのは昭和天皇の開戦の詔勅『まことに已むを得ざるものあり、あに朕が志ならんや』。陛下の真情がどのようにあったかは別にして、当時の為政者や軍属の人々にも受け入れられるメンタリティーであったのだなあ。「なるべくしてなる」という日本人の感覚は、外国から見たら無責任に取られたりもするのだろうか。
読了日:05月18日 著者:養老 孟司
 兄の終いの感想
兄の終いの感想いうなれば「毒兄」。よく聞くお名前なので、恥ずかしながらてっきり小説だと思って読み始め、同じ苗字の主人公に、どうやらノンフィクションらしいと気づいて動揺した。なんとトーマス・トウェイツ本の翻訳者さんでした。さて、生前いくら怒りを覚え、拒絶し倒すしか処しようのなかった相手でも、死後もずっと憎み続けることは、人にはできないのだろう。相手の精神の消滅と同時に、脅威は消え、自らの中で何かが変わり始める。こちらに真実に向き合おうなんて気持ちが欠片でも浮かぶ場合は特に。悔いも生まれる。きっとそれが「弔う」ことなのだ。
読了日:05月17日 著者:村井 理子

 佐藤優の裏読み! 国際関係論の感想
佐藤優の裏読み! 国際関係論の感想約1年前の著作であり、残念ながらウクライナには触れていないが、ロシアの北方領土交渉や地球温暖化についての見解は興味深い。読みどころは、氏の珍しく感情の混じる文章である。沖縄人としての強い思いと元外交官としての判断が相克している。本土人として胸に手を当てずにいられない。また、どうやら私たちは新型コロナやらウクライナ動乱やらを機にますます危うい情勢に巻き込まれつつある。自発性を重んじる"翼賛"の思想が同調圧力という強制に転じるのは、日本の政治文化であるという。恐怖政治の気配といい、どちらを向いても恐ろしい。
氏は、当時の菅政権の外交が満点に近いと評価する。外務省のトップが優秀である点と、政権が任せた点が良かったとのことだ。つまり、政権が無能のポンコツでも、外務省の要がしっかりしていればきちんと折り合いをつける外交ができるということだと理解した。極右政治家がわあわあ騒いでも、脊髄反射的に罵ったりせず、じっと見定める姿勢が大事である。戦闘能力や憲法を云々する前に、非常事態を回避する外交が必要。
読了日:05月16日 著者:佐藤 優

 限りなく完璧に近い人々 なぜ北欧の暮らしは世界一幸せなのか?の感想
限りなく完璧に近い人々 なぜ北欧の暮らしは世界一幸せなのか?の感想フィンランドの章。ソ連との浅からぬ因縁が書かれていたと記憶していたので再読。西欧と東欧のはざまに位置するのはウクライナと同じである。ロシア帝国からの独立後、1939-40年のソ連との冬戦争により賠償金と領土を失い、第二次世界大戦で敵(ソ連)の敵=ドイツに与したことで敗戦、再びソ連に領土のうち豊かな農地や発電所、港を割譲させられている。しかしアメリカやNATOには頼らず基地もつくらせない方針で、ソ連との折り合いをつけてきた国だ。それがその方針を転換しようとしているのは、歴史的な事件なのだと、改めて確認した。
読了日:05月15日 著者:マイケル・ブース

 「十五少年漂流記」への旅 ―幻の島を探して (新潮文庫)の感想
「十五少年漂流記」への旅 ―幻の島を探して (新潮文庫)の感想「十五少年漂流記」は少年シーナマコトの冒険心の芽を育んだ。そのモデルとなった無人島へ上陸する企画。とはいえ、現地の描写は数ページである。脱線のように過去の旅での体験や知識が披瀝されるので、意図を計りかねて置き去りにされそうになる。もちろん適当な紙面埋めなどではなく、言わんとすることがあるのだ。椎名家の書棚にはフィクション・ノンフィクションを問わず、冒険記や漂流記が膨大に並んでいると推察される。経験と知識が合わさって初めて立つ仮説、実感があるのだなあ。シーナ級でないとできない偉業である。珍しくちょい辛口。
読了日:05月14日 著者:椎名 誠
 言壺 (ハヤカワ文庫JA)の感想
言壺 (ハヤカワ文庫JA)の感想面白い面白い。言葉にまつわるSF短編集。言葉そのものの在りかたが変化してしまった世界は、スイッチ一つで小説が目の前から消え去ってしまう電子書籍や、スマホの予測機能で出る単語をつないで他者とやり取りするスマホネイティブの、延長線上にあるかもしれない世界だ。文字ができ、印刷技術が発達し、手書きしなくなり、そのたび言葉の機能も変わってきたはずで、さらに身体性が弱り、言葉にどっぷり浸かっていると、どちらがどちらを支配しているのかわからない感じとか、言葉の破壊が社会や人間をも破壊してしまう想像とか、脳内に遊ばせる。
「栽培文」が幻想的で好い。映像化できそう。『その言葉を枯葉の状態からよみがえらせるには、それを生んだときの気分が必要らしい。その言葉を読むと、その気持ちがよみがえるのか、その気持ちを忘れないでいるから、その枯葉がよみがえるのか、どちらなのか、と娘は考えた。言葉が先か、気持ちが先か、どちらなのだろう。』彼女の素朴な疑問は、実は深い意味を湛えてこちらの気持ちをゆらゆら揺らす。
1994年の刊行と聞いて腰を抜かしそうになる。1994年と言えばWindowsは95以前で、電子書籍もスマホもありゃしない。オフコンからワーカムを発想する凄さたるや。…しかし、ワーカムを今のWindows11よりもすごげな、VRみたいなガジェットに想像したのは、著者ではなく私の脳みそなのである。言葉。その威力をまざまざと感じる。
読了日:05月12日 著者:神林長平

 日本でわたしも考えた:インド人ジャーナリストが体感した禅とトイレと温泉との感想
日本でわたしも考えた:インド人ジャーナリストが体感した禅とトイレと温泉との感想インド人というより、インド生まれの国際人であるジャーナリストの日本滞在記として、インドで刊行された書籍の翻訳本。著者は日本を気に入っているが、日本礼賛本ではなく、社会や政治の在り様への辛辣な指摘も多い。これが何度も来日してくれる人々の本音だろう。切り口が面白い。子供が独りで通学するのは、コミュニティへの信頼が生きている証と洞察する。自分で掃除するのは自ら清潔にするための手段であって、罰でも人の尊厳を損なうものでない。私たちには当たり前のことが外国ではそうではないと気づく瞬間は、やはり醍醐味である。
読了日:05月10日 著者:パーラヴィ・アイヤール
 特殊清掃 (ディスカヴァー携書)の感想
特殊清掃 (ディスカヴァー携書)の感想一人身の人間が増えれば孤独死も増える。孤独死に心理的拒否感は無いけれど、まあ、その後は問題よね。死は現代社会では表向き異質なものだ。存命中の姿を知らず、三人称の死と割り切れれば、モノの始末と処理をこなすことはできるのではと想像していたが、人体が腐乱し融解する過程は、プロでも抑えきれない拒否感を生じさせるようだ。この本能レベルの反応は、同様に死体を扱う例えば納棺師のような職業では聞かない。自然に還ることもできない人体を汚物として扱うしかない点が、人間の脳が持つバグを突く。ここがこの職業の特殊さかと想像した。
読了日:05月08日 著者:特掃隊長

 最後の講義 完全版 上野千鶴子 これからの時代を生きるあなたへ安心して弱者になれる社会をつくりたいの感想
最後の講義 完全版 上野千鶴子 これからの時代を生きるあなたへ安心して弱者になれる社会をつくりたいの感想NHKの番組はつまみぐいだったようだ。記憶より分量がある。講義は無論、対話も各々がどういう生き方を選んで、課題を抱え、どのような社会システムを望んでいるか知れて良い。日本は子育ても介護も家事も、公助/共助とも絶対的に足りない。今まで女がタダでやってきたから、そんなことにおカネを払う理由がないと誰かが考えている。私の夫はリベラルな方だが、それらにさほどの対価は払えないなどと考えるようになったとしたら、それは私のせいだなと自戒。『こんな世の中にしてごめんなさいと言わなくてすむ社会を手渡したい』の言葉が温かい。
観て好きだった講義。女が親になったら、子供に対して人生最大の権力者になる、という発言を鮮烈に記憶している。自らの体感は確実に人の人生の軌道を左右する。上野さんの切れの良い話しかたが好きだ。全てを抱え込んで途方に暮れている受講者には優しく助言する。一方、無神経に懐古的な発言をする受講者には間髪入れずぴしゃりと批判する。『年を取るっていうのは、現実の多様性にぶつかって、脱洗脳、つまり洗脳が解けていく過程なので、わたしは年を取ったほうがはるかに柔軟になって、寛容になりました』。まさに。
読了日:05月07日 著者:上野 千鶴子,NHKグローバルメディアサービス,テレビマンユニオン

 宮辻薬東宮 (講談社文庫)の感想
宮辻薬東宮 (講談社文庫)の感想妹本。そうそうたる面々の短編リレー。最初に宮部さんがちょいホラーで縛ってしまった流れなのだろうか。それぞれの作家のカラーが出ておもしろかった。タイトルも意味深なニュアンスが中黒で表されていて、読後になるほどなあ、と作家の創意に唸ったものだが、うしろ2編はよくわからなかった。なにかダブルミーニングのようなひねりはあったのだろうか。そこも解説が欲しかった。記念撮影はどないことなったんかな。
読了日:05月02日 著者:宮部 みゆき,辻村 深月,薬丸 岳,東山 彰良,宮内 悠介
注:
 は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。 2022年05月02日
2022年4月の記録
なんだかKindle本ばっかり読んでいるなあ。
積読本棚がぱつぱつだなあ。
思い返してみると、猫の「撫でて撫でて」要求が激しいので、
片手で撫でながらのもう片手で読めるKindleでしか読めないのでした。
<今月のデータ>
購入17冊、購入費用10,962円。
読了18冊。
積読本311冊(うちKindle本139冊、Honto本13冊)。

4月の読書メーター
読んだ本の数:11
 魔女の1ダース―正義と常識に冷や水を浴びせる13章 (新潮文庫)の感想
魔女の1ダース―正義と常識に冷や水を浴びせる13章 (新潮文庫)の感想
今のウクライナを見たら米原万里はなんと言うだろう。人脈の広い著者ならでは、ワールドワイドなエッセイ集。そしてユダヤ、東西冷戦、ユーゴと絶えぬ紛争に繰り返し言及する。『本来身近な者を遠のかせ、可変的な物を固定的なものと捉えていくフィクションによる観念操作、それも国家的規模の観念操作の恐ろしさ』は進行形で実感するところであるし、また日本の過度な欧米偏重、「先進国」らの歴史的傲慢、彼らが異文化やその歴史的背景に想像力を欠如している前提のうえで、時間軸、空間軸とも広い視野で捉え、自ら考えることが必要と受け止めた。
読了日:04月30日 著者:米原 万里
 Humankind 希望の歴史 下 人類が善き未来をつくるための18章の感想
Humankind 希望の歴史 下 人類が善き未来をつくるための18章の感想
なにが希望かと吐き捨てたい時勢だが、だからこそ多くの人に読んでほしい。特に行政に携わる人。制度設計に必要なのは民への猜疑心や水も漏らさぬ管理体制ではないとよく解る。人間はおおむね他者に友好的で、善なる素質を持った生き物だ。集団で協力し合い物事をより良くすることもできる。しかし、今多発する海外の紛争や、国内のきな臭い動きをも説明できたとは思えない。罪なき人々を苦しませるのは『悪を駆り立てる少数の』政治家、司令官、主戦論者の煽動や洗脳だとして、また皆して被害者面でPTSDに苦しむ歴史を繰り返すしかないのか。
「共感は良いことではない」の言葉に考え込む。共感は、特定の人々に同調し集中する行為だ。それは裏返せば、それ以外の人に対しては理解しようとする努力が疎かになり、排他的になり、敵とみなす原動力にもなると著者は言う。それこそが人間の残虐性の源、戦争の要因と著者は考える。いわゆるウチとソトと表現する日本の概念と被る。入管でウィシュマさんにした仕打ちや、ウクライナ人に肩入れするあまりロシア人を一概に拒む風潮、いつまでも続くアジア人へのヘイト、新型コロナで他県人の流入を疎む気持ちだって安易な共感の裏返しと言えよう。
間違いなく希望は必要だ。著者は利他、コモンズ、信頼型の企業経営など、いま流行りの思想にも言及する。これらは「人間は本質的に悪」とするホッブスの考え方や、それを裏付けてきた心理学/社会学の実験捏造によって育まれた社会思想への反動なのだろうか。それともただの流行で、10年後にはまた別の思想が生まれて人口に膾炙するのだろうか。あるいは人類は本当により良くなれるのだろうか。私個人、他者にもっと優しくなれそうな気がする。しかし「ファクトフルネス」の指摘する数字の改善を知ってなお、やはり人類に楽観的にはなれないのだ。
読了日:04月27日 著者:ルトガー・ブレグマン
 ミシマ社の雑誌 ちゃぶ台 「移住×仕事」号の感想
ミシマ社の雑誌 ちゃぶ台 「移住×仕事」号の感想
記念すべき第1号。無頓着に脱力しているようでてんこ盛りな目次が楽しい。「移住×仕事」についてもさながら、今の時勢だから響くこともたくさんある。内田先生の「農作物は商品ではない」話。藤原さんの戦争と飢餓と農業の話。日本農業新聞を読んでいると、農政は農作物輸出、農地集約化、第6次産業振興と、いかに稼ぐかばかりに目を血走らせているけれど、異状めいてくると農業と資本主義のかみ合わない歪さが露呈してくる。日本人は皆でちょっと困って、軌道修正すればいいのだ。"小さな単位での食料自給率"を上げることならできそうやん。
読了日:04月25日 著者:ミシマ社 編
 〈屍人荘の殺人〉エピソード0 明智恭介 最初でも最後でもない事件 屍人荘の殺人シリーズの感想
〈屍人荘の殺人〉エピソード0 明智恭介 最初でも最後でもない事件 屍人荘の殺人シリーズの感想
在りし日の明智さんの日常。彼は葉村という良い相棒を得て、生き生きと大学構内外を駆け回っていたのだ。彼が楽しそうであるほど、全体にかかったフィルターが青みを増して感じられる。昨日もそうだったし、明日もそうであろう平和な日々、屍人荘へ着くまでは。返すがえすも、惜しい気持ちが湧き起こる。エピソード0ってこういうものなんでしょうね。ホームズの復活を願う読者の声がよほど多かったとみた。
読了日:04月24日 著者:今村 昌弘
 感じるオープンダイアローグ (講談社現代新書)の感想
感じるオープンダイアローグ (講談社現代新書)の感想
人生には対話が必要。当たり前だが、それができずに人は生きづらさを抱え込んでしまう。フィンランドのケロプダス病院で始まったオープンダイアローグという手法。対話だけで困難や誤解を解消することを目指す。著者はその手法を学びたいと思い、トレーニングの過程で自らの分厚い鎧を脱ぐ経験をする。考えてみれば、人の心を救う道に進んだ人は、ほかならぬ自身が苦しかった過去があるのだ。そして心に分厚い鎧をまとい、自分を他人に見せることができないのは私も同じ。苦しくなったときに頼れる療法の場として、こういうのが身近にあってほしい。
読了日:04月22日 著者:森川 すいめい
 地球の未来のため僕が決断したことの感想
地球の未来のため僕が決断したことの感想
ゲイツは今の世界で、諸分野トップクラスの知性にアクセスできる存在だ。その彼が結論したのなら、それは世界で最も優等生な結論だろう。しかし聞けば聞くほど私には無理ゲーとしか感じられない。なぜなら脱炭素のためだけでも2050年には今の3倍の電気が必要になる見通しなのだ。そして高度かつ複雑な技術革新には、より大きなエネルギーと資源が必要になる。鉄も銅もアルミもレアメタルも。気候変動に対処したいのなら、新たに木を植えるのではなく、『すでにある木をいまのようにたくさん切るのをやめ』なければならない。諸事において。
今や世界中の企業がこぞって目指す炭素低減の目算値は、果たして正しいのだろうか。消費資源を増やす方向へばかり進んでいることに、私は疑問が拭えない。確かにゲイツは財団を興し、長年世界の貧困問題を解決するための技術支援や投資をしてきたから、技術革新の大切さ、政府や国際機構の役割、うまい交渉方法などよく理解している。施策が状態を改善してきたのも確かだ。インセンティヴの使いかたに学ぶものも多い。しかし、どこか技術革新への過信、驕りがあるような気がして、人間世界の破滅へギアを上げる行為のような気がして仕方ないのだ。
読了日:04月21日 著者:ビル・ゲイツ,Bill Gates
 神も仏もありませぬ (ちくま文庫)の感想
神も仏もありませぬ (ちくま文庫)の感想
洋子さんのエッセイを読むと、しばらくは心の声がでかくなる。開けっぴろげで格好悪いことも堂々と言ってしまう洋子さんを、好いなとどこかで思って真似るのだろう。浅間の見える北軽井沢で、自然や農作物に恵まれて、近所の人とゆるくつながりながら暮らしている様子。羨ましい。洋子さんは若い頃からたくさん猫を飼ってきたのに、60歳過ぎても飼い猫が死ぬことに動揺し、生き物の宿命である死をそのまま受け入れる、"小さな獣の偉大さ"に感動する。ということは、人間は死に対して覚悟もできず達観もできないのだ。きっと、私もこの先ずっと。
読了日:04月20日 著者:佐野 洋子
 猫に教わるの感想
猫に教わるの感想
表題に"猫"とあってつい手に取ったけれど、なにげない日々のいつものエッセイよね。とぼんやり読んでいると、新型コロナワクチン接種担当に名乗り出たとか山行の文章を書くのをやめたとかの近況に交じって、力強い文章に目が留まる。『未来は明日ですら完璧に隠されていると了解し、夢など抱かず、とりあえずいまを生きる』。若い頃とは見えない何かが変わってしまったと感じる。私自身の身辺の変化や戦争や社会の迷走、つまり近未来の不透明さに私は消耗している。"いま"に立ち返ろう。やはり南木さんの文章は私に無くてはならないと思い直す。
読了日:04月17日 著者:南木 佳士
 ウンコはどこから来て、どこへ行くのか ――人糞地理学ことはじめ (ちくま新書)の感想
ウンコはどこから来て、どこへ行くのか ――人糞地理学ことはじめ (ちくま新書)の感想
気になっていた本。ヨーロッパで人々が家の窓から糞尿を投げ捨てていた頃から、日本人は高値で取引して田畑の肥料にしていた。それをいつ何故やめてしまったか。転機は下肥利用を駆逐すべき習俗と断じたGHQと米軍による指導だった。その後都市化が進み、つまり土から離れて消費するだけの人口が増加するにつれて精神面でも構造面でも不可逆的変化が進み、糞尿は臭くて汚くて忌まわしいものになった。そしてバクテリアを使った下水道処理でできる乾燥汚泥を堆肥にしないのはなぜか。今の人間は土に還元できないほど汚染されている、と言うのだが。
化学合成添加物まみれになっているのは残飯も同じだし、どうせ化学合成添加物まみれにして食べるのだから、少々の汚染はもはや仕方ないのではないだろうか。マイクロプラスチックだって、既に人体内組織に入り込んでいるというし。つまり、化学合成添加物を含んでいるから糞尿からできる堆肥は田畑で使えないという言い分が、やりたくない理由にしか聞こえなくなってきた。
読了日:04月13日 著者:湯澤 規子
 戦争は女の顔をしていないの感想
戦争は女の顔をしていないの感想
戦場に出た女性たちの、たくさんの声。ひとりひとりの、胸に涙を湛えながら集められたであろう小さな声が、怒涛となってこちらを打ちのめす。千人いれば、千の戦争と千の真実がある。今ウクライナについて語る著者の背後には深い悲しみが満ちて見える。頭から離れないのは、砲弾を運ぶ車両を運転していた女性の話。ドイツ兵の死体の上を通過するとき、頭蓋骨の砕ける音が嬉しかったと。憎しみは人の中にもともとあるのではない。生まれるのだ。今このときも、人々の中に育ちつつある憎しみが恐ろしい。他方、憎み抜けないことは救い。人間らしさだ。
『戦闘は夜中に終わりました。朝になって雪が降りました。亡くなった人たちの身体が雪に覆われました……その多くが手を上にあげていました……空の方に……。』読んでいるものと同じ行為が再現されているかのような映像が絶えず目前に流れ、辛い。だんだん、私がこの本を読んでいるから、同じことがウクライナに起きてしまうかのような倒錯が起きる。過去のエピソードも現実の報道も、当人には永遠に続くかのように感じるだろう深い慟哭がまとわりついている。
読了日:04月12日 著者:スヴェトラーナ アレクシエーヴィチ
 ルポ新大久保 移民最前線都市を歩くの感想
ルポ新大久保 移民最前線都市を歩くの感想
移民として日本に住み着く人たちは、日本は決してオープンな社会ではないのに、なぜ選んでくれるのかとずっと思っていた。その理由は、稼ぐためだったり、日本の学歴が本国の就職に有利だからだったりするが、以前から言われる治安の良さだけではなく、今や韓国やオーストラリアより"割安だから"という選択に愕然とする。日本は「近くて安い国」になったのだ。まあ、それでもいい。彼らに優しい国であってほしい。多文化共生の基盤が整いつつある新大久保は今や先進地域。その発散するエネルギーを浴びに行ってみたくなるようなルポだった。
読了日:04月11日 著者:室橋 裕和
注: は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。
積読本棚がぱつぱつだなあ。
思い返してみると、猫の「撫でて撫でて」要求が激しいので、
片手で撫でながらのもう片手で読めるKindleでしか読めないのでした。
<今月のデータ>
購入17冊、購入費用10,962円。
読了18冊。
積読本311冊(うちKindle本139冊、Honto本13冊)。

4月の読書メーター
読んだ本の数:11
 魔女の1ダース―正義と常識に冷や水を浴びせる13章 (新潮文庫)の感想
魔女の1ダース―正義と常識に冷や水を浴びせる13章 (新潮文庫)の感想今のウクライナを見たら米原万里はなんと言うだろう。人脈の広い著者ならでは、ワールドワイドなエッセイ集。そしてユダヤ、東西冷戦、ユーゴと絶えぬ紛争に繰り返し言及する。『本来身近な者を遠のかせ、可変的な物を固定的なものと捉えていくフィクションによる観念操作、それも国家的規模の観念操作の恐ろしさ』は進行形で実感するところであるし、また日本の過度な欧米偏重、「先進国」らの歴史的傲慢、彼らが異文化やその歴史的背景に想像力を欠如している前提のうえで、時間軸、空間軸とも広い視野で捉え、自ら考えることが必要と受け止めた。
読了日:04月30日 著者:米原 万里

 Humankind 希望の歴史 下 人類が善き未来をつくるための18章の感想
Humankind 希望の歴史 下 人類が善き未来をつくるための18章の感想なにが希望かと吐き捨てたい時勢だが、だからこそ多くの人に読んでほしい。特に行政に携わる人。制度設計に必要なのは民への猜疑心や水も漏らさぬ管理体制ではないとよく解る。人間はおおむね他者に友好的で、善なる素質を持った生き物だ。集団で協力し合い物事をより良くすることもできる。しかし、今多発する海外の紛争や、国内のきな臭い動きをも説明できたとは思えない。罪なき人々を苦しませるのは『悪を駆り立てる少数の』政治家、司令官、主戦論者の煽動や洗脳だとして、また皆して被害者面でPTSDに苦しむ歴史を繰り返すしかないのか。
「共感は良いことではない」の言葉に考え込む。共感は、特定の人々に同調し集中する行為だ。それは裏返せば、それ以外の人に対しては理解しようとする努力が疎かになり、排他的になり、敵とみなす原動力にもなると著者は言う。それこそが人間の残虐性の源、戦争の要因と著者は考える。いわゆるウチとソトと表現する日本の概念と被る。入管でウィシュマさんにした仕打ちや、ウクライナ人に肩入れするあまりロシア人を一概に拒む風潮、いつまでも続くアジア人へのヘイト、新型コロナで他県人の流入を疎む気持ちだって安易な共感の裏返しと言えよう。
間違いなく希望は必要だ。著者は利他、コモンズ、信頼型の企業経営など、いま流行りの思想にも言及する。これらは「人間は本質的に悪」とするホッブスの考え方や、それを裏付けてきた心理学/社会学の実験捏造によって育まれた社会思想への反動なのだろうか。それともただの流行で、10年後にはまた別の思想が生まれて人口に膾炙するのだろうか。あるいは人類は本当により良くなれるのだろうか。私個人、他者にもっと優しくなれそうな気がする。しかし「ファクトフルネス」の指摘する数字の改善を知ってなお、やはり人類に楽観的にはなれないのだ。
読了日:04月27日 著者:ルトガー・ブレグマン

 ミシマ社の雑誌 ちゃぶ台 「移住×仕事」号の感想
ミシマ社の雑誌 ちゃぶ台 「移住×仕事」号の感想記念すべき第1号。無頓着に脱力しているようでてんこ盛りな目次が楽しい。「移住×仕事」についてもさながら、今の時勢だから響くこともたくさんある。内田先生の「農作物は商品ではない」話。藤原さんの戦争と飢餓と農業の話。日本農業新聞を読んでいると、農政は農作物輸出、農地集約化、第6次産業振興と、いかに稼ぐかばかりに目を血走らせているけれど、異状めいてくると農業と資本主義のかみ合わない歪さが露呈してくる。日本人は皆でちょっと困って、軌道修正すればいいのだ。"小さな単位での食料自給率"を上げることならできそうやん。
読了日:04月25日 著者:ミシマ社 編
 〈屍人荘の殺人〉エピソード0 明智恭介 最初でも最後でもない事件 屍人荘の殺人シリーズの感想
〈屍人荘の殺人〉エピソード0 明智恭介 最初でも最後でもない事件 屍人荘の殺人シリーズの感想在りし日の明智さんの日常。彼は葉村という良い相棒を得て、生き生きと大学構内外を駆け回っていたのだ。彼が楽しそうであるほど、全体にかかったフィルターが青みを増して感じられる。昨日もそうだったし、明日もそうであろう平和な日々、屍人荘へ着くまでは。返すがえすも、惜しい気持ちが湧き起こる。エピソード0ってこういうものなんでしょうね。ホームズの復活を願う読者の声がよほど多かったとみた。
読了日:04月24日 著者:今村 昌弘

 感じるオープンダイアローグ (講談社現代新書)の感想
感じるオープンダイアローグ (講談社現代新書)の感想人生には対話が必要。当たり前だが、それができずに人は生きづらさを抱え込んでしまう。フィンランドのケロプダス病院で始まったオープンダイアローグという手法。対話だけで困難や誤解を解消することを目指す。著者はその手法を学びたいと思い、トレーニングの過程で自らの分厚い鎧を脱ぐ経験をする。考えてみれば、人の心を救う道に進んだ人は、ほかならぬ自身が苦しかった過去があるのだ。そして心に分厚い鎧をまとい、自分を他人に見せることができないのは私も同じ。苦しくなったときに頼れる療法の場として、こういうのが身近にあってほしい。
読了日:04月22日 著者:森川 すいめい

 地球の未来のため僕が決断したことの感想
地球の未来のため僕が決断したことの感想ゲイツは今の世界で、諸分野トップクラスの知性にアクセスできる存在だ。その彼が結論したのなら、それは世界で最も優等生な結論だろう。しかし聞けば聞くほど私には無理ゲーとしか感じられない。なぜなら脱炭素のためだけでも2050年には今の3倍の電気が必要になる見通しなのだ。そして高度かつ複雑な技術革新には、より大きなエネルギーと資源が必要になる。鉄も銅もアルミもレアメタルも。気候変動に対処したいのなら、新たに木を植えるのではなく、『すでにある木をいまのようにたくさん切るのをやめ』なければならない。諸事において。
今や世界中の企業がこぞって目指す炭素低減の目算値は、果たして正しいのだろうか。消費資源を増やす方向へばかり進んでいることに、私は疑問が拭えない。確かにゲイツは財団を興し、長年世界の貧困問題を解決するための技術支援や投資をしてきたから、技術革新の大切さ、政府や国際機構の役割、うまい交渉方法などよく理解している。施策が状態を改善してきたのも確かだ。インセンティヴの使いかたに学ぶものも多い。しかし、どこか技術革新への過信、驕りがあるような気がして、人間世界の破滅へギアを上げる行為のような気がして仕方ないのだ。
読了日:04月21日 著者:ビル・ゲイツ,Bill Gates

 神も仏もありませぬ (ちくま文庫)の感想
神も仏もありませぬ (ちくま文庫)の感想洋子さんのエッセイを読むと、しばらくは心の声がでかくなる。開けっぴろげで格好悪いことも堂々と言ってしまう洋子さんを、好いなとどこかで思って真似るのだろう。浅間の見える北軽井沢で、自然や農作物に恵まれて、近所の人とゆるくつながりながら暮らしている様子。羨ましい。洋子さんは若い頃からたくさん猫を飼ってきたのに、60歳過ぎても飼い猫が死ぬことに動揺し、生き物の宿命である死をそのまま受け入れる、"小さな獣の偉大さ"に感動する。ということは、人間は死に対して覚悟もできず達観もできないのだ。きっと、私もこの先ずっと。
読了日:04月20日 著者:佐野 洋子
 猫に教わるの感想
猫に教わるの感想表題に"猫"とあってつい手に取ったけれど、なにげない日々のいつものエッセイよね。とぼんやり読んでいると、新型コロナワクチン接種担当に名乗り出たとか山行の文章を書くのをやめたとかの近況に交じって、力強い文章に目が留まる。『未来は明日ですら完璧に隠されていると了解し、夢など抱かず、とりあえずいまを生きる』。若い頃とは見えない何かが変わってしまったと感じる。私自身の身辺の変化や戦争や社会の迷走、つまり近未来の不透明さに私は消耗している。"いま"に立ち返ろう。やはり南木さんの文章は私に無くてはならないと思い直す。
読了日:04月17日 著者:南木 佳士
 ウンコはどこから来て、どこへ行くのか ――人糞地理学ことはじめ (ちくま新書)の感想
ウンコはどこから来て、どこへ行くのか ――人糞地理学ことはじめ (ちくま新書)の感想気になっていた本。ヨーロッパで人々が家の窓から糞尿を投げ捨てていた頃から、日本人は高値で取引して田畑の肥料にしていた。それをいつ何故やめてしまったか。転機は下肥利用を駆逐すべき習俗と断じたGHQと米軍による指導だった。その後都市化が進み、つまり土から離れて消費するだけの人口が増加するにつれて精神面でも構造面でも不可逆的変化が進み、糞尿は臭くて汚くて忌まわしいものになった。そしてバクテリアを使った下水道処理でできる乾燥汚泥を堆肥にしないのはなぜか。今の人間は土に還元できないほど汚染されている、と言うのだが。
化学合成添加物まみれになっているのは残飯も同じだし、どうせ化学合成添加物まみれにして食べるのだから、少々の汚染はもはや仕方ないのではないだろうか。マイクロプラスチックだって、既に人体内組織に入り込んでいるというし。つまり、化学合成添加物を含んでいるから糞尿からできる堆肥は田畑で使えないという言い分が、やりたくない理由にしか聞こえなくなってきた。
読了日:04月13日 著者:湯澤 規子

 戦争は女の顔をしていないの感想
戦争は女の顔をしていないの感想戦場に出た女性たちの、たくさんの声。ひとりひとりの、胸に涙を湛えながら集められたであろう小さな声が、怒涛となってこちらを打ちのめす。千人いれば、千の戦争と千の真実がある。今ウクライナについて語る著者の背後には深い悲しみが満ちて見える。頭から離れないのは、砲弾を運ぶ車両を運転していた女性の話。ドイツ兵の死体の上を通過するとき、頭蓋骨の砕ける音が嬉しかったと。憎しみは人の中にもともとあるのではない。生まれるのだ。今このときも、人々の中に育ちつつある憎しみが恐ろしい。他方、憎み抜けないことは救い。人間らしさだ。
『戦闘は夜中に終わりました。朝になって雪が降りました。亡くなった人たちの身体が雪に覆われました……その多くが手を上にあげていました……空の方に……。』読んでいるものと同じ行為が再現されているかのような映像が絶えず目前に流れ、辛い。だんだん、私がこの本を読んでいるから、同じことがウクライナに起きてしまうかのような倒錯が起きる。過去のエピソードも現実の報道も、当人には永遠に続くかのように感じるだろう深い慟哭がまとわりついている。
読了日:04月12日 著者:スヴェトラーナ アレクシエーヴィチ

 ルポ新大久保 移民最前線都市を歩くの感想
ルポ新大久保 移民最前線都市を歩くの感想移民として日本に住み着く人たちは、日本は決してオープンな社会ではないのに、なぜ選んでくれるのかとずっと思っていた。その理由は、稼ぐためだったり、日本の学歴が本国の就職に有利だからだったりするが、以前から言われる治安の良さだけではなく、今や韓国やオーストラリアより"割安だから"という選択に愕然とする。日本は「近くて安い国」になったのだ。まあ、それでもいい。彼らに優しい国であってほしい。多文化共生の基盤が整いつつある新大久保は今や先進地域。その発散するエネルギーを浴びに行ってみたくなるようなルポだった。
読了日:04月11日 著者:室橋 裕和

注:
 は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。 2022年04月02日
2022年3月の記録
読んでも読んでも、それ以上に本を買い込むのだから減りませんわね。
使命感と依存症状の混じりあった悦楽。
<今月のデータ>
購入24冊、購入費用30,350円。
読了20冊。
積読本313冊(うちKindle本143冊、Honto本14冊)。

3月の読書メーター
読んだ本の数:18
 新たなるインド映画の世界の感想
新たなるインド映画の世界の感想
我が家はインド映画にはまり、まあまあの数を観てきた。どれがどれかわからなくなっていたりもするので、写真で思い出したり、まだ観ていない映画をリストアップしてきゃぴきゃぴ楽しめたらくらいの感覚で開いたら、全く真剣な分析と論評の本だった。広いインドは言語も文化も土地によってばらばらで、従って一口にボリウッドと呼んでしまっていたけれど、映画も違うのだそうだ。シネコンの興隆によって、従来インド人が楽しんだ楽しみ方ができる映画が減った話は寂しい。話の流れを踏み倒すほど盛ったシーンやダンスが私は気に入っているのに。
読了日:03月29日 著者:夏目 深雪,松岡 環,高倉 嘉男,安宅 直子,岡本 敦史,浦川 留
 もう過去はいらない (創元推理文庫)の感想
もう過去はいらない (創元推理文庫)の感想
アメリカ在住者でないとそこにあるとわからない感覚が必要とされる小説。メンフィスの街でユダヤ人が悪目立ちしないようにという動機が、主人公の中で常に働いている。黒人に次いで蔑まれるユダヤ人は、悪事を働けばすぐに迫害された。"偏見と敵意のごった煮"の中で自分や家族の身を守るためだ。とはいいつつ、彼は歩くことすら覚束なくなっても尋問の途中で確信がおぼろげになっても、愛用の357マグナムは持ち歩き、機会あらばぶっ放す気満々の困った爺さんだ。人は生きてきたようにしか生きられない。息子の死の謎については次に持ち越し。
読了日:03月29日 著者:ダニエル・フリードマン
 親指が行方不明: 心も身体もままならないけど生きてますの感想
親指が行方不明: 心も身体もままならないけど生きてますの感想
たぶんすごい本なのだ。親指が行方不明くらいならぼんやり想像もできようが、その後のあれこれに至っては全く途方に暮れる。尹さんの「体の知性を取り戻す」が私と私の身体の融和への光明になっただけに、この圧倒的な置いて行かれ感に呆然としてしまった。しかし私には私の、身体的にも精神的にも"他にどうしようもできなかった"記憶があって、それのことなんだろうと含むしかない。意識と身体のズレ、思考と時間のズレ、かと。手首の関節を限りなく曲げていく光岡先生の練習が興味深い。加減を知悉しないと折れるし、信頼がないと任せられない。
読了日:03月24日 著者:尹雄大
 月と海豹の感想
月と海豹の感想
朗読を聴いたとき、子アザラシの皮でつくったかもしれない太鼓を母アザラシに渡すなど、なんてブラックな童話かと腰を抜かしそうになった。そんなうがった見方をする私のようなのは少数派らしく、調べてみた。小川未明自身が二人の子供を亡くしている。ならばこれは、自ら味わった子を失う悲しみ、その癒やしを描いた作品なのだ。氷の上を渡る太鼓の音、それが少しでも癒やしになるならば、よいではないか。と言いながら、その音は南の人間たちの楽しんだ音とは違って、寒々しい音、気紛らわしの手慰みであったのではないかと思ってしまうのだ。
読了日:03月24日 著者:小川 未明
 可愛い女の感想
可愛い女の感想
可愛げのない女としては、「可愛いひと!」と賛嘆されるためにはどうあればよいのか探るように読んだ。わかっていたことだが、これは、仮に若い時分に読んだとしても真似るのは無理だ。空っぽ。リンドバーグ「海からの贈物」を思い出した。満たして、こぼす。自分に意見やらやりたい事やらがあったらたちまち目に漏れてしまう。空っぽであればこそ、相手に満額合わせることができるし、相手に惜しみなく注ぐこともできるのだ。そして露ほども疑うことがないという最強の無邪気さ。相手があってこその生。そういう人と生きたら、しあわせだろうか…?
読了日:03月23日 著者:アントン チェーホフ
 Humankind 希望の歴史 上 人類が善き未来をつくるための18章の感想
Humankind 希望の歴史 上 人類が善き未来をつくるための18章の感想
ホモ・サピエンスは生来、善である。ルソーの描いた社会ではなく、ホッブスの描いたそれを実現してしまった現代はいろいろ間違えてしまっているが、空爆や大災害で人間の善良さは損なわれない、と学者たちは事実を挙げてみせた。オキシトシンは身内に優しくなる物質だ。人々の行動は平和で善である。私もそれを信じたい。しかし、ならばなぜシリアやウクライナのようなことが起きるのか。上巻では、人間の悪について証明したと考えられている有名な研究結果や事例を数々喝破しており、私たちに摺り込まれたバイアスを突き崩す。読んで良かった。
イースター島文明の衰退は、内乱ではなく堕落でも乱伐でもなく侵略ゆえであったと判明した。わりと直近に西洋人に上陸され、西洋人の基準で解釈された記憶を持つ国民としては、イースター島の内乱の記録が虚偽であったと知ってもやもやする。欧米人の、世界の支配者としての、歴史観の独善が鼻につく。イースター島の人々は善であった。機智と知恵で繁栄してきた。では、なぜ絶滅に追い込まれたのか。そうではない結末がもっともらしく流布されてきたのは何故か。訪れた側、欧米人の中に平和でも善でもない意志があったということにならないか?
なぜこんな戦争が起きるのか。プーチンというサイコパスと、プーチンを信じるアイヒマンと、プーチンに騙された善人がウクライナの人々を虐殺したのか。違うだろう。誰が決定し、引き金を引き、ミサイルのスイッチを押したのか。目の前にいる人間は撃てなくても、遠隔なら学校にも病院にも大型ミサイルを撃ち込めるのか。ロシア軍の攻撃は見境なくなっており、人を殺すことに慣れてきたようにさえ見える。善なるものはいつなんどきでも善ではない。真実を知りたい。解決する道を知りたい。
読了日:03月22日 著者:ルトガー・ブレグマン
 お味噌知る。の感想
お味噌知る。の感想
味噌汁から始まる自立。この春新たに独立する若者に向けた餞のような、応援されている感じがうきうきする。味噌汁の基本は水と味噌。「一汁一菜~」では、煮干しは最初から食べるまで入れっぱなしでよいという発想を教えていただいたが、今回はなんと、事前に取る出汁は重要でないのだよとハードルを下げる下げる。改めて「こうあるべき」ではない、味噌汁の自由を知る。自分のためだけの"自立の味噌汁"と、食べさせる相手ができたときの"家族の味噌汁"などにレシピが大別されているが、私は分け隔てなく食卓に出すつもりだ。父娘共著が面映い。
父ということは、土井勝氏?が高松出身とは知らなかった。白味噌仕立てのあん餅雑煮が常とは俄然親近感がわく。私はこの雑煮に開眼するのが遅くて、というのもあん餅雑煮の出汁はいりこが良いと知らずにきてしまったからだ。それを知ってから、出汁と味噌の関係の奥深さに気づき、いろいろ試してみるようになった。それにしても、昨日つくってみたところの、水にツナの水煮缶をぶっ込んだ味噌汁の旨さには仰天した。ああ、我が脳みその、なんと雁字搦めに縛られていることよ。
『腹中をくつろげ、血を活かし、百薬の毒を排出する。胃に入って、消化を助け、元気を運び、血のめぐりを良くする。痛みを鎮めて、よく食欲をひきだしてくれる。嘔吐をおさえ、腹下しを止める。また、髪を黒くし、皮膚を潤す』(本朝食鑑)。もう、ええことしかない。
読了日:03月21日 著者:土井 善晴,土井 光
 蘆屋家の崩壊 (ちくま文庫)の感想
蘆屋家の崩壊 (ちくま文庫)の感想
気になっていた作家の短編集。豆腐好きとか車好きとか飲んだくれとか、物語に関係あるんだかよくわからない人物設定と、安倍晴明と狐の伝説がとか、長野の食蟲文化はすごいみたいな、博識なんだかよくわからない知識を織り込んだ展開で、つい読み進まされてしまう。どっちとも取れる結末の真意が気になりつつも、まあよし。表題といい、古臭いような怪異譚なのだが、京極夏彦のようにずぶずぶと暗い迷路に沈み込んでいく生真面目さも無いので気楽だ。これは、続きがあったりするのだろうか。またいずれかの機会に読んでみたい。もし憶えていたら。
読了日:03月21日 著者:津原 泰水
 「奴隷」になった犬、そして猫の感想
「奴隷」になった犬、そして猫の感想
生体販売ビジネスの闇は動愛法改正によって改善されたか、との問いには否と答えよう。生体販売の8週齢規制、飼育環境規制案に対し、繁殖業者、販売業者、フード販売業者、品種認定団体、保険業者で構成する団体は全力で抵抗してきた。最終的に8週齢規制は成ったが、まさか生年月日を偽装してくるとは仰天だ。つまり、一般人にたくさん飼ってもらわないと業界は困るのだ。環境省は適正な専門家の知見に基づく数値規制を怠り、自治体は判断できず責任逃れ、悪質な業者は取り締まられないままだ。環境省や業者の発言の迷走が生々しい。
『生後35日くらいの大きさで持っていけば、最低でも10万円くらいになる。しかし生後35日で離したら、社会化もできない、股関節の発育も不完全、母乳もしっかり飲めていないから免疫力も高まっていない。そんな犬では、飼い主さんに安心して飼ってもらえないですよ。親犬に何度も転がされて、きょうだいたちと取っ組み合いのケンカをして、そういう経験によって社会化されるんです』。良い仔犬を飼い主に繋ぐことが優先で、そのために余分にかかるお金が惜しいなんて絶対言わない。これが本来のブリーダーとしての矜持。
読了日:03月17日 著者:太田匡彦
 断片的なものの社会学の感想
断片的なものの社会学の感想
私が専攻したのは心理学だった。しかし私が興味があったのは人間ではなく、自分だったのだと後に気づいた。著者は他者を見るまなざしが温かくて、さぞ人間が好きなのだろうと思いきや、そうではないと言う。他人が嫌いで、ひとりでいることが好きだと言う。日々出会う、ひとかたまりの言葉。芸術的でも高尚でもないそれらを、それぞれ胸に留め、ふと胸のうちでなにかと繋がる。生きている限り付き合うしかない、どうしようもない自分。私同様に、相手もどうしようもない自分を抱えている事実に行き会うことで、私たちは自分を肯定できているのか。
『私たちは小さな断片だからこそ、自分が思う正しさを述べる「権利」がある。それはどこか、「祈り」にも似ている。その正しさが届くかどうかは自分で決めることができない。私たちにできるのは、瓶のなかに紙切れを入れ、封をして海に流すことだけだ。それがどこの誰に届くか、そもそも誰にも届かないのかを自分ではどうすることもできない』。そうだな、と思う。SNSはまるきり海のようだ。精一杯練った言葉も、呪いの言葉も、放ったところで誰に届くことないとどこかで思っているから、受け取られ受け取る先を期待していないのかもしれない。
読了日:03月16日 著者:岸 政彦
 もっとヘンな論文の感想
もっとヘンな論文の感想
引き続き「論文」の紹介。竹取の翁が話を盛る癖のある中年だった、走るメロスの速度がほぼ徒歩だったなどという内容がくだらなく思えても、検証方法が正当と受け止められる論文は立派に論文である。書いた人の情熱がいつか誰かの役に立つかもしれないと記す著者のロマンが眩しい。さて、昔の「追いかけてくるもの」が気配や鳴き声など五感的な怪しさを持っていたのに対し、現代のそれは首無しや四つん這いなど、ずいぶん視覚的な性質がかっているのは興味深い。五感の中でも視覚がおおかたを占める現代の生活を反映しているのだろう。動画時代よの。
読了日:03月15日 著者:サンキュータツオ
 ナイルに死す〔新訳版〕 (ハヤカワ文庫 クリスティー文庫 15)の感想
ナイルに死す〔新訳版〕 (ハヤカワ文庫 クリスティー文庫 15)の感想
女性が憎らしくなるような女性の造形。それがヒロインというだけで掴みは万全なのに、女性がつい肩入れしたくなる女性やら蹴り倒したくなる男性やらがごろごろ登場するのだから、読み手は完全にクリスティの手中である。ナイルはクリスティの創作意欲をいたく刺激したのだろう、『岩の野蛮な感じ、風景の容赦ない残酷な感じ』は世界の不公平に尖る人心の暗喩とばかり、企みは強行される。もう引き返せない。そう思うことで破滅に向かう心は、片や挫けない心と対比されてどうしたって暗いはずなのに、よもやあっけらかんとした結末には呆然とした。
読了日:03月15日 著者:アガサ・クリスティー
 世界の辺境とハードボイルド室町時代の感想
世界の辺境とハードボイルド室町時代の感想
高野さんの知的好奇心や疑問に応え、また一緒に考察してくれる激レアさんは、日本中世専門の歴史研究者だった。怒涛トークでお互いに刺激し合っている気配が好い。日本中世の在り様を知ってアジアやアフリカの人の行動や習慣の意味合いに思い当たることも、またその逆も、世界を理解する手掛かりになる。「世界の辺境」と「昔の日本」は、多次元に交錯する世界の近接点なのだ。未確認動物と物の怪の共通点として『本当に信じている人たちに近づけば近づくほど、形がなくなっていく』は何気にすごい発見。口伝するうちに形が生まれてしまうのだろう。
読了日:03月13日 著者:高野 秀行,清水 克行
 地球温暖化/電気の話と、私たちにできること (扶桑社新書)の感想
地球温暖化/電気の話と、私たちにできること (扶桑社新書)の感想
日本国内で二酸化炭素を排出している上位は電力会社と大工場、これは統計上明らかである。これを変えるには国を変えなければならず、時機を待つしかないだろう。日本の世帯当たりエネルギー消費量は他国に比べて少ないという。ならば個々人はオフグリッドを心がけるのが良いというのが私の意見だ。中央集権的な現在の送電システムを拒否する。太陽光発電の自家消費で100%自給は難しいだろうが、家の断熱、ガスと太陽光温水器の有効利用で補い、使用量を低減するという絵図を夢想している。エコワンソーラーが面白そうなので憶えておく。
廃棄物処理についても興味深い記述があったので書きおいておく。生ごみはたい肥に、下水は液肥に、下水スラッジは肥料にして田畑に還元する試みが自治体レベルであるらしい。これは素晴らしいと思う。江戸への回帰である。全ての自治体で実用化されることを夢見つつ、コンポストがんばる。
読了日:03月10日 著者:田中 優
 男も女もみんなフェミニストでなきゃの感想
男も女もみんなフェミニストでなきゃの感想
著者はナイジェリア生まれの"男嫌いではないハッピーなアフリカ的フェミニスト"を自称する作家。2013年のTEDトークが基だ。『フェミニストとは、社会的、政治的、経済的に両性が平等だと信じる者』。ナイジェリアと日本の間に習俗的な差異はあれど、女性に課せられた足かせの性質はほとんど同じである。無論、男性のそれも。お互いほんまにしんどいことやなと思う。ジェンダーギャップ指数120位の日本としては、ひとつひとつ根気よく解除するしかないが、"上"が考え方をアップデートして決め事を変えないとどうもならん、と痛感する。
四国で数百人いるある集まりに、女性は私一人である。この状態で、もう10年以上になる。所属する地域の部会では、皆私の存在に慣れているが、私が入る前と後では、雰囲気が変わっただろうと思う。それがお互いにとって良いことか悪いことか、私には今も解らない。そしてなぜ女性が増えないか。当たり前だ。大変な思いをすることは、最初から想像のつくことだし、親だってそんなところに娘をやりたくはないだろう。結果得たものも多いけれど、未だに息苦しい思いをすることや、無意識に受け流すものごとも多い。もう、ええかな。と思う。
読了日:03月09日 著者:チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ
 ヤバい経済学 ─悪ガキ教授が世の裏側を探検するの感想
ヤバい経済学 ─悪ガキ教授が世の裏側を探検するの感想
『経済学は突き詰めるとインセンティヴの学問だ』。有名な研究者だそうだが、トピックが不正や犯罪なのでつい興味を惹かれて、読みやすい。疑問に思う事象の真実を見定めるための、着眼×充分条件を備えたデータ×分析。ワシントンのベイグル屋さんの話が私には印象深かった。都市に住む人間の善性を表わした結果がシンプルに出ている、"道徳と経済の交差点"。無人販売で誰も見ていなくても、87%の人はベイグルの対価を払う。たった1$の対価を払わず盗るのは、士気が低い企業の、大きなオフィスで、地位の高い人が多いそうだ。数字って雄弁。
道徳的インセンティヴが経済的インセンティヴに入れ替わり、経済的インセンティヴがなくなっても道徳的インセンティヴが戻らないという実例は、近頃特に多くなっているのではないかと推測する。例えば、車のスピード違反で捕まって、いかんなと反省しかかっているところに、罰金の金額を知らされ、憤慨しながら罰金を払ったが最後、反省は遠く彼方にぶっ飛んだまま戻ってこないような…ちょっと違うか。もとい、「罰金」なり「延長料金」なり、金銭を払えば済まされる決まりは、最近多いと思う。しかし実は、それは人間の道徳を損なう仕組みなのだ。
読了日:03月08日 著者:スティーヴン・レヴィット,スティーヴン・ダブナー
 サバイバル家族 (単行本)の感想
サバイバル家族 (単行本)の感想
小雪さんのエッセイと対になるエッセイ、自称"繁殖奮闘記"。もはや相聞歌と呼べないか。『俺といっしょに暮らしたほうが絶対面白いから』と口説き落としたという、自慢の奥さんである小雪さんが描く服部文祥ははちゃめちゃだったから、服部文祥の側から見たら物事はかくも反転するのかと感心しきりだった。3人の子供たちもそれぞれ相応にたくましく育って、独特な服部家のかたちはとても幸せそうに見えた。なお、シカの脳みそを食べたニワトリの卵が濃厚でべらぼうに旨いという強烈すぎる事実は、私の人生には役立ちそうにはないが、覚えておく。
読了日:03月07日 著者:服部 文祥
 イラストで見る昭和の消えた仕事図鑑 (角川ソフィア文庫)の感想
イラストで見る昭和の消えた仕事図鑑 (角川ソフィア文庫)の感想
時代に必要とされて生まれた仕事が、技術革新によって、あるいは資本による集約化によって消えた。特に後者のうちいくつかは見直される時期がくるのではと私は想像している。それらは経済とは別の次元の価値が見失われているだけなので、ある意味令和の時代のビジネスアイデアの芽と呼べるものが落ちている期待を持って読んだのだ。ただ職人の技術には復活しえないものもあるので、これらが失われつつあるのは残念極まりない。心根の卑しい仕事は今も似たり寄ったりなのに。なお、私は、かの時代なら、新聞社の編集局機報部鳩室伝書鳩係になりたい。
高木護の乞食見習いの話が面白い。『服装は百年一日のごとく、言葉は不明瞭に、月日は気にしないこと。明瞭に礼を言うと、相手は恵んだ気持ちになるが、不明瞭に言えば神様に物を供えたような気持になる』。これって実は深い話だと唸る。深いと言えば指物大工の言葉も。 『専門性が高いのです。逆にいろんな分野の経験をしたら平べったい知識しか生まれません』。
おばけ暦。明治政府が太陰暦を廃した時、六曜やさんりんぼうなどは迷信として削除され、太陽暦には七曜と干支、太陽と月の出入りが掲載された。庶民はそれでは困るんで、こっそり六曜やさんりんぼうの入った暦を印刷して使っていた。それがおばけ暦。戦後、自由化と共におばけ暦は晴れておばけでなくなったのだそうだ。現代でも商売をしていれば無縁ではいられないので、入ったカレンダーを選んで使っている。ちょっと大きな買い物をするときは神宮暦を見る。おっと、正確には高島暦か。神宮暦は今も"迷信を廃し"ているとのこと。見てみたい。
読了日:03月04日 著者:澤宮 優
注: は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。
使命感と依存症状の混じりあった悦楽。
<今月のデータ>
購入24冊、購入費用30,350円。
読了20冊。
積読本313冊(うちKindle本143冊、Honto本14冊)。

3月の読書メーター
読んだ本の数:18
 新たなるインド映画の世界の感想
新たなるインド映画の世界の感想我が家はインド映画にはまり、まあまあの数を観てきた。どれがどれかわからなくなっていたりもするので、写真で思い出したり、まだ観ていない映画をリストアップしてきゃぴきゃぴ楽しめたらくらいの感覚で開いたら、全く真剣な分析と論評の本だった。広いインドは言語も文化も土地によってばらばらで、従って一口にボリウッドと呼んでしまっていたけれど、映画も違うのだそうだ。シネコンの興隆によって、従来インド人が楽しんだ楽しみ方ができる映画が減った話は寂しい。話の流れを踏み倒すほど盛ったシーンやダンスが私は気に入っているのに。
読了日:03月29日 著者:夏目 深雪,松岡 環,高倉 嘉男,安宅 直子,岡本 敦史,浦川 留
 もう過去はいらない (創元推理文庫)の感想
もう過去はいらない (創元推理文庫)の感想アメリカ在住者でないとそこにあるとわからない感覚が必要とされる小説。メンフィスの街でユダヤ人が悪目立ちしないようにという動機が、主人公の中で常に働いている。黒人に次いで蔑まれるユダヤ人は、悪事を働けばすぐに迫害された。"偏見と敵意のごった煮"の中で自分や家族の身を守るためだ。とはいいつつ、彼は歩くことすら覚束なくなっても尋問の途中で確信がおぼろげになっても、愛用の357マグナムは持ち歩き、機会あらばぶっ放す気満々の困った爺さんだ。人は生きてきたようにしか生きられない。息子の死の謎については次に持ち越し。
読了日:03月29日 著者:ダニエル・フリードマン

 親指が行方不明: 心も身体もままならないけど生きてますの感想
親指が行方不明: 心も身体もままならないけど生きてますの感想たぶんすごい本なのだ。親指が行方不明くらいならぼんやり想像もできようが、その後のあれこれに至っては全く途方に暮れる。尹さんの「体の知性を取り戻す」が私と私の身体の融和への光明になっただけに、この圧倒的な置いて行かれ感に呆然としてしまった。しかし私には私の、身体的にも精神的にも"他にどうしようもできなかった"記憶があって、それのことなんだろうと含むしかない。意識と身体のズレ、思考と時間のズレ、かと。手首の関節を限りなく曲げていく光岡先生の練習が興味深い。加減を知悉しないと折れるし、信頼がないと任せられない。
読了日:03月24日 著者:尹雄大
 月と海豹の感想
月と海豹の感想朗読を聴いたとき、子アザラシの皮でつくったかもしれない太鼓を母アザラシに渡すなど、なんてブラックな童話かと腰を抜かしそうになった。そんなうがった見方をする私のようなのは少数派らしく、調べてみた。小川未明自身が二人の子供を亡くしている。ならばこれは、自ら味わった子を失う悲しみ、その癒やしを描いた作品なのだ。氷の上を渡る太鼓の音、それが少しでも癒やしになるならば、よいではないか。と言いながら、その音は南の人間たちの楽しんだ音とは違って、寒々しい音、気紛らわしの手慰みであったのではないかと思ってしまうのだ。
読了日:03月24日 著者:小川 未明
 可愛い女の感想
可愛い女の感想可愛げのない女としては、「可愛いひと!」と賛嘆されるためにはどうあればよいのか探るように読んだ。わかっていたことだが、これは、仮に若い時分に読んだとしても真似るのは無理だ。空っぽ。リンドバーグ「海からの贈物」を思い出した。満たして、こぼす。自分に意見やらやりたい事やらがあったらたちまち目に漏れてしまう。空っぽであればこそ、相手に満額合わせることができるし、相手に惜しみなく注ぐこともできるのだ。そして露ほども疑うことがないという最強の無邪気さ。相手があってこその生。そういう人と生きたら、しあわせだろうか…?
読了日:03月23日 著者:アントン チェーホフ
 Humankind 希望の歴史 上 人類が善き未来をつくるための18章の感想
Humankind 希望の歴史 上 人類が善き未来をつくるための18章の感想ホモ・サピエンスは生来、善である。ルソーの描いた社会ではなく、ホッブスの描いたそれを実現してしまった現代はいろいろ間違えてしまっているが、空爆や大災害で人間の善良さは損なわれない、と学者たちは事実を挙げてみせた。オキシトシンは身内に優しくなる物質だ。人々の行動は平和で善である。私もそれを信じたい。しかし、ならばなぜシリアやウクライナのようなことが起きるのか。上巻では、人間の悪について証明したと考えられている有名な研究結果や事例を数々喝破しており、私たちに摺り込まれたバイアスを突き崩す。読んで良かった。
イースター島文明の衰退は、内乱ではなく堕落でも乱伐でもなく侵略ゆえであったと判明した。わりと直近に西洋人に上陸され、西洋人の基準で解釈された記憶を持つ国民としては、イースター島の内乱の記録が虚偽であったと知ってもやもやする。欧米人の、世界の支配者としての、歴史観の独善が鼻につく。イースター島の人々は善であった。機智と知恵で繁栄してきた。では、なぜ絶滅に追い込まれたのか。そうではない結末がもっともらしく流布されてきたのは何故か。訪れた側、欧米人の中に平和でも善でもない意志があったということにならないか?
なぜこんな戦争が起きるのか。プーチンというサイコパスと、プーチンを信じるアイヒマンと、プーチンに騙された善人がウクライナの人々を虐殺したのか。違うだろう。誰が決定し、引き金を引き、ミサイルのスイッチを押したのか。目の前にいる人間は撃てなくても、遠隔なら学校にも病院にも大型ミサイルを撃ち込めるのか。ロシア軍の攻撃は見境なくなっており、人を殺すことに慣れてきたようにさえ見える。善なるものはいつなんどきでも善ではない。真実を知りたい。解決する道を知りたい。
読了日:03月22日 著者:ルトガー・ブレグマン

 お味噌知る。の感想
お味噌知る。の感想味噌汁から始まる自立。この春新たに独立する若者に向けた餞のような、応援されている感じがうきうきする。味噌汁の基本は水と味噌。「一汁一菜~」では、煮干しは最初から食べるまで入れっぱなしでよいという発想を教えていただいたが、今回はなんと、事前に取る出汁は重要でないのだよとハードルを下げる下げる。改めて「こうあるべき」ではない、味噌汁の自由を知る。自分のためだけの"自立の味噌汁"と、食べさせる相手ができたときの"家族の味噌汁"などにレシピが大別されているが、私は分け隔てなく食卓に出すつもりだ。父娘共著が面映い。
父ということは、土井勝氏?が高松出身とは知らなかった。白味噌仕立てのあん餅雑煮が常とは俄然親近感がわく。私はこの雑煮に開眼するのが遅くて、というのもあん餅雑煮の出汁はいりこが良いと知らずにきてしまったからだ。それを知ってから、出汁と味噌の関係の奥深さに気づき、いろいろ試してみるようになった。それにしても、昨日つくってみたところの、水にツナの水煮缶をぶっ込んだ味噌汁の旨さには仰天した。ああ、我が脳みその、なんと雁字搦めに縛られていることよ。
『腹中をくつろげ、血を活かし、百薬の毒を排出する。胃に入って、消化を助け、元気を運び、血のめぐりを良くする。痛みを鎮めて、よく食欲をひきだしてくれる。嘔吐をおさえ、腹下しを止める。また、髪を黒くし、皮膚を潤す』(本朝食鑑)。もう、ええことしかない。
読了日:03月21日 著者:土井 善晴,土井 光
 蘆屋家の崩壊 (ちくま文庫)の感想
蘆屋家の崩壊 (ちくま文庫)の感想気になっていた作家の短編集。豆腐好きとか車好きとか飲んだくれとか、物語に関係あるんだかよくわからない人物設定と、安倍晴明と狐の伝説がとか、長野の食蟲文化はすごいみたいな、博識なんだかよくわからない知識を織り込んだ展開で、つい読み進まされてしまう。どっちとも取れる結末の真意が気になりつつも、まあよし。表題といい、古臭いような怪異譚なのだが、京極夏彦のようにずぶずぶと暗い迷路に沈み込んでいく生真面目さも無いので気楽だ。これは、続きがあったりするのだろうか。またいずれかの機会に読んでみたい。もし憶えていたら。
読了日:03月21日 著者:津原 泰水

 「奴隷」になった犬、そして猫の感想
「奴隷」になった犬、そして猫の感想生体販売ビジネスの闇は動愛法改正によって改善されたか、との問いには否と答えよう。生体販売の8週齢規制、飼育環境規制案に対し、繁殖業者、販売業者、フード販売業者、品種認定団体、保険業者で構成する団体は全力で抵抗してきた。最終的に8週齢規制は成ったが、まさか生年月日を偽装してくるとは仰天だ。つまり、一般人にたくさん飼ってもらわないと業界は困るのだ。環境省は適正な専門家の知見に基づく数値規制を怠り、自治体は判断できず責任逃れ、悪質な業者は取り締まられないままだ。環境省や業者の発言の迷走が生々しい。
『生後35日くらいの大きさで持っていけば、最低でも10万円くらいになる。しかし生後35日で離したら、社会化もできない、股関節の発育も不完全、母乳もしっかり飲めていないから免疫力も高まっていない。そんな犬では、飼い主さんに安心して飼ってもらえないですよ。親犬に何度も転がされて、きょうだいたちと取っ組み合いのケンカをして、そういう経験によって社会化されるんです』。良い仔犬を飼い主に繋ぐことが優先で、そのために余分にかかるお金が惜しいなんて絶対言わない。これが本来のブリーダーとしての矜持。
読了日:03月17日 著者:太田匡彦
 断片的なものの社会学の感想
断片的なものの社会学の感想私が専攻したのは心理学だった。しかし私が興味があったのは人間ではなく、自分だったのだと後に気づいた。著者は他者を見るまなざしが温かくて、さぞ人間が好きなのだろうと思いきや、そうではないと言う。他人が嫌いで、ひとりでいることが好きだと言う。日々出会う、ひとかたまりの言葉。芸術的でも高尚でもないそれらを、それぞれ胸に留め、ふと胸のうちでなにかと繋がる。生きている限り付き合うしかない、どうしようもない自分。私同様に、相手もどうしようもない自分を抱えている事実に行き会うことで、私たちは自分を肯定できているのか。
『私たちは小さな断片だからこそ、自分が思う正しさを述べる「権利」がある。それはどこか、「祈り」にも似ている。その正しさが届くかどうかは自分で決めることができない。私たちにできるのは、瓶のなかに紙切れを入れ、封をして海に流すことだけだ。それがどこの誰に届くか、そもそも誰にも届かないのかを自分ではどうすることもできない』。そうだな、と思う。SNSはまるきり海のようだ。精一杯練った言葉も、呪いの言葉も、放ったところで誰に届くことないとどこかで思っているから、受け取られ受け取る先を期待していないのかもしれない。
読了日:03月16日 著者:岸 政彦
 もっとヘンな論文の感想
もっとヘンな論文の感想引き続き「論文」の紹介。竹取の翁が話を盛る癖のある中年だった、走るメロスの速度がほぼ徒歩だったなどという内容がくだらなく思えても、検証方法が正当と受け止められる論文は立派に論文である。書いた人の情熱がいつか誰かの役に立つかもしれないと記す著者のロマンが眩しい。さて、昔の「追いかけてくるもの」が気配や鳴き声など五感的な怪しさを持っていたのに対し、現代のそれは首無しや四つん這いなど、ずいぶん視覚的な性質がかっているのは興味深い。五感の中でも視覚がおおかたを占める現代の生活を反映しているのだろう。動画時代よの。
読了日:03月15日 著者:サンキュータツオ

 ナイルに死す〔新訳版〕 (ハヤカワ文庫 クリスティー文庫 15)の感想
ナイルに死す〔新訳版〕 (ハヤカワ文庫 クリスティー文庫 15)の感想女性が憎らしくなるような女性の造形。それがヒロインというだけで掴みは万全なのに、女性がつい肩入れしたくなる女性やら蹴り倒したくなる男性やらがごろごろ登場するのだから、読み手は完全にクリスティの手中である。ナイルはクリスティの創作意欲をいたく刺激したのだろう、『岩の野蛮な感じ、風景の容赦ない残酷な感じ』は世界の不公平に尖る人心の暗喩とばかり、企みは強行される。もう引き返せない。そう思うことで破滅に向かう心は、片や挫けない心と対比されてどうしたって暗いはずなのに、よもやあっけらかんとした結末には呆然とした。
読了日:03月15日 著者:アガサ・クリスティー
 世界の辺境とハードボイルド室町時代の感想
世界の辺境とハードボイルド室町時代の感想高野さんの知的好奇心や疑問に応え、また一緒に考察してくれる激レアさんは、日本中世専門の歴史研究者だった。怒涛トークでお互いに刺激し合っている気配が好い。日本中世の在り様を知ってアジアやアフリカの人の行動や習慣の意味合いに思い当たることも、またその逆も、世界を理解する手掛かりになる。「世界の辺境」と「昔の日本」は、多次元に交錯する世界の近接点なのだ。未確認動物と物の怪の共通点として『本当に信じている人たちに近づけば近づくほど、形がなくなっていく』は何気にすごい発見。口伝するうちに形が生まれてしまうのだろう。
読了日:03月13日 著者:高野 秀行,清水 克行

 地球温暖化/電気の話と、私たちにできること (扶桑社新書)の感想
地球温暖化/電気の話と、私たちにできること (扶桑社新書)の感想日本国内で二酸化炭素を排出している上位は電力会社と大工場、これは統計上明らかである。これを変えるには国を変えなければならず、時機を待つしかないだろう。日本の世帯当たりエネルギー消費量は他国に比べて少ないという。ならば個々人はオフグリッドを心がけるのが良いというのが私の意見だ。中央集権的な現在の送電システムを拒否する。太陽光発電の自家消費で100%自給は難しいだろうが、家の断熱、ガスと太陽光温水器の有効利用で補い、使用量を低減するという絵図を夢想している。エコワンソーラーが面白そうなので憶えておく。
廃棄物処理についても興味深い記述があったので書きおいておく。生ごみはたい肥に、下水は液肥に、下水スラッジは肥料にして田畑に還元する試みが自治体レベルであるらしい。これは素晴らしいと思う。江戸への回帰である。全ての自治体で実用化されることを夢見つつ、コンポストがんばる。
読了日:03月10日 著者:田中 優

 男も女もみんなフェミニストでなきゃの感想
男も女もみんなフェミニストでなきゃの感想著者はナイジェリア生まれの"男嫌いではないハッピーなアフリカ的フェミニスト"を自称する作家。2013年のTEDトークが基だ。『フェミニストとは、社会的、政治的、経済的に両性が平等だと信じる者』。ナイジェリアと日本の間に習俗的な差異はあれど、女性に課せられた足かせの性質はほとんど同じである。無論、男性のそれも。お互いほんまにしんどいことやなと思う。ジェンダーギャップ指数120位の日本としては、ひとつひとつ根気よく解除するしかないが、"上"が考え方をアップデートして決め事を変えないとどうもならん、と痛感する。
四国で数百人いるある集まりに、女性は私一人である。この状態で、もう10年以上になる。所属する地域の部会では、皆私の存在に慣れているが、私が入る前と後では、雰囲気が変わっただろうと思う。それがお互いにとって良いことか悪いことか、私には今も解らない。そしてなぜ女性が増えないか。当たり前だ。大変な思いをすることは、最初から想像のつくことだし、親だってそんなところに娘をやりたくはないだろう。結果得たものも多いけれど、未だに息苦しい思いをすることや、無意識に受け流すものごとも多い。もう、ええかな。と思う。
読了日:03月09日 著者:チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ

 ヤバい経済学 ─悪ガキ教授が世の裏側を探検するの感想
ヤバい経済学 ─悪ガキ教授が世の裏側を探検するの感想『経済学は突き詰めるとインセンティヴの学問だ』。有名な研究者だそうだが、トピックが不正や犯罪なのでつい興味を惹かれて、読みやすい。疑問に思う事象の真実を見定めるための、着眼×充分条件を備えたデータ×分析。ワシントンのベイグル屋さんの話が私には印象深かった。都市に住む人間の善性を表わした結果がシンプルに出ている、"道徳と経済の交差点"。無人販売で誰も見ていなくても、87%の人はベイグルの対価を払う。たった1$の対価を払わず盗るのは、士気が低い企業の、大きなオフィスで、地位の高い人が多いそうだ。数字って雄弁。
道徳的インセンティヴが経済的インセンティヴに入れ替わり、経済的インセンティヴがなくなっても道徳的インセンティヴが戻らないという実例は、近頃特に多くなっているのではないかと推測する。例えば、車のスピード違反で捕まって、いかんなと反省しかかっているところに、罰金の金額を知らされ、憤慨しながら罰金を払ったが最後、反省は遠く彼方にぶっ飛んだまま戻ってこないような…ちょっと違うか。もとい、「罰金」なり「延長料金」なり、金銭を払えば済まされる決まりは、最近多いと思う。しかし実は、それは人間の道徳を損なう仕組みなのだ。
読了日:03月08日 著者:スティーヴン・レヴィット,スティーヴン・ダブナー

 サバイバル家族 (単行本)の感想
サバイバル家族 (単行本)の感想小雪さんのエッセイと対になるエッセイ、自称"繁殖奮闘記"。もはや相聞歌と呼べないか。『俺といっしょに暮らしたほうが絶対面白いから』と口説き落としたという、自慢の奥さんである小雪さんが描く服部文祥ははちゃめちゃだったから、服部文祥の側から見たら物事はかくも反転するのかと感心しきりだった。3人の子供たちもそれぞれ相応にたくましく育って、独特な服部家のかたちはとても幸せそうに見えた。なお、シカの脳みそを食べたニワトリの卵が濃厚でべらぼうに旨いという強烈すぎる事実は、私の人生には役立ちそうにはないが、覚えておく。
読了日:03月07日 著者:服部 文祥
 イラストで見る昭和の消えた仕事図鑑 (角川ソフィア文庫)の感想
イラストで見る昭和の消えた仕事図鑑 (角川ソフィア文庫)の感想時代に必要とされて生まれた仕事が、技術革新によって、あるいは資本による集約化によって消えた。特に後者のうちいくつかは見直される時期がくるのではと私は想像している。それらは経済とは別の次元の価値が見失われているだけなので、ある意味令和の時代のビジネスアイデアの芽と呼べるものが落ちている期待を持って読んだのだ。ただ職人の技術には復活しえないものもあるので、これらが失われつつあるのは残念極まりない。心根の卑しい仕事は今も似たり寄ったりなのに。なお、私は、かの時代なら、新聞社の編集局機報部鳩室伝書鳩係になりたい。
高木護の乞食見習いの話が面白い。『服装は百年一日のごとく、言葉は不明瞭に、月日は気にしないこと。明瞭に礼を言うと、相手は恵んだ気持ちになるが、不明瞭に言えば神様に物を供えたような気持になる』。これって実は深い話だと唸る。深いと言えば指物大工の言葉も。 『専門性が高いのです。逆にいろんな分野の経験をしたら平べったい知識しか生まれません』。
おばけ暦。明治政府が太陰暦を廃した時、六曜やさんりんぼうなどは迷信として削除され、太陽暦には七曜と干支、太陽と月の出入りが掲載された。庶民はそれでは困るんで、こっそり六曜やさんりんぼうの入った暦を印刷して使っていた。それがおばけ暦。戦後、自由化と共におばけ暦は晴れておばけでなくなったのだそうだ。現代でも商売をしていれば無縁ではいられないので、入ったカレンダーを選んで使っている。ちょっと大きな買い物をするときは神宮暦を見る。おっと、正確には高島暦か。神宮暦は今も"迷信を廃し"ているとのこと。見てみたい。
読了日:03月04日 著者:澤宮 優

注:
 は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。 2022年03月01日
2022年2月の記録
ウクライナがこんなことになって、テレビやSNSを見ては腹を立てたり涙ぐんだりしている。
「同志少女よ、敵を撃て」を読んで、二次大戦の独ソ戦のことを初めて知った矢先。
次いで「戦争は女の顔をしていない」を読んでいる。
民間人が女性も年寄りも火器を手に取り、国を守ろうと立ち上がる心性は日本人には無い。
ドイツと戦った記憶が、今度はウクライナ国民をロシアに立ち向かわせている。
どうか早く早く、戦争が終わりますように。
<今月のデータ>
購入16冊、購入費用9,564円。
読了12冊。
積読本309冊(うちKindle本140冊、Honto本14冊)。

2月の読書メーター
読んだ本の数:12
 新装版 海も暮れきる (講談社文庫)の感想
新装版 海も暮れきる (講談社文庫)の感想
私には難題だった。放哉をどう見ればよいのか。はっきり言えば、人としてどう「評価」していいかわからない、と思ってしまうのだ。托鉢僧でも乞食でも、米や金を喜捨すれば謙虚に振る舞う。それを放哉は貰って当たり前とうそぶき、罵倒で返すのだ。酒に溺れる自身を正当化し、開き直り、そのくせ自己憐憫がちで卑屈で、周りを不快にする。その放哉を許せないことは、私自身をも許されない対象になりうる危うさを自覚させるのだ。しかし放哉は、幾人もの他人に支えられ、木瓜を活けた庵の畳の上で往生する。意味を考えあぐねて途方に暮れる春が来る。
酒に関しては私もがめつい方で、行儀が良いとは言えない。若い頃は泥酔して同席者や店に迷惑をかけたことは数えきれない。そう、迷惑。この言葉は要注意だ。「迷惑をかけない」ことは、近代現代になって美徳と成ったのではなかったか。自分は他人に迷惑をかけないようにする。だから他人も私に迷惑をかけるな。その心根は言わずともにじみ出るもの。誰にも迷惑をかけず生きることなどできないと、私はいつか思い知るだろう。そのとき初めて、人は許すものではない、頼り、支え合い、共に生きるものとわかるだろう。
読了日:02月28日 著者:吉村 昭
 絶対に挫折しない日本史 (新潮新書)の感想
絶対に挫折しない日本史 (新潮新書)の感想
挫折しかけた。「サピエンス全史」に触発されて書きたいと思ったのだそうだ。歴史を通観する試みは、全体を掴む手法として良い。人々の常識や価値観はその時代の置かれた状況によって違うもので、絶えず変転してきたのだから。しかし彼自身が現代の常識や価値観に囚われていることが透けて見える書き方なので、読み手の方が詳しければ鼻白む箇所もあるだろう。また落合陽一や杉田水脈をディスったところで主張が浮き上がるものでもない。とはいえ、大量の文献を引っぱり出し、引用した内容を比較考察し、彼らしい所感をぶっ込んできた勇気に拍手。
読了日:02月25日 著者:古市 憲寿
 土になるの感想
土になるの感想
うわあ、過剰な人。自分の関心事には時間の限り詰め込むのだから、それは消耗する。『僕たちは土から離されてい』たから心身の均衡を崩していた。土と向かい合うことで「自然」に合わせるられるようになったと繰り返し書いている。しかし「自分優先」なリズムは変わらないもののようだ。さて、ものづくりを新しく手にかけ、持続するためには何が必要なのだろう。好奇心だけではだめなのだ。下手な器用さはもっとだめだ。もっと、身の内側から湧くなにかを時期良く捉えないと、自分の一生ものにはならない。それがこの人は、とても上手いのだと思う。
読了日:02月24日 著者:坂口 恭平
 老ヴォールの惑星 (次世代型作家のリアル・フィクション ハヤカワ文庫 JA (809))の感想
老ヴォールの惑星 (次世代型作家のリアル・フィクション ハヤカワ文庫 JA (809))の感想
やさしいSF。設定はガチだが、技術面は深く考えなくても、そんなに哲学的にならなくても、楽しんで読めるところがいい。「ギャルナフカの迷宮」と「漂った男」が気に入っている。どちらも人類向きではない、未知の地で、なんとか生き延びようとする男の話である。なんだけど、深刻に"生きる意味"など考え込ませない、圧迫感のなさが心地よい。他に生命体のいない惑星の海面に浮かんで、服を着るか捨てるか、清潔を保つよう心がけるかおざなりにするか問題とか。ますますお気に入りの作家さん、しかし《天冥の標》はさすがに長そうで手が出ない。
読了日:02月24日 著者:小川 一水
 バーバ・ヤガーの感想
バーバ・ヤガーの感想
読み友さんの感想から、不思議な雰囲気に惹かれて手に取る。ほんまや、足はえとる…。しかもなかなか破壊力のある家である。台風にも洪水にも負けそうにない。そしてバーバ・ヤガーの乗り物は、臼なのである。いろいろと想像をぶっ超えてくるのは、文化の違い故なのか、作者の想像力の賜物なのか判然としないのだけれど、楽しい。絵は、版画だろうか。木々や部屋のニュアンスが、異国文化の情調と相まってうっとり眺めてしまう。文字多めの絵本。
読了日:02月23日 著者:アーネスト スモール
 室町は今日もハードボイルド: 日本中世のアナーキーな世界の感想
室町は今日もハードボイルド: 日本中世のアナーキーな世界の感想
たくましいな室町日本人。「くらしのアナキズム」でひとしきり考えた後に読むと、権力者によって一元的に支配されるのではなく、むしろ自分たちで決めたローカルルールでうまいことやっていた感じがわかる。国家使節団になりすまして朝鮮王朝に再々乗り込むとか、夫が浮気したら浮気相手の家を集団で襲撃するとか、自分勝手に改元した年号を使うとか、耳を疑うようなことも、詳しく聞くとなるほどなあ、と納得する論理がある。『虹の立つところに市を立てる』習俗が素敵だ。物の売買が日常的でなかったころ、同じくレアな虹に結び付けた純粋さよ。
読了日:02月20日 著者:清水 克行
 サマルカンドへ 〔ロング・マルシュ 長く歩く 2〕の感想
サマルカンドへ 〔ロング・マルシュ 長く歩く 2〕の感想
シルクロードを歩く旅は続く。今回はトルコからイラン、トルクメニスタン、ウズベキスタンまで。イランは豊かな地だ。人々は寛容で親切で、陽気に熱心に旅人をお茶に誘う。泊める。国際社会から嫌われている権力者たちは国民にも嫌われている。大いなる自然、それにペルシャ建築の美しい遺構。著者は苦労して、その美しさを味わう権利を手に入れる。サマルカンドの市場は、民族も香りも品物も色彩も言語もごったに溢れて、圧巻のクライマックスだ。次巻はまだ日本語で出版されていない。ぜひ訳して出版してほしいと、これから出版社に葉書を出す。
トルコ、イラン、トルクメニスタン、ウズベキスタン、中国と、シルクロードの通る地が今はどれも独裁的な国家だと気づいた。素人の想像では、西へ東への交流が多かったことによって他民族が混在し、それを統制するために、より強権的、独裁的な国家が生まれやすいという考え方は的外れだろうか? 人々の新しもの好きや寛容さもまた、同じくシルクロード商人の遺伝子の発露と考えれば、いずれの国でもこの2点は両立しうるのだ。
読了日:02月17日 著者:ベルナール・オリヴィエ
 くらしのアナキズムの感想
くらしのアナキズムの感想
「できるだけ国に頼らず生きる」方法を最近よく考える。私は無政府主義者になりつつあるのだろうか。それは、日々感じる、国や社会の仕組みの不全によるものとは気づいていたが、こう考えればよかったのか、と納得することしきりの読書だった。自分たちの自由や平等を損なうものの正体は、資本主義であり、行政や専門家に全て丸投げする社会の仕組みであり、古来の高度なスキルとすり替わった合理性偏重の思考である。私の感覚はその流れに呼応したものであり、諸事いろいろに繋がっていると知る。身の回り、小さなことからアナキズムを実践しよう。
アナキズムは国家の有無と関係ないと考えてみることは新鮮だった。民主主義国家であれ独裁国家であれ、諸大国は新型コロナを抑え込めなかった。集団が大きくなって解決できることもあるけれど、まとめるために漏れてしまうものも無視できないくらい多くなってしまっている。アナキズムこそは人類にとってのデフォルト。だから他者と共に生きるための高度なスキルが民族ごと、日本人の間にも古来育まれてきたことは、民俗学や人類学の文献にも明らかだ。さて、では時間や空間を自分のためだけに使う自由を、私たちは手放すことができるのだろうか?
読了日:02月16日 著者:松村圭一郎
 余興の感想
余興の感想
鴎外を耳で聴くのも予想どおり難しかった。読み直すと、耳を素通りしていた熟語が多々あった。しかし面白い。同郷人の集まりでの一幕。宴席で若い芸者を前に、猪口を反射的に引っこめ、思い直して差し出す、一瞬の葛藤がたまらなく好い。賑やかに酌み交わす場の片隅で、自分だけが間隙にはまったようにもがき、フル回転で気持ちの整理をしている、その静寂。親近感を覚えてにやにやしてしまう。きすさんはいい人だ。彼の内心を読めるような人ではない。彼が自分を軽く見ているのに気づいていて、なお優しい。そこにも気づくか、悩むか、悩まないか。
読了日:02月08日 著者:森 鴎外
 都市で進化する生物たち: ❝ダーウィン❞が街にやってくるの感想
都市で進化する生物たち: ❝ダーウィン❞が街にやってくるの感想
「人間vs.自然」ではなく、自然の一部であるところの人間が殖えすぎただけ。まあ、そうなのだろう。しかし人間が余りに早く大規模に環境を改変してしまった事実への私の青臭い罪悪感は拭えない。多数の種は適応できずに絶滅するのであり、他方、一部の種はその改変速度と競うように遺伝子を変化させて生存の道を探る。私にそのダイナミクス全体が捉えきれていないのは確かだ。仰天したのは、タバコの吸い殻を持ち帰って巣のダニ除けにする鳥。そしてPCBに汚染された湾で生き抜く生物。目を皿にして会社の周りを毎朝掃除する私は何なのだろう。
環境に関して、良くない話ばかりなので、明るい気分になりたくてこの本を選んだけれど、失敗かな。「人為性の急変的進化」は、人間側から言って「自然のたくましさ」と呼ぶことができるだろう。たくましいとは思うけれど、人間がコンクリートの床より木の床に触れて安心するように、鳥だってワイヤーハンガーの巣より木枝の巣の方が、ラップがへばりついた残飯より柿の実の方が、健やかに生きられるんじゃないかと思う。
都市の庭は、多くの種の微小生息地として、それぞれは小さくとも生態系は豊かだという。しかも建物や道路によって生息域が分断されることにより、庭によって動植物相は完全に異なる。そう考えることは、星の数ほどの生態系が身近にあるようで嬉しくなる。先日、亡き祖母の庭を潰す作業をした。祖母が長年にわたって生ごみをぽいぽい投げ捨てていた庭の土は肥料知らずながら豊かで、土と植物の断片からはふくよかな良い匂いがした。小宇宙をひとつ壊したような切なさを、仕方ないものとしてぐっと抑え込んだ。
読了日:02月07日 著者:メノ スヒルトハウゼン
 老虎残夢の感想
老虎残夢の感想
江戸川乱歩受賞作。特殊設定下の本格には違いない。中国武術の修練の末に得た、凡人には不可能なスキルが、犯人を絞り込む手掛かりになるあたり、中国武術を習う者の端くれとしても面白い。内功が剣に流れ込むイメージは練習に使えそうな気がするな、うん。しかし、、、露骨な百合が私には邪魔。人物を置いていったら、そういう関係が必要になってしまったかもしれないけれど、もう少し秘めた感じでもよかったんじゃないかなあ。それと、泰隆のイメージが十二国記の尚隆に重なってしまったんだが、なんか似すぎてやいないかと勘繰るのは穿ちすぎか。
読了日:02月04日 著者:桃野 雑派
 芥川龍之介『藪の中』を読む(文芸漫談コレクション) (集英社ebookオリジナル)の感想
芥川龍之介『藪の中』を読む(文芸漫談コレクション) (集英社ebookオリジナル)の感想
「藪の中」が好きな身には不興な対談。何故だ面白いのに。いとう氏と奥泉氏が評価しない理由は、原典とされる『今昔物語集』に対して、平面的で人間の掘り下げが無いただのストーリーだからだそうだ。そうだろうか? 若い頃から芥川を読んで悶々としていた私には、「藪の中」の三人の証言に見え隠れする人間の業が、今回改めて聴いた青空朗読の声の裏に凝るようでやはり面白かった。私は三人とも嘘をついていると解釈している。他者に対して嘘をつかせるもの、三者それぞれに理由がある。一人称だから書ける。このシリーズは私に合いそうにないな。
読了日:02月02日 著者:奥泉光,いとうせいこう
注: は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。
「同志少女よ、敵を撃て」を読んで、二次大戦の独ソ戦のことを初めて知った矢先。
次いで「戦争は女の顔をしていない」を読んでいる。
民間人が女性も年寄りも火器を手に取り、国を守ろうと立ち上がる心性は日本人には無い。
ドイツと戦った記憶が、今度はウクライナ国民をロシアに立ち向かわせている。
どうか早く早く、戦争が終わりますように。
<今月のデータ>
購入16冊、購入費用9,564円。
読了12冊。
積読本309冊(うちKindle本140冊、Honto本14冊)。

2月の読書メーター
読んだ本の数:12
 新装版 海も暮れきる (講談社文庫)の感想
新装版 海も暮れきる (講談社文庫)の感想私には難題だった。放哉をどう見ればよいのか。はっきり言えば、人としてどう「評価」していいかわからない、と思ってしまうのだ。托鉢僧でも乞食でも、米や金を喜捨すれば謙虚に振る舞う。それを放哉は貰って当たり前とうそぶき、罵倒で返すのだ。酒に溺れる自身を正当化し、開き直り、そのくせ自己憐憫がちで卑屈で、周りを不快にする。その放哉を許せないことは、私自身をも許されない対象になりうる危うさを自覚させるのだ。しかし放哉は、幾人もの他人に支えられ、木瓜を活けた庵の畳の上で往生する。意味を考えあぐねて途方に暮れる春が来る。
酒に関しては私もがめつい方で、行儀が良いとは言えない。若い頃は泥酔して同席者や店に迷惑をかけたことは数えきれない。そう、迷惑。この言葉は要注意だ。「迷惑をかけない」ことは、近代現代になって美徳と成ったのではなかったか。自分は他人に迷惑をかけないようにする。だから他人も私に迷惑をかけるな。その心根は言わずともにじみ出るもの。誰にも迷惑をかけず生きることなどできないと、私はいつか思い知るだろう。そのとき初めて、人は許すものではない、頼り、支え合い、共に生きるものとわかるだろう。
読了日:02月28日 著者:吉村 昭
 絶対に挫折しない日本史 (新潮新書)の感想
絶対に挫折しない日本史 (新潮新書)の感想挫折しかけた。「サピエンス全史」に触発されて書きたいと思ったのだそうだ。歴史を通観する試みは、全体を掴む手法として良い。人々の常識や価値観はその時代の置かれた状況によって違うもので、絶えず変転してきたのだから。しかし彼自身が現代の常識や価値観に囚われていることが透けて見える書き方なので、読み手の方が詳しければ鼻白む箇所もあるだろう。また落合陽一や杉田水脈をディスったところで主張が浮き上がるものでもない。とはいえ、大量の文献を引っぱり出し、引用した内容を比較考察し、彼らしい所感をぶっ込んできた勇気に拍手。
読了日:02月25日 著者:古市 憲寿

 土になるの感想
土になるの感想うわあ、過剰な人。自分の関心事には時間の限り詰め込むのだから、それは消耗する。『僕たちは土から離されてい』たから心身の均衡を崩していた。土と向かい合うことで「自然」に合わせるられるようになったと繰り返し書いている。しかし「自分優先」なリズムは変わらないもののようだ。さて、ものづくりを新しく手にかけ、持続するためには何が必要なのだろう。好奇心だけではだめなのだ。下手な器用さはもっとだめだ。もっと、身の内側から湧くなにかを時期良く捉えないと、自分の一生ものにはならない。それがこの人は、とても上手いのだと思う。
読了日:02月24日 著者:坂口 恭平
 老ヴォールの惑星 (次世代型作家のリアル・フィクション ハヤカワ文庫 JA (809))の感想
老ヴォールの惑星 (次世代型作家のリアル・フィクション ハヤカワ文庫 JA (809))の感想やさしいSF。設定はガチだが、技術面は深く考えなくても、そんなに哲学的にならなくても、楽しんで読めるところがいい。「ギャルナフカの迷宮」と「漂った男」が気に入っている。どちらも人類向きではない、未知の地で、なんとか生き延びようとする男の話である。なんだけど、深刻に"生きる意味"など考え込ませない、圧迫感のなさが心地よい。他に生命体のいない惑星の海面に浮かんで、服を着るか捨てるか、清潔を保つよう心がけるかおざなりにするか問題とか。ますますお気に入りの作家さん、しかし《天冥の標》はさすがに長そうで手が出ない。
読了日:02月24日 著者:小川 一水

 バーバ・ヤガーの感想
バーバ・ヤガーの感想読み友さんの感想から、不思議な雰囲気に惹かれて手に取る。ほんまや、足はえとる…。しかもなかなか破壊力のある家である。台風にも洪水にも負けそうにない。そしてバーバ・ヤガーの乗り物は、臼なのである。いろいろと想像をぶっ超えてくるのは、文化の違い故なのか、作者の想像力の賜物なのか判然としないのだけれど、楽しい。絵は、版画だろうか。木々や部屋のニュアンスが、異国文化の情調と相まってうっとり眺めてしまう。文字多めの絵本。
読了日:02月23日 著者:アーネスト スモール
 室町は今日もハードボイルド: 日本中世のアナーキーな世界の感想
室町は今日もハードボイルド: 日本中世のアナーキーな世界の感想たくましいな室町日本人。「くらしのアナキズム」でひとしきり考えた後に読むと、権力者によって一元的に支配されるのではなく、むしろ自分たちで決めたローカルルールでうまいことやっていた感じがわかる。国家使節団になりすまして朝鮮王朝に再々乗り込むとか、夫が浮気したら浮気相手の家を集団で襲撃するとか、自分勝手に改元した年号を使うとか、耳を疑うようなことも、詳しく聞くとなるほどなあ、と納得する論理がある。『虹の立つところに市を立てる』習俗が素敵だ。物の売買が日常的でなかったころ、同じくレアな虹に結び付けた純粋さよ。
読了日:02月20日 著者:清水 克行

 サマルカンドへ 〔ロング・マルシュ 長く歩く 2〕の感想
サマルカンドへ 〔ロング・マルシュ 長く歩く 2〕の感想シルクロードを歩く旅は続く。今回はトルコからイラン、トルクメニスタン、ウズベキスタンまで。イランは豊かな地だ。人々は寛容で親切で、陽気に熱心に旅人をお茶に誘う。泊める。国際社会から嫌われている権力者たちは国民にも嫌われている。大いなる自然、それにペルシャ建築の美しい遺構。著者は苦労して、その美しさを味わう権利を手に入れる。サマルカンドの市場は、民族も香りも品物も色彩も言語もごったに溢れて、圧巻のクライマックスだ。次巻はまだ日本語で出版されていない。ぜひ訳して出版してほしいと、これから出版社に葉書を出す。
トルコ、イラン、トルクメニスタン、ウズベキスタン、中国と、シルクロードの通る地が今はどれも独裁的な国家だと気づいた。素人の想像では、西へ東への交流が多かったことによって他民族が混在し、それを統制するために、より強権的、独裁的な国家が生まれやすいという考え方は的外れだろうか? 人々の新しもの好きや寛容さもまた、同じくシルクロード商人の遺伝子の発露と考えれば、いずれの国でもこの2点は両立しうるのだ。
読了日:02月17日 著者:ベルナール・オリヴィエ
 くらしのアナキズムの感想
くらしのアナキズムの感想「できるだけ国に頼らず生きる」方法を最近よく考える。私は無政府主義者になりつつあるのだろうか。それは、日々感じる、国や社会の仕組みの不全によるものとは気づいていたが、こう考えればよかったのか、と納得することしきりの読書だった。自分たちの自由や平等を損なうものの正体は、資本主義であり、行政や専門家に全て丸投げする社会の仕組みであり、古来の高度なスキルとすり替わった合理性偏重の思考である。私の感覚はその流れに呼応したものであり、諸事いろいろに繋がっていると知る。身の回り、小さなことからアナキズムを実践しよう。
アナキズムは国家の有無と関係ないと考えてみることは新鮮だった。民主主義国家であれ独裁国家であれ、諸大国は新型コロナを抑え込めなかった。集団が大きくなって解決できることもあるけれど、まとめるために漏れてしまうものも無視できないくらい多くなってしまっている。アナキズムこそは人類にとってのデフォルト。だから他者と共に生きるための高度なスキルが民族ごと、日本人の間にも古来育まれてきたことは、民俗学や人類学の文献にも明らかだ。さて、では時間や空間を自分のためだけに使う自由を、私たちは手放すことができるのだろうか?
読了日:02月16日 著者:松村圭一郎

 余興の感想
余興の感想鴎外を耳で聴くのも予想どおり難しかった。読み直すと、耳を素通りしていた熟語が多々あった。しかし面白い。同郷人の集まりでの一幕。宴席で若い芸者を前に、猪口を反射的に引っこめ、思い直して差し出す、一瞬の葛藤がたまらなく好い。賑やかに酌み交わす場の片隅で、自分だけが間隙にはまったようにもがき、フル回転で気持ちの整理をしている、その静寂。親近感を覚えてにやにやしてしまう。きすさんはいい人だ。彼の内心を読めるような人ではない。彼が自分を軽く見ているのに気づいていて、なお優しい。そこにも気づくか、悩むか、悩まないか。
読了日:02月08日 著者:森 鴎外

 都市で進化する生物たち: ❝ダーウィン❞が街にやってくるの感想
都市で進化する生物たち: ❝ダーウィン❞が街にやってくるの感想「人間vs.自然」ではなく、自然の一部であるところの人間が殖えすぎただけ。まあ、そうなのだろう。しかし人間が余りに早く大規模に環境を改変してしまった事実への私の青臭い罪悪感は拭えない。多数の種は適応できずに絶滅するのであり、他方、一部の種はその改変速度と競うように遺伝子を変化させて生存の道を探る。私にそのダイナミクス全体が捉えきれていないのは確かだ。仰天したのは、タバコの吸い殻を持ち帰って巣のダニ除けにする鳥。そしてPCBに汚染された湾で生き抜く生物。目を皿にして会社の周りを毎朝掃除する私は何なのだろう。
環境に関して、良くない話ばかりなので、明るい気分になりたくてこの本を選んだけれど、失敗かな。「人為性の急変的進化」は、人間側から言って「自然のたくましさ」と呼ぶことができるだろう。たくましいとは思うけれど、人間がコンクリートの床より木の床に触れて安心するように、鳥だってワイヤーハンガーの巣より木枝の巣の方が、ラップがへばりついた残飯より柿の実の方が、健やかに生きられるんじゃないかと思う。
都市の庭は、多くの種の微小生息地として、それぞれは小さくとも生態系は豊かだという。しかも建物や道路によって生息域が分断されることにより、庭によって動植物相は完全に異なる。そう考えることは、星の数ほどの生態系が身近にあるようで嬉しくなる。先日、亡き祖母の庭を潰す作業をした。祖母が長年にわたって生ごみをぽいぽい投げ捨てていた庭の土は肥料知らずながら豊かで、土と植物の断片からはふくよかな良い匂いがした。小宇宙をひとつ壊したような切なさを、仕方ないものとしてぐっと抑え込んだ。
読了日:02月07日 著者:メノ スヒルトハウゼン

 老虎残夢の感想
老虎残夢の感想江戸川乱歩受賞作。特殊設定下の本格には違いない。中国武術の修練の末に得た、凡人には不可能なスキルが、犯人を絞り込む手掛かりになるあたり、中国武術を習う者の端くれとしても面白い。内功が剣に流れ込むイメージは練習に使えそうな気がするな、うん。しかし、、、露骨な百合が私には邪魔。人物を置いていったら、そういう関係が必要になってしまったかもしれないけれど、もう少し秘めた感じでもよかったんじゃないかなあ。それと、泰隆のイメージが十二国記の尚隆に重なってしまったんだが、なんか似すぎてやいないかと勘繰るのは穿ちすぎか。
読了日:02月04日 著者:桃野 雑派
 芥川龍之介『藪の中』を読む(文芸漫談コレクション) (集英社ebookオリジナル)の感想
芥川龍之介『藪の中』を読む(文芸漫談コレクション) (集英社ebookオリジナル)の感想「藪の中」が好きな身には不興な対談。何故だ面白いのに。いとう氏と奥泉氏が評価しない理由は、原典とされる『今昔物語集』に対して、平面的で人間の掘り下げが無いただのストーリーだからだそうだ。そうだろうか? 若い頃から芥川を読んで悶々としていた私には、「藪の中」の三人の証言に見え隠れする人間の業が、今回改めて聴いた青空朗読の声の裏に凝るようでやはり面白かった。私は三人とも嘘をついていると解釈している。他者に対して嘘をつかせるもの、三者それぞれに理由がある。一人称だから書ける。このシリーズは私に合いそうにないな。
読了日:02月02日 著者:奥泉光,いとうせいこう

注:
 は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。 2022年02月01日
2022年1月の記録
お腹がすいたなあ、と感じると、手近な食べ物をとりあえず口に入れてやりすごしたり、視界に入る食べ物をつい買ってしまうような行為を取る。
本を読む時間を満足に取れないと、本読みたさに苛々し、穴埋めとばかり本をまとめ買いしたりする。
食べ物同様、本を買っただけでは当然だめで、読まない限り満たされないのであり、期待に外れた本だとやはり満たされず、飢えている。
本棚には読むべき本がこんなに積みあがっているというのに。
厄介なものよ。
<今月のデータ>
購入12冊、購入費用14,559円。
読了11冊。
積読本304冊(うちKindle本137冊、Honto本14冊)。

1月の読書メーター
読んだ本の数:10
 私たちはいつまで危険な場所に住み続けるのかの感想
私たちはいつまで危険な場所に住み続けるのかの感想
住む場所を選べるなら、リスクは最低限にしたい。しかし日本人の半分は洪水氾濫区域に居住している。行政がハザードマップに特別警戒区域や警戒区域を策定しても、既に人々が住んでいる地域を居住誘導区域から除くと町が成り立たなくなる。豪雨の増加とさらなる人口の流入により、浸水想定区域内の浸水被害件数は今後も増えるとあれば、各種保険料も上がるのだろう。そして策定に盛り込みきれないリスクもあると言い、もう、最終的には自分で判断するしかないが、どうすればよいものか頭を抱える。真備や熱海ほか、直近の災害についても詳しい。
読了日:01月31日 著者:木村駿,真鍋政彦,荒川尚美
 地底旅行 (角川文庫)の感想
地底旅行 (角川文庫)の感想
久しぶりにわくわくする読書だった。当時のフランス人にとって、アイスランドはどのくらい遠い地だったろうか。現代の私にとってもアイスランドは遠い地だけれど、Google Earthで海岸線をたどってみたり、放たれた馬を眺めてみたり、郊外の荒涼とした野は、アスファルト舗装以外は当時とあんまり変わらないのだろう。そして奇想天外な冒険譚! これを読んで冒険家や地質学者、古生物学者を目指す少年が多発したことだろう。世界には知らないことがたくさんあると気づくことは、身の内にこんなにも活力を生むことなんだと思い出した。
読了日:01月31日 著者:ヴェルヌ
 献灯使 (講談社文庫)の感想
献灯使 (講談社文庫)の感想
壊滅的な過ちを犯し、国外との交信を絶った日本。ディストピア、なのだろう。しかしある面において私は、この世界が羨ましくも思ったのだ。日本国と日本人に未来が無いことが白日の下に明らかになり、希望がないという共通認識を持つ者どうしが、生きられるだけ生きんとする世界。現状を自らの罪と断罪し、若者を失う痛みを受け入れ、江戸に回帰するような日々は淡々と穏やかに進んでゆくだろう。いっこうに死ねないのは嫌だけれど。世界はもっと善くあるべきと、もがくことに私は疲れているのかもしれない。「不死の島」は「献灯使」と表裏か。
フクシマ原発事故の衝撃をなんとか嚥下しようと咀嚼するような連作。「彼岸」では原爆による被爆の地獄絵図が再現される。日本を離れなければ生き延びることができない世界では、日本人たちは難民として大陸に渡る。ここでは「日本沈没」を連想する。現代の日本人は意味もなくヘイトした地で、難民として生きていくことはできるのだろうか。戦前戦後の相似形だ。そんな日がひょっとしたらくるのかと思ったり、そうはいっても日本人はこれまで数多の災害をなんとかかんとか生き延びてきたのだしと思ったり、嚥下もままならないまま、忘れるのか。
読了日:01月30日 著者:多和田 葉子
 夜釣の感想
夜釣の感想
青空朗読で聴いた後、青空文庫で読んだ。泉鏡花は、音読を念頭に置いて文章を書いていないように思う。文章を読んでいても、途中で文脈が切り替わっているのに気づいて戻ること度々だからだ。しかし、夜の空が妖しくなる様子や、子供たちの不可解な様子は、聴いていて背筋がぞっと寒くなるような凄みがあって、聴いてみるのも面白いなあと、読み返しながら思ったことだった。言葉選びに既に世界観があるからかしら。初出表題は「鰻」。末尾の山東京伝はなにか所以あってだろうか?
読了日:01月29日 著者:泉 鏡花
 FOOTPRINTS(フットプリント) 未来から見た私たちの痕跡の感想
FOOTPRINTS(フットプリント) 未来から見た私たちの痕跡の感想
例えば1000年後。地面を掘ったら、中世の石畳のようにアスファルトが、貝塚のように埋立ゴミが、地中や海底にビルが立ち現れる。それらが、私たちが未来に残す足跡だ。著者はイギリスの文学の教授なので、見聞きしたものから連想された古典から現代詩まで、古今東西の著作の引用が多いあたりが他のノンフィクションと違う。回りくどくも感じる一方、情報だけでない、練られた言葉による比喩や情緒まで書き込まれることで、私の気持ちにもさざ波をおこし、生身の人間の感覚、未来への想像力を働かせることを許される。
原発の使用済み燃料、つまり核廃棄物はおそらく最も長く残る私たちの足跡だ。地中深くに埋める取組みが世界では既に始まっている。アメリカでは埋設地を掘らないよう石碑に警告を、言語のほか表象、苦悶の顔などで彫り込んだ。フィンランドでは太古にできた岩盤上に深く埋め、目印をあえて残さない方策を取った。核廃棄物は400年も経てば天然鉱物同等の危険度に減衰するという。そしていずれ都市も消え去る。海面上昇や地盤変動で、海の近くで地の利を得て発達した大都市はその頃には海に沈んでいるだろう。沈むのは南洋の島だけじゃあない。
読了日:01月15日 著者:デイビッド・ファリアー
 おうち避難のための マンガ 防災図鑑の感想
おうち避難のための マンガ 防災図鑑の感想
私が平均寿命まで日本で生きたなら、それまでに少なくとも2、3の甚大災害を目にするだろうし、自身も平時と違う被災状態に置かれる事態は想像に難くない。当然、日本において防災対策は他人事でない。この手の心構え本は多数あるも、東日本大震災をはじめ、数多の大災害を経て、つまりたくさんの人の被災経験を集成して、ずいぶんアップデートされている。ありがたく備えさせていただく。さらに新型コロナにより、分散避難、特に在宅避難が重視されている。百均の多用が気に入らないが、備えへのハードルを下げさせるためには致し方ないだろう。
読了日:01月10日 著者:草野かおる
 選挙活動、ビラ配りからやってみた。「香川1区」密着日記の感想
選挙活動、ビラ配りからやってみた。「香川1区」密着日記の感想
マイク納めの時、場に満ちていたのは希望だった。小川家の人々を囲んで、私たちはひと時安堵し、未来を想った。裏でそんな事件が起きていたなんて知らなかった。妻・娘タスキの件だ。明子さんと娘さんたちを家父長制を思わせるタスキで表わすのはおかしいと和田さんが伝えたという。なんかもう、想像して泣けた。今の香川県で、高齢に偏った有権者に受け入れてもらうために、小川家の人々はドブ板でも集会でもいろんな試みを積み重ねてきた。昨今の風潮に鑑みておかしいことくらいとっくにご存じだ。それをなんで和田さんの立ち位置から言えたのか。
清濁併せ呑む、という表現がある。小川さんはそういうの苦手だよね、というイメージが先行しているが、ある程度は合理的な判断で行動されていることが垣間見える。つまり、ポリティカルコレクトネス的にはこれが正しいけれど、細かい点ではとりあえず、今のところは、そうでない意見や方法を取り入れておいて、時宜を見て修正していくような。正しさばかりで国は動かせない。それを家族にも強いてしまうことの重たさは、小川さん自身感じておられて、ご家族皆さん共有されているように感じられる。だから…ああああもう腹が立つ!!!
読了日:01月10日 著者:和田靜香,小川淳也
 100万回死んだねこ 覚え違いタイトル集の感想
100万回死んだねこ 覚え違いタイトル集の感想
以前本屋で、探している本のタイトルが思い出せず、店主に思いつく限りを挙げた末に全く重ならないタイトルの本が言い当てられて、店主の慧眼と感嘆したことがある。自分の記憶のいい加減さもたいがいだった。表題を含めこれら誤タイトルには、そんなんないやろ!とつっこみたい素っ頓狂なものもあるが、人の勘違いは百人百通り。読み間違い勘違いのデータベースのみならず、概要や連想の必要な難題もあり、AIがすべてクリアできる時代はもう少し先ではないかしら。絵本も児童書も、古典も流行りものもあるから、これはたいへんだわ。
読了日:01月09日 著者:福井県立図書館
 最近、地球が暑くてクマってます。 シロクマが教えてくれた温暖化時代を幸せに生き抜く方法の感想
最近、地球が暑くてクマってます。 シロクマが教えてくれた温暖化時代を幸せに生き抜く方法の感想
動物を擬人化した趣向が好きでないのだけれど、読んでみると会社に置いておきたくなった。監修がしっかりしていて、メインの文章で浅く読むことも、「熊の巻」で深く知ることもできる。軽く手に取ってもらえそうだ。強調しているのは、温暖化対策は個々人の我慢に依存するものではなく、国を動かすアクションをこそ起こすべきである点だ。なぜなら二酸化炭素排出の4割を石油・石炭による発電等が占めており、個人の我慢など知れているからだ。だからといって原子力発電の増設はまっぴらごめん、なのであれば、しつこく意見表明しなければならない。
地球全体の二酸化炭素濃度は一次関数的に上昇し続けている。温暖化がガスの影響と言われ始めて以降、2020年に至るまで、である。つい最近まで懐疑派だった私につべこべ言う資格は無いのだけれど、この温暖化はもう止まらないのではないか、臨界点は既に越えつつあるのではないかという感覚が拭えない。しかしそれは無根拠な感覚的なものであって、論理的ではない。無責任と反省した。目の前の現象を平易な目で見守り、確かな分析を追わなければならない。
シロクマは、温暖化が進めばどのみち生きていくことはできない。種を守るために動物園のシロクマに生きてもらわなければなんて悪い冗談だ。
読了日:01月08日 著者:水野敬也,長沼直樹
 You are what you read あなたは読んだものに他ならないの感想
You are what you read あなたは読んだものに他ならないの感想
理屈ぽくて皮肉屋で真面目で、近くにいたら面倒くさそうな服部文祥が、読むほどになんだか愛すべきキャラに思えてきたのだ。極限状態の中に、服部文祥は生きることの謎を解く鍵を探す。自らの極限体験では飽き足らず、他人の極限である状況と言葉を覗き見て、本質に触れたい欲求はわかるように思う。答えは一向に得られないけれど。『自然界で起こったことは信じる信じないではなく、受け入れるか受け入れないかだ。セメントに囲まれて暮らしている我々が、動物の奥深い能力や自然のありようにまで、人間の常識を当てはめるべきではない』は至言だ。
昨年末は特に年賀状の支度をしたくなくて、ずるずると今日に至り、ええ歳こいて年始早々に不義理をした。本の中で服部文祥が、登山に行ったら事故で帰ってこないかもしれない、それを思うので登山の予定を挟んだちょっと先の約束すら嫌だったというようなことを書いていて、思い当たった。ああ、私は去年、人や猫の生き死ににたくさん出会って、今このときのことで手一杯な日々を乗り越えてこなして、見知らぬ来年のことなどもう考えたくなかったのだと。年賀状は自分にも相手にも「今年」がある前提の遣り取りで、その儚さが辛かったのだ。
読了日:01月07日 著者:服部文祥
注: は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。
本を読む時間を満足に取れないと、本読みたさに苛々し、穴埋めとばかり本をまとめ買いしたりする。
食べ物同様、本を買っただけでは当然だめで、読まない限り満たされないのであり、期待に外れた本だとやはり満たされず、飢えている。
本棚には読むべき本がこんなに積みあがっているというのに。
厄介なものよ。
<今月のデータ>
購入12冊、購入費用14,559円。
読了11冊。
積読本304冊(うちKindle本137冊、Honto本14冊)。

1月の読書メーター
読んだ本の数:10
 私たちはいつまで危険な場所に住み続けるのかの感想
私たちはいつまで危険な場所に住み続けるのかの感想住む場所を選べるなら、リスクは最低限にしたい。しかし日本人の半分は洪水氾濫区域に居住している。行政がハザードマップに特別警戒区域や警戒区域を策定しても、既に人々が住んでいる地域を居住誘導区域から除くと町が成り立たなくなる。豪雨の増加とさらなる人口の流入により、浸水想定区域内の浸水被害件数は今後も増えるとあれば、各種保険料も上がるのだろう。そして策定に盛り込みきれないリスクもあると言い、もう、最終的には自分で判断するしかないが、どうすればよいものか頭を抱える。真備や熱海ほか、直近の災害についても詳しい。
読了日:01月31日 著者:木村駿,真鍋政彦,荒川尚美
 地底旅行 (角川文庫)の感想
地底旅行 (角川文庫)の感想久しぶりにわくわくする読書だった。当時のフランス人にとって、アイスランドはどのくらい遠い地だったろうか。現代の私にとってもアイスランドは遠い地だけれど、Google Earthで海岸線をたどってみたり、放たれた馬を眺めてみたり、郊外の荒涼とした野は、アスファルト舗装以外は当時とあんまり変わらないのだろう。そして奇想天外な冒険譚! これを読んで冒険家や地質学者、古生物学者を目指す少年が多発したことだろう。世界には知らないことがたくさんあると気づくことは、身の内にこんなにも活力を生むことなんだと思い出した。
読了日:01月31日 著者:ヴェルヌ

 献灯使 (講談社文庫)の感想
献灯使 (講談社文庫)の感想壊滅的な過ちを犯し、国外との交信を絶った日本。ディストピア、なのだろう。しかしある面において私は、この世界が羨ましくも思ったのだ。日本国と日本人に未来が無いことが白日の下に明らかになり、希望がないという共通認識を持つ者どうしが、生きられるだけ生きんとする世界。現状を自らの罪と断罪し、若者を失う痛みを受け入れ、江戸に回帰するような日々は淡々と穏やかに進んでゆくだろう。いっこうに死ねないのは嫌だけれど。世界はもっと善くあるべきと、もがくことに私は疲れているのかもしれない。「不死の島」は「献灯使」と表裏か。
フクシマ原発事故の衝撃をなんとか嚥下しようと咀嚼するような連作。「彼岸」では原爆による被爆の地獄絵図が再現される。日本を離れなければ生き延びることができない世界では、日本人たちは難民として大陸に渡る。ここでは「日本沈没」を連想する。現代の日本人は意味もなくヘイトした地で、難民として生きていくことはできるのだろうか。戦前戦後の相似形だ。そんな日がひょっとしたらくるのかと思ったり、そうはいっても日本人はこれまで数多の災害をなんとかかんとか生き延びてきたのだしと思ったり、嚥下もままならないまま、忘れるのか。
読了日:01月30日 著者:多和田 葉子
 夜釣の感想
夜釣の感想青空朗読で聴いた後、青空文庫で読んだ。泉鏡花は、音読を念頭に置いて文章を書いていないように思う。文章を読んでいても、途中で文脈が切り替わっているのに気づいて戻ること度々だからだ。しかし、夜の空が妖しくなる様子や、子供たちの不可解な様子は、聴いていて背筋がぞっと寒くなるような凄みがあって、聴いてみるのも面白いなあと、読み返しながら思ったことだった。言葉選びに既に世界観があるからかしら。初出表題は「鰻」。末尾の山東京伝はなにか所以あってだろうか?
読了日:01月29日 著者:泉 鏡花

 FOOTPRINTS(フットプリント) 未来から見た私たちの痕跡の感想
FOOTPRINTS(フットプリント) 未来から見た私たちの痕跡の感想例えば1000年後。地面を掘ったら、中世の石畳のようにアスファルトが、貝塚のように埋立ゴミが、地中や海底にビルが立ち現れる。それらが、私たちが未来に残す足跡だ。著者はイギリスの文学の教授なので、見聞きしたものから連想された古典から現代詩まで、古今東西の著作の引用が多いあたりが他のノンフィクションと違う。回りくどくも感じる一方、情報だけでない、練られた言葉による比喩や情緒まで書き込まれることで、私の気持ちにもさざ波をおこし、生身の人間の感覚、未来への想像力を働かせることを許される。
原発の使用済み燃料、つまり核廃棄物はおそらく最も長く残る私たちの足跡だ。地中深くに埋める取組みが世界では既に始まっている。アメリカでは埋設地を掘らないよう石碑に警告を、言語のほか表象、苦悶の顔などで彫り込んだ。フィンランドでは太古にできた岩盤上に深く埋め、目印をあえて残さない方策を取った。核廃棄物は400年も経てば天然鉱物同等の危険度に減衰するという。そしていずれ都市も消え去る。海面上昇や地盤変動で、海の近くで地の利を得て発達した大都市はその頃には海に沈んでいるだろう。沈むのは南洋の島だけじゃあない。
読了日:01月15日 著者:デイビッド・ファリアー

 おうち避難のための マンガ 防災図鑑の感想
おうち避難のための マンガ 防災図鑑の感想私が平均寿命まで日本で生きたなら、それまでに少なくとも2、3の甚大災害を目にするだろうし、自身も平時と違う被災状態に置かれる事態は想像に難くない。当然、日本において防災対策は他人事でない。この手の心構え本は多数あるも、東日本大震災をはじめ、数多の大災害を経て、つまりたくさんの人の被災経験を集成して、ずいぶんアップデートされている。ありがたく備えさせていただく。さらに新型コロナにより、分散避難、特に在宅避難が重視されている。百均の多用が気に入らないが、備えへのハードルを下げさせるためには致し方ないだろう。
読了日:01月10日 著者:草野かおる
 選挙活動、ビラ配りからやってみた。「香川1区」密着日記の感想
選挙活動、ビラ配りからやってみた。「香川1区」密着日記の感想マイク納めの時、場に満ちていたのは希望だった。小川家の人々を囲んで、私たちはひと時安堵し、未来を想った。裏でそんな事件が起きていたなんて知らなかった。妻・娘タスキの件だ。明子さんと娘さんたちを家父長制を思わせるタスキで表わすのはおかしいと和田さんが伝えたという。なんかもう、想像して泣けた。今の香川県で、高齢に偏った有権者に受け入れてもらうために、小川家の人々はドブ板でも集会でもいろんな試みを積み重ねてきた。昨今の風潮に鑑みておかしいことくらいとっくにご存じだ。それをなんで和田さんの立ち位置から言えたのか。
清濁併せ呑む、という表現がある。小川さんはそういうの苦手だよね、というイメージが先行しているが、ある程度は合理的な判断で行動されていることが垣間見える。つまり、ポリティカルコレクトネス的にはこれが正しいけれど、細かい点ではとりあえず、今のところは、そうでない意見や方法を取り入れておいて、時宜を見て修正していくような。正しさばかりで国は動かせない。それを家族にも強いてしまうことの重たさは、小川さん自身感じておられて、ご家族皆さん共有されているように感じられる。だから…ああああもう腹が立つ!!!
読了日:01月10日 著者:和田靜香,小川淳也
 100万回死んだねこ 覚え違いタイトル集の感想
100万回死んだねこ 覚え違いタイトル集の感想以前本屋で、探している本のタイトルが思い出せず、店主に思いつく限りを挙げた末に全く重ならないタイトルの本が言い当てられて、店主の慧眼と感嘆したことがある。自分の記憶のいい加減さもたいがいだった。表題を含めこれら誤タイトルには、そんなんないやろ!とつっこみたい素っ頓狂なものもあるが、人の勘違いは百人百通り。読み間違い勘違いのデータベースのみならず、概要や連想の必要な難題もあり、AIがすべてクリアできる時代はもう少し先ではないかしら。絵本も児童書も、古典も流行りものもあるから、これはたいへんだわ。
読了日:01月09日 著者:福井県立図書館
 最近、地球が暑くてクマってます。 シロクマが教えてくれた温暖化時代を幸せに生き抜く方法の感想
最近、地球が暑くてクマってます。 シロクマが教えてくれた温暖化時代を幸せに生き抜く方法の感想動物を擬人化した趣向が好きでないのだけれど、読んでみると会社に置いておきたくなった。監修がしっかりしていて、メインの文章で浅く読むことも、「熊の巻」で深く知ることもできる。軽く手に取ってもらえそうだ。強調しているのは、温暖化対策は個々人の我慢に依存するものではなく、国を動かすアクションをこそ起こすべきである点だ。なぜなら二酸化炭素排出の4割を石油・石炭による発電等が占めており、個人の我慢など知れているからだ。だからといって原子力発電の増設はまっぴらごめん、なのであれば、しつこく意見表明しなければならない。
地球全体の二酸化炭素濃度は一次関数的に上昇し続けている。温暖化がガスの影響と言われ始めて以降、2020年に至るまで、である。つい最近まで懐疑派だった私につべこべ言う資格は無いのだけれど、この温暖化はもう止まらないのではないか、臨界点は既に越えつつあるのではないかという感覚が拭えない。しかしそれは無根拠な感覚的なものであって、論理的ではない。無責任と反省した。目の前の現象を平易な目で見守り、確かな分析を追わなければならない。
シロクマは、温暖化が進めばどのみち生きていくことはできない。種を守るために動物園のシロクマに生きてもらわなければなんて悪い冗談だ。
読了日:01月08日 著者:水野敬也,長沼直樹
 You are what you read あなたは読んだものに他ならないの感想
You are what you read あなたは読んだものに他ならないの感想理屈ぽくて皮肉屋で真面目で、近くにいたら面倒くさそうな服部文祥が、読むほどになんだか愛すべきキャラに思えてきたのだ。極限状態の中に、服部文祥は生きることの謎を解く鍵を探す。自らの極限体験では飽き足らず、他人の極限である状況と言葉を覗き見て、本質に触れたい欲求はわかるように思う。答えは一向に得られないけれど。『自然界で起こったことは信じる信じないではなく、受け入れるか受け入れないかだ。セメントに囲まれて暮らしている我々が、動物の奥深い能力や自然のありようにまで、人間の常識を当てはめるべきではない』は至言だ。
昨年末は特に年賀状の支度をしたくなくて、ずるずると今日に至り、ええ歳こいて年始早々に不義理をした。本の中で服部文祥が、登山に行ったら事故で帰ってこないかもしれない、それを思うので登山の予定を挟んだちょっと先の約束すら嫌だったというようなことを書いていて、思い当たった。ああ、私は去年、人や猫の生き死ににたくさん出会って、今このときのことで手一杯な日々を乗り越えてこなして、見知らぬ来年のことなどもう考えたくなかったのだと。年賀状は自分にも相手にも「今年」がある前提の遣り取りで、その儚さが辛かったのだ。
読了日:01月07日 著者:服部文祥
注:
 は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。 2022年01月06日
2021年の総括
2021年、読んだ本の冊数は185冊。
購入費用239,230円。
積読本301冊(うちKindle本136冊、Honto本14冊)。
もはや使命のように、本を買い込み続けている。
去年はまた書籍代の最高額を更新した。
積読本の棚はこうなった。

本は、買ったからといって読み切れなくても良いと思う。
真剣に向きあわなければならないのは、それが我が身の丈に合っているかどうかである。
…正直なところ、合っていない。
量をこなそうと読み飛ばして深みを損なうのであれば、本末転倒だ。
今年のお題は「You are what you read」にした。
あなたは読んだものに他ならない。服部文祥の本の表題からもらった。
関心が増え、また深まれば、読みたい本は増えて当然である。
それが自分に何らかの意味を与える本だと思ったなら、見合う深度で読みたい。
2022年も良い本に出会えますように。

2021年、私に影響を与えた本たち。
読書メーターのページはこちら。
<知らないことはまだまだたくさんあるのだなあ>
 逝きし世の面影 (平凡社ライブラリー) 渡辺 京二
逝きし世の面影 (平凡社ライブラリー) 渡辺 京二
 中国はここにある 梁 鴻
中国はここにある 梁 鴻
 ニホンオオカミの最後 狼酒・狼狩り・狼祭りの発見 遠藤 公男
ニホンオオカミの最後 狼酒・狼狩り・狼祭りの発見 遠藤 公男
 逆転の大中国史 ユーラシアの視点から 楊 海英
逆転の大中国史 ユーラシアの視点から 楊 海英
 その犬の名を誰も知らない (ShoPro Books) 嘉悦 洋
その犬の名を誰も知らない (ShoPro Books) 嘉悦 洋
 先祖返りの国へ 日本の身体‐文化を読み解く エバレット ブラウン,エンゾ早川
先祖返りの国へ 日本の身体‐文化を読み解く エバレット ブラウン,エンゾ早川
<知識があれば暮らしはより深くなる>
 RANGE(レンジ)知識の「幅」が最強の武器になる デイビッド・エプスタイン
RANGE(レンジ)知識の「幅」が最強の武器になる デイビッド・エプスタイン
 症例から学ぶ和漢診療学 寺澤 捷年
症例から学ぶ和漢診療学 寺澤 捷年
 決定版 犬・猫に効くツボ・マッサージ 指圧と漢方でみるみる元気になる シェリル・シュワルツ
決定版 犬・猫に効くツボ・マッサージ 指圧と漢方でみるみる元気になる シェリル・シュワルツ
 無農薬で安心・ラクラク はじめての手づくりオーガニック・ガーデン (PHPビジュアル実用BOOKS) 曳地 トシ,曳地 義治
無農薬で安心・ラクラク はじめての手づくりオーガニック・ガーデン (PHPビジュアル実用BOOKS) 曳地 トシ,曳地 義治
<遠からず来る未来>
 ブルシット・ジョブ――クソどうでもいい仕事の理論 デヴィッド・グレーバー
ブルシット・ジョブ――クソどうでもいい仕事の理論 デヴィッド・グレーバー
 本当に君は総理大臣になれないのか (講談社現代新書) 小川 淳也,中原 一歩
本当に君は総理大臣になれないのか (講談社現代新書) 小川 淳也,中原 一歩
 いまこそ税と社会保障の話をしよう! 井手 英策
いまこそ税と社会保障の話をしよう! 井手 英策
 富士山噴火と南海トラフ 海が揺さぶる陸のマグマ (ブルーバックス) 鎌田 浩毅
富士山噴火と南海トラフ 海が揺さぶる陸のマグマ (ブルーバックス) 鎌田 浩毅
 老いた家 衰えぬ街 住まいを終活する (講談社現代新書) 野澤 千絵
老いた家 衰えぬ街 住まいを終活する (講談社現代新書) 野澤 千絵
<面白い小説にたくさん出会った>
 神無き月十番目の夜 (小学館文庫) 飯嶋 和一
神無き月十番目の夜 (小学館文庫) 飯嶋 和一
 同志少女よ、敵を撃て 逢坂 冬馬
同志少女よ、敵を撃て 逢坂 冬馬
 曾根崎心中 角田 光代,近松 門左衛門
曾根崎心中 角田 光代,近松 門左衛門
 地べたを旅立つ 掃除機探偵の推理と冒険 そえだ 信
地べたを旅立つ 掃除機探偵の推理と冒険 そえだ 信
購入費用239,230円。
積読本301冊(うちKindle本136冊、Honto本14冊)。
もはや使命のように、本を買い込み続けている。
去年はまた書籍代の最高額を更新した。
積読本の棚はこうなった。

本は、買ったからといって読み切れなくても良いと思う。
真剣に向きあわなければならないのは、それが我が身の丈に合っているかどうかである。
…正直なところ、合っていない。
量をこなそうと読み飛ばして深みを損なうのであれば、本末転倒だ。
今年のお題は「You are what you read」にした。
あなたは読んだものに他ならない。服部文祥の本の表題からもらった。
関心が増え、また深まれば、読みたい本は増えて当然である。
それが自分に何らかの意味を与える本だと思ったなら、見合う深度で読みたい。
2022年も良い本に出会えますように。

2021年、私に影響を与えた本たち。
読書メーターのページはこちら。
<知らないことはまだまだたくさんあるのだなあ>
 逝きし世の面影 (平凡社ライブラリー) 渡辺 京二
逝きし世の面影 (平凡社ライブラリー) 渡辺 京二 中国はここにある 梁 鴻
中国はここにある 梁 鴻 ニホンオオカミの最後 狼酒・狼狩り・狼祭りの発見 遠藤 公男
ニホンオオカミの最後 狼酒・狼狩り・狼祭りの発見 遠藤 公男 逆転の大中国史 ユーラシアの視点から 楊 海英
逆転の大中国史 ユーラシアの視点から 楊 海英 その犬の名を誰も知らない (ShoPro Books) 嘉悦 洋
その犬の名を誰も知らない (ShoPro Books) 嘉悦 洋 先祖返りの国へ 日本の身体‐文化を読み解く エバレット ブラウン,エンゾ早川
先祖返りの国へ 日本の身体‐文化を読み解く エバレット ブラウン,エンゾ早川<知識があれば暮らしはより深くなる>
 RANGE(レンジ)知識の「幅」が最強の武器になる デイビッド・エプスタイン
RANGE(レンジ)知識の「幅」が最強の武器になる デイビッド・エプスタイン 症例から学ぶ和漢診療学 寺澤 捷年
症例から学ぶ和漢診療学 寺澤 捷年 決定版 犬・猫に効くツボ・マッサージ 指圧と漢方でみるみる元気になる シェリル・シュワルツ
決定版 犬・猫に効くツボ・マッサージ 指圧と漢方でみるみる元気になる シェリル・シュワルツ 無農薬で安心・ラクラク はじめての手づくりオーガニック・ガーデン (PHPビジュアル実用BOOKS) 曳地 トシ,曳地 義治
無農薬で安心・ラクラク はじめての手づくりオーガニック・ガーデン (PHPビジュアル実用BOOKS) 曳地 トシ,曳地 義治<遠からず来る未来>
 ブルシット・ジョブ――クソどうでもいい仕事の理論 デヴィッド・グレーバー
ブルシット・ジョブ――クソどうでもいい仕事の理論 デヴィッド・グレーバー 本当に君は総理大臣になれないのか (講談社現代新書) 小川 淳也,中原 一歩
本当に君は総理大臣になれないのか (講談社現代新書) 小川 淳也,中原 一歩 いまこそ税と社会保障の話をしよう! 井手 英策
いまこそ税と社会保障の話をしよう! 井手 英策 富士山噴火と南海トラフ 海が揺さぶる陸のマグマ (ブルーバックス) 鎌田 浩毅
富士山噴火と南海トラフ 海が揺さぶる陸のマグマ (ブルーバックス) 鎌田 浩毅 老いた家 衰えぬ街 住まいを終活する (講談社現代新書) 野澤 千絵
老いた家 衰えぬ街 住まいを終活する (講談社現代新書) 野澤 千絵<面白い小説にたくさん出会った>
 神無き月十番目の夜 (小学館文庫) 飯嶋 和一
神無き月十番目の夜 (小学館文庫) 飯嶋 和一 同志少女よ、敵を撃て 逢坂 冬馬
同志少女よ、敵を撃て 逢坂 冬馬 曾根崎心中 角田 光代,近松 門左衛門
曾根崎心中 角田 光代,近松 門左衛門 地べたを旅立つ 掃除機探偵の推理と冒険 そえだ 信
地べたを旅立つ 掃除機探偵の推理と冒険 そえだ 信2022年01月05日
2021年12月の記録
積読は一気に加速して300冊の大台を突破した。
半分は電子書籍になった。
電子書籍の市場が熟成しつつあるということなのか、明らかにセールが増えた。
年末などモグラたたきのようで大変だった。財布が。
新刊では考えられないような値段で"本"が手元に転がり込んでくるので、情報の獲得に怠りないよう毎日PC画面を眺め渡している。
装丁が素敵な本や、電子で読んで手元に置きたいものは本で買い直すが、電子市場が活性化すればするほど本の印刷や装丁にかかるコストは逆に増し、贅沢品になってゆくのだろう。
<今月のデータ>
購入32冊、購入費用36,849円。
読了12冊。
積読本301冊(うちKindle本136冊、Honto本14冊)。

12月の読書メーター
読んだ本の数:12
 エレファントム 象はなぜ遠い記憶を語るのかの感想
エレファントム 象はなぜ遠い記憶を語るのかの感想
海に臨む象の姿が心に残る。地位ある者も貧しき者も欧米人も現地人も、皆して象を狩った長い時代の果てに南アフリカの今がある。著者はローレンツに教えを乞う機会を得ながら拒み、デズモンド・モリスに師事して動物行動学を学んだ。象を"自然の生んだ大天使"と呼ぶ。その歴史や生態を追ったのは、著者が幼い頃出会った白い象と!カンマの記憶があったからだ。象は遊び、おどけ、怒り、超低周波音や足音を使ってはるか遠くの象と意思疎通する。象のことを理解したいならこちらをお勧めしたい。人間の知らないことはまだまだあるに違いないから。
当然、ワトソン氏も動物園という施設には懐疑的だったが、動物行動学者としてヨハネスブルグ動物園の勤務を引き受けた。そこにいたデライラは、初対面のワトソン氏に食べ物より友情を求め、檻の中で先に逝った同族を悼む儀式を行ない、ライオンとワトソン氏の間に立ちはだかって全身で威嚇する姿を見せる。象の世界の深さを、おおかたの人間は理解どころか、未だ知ってすらいないのだ。現代の動物園は、当時より進化しているだろうか。それとも、現代の動物園の象は、象から象へ伝わる智を受け継ぐ術もなく孤立し、鬱々と過ごしているのだろうか。
読了日:12月28日 著者:ライアル・ワトソン
 歌おう、感電するほどの喜びを!〔新版〕 (ハヤカワ文庫 SF フ 16-8)の感想
歌おう、感電するほどの喜びを!〔新版〕 (ハヤカワ文庫 SF フ 16-8)の感想
ブラッドベリのことは、これからは「SF作家」じゃなくて「稀代のストーリーテラー」と呼ぼう。これらの短編小説は全てがSFではない。しかしどれも冒頭でぐっと掴まれ、どこへ連れていかれるのかとわくわくするものばかりだ。『その穴から、機械油がゆっくりとしたたり落ちる』。たった1文で見える世界が転換する鮮やかさといったらたまらない。短編集にありがちなこととして、私はいつかこの本を読んだことを失念して再度手に取るかもしれない。そうしたらもう一度最初から楽しむことができる。それはもはや祝福されるべき事態だと思うのだ。
読了日:12月27日 著者:レイ・ブラッドベリ
 逃北 つかれたときは北へ逃げます (文春文庫 の 16-6)の感想
逃北 つかれたときは北へ逃げます (文春文庫 の 16-6)の感想
どこかさびれた場所、観光客の行かない地元民だけの場所、両親や祖母のゆかりの場所。能町さんの逃げる先はいつも北という。私も、北は好きだ。というより、皮膚のすぐ外側を冷えた空気が吹き去っていくその身一つ感、孤独感が落ち着く。南のように、身の内にこもったものが外へ溶け出ていくことなく、自分の中で処理することを強いる、ストイックさを気に入っている。地球の北端に人が暮らす景色を、私も見てみたい。北海道の人が北海道を愛するように、グリーンランドの人はなぜグリーンランドを愛して暮らせないのだろう。あんなに美しいのに…。
読了日:12月25日 著者:能町 みね子
](https://m.media-amazon.com/images/I/51IK6P-CdqL._SL120_.jpg) 週刊東洋経済 2021年9/4特大号[雑誌](すごいベンチャー100 2021年最新版)の感想
週刊東洋経済 2021年9/4特大号[雑誌](すごいベンチャー100 2021年最新版)の感想
「すごいベンチャー100」特集。いつの間にやら日本のスタートアップ企業の資金調達も、ベンチャーキャピタルや事業会社による投資が大部分を占めるようになり、何億もの資本金を集める企業も散見される。日本にもスタートアップの波が来ていると言えるのだろうか? 海外との比較記事を探してみたい。分野も多岐にわたるが、紹介されているのはデジタルや先端技術を使った技術革新が経済成長や社会貢献につながるというものが多い。経済誌なのでそこが強調されている可能性も想定しておく。トレンドは以前ソーシャルゲーム、今SaaSとのこと。
ある人のある着想が企業の形になり、耳目を集め、資金を集め、人を雇い、動き始める。会社が生まれ、育ち、変異し、あるいは別の流れに合流し、あるいは消えていく、有機的なうねり。それがここに取材されただけでもこんなにあるなんて、眩暈がしそうになった。日本のどこかで起きた動きが、現代ではインターネットを通じて素早く詳しく、私みたいな一般人でも知ることができる、そんな時代なのだなあ。
読了日:12月24日 著者:

季刊環境ビジネス2022年冬号の感想
至上命題は「環境・社会問題に対応しつつ、事業を成長させる」である。SDG'sを謳った新しい産業=飯のタネ探しに総がかりで血眼だ。WWFのCOP26についての寄稿も弱い。ほんとうに社会のためになる選択の手掛かりを探して、上滑りしがちな目をなだめながら読んだ。電気の自家消費はいずれ必須になるだろう。洋上風力発電が注目を集めているが、国がぶち上げたとおりに成功するとは思えない。発電場所と使用場所の距離がどんどん遠くなる。特集では東京水産振興会長谷理事の寄稿が現状と展望に堂々と釘を刺していて少しだけすっきりした。
読了日:12月21日 著者:
 国家を考えてみよう (ちくまプリマー新書)の感想
国家を考えてみよう (ちくまプリマー新書)の感想
『民主主義国家で、「政治って、どこかで関係ない誰かがやってるんでしょ?」というような声が平気で出て来たら、それはもう衆愚政治です』。国民の国家とは何か。国家主義は何が違うか。若者を念頭において、部活などわかりやすい例えで説く。この国をなんとかしなければならない焦燥感。批判するために論じるのではない。おおもとを理解して、自ずと非に気づき、曲げさせないためだ。末尾に自民党の憲法改正草案に触れる。憲法は権力者を縛って国民を守るものであって、権力者を守って国民を縛るのは憲法ではない。『国家は我々国民のものである』
初めには言葉遊びのように古今東西の「国」を表わす言葉を挙げていく。国の土台が領土か人間かが如実に現れているとは、面白いなあ。国とか藩とか、身分によって見えているものが違うのは外国も似た部分があるようには思うけど。政と暮らしの乖離が日本人のメンタリティに深く影響しているという指摘が興味深い。国の頂点に天皇を頂いたときから綿々と、土地所有や支配の構図にはズレがあり、日本人の「国」に対する感覚は「国家」と結びついていない。自分たちが主体となって国家を動かすということがピンとこない理由、そういうことなのかなと。
読了日:12月21日 著者:橋本 治
 クレイジーで行こう! グーグルとスタンフォードが認めた男、「水道管」に挑むの感想
クレイジーで行こう! グーグルとスタンフォードが認めた男、「水道管」に挑むの感想
米国でスタートアップ(=ベンチャー企業)を立ち上げた日本人の奮闘記。同じ"ビジネス"でも受け継いだものと新しく立ち上げるものでは全然違う。なにしろ軍資金が元手にある訳ではなく、顧客との契約を成立させるまでは収入ゼロ、製品づくりも営業活動も、給与も家賃も、投資家から集めた借金からのスタートなのだ。考えただけでひりひりする。氏は事業を磨く作業をルービックキューブに例える。ビジネスの方向性が社会の需要に沿っていて、「光るものがあれば使ってみよう」と考える顧客がいて、企業が伸びていける、そんな社会であってほしい。
読了日:12月08日 著者:加藤 崇
 同志少女よ、敵を撃ての感想
同志少女よ、敵を撃ての感想
評判に違わぬ読みごたえ。第二次世界大戦、ソ連の対ドイツ戦線という、日本人には取っつきにくい設定にもかかわらず、現代にも続く普遍的な視点も織り込まれ、読ませる。近しい者も故郷も失ったら、私は死にたいと思う。しかしその瞬間の衝動を逃したら、惰性で生きてしまうのかもしれない。そのうちに後ろ向きなそれを前向きに反転させる怒りや恨み、復讐心を抱いたら、誰かを"守りたい"と思い始めたら、私でも武器を取るのかもしれない。人を敵と呼び、殺すことをも正当化するのかもしれない。非常時、そこには、想像するほど段差は無いのかも。
ジェンダーや慰安婦の問題、民族問題、ソ連から東欧・中央アジアにかけての地政学も、まったく現代に繋がった深いテーマだ。折しも、ロシアがウクライナに侵攻するのではなど報道されている。この文献の多さ、読み捨てのエンタメにはもったいない骨太感だった。いや、すごいもの読みました。今ならアレクシエーヴィッチ「戦争は女の顔をしていない」読めるかもしれん。
読了日:12月06日 著者:逢坂 冬馬
 猫の學校: 猫と人の快適生活レッスン (ポプラ新書)の感想
猫の學校: 猫と人の快適生活レッスン (ポプラ新書)の感想
猫がふたりして旅立ってのち、残されたひとりの戸惑いと寂しさは生半可でなく、人間へのもっと一緒にいて!もっと撫でて!の要求が叫びのようになってきた。これはお互い良くないと、腹を括り、新たに猫を迎えることにした。とはいえ、仔猫を迎えるのは13年ぶり。復習のために再読。家の中に猫が1匹か複数かでの違いについての章が、実感として迫る。複数頭いるとくっついて寝たり遊んだりできる以外に、健康面、精神面でも利点が多い。単独だと人間との間に共依存めいた関係が生じるので、やはり複数の関係をつくったほうが良いのだと納得した。
読了日:12月04日 著者:南里 秀子
 渦巻ける烏の群の感想
渦巻ける烏の群の感想
シベリアに駐留する日本軍の話。軍隊の論理、男の論理で動く兵営から少しでも逃れようと、男たちはささやかな食べ物を手土産に携えて、それぞれにロシア人の家に上がり込む。欲しかったのは刺激や性欲が満たされる情事ではなくて家庭の温かさだった、とは、冷えきった地に出征した経験者ならではの実感だろう。中隊は約200人と聞く。表題の意味が察せられた時、白と黒の強烈なコントラストが脳内に想像せられて慄然とする。小豆島に生まれ、また生を終えた作家とは恥ずかしながら知らなかった。青空文庫ではなくまとまった文庫で読んでみたい。
読了日:12月03日 著者:黒島 伝治
 小豆島
小豆島
読了日:12月02日 著者:黒島 伝治
 ねこのふしぎ話の感想
ねこのふしぎ話の感想
描かれたのは昭和。人と猫の距離感って、いつの時代もこんな感じなんやろなあ。いるのが当たり前の日々。ちょっとうっとうしい日もある。でも笑えるわけでもない、泣けるわけでもない、ほんの小さなエピソードがとても大事で。でも言葉にしたらやっぱりあまりに些細で、他人には届かなくて。『こんなに 問いかけてくる瞳の奥が 空っぽなわけがないよね』。逝った猫への消えることのない追慕の気持ちも、その気配が家の中に現れるのを心待ちにする気持ちも、この著者なら当たり前のことのように「わかるわ」と言ってくれそうな気がした。
読了日:12月02日 著者:やまだ 紫
注: は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。
半分は電子書籍になった。
電子書籍の市場が熟成しつつあるということなのか、明らかにセールが増えた。
年末などモグラたたきのようで大変だった。財布が。
新刊では考えられないような値段で"本"が手元に転がり込んでくるので、情報の獲得に怠りないよう毎日PC画面を眺め渡している。
装丁が素敵な本や、電子で読んで手元に置きたいものは本で買い直すが、電子市場が活性化すればするほど本の印刷や装丁にかかるコストは逆に増し、贅沢品になってゆくのだろう。
<今月のデータ>
購入32冊、購入費用36,849円。
読了12冊。
積読本301冊(うちKindle本136冊、Honto本14冊)。

12月の読書メーター
読んだ本の数:12
 エレファントム 象はなぜ遠い記憶を語るのかの感想
エレファントム 象はなぜ遠い記憶を語るのかの感想海に臨む象の姿が心に残る。地位ある者も貧しき者も欧米人も現地人も、皆して象を狩った長い時代の果てに南アフリカの今がある。著者はローレンツに教えを乞う機会を得ながら拒み、デズモンド・モリスに師事して動物行動学を学んだ。象を"自然の生んだ大天使"と呼ぶ。その歴史や生態を追ったのは、著者が幼い頃出会った白い象と!カンマの記憶があったからだ。象は遊び、おどけ、怒り、超低周波音や足音を使ってはるか遠くの象と意思疎通する。象のことを理解したいならこちらをお勧めしたい。人間の知らないことはまだまだあるに違いないから。
当然、ワトソン氏も動物園という施設には懐疑的だったが、動物行動学者としてヨハネスブルグ動物園の勤務を引き受けた。そこにいたデライラは、初対面のワトソン氏に食べ物より友情を求め、檻の中で先に逝った同族を悼む儀式を行ない、ライオンとワトソン氏の間に立ちはだかって全身で威嚇する姿を見せる。象の世界の深さを、おおかたの人間は理解どころか、未だ知ってすらいないのだ。現代の動物園は、当時より進化しているだろうか。それとも、現代の動物園の象は、象から象へ伝わる智を受け継ぐ術もなく孤立し、鬱々と過ごしているのだろうか。
読了日:12月28日 著者:ライアル・ワトソン
 歌おう、感電するほどの喜びを!〔新版〕 (ハヤカワ文庫 SF フ 16-8)の感想
歌おう、感電するほどの喜びを!〔新版〕 (ハヤカワ文庫 SF フ 16-8)の感想ブラッドベリのことは、これからは「SF作家」じゃなくて「稀代のストーリーテラー」と呼ぼう。これらの短編小説は全てがSFではない。しかしどれも冒頭でぐっと掴まれ、どこへ連れていかれるのかとわくわくするものばかりだ。『その穴から、機械油がゆっくりとしたたり落ちる』。たった1文で見える世界が転換する鮮やかさといったらたまらない。短編集にありがちなこととして、私はいつかこの本を読んだことを失念して再度手に取るかもしれない。そうしたらもう一度最初から楽しむことができる。それはもはや祝福されるべき事態だと思うのだ。
読了日:12月27日 著者:レイ・ブラッドベリ

 逃北 つかれたときは北へ逃げます (文春文庫 の 16-6)の感想
逃北 つかれたときは北へ逃げます (文春文庫 の 16-6)の感想どこかさびれた場所、観光客の行かない地元民だけの場所、両親や祖母のゆかりの場所。能町さんの逃げる先はいつも北という。私も、北は好きだ。というより、皮膚のすぐ外側を冷えた空気が吹き去っていくその身一つ感、孤独感が落ち着く。南のように、身の内にこもったものが外へ溶け出ていくことなく、自分の中で処理することを強いる、ストイックさを気に入っている。地球の北端に人が暮らす景色を、私も見てみたい。北海道の人が北海道を愛するように、グリーンランドの人はなぜグリーンランドを愛して暮らせないのだろう。あんなに美しいのに…。
読了日:12月25日 著者:能町 みね子

](https://m.media-amazon.com/images/I/51IK6P-CdqL._SL120_.jpg) 週刊東洋経済 2021年9/4特大号[雑誌](すごいベンチャー100 2021年最新版)の感想
週刊東洋経済 2021年9/4特大号[雑誌](すごいベンチャー100 2021年最新版)の感想「すごいベンチャー100」特集。いつの間にやら日本のスタートアップ企業の資金調達も、ベンチャーキャピタルや事業会社による投資が大部分を占めるようになり、何億もの資本金を集める企業も散見される。日本にもスタートアップの波が来ていると言えるのだろうか? 海外との比較記事を探してみたい。分野も多岐にわたるが、紹介されているのはデジタルや先端技術を使った技術革新が経済成長や社会貢献につながるというものが多い。経済誌なのでそこが強調されている可能性も想定しておく。トレンドは以前ソーシャルゲーム、今SaaSとのこと。
ある人のある着想が企業の形になり、耳目を集め、資金を集め、人を雇い、動き始める。会社が生まれ、育ち、変異し、あるいは別の流れに合流し、あるいは消えていく、有機的なうねり。それがここに取材されただけでもこんなにあるなんて、眩暈がしそうになった。日本のどこかで起きた動きが、現代ではインターネットを通じて素早く詳しく、私みたいな一般人でも知ることができる、そんな時代なのだなあ。
読了日:12月24日 著者:

季刊環境ビジネス2022年冬号の感想
至上命題は「環境・社会問題に対応しつつ、事業を成長させる」である。SDG'sを謳った新しい産業=飯のタネ探しに総がかりで血眼だ。WWFのCOP26についての寄稿も弱い。ほんとうに社会のためになる選択の手掛かりを探して、上滑りしがちな目をなだめながら読んだ。電気の自家消費はいずれ必須になるだろう。洋上風力発電が注目を集めているが、国がぶち上げたとおりに成功するとは思えない。発電場所と使用場所の距離がどんどん遠くなる。特集では東京水産振興会長谷理事の寄稿が現状と展望に堂々と釘を刺していて少しだけすっきりした。
読了日:12月21日 著者:
 国家を考えてみよう (ちくまプリマー新書)の感想
国家を考えてみよう (ちくまプリマー新書)の感想『民主主義国家で、「政治って、どこかで関係ない誰かがやってるんでしょ?」というような声が平気で出て来たら、それはもう衆愚政治です』。国民の国家とは何か。国家主義は何が違うか。若者を念頭において、部活などわかりやすい例えで説く。この国をなんとかしなければならない焦燥感。批判するために論じるのではない。おおもとを理解して、自ずと非に気づき、曲げさせないためだ。末尾に自民党の憲法改正草案に触れる。憲法は権力者を縛って国民を守るものであって、権力者を守って国民を縛るのは憲法ではない。『国家は我々国民のものである』
初めには言葉遊びのように古今東西の「国」を表わす言葉を挙げていく。国の土台が領土か人間かが如実に現れているとは、面白いなあ。国とか藩とか、身分によって見えているものが違うのは外国も似た部分があるようには思うけど。政と暮らしの乖離が日本人のメンタリティに深く影響しているという指摘が興味深い。国の頂点に天皇を頂いたときから綿々と、土地所有や支配の構図にはズレがあり、日本人の「国」に対する感覚は「国家」と結びついていない。自分たちが主体となって国家を動かすということがピンとこない理由、そういうことなのかなと。
読了日:12月21日 著者:橋本 治

 クレイジーで行こう! グーグルとスタンフォードが認めた男、「水道管」に挑むの感想
クレイジーで行こう! グーグルとスタンフォードが認めた男、「水道管」に挑むの感想米国でスタートアップ(=ベンチャー企業)を立ち上げた日本人の奮闘記。同じ"ビジネス"でも受け継いだものと新しく立ち上げるものでは全然違う。なにしろ軍資金が元手にある訳ではなく、顧客との契約を成立させるまでは収入ゼロ、製品づくりも営業活動も、給与も家賃も、投資家から集めた借金からのスタートなのだ。考えただけでひりひりする。氏は事業を磨く作業をルービックキューブに例える。ビジネスの方向性が社会の需要に沿っていて、「光るものがあれば使ってみよう」と考える顧客がいて、企業が伸びていける、そんな社会であってほしい。
読了日:12月08日 著者:加藤 崇

 同志少女よ、敵を撃ての感想
同志少女よ、敵を撃ての感想評判に違わぬ読みごたえ。第二次世界大戦、ソ連の対ドイツ戦線という、日本人には取っつきにくい設定にもかかわらず、現代にも続く普遍的な視点も織り込まれ、読ませる。近しい者も故郷も失ったら、私は死にたいと思う。しかしその瞬間の衝動を逃したら、惰性で生きてしまうのかもしれない。そのうちに後ろ向きなそれを前向きに反転させる怒りや恨み、復讐心を抱いたら、誰かを"守りたい"と思い始めたら、私でも武器を取るのかもしれない。人を敵と呼び、殺すことをも正当化するのかもしれない。非常時、そこには、想像するほど段差は無いのかも。
ジェンダーや慰安婦の問題、民族問題、ソ連から東欧・中央アジアにかけての地政学も、まったく現代に繋がった深いテーマだ。折しも、ロシアがウクライナに侵攻するのではなど報道されている。この文献の多さ、読み捨てのエンタメにはもったいない骨太感だった。いや、すごいもの読みました。今ならアレクシエーヴィッチ「戦争は女の顔をしていない」読めるかもしれん。
読了日:12月06日 著者:逢坂 冬馬

 猫の學校: 猫と人の快適生活レッスン (ポプラ新書)の感想
猫の學校: 猫と人の快適生活レッスン (ポプラ新書)の感想猫がふたりして旅立ってのち、残されたひとりの戸惑いと寂しさは生半可でなく、人間へのもっと一緒にいて!もっと撫でて!の要求が叫びのようになってきた。これはお互い良くないと、腹を括り、新たに猫を迎えることにした。とはいえ、仔猫を迎えるのは13年ぶり。復習のために再読。家の中に猫が1匹か複数かでの違いについての章が、実感として迫る。複数頭いるとくっついて寝たり遊んだりできる以外に、健康面、精神面でも利点が多い。単独だと人間との間に共依存めいた関係が生じるので、やはり複数の関係をつくったほうが良いのだと納得した。
読了日:12月04日 著者:南里 秀子
 渦巻ける烏の群の感想
渦巻ける烏の群の感想シベリアに駐留する日本軍の話。軍隊の論理、男の論理で動く兵営から少しでも逃れようと、男たちはささやかな食べ物を手土産に携えて、それぞれにロシア人の家に上がり込む。欲しかったのは刺激や性欲が満たされる情事ではなくて家庭の温かさだった、とは、冷えきった地に出征した経験者ならではの実感だろう。中隊は約200人と聞く。表題の意味が察せられた時、白と黒の強烈なコントラストが脳内に想像せられて慄然とする。小豆島に生まれ、また生を終えた作家とは恥ずかしながら知らなかった。青空文庫ではなくまとまった文庫で読んでみたい。
読了日:12月03日 著者:黒島 伝治

 小豆島
小豆島読了日:12月02日 著者:黒島 伝治

 ねこのふしぎ話の感想
ねこのふしぎ話の感想描かれたのは昭和。人と猫の距離感って、いつの時代もこんな感じなんやろなあ。いるのが当たり前の日々。ちょっとうっとうしい日もある。でも笑えるわけでもない、泣けるわけでもない、ほんの小さなエピソードがとても大事で。でも言葉にしたらやっぱりあまりに些細で、他人には届かなくて。『こんなに 問いかけてくる瞳の奥が 空っぽなわけがないよね』。逝った猫への消えることのない追慕の気持ちも、その気配が家の中に現れるのを心待ちにする気持ちも、この著者なら当たり前のことのように「わかるわ」と言ってくれそうな気がした。
読了日:12月02日 著者:やまだ 紫
注:
 は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。 2021年12月02日
2021年11月の記録
積読本は300冊の大台が見えてきた。
誰かが言っていたとおり、これら積んだ本全てを読み切る日は、私の人生には来ないだろう。
読みたいと思った本は、機会あらば買っておく。
そして読みたいと思ったタイミングで、読む。
その追いかけっこ人生を、これからずっと営んでいくのだなあ。
<今月のデータ>
購入28冊、購入費用26,710円。
読了16冊。
積読本280冊(うちKindle本118冊、Honto本14冊)。

11月の読書メーター
読んだ本の数:16
 無農薬で安心・ラクラク はじめての手づくりオーガニック・ガーデン (PHPビジュアル実用BOOKS)の感想
無農薬で安心・ラクラク はじめての手づくりオーガニック・ガーデン (PHPビジュアル実用BOOKS)の感想
賃貸に住んで知った。高層階では、ホームセンターで買った土を入れたプランターには草が生えない。虫も蜂も来ない。植えたものがただ大きくなるだけで、芽の出たサツマイモを置いたら軒下の水不足で枯れて後、そのままミイラ化した。いつまで経っても腐らない。私が曳地メソッドの庭に惹かれるのは、樹木と草花があって虫がいて鳥がいて、雑草もすべてが生き生きと共存し循環しているから。庭の維持には大変な労働を伴うだろう。それでも、その繁茂する力に私は焦がれるのだ。この本は木の剪定や雨水タンクにも触れていて、全体が見える感じ。
読了日:11月30日 著者:曳地 トシ,曳地 義治
 滅びの園 (幽BOOKS)の感想
滅びの園 (幽BOOKS)の感想
言っても詮無いことだけれど。なぜ人はそういうふうに生きていくことができないのだろう。誰が誠一を責められようか。確かに想念の異界は、ご都合主義的に金銭的物質的束縛から逃れている。しかし今この世界が生きづらいのは、それだけのせいだろうか。目の前に生きやすい世界があったら、そこで生きたいと願うのは駄目ですか。差し置いて人類全体とやらを考えなきゃ駄目ですか。突入者が異形に見えるのはなぜですか。希望をどこかに見出さなければ生きていけないなら、空に自然に、人と人とのやり取りに。邪なものは白い海に全て呑まれてしまえ。
戦争、テロ、感染症、未知の生物。それらに立ち向かう個々の意志は尊い。自分のことだけじゃない、身近な他者を想う利他が発揮されるから。なのにその母集団がでかくなって一つの到達点を目指すと、強権的な、因果をはき違えた、歪なものになる。AIによる司令という設定が象徴的だ。確かに目的達成のために遠回りや揺らぎはないだろう。それで人類みな幸せになったか。有機物のスープであったかつての地球。プーニーは地球リセットの仕掛けではなかったかと想像したり。ならば《未知なるもの》はノアの箱舟だったか。恒川マジックにやられた。
読了日:11月28日 著者:恒川 光太郎
 人事の組み立て~脱日本型雇用のトリセツ~欧米のモノマネをしようとして全く違うものになり続けた日本の人事制度の感想
人事の組み立て~脱日本型雇用のトリセツ~欧米のモノマネをしようとして全く違うものになり続けた日本の人事制度の感想
熱くて理解の進む人事本。私は日本型雇用制度が悪いとは思っていない。むしろ、日米欧の制度を客観視することで、中途半端に輸入した概念を切り分けて、日本の中小企業に最適化したシステムを見通せないかという読みは当たった。わかりやすい。職能vs職務の理解と、企業の持つ性質によるキャリアのタイプ分けで、ずいぶんすっきりした。大企業を念頭におく解説だが、零細企業にもじゅうぶん解釈流用可能だ。年功序列万歳。この考え方があれば、世間の流行りメソッドに振り回される無駄は無くなるだろう。役所の押し付けに惑わされる無駄もまた。
「役職の階段を上がらない正規」は働き方の多様化に向けての一つの解だろう。まあ、零細企業ではそれほど理詰めでなくてもそんな感じになってしまうのだけれど、これを意識化かつ容認する意味は大きいと思う。かつ若くても給料を上げられる、いやむしろ若いうちに給料を上げて生活を設計できる給与体系に変えていくつもりだ。言葉を借りれば『若者に階段を上がらせると、企業が自ずから儲かる』システムづくり。それにはボトムアップ期間と内容、定昇の上限の見定めが重要になってくる。そうすると、どんな年功カーブになるだろうか?
読了日:11月27日 著者:海老原 嗣生
 ちいさな王子 (光文社古典新訳文庫)の感想
ちいさな王子 (光文社古典新訳文庫)の感想
「坊ちゃん」と並んで、私の"どうしても読み終えることができない本"だった「星の王子さま」。光文社古典新薬文庫の甘すぎない翻訳に助けられて、存外にさらりと読み終えてしまった。こういう結末だったのですね。初めて読むなら、中学生の頃かしら。持てる純粋さもすり減ってから読んだのでは、物語に深く潜ろうとするエネルギー量が足りなかったのだと知った。つべこべ解釈もしないほうがいい。『ヒツジは花を食べたか、食べなかったか?』。ふと見上げる夜空に、見えないなにかを探る。そういう存在なのかなと、想像してみたことでした。
読了日:11月27日 著者:サン=テグジュペリ
 泣くなら、ひとり 壇蜜日記3 (文春文庫 た 92-3)の感想
泣くなら、ひとり 壇蜜日記3 (文春文庫 た 92-3)の感想
もはや自虐芸と呼びたい自虐ぶり。とはいえ、前巻まで全体に漂っていた悲壮感は薄らいでいるように感じられ、歳を重ねて不利になりつつあるはずの業界で、それすら切り返してみせる余裕が出たようにも思える。彼女が何によって稼いでいるかより、短くても情景をありありと想像させる言葉選びの感覚が好きだから、つい読む。今回も切れが良い。初めて短編小説が入った。エッセイと同じトーン、ただ自身の中核にあるものへの自己分析がより剥きだしになっていて、どきりとした。巻末は自筆のあとがき。言葉への感度と文字の整い方は相関しないものか。
読了日:11月26日 著者:壇 蜜
 やけに植物に詳しい僕の街のスキマ植物図鑑の感想
やけに植物に詳しい僕の街のスキマ植物図鑑の感想
雑草は人の生活の近くで生きている。というよりは、人の生活の近くで生きるから、これらの植物は「雑草」という不名誉な称号を得たのだ。カラスがスカベンジャーぶりを発揮して嫌われるのと似ているか。あえて厳しい条件の場所で生きることを選んだがゆえに、個性的な生態が人目につく。その場の環境に応じて姿を変えるのを「可塑性」というそうだ。同じ種でも見た目が変わるって、不思議。そしてたくましいなあ。雑草にまつわる本を読むたび、その生存戦略の妙に感心してはもっと憶えたいと思うのだけれど、読んだ冊数のわりに、はかが行かない。
読了日:11月25日 著者:瀬尾 一樹
 残したい日本の手仕事 (Discover Japan Books)の感想
残したい日本の手仕事 (Discover Japan Books)の感想
手仕事の写真を眺めて惚れ惚れするのはもちろん、文章の読みどころも多くて、それぞれの物語の深さに感じ入る。本来はある地域において生活や生業からくる需要があって、身近に手に入る素材によって、用途に合わせたかたちで、「つくる」と「つかう」の循環が成り立っていたものが、需給が崩れたために手仕事そのものが消えていっている。カゴやザル、箕。編組品と括ると知る。無くすには惜しいそれらを繋ぎたい。でもどう使っていいかわからない。かといって家の装飾として飾るのは違うと思う。理解を深めた今をきっかけに、一歩踏み込みたい。
章立ては「○○さんの箕」のように、つくる人があって、その美しい手仕事を紹介するという流れになっている。しかし2015年までの連載の、6年前には既に職人が高齢で、途絶えかけていた手仕事たちは今どうなっているだろうか。国内を旅するたび、店で見かける工芸品は、土地によってその需要や植生が違う以上、素材や形、編み方も違っていたはずなのだ。それを、ああカゴだね、器だねと余りにざっくりした目でしか見ていなかった自分を恥じる。同時に、自分の地元の手仕事の持つ良さをもっとじっくり見たいとも思った。
読了日:11月23日 著者:久野 恵一
 ブックセラーズ・ダイアリー:スコットランド最大の古書店の一年の感想
ブックセラーズ・ダイアリー:スコットランド最大の古書店の一年の感想
書評で知り、店で手に取る。やや厚いので電子本で出ていないか逡巡しつつページをめくると、イーベイで買ったキンドルをショットガンで撃ち抜いた記述に行き当たった。これは電子本は無いなと察し、買って読んだ。その後、撃ち抜いたキンドルは店の壁に掛けられた。この店主が憎むべきは電子本そのものではなく、古書に価値が無いと決めつけ、僅かでも安く本を手に入れようとする客のさもしさや、出品する古本屋を買い叩くアマゾンのビジネスモデルではないか。持ち込んだ本のほとんどが「価値無し」で買い取られんけん、電子本で回避しよんやんか。
『これは奇妙な現象なのだが、うちの店に初めて来たお客さんは、禁じられた領域に立ち入ったと誰かに叱られるのを恐れているみたいに、おずおず歩くことが多い』。私も教養のない有象無象の一人なので、街の古書店(言わずもがな、ブックオフではない)にはいつもアンビバレントな思いを抱いて入る。思いがけない良書との出会いへの期待と、お前にここにある本の価値がわかるかと問われているような畏怖と。そういう客の心の機微がこの店主にはわからないものかな? お客や本を売ろうとしている人を見下す感じ、私も知り合いの古書店主にいるいる。
読了日:11月21日 著者:ショーン・バイセル
 山と溪谷 田部重治選集 (ヤマケイ文庫)の感想
山と溪谷 田部重治選集 (ヤマケイ文庫)の感想
『交通が今日ほど便利でなくて、山の地図が今日よりも不完全であったころ』の登山が最も楽しかったと懐古する。時代は明治から大正。無論、登山道も整備などされておらず、土地の猟師が足跡を幽かに残すだけ。目の前にどのような光景が現れるかわからない楽しみ、山に入れば自由を感じ、何か足りなくてもなんとかなると思える心持ちが清々しい。私が里山歩きを好きなのは、現代では逆に里山の方が手入れが届かず、判断力を試されてわくわくするからかもしれない。一日に50km余も歩けるのは草鞋のおかげ、靴では無理とのこと。草鞋履いてみたい。
読了日:11月19日 著者:田部重治
 神無き月十番目の夜 (小学館文庫)の感想
神無き月十番目の夜 (小学館文庫)の感想
これほど引き込まれると判っていたら長く積まなかった。どこにでもありそうな集落の、このような惨い結末は何故かと、新しい事実が明るみに出た端から別の謎が浮かぶ。そして希望が削がれては、あぁ、と嘆息した。守ろうとしただけなのに。秀でた頭目がいなければ、良い自治は成らない。集落に住む者が絶えれば、伝統も信仰も繋がらない。しかし一人の思惑は、他の思惑と反発し、混じり、総意として集落を丸ごと巻き込んでゆく。御田が残ったとて、集落に人を呼んだとて、元どおりにはならない。藤九郎と新月の影。余りに余りに惜しいと思う。
「重い年貢に苦しむ農民」のイメージは、江戸初期、徳川の直轄地におけるものだったと別の本で読んだ。新しい配下への褒賞のため、幕府は各領地に年貢を確保する必要があった。一方、あえて年貢を緩く認められていた地では、徳川配下に下り、ただの米生産マシーンに成り下がることは、生きる糧の搾取であると同時に、土地柄に合うよう練られた伝統や信仰、自治の仕組みの破壊でもあっただろう。取立てが厳しいほど、集落は人の心の豊かさやおおらかさも失う。それでも生き、江戸末期には再び豊かな郷土をつくり上げていた、人間は凄いなと思う。
読了日:11月17日 著者:飯嶋 和一
 ぼくはお金を使わずに生きることにしたの感想
ぼくはお金を使わずに生きることにしたの感想
1年間、お金を使わず、かつ受け取らない生活をする。現代社会の歪みはお金に起因するとし、生活から排除すべきと著者は考えている。フリーエコノミー運動は極端だ。ここまでは無理でも、先進国の人々が皆、幾分かずつ生活をこの方向へ寄せれば、CO2排出量削減などは他愛ない話なのだけど。強要されることなく、ただ自分のために、ただ生きるために、身体を働かせる暮らし。それは時間がかかることだけれど、この上ない達成感であり、余剰を恵みとして満喫することができる。そういうの、幸せって呼ぶのだと思うよ。羨ましいと感じる自分がいる。
物を無償で必要な人に渡し合う仕組み。生きていく上での必要スキルを無料で教え合う仕組み。こういう仕組みが日本には少ない、と思ったけれど、ジモティーのように無料でも使えるものも無いわけではないし、平日なら安価な講習会みたいなのもあるし、もっとローカルな、草の根的には探せばあるのだろうな。フリーエコノミーは必需を安価に済ませるという意味ではない。DIYや手芸も生活を自分で何とかするという意味合いは同じでも、趣味的に、必需でない材料やキットをそのために買わなければならないのでは、フリーエコノミーに反してすらいる。
読了日:11月11日 著者:マーク ボイル
 チェンジング・ブルー――気候変動の謎に迫る (岩波現代文庫)の感想
チェンジング・ブルー――気候変動の謎に迫る (岩波現代文庫)の感想
氷期から間氷期に気候がシフトした際に、CO2濃度が200から280ppmに増加していた事実について、研究者は『大気中の二酸化炭素やメタンの濃度の変動は、気候変動の「原因」ではなく、気候変動にともなって地球環境中の炭素のサイクルが変化したことによる「結果」だと考えている』という。ではなぜ、現在のCO2濃度が産業革命前より135ppm増加したことが全て人為だとして、それが気候変動の原因と断定するのか。CO2濃度増減と気温の高低は比例関係にあるのか。食らいつくように読んだが、どうにも消化できないのでもう諦める。
おそらく成毛氏の解説が全てなのだろう。『過去一〇〇年間に人類が放出した温室効果ガスが、地球温暖化を引き起こしていると、われわれが証明できないという事実は、さして重要なことではない。むしろ、赤外線を吸収するガスを大気に加えることにより、われわれの気候に対してロシアン・ルーレット5で遊んでいること自体が問題なのだ』。実質的に原油の生産量≒使用量が過去最高である事実を見れば、自ら決めた目標すら達成しそうにない。逆に、"新エネルギーへの転換"という御旗のもと、これまでにも増してエネルギーを消費しているからだ。
読了日:11月10日 著者:大河内 直彦
 火星に住むつもりです ~二酸化炭素が地球を救うの感想
火星に住むつもりです ~二酸化炭素が地球を救うの感想
『二酸化炭素は可能性の塊』。CO2の研究に携わる著者は、ずっと温暖化解決と火星移住のことを考えているという。どうやら本気だ。CO2を直接空気回収するための装置「ひやっしー」を開発、さらに回収したCO2を燃料化して運用することを目指している。ゆるふわな装丁に反し、著者の熱量と成果に圧倒される。CO2分子が赤外線を地球外に放出させない原理「共振」をさらりと説明している。CO2は他の気体より『総合的に考えて』影響力が大きいから、CO2を名指しして排出量を削減するべきと考えるのが、現代のコンセンサスなのだな。
「ひやっしー」は既に家庭・オフィス向けに提供されている。特にSDGs圧の掛かる企業には訴求力のあるアイテムだ。「ひやっしー」が拡販されることは「ひやっしー」の能力を高め、研究を推進し、ついには科学技術の発展に資するだろう。ただ、企業にとってそれがグリーンウォッシュにならないかが気にかかる。それを言えば大抵の取組みはグリーンウォッシュなんだけどね。それで温暖化が止められるとは考えづらい。コロナ禍で人間の移動が抑制されたはずなのに、なぜCO2排出量が増えているのか。根本を解決することはもうできないのだろうか。
あと私が理解しきれないのは、よくある「それはもともと空気中にあったCO2だから±ゼロ」という考え方だ。そのCO2は別のプロセスでも計算に入れられていないか。過程で運搬や製造、廃棄処理に係るCO2は計算に入っているのか。机上の空論にならないことを願う。
読了日:11月05日 著者:村木 風海
 薬膳サラダごはんの感想
薬膳サラダごはんの感想
野菜でも豆でもスープにしてしまえば美味しいし温まるしで私は大好きなのだけど、夫はそうではないらしく生に近いサラダを欲しがる。熱で失われる栄養素や、体内の熱を冷ます役割を、本能が求めているのかもと推測したり。ならば薬膳サラダ、一石二鳥ではないですか。ベースとなるシンプルな献立に、プラスアルファの食材(効能)を足せるようになっている。五性、五味、帰経の説明や効能もさらりと書き込まれており、食材の効能覚えるのしんどいわと思っていた私にはちょうどよかった。豆類や木の実、香草などの乾物類は補助に重宝。常備すること。
読了日:11月05日 著者:植木 もも子
 人体模型の夜 (集英社文庫)の感想
人体模型の夜 (集英社文庫)の感想
短編を集めて一体にまとまる趣向。らもさんがまともなホラーなんて珍しい、と読み進めると、じわじわと言いようのない後味の物語になっていく。ホラーとは人の外にある怪異を人が怖がるものと定義できるだろうか。だとするとこれは、それが人の内側に取り込まれてゆく過程と言い換えることができる。身の内に巣くう異形。目、耳、胃袋、膝と人体模型を照らし合わせていくと、パーツが足りないことに気づいてしまう。取り込まれてはいけない。これはきっとらもさんの企みなのだ。「骨喰う調べ」が想像をどーんと越えてきて好き。どんな調べだよそれ。
読了日:11月05日 著者:中島 らも
 逝きし世の面影 (平凡社ライブラリー)の感想
逝きし世の面影 (平凡社ライブラリー)の感想
江戸の気配色濃く残る明治の日本を、多くの外国人が書き残している。近代化以前の辺境国の独特の在りようが、西洋産業文明の流入に伴って喪われる確信あればこそ、外国人は哀惜した。資本主義の進行に伴う西洋人の心の荒廃と相対したゆえに日本人の美徳が目立って見えた点を除いても、貧しくとも悲惨ではない暮らし、底抜けな陽気さと旺盛な好奇心、余分を求めないがために発揮された創意工夫や手工芸の技術は、稀有な到達点だったのだ。現代の私たちは既に西洋人の論理で過去を見、とかく言う。日本礼賛や懐古でなく、別の物差しを取り戻せないか。
大陸生まれの著者にとって、祖国日本は異国であったという。私にとっては故郷、しかしなにもかも江戸から様変わりしてしまった故郷だ。社会装置としての江戸は滅ぶべくして滅んだ。多くの伝統文化は形骸化した。しかし、明治に捨て去られた有形無形の痕跡は、実は江戸から細々とつながって、意味を変えることなく現代に垣間見ることができるのではないかと私は思う。江戸。様々の愛おしいことやものたちのルーツ。私も見てみたかった。復古は無理でも、拾い出して知り、できることなら暮らしに取り入れてみる。それは豊かな生き方ではないだろうか。
ビジネス論としても座右の書としたいくらい、目から鱗だった。近代化以前の日本では、労働は『貨幣化され商品化された苦役』ではなかった。眉間にしわ寄せて効率化を争うような生活ではなかった。自身が働きたいときに、働きたいように働く日々だった。『主体的な生命活動としての労働』を尊重してこそ、皆が陽気に機嫌よく、技能を発揮できた。労働がよろこびであればこそ、創意工夫も生まれる。これは現代の生活にも実は片鱗を見て取れるのではないだろうか。つまり、「機嫌のよい会社」が伸びる論である。それはまだ可能なのではないだろうか。
読了日:11月01日 著者:渡辺 京二
注: は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。
誰かが言っていたとおり、これら積んだ本全てを読み切る日は、私の人生には来ないだろう。
読みたいと思った本は、機会あらば買っておく。
そして読みたいと思ったタイミングで、読む。
その追いかけっこ人生を、これからずっと営んでいくのだなあ。
<今月のデータ>
購入28冊、購入費用26,710円。
読了16冊。
積読本280冊(うちKindle本118冊、Honto本14冊)。

11月の読書メーター
読んだ本の数:16
 無農薬で安心・ラクラク はじめての手づくりオーガニック・ガーデン (PHPビジュアル実用BOOKS)の感想
無農薬で安心・ラクラク はじめての手づくりオーガニック・ガーデン (PHPビジュアル実用BOOKS)の感想賃貸に住んで知った。高層階では、ホームセンターで買った土を入れたプランターには草が生えない。虫も蜂も来ない。植えたものがただ大きくなるだけで、芽の出たサツマイモを置いたら軒下の水不足で枯れて後、そのままミイラ化した。いつまで経っても腐らない。私が曳地メソッドの庭に惹かれるのは、樹木と草花があって虫がいて鳥がいて、雑草もすべてが生き生きと共存し循環しているから。庭の維持には大変な労働を伴うだろう。それでも、その繁茂する力に私は焦がれるのだ。この本は木の剪定や雨水タンクにも触れていて、全体が見える感じ。
読了日:11月30日 著者:曳地 トシ,曳地 義治
 滅びの園 (幽BOOKS)の感想
滅びの園 (幽BOOKS)の感想言っても詮無いことだけれど。なぜ人はそういうふうに生きていくことができないのだろう。誰が誠一を責められようか。確かに想念の異界は、ご都合主義的に金銭的物質的束縛から逃れている。しかし今この世界が生きづらいのは、それだけのせいだろうか。目の前に生きやすい世界があったら、そこで生きたいと願うのは駄目ですか。差し置いて人類全体とやらを考えなきゃ駄目ですか。突入者が異形に見えるのはなぜですか。希望をどこかに見出さなければ生きていけないなら、空に自然に、人と人とのやり取りに。邪なものは白い海に全て呑まれてしまえ。
戦争、テロ、感染症、未知の生物。それらに立ち向かう個々の意志は尊い。自分のことだけじゃない、身近な他者を想う利他が発揮されるから。なのにその母集団がでかくなって一つの到達点を目指すと、強権的な、因果をはき違えた、歪なものになる。AIによる司令という設定が象徴的だ。確かに目的達成のために遠回りや揺らぎはないだろう。それで人類みな幸せになったか。有機物のスープであったかつての地球。プーニーは地球リセットの仕掛けではなかったかと想像したり。ならば《未知なるもの》はノアの箱舟だったか。恒川マジックにやられた。
読了日:11月28日 著者:恒川 光太郎
 人事の組み立て~脱日本型雇用のトリセツ~欧米のモノマネをしようとして全く違うものになり続けた日本の人事制度の感想
人事の組み立て~脱日本型雇用のトリセツ~欧米のモノマネをしようとして全く違うものになり続けた日本の人事制度の感想熱くて理解の進む人事本。私は日本型雇用制度が悪いとは思っていない。むしろ、日米欧の制度を客観視することで、中途半端に輸入した概念を切り分けて、日本の中小企業に最適化したシステムを見通せないかという読みは当たった。わかりやすい。職能vs職務の理解と、企業の持つ性質によるキャリアのタイプ分けで、ずいぶんすっきりした。大企業を念頭におく解説だが、零細企業にもじゅうぶん解釈流用可能だ。年功序列万歳。この考え方があれば、世間の流行りメソッドに振り回される無駄は無くなるだろう。役所の押し付けに惑わされる無駄もまた。
「役職の階段を上がらない正規」は働き方の多様化に向けての一つの解だろう。まあ、零細企業ではそれほど理詰めでなくてもそんな感じになってしまうのだけれど、これを意識化かつ容認する意味は大きいと思う。かつ若くても給料を上げられる、いやむしろ若いうちに給料を上げて生活を設計できる給与体系に変えていくつもりだ。言葉を借りれば『若者に階段を上がらせると、企業が自ずから儲かる』システムづくり。それにはボトムアップ期間と内容、定昇の上限の見定めが重要になってくる。そうすると、どんな年功カーブになるだろうか?
読了日:11月27日 著者:海老原 嗣生
 ちいさな王子 (光文社古典新訳文庫)の感想
ちいさな王子 (光文社古典新訳文庫)の感想「坊ちゃん」と並んで、私の"どうしても読み終えることができない本"だった「星の王子さま」。光文社古典新薬文庫の甘すぎない翻訳に助けられて、存外にさらりと読み終えてしまった。こういう結末だったのですね。初めて読むなら、中学生の頃かしら。持てる純粋さもすり減ってから読んだのでは、物語に深く潜ろうとするエネルギー量が足りなかったのだと知った。つべこべ解釈もしないほうがいい。『ヒツジは花を食べたか、食べなかったか?』。ふと見上げる夜空に、見えないなにかを探る。そういう存在なのかなと、想像してみたことでした。
読了日:11月27日 著者:サン=テグジュペリ

 泣くなら、ひとり 壇蜜日記3 (文春文庫 た 92-3)の感想
泣くなら、ひとり 壇蜜日記3 (文春文庫 た 92-3)の感想もはや自虐芸と呼びたい自虐ぶり。とはいえ、前巻まで全体に漂っていた悲壮感は薄らいでいるように感じられ、歳を重ねて不利になりつつあるはずの業界で、それすら切り返してみせる余裕が出たようにも思える。彼女が何によって稼いでいるかより、短くても情景をありありと想像させる言葉選びの感覚が好きだから、つい読む。今回も切れが良い。初めて短編小説が入った。エッセイと同じトーン、ただ自身の中核にあるものへの自己分析がより剥きだしになっていて、どきりとした。巻末は自筆のあとがき。言葉への感度と文字の整い方は相関しないものか。
読了日:11月26日 著者:壇 蜜

 やけに植物に詳しい僕の街のスキマ植物図鑑の感想
やけに植物に詳しい僕の街のスキマ植物図鑑の感想雑草は人の生活の近くで生きている。というよりは、人の生活の近くで生きるから、これらの植物は「雑草」という不名誉な称号を得たのだ。カラスがスカベンジャーぶりを発揮して嫌われるのと似ているか。あえて厳しい条件の場所で生きることを選んだがゆえに、個性的な生態が人目につく。その場の環境に応じて姿を変えるのを「可塑性」というそうだ。同じ種でも見た目が変わるって、不思議。そしてたくましいなあ。雑草にまつわる本を読むたび、その生存戦略の妙に感心してはもっと憶えたいと思うのだけれど、読んだ冊数のわりに、はかが行かない。
読了日:11月25日 著者:瀬尾 一樹
 残したい日本の手仕事 (Discover Japan Books)の感想
残したい日本の手仕事 (Discover Japan Books)の感想手仕事の写真を眺めて惚れ惚れするのはもちろん、文章の読みどころも多くて、それぞれの物語の深さに感じ入る。本来はある地域において生活や生業からくる需要があって、身近に手に入る素材によって、用途に合わせたかたちで、「つくる」と「つかう」の循環が成り立っていたものが、需給が崩れたために手仕事そのものが消えていっている。カゴやザル、箕。編組品と括ると知る。無くすには惜しいそれらを繋ぎたい。でもどう使っていいかわからない。かといって家の装飾として飾るのは違うと思う。理解を深めた今をきっかけに、一歩踏み込みたい。
章立ては「○○さんの箕」のように、つくる人があって、その美しい手仕事を紹介するという流れになっている。しかし2015年までの連載の、6年前には既に職人が高齢で、途絶えかけていた手仕事たちは今どうなっているだろうか。国内を旅するたび、店で見かける工芸品は、土地によってその需要や植生が違う以上、素材や形、編み方も違っていたはずなのだ。それを、ああカゴだね、器だねと余りにざっくりした目でしか見ていなかった自分を恥じる。同時に、自分の地元の手仕事の持つ良さをもっとじっくり見たいとも思った。
読了日:11月23日 著者:久野 恵一
 ブックセラーズ・ダイアリー:スコットランド最大の古書店の一年の感想
ブックセラーズ・ダイアリー:スコットランド最大の古書店の一年の感想書評で知り、店で手に取る。やや厚いので電子本で出ていないか逡巡しつつページをめくると、イーベイで買ったキンドルをショットガンで撃ち抜いた記述に行き当たった。これは電子本は無いなと察し、買って読んだ。その後、撃ち抜いたキンドルは店の壁に掛けられた。この店主が憎むべきは電子本そのものではなく、古書に価値が無いと決めつけ、僅かでも安く本を手に入れようとする客のさもしさや、出品する古本屋を買い叩くアマゾンのビジネスモデルではないか。持ち込んだ本のほとんどが「価値無し」で買い取られんけん、電子本で回避しよんやんか。
『これは奇妙な現象なのだが、うちの店に初めて来たお客さんは、禁じられた領域に立ち入ったと誰かに叱られるのを恐れているみたいに、おずおず歩くことが多い』。私も教養のない有象無象の一人なので、街の古書店(言わずもがな、ブックオフではない)にはいつもアンビバレントな思いを抱いて入る。思いがけない良書との出会いへの期待と、お前にここにある本の価値がわかるかと問われているような畏怖と。そういう客の心の機微がこの店主にはわからないものかな? お客や本を売ろうとしている人を見下す感じ、私も知り合いの古書店主にいるいる。
読了日:11月21日 著者:ショーン・バイセル
 山と溪谷 田部重治選集 (ヤマケイ文庫)の感想
山と溪谷 田部重治選集 (ヤマケイ文庫)の感想『交通が今日ほど便利でなくて、山の地図が今日よりも不完全であったころ』の登山が最も楽しかったと懐古する。時代は明治から大正。無論、登山道も整備などされておらず、土地の猟師が足跡を幽かに残すだけ。目の前にどのような光景が現れるかわからない楽しみ、山に入れば自由を感じ、何か足りなくてもなんとかなると思える心持ちが清々しい。私が里山歩きを好きなのは、現代では逆に里山の方が手入れが届かず、判断力を試されてわくわくするからかもしれない。一日に50km余も歩けるのは草鞋のおかげ、靴では無理とのこと。草鞋履いてみたい。
読了日:11月19日 著者:田部重治

 神無き月十番目の夜 (小学館文庫)の感想
神無き月十番目の夜 (小学館文庫)の感想これほど引き込まれると判っていたら長く積まなかった。どこにでもありそうな集落の、このような惨い結末は何故かと、新しい事実が明るみに出た端から別の謎が浮かぶ。そして希望が削がれては、あぁ、と嘆息した。守ろうとしただけなのに。秀でた頭目がいなければ、良い自治は成らない。集落に住む者が絶えれば、伝統も信仰も繋がらない。しかし一人の思惑は、他の思惑と反発し、混じり、総意として集落を丸ごと巻き込んでゆく。御田が残ったとて、集落に人を呼んだとて、元どおりにはならない。藤九郎と新月の影。余りに余りに惜しいと思う。
「重い年貢に苦しむ農民」のイメージは、江戸初期、徳川の直轄地におけるものだったと別の本で読んだ。新しい配下への褒賞のため、幕府は各領地に年貢を確保する必要があった。一方、あえて年貢を緩く認められていた地では、徳川配下に下り、ただの米生産マシーンに成り下がることは、生きる糧の搾取であると同時に、土地柄に合うよう練られた伝統や信仰、自治の仕組みの破壊でもあっただろう。取立てが厳しいほど、集落は人の心の豊かさやおおらかさも失う。それでも生き、江戸末期には再び豊かな郷土をつくり上げていた、人間は凄いなと思う。
読了日:11月17日 著者:飯嶋 和一

 ぼくはお金を使わずに生きることにしたの感想
ぼくはお金を使わずに生きることにしたの感想1年間、お金を使わず、かつ受け取らない生活をする。現代社会の歪みはお金に起因するとし、生活から排除すべきと著者は考えている。フリーエコノミー運動は極端だ。ここまでは無理でも、先進国の人々が皆、幾分かずつ生活をこの方向へ寄せれば、CO2排出量削減などは他愛ない話なのだけど。強要されることなく、ただ自分のために、ただ生きるために、身体を働かせる暮らし。それは時間がかかることだけれど、この上ない達成感であり、余剰を恵みとして満喫することができる。そういうの、幸せって呼ぶのだと思うよ。羨ましいと感じる自分がいる。
物を無償で必要な人に渡し合う仕組み。生きていく上での必要スキルを無料で教え合う仕組み。こういう仕組みが日本には少ない、と思ったけれど、ジモティーのように無料でも使えるものも無いわけではないし、平日なら安価な講習会みたいなのもあるし、もっとローカルな、草の根的には探せばあるのだろうな。フリーエコノミーは必需を安価に済ませるという意味ではない。DIYや手芸も生活を自分で何とかするという意味合いは同じでも、趣味的に、必需でない材料やキットをそのために買わなければならないのでは、フリーエコノミーに反してすらいる。
読了日:11月11日 著者:マーク ボイル

 チェンジング・ブルー――気候変動の謎に迫る (岩波現代文庫)の感想
チェンジング・ブルー――気候変動の謎に迫る (岩波現代文庫)の感想氷期から間氷期に気候がシフトした際に、CO2濃度が200から280ppmに増加していた事実について、研究者は『大気中の二酸化炭素やメタンの濃度の変動は、気候変動の「原因」ではなく、気候変動にともなって地球環境中の炭素のサイクルが変化したことによる「結果」だと考えている』という。ではなぜ、現在のCO2濃度が産業革命前より135ppm増加したことが全て人為だとして、それが気候変動の原因と断定するのか。CO2濃度増減と気温の高低は比例関係にあるのか。食らいつくように読んだが、どうにも消化できないのでもう諦める。
おそらく成毛氏の解説が全てなのだろう。『過去一〇〇年間に人類が放出した温室効果ガスが、地球温暖化を引き起こしていると、われわれが証明できないという事実は、さして重要なことではない。むしろ、赤外線を吸収するガスを大気に加えることにより、われわれの気候に対してロシアン・ルーレット5で遊んでいること自体が問題なのだ』。実質的に原油の生産量≒使用量が過去最高である事実を見れば、自ら決めた目標すら達成しそうにない。逆に、"新エネルギーへの転換"という御旗のもと、これまでにも増してエネルギーを消費しているからだ。
読了日:11月10日 著者:大河内 直彦

 火星に住むつもりです ~二酸化炭素が地球を救うの感想
火星に住むつもりです ~二酸化炭素が地球を救うの感想『二酸化炭素は可能性の塊』。CO2の研究に携わる著者は、ずっと温暖化解決と火星移住のことを考えているという。どうやら本気だ。CO2を直接空気回収するための装置「ひやっしー」を開発、さらに回収したCO2を燃料化して運用することを目指している。ゆるふわな装丁に反し、著者の熱量と成果に圧倒される。CO2分子が赤外線を地球外に放出させない原理「共振」をさらりと説明している。CO2は他の気体より『総合的に考えて』影響力が大きいから、CO2を名指しして排出量を削減するべきと考えるのが、現代のコンセンサスなのだな。
「ひやっしー」は既に家庭・オフィス向けに提供されている。特にSDGs圧の掛かる企業には訴求力のあるアイテムだ。「ひやっしー」が拡販されることは「ひやっしー」の能力を高め、研究を推進し、ついには科学技術の発展に資するだろう。ただ、企業にとってそれがグリーンウォッシュにならないかが気にかかる。それを言えば大抵の取組みはグリーンウォッシュなんだけどね。それで温暖化が止められるとは考えづらい。コロナ禍で人間の移動が抑制されたはずなのに、なぜCO2排出量が増えているのか。根本を解決することはもうできないのだろうか。
あと私が理解しきれないのは、よくある「それはもともと空気中にあったCO2だから±ゼロ」という考え方だ。そのCO2は別のプロセスでも計算に入れられていないか。過程で運搬や製造、廃棄処理に係るCO2は計算に入っているのか。机上の空論にならないことを願う。
読了日:11月05日 著者:村木 風海
 薬膳サラダごはんの感想
薬膳サラダごはんの感想野菜でも豆でもスープにしてしまえば美味しいし温まるしで私は大好きなのだけど、夫はそうではないらしく生に近いサラダを欲しがる。熱で失われる栄養素や、体内の熱を冷ます役割を、本能が求めているのかもと推測したり。ならば薬膳サラダ、一石二鳥ではないですか。ベースとなるシンプルな献立に、プラスアルファの食材(効能)を足せるようになっている。五性、五味、帰経の説明や効能もさらりと書き込まれており、食材の効能覚えるのしんどいわと思っていた私にはちょうどよかった。豆類や木の実、香草などの乾物類は補助に重宝。常備すること。
読了日:11月05日 著者:植木 もも子
 人体模型の夜 (集英社文庫)の感想
人体模型の夜 (集英社文庫)の感想短編を集めて一体にまとまる趣向。らもさんがまともなホラーなんて珍しい、と読み進めると、じわじわと言いようのない後味の物語になっていく。ホラーとは人の外にある怪異を人が怖がるものと定義できるだろうか。だとするとこれは、それが人の内側に取り込まれてゆく過程と言い換えることができる。身の内に巣くう異形。目、耳、胃袋、膝と人体模型を照らし合わせていくと、パーツが足りないことに気づいてしまう。取り込まれてはいけない。これはきっとらもさんの企みなのだ。「骨喰う調べ」が想像をどーんと越えてきて好き。どんな調べだよそれ。
読了日:11月05日 著者:中島 らも

 逝きし世の面影 (平凡社ライブラリー)の感想
逝きし世の面影 (平凡社ライブラリー)の感想江戸の気配色濃く残る明治の日本を、多くの外国人が書き残している。近代化以前の辺境国の独特の在りようが、西洋産業文明の流入に伴って喪われる確信あればこそ、外国人は哀惜した。資本主義の進行に伴う西洋人の心の荒廃と相対したゆえに日本人の美徳が目立って見えた点を除いても、貧しくとも悲惨ではない暮らし、底抜けな陽気さと旺盛な好奇心、余分を求めないがために発揮された創意工夫や手工芸の技術は、稀有な到達点だったのだ。現代の私たちは既に西洋人の論理で過去を見、とかく言う。日本礼賛や懐古でなく、別の物差しを取り戻せないか。
大陸生まれの著者にとって、祖国日本は異国であったという。私にとっては故郷、しかしなにもかも江戸から様変わりしてしまった故郷だ。社会装置としての江戸は滅ぶべくして滅んだ。多くの伝統文化は形骸化した。しかし、明治に捨て去られた有形無形の痕跡は、実は江戸から細々とつながって、意味を変えることなく現代に垣間見ることができるのではないかと私は思う。江戸。様々の愛おしいことやものたちのルーツ。私も見てみたかった。復古は無理でも、拾い出して知り、できることなら暮らしに取り入れてみる。それは豊かな生き方ではないだろうか。
ビジネス論としても座右の書としたいくらい、目から鱗だった。近代化以前の日本では、労働は『貨幣化され商品化された苦役』ではなかった。眉間にしわ寄せて効率化を争うような生活ではなかった。自身が働きたいときに、働きたいように働く日々だった。『主体的な生命活動としての労働』を尊重してこそ、皆が陽気に機嫌よく、技能を発揮できた。労働がよろこびであればこそ、創意工夫も生まれる。これは現代の生活にも実は片鱗を見て取れるのではないだろうか。つまり、「機嫌のよい会社」が伸びる論である。それはまだ可能なのではないだろうか。
読了日:11月01日 著者:渡辺 京二

注:
 は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。 2021年11月01日
2021年10月の記録
衆院選の投票を終えて一夜明け、惨憺たる結果を目の当たりにする。
日本はますます生きづらい国になるだろう。
そこに、私が得てきた知識も倫理も、絶望感を助長するばかりだ。
私は何のために本を読んでいるのだろうか。
<今月のデータ>
購入22冊、購入費用23,830円。
読了18冊。
積読本272冊(うちKindle本114冊、Honto本13冊)。

10月の読書メーター
読んだ本の数:18
 崩れ (講談社文庫)の感想
崩れ (講談社文庫)の感想
文さん72歳、52kg。執着したのは「崩れ」、なんと山崩れと暴れ川である。窮屈なズボンをはき、人に負ぶってもらってでも登り我が目で確かめるのだ。無意識のうちに心に貯めた『ものの種が芽に置きあがる時の力は、土を押し破るほど強い』。文さんの、炎が噴き出るような気性が発揮される。「木」が生命力の象徴であるのに対比し、山崩れは荒涼や麓の命を脅かす存在だ。恐怖に圧倒されながら、崩落の打当たって割れる落石の真新しい断面の美をも瞬間に捉える。文さんの文章は、自身の感性を逃さず、豊かだ。大山の崩れを思い浮かべつつ読んだ。
読了日:10月28日 著者:幸田 文
 動物園は進化する (ちくまプリマー新書)の感想
動物園は進化する (ちくまプリマー新書)の感想
動物園でゾウを飼育展示するようになった当初は見世物だったのが、時代と共に動物を通じて自然のしくみを教える、種を保存するなど機能を変えてきた。体が大きいゆえに飼育係の安全問題は喫緊であり、動物福祉も言われる今、変わりつつあるという。しかし繁殖は上手くいっていない。繁殖するためにはゾウが自然体で生きられる環境が必要だ。なのに群れの構造が複雑なゾウの少数飼育やコンクリートと鉄の檻、夜に自由に歩いたり食べたりできないスケジュール、なにより他者の視線など、人間に置き換えれば当たり前のことが動物のことになると難しい。
『ゾウの自然な生活を参考にして、家族群をつくり繁殖させる。そのためには、日々進歩する科学に基づいた飼育方針のもと、古い飼育方法ではなく、ゾウに適した高度な生息環境を整え、これまで無視してきた動物の福祉に配慮する』。その志は尊い。だけれども。
私は動物園の動物を憐憫する子供だったので、そもそも動物園にゾウは必要かとの疑念が消せない。私たちも、飼育に関わる人たちも、ゾウやライオンやが動物園にいる前提で話をする。だけどリアルな映像や情報の溢れる現代に、日本全国に何百もの動物園と100頭余ものゾウをはじめとする大型動物は必要だろうか。環境破壊や密猟がなくならないから動物園で種の保存をという考え方に、私はぞっとする。動物の餌代など"維持コスト"を議論するくらいなら、どのみち"触れあい"とは無縁な動物たちの飼育は諦めようという方向にはならないのだろうか。
読了日:10月25日 著者:川口 幸男,アラン ルークロフト
 彼岸花が咲く島の感想
彼岸花が咲く島の感想
話し言葉だけではなく、地の文の言葉にも違和感が激しく、なかなか読み進まない。普段使っている母語の機微を、ごく無意識に使い分けていることに改めて気づかされる。芥川賞だから、日本語を"正しく"使っていないといけないという規則はないはずなのに、ならばなぜこの作品が選ばれたのかと神経を鋭くして読んでしまう自分は、嫌な奴だ。さて、拓慈。最も身近な、異なる存在。彼を怖いと感じるのはなぜなのだろう。男だから。無知ゆえの無邪気さをぶつけてくるから。決定的に共有できないものが立ちはだかるから。それは理不尽なことだろうか?
読了日:10月22日 著者:李 琴峰
![農家が教える 竹やぶ減らし 2021年 10 月号 [雑誌]: 現代農業 増刊](https://m.media-amazon.com/images/I/51pUqClFyEL._SL120_.jpg) 農家が教える 竹やぶ減らし 2021年 10 月号 [雑誌]: 現代農業 増刊の感想
農家が教える 竹やぶ減らし 2021年 10 月号 [雑誌]: 現代農業 増刊の感想
際限なく増殖する竹林と人の闘い。苦労されている人には申し訳ないけれど、自然との知恵比べみたいで面白かった。タケノコやメンマで食べて美味しいのも良し、竹チップに粉砕して発酵させ、堆肥化するのも良し。いや好い。専門誌で繰り返し特集されるほど繁殖力の強い竹に困らされても、私たちはまだまだ自分たちの生活に役立てることができるのだ。なかでも、高さ1mで切るだけという、竹の生態を逆手にとった根絶やし方法は、よくぞ見出したと感嘆する。竹やぶはたいてい里との境目でもあるので、イノシシ対策も兼ねた自然との格闘技みたいだな。
読了日:10月21日 著者:
 ヤマケイ新書 山を買うの感想
ヤマケイ新書 山を買うの感想
自分の山が欲しいと思っていた頃があって、それは新型コロナやソロキャンの流行より前からなのだけど、それは安易な衝動であろう、と戒めのために読んでみた。さすがヤマケイ。甘くない。ゆるくない。しかしやっぱり欲しくなってしまった。ここに出てくる人々が山を買い求めた目的は様々で、なかでも山を守ることに使命感を見出した人たちへの共感と共振は、固定資産税ぐらい何年でも払ったるわ!という気分にさせる。『荒れた山を美しい里山に戻しながら、楽しむ』。そうだそうだと乗り気になりかける私に、立ちはだかる数多の障害の解説が詳しい。
読了日:10月19日 著者:福崎 剛
 マイル81 わるい夢たちのバザールI (文春文庫 キ 2-61 わるい夢たちのバザール 1)の感想
マイル81 わるい夢たちのバザールI (文春文庫 キ 2-61 わるい夢たちのバザール 1)の感想
"カップ"と"取っ手"の湧いて出る泉が健在であることに感謝する。「UR」は以前、原語で読もうとしたことがある。キングの文体を非ネイティヴが読むなど無謀だったと改めて思った。キーボード付Kindleは懐かしく、キングが『ちび助マシン』にわくわくする気配が好ましい。パラドックス警察より怖いのは、文学の研究者にとっては専門の作家の知らない作品が続々出現する事態であり、私にとっては買えども未読の本が並んでいる現実ではないかな。『わしの名前ではない』。「砂丘」の結末は私も大好きだ。しゃれこうべのニヤニヤ笑い最高。
読了日:10月17日 著者:スティーヴン・キング
 西日本大震災に備えよ 日本列島大変動の時代 (PHP新書)の感想
西日本大震災に備えよ 日本列島大変動の時代 (PHP新書)の感想
3.11以降、日本列島は『「大地変動の時代」が始まってしまった』。2030年代に発生が予測されるM9級の南海トラフ巨大地震をはじめ、東日本に再度の大地震、それに誘発される直下型地震。これらの発生は地球科学の分野では既定路線だという。活動周期や地盤の沈下/隆起現象の解析などの具体的な根拠を読み、自分が生きているうちに必ず来ると知り、備えなければならないと思いつつも、正常性バイアスとは厄介なもので、困ったなあ、とただぼやいている。日本人古来のメンタリティなどに思いをはせている場合ではない。備えんか自分。
今の日本列島が置かれた状況は、9世紀の日本に似ているのだという。9世紀は一般人には遠すぎるが、地球科学者には直近。驚嘆。
読了日:10月16日 著者:鎌田 浩毅
 アメリカ人の4人に1人はトランプが大統領だと信じているの感想
アメリカ人の4人に1人はトランプが大統領だと信じているの感想
我が家は"あめしる"も欠かさず見る町山ファンなので、たいていの話題は町山さんから既に聞いたものだ。それにしても議事堂占拠は有り得ない事態だった。だからこそバイデン大統領の就任式が、オバマのとは違う意味で胸にずしりときたことを思い出した。さて、富豪たちの宇宙旅行合戦。ウィリアム王子の言うように、今やらないかんことはそれや無いやろ、である。全ての富豪に社会貢献の義務があるわけではない。だったら不労所得には重税をかけて社会に強制還元してもらわねば。Kindleを生んだ功績は多大なれど、ベゾスにはがっかりだ。
読了日:10月16日 著者:町山 智浩
 武漢日記:封鎖下60日の魂の記録の感想
武漢日記:封鎖下60日の魂の記録の感想
湖北省武漢市が突如封鎖された、新型コロナ発生ごく初期の60日間の記録。新型コロナの本質的な事象は既にここにある。あと1週間の我慢だ。ワクチンができるまでの我慢だ。初期のそんな心持が今となっては新鮮なほど、あれはほんの始まりでしかなかったと知れる。発生場所が中国であるという一点で、私たちの頭の中にはフィルターがかかった。特殊な国家だからと。この本を読んで感じたのは、著者も著者のまわりの人々も、信じているということ。民主主義ではなくとも、在る秩序。人々との紐帯。善なるものへの信頼。『法治社会』としての中国を。
『政治的公正』の名分のもとに、ネット検閲官によってWeb上の投稿が通告なく削除されるのはよくあることのようだ。それでも諦めず思うことを投稿し、削除を免れたものによって意思を表明し、人々と意思疎通する。削除されることがわかっていても、怒りを表明する。そういう形で、社会は正しくあることができると、信じているようだ。それでも、バルガス=リョサの著作が本屋の棚から消えたことを知り、彼がなにか発言をしたからではないかと推測し、気落ちしている。その先には何が残るのだろう。先日読んだSF、馬伯庸の「沈黙都市」を想う。
読了日:10月15日 著者:方方
 出版翻訳家なんてなるんじゃなかった日記の感想
出版翻訳家なんてなるんじゃなかった日記の感想
なぜこの時代に、出版社と翻訳家の契約が書面でなく口頭なのか。そもそもそこに問題があると思うが、それにしても印税カットも出版中止も、出版社の翻しようが酷いのなんの。著者のプライドゆえの災厄とは言いきれず、出版社の大小の問題とも判じきれず、こちらまで出版業界不信になりそう。私の支払った代金は正当に翻訳者に届いているのか。商業主義的と出版社を非難するのは簡単だが、出版不況と言われると、あのしっかりしたつくりの美しいものに正当な対価を払わない読者側の問題も絡む。これからは本を買うのに出版社も選ぶ時代かもしれない。
今年のノーベル文学賞を受賞したグルナ氏の著作は和訳されるのかどうか、翻訳本をつくるには時間がかかる。まず翻訳しなければどのような感触の作品か出版社にもわからないのが、翻訳本の事情のややこしいところだ。今頃、出版社が翻訳家に最短期間で訳せるかせっついているところかもしれない。売れるチャンスなのだから。だけど翻訳本は以前に比べますます売れないのだろう、有名作家の新刊小説でも、地方の書店は置いていないことが多いものなあ。出版物数がやたら多いのも問題だろうし。つい安い本の方を選んじゃうのも問題だろうし。難しい。
読了日:10月10日 著者:宮崎 伸治
 ゴッホのあしあと (幻冬舎文庫)の感想
ゴッホのあしあと (幻冬舎文庫)の感想
「たゆたえども沈まず」の副読本と謳ったエッセイ。「たゆたえども~」のどの部分が創作だったか明らかにされていて興味深い。中野京子さんが“爆発し続けた”と表現したゴッホの晩年5年間。その起爆剤はパリと浮世絵だった。ゴッホの絵の奥底にある彼の孤独を探り当て、対象として眺めるんじゃなくて手繰り寄せるような、そんな感受性があるから、原田マハは小説を書けるのだと思った。一方、林忠正が同胞のはずの日本人から国賊呼ばわりされた当人であると知る。私はこちらを手繰ってみたい。
読了日:10月09日 著者:原田マハ
 たゆたえども沈まず (幻冬舎文庫)の感想
たゆたえども沈まず (幻冬舎文庫)の感想
重吉、忠正、テオと登場し、フィンセントが現れて、役者は揃う。フィクションである日本人の、重吉にはテオの心情描写、忠正にはフィンセントの運命示唆が役割として割り振られ、それがしかも対比構造になっている。私は彼らの本当のところを知らないながら、上手いな、面白いなぁ、と思った。中野京子さんの本の続きで言うと、印象派の画家たちは、被写体の心情や立場に関心をもたなかったかもしれないけれど、自身の絵を描きたい情熱には真摯だった。日々食べるものにも事欠きながらも描くことをやめない、やめられない情熱なんて想像もつかない。
読了日:10月09日 著者:原田マハ
 聊斎志異の怪 (角川ソフィア文庫)の感想
聊斎志異の怪 (角川ソフィア文庫)の感想
17世紀中国のあやかし説話集。幽霊が賄賂を贈ったり嫉妬したり、取っ組み合いの喧嘩を始めたりと騒々しく人間臭い。性愛絡みの物語も多く、幽玄という美的感覚が中国にはないのかとぼやいてみるが、思い返せば日本の説話だって似たようなもの。説話は骨組であって、要は想像力の膨らませようか。現に巻末の芥川と太宰が翻案した作品から、原案に肉をつけると物語として違和感がないとわかる。これは彼らの膨らませ方が上手いこともあろうけれども、中国と日本の物語の構造もきっと似ているのだろう。「狐の嫁女」は映像にしたらさぞ美しかろうな。
『これはきみの心だ。きみの作文が下手なのは、きみの心の毛穴がふさがっていたためだから、いま、冥途にある千万の心の中からよいものを一つ選び出して、きみの心と取り替えたのだ。きみの心は取っておいて、不足した冥途の分を補充するのだ』。と閻魔王のとこの判官が主人公のイマイチな文才の改善に便宜を図ってくれる。なんとも人間の願望の透けて見えることよ。さらに奥さんの顔と性根も美しい人のそれと取り替えてくれるという「首のすげかえ」は至れり尽くせり。閻魔王のとこの判官さんは、そんなに退屈しとったのだろうか。
読了日:10月08日 著者:蒲 松齢
 印象派で「近代」を読む 光のモネから、ゴッホの闇へ (NHK出版新書)の感想
印象派で「近代」を読む 光のモネから、ゴッホの闇へ (NHK出版新書)の感想
印象派は『何が描かれているかより、どんなふうに描かれているか』を重視する代わり、悲惨も鬱屈も顧みることない、人の心の深みとは切り離された絵画だった。当時の庶民同様、西洋史の教養も無しに眺めていた私に、絵は背景を知って観るのが面白いと中野さんは教えてくれる。ただ楽しむための絵画にも時代背景はある。屋外で描くという行為自体がたいへんな変革だったとか、エッフェル塔は醜いと嫌われたとか、中でも踊り子や上流階級の妻やお針子や、その時代の人々、同時に画家自身の生き方が絵の中に現れていると新たに知って俄然楽しくなる。
読了日:10月07日 著者:中野 京子
 老いた家 衰えぬ街 住まいを終活する (講談社現代新書)の感想
老いた家 衰えぬ街 住まいを終活する (講談社現代新書)の感想
全国民を挙げての大ババ抜き大会である。人口が急減を始めるなか、それはもう既に始まっていて、たとえば20年後に処分できそうにない不動産を今買うなどもってのほかで、親や親族の不動産が転がり込んでくる可能性や、近隣が放棄物件で荒廃する可能性を考えれば、無縁でいられない人の方が多そうだ。個人ではどうしようもないケースも考えると、個人を厳罰化しても根本的な解決にはならず、マッチングにせよ近隣需要への橋渡しにせよ、譲渡推進にも早晩限界が出るのではないのかしら。法制面をはじめ、ババをババでなくする仕組みづくりが急務。
町を歩いていて明らかに空き家とわかる物件でも、様々な事情で放置/留置されている事情がある。所有者が施設に入ったなどはこの本にも書かれているが、不動産屋さんと話していると、親族や近隣住民との関係の都合で、堂々と売りに出すことができない様々の問題があるのだそうだ。かといって売れない実家、山林や原野="負動産"にかかる税金などの経費は年々かかり続け、ボディブローのように効いてくるのだから、持ち続けることにも無理がある。いやー、どうすんだこれ。
読了日:10月05日 著者:野澤 千絵
 猫と住まいの解剖図鑑の感想
猫と住まいの解剖図鑑の感想
我が家の猫は1匹になってしまったけれど、縁があるなら、また猫を迎えたい。で、猫ズに優しい家を妄想する。猫を優先にして家をつくるのは本末転倒で、人間のための家を設計する中で、猫にも優しい工夫をするべきという前提には同意する。脱走防止に引き戸をつけるなどもよいけれど、今はいろいろな商材が出ていて、爪とぎやキャットウォークはもちろん、壁の漆喰塗りや、窓を開けておくための格子もDIYできるという情報がためになった。和のしつらえも案外大丈夫と知る。障子や襖は貼り直せばよく、畳も爪とぎされそうで実は大丈夫らしい。
読了日:10月03日 著者:いしまるあきこ
 「男女格差後進国」の衝撃: 無意識のジェンダー・バイアスを克服する (小学館新書)の感想
「男女格差後進国」の衝撃: 無意識のジェンダー・バイアスを克服する (小学館新書)の感想
セミナーで紹介された本。以前「女性活躍」と言われると、もやっとした違和感が拭えなかった。余計な意味合いが含蓄されて感じた。ではなく「ジェンダー・ギャップの解消」なら、目的は明瞭で社会の目標として掲げてよいと思う。さて、性別に基づく無意識の決めつけは男性だけでなく女性にもあり、地域差や世代差もある。組織において"女性ならではの"視点をという言い方もそれ自体が決めつけ的なものだが、できることがあるとすれば、「少数派としての体験」を生かして、マイノリティ属性の人の困りそうな状況を察知し、解消を発想することかも。
グローバル・ジェンダー・ギャップ指数(経済分野)の算出根拠は ①女性の労働参加率 ②類似職業の男女賃金格差 ③全体の男女賃金格差 ④管理職に占める女性比率 ⑤総合職・専門職に占める女性比率。家事育児介護の負担をアウトソーシングできる国柄の国の方が指数が高くなる傾向にある。公共サービスとしてアウトソーシングできる北欧の国と同様、新興国・途上国であるアジアやアフリカにも指数が高い国がある。それは、所得の多い家は低所得の女性を雇って家事育児介護をさせることができるので、自分も働きに出られるからであるとのことだ。
読了日:10月02日 著者:治部 れんげ
 これってホントにエコなの?の感想
これってホントにエコなの?の感想
人間はものを造る。運ぶ。使う。捨てる。それらは地球環境には全て負荷になる。衣食住、毎日毎日の膨大な選択で、負荷を減らせる選択について書いている。関心があっても眩暈がしてくる分量だが、それによって環境負荷を減らすための原則が解ると同時に、より複合的な問題、一律に答えを出せない問いが多い事実も、浮き彫りになっている。つまり選択は程度の問題で、次善の策を取るしかないことも解って、選んでいくしかないのだ。カーボンオフセットは、自力で解決できないから金銭で協力しようという行為。必要だけど、取組として本質的ではない。
自然の中で分解されない化学物質を使った洗剤より、水を余分に使ってでも自然に還る原料を使った洗剤で食器を洗うほうがグリーン。キッチンペーパーを使い捨てするより、水や洗剤を使ってでもふきんを洗濯して繰り返し使う方がグリーン。FSC認証のバージンパルプでつくったトイレットペーパーよりも、再生紙でつくったトイレットペーパーを選ぶほうがグリーン。
読了日:10月01日 著者:ジョージーナ・ウィルソン=パウエル
注: は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。
日本はますます生きづらい国になるだろう。
そこに、私が得てきた知識も倫理も、絶望感を助長するばかりだ。
私は何のために本を読んでいるのだろうか。
<今月のデータ>
購入22冊、購入費用23,830円。
読了18冊。
積読本272冊(うちKindle本114冊、Honto本13冊)。

10月の読書メーター
読んだ本の数:18
 崩れ (講談社文庫)の感想
崩れ (講談社文庫)の感想文さん72歳、52kg。執着したのは「崩れ」、なんと山崩れと暴れ川である。窮屈なズボンをはき、人に負ぶってもらってでも登り我が目で確かめるのだ。無意識のうちに心に貯めた『ものの種が芽に置きあがる時の力は、土を押し破るほど強い』。文さんの、炎が噴き出るような気性が発揮される。「木」が生命力の象徴であるのに対比し、山崩れは荒涼や麓の命を脅かす存在だ。恐怖に圧倒されながら、崩落の打当たって割れる落石の真新しい断面の美をも瞬間に捉える。文さんの文章は、自身の感性を逃さず、豊かだ。大山の崩れを思い浮かべつつ読んだ。
読了日:10月28日 著者:幸田 文

 動物園は進化する (ちくまプリマー新書)の感想
動物園は進化する (ちくまプリマー新書)の感想動物園でゾウを飼育展示するようになった当初は見世物だったのが、時代と共に動物を通じて自然のしくみを教える、種を保存するなど機能を変えてきた。体が大きいゆえに飼育係の安全問題は喫緊であり、動物福祉も言われる今、変わりつつあるという。しかし繁殖は上手くいっていない。繁殖するためにはゾウが自然体で生きられる環境が必要だ。なのに群れの構造が複雑なゾウの少数飼育やコンクリートと鉄の檻、夜に自由に歩いたり食べたりできないスケジュール、なにより他者の視線など、人間に置き換えれば当たり前のことが動物のことになると難しい。
『ゾウの自然な生活を参考にして、家族群をつくり繁殖させる。そのためには、日々進歩する科学に基づいた飼育方針のもと、古い飼育方法ではなく、ゾウに適した高度な生息環境を整え、これまで無視してきた動物の福祉に配慮する』。その志は尊い。だけれども。
私は動物園の動物を憐憫する子供だったので、そもそも動物園にゾウは必要かとの疑念が消せない。私たちも、飼育に関わる人たちも、ゾウやライオンやが動物園にいる前提で話をする。だけどリアルな映像や情報の溢れる現代に、日本全国に何百もの動物園と100頭余ものゾウをはじめとする大型動物は必要だろうか。環境破壊や密猟がなくならないから動物園で種の保存をという考え方に、私はぞっとする。動物の餌代など"維持コスト"を議論するくらいなら、どのみち"触れあい"とは無縁な動物たちの飼育は諦めようという方向にはならないのだろうか。
読了日:10月25日 著者:川口 幸男,アラン ルークロフト

 彼岸花が咲く島の感想
彼岸花が咲く島の感想話し言葉だけではなく、地の文の言葉にも違和感が激しく、なかなか読み進まない。普段使っている母語の機微を、ごく無意識に使い分けていることに改めて気づかされる。芥川賞だから、日本語を"正しく"使っていないといけないという規則はないはずなのに、ならばなぜこの作品が選ばれたのかと神経を鋭くして読んでしまう自分は、嫌な奴だ。さて、拓慈。最も身近な、異なる存在。彼を怖いと感じるのはなぜなのだろう。男だから。無知ゆえの無邪気さをぶつけてくるから。決定的に共有できないものが立ちはだかるから。それは理不尽なことだろうか?
読了日:10月22日 著者:李 琴峰
![農家が教える 竹やぶ減らし 2021年 10 月号 [雑誌]: 現代農業 増刊](https://m.media-amazon.com/images/I/51pUqClFyEL._SL120_.jpg) 農家が教える 竹やぶ減らし 2021年 10 月号 [雑誌]: 現代農業 増刊の感想
農家が教える 竹やぶ減らし 2021年 10 月号 [雑誌]: 現代農業 増刊の感想際限なく増殖する竹林と人の闘い。苦労されている人には申し訳ないけれど、自然との知恵比べみたいで面白かった。タケノコやメンマで食べて美味しいのも良し、竹チップに粉砕して発酵させ、堆肥化するのも良し。いや好い。専門誌で繰り返し特集されるほど繁殖力の強い竹に困らされても、私たちはまだまだ自分たちの生活に役立てることができるのだ。なかでも、高さ1mで切るだけという、竹の生態を逆手にとった根絶やし方法は、よくぞ見出したと感嘆する。竹やぶはたいてい里との境目でもあるので、イノシシ対策も兼ねた自然との格闘技みたいだな。
読了日:10月21日 著者:
 ヤマケイ新書 山を買うの感想
ヤマケイ新書 山を買うの感想自分の山が欲しいと思っていた頃があって、それは新型コロナやソロキャンの流行より前からなのだけど、それは安易な衝動であろう、と戒めのために読んでみた。さすがヤマケイ。甘くない。ゆるくない。しかしやっぱり欲しくなってしまった。ここに出てくる人々が山を買い求めた目的は様々で、なかでも山を守ることに使命感を見出した人たちへの共感と共振は、固定資産税ぐらい何年でも払ったるわ!という気分にさせる。『荒れた山を美しい里山に戻しながら、楽しむ』。そうだそうだと乗り気になりかける私に、立ちはだかる数多の障害の解説が詳しい。
読了日:10月19日 著者:福崎 剛

 マイル81 わるい夢たちのバザールI (文春文庫 キ 2-61 わるい夢たちのバザール 1)の感想
マイル81 わるい夢たちのバザールI (文春文庫 キ 2-61 わるい夢たちのバザール 1)の感想"カップ"と"取っ手"の湧いて出る泉が健在であることに感謝する。「UR」は以前、原語で読もうとしたことがある。キングの文体を非ネイティヴが読むなど無謀だったと改めて思った。キーボード付Kindleは懐かしく、キングが『ちび助マシン』にわくわくする気配が好ましい。パラドックス警察より怖いのは、文学の研究者にとっては専門の作家の知らない作品が続々出現する事態であり、私にとっては買えども未読の本が並んでいる現実ではないかな。『わしの名前ではない』。「砂丘」の結末は私も大好きだ。しゃれこうべのニヤニヤ笑い最高。
読了日:10月17日 著者:スティーヴン・キング
 西日本大震災に備えよ 日本列島大変動の時代 (PHP新書)の感想
西日本大震災に備えよ 日本列島大変動の時代 (PHP新書)の感想3.11以降、日本列島は『「大地変動の時代」が始まってしまった』。2030年代に発生が予測されるM9級の南海トラフ巨大地震をはじめ、東日本に再度の大地震、それに誘発される直下型地震。これらの発生は地球科学の分野では既定路線だという。活動周期や地盤の沈下/隆起現象の解析などの具体的な根拠を読み、自分が生きているうちに必ず来ると知り、備えなければならないと思いつつも、正常性バイアスとは厄介なもので、困ったなあ、とただぼやいている。日本人古来のメンタリティなどに思いをはせている場合ではない。備えんか自分。
今の日本列島が置かれた状況は、9世紀の日本に似ているのだという。9世紀は一般人には遠すぎるが、地球科学者には直近。驚嘆。
読了日:10月16日 著者:鎌田 浩毅

 アメリカ人の4人に1人はトランプが大統領だと信じているの感想
アメリカ人の4人に1人はトランプが大統領だと信じているの感想我が家は"あめしる"も欠かさず見る町山ファンなので、たいていの話題は町山さんから既に聞いたものだ。それにしても議事堂占拠は有り得ない事態だった。だからこそバイデン大統領の就任式が、オバマのとは違う意味で胸にずしりときたことを思い出した。さて、富豪たちの宇宙旅行合戦。ウィリアム王子の言うように、今やらないかんことはそれや無いやろ、である。全ての富豪に社会貢献の義務があるわけではない。だったら不労所得には重税をかけて社会に強制還元してもらわねば。Kindleを生んだ功績は多大なれど、ベゾスにはがっかりだ。
読了日:10月16日 著者:町山 智浩

 武漢日記:封鎖下60日の魂の記録の感想
武漢日記:封鎖下60日の魂の記録の感想湖北省武漢市が突如封鎖された、新型コロナ発生ごく初期の60日間の記録。新型コロナの本質的な事象は既にここにある。あと1週間の我慢だ。ワクチンができるまでの我慢だ。初期のそんな心持が今となっては新鮮なほど、あれはほんの始まりでしかなかったと知れる。発生場所が中国であるという一点で、私たちの頭の中にはフィルターがかかった。特殊な国家だからと。この本を読んで感じたのは、著者も著者のまわりの人々も、信じているということ。民主主義ではなくとも、在る秩序。人々との紐帯。善なるものへの信頼。『法治社会』としての中国を。
『政治的公正』の名分のもとに、ネット検閲官によってWeb上の投稿が通告なく削除されるのはよくあることのようだ。それでも諦めず思うことを投稿し、削除を免れたものによって意思を表明し、人々と意思疎通する。削除されることがわかっていても、怒りを表明する。そういう形で、社会は正しくあることができると、信じているようだ。それでも、バルガス=リョサの著作が本屋の棚から消えたことを知り、彼がなにか発言をしたからではないかと推測し、気落ちしている。その先には何が残るのだろう。先日読んだSF、馬伯庸の「沈黙都市」を想う。
読了日:10月15日 著者:方方

 出版翻訳家なんてなるんじゃなかった日記の感想
出版翻訳家なんてなるんじゃなかった日記の感想なぜこの時代に、出版社と翻訳家の契約が書面でなく口頭なのか。そもそもそこに問題があると思うが、それにしても印税カットも出版中止も、出版社の翻しようが酷いのなんの。著者のプライドゆえの災厄とは言いきれず、出版社の大小の問題とも判じきれず、こちらまで出版業界不信になりそう。私の支払った代金は正当に翻訳者に届いているのか。商業主義的と出版社を非難するのは簡単だが、出版不況と言われると、あのしっかりしたつくりの美しいものに正当な対価を払わない読者側の問題も絡む。これからは本を買うのに出版社も選ぶ時代かもしれない。
今年のノーベル文学賞を受賞したグルナ氏の著作は和訳されるのかどうか、翻訳本をつくるには時間がかかる。まず翻訳しなければどのような感触の作品か出版社にもわからないのが、翻訳本の事情のややこしいところだ。今頃、出版社が翻訳家に最短期間で訳せるかせっついているところかもしれない。売れるチャンスなのだから。だけど翻訳本は以前に比べますます売れないのだろう、有名作家の新刊小説でも、地方の書店は置いていないことが多いものなあ。出版物数がやたら多いのも問題だろうし。つい安い本の方を選んじゃうのも問題だろうし。難しい。
読了日:10月10日 著者:宮崎 伸治

 ゴッホのあしあと (幻冬舎文庫)の感想
ゴッホのあしあと (幻冬舎文庫)の感想「たゆたえども沈まず」の副読本と謳ったエッセイ。「たゆたえども~」のどの部分が創作だったか明らかにされていて興味深い。中野京子さんが“爆発し続けた”と表現したゴッホの晩年5年間。その起爆剤はパリと浮世絵だった。ゴッホの絵の奥底にある彼の孤独を探り当て、対象として眺めるんじゃなくて手繰り寄せるような、そんな感受性があるから、原田マハは小説を書けるのだと思った。一方、林忠正が同胞のはずの日本人から国賊呼ばわりされた当人であると知る。私はこちらを手繰ってみたい。
読了日:10月09日 著者:原田マハ
 たゆたえども沈まず (幻冬舎文庫)の感想
たゆたえども沈まず (幻冬舎文庫)の感想重吉、忠正、テオと登場し、フィンセントが現れて、役者は揃う。フィクションである日本人の、重吉にはテオの心情描写、忠正にはフィンセントの運命示唆が役割として割り振られ、それがしかも対比構造になっている。私は彼らの本当のところを知らないながら、上手いな、面白いなぁ、と思った。中野京子さんの本の続きで言うと、印象派の画家たちは、被写体の心情や立場に関心をもたなかったかもしれないけれど、自身の絵を描きたい情熱には真摯だった。日々食べるものにも事欠きながらも描くことをやめない、やめられない情熱なんて想像もつかない。
読了日:10月09日 著者:原田マハ
 聊斎志異の怪 (角川ソフィア文庫)の感想
聊斎志異の怪 (角川ソフィア文庫)の感想17世紀中国のあやかし説話集。幽霊が賄賂を贈ったり嫉妬したり、取っ組み合いの喧嘩を始めたりと騒々しく人間臭い。性愛絡みの物語も多く、幽玄という美的感覚が中国にはないのかとぼやいてみるが、思い返せば日本の説話だって似たようなもの。説話は骨組であって、要は想像力の膨らませようか。現に巻末の芥川と太宰が翻案した作品から、原案に肉をつけると物語として違和感がないとわかる。これは彼らの膨らませ方が上手いこともあろうけれども、中国と日本の物語の構造もきっと似ているのだろう。「狐の嫁女」は映像にしたらさぞ美しかろうな。
『これはきみの心だ。きみの作文が下手なのは、きみの心の毛穴がふさがっていたためだから、いま、冥途にある千万の心の中からよいものを一つ選び出して、きみの心と取り替えたのだ。きみの心は取っておいて、不足した冥途の分を補充するのだ』。と閻魔王のとこの判官が主人公のイマイチな文才の改善に便宜を図ってくれる。なんとも人間の願望の透けて見えることよ。さらに奥さんの顔と性根も美しい人のそれと取り替えてくれるという「首のすげかえ」は至れり尽くせり。閻魔王のとこの判官さんは、そんなに退屈しとったのだろうか。
読了日:10月08日 著者:蒲 松齢

 印象派で「近代」を読む 光のモネから、ゴッホの闇へ (NHK出版新書)の感想
印象派で「近代」を読む 光のモネから、ゴッホの闇へ (NHK出版新書)の感想印象派は『何が描かれているかより、どんなふうに描かれているか』を重視する代わり、悲惨も鬱屈も顧みることない、人の心の深みとは切り離された絵画だった。当時の庶民同様、西洋史の教養も無しに眺めていた私に、絵は背景を知って観るのが面白いと中野さんは教えてくれる。ただ楽しむための絵画にも時代背景はある。屋外で描くという行為自体がたいへんな変革だったとか、エッフェル塔は醜いと嫌われたとか、中でも踊り子や上流階級の妻やお針子や、その時代の人々、同時に画家自身の生き方が絵の中に現れていると新たに知って俄然楽しくなる。
読了日:10月07日 著者:中野 京子

 老いた家 衰えぬ街 住まいを終活する (講談社現代新書)の感想
老いた家 衰えぬ街 住まいを終活する (講談社現代新書)の感想全国民を挙げての大ババ抜き大会である。人口が急減を始めるなか、それはもう既に始まっていて、たとえば20年後に処分できそうにない不動産を今買うなどもってのほかで、親や親族の不動産が転がり込んでくる可能性や、近隣が放棄物件で荒廃する可能性を考えれば、無縁でいられない人の方が多そうだ。個人ではどうしようもないケースも考えると、個人を厳罰化しても根本的な解決にはならず、マッチングにせよ近隣需要への橋渡しにせよ、譲渡推進にも早晩限界が出るのではないのかしら。法制面をはじめ、ババをババでなくする仕組みづくりが急務。
町を歩いていて明らかに空き家とわかる物件でも、様々な事情で放置/留置されている事情がある。所有者が施設に入ったなどはこの本にも書かれているが、不動産屋さんと話していると、親族や近隣住民との関係の都合で、堂々と売りに出すことができない様々の問題があるのだそうだ。かといって売れない実家、山林や原野="負動産"にかかる税金などの経費は年々かかり続け、ボディブローのように効いてくるのだから、持ち続けることにも無理がある。いやー、どうすんだこれ。
読了日:10月05日 著者:野澤 千絵

 猫と住まいの解剖図鑑の感想
猫と住まいの解剖図鑑の感想我が家の猫は1匹になってしまったけれど、縁があるなら、また猫を迎えたい。で、猫ズに優しい家を妄想する。猫を優先にして家をつくるのは本末転倒で、人間のための家を設計する中で、猫にも優しい工夫をするべきという前提には同意する。脱走防止に引き戸をつけるなどもよいけれど、今はいろいろな商材が出ていて、爪とぎやキャットウォークはもちろん、壁の漆喰塗りや、窓を開けておくための格子もDIYできるという情報がためになった。和のしつらえも案外大丈夫と知る。障子や襖は貼り直せばよく、畳も爪とぎされそうで実は大丈夫らしい。
読了日:10月03日 著者:いしまるあきこ
 「男女格差後進国」の衝撃: 無意識のジェンダー・バイアスを克服する (小学館新書)の感想
「男女格差後進国」の衝撃: 無意識のジェンダー・バイアスを克服する (小学館新書)の感想セミナーで紹介された本。以前「女性活躍」と言われると、もやっとした違和感が拭えなかった。余計な意味合いが含蓄されて感じた。ではなく「ジェンダー・ギャップの解消」なら、目的は明瞭で社会の目標として掲げてよいと思う。さて、性別に基づく無意識の決めつけは男性だけでなく女性にもあり、地域差や世代差もある。組織において"女性ならではの"視点をという言い方もそれ自体が決めつけ的なものだが、できることがあるとすれば、「少数派としての体験」を生かして、マイノリティ属性の人の困りそうな状況を察知し、解消を発想することかも。
グローバル・ジェンダー・ギャップ指数(経済分野)の算出根拠は ①女性の労働参加率 ②類似職業の男女賃金格差 ③全体の男女賃金格差 ④管理職に占める女性比率 ⑤総合職・専門職に占める女性比率。家事育児介護の負担をアウトソーシングできる国柄の国の方が指数が高くなる傾向にある。公共サービスとしてアウトソーシングできる北欧の国と同様、新興国・途上国であるアジアやアフリカにも指数が高い国がある。それは、所得の多い家は低所得の女性を雇って家事育児介護をさせることができるので、自分も働きに出られるからであるとのことだ。
読了日:10月02日 著者:治部 れんげ

 これってホントにエコなの?の感想
これってホントにエコなの?の感想人間はものを造る。運ぶ。使う。捨てる。それらは地球環境には全て負荷になる。衣食住、毎日毎日の膨大な選択で、負荷を減らせる選択について書いている。関心があっても眩暈がしてくる分量だが、それによって環境負荷を減らすための原則が解ると同時に、より複合的な問題、一律に答えを出せない問いが多い事実も、浮き彫りになっている。つまり選択は程度の問題で、次善の策を取るしかないことも解って、選んでいくしかないのだ。カーボンオフセットは、自力で解決できないから金銭で協力しようという行為。必要だけど、取組として本質的ではない。
自然の中で分解されない化学物質を使った洗剤より、水を余分に使ってでも自然に還る原料を使った洗剤で食器を洗うほうがグリーン。キッチンペーパーを使い捨てするより、水や洗剤を使ってでもふきんを洗濯して繰り返し使う方がグリーン。FSC認証のバージンパルプでつくったトイレットペーパーよりも、再生紙でつくったトイレットペーパーを選ぶほうがグリーン。
読了日:10月01日 著者:ジョージーナ・ウィルソン=パウエル
注:
 は電子書籍で読んだ本。
は電子書籍で読んだ本。 






